
コラム
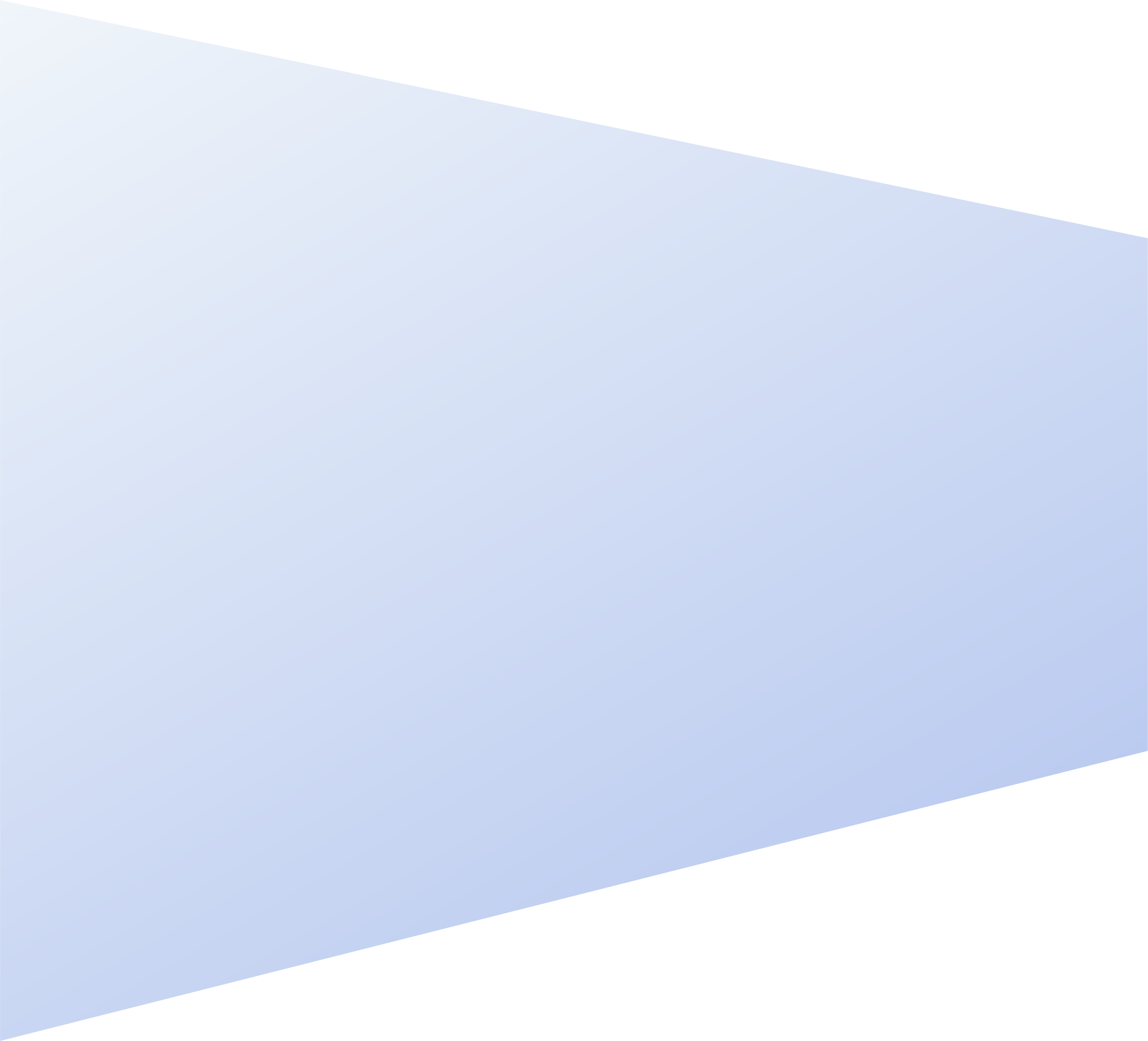
「上代(じょうだい)」とは?下代(げだい)や定価との違い、計算方法を解説
2025.07.31|最終更新日:2025.07.31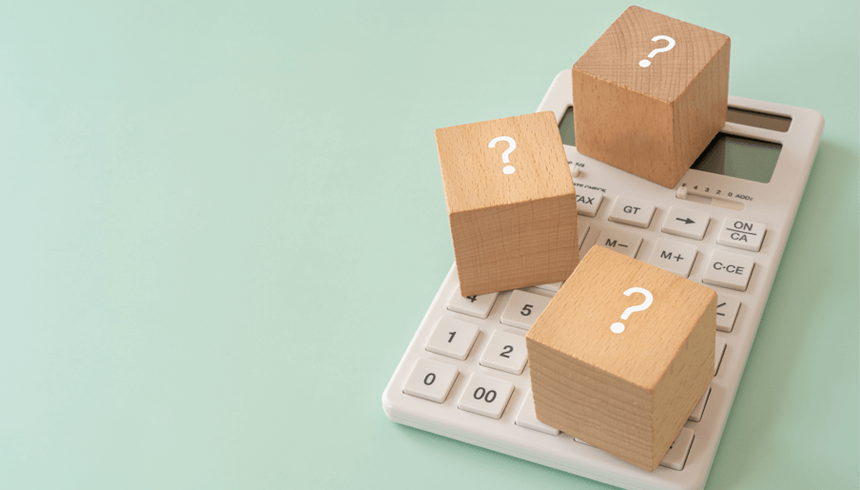
企業間取引、特に卸売や小売業界では「上代(じょうだい)」「下代(げだい)」といった用語が使われており、日常的に使っている人は少なくないでしょう。しかし、その意味や「定価」などの類語との違いについて、明確な説明ができる人は多くないかもしれません。
ここでは、「上代」の正確な意味や関連用語との違い、利益計算の方法、そして実際の取引における注意点などを詳しく解説します。
目次
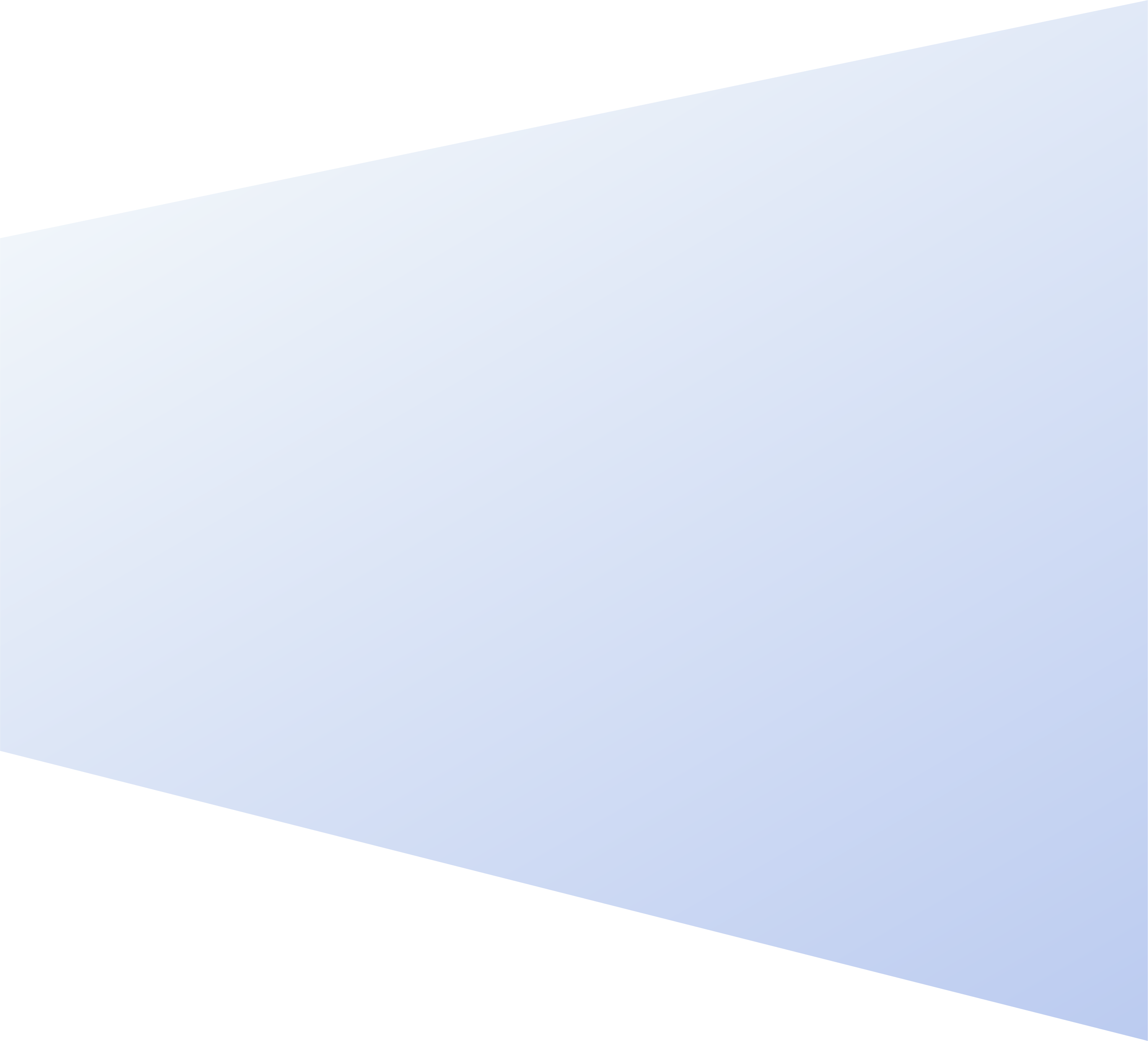
1.上代とは?
まず、上代(じょうだい)という言葉の基本的な意味について解説します。
1-1.上代(じょうだい)は希望小売価格に相当するもの
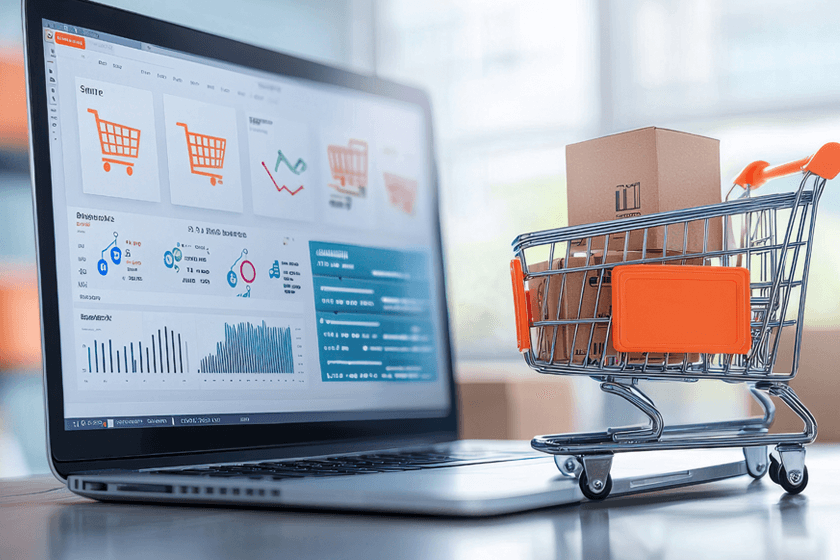
上代(じょうだい)とは、製造業者(メーカー)や卸売業者が、小売業者に対して「この価格で販売することが望ましい」と提示する商品の販売価格のことです。「上代価格」とも呼ばれ、一般消費者が店頭などで目にする、いわゆる希望小売価格に相当します。
上代は、市場における商品の価値やブランドイメージを維持し、販売価格の極端なばらつきを防ぐ目的で設定されることが一般的です。
1-2.下代(げだい)との関係
上代と対になるのが「下代(げだい)」という言葉です。下代とは、小売業者がメーカーや卸売業者から商品を仕入れる際の価格であり、「卸価格」や「仕入原価」に該当します。
小売業者は「下代」で商品を仕入れ、それに利益を乗せて「上代」を目安に消費者に販売します。この上代と下代の価格差が、小売業者の利益となるのです。
「掛け率を間違えてしまった」「得意先ごとの単価がバラバラで最新がわからない」
そんな価格管理のヒヤリを防ぐ仕組みを“受発注のデジタル化”で
上代・下代・掛け率の管理は、利益に直結する重要な業務ですが、Excelや紙の単価表、担当者の記憶に頼っていると、「単価の転記ミス」「過去のままの価格で受注」「掛け率の更新漏れ」といったトラブルが起きやすくなります。
カシオのBC受発注で“受発注のデジタル化”を進めることで、得意先ごとの商品マスタや掛け率・単価情報を一元的に管理でき、担当者によって価格がブレることや、仕入・販売価格の取り違えを防げます。発注データはBC受発注の管理画面に自動連携されるため、利益計算に必要な情報も正確な状態で蓄積され、後処理も大幅に効率化できます。
導入企業様の秘話をご紹介!

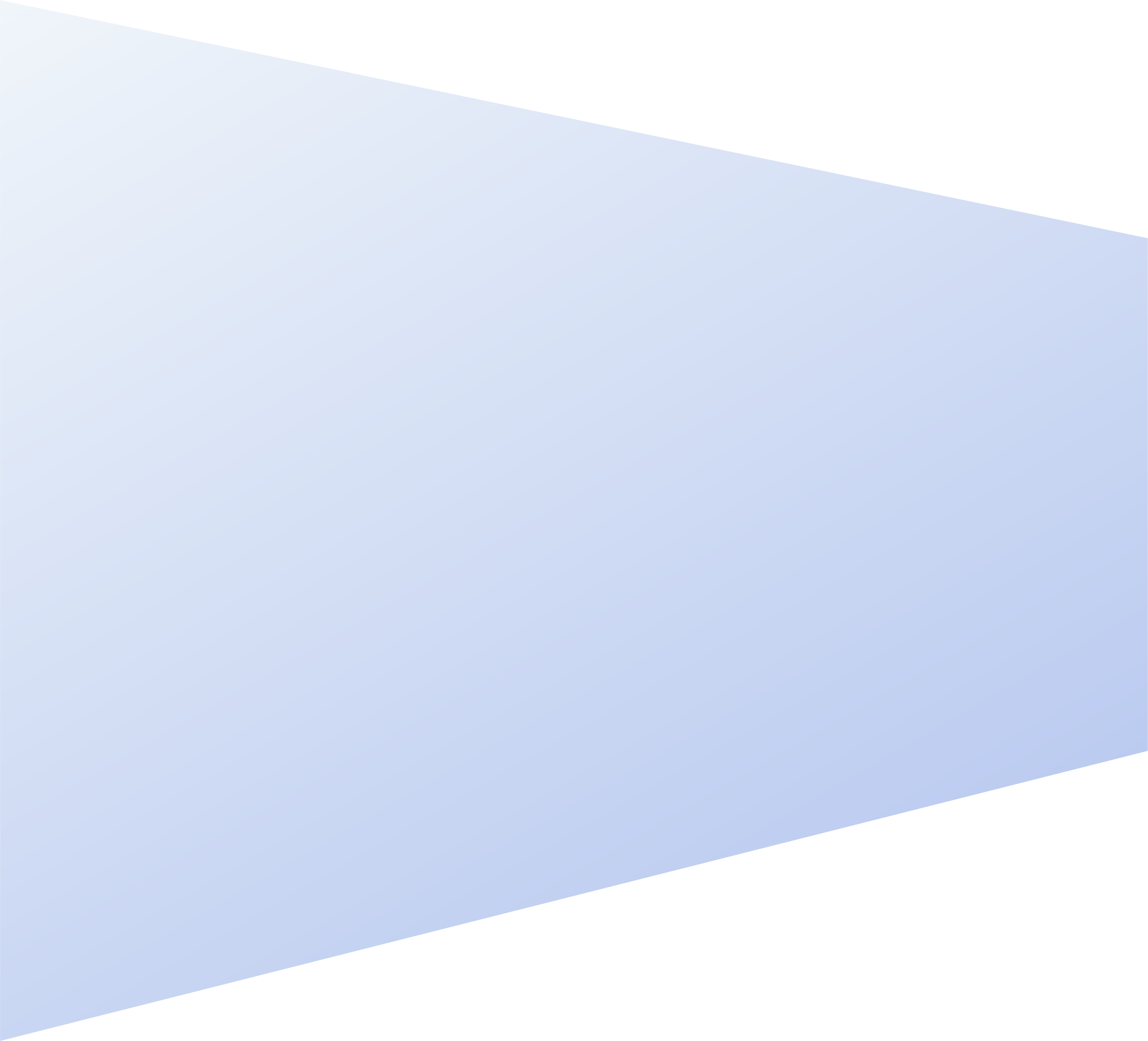
2.上代と混同しやすい関連用語
上代と意味合いが似ていて混同しやすい価格用語がいくつかあります。ここでは、それぞれの違いについて解説します。
2-1.上代と 「定価」の違い
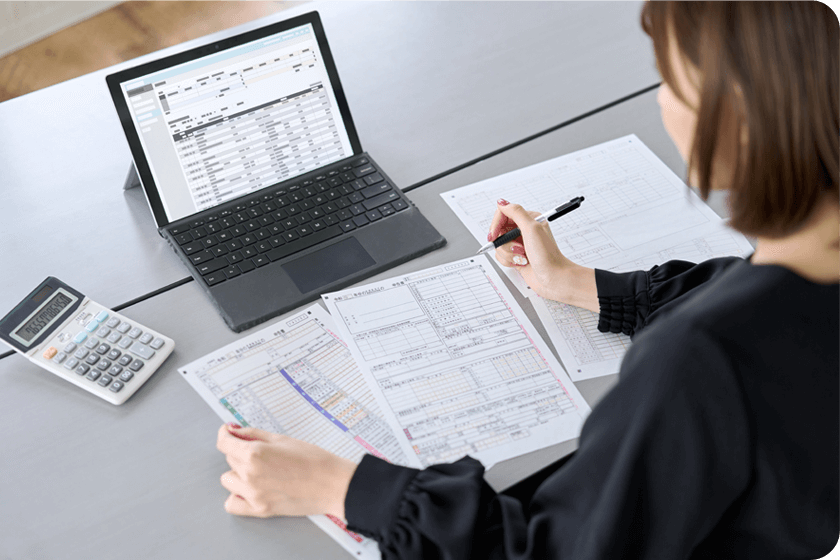
上代と最も混同されやすいのが「定価」です。両者の本質的な違いは、その価格が持つ「法的な拘束力の有無」にあります。
上代はあくまでメーカーなどが希望する価格であり、小売業者は原則として自由に販売価格を決定できます。
一方「定価」は、再販売価格維持制度(再販制度)の対象商品に限られており、小売業者が価格を変更できない仕組みになっています。現在は、書籍、新聞、音楽CD、雑誌などに定価が設定されています。
2-2.「参考上代」「メーカー希望小売価格」との相違点
「参考上代」や「メーカー希望小売価格」は、メーカー側が小売業者に希望する販売価格として提示するものです。どちらも上代と同様に法的な拘束力はなく、最終的な販売価格は小売業者が決定できます。
なお、業界や文脈によってニュアンスや使い方がやや異なる場合があり、たとえば「参考上代」は価格決定の自由度がより高いとされる場合もあります。
2-3.「オープン価格」の意味
オープン価格とは、メーカーや卸売業者が上代(希望小売価格)を具体的に設定せず、価格決定を完全に小売業者に委ねる方式のことです。
価格変動が激しい家電製品で採用されることが多く、小売業者は市場の競争状況に応じて柔軟に価格を設定できます。
2-4.上代・下代が使われているのは商慣習
メーカー希望小売価格など、より一般的な言葉があるにもかかわらず、「上代」「下代」という用語が使われるのは、昔からの商慣習によるものです。
メリットとしては、専門用語を使うことで自分たちの利益が顧客に伝わりにくいことなどが挙げられますが、「上代」「下代」という用語を使う一番の理由は、業界でのコミュニケーションがスムーズになることと言えるでしょう。
3.上代を用いた価格と利益の計算
ここでは、上代を基にした実際の仕入価格と利益の計算方法について解説します。
3-1.仕入価格を決める「掛け率」とは

「掛け率(かけりつ)」とは、下代(仕入価格)を決定する際に用いられる指標のことです。
上代に対する下代の割合を示すもので、「6掛け(60%)」や「7掛け(70%)」のように表現されるのが一般的です。
3-2.掛け率を用いた下代の計算方法
下代は、上代に掛け率を掛けることで算出されます。計算式は以下のようになります。
上代 × 掛け率 = 下代
例えば、上代が10,000円の商品で、掛け率が60%の場合、下代は「10,000円 × 60% = 6,000円」となります。
この場合、小売業者は商品を6,000円で仕入れ、10,000円で販売します。その差額である4,000円は小売業者の利益です。この掛け率の交渉が、企業の収益を直接左右します。
4.上代の注意点
上代を用いた取引を行う際には、事前に確認しておくべき注意点があります。
4-1.消費税の扱い

商慣習上、上代は消費税を含まない「税抜価格」で提示されることが一般的です。
しかし、取引によっては税込価格を上代として扱う場合が稀にあります。見積や契約の段階で、提示された上代が「税抜」か「税込」かを必ず確認することが、後のトラブルを未然に防ぎます。
4-2.上代の価格拘束力
上代を推奨価格として提示すること自体に問題はありませんが、小売業者に対してこの価格で販売するよう強制または誘導すると、独占禁止法に抵触する恐れがあります。
しかし一般的に、メーカーが設定したブランド価値を大きく損なう価格設定は、取引関係の悪化を招く可能性があります。長期的な取引を考えれば、この点も念頭に置く必要があると言えるでしょう。
5.まとめ
価格の基本用語である「上代」の意味や、下代との関係、定価などの関連用語との違いを解説しました。
上代はメーカーなどが提示する希望小売価格と同じ意味を持ち、下代は仕入価格を指します。また、法的に価格が拘束される「定価」との違いも理解することが大切です。
こうした価格用語を正しく理解し、適切に使い分けることで、仕入れ交渉をスムーズに進められるようになるでしょう。
手作業によるミスを削減する、カシオの「BC受発注」
受発注業務には「品番や数量の入力ミス」「電話での聞き間違い」「FAXの読み取りミス」といった、ヒューマンエラーが起こりやすいポイントが数多く存在します。特に、手作業でのデータ転記や、特定の担当者しか状況を把握していない「業務の属人化」が常態化しているアナログな環境では、ミスを完全になくすことは困難です。
こうした受発注のミスを根本から削減し、担当者の心理的負担を軽減するのが、カシオのBtoB受発注システム「BC受発注」です。
「BC受発注」を導入することで、取引先とのやり取りはWeb上のシステムで完結し、電話やFAXでの注文を手作業で入力する必要がなくなります。発注データはシステムに一元管理されるため、いつでも誰でも状況を確認でき、業務の属人化も解消されます。
「BC受発注」は単なる業務効率化ツールではなく、ミスが発生しにくい仕組み作りに貢献します。担当者が自らのミスで「生きた心地がしない」と感じてしまうような事態を減らし、安心して働ける環境を実現するための助けとなるでしょう。
