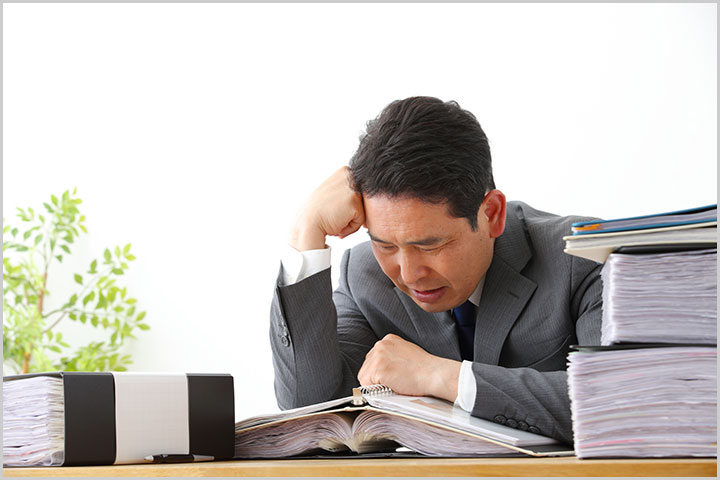手書き伝票、手計算から脱却する手順
中小企業における「手書き伝票、手計算」の実態

執筆者:株式会社船井総研ITソリューションズ
多くの中小企業では、一般的に税理士または会計士と契約しており、社内で起票した「手書き伝票」を月1回、場合によっては年1回、顧問税理士に送り、税務計算や会計帳票を作成してもらっています。場合によっては、伝票すら作成せず、売上や仕入の根拠となる請求書や領収書をそのまま顧問税理士に送っている企業も少なくありません。
中小企業の経営者にとって、全体の売上や利益は、概ね感覚で捉えており、顧問税理士に伝票や書類等を提出する目的は、「税金を正しく計算する」であることがほとんどです。
また、販売管理業務においても、納品伝票や、発注伝票、見積書等を手書きで記入しているケースが多く見られます。特に、食品製造業においては、取引先毎の指定伝票フォーマットにソフトウェアで対応することが難しく、それぞれ手書きで対応せざるを得ない状況もあるようです。
最大の難関「手書き伝票」からの脱却
では、どのようにして「手書き伝票」「手書き計算」から脱却をして行けばよいのでしょうか。
先ずは、「会計ソフト」や「販売管理ソフト」の導入を決断する事です。
会計ソフトは、企業の全ての数字を管理するソフトウェアで、なおかつ商法というルールで統一されています。また、経営者が全体の数字を正確に把握するには、最適なソフトウェアです。
会計ソフトを運用する為には、経理担当がこれを使わなくてはならない為、今いる経理担当をこのソフトウェアの担当に任命する必要があります。
販売管理ソフトは、見積書の管理や、受発注、請求書の管理等、販売に関わる数字や履歴を管理するソフトウェアです。最近では、顧客毎に異なる指定伝票フォーマットにも柔軟に対応出来るソフトウェアが出てきているため、これらを導入・活用することで、これまで手作業で実施していた業務を大幅に効率化出来ます。
「会計ソフト」や「販売管理ソフト」を導入し、活用する事で、通常、これまで手書きで作成していた伝票のうち、70%~80%の伝票は手書きから脱却出来ます。
以下に「手書き伝票」からの脱却手順を記載します。既に「会計ソフト」を導入・活用されている方は、「Ⅱ.販売管理業務における「手書き伝票」からの脱却手順」からご覧ください。
Ⅰ. 経理業務における「手書き伝票」からの脱却手順
① 会計ソフトの導入・活用担当者を任命する
② 会計ソフトを選定・導入する
③ 仕訳の範囲を決め、パターンを洗い出す
④ 売上や仕入の計上基準を決める(税理士と確認の必要有)
⑤ 請求書、領収書等から実際に仕訳を入力してみる
⑥ 試算表、損益計算書(P/L)等を出力してみる
⑦ 税理士と並行して会計ソフトを運用する(3か月程度)
⑧ ⑦の手順で双方の数字があったら、会計ソフトだけで運用する
Ⅱ. 販売管理業務における「手書き伝票」からの脱却手順
① 販売管理ソフトの導入・活用担当者を任命する
② 販売管理業務の流れを確認する
③ 伝票の種類を確認する
④ 販売管理ソフトを使用する前提で、現状の販売管理業務に対応できるか、手書き伝票に対応可能かを確認する
⑤ 販売管理ソフトを使用した販売管理業務の流れを整理する
⑥ 販売管理ソフトを導入し、運用する(可能であれば、お試し利用する)
⑦ 必要に応じて業務の流れを修正する
⑧ 販売管理ソフトの運用を定着させる
会計ソフトが導入され、自社で運用できるようになった後、受注や売上等の手書き伝票のシステム化(販売管理ソフトの導入)を実施する事で業務効率が一気に向上することが期待できます。