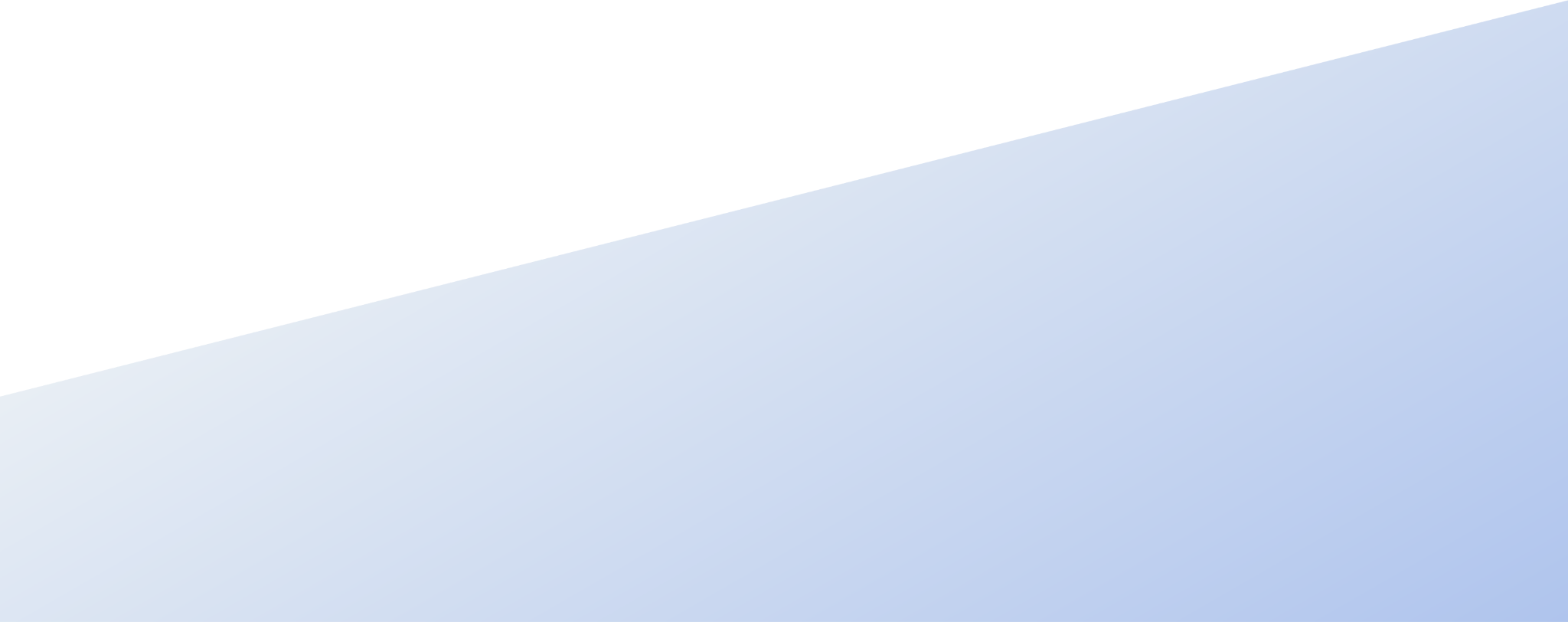導入事例
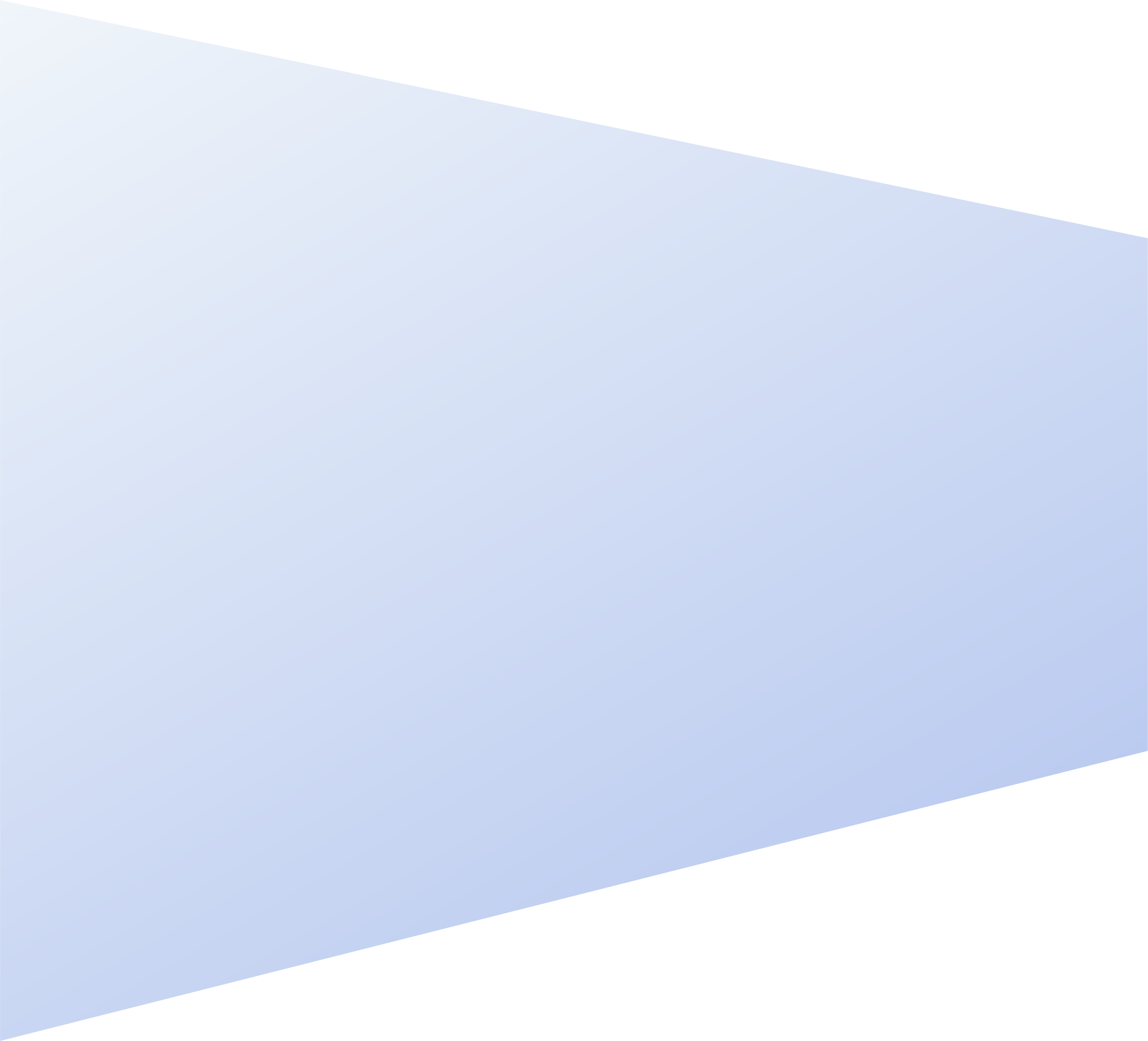
発注ミスがゼロに。業務負担も2割減。
LINEを使った発注の悩みすっきり!

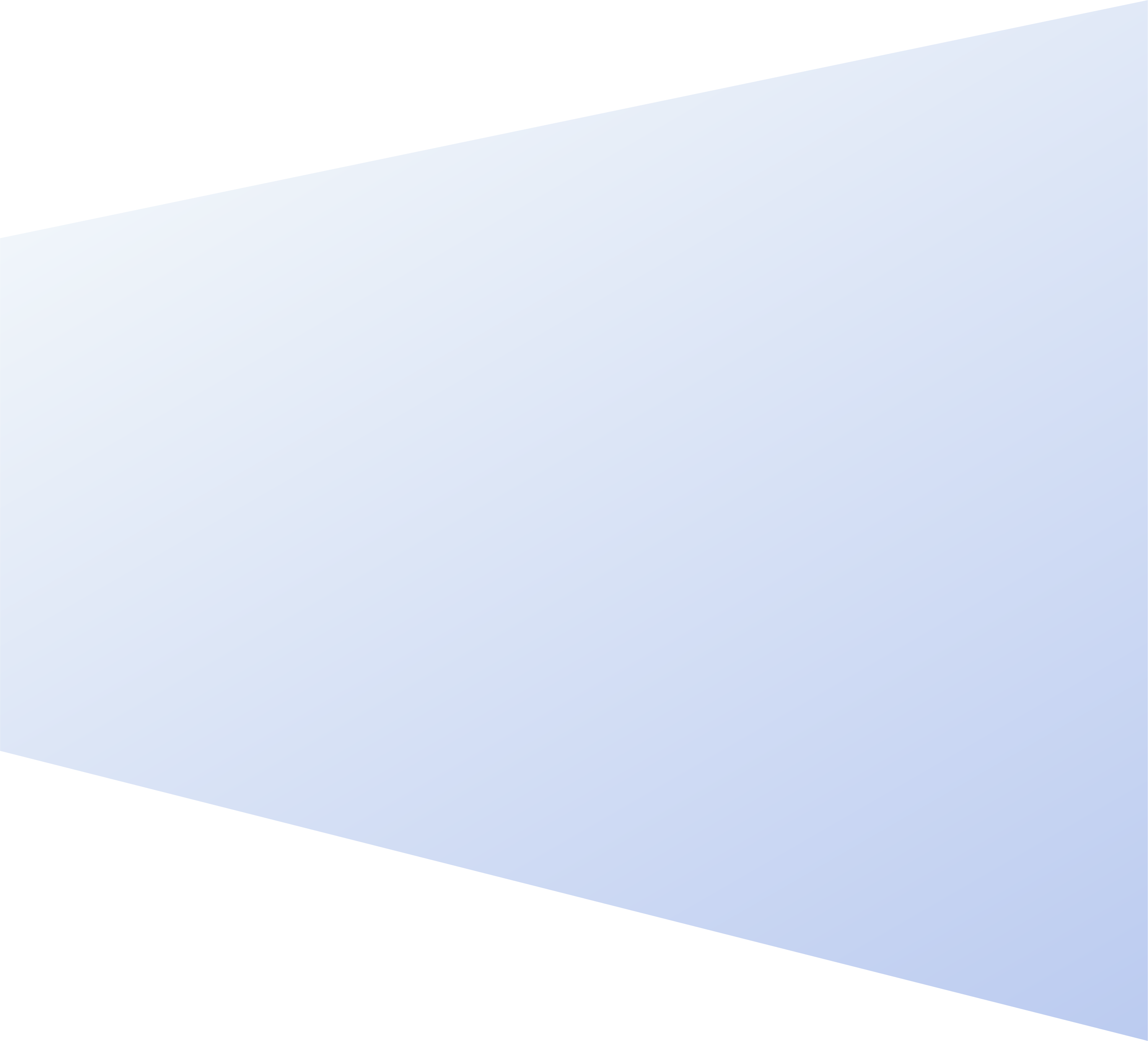
貴社のプロフィールや特徴などを教えていただけますか?
鹿児島市でホームページやECサイトの制作、動画コンテンツの企画・制作など、Webに関するクリエイティブ業務全般を手がけております。2024年からはこの土地ならではの人と人との近さや温かさ、信頼関係がきっかけで餃子の販売という新たな事業もスタートし、無人販売所の運営にも取り組んでいます。
メインのWeb制作事業と新しく始めた餃子事業、どちらも地域のニーズに応える形で展開しており、地域に根ざした多角的なビジネスモデルを構築しているのが弊社の強みです。本当に人とのつながりを大切にした事業展開を心がけております。

貴社の発注業務について教えてください。
現在弊社では、約50社の仕入先様とお取引をさせていただいています。餃子事業で扱っている商品は、年間を通してほぼ定番のものばかりなので、商品ごとの切り替えや頻繁な調整はあまりありません。発注業務は基本的に担当者が行っており、もし担当者が不在の場合は代表が代行して発注する体制になっています。毎日在庫の状況を見ながら、足りない分をその都度発注しているので、「この曜日に一斉に」というよりは、毎日どこかの仕入先様に個別にお願いしています。時間が空いたときにサクッとやる、というスタイルです。発注の方法は仕入先様によってまちまちで、BC受発注を含めて3社がWeb経由、あとはLINEでの発注がメインです。電話でお願いすることもありますが、やはり手軽なLINEでのやり取りが多いです。

仕入業務における課題はありましたか?
受注業務には専用のシステムを導入しており、システムで集計された受注内容を確認した後、必要な数量をFAX用紙に記入し、発注するという流れです。FAXによる発注では、用紙やトナーのコストがかかる、注文書を紛失する、手書きの文字が読み取りにくく、発注内容や数量を誤解しやすいなどの、さまざまなトラブルが頻繁に発生しておりました。
BC受発注導入のきっかけをおしえてください。
BC受発注を導入する前は、主にLINEで発注していましたが、正直いろいろと課題がありました。一番の悩みは「誤発注」でした。商品名や数量を手入力していると、どうしても打ち間違いや桁ミスが発生してしまうのです。特に、名前が似ている商品や、数量の「0」が一つ多かった…といったミスは避けられませんでした。また、発注内容の管理もかなり大変でした。過去の発注履歴を確認しようと思ったら、LINEのやり取りをスクロールして探し出し、手作業で集計する必要がありました。これが想像以上に手間で、「あれ、前回何個頼んだっけ?」と確認したいときにすぐに見つけられないのが、地味にストレスでした。さらに、LINE特有の課題として、仕入先様の受注確認漏れが起きることもありました。おそらく、LINEで発注内容を確認して既読にした時点で安心され、その後の出荷手配を忘れてしまうケースがあったのだと思います。

BC受発注の導入の経緯と使ってみての感想を教えていただけますか。
BC受発注の導入は、お取引先のビッグファイブさんから「これで発注してください」とご案内いただいたのがきっかけでした。特に抵抗もなく導入が決まりました。
使ってみた最初の印象は、「とてもシンプルで使いやすい」ということでした。他社さんのシステムだと、説明を聞かないと分からなかったりすることもありますけど、BC受発注は直感的に操作できて、特に問い合わせることもなく、すぐに慣れることができました。

BC受発注を導入してどのような効果がありましたか?
最も大きく変わったのは、誤発注が「ゼロ」になったことです。商品を選択するだけで発注が完了するため、打ち間違いによる誤発注は完全に解消されました。
それから、発注履歴の確認がすごくラクになったのも大きな変化です。今は履歴がすぐ見られるので、確認や再発注の時もスムーズになりました。商品名の入力作業も、今では選ぶだけで済むので、だいぶ時間短縮になっています。全体的に見て、発注業務にかかる時間は1〜2割は削減できていると思いますし、紙やトナーの消費も減って、エコにもなっています。あと、思いがけず良かったのが「納期確認のしやすさ」ですね。この日に欲しいけど大丈夫かな…って迷う場面でも、システム上で納品可能な日しか選べないようになっているので、安心して発注できるようになりました。それともう一つ。LINEのときは、夜遅かったり土日だったりすると「今送っていいかな…」と気を遣うことが多かったのですが、BC受発注なら時間を気にせずポチッと送れるのも、地味に大きなメリットだなと感じています。

今後の発注業務についての希望をお聞かせください。
今後についてですが、発注データの集計機能があると嬉しいですね。たとえば「今月この商品を何個頼んだか」「どの仕入先にどれだけ発注したか」みたいな情報が自動で出せると、請求処理や在庫管理にも活かせて、業務の効率もグンと上がると思います。それと、やっぱり仕入先さんごとにシステムがバラバラだと、逆に手間が増えてしまうので、できればひとつのシステムに統一できたら理想です。BC受発注みたいに使いやすいシステムであれば、他の仕入先さんにも「ぜひ使ってください」とお願いしたいくらいです。今後も、地域に根ざした事業を大切にしながら、こうした便利な仕組みをうまく取り入れて、もっと快適に、もっと効率よく、仕事を進めていけたらと思っています。