【2025年施行】2024年成立の改正雇用保険法について解説
2025.03.19
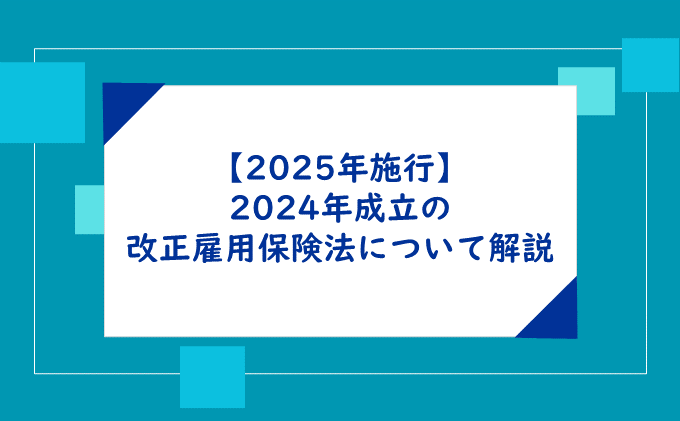
2024年に成立した改正雇用保険法では、雇用保険の適用拡大や教育訓練給付の拡充など新たに変更・追加となった項目があります。企業の人事担当者としては、十分に理解しておきたいところです。
本記事では、雇用保険制度や雇用保険法の改正内容を紹介します。また、改正により企業に生じる影響についても解説します。
目次
製品の詳細を知りたい方はこちら
「雇用保険制度」および「雇用保険法」とは
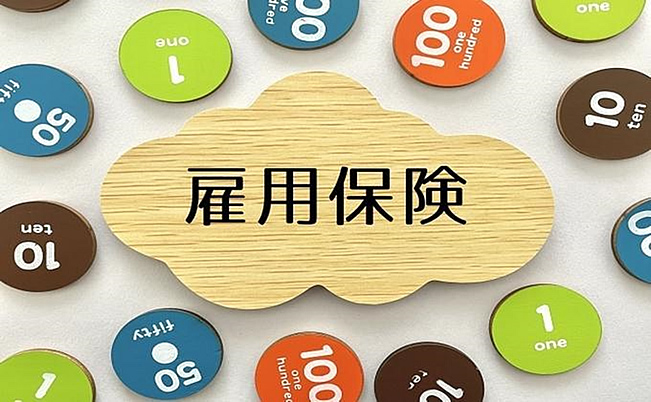
2024年成立の改正雇用保険法について解説する前に、雇用保険制度と雇用保険法の概要について紹介します。
二事業を主体とする「雇用保険制度」
雇用保険制度は、雇用保険法に基づいて発足した強制保険制度(労働者を雇用している事業所に原則として強制的に適用される制度)です。
具体的には、次の二事業を主体として行っています。
- 失業して所得の源泉を喪失した労働者や教育訓練受講者に対して、失業等給付を支給する
- 失業予防や雇用状況の是正および雇用機会の増大、労働者の能力の開発や向上、労働者の福祉の増進を図る
雇用保険制度は改正が重ねられ、失業・教育訓練・育児休業等の各種給付を実施するほか、雇用安定事業および能力開発事業を行っています。
なお、雇用保険制度は、失業や休業で収入が減少した際に給付を行う公的保険です。正しく運用するためには、雇用保険法への理解を深めることが欠かせません。
「雇用保険法」は雇用保険制度に関する法律
雇用保険法は、雇用保険制度についてまとめた法律です。雇用保険法では、次のことを目的として定められています。
- 労働者の生活および雇用の安定と就職の促進
- 失業の予防、雇用状態の是正および雇用機会の増大、労働者の能力の開発および向上、労働者の福祉の増進
雇用保険法の適用範囲は、原則として労働者を一人でも雇用している事業所です。雇用保険への加入条件は、次のとおりです。
- 所定労働時間(1週間)が20時間以上ある
- 同一の事業主に継続して31日以上の雇用が見込まれている
上記の条件を満たしていれば、雇用形態は問われません。一定の季節のみ雇用される場合は被保険者に該当しない可能性があるため、判断に迷う場合はハローワークに相談しましょう。
改正雇用保険法の内容と施行日一覧

2024年に、雇用保険制度に関する雇用保険法と子ども・子育て支援法の一部が改正されました。それぞれの改正内容と施行日は次の表のとおりです。
| 雇用保険法等の一部を改正する法律の概要 | |
| 改正内容 | 施行日 |
| 1.雇用保険の適用拡大 | 2028年10月1日 |
| 2.教育訓練やリスキリング支援の充実 | 2025年4月1日(一部は2024年10月1日) |
| 3.育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保 | 2025年4月1日(一部は公布日) |
| 4.その他雇用保険制度の見直し | 2025年4月1日(一部は公布日) |
| 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の概要 | |
| 改正内容 | 施行日 |
| 1.育児時短就業給付の創設 | 2024年10月1日 |
| 2.子ども・子育て支援特別会計の創設 | 2025年4月1日 |
改正の目的としては次のようなことが考えられます。
<雇用保険法等の一部を改正する法律>
労働者が自身の希望と状況に応じて能力を十分に発揮できるように、労働者の主体的なキャリア形成を支援する
<子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律>
少子化が進む中で、男女ともに働きながら育児を担える環境整備に向けて、とくに男性の育児休業の取得促進や育児期の柔軟な働き方を推進させる
それぞれの改正内容については後述する内容を参考にしてください。
参考:厚生労働省「令和6年雇用保険制度の改正内容について(雇用保険法等の一部を改正する法律)」
参考:厚生労働省「令和6年雇用保険制度の改正内容について(子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律)」
「雇用保険法等の一部を改正する法律」の概要

今回の雇用保険法改正では、多様な働き方を効果的に支えるセーフティネットの構築や、人に対する投資の強化等を目的としています。
「雇用保険法等の一部を改正する法律」の改正事項は次の4つです。
- 雇用保険の適用拡大
- 教育訓練やリスキリング支援の充実
- 育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保
- その他雇用保険制度の見直しについて
それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。
1.雇用保険の適用拡大
今回の改正では、雇用保険の適用拡大が行われています。具体的には、被保険者期間の算定基準や失業認定基準などが変更されました。変更点は、次の表のとおりです。
| 改正前 | 改正後 | |
| 被保険者期間の算定基準 | ・賃金の支払の基礎となった日数→11日以上 または ・賃金の支払の基礎となった労働時間数→80時間以上 を1月とカウントする |
・賃金の支払の基礎となった日数→6日以上 または ・賃金の支払の基礎となった労働時間数→40時間以上 を1月とカウントする |
| 失業認定基準 | ・労働した場合でも1日の労働時間が「4時間未満」にとどまる場合は失業日と認定する | ・労働した場合でも1日の労働時間が「2時間未満」にとどまる場合は失業日と認定する |
| ①法定の賃金日額の下限額 ②最低賃金日額 |
①屈折点(給付率が80%となる点)の額の2分の1 ②最低賃金(全国加重平均)で週20時間を働いた場合を基礎として設定 |
①屈折点(給付率が80%となる点)の額の4分の1 ②最低賃金(全国加重平均)で週10時間を働いた場合を基礎として設定 |
※「①を毎月勤労統計の平均定期給与額の変化率を用いて毎年自動改定した額」と②を毎年比較し、高いほうを賃金日額の下限額として設定する
労働者の働き方や生計維持の在り方は多様化しているため、雇用のセーフティネットを広げるべく、1週間の所定労働時間が20時間以上から10時間以上に適用対象が拡大されました。
ただし、祝日や夏季休暇などの特別な休暇は含まれません。
2028年10月1日施行(予定)以降は、週の所定労働時間が10時間以上で新たに雇用保険法の適用対象となる者は、現行の被保険者と同様に基本手当や教育訓練給付などの各種給付を受け取れます。
そのほか、被保険者期間は、賃金の支払の基礎となった日数が6日以上、または賃金の支払の基礎となった時間数が40時間以上である場合に1か月としてカウントされます。
失業日として認定される基準は、次のように変更されました。
- 1日の労働時間:4時間未満→2時間未満
2.教育訓練やリスキリング支援の充実
雇用保険法改正によって、教育訓練やリスキリング支援の充実も行われます。また、自己都合退職者が安心して再就職活動できるように、給付制限の見直しが行われました。
| 改正前 | 改正後 |
| 自己都合離職者に対しては、失業給付(基本手当)の受給にあたり給付制限期間あり | 離職期間中や離職日前1年以内に、自ら雇用の安定および就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、給付制限を解除 |
これまでは、失業給付(基本手当)の受給にあたり、給付制限期間が設けられていました(待機満了の翌日から原則2か月間、5年以内に2回を超える場合は3か月)。
一方、今回の改正では、離職期間中や離職日前1年以内に自ら雇用の安定および就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、給付制限が解除されます。施行は2025年4月1日からです。
なお、労働者が主体的にリスキリングできるように、次のように変更されました。
- 教育訓練給付金の給付率上限引上げ教育訓練の受講後に賃金が上昇した場合の追加給付の実施
2024年10月1日から施行されます。
| 改正前 | 改正後 | |||
| 本体給付 | 50% | 40% | 50% | 40% |
| 追加給付① (資格取得等) |
20% | ー | 20% | 10% |
| 追加給付② (賃金上昇) |
ー | ー | 10% | ー |
| 最大給付率 | 70% | 40% | 80% | 60% |
さらに、教育訓練休暇給付金も新たに創設されました。
| 対象者 | 雇用保険被保険者 |
| 支給要件 | 教育訓練のための休暇(無給)を取得する被保険者期間が5年以上ある |
| 給付内容 | 離職した場合に支給される基本手当の額と同じ給付日数は、被保険者期間に応じて次のいずれか90日、120日、150日 |
| 国庫負担 | 給付に要する費用の4分の1または40分の1(基本手当と同じ) |
現行法では、労働者が教育訓練に専念するために自発的に仕事から離れる際、訓練期間中の生活費を支援する仕組みはありません。
今回の改正では、離職者等を含めた労働者が教育訓練に専念できるように、賃金の一定割合を支給する教育訓練休暇給付金が創設されました。対象は、雇用保険被保険者が教育訓練のために休暇を取得した者です。
施行は、2025年10月1日からです。
3.育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保
育児休業の取得者数が増加傾向にあるため、育児休業給付は支給額が年々増加しており、財政基盤の強化が急務でした。男性育休の大幅な取得増への対応を見据えて、育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保のために、次のような改正が行われます。
- 育児休業給付に関する国庫負担割合を8分の1へ引上げる
- 保険料率は当面0.4%に据え置きつつ、本則料率を2025年から0.5%に引上げる。実際の保険料率は保険財政の状況に応じて調整する仕組みを導入する
| 改正前 | 改正後 | |
| 国庫負担割合 | 1分の80 | 8分の1に引上げ |
| 保険料率 | 0.4% | 0.5%に引上げ |
施行日は、次のとおりです。
国庫負担割合:公布日または2024年4月1日のいずれか遅いほう
保険料率:2025年4月1日
4.その他雇用保険制度の見直しについて
ほかにも、雇用保険制度の見直しとして、雇止めによる離職者の基本手当の給付日数や教育訓練支援給付金についての変更が挙げられます。
現行法では、次の事項に関する特例は2024年度末までの暫定措置です。
- 雇止めによる離職者の基本手当の給付日数に係る特例
- 地域延長給付
- 教育訓練支援給付金
今回の改正では、上記事項の暫定措置がいずれも2年間延長されました。
ただし、教育訓練支援給付金の給付率は、基本手当日額の80%から60%に引き下げられていることに注意しましょう。施行は、2025年4月1日からです。
| 改正前 | 改正後 | |
| 雇止めによる離職者の基本手当の給付日数 | 90日~150日 | 90日~330日(暫定措置) |
| 教育訓練支援給付金 | 基本手当日額の80%を訓練受講中に2か月ごとに支給 | 基本手当日額の60%を訓練受講中に2か月ごとに支給 |
参考:厚生労働省「令和6年雇用保険制度の改正内容について(雇用保険法等の一部を改正する法律)」
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の概要

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の概要について解説します。雇用保険制度に関連する改正は、次の2つです。
- 育児時短就業給付の創設
- 子ども・子育て支援特別会計の創設
1.育児時短就業給付の創設
子ども・子育て支援法等の一部改正にともない、育児時短就業給付が創設されます。
現行法では、育児のために短時間勤務制度を選んだ結果賃金が低下した従業員に対する給付制度がありません。また、共働き・共育ての推進や子の出生・育児休業後の従業員の育児とキャリア形成の両立支援の観点から、選択可能な時短勤務制度が求められていました。
今回の改正にともなって創設された育児時短就業給付金では、被保険者が2歳未満の子を養育するために時短勤務をすることで給与額が下がる場合、時短勤務中に支払われた賃金額の10%を上限に給付金が支給されます。
また、育児休業給付の給付率引上げ(出生後休業支援給付金)も実施される予定です。子どもの出生直後の一定期間※以内に、被保険者とその配偶者が14日以上の育児休業を取得すると、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額が支給されます。
育児時短就業給付と出生後休業支援給付を合わせた給付率は、休業前賃金の80%です。
施行は、いずれも2025年4月1日からです。
※一定期間以内:男性は出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内
2.子ども・子育て支援特別会計の創設
子ども・子育て支援特別会計も新たに創設されます。子ども・子育て支援特別会計の創設の目的は、子ども・子育て政策の全体像と費用負担の見える化促進です。
具体的には、次のとおりです。
- 子ども・子育て支援特別会計の区分:「子ども・子育て支援勘定」と「育児休業等給付勘定」の2つとする
- 管轄:「子ども・子育て支援勘定」は内閣総理大臣、「育児休業等給付勘定」は厚生労働大臣が管理する
- 決算剰余金の管理区分:事業主拠出金、子ども・子育て支援納付金、雇用保険料などの特定の財源に係る決算剰余金が特定の財源を充当する経費以外に使われないよう、以下の区分で分割管理する
子ども・子育て支援勘定:積立金(事業主拠出金)および子ども・子育て支援資金(子ども・子育て支援納付金)
育児休業等給付勘定:育児休業給付資金(育児休業給付に充てる雇用保険料)
子ども・子育て支援特別会計の創設は、2025年度になる予定です。
参考:厚生労働省「令和6年雇用保険制度の改正内容について(子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律)」
雇用保険法改正による企業への影響と対策

雇用保険法改正による企業への影響と対策について紹介します。考えられる影響は次の4点です。
- 企業側が負担する保険料の増加
- 育児休業取得者の増加
- 保険加入手続きに関する業務の増加
- 就業管理の強化
1.企業が負担する保険料の増加
改正にともなう雇用保険適用拡大により被保険者数の増加が予想されるため、企業側の負担する保険料負担は増加します。
従来の社会保険への加入条件は、1週間の所定労働時間が20時間以上でした。改正により1週間の所定労働時間が10時間以上に変更され、新たに社会保険の適用対象となった人は、強制的に被保険者になります。
厚生年金保険や健康保険の保険料は、企業と従業員が折半するため、社会保険の加入者が増えるほど企業が支払う保険料も増えます。1週間の所定労働時間が10時間以上の従業員を多く抱える企業では、負担する保険料が大幅に増えるかもしれません。
なお、企業側は新たに加入対象となる短時間勤務者に対して、今回の制度の内容を周知しておくことも大切です。被保険者となった従業員は、将来の年金額は増えますが、社会保険料が控除されることで手取額は減ります。
2.育児休業取得者の増加
出生後休業支援給付金の支給が創設されることで、育児休業を1か月以上取得する男性が増える可能性が高まります。また、育児時短就業給付金の新設により、育児休業から復帰する際には、フルタイムではなく短時間勤務を選択するケースが増えるかもしれません。
育児休暇や短時間勤務を望む従業員が増えれば、企業は業務の再配分や短時間勤務者に対する環境整備が求められます。業務の属人化を解消しつつ、いつ誰が育児休暇に入っても業務が滞らない体制づくりを心がけましょう。
3.保険加入手続きに関する業務の増加
雇用保険拡大で被保険者の数が増加すれば、保険加入手続きに関する業務が増加する可能性があります。事業主が行う雇用保険の加入手続きは次のとおりです。
- 労働基準監督署に「保険関係成立届」を提出する
- ハローワークに「保険関係成立届の控え」と「雇用保険適用事業所設置届」を提出する
- ハローワークに従業員の「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する
「雇用保険被保険者資格取得届」は、従業員が雇用保険に加入する際に、都度提出が必要です。新規加入者が数人であれば手間はかからないかもしれませんが、大企業であれば手間や時間が多くかかる可能性があります。新たに加入対象となる従業員をあらかじめ把握しておきましょう。
なお、保険加入手続きに関する業務負担を軽減するためには、労務管理システムの導入がひとつの解決策です。労務管理システムとは、従業員の社会保険手続きや福利厚生の加入管理などを効率化できるシステムを指します。
労務管理システムの中には、社会保険手続きを電子申請で行えるものもあります。新規加入者が多い場合は、労務管理システムの導入を検討しましょう。
4.就業管理の強化
企業には、就業管理の強化も求められます。被保険者の条件が「1週間の所定労働時間が10時間以上」に変更になることで、短時間勤務者の労働時間の管理がより重要視されるためです。とくに、パートタイムやアルバイトなどの短時間勤務者の労働時間を正しく把握して、適切に管理することが求められます。
適切に管理できていないと労働基準法違反となる恐れもあるため、タイムカードや労働管理システムなどを導入して労働時間の適切な管理に努めましょう。
人事管理システム「ADPS」で就業管理をスムーズかつ正確に

企業の人事・総務部門では、今回の雇用保険の適用拡大により、新たに社会保険の適用対象者となった従業員に対する労働時間の管理や社会保険料の計算などに追われることになります。また、給与や年金など、お金に関連する手続きはミスが許されません。
給与計算を自動化できるシステムを導入することで、作業漏れやミスを防げるうえ、従業員の事務処理負担も軽減できます。
カシオヒューマンシステムズ株式会社が提供する人事管理システム「ADPS」は、1990年の誕生以来、累計5,000社を超える導入実績を重ねてきました。勤怠管理や給与計算などのフローを共有化できるため、属人化も防止できます。また、シフト管理の多様なパターン登録にも対応しており、アルバイトやパートタイマーなどがいる職場の管理コストを削減することが可能です。
人事管理システム「ADPS」を導入して、就業管理をスムーズかつ正確に行えるようにしましょう。
製品の詳細を知りたい方はこちら
まとめ

2024年成立の改正雇用保険法では、雇用保険制度に関する雇用保険法と子ども・子育て支援法の一部が改正されました。雇用保険の適用拡大により、1週間の所定労働時間が10時間以上に変更されます。また、育児時短就業給付や出生後休業支援給付金が新設される予定です。
一方で、雇用保険法改正による企業への影響も考えられます。なかでも、企業が負担する保険料や保険加入手続きに関する業務の増加をはじめ、就業管理の強化は企業にとって大きな責務です。
法改正に対応するためにも、労務管理システムの導入を検討してはいかがでしょうか。
製品の詳細を知りたい方はこちら
カシオヒューマンシステムズコラム編集チームです。
人事業務に関するソリューションを長年ご提供してきた知見を踏まえ、
定期的に「人事部の皆様に必ず今後の業務に役立つ情報」を紹介しています。




