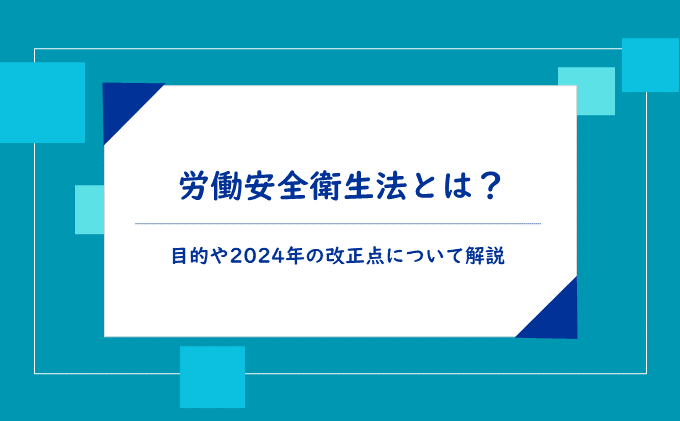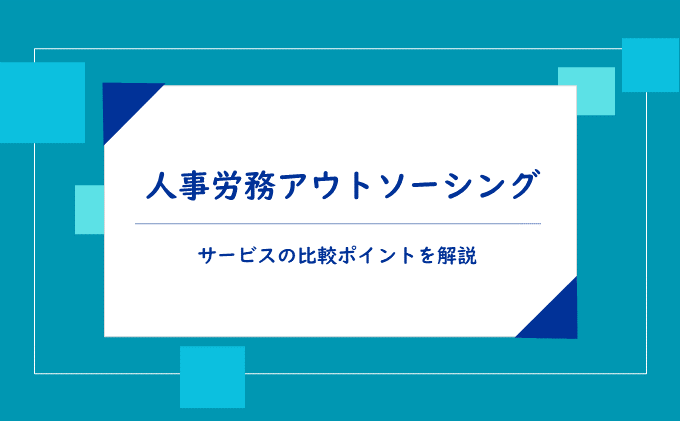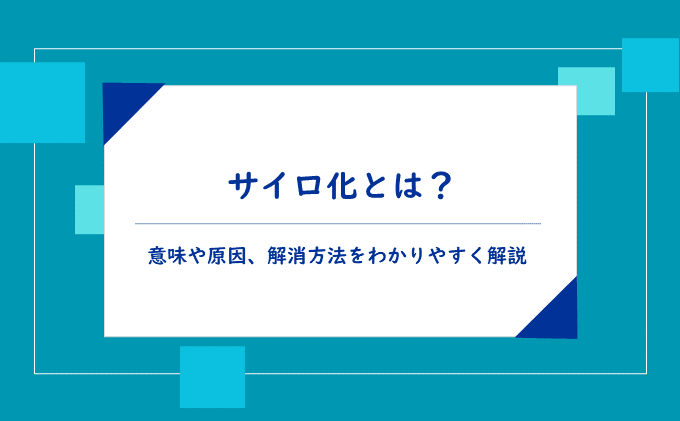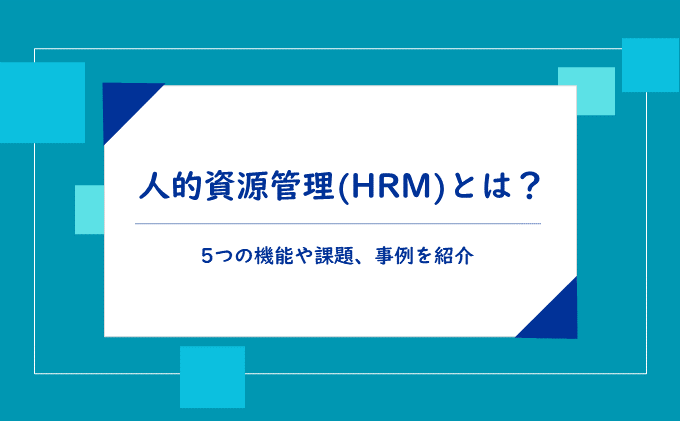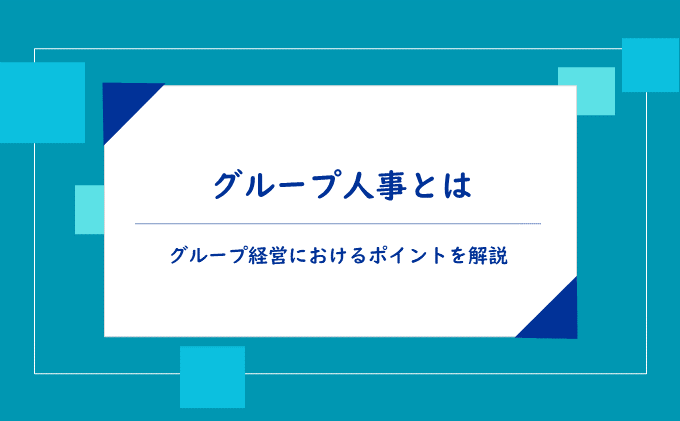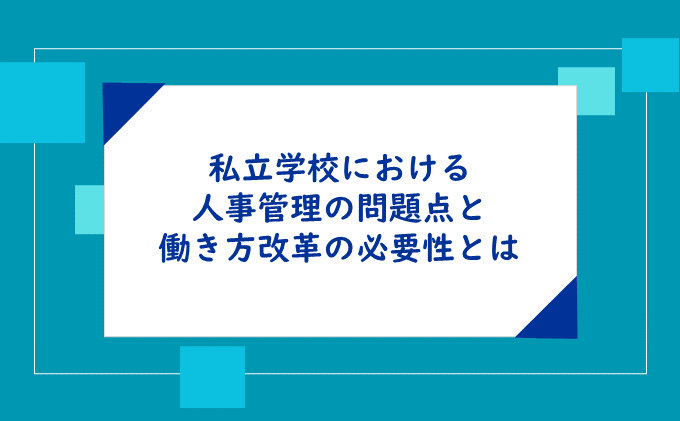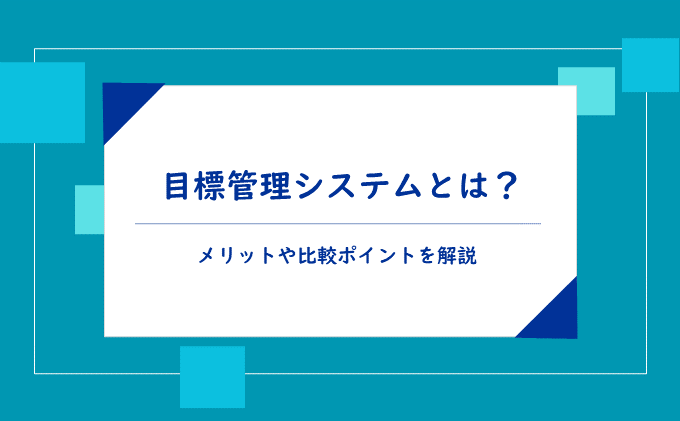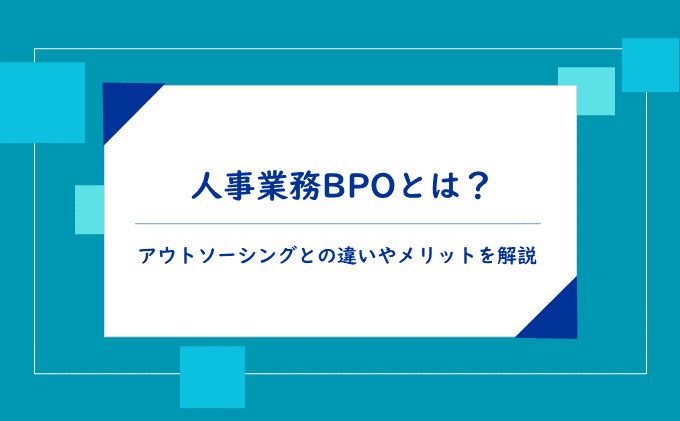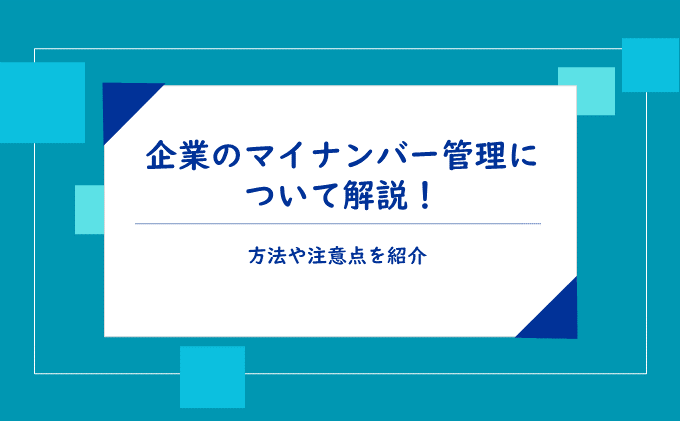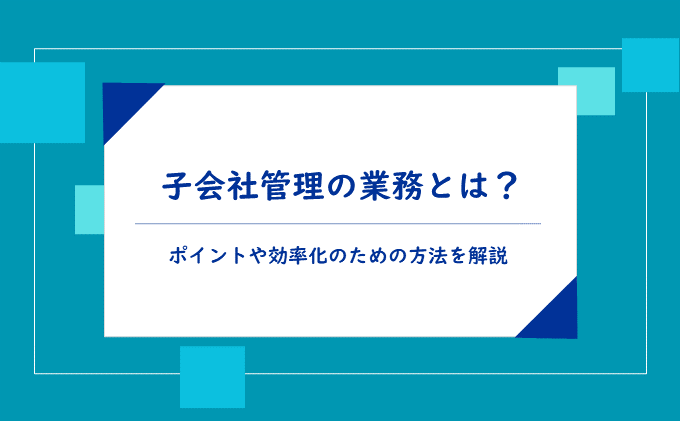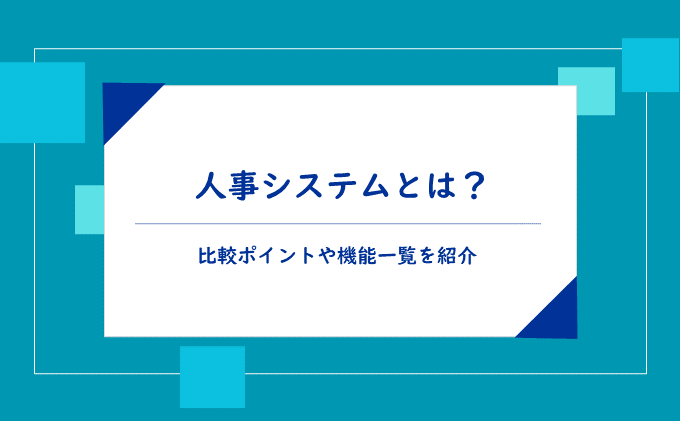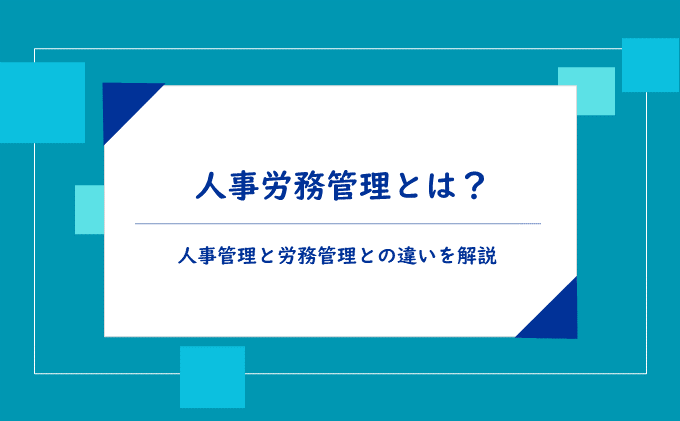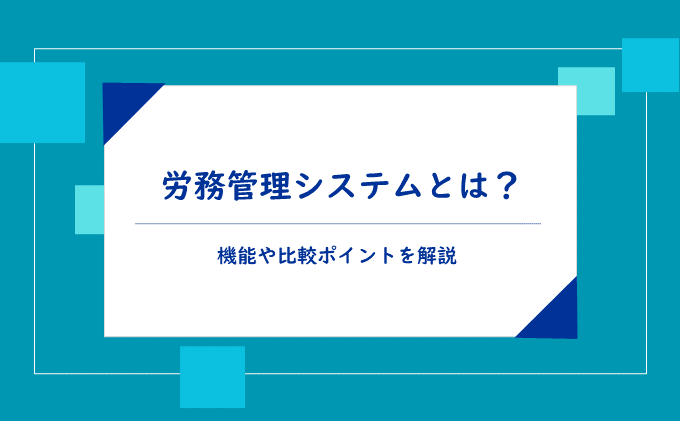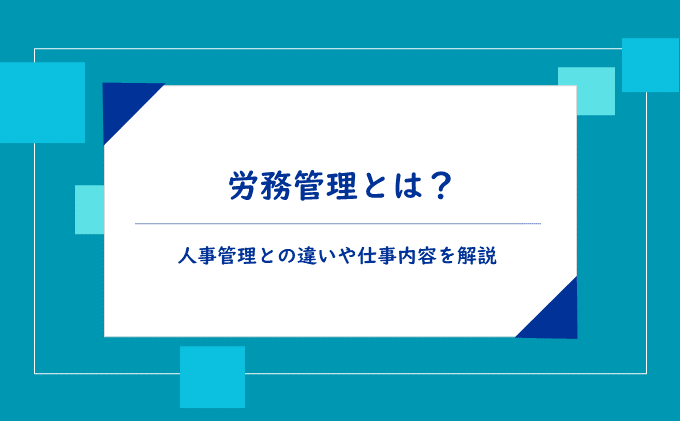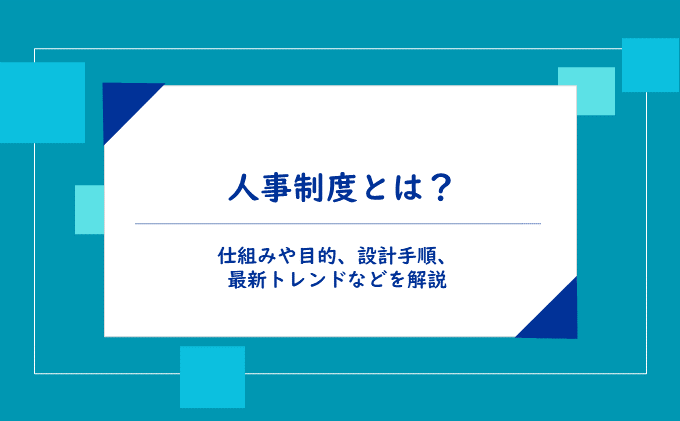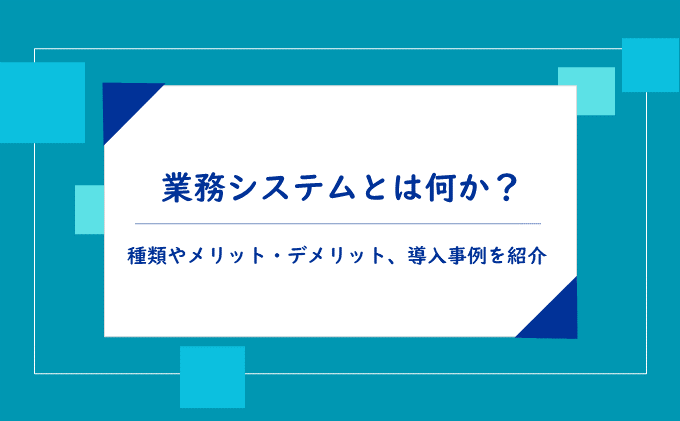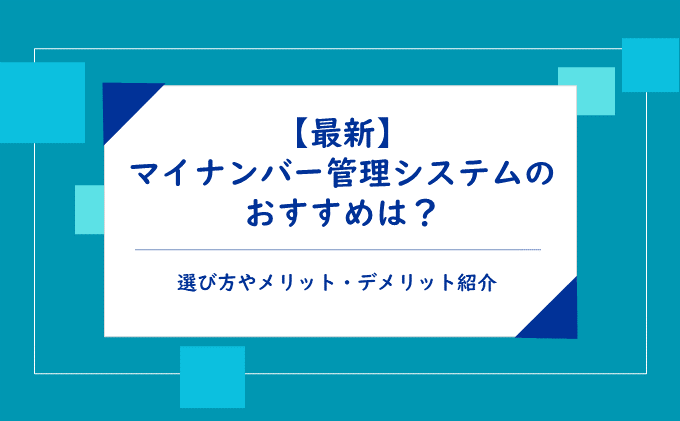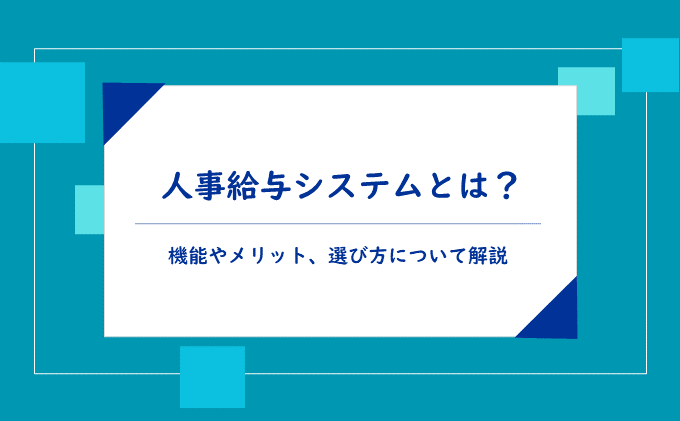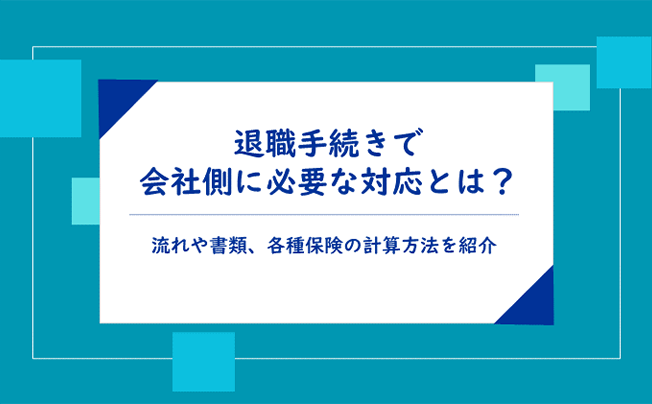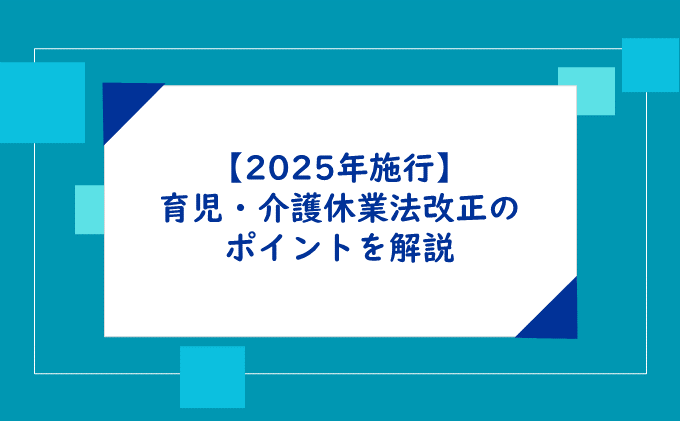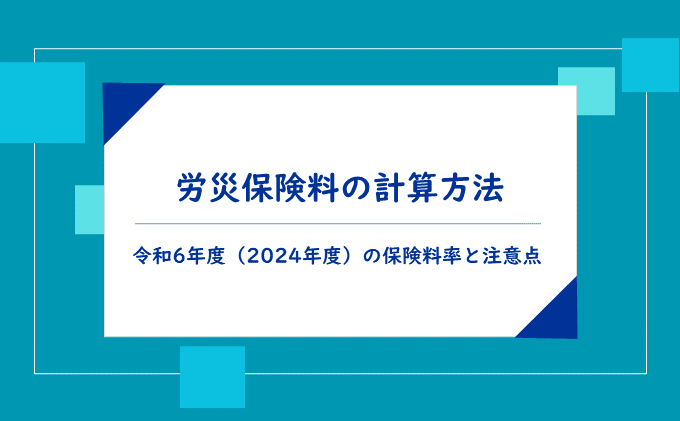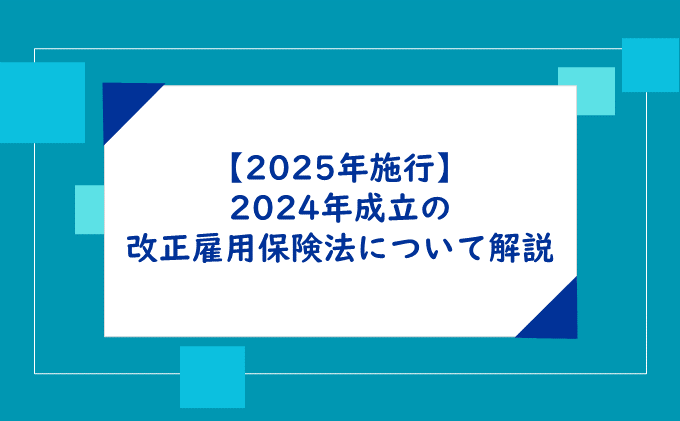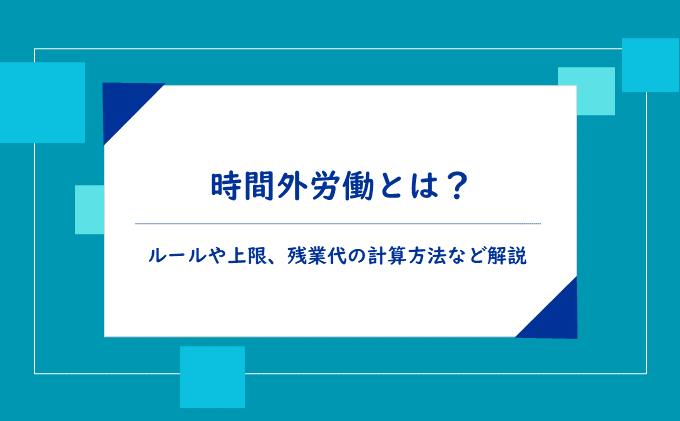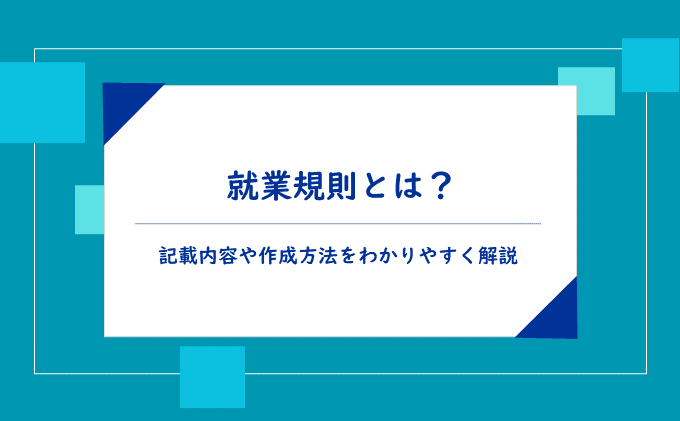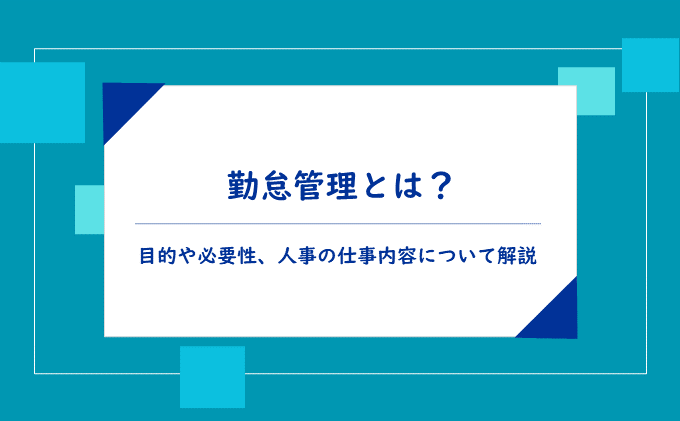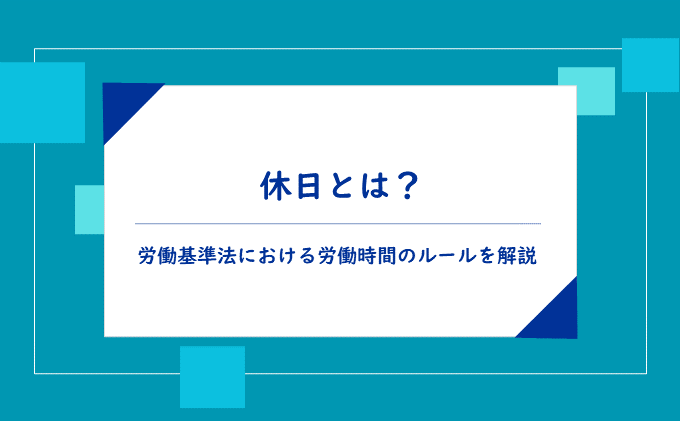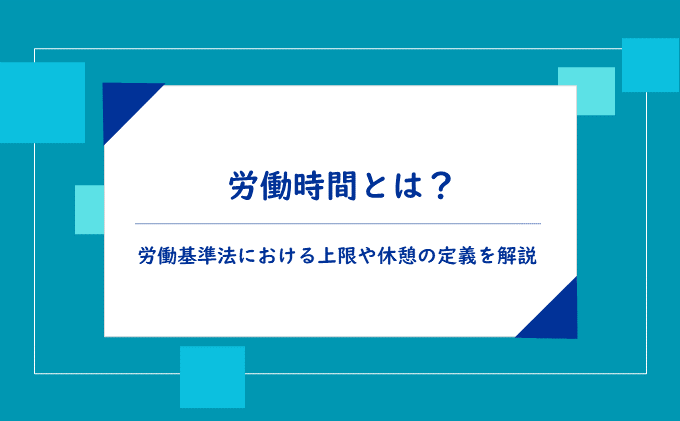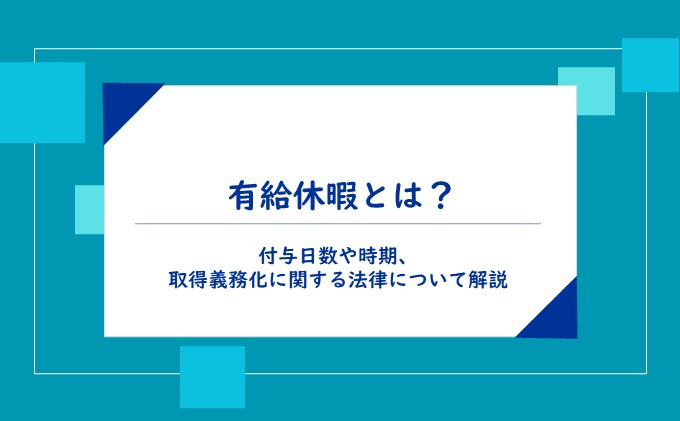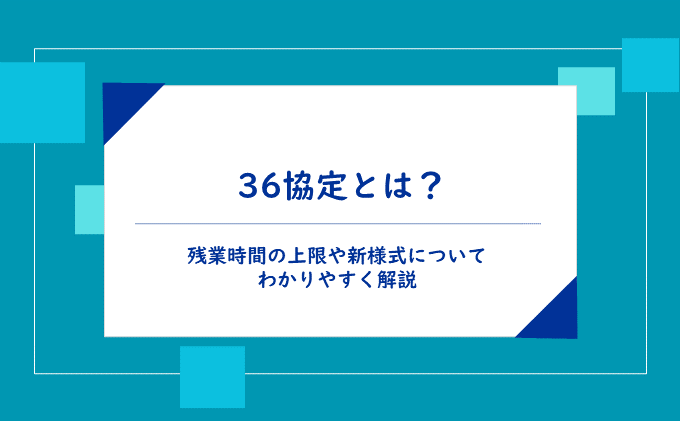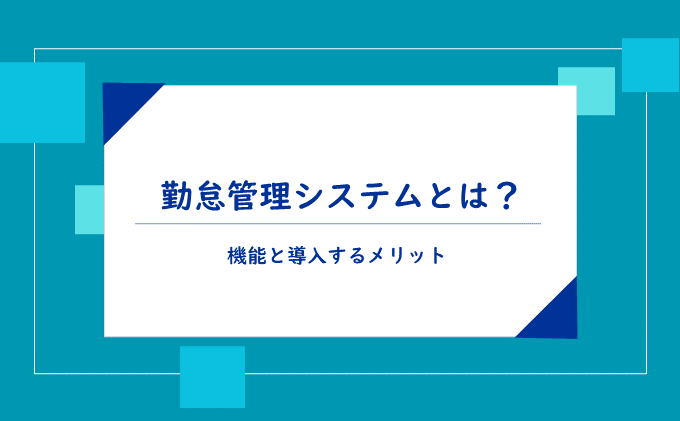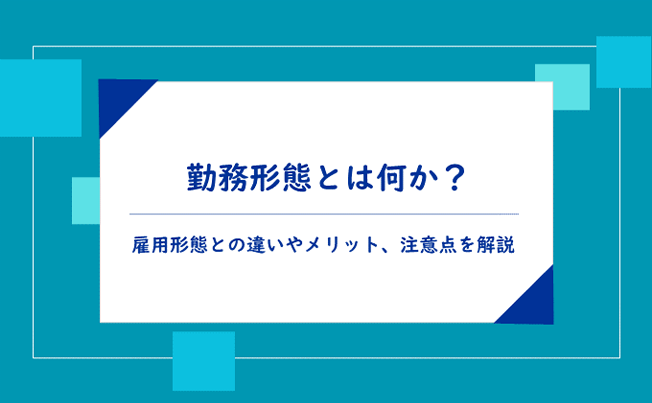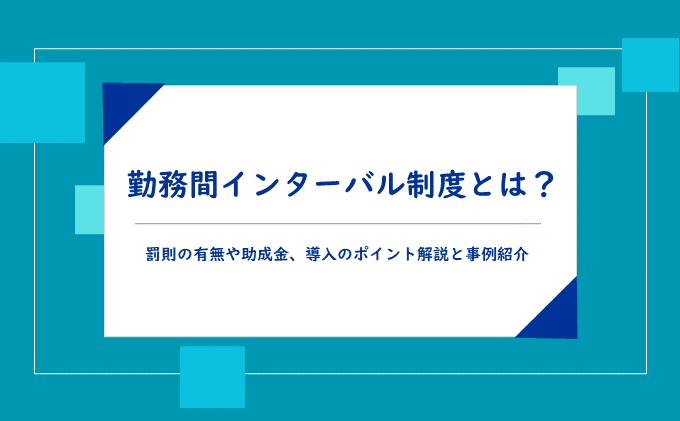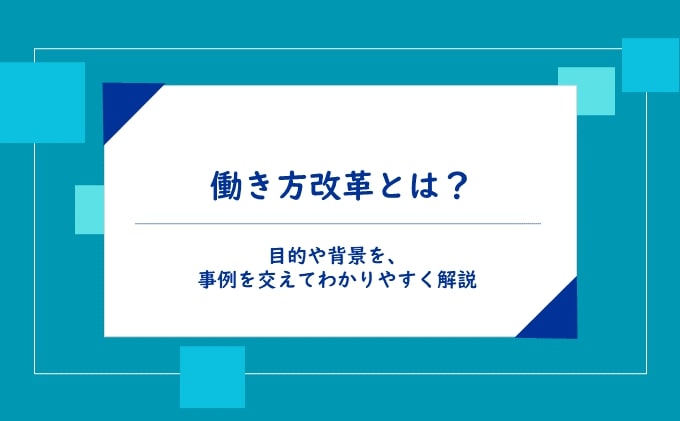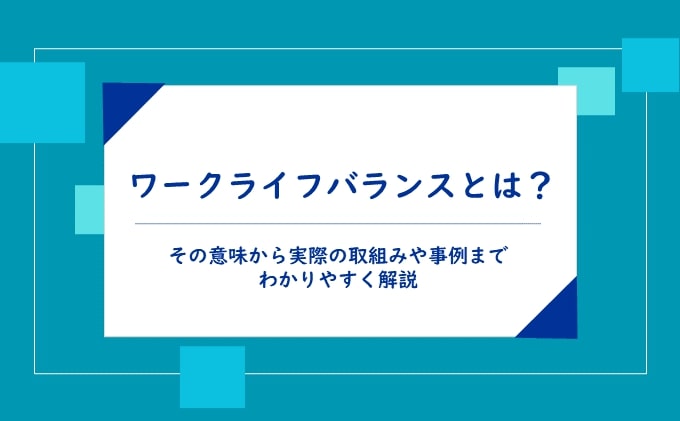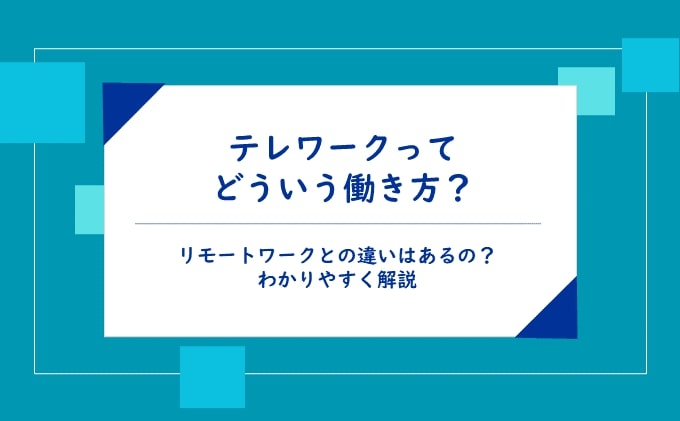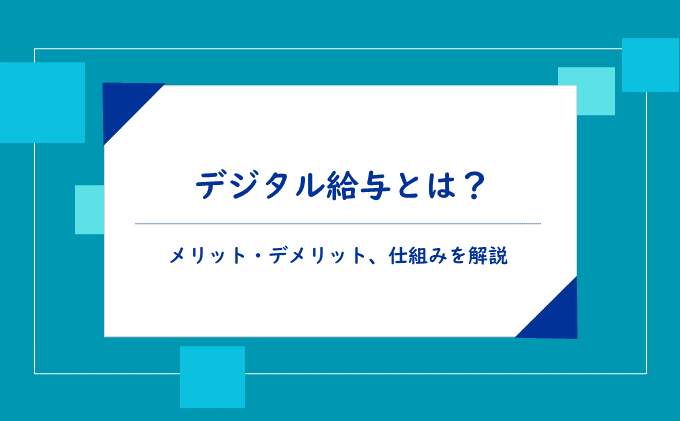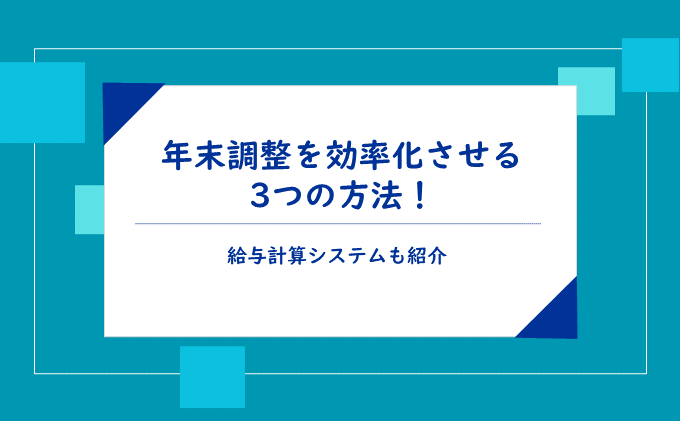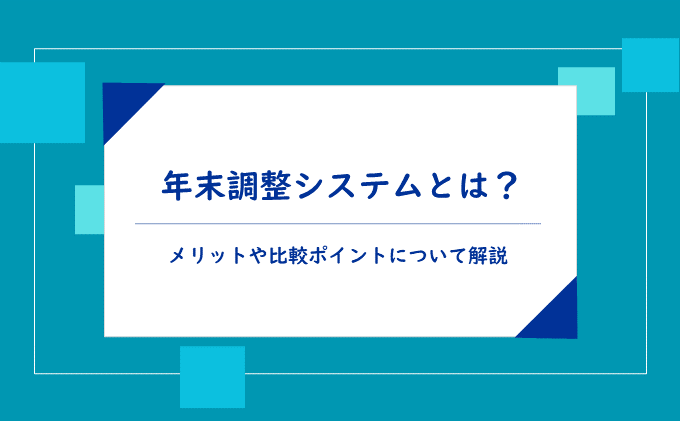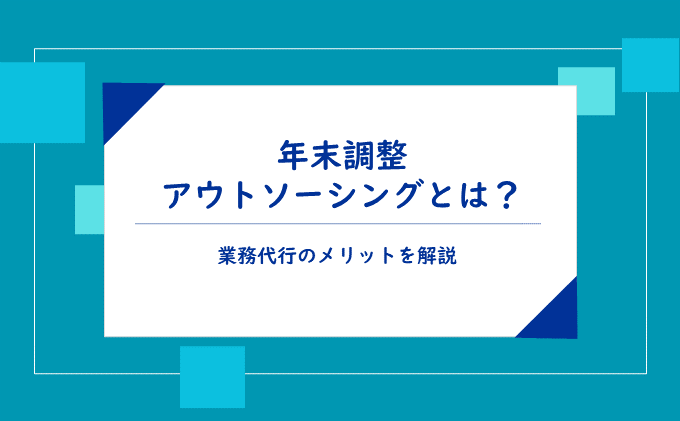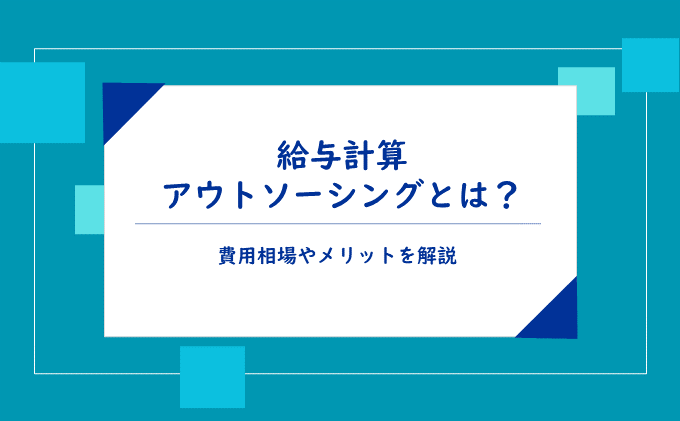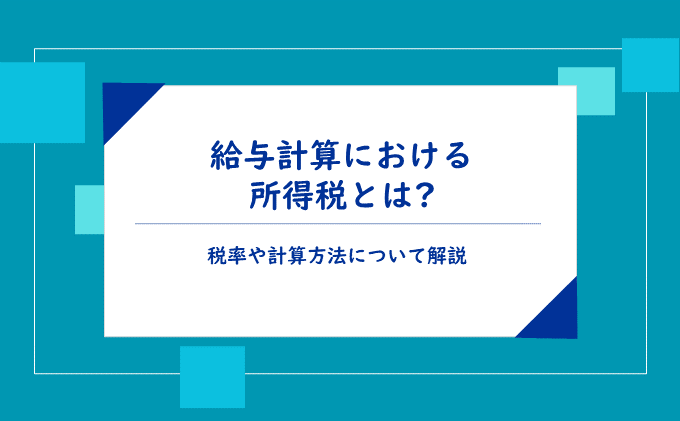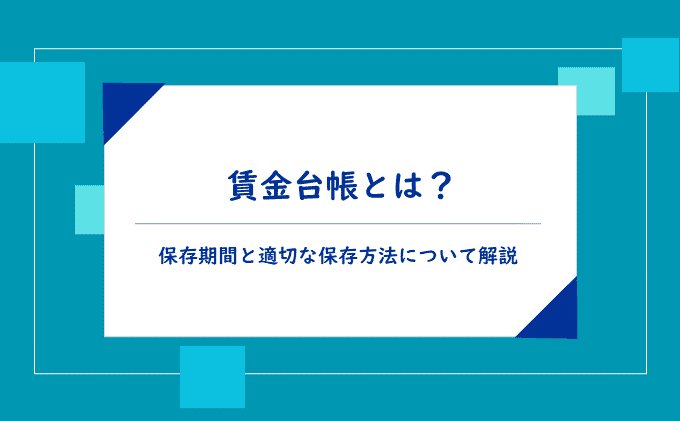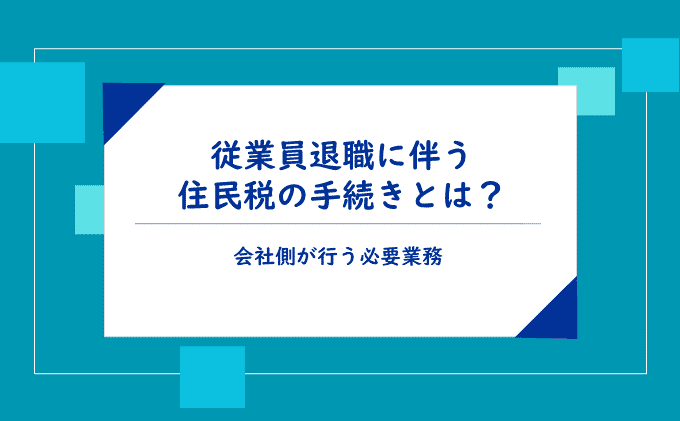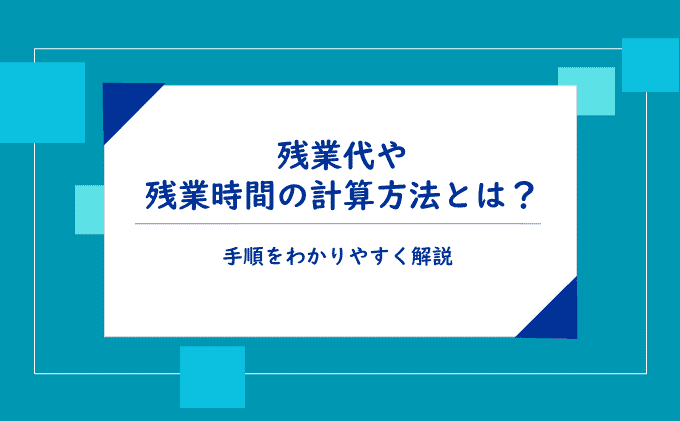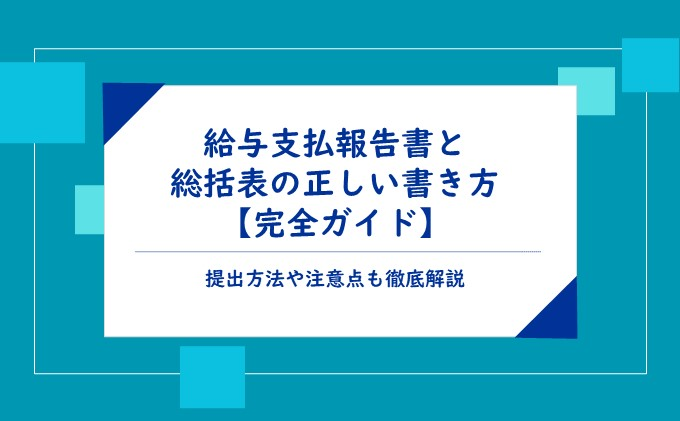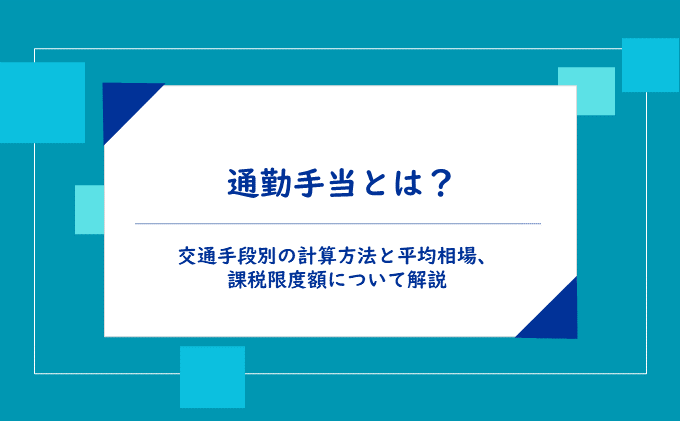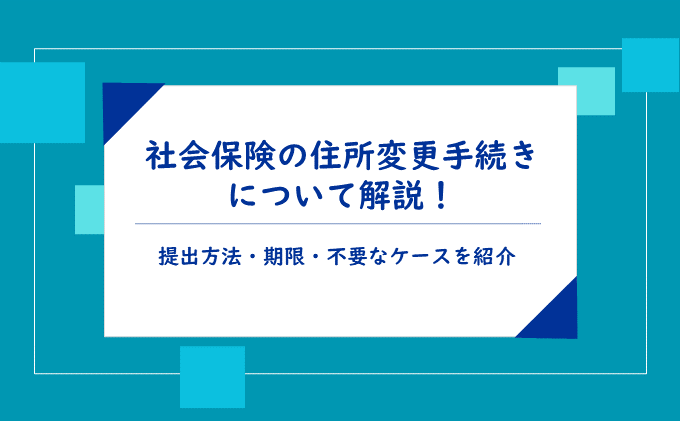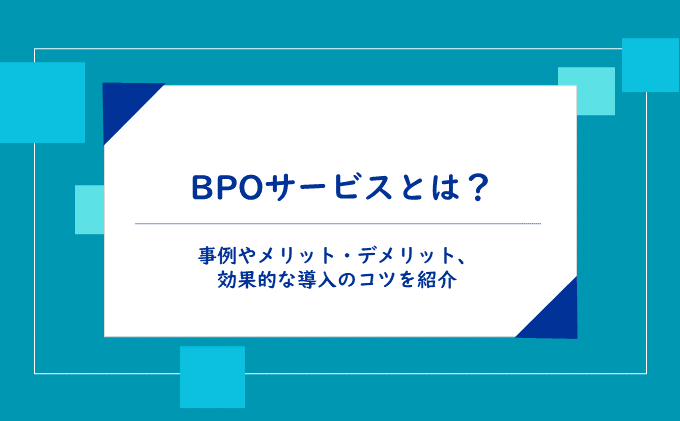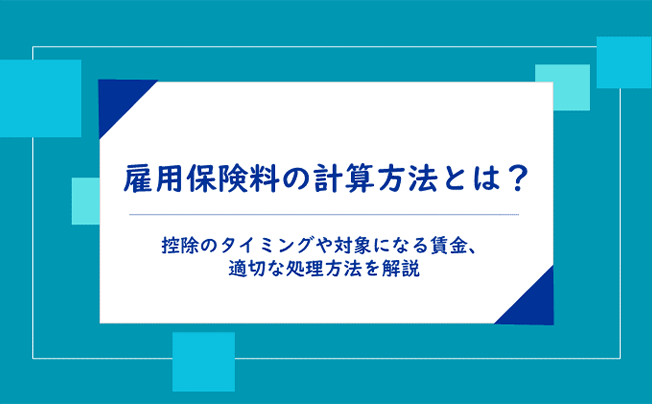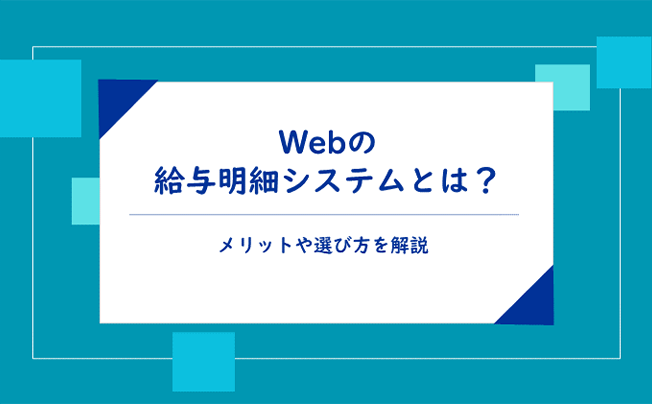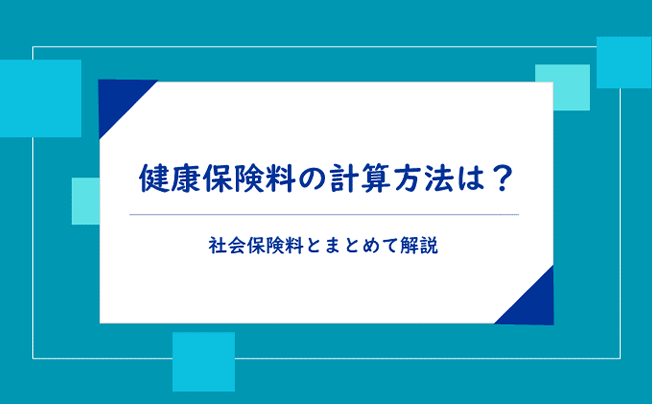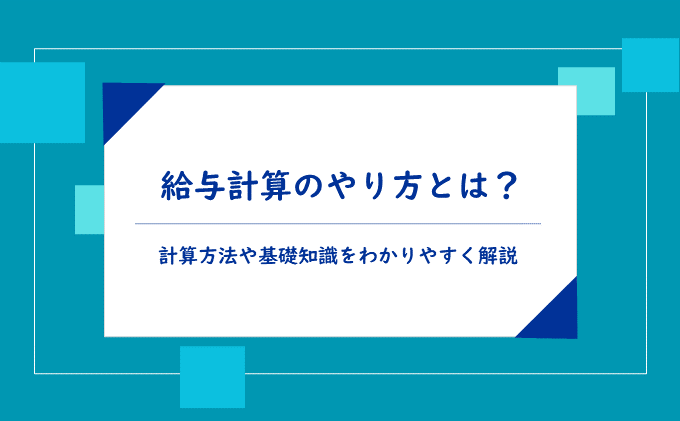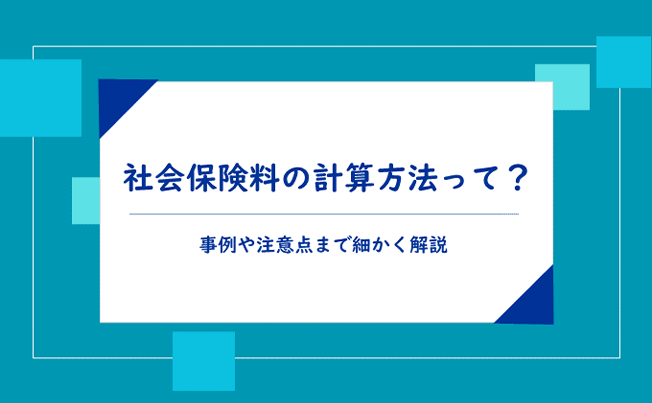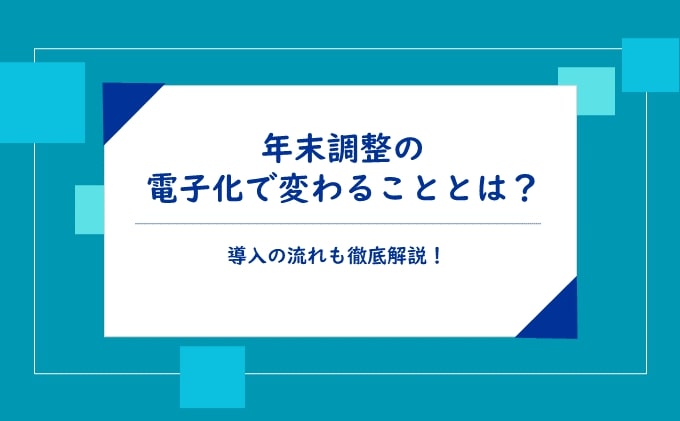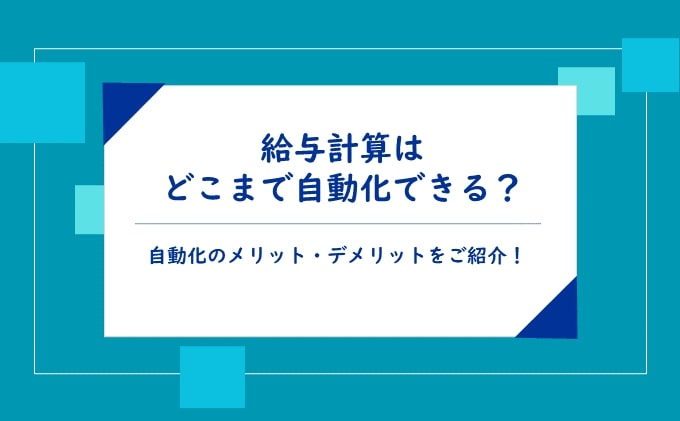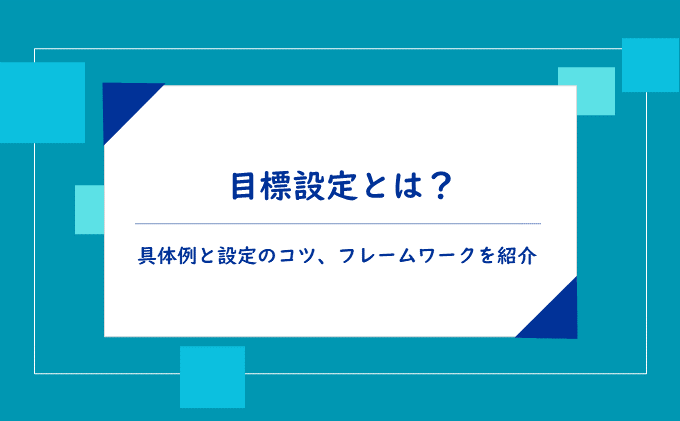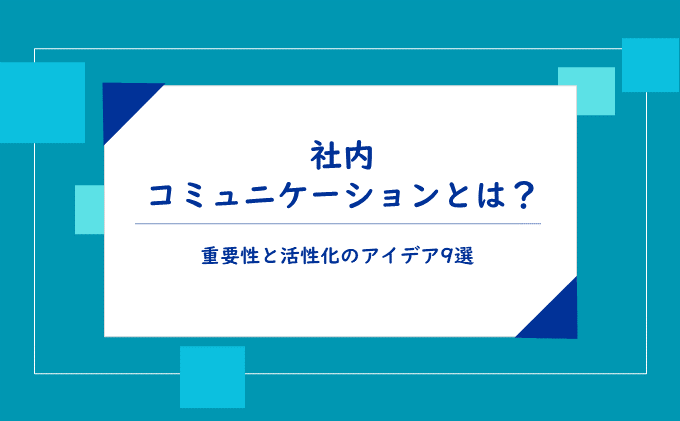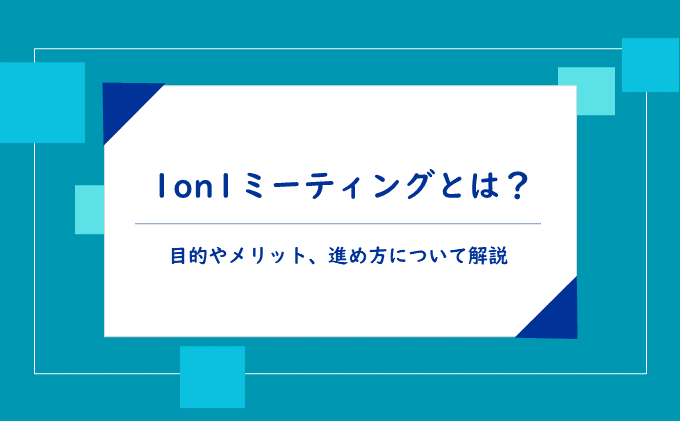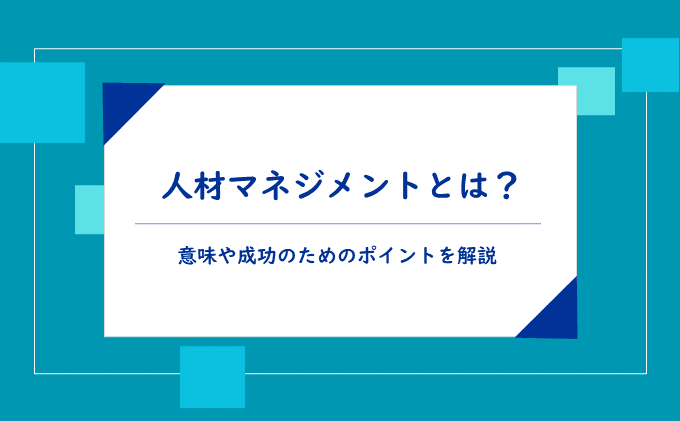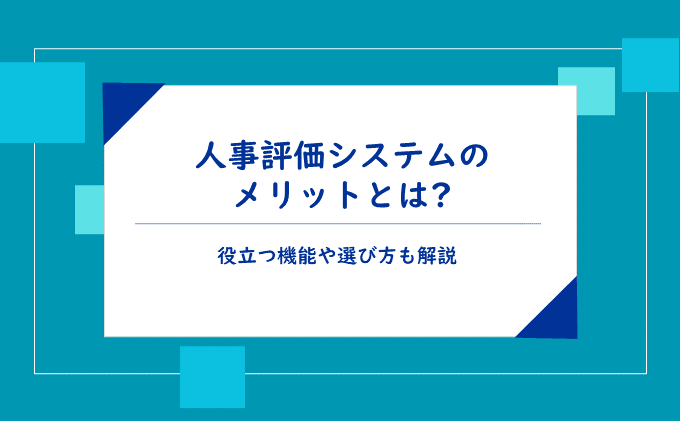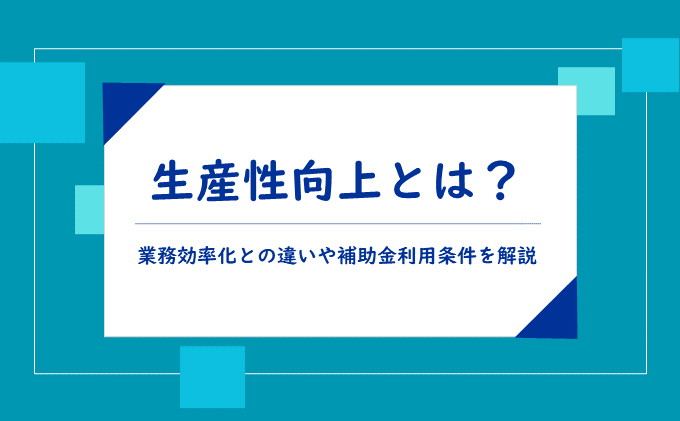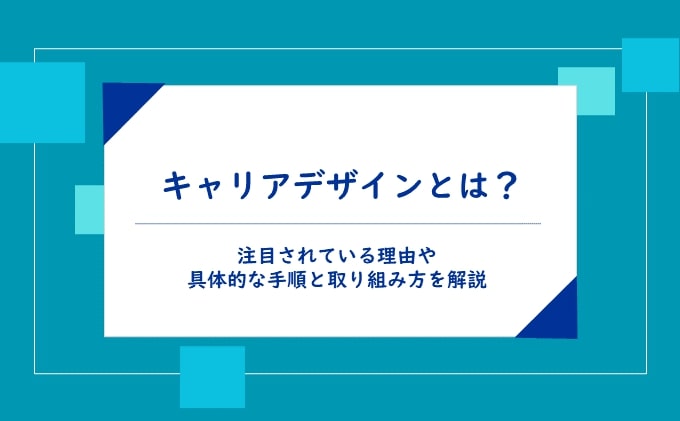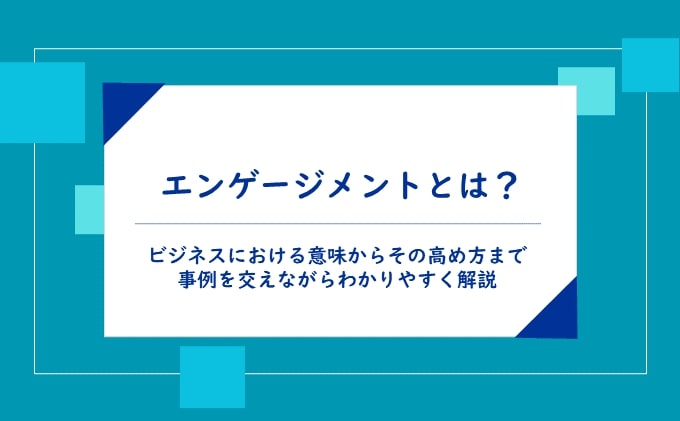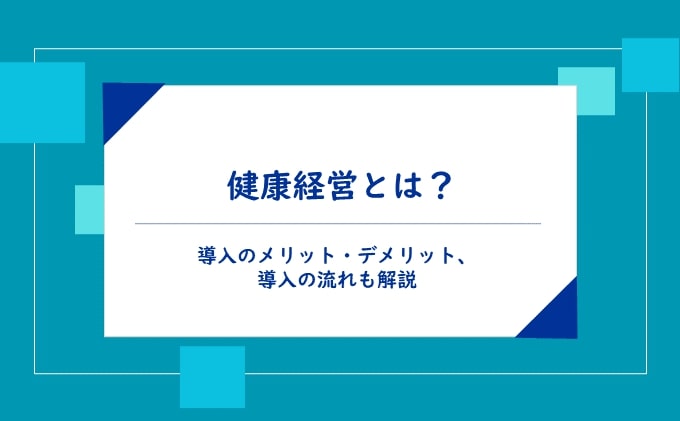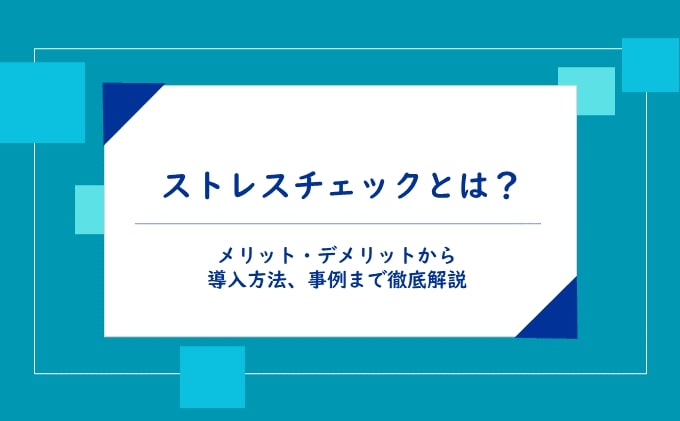給与所得控除とは?所得控除との違いや計算方法をわかりやすく解説
2025.03.19
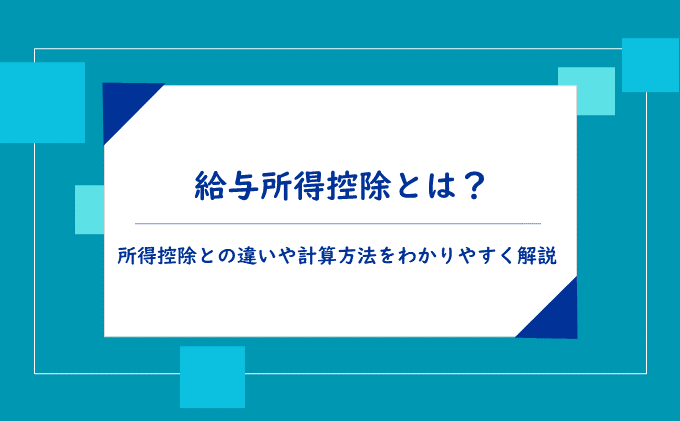
給与所得控除は、従業員などの勤務先から給与を得ている人が1年間の給与収入に応じて一定額を控除できる制度です。所得税の課税対象となる給与所得の算出に使用されます。経営者をはじめ、経理や労務担当者など、すべての立場の人が知っておくべき制度です。似たようなものに給与収入や所得控除がありますが、混同しないよう注意してください。本記事では、給与所得控除と所得控除との違いや、給与所得控除の計算方法をわかりやすく解説します。
目次
製品の詳細を知りたい方はこちら
「給与所得控除」とは

給与所得控除とは、企業から給与を受け取る給与所得者に適用される制度で、正社員だけでなく、アルバイトやパートなどにも適用される制度です。自営業者や事業所得者は、所得税の算出時に交際費や外注費などの必要経費を売上から差し引けます。
ただし、企業から給与を受け取る場合、スーツや文房具などの仕事で使用するためのものに対する支出であっても、経費として差し引きできません。一方の給与所得控除は、給与収入に応じて経費として差し引きできます。
また、給与所得控除は所得税の課税対象となる給与所得を算出するために用いられ、1年間の給与収入額に応じて一定額を控除することが可能です。給与所得控除として引かれた金額は、所得税の課税対象から除外されます。
本項では、給与所得や給与収入に含まれるものについて解説するとともに、パート年収のボーダーラインと言われる、103万円についても解説します。
そもそも「給与所得」とは
給与所得とは、従業員に支払われた給与や賞与から、経費に該当する給与所得控除額を差し引いた金額のことです。給与所得と似たような言葉に給与収入がありますが、実際には異なります。
給与収入は、勤務先から受け取る給与や賞与、残業代などを含む収入で、給与の額面を指します。一方の給与所得は、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額のことです。
自営業者や事業所得者は仕事で生じる支出を経費にできますが、給与所得者には経費計上ができません。ただし、給与所得控除では必要経費相当額を給与収入から一定額差し引きます。
給与収入に含まれるもの
給与収入には基本給や残業代をはじめ、家族手当や住宅手当などを含む給与や賞与、現物支給、経済的利益が含まれます。現物支給や経済的利益の一例は下記の通りです。
- 物品を無償で、または低価格で受け取った場合
- 会社が所有する土地や建物を無償、もしくは低価格で借りた場合
- 金銭を無利息、または低い金利で借りた場合
ただし、月額15万円以下の通勤手当や、一定金額以下の宿直、日直手当は給与収入の対象にはなりません。
給与所得控除額は給与収入額から算出されます。対象となるのは、1月1日から12月31日までの1年間に支払われた給与収入で、給与収入が複数ある場合はすべて合算した金額から算出します。
パート年収のボーダーライン「103万円」とは
パート年収のボーダーラインと言われる103万円とは、非課税になる年収のボーダーラインを指します。税制上、年収162万5千円までの給与所得控除額は一律55万円と定められています。非課税になる年収は55万円までと誤解している方もいますが、実際には給与所得控除以外にも基礎控除を受けることが可能です。
基礎控除は、納税者本人の所得金額が2,400万円以下であれば、収入から基礎控除額として48万円を差し引ける制度です。前述の給与所得控除の55万円と基礎控除額の48万円を合算すると103万円になります。パート収入が103万円までの場合、給与所得金額と基礎控除額を差し引くと所得金額が0円になるため、税金はかかりません。
関連記事:扶養から外れる手続きの方法は?条件やメリット・デメリットを紹介
給与所得控除と所得控除の違いとは

給与所得控除と似たような制度に所得控除がありますが、両者の控除内容は異なります。前述のとおり、勤務先から給与を得ている人が、1年間の給与収入に応じて一定額を控除できる制度が給与所得控除です。一方の所得控除は、個人的事情を考慮して所得税を減らす制度です。
所得控除の例として医療費や保険料などが挙げられますが、所得控除は一定の要件に該当する場合に適用され、給与所得から所得控除を際し引いて課税所得が算出されます。前述の基礎控除や配偶者控除など、所得控除は15種類に分類されており、控除ごとに差し引ける金額の計算方法は異なります。
所得控除を活用して多くの金額を所得から差し引くことで税金が減りますが、所得控除の適用を受けるためには自己申告が必要です。多くの所得控除は年末調整時に申請できますが、医療控除や雑損控除、寄付控除などは個人で確定申告しなければなりません。年末調整が主体であれば、控除申請を忘れないようにしてください。
給与所得と給与所得控除額の計算方法

給与所得は、1年間の給与収入から給与所得控除を除いた金額ですが、食事など現物で支給されたものも金額に換算して算出します。また、給与所得控除額を計算する際には給与収入に応じて定められた計算式を用いますが、計算式は頻繁に更新されています。直近では2020年の年末調整から計算式が変更されました。2020年以降の給与所得控除の計算式は下記の通りです。
| 給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 |
|---|---|
| 1,625,000円まで | 550,000円 |
| 1,625,001円から 1,800,000円まで | 収入金額 × 40% - 100,000円 |
| 1,800,001円から 3,600,000円まで | 収入金額 × 30% + 80,000円 |
| 3,600,001円から 6,600,000円まで | 収入金額 × 20% + 440,000円 |
| 6,600,001円から 8,500,000円まで | 収入金額 × 10% + 1,100,000円 |
| 8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、上の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)により給与所得の金額を求めます。
参考:No.1410 給与所得控除 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表(令和6年分)
例として、年収400万円の従業員の給与所得控除額を算出します。
400万円(給与収入) × 20% + 44万円 = 124万円
給与所得は、以下のように給与収入から給与所得控除を除いた金額です。
400万円(給与収入) - 124万円(給与所得控除額) = 276万円
給与所得者に関係する「特定支出控除」とは

給与所得者が受けられる控除のひとつに、給与所得控除以外にも転居や資格取得など、特定の支出をした場合に適用される特定支出控除があります。
特定支出控除は、接待や研修などの業務にかかった支出を自己負担した場合に受けられる控除で、給与所得控除額の1/2以上を超える支払いに適用されます。ただし、特定支出控除が受けられる対象の支出は、給与支払い者による特定支出としての証明が必要です。
年収600万円の従業員の場合、給与所得控除は166万円で、1/2にあたる84万円を超える自己負担があった場合に適用されます。
年末調整における給与所得の申告方法

給与収入がある場合、雇用元の企業が実施する年末調整により行われるのが給与所得の申告手続きです。
年末調整では、「給与所得者の基礎控除申告書」に必要事項を記入することで、給与所得控除額および所得金額を算出します。また、紙による申請の場合、「配偶者控除等申告書」と「所得金額調整控除申告」が加わります。正社員のみでなく、パートやアルバイトなど、年末調整の対象者全員の提出が必要です。
本項では、年末調整で提出が必要な3つの申告書についてそれぞれ解説します。
給与所得者の基礎控除申告書
基礎控除申告書は、正社員、パート、アルバイトなどの契約形態を問わず、企業が雇用する年末調整の対象者全員が提出しなくてはならない申告書です。
従業員自身が給与所得控除額を計算して所得金額を算出する必要があります。なお、所得金額は所得税額計算の基礎となるため、給与収入に何が該当するかを判断したり、計算ミスがないかを確認したりすることが重要です。
給与所得者の配偶者控除等申告書
配偶者控除等申告書は、申告者の配偶者に関連する控除を受けるために作成する申告書です。申告書に必要事項を記入して申告し、要件に該当すれば「配偶者控除」または「配偶者特別控除」が適用されます。配偶者控除は配偶者の所得が48万円以下の場合に、配偶者特別控除は配偶者の所得が48万円超133万円以下の場合にそれぞれ受けられます。
なお、年末調整をスムーズに実施するためには、配偶者のいる従業員に対して、配偶者の収入の事前確認を依頼することが重要です。ただし、「配偶者控除」および「配偶者特別控除」で定められている配偶者の所得金額には、年金や生命保険、損害保険の返戻金収入など、給与以外のものも含まれるため、満期保険金が振り込まれる場合などは注意が必要です。
また、配偶者控除等申告書は「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を受けるために必要な書類ですが、提出義務はありません。ただし、従業員の控除状況を把握するためにも、すべての従業員に提出を求めたほうがいいでしょう。
所得金額調整控除申告書
所得金額調整控除申告書は、「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の制度を受けるために作成する申告書です。
2020年から導入された制度で、2018年度の税制改正で給与所得控除額の10万円引き下げにより導入されました。給与所得控除の引き下げによる所得の増加が、税負担の増加につながる可能性があるため、税制改正の影響緩和のための制度です。
子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の対象は、申告者が得た給与収入が850万円超で、下記のいずれかに該当する場合です。
- 本人が特別障害者に該当する者
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
- 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者
控除額は給与収入に応じて変動し、最大控除額は15万円です。子どもがいることで適用される控除には扶養控除もあります。
扶養親族が16歳以上で夫婦いずれかの所得者にのみ適用されるのが扶養控除です。一方の子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除は、扶養親族が16歳未満であっても適用され、共働き世帯で夫婦双方の給与収入が850万円超であれば、控除がそれぞれに適用されます。
所得金額調整控除には「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」と「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」の2つがあります。
2つの控除は併用可能であるものの、年末調整では年金に関連する申告はできないため、「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」を利用する際には確定申告が必要です。
関連記事:給与計算のやり方とは?計算方法や基礎知識をわかりやすく解説
人事管理システム「ADPS」で年末調整業務をスムーズに

年末調整業務は、正社員、パート、アルバイトなど、年末調整対象者への申告書配布や回収が必要で、多くの手間と時間がかかります。また、給与所得控除額や所得額の算出は所得税額計算の基礎となるため、確認作業が重要です。年末調整業務をスムーズに実施したいのであれば、人事管理システムの導入が効果的です。
カシオヒューマンシステムズ株式会社では、年末調整や給与計算などの人事業務を一元管理できる人事管理システム「ADPS(アドプス)」を提供しています。人事、給与、申請などの人事業務をトータルにサポートするため、年末調整業務に向けて導入を検討してはいかがでしょうか。
製品の詳細を知りたい方はこちら
まとめ

給与所得控除とは、1年間の給与収入に応じて一定額を控除できる制度で、所得税の課税対象となる給与所得の算出に使用されます。所得控除と混同されることがありますが、給与収入に応じて一定額を控除できる給与所得控除とは異なります。
年末調整業務は、似たような制度が多くわかりにくいうえ、申告書の配布や回収、記載内容の確認などに多くの手間と時間がかかる作業です。
年末調整業務をスムーズに行いたいのであれば、カシオヒューマンシステムズ株式会社が提供する、人事管理システム「ADPS(アドプス)」の導入を検討してはいかがでしょうか。人事業務をトータルにサポートしているため、年末調整業務だけでなく、給与計算などの人事業務に対する負担の軽減や効率化が期待できます。
製品の詳細を知りたい方はこちら
カシオヒューマンシステムズコラム編集チームです。
人事業務に関するソリューションを長年ご提供してきた知見を踏まえ、
定期的に「人事部の皆様に必ず今後の業務に役立つ情報」を紹介しています。