短時間労働者に対する社会保険の適用拡大│2024年10月からの変更点など解説
2025.03.19
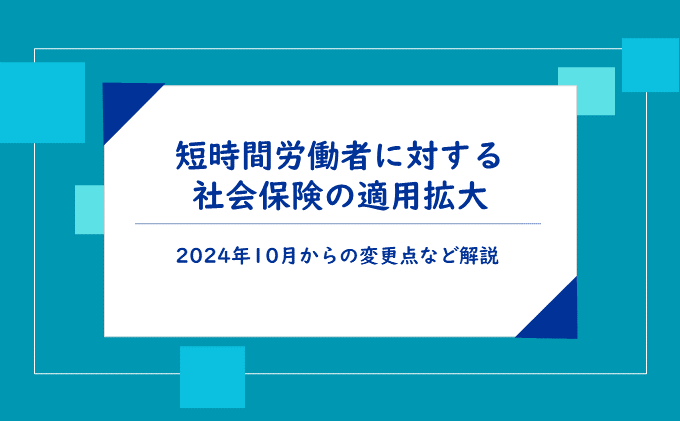
2024年10月に社会保険の加入対象が拡大されました。社会保険の対象になると、年金が増額されたり、公的な医療保険が充実したりするなどのメリットがあります。本記事では、社会保険の適用拡大について、具体的な内容や企業に求められる対応を解説します。
目次
製品の詳細を知りたい方はこちら
2024年10月│短時間労働者に対する社会保険の適用要件が拡大

2024年10月から、短時間労働者に対する社会保険の適用要件が拡大されました。短時間労働者とは、主にパートやアルバイトとして就労する人たちのことです。短い時間で働く人の数が増えていることから、社会保険の適用範囲が拡大されました。
社会保険とは、厚生年金保険と公的医療保険(健康保険)のことです。適用要件が拡大されたことにより、これまでは国民健康保険に加入していた従業員も厚生年金保険の被保険者となり、健康保険組合や協会けんぽに加入できるようになります。
将来の年金に厚生年金保険分が上乗せされれば、医療保険も給付が充実するなどのメリットが生まれます。国民健康保険の保険料は加入者が全額を支払う必要がありますが、健康保険組合や協会けんぽの保険料は原則として企業と加入者の折半です。
また、企業が適用拡大の対象になると、厚生年金保険料と健康保険料の半額を、新たに支払わなければなりません。企業の負担は増えますが、従業員の福利厚生が充実し、求人を行う際には「社保完備」をアピールできるため、企業の魅力度アップが期待できます。
「特定適用事業所」とは

適用拡大の要件を満たす企業を「特定適用事業所」と呼びます。2024年10月からは、従業員51~100人の企業が該当するようになりました。支店があるケースなどは、合計の従業員数が判断基準です。
従業員数51人以上
適用拡大は、従業員数51~100人の企業が対象です。対象は2016年10月以降、段階的に拡大されてきました。2016年10月からは従業員500人超の企業が、2022年10月からは従業員数101~500人の企業が対象になっています。
対象従業員のカウント方法
対象となるかどうかの基準は、企業に勤めている人数ではなく、厚生年金保険の被保険者総数です。被保険者の総数が50人を超える月が、直近11か月のうち6か月以上あると見込まれる場合は対象になります。
従業員数として計算されるのは、「フルタイムの従業員数」と、「週あたりフルタイムの4分の3以上の労働時間がある従業員数」の合計です。パートやアルバイト、契約社員などであっても、週の労働時間がフルタイムの4分の3以上あれば人数に含まれます。
従業員数50人超という基準に満たない企業でも、企業から申し出ることにより社会保険に加入させることが可能です。労使間で合意していることが条件です。このような企業を「任意特定適用事業所」と呼びます。
「任意特定適用事業所」の概要

任意特定適用事業所になるためには、「労使合意」が必要です。労使合意は、以下のどちらかを満たすことで得られます。
- 労働組合がある場合は、労働組合の同意
- 労働組合がない場合は、従業員の過半数を代表するもの(または従業員の過半数)の同意
任意特定適用事業所となるための手続きは、年金事務センターか管轄の年金事務所で行います。
手続きに必要な書類は、以下のとおりです。
- 任意特定適用事業所申出書/取消申出書
- 労使合意を得ていることを示す従業員側の同意書
- 労働組合や従業員の代表であることを示す事業主の証明書
任意特定適用事業所申出書は、取消手続きの際に使う取消申出書と一体になった様式です。郵送または窓口に持参して提出します。
短時間労働者の要件は5つ

社会保険の適用拡大の対象となる短時間労働者は、以下の5つが要件です。
- 対象企業に勤務している
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月収8.8万円以上
- 学生ではない
- 2か月以上雇用される見込みがある
以下の項で、それぞれについて説明していきます。
1.対象企業に勤務している
短時間労働者の要件として、社会保険の適用対象となる企業に勤めていることが必須です。具体的には、特定適用事業所や任意特定適用事業所をはじめ、国や地方公共団体に属する事業所に勤務している人も含まれます。
対象企業に勤めており、週あたりフルタイムの4分の3未満の労働時間がある従業員であれば、短時間労働者に該当します。
2.週の所定労働時間が20時間以上
短時間労働者は、週の「所定労働時間」が20時間以上であることが条件です。
所定労働時間とは、通常の1週間に働くべき時間として、雇用契約や就業規則などで定められた時間をいいます。
「短時間」と名称にありますが、勤務時間が20時間に満たない場合は該当しません。
3.所定内賃金が月額8.8万円以上
短時間労働者の要件として、月収が8.8万円以上であることも必要です。ここでいう月収は「所定内賃金」と呼ばれ時給や日給、週給を月額に計算し直し、各種手当を含めた金額です。ただし、以下のような手当などは含まれません。
- 賞与や結婚手当のような、1か月を超えない期間で支払われたり、臨時に支払われたりするもの
- 割増賃金など、時間外労働や休日出勤、深夜業に対して支払われるもの
- 通勤手当や家族手当など、最低賃金法で算入しないと定められているもの
月収8.8万円は12倍すると105.6万円で、年収約106万円に相当します。社会保険料の支払いが発生し、手取り収入が減少するのを防ぐためにパートやアルバイトで雇用されている人が働き控えを行う「106万円の壁」は、この項目と関係しています。
※2024年12月時点、現在106万円の壁について国会などで審議されている通り、今後上記の内容に変更が生じる可能性があります。
4.学生ではない
パートやアルバイトでも、学生であれば短時間労働者に該当しません。
ただし、以下のようなケースでは、学生であっても短時間労働者とカウントされます。
- 高校や大学の夜間部、定時制などに通学している
- 休学中の学生
- 卒業見込証明書が発行されていて、すでに就職しており、卒業後も同じ企業などに勤務する予定の学生
5.雇用見込みが2か月以上
短時間労働者の要件として雇用される期間が2か月以上見込まれることも必要です。契約は2か月間だけでも、3か月目以降も契約が継続する可能性があれば「2か月以上の雇用の見込みがある」と判断されます。
2か月以上の見込みを必要とする点は、正社員など一般の社会保険の被保険者と同様です。
社会保険の適用対象となった企業がすべき対応

社会保険の適用対象となった企業がすべき対応は、以下のとおりです。
- 対象者の把握と従業員への周知
- 書類の作成・届出
それぞれについて、以下から詳述します。
対象者の把握と従業員への周知
まずは、短時間労働者に該当する対象者の把握を行いましょう。人事システムを導入している企業であれば、データベースから検索できる可能性があります。
対象者が把握できれば、周知を行ってください。周知する内容は、以下のとおりです。
- 社会保険の説明
- 社会保険に加入するメリット
- 社会保険料の自己負担が発生し手取り収入が減少すること
社会保険加入のメリットには、年金と医療の両面があります。厚生年金保険に加入することになるため、将来受け取れる年金額が基礎年金よりも増額されることがメリットです。
病気やけがなどで障害状態と認定された場合には、障害年金が受け取れます。遺族が受け取れる遺族年金の制度もあります。
また、医療の面では、健康保険から傷病手当金や出産手当金が給付されるようになることがメリットです。傷病手当金は業務外のけがや病気で4日以上休業した場合、4日目以降、原則として支払われなかった給与の3分の2相当が給付されます。期間は最長で、通算1年6か月です。
出産手当金は、出産のために会社を休んでいた期間に支払われなかった給与の3分の2相当を受け取れる制度です。多胎妊娠でない場合には、出産前42日と出産後56日までが範囲となります。
次に、対象者にシミュレーション結果を示すことで、手取り額の減少に対する理解度が高まり、不安を払拭できます。
また、説明会の開催や、個人面談などを行うこともおすすめです。対象者に周知をはかり、納得してもらったうえで社会保険に加入してもらうことが望ましいといえます。
社会保険は要件を満たせば加入するのが原則です。しかし、新たな自己負担が発生することを嫌って、加入を拒否する人がいるかもしれません。そのような場合は、人生設計や労働時間についての考え方などを話し合い、十分な理解を得たうえで加入するかどうかを決めてもらうことが重要です。
書類の作成・届出
適用拡大の対象となった企業には、日本年金機構から通知が届きます。通知が届いたら、厚生年金保険の被保険者資格取得届を準備します。書式は日本年金機構のホームページからダウンロード可能です。
被保険者資格取得届は、オンラインで届出ができます。
人事管理から給与確認まで「ADPS」が人事業務を効率化

カシオヒューマンシステムズ株式会社が提供する人事管理システム「ADPS(アドプス)」は、1990年の登場以来、累計5000社以上に導入されています。複雑な業務手順を、ビジュアル化したフローでわかりやすく表示できる点が特徴です。
蓄積された人事データをさまざまな条件指定で検索でき、社会保険の業務で対象者をピックアップすることも容易です。
製品の詳細を知りたい方はこちら
まとめ

2024年10月から、短時間労働者に対する社会保険の適用が「従業員51人以上」の企業に拡大されています。適用対象となった企業は、新たに社会保険に加入する従業員の把握や、対象者に制度に対する説明を行わなくてはなりません。
人事システムを導入していれば、対象者の把握や、加入後の社会保険関連の業務がスムーズに進むことが期待できます。人事・給与系の業務は間違いが許されないことであり、担当者には負荷がかかります。社会保険の適用拡大を契機にシステムを導入して、負担が少なく生産性が高い人事部門を目指してはいかがでしょうか。
製品の詳細を知りたい方はこちら
カシオヒューマンシステムズコラム編集チームです。
人事業務に関するソリューションを長年ご提供してきた知見を踏まえ、
定期的に「人事部の皆様に必ず今後の業務に役立つ情報」を紹介しています。





