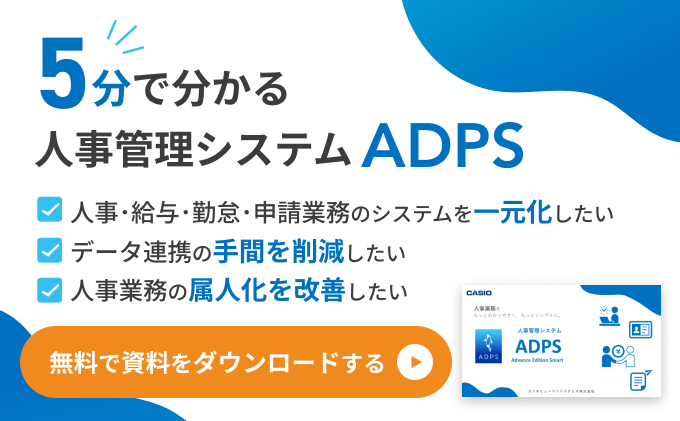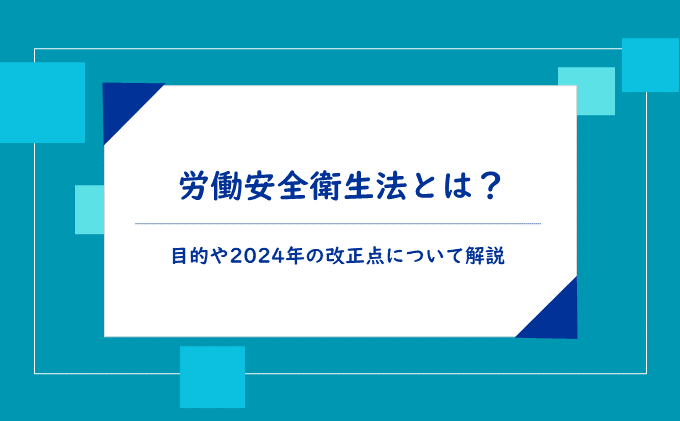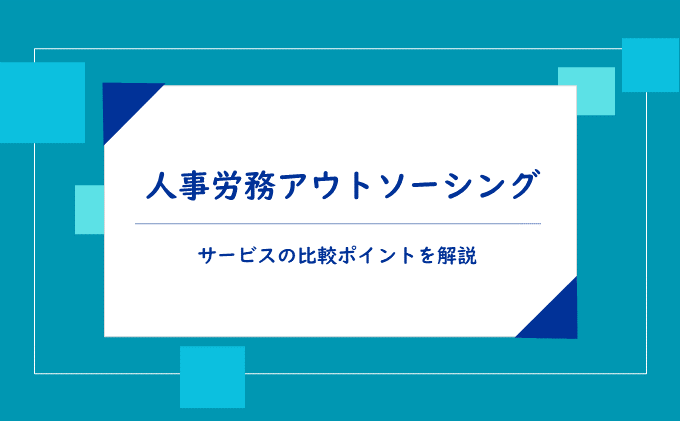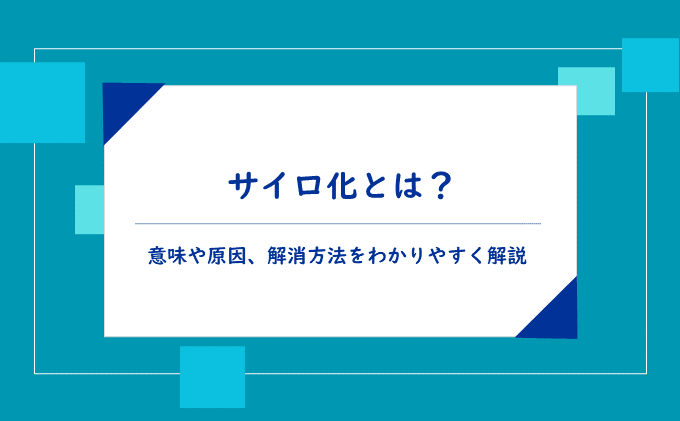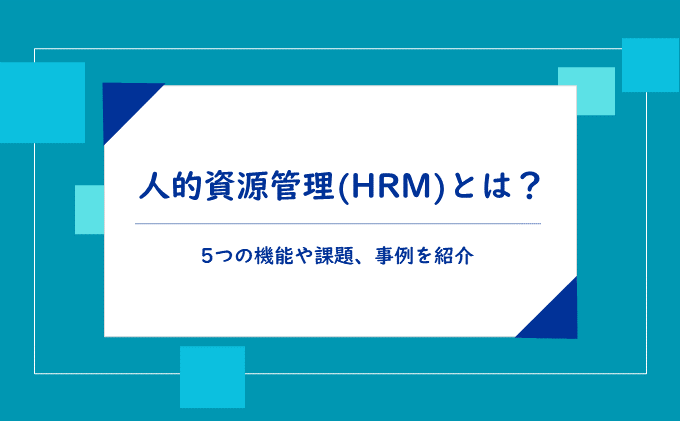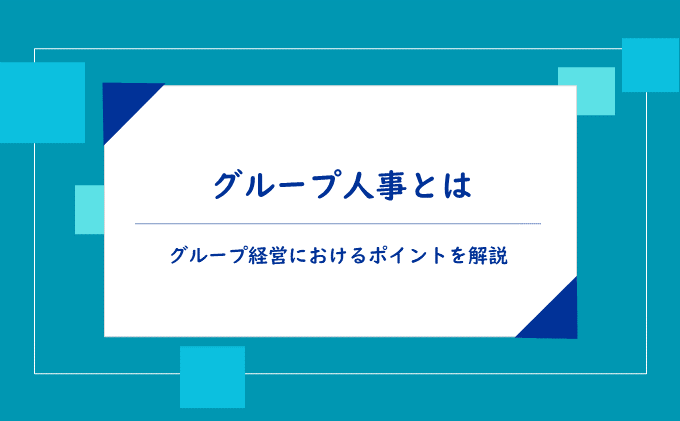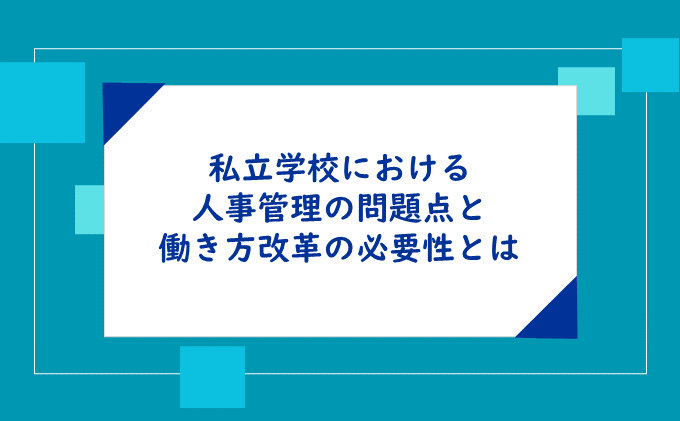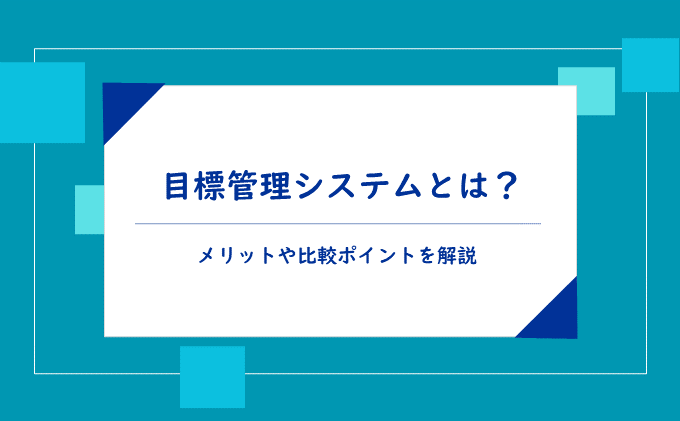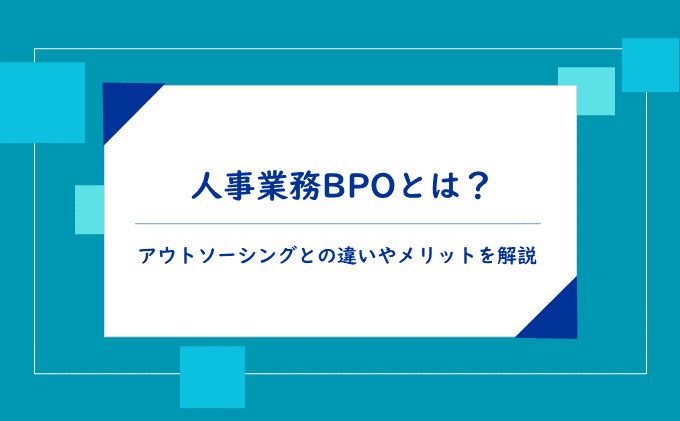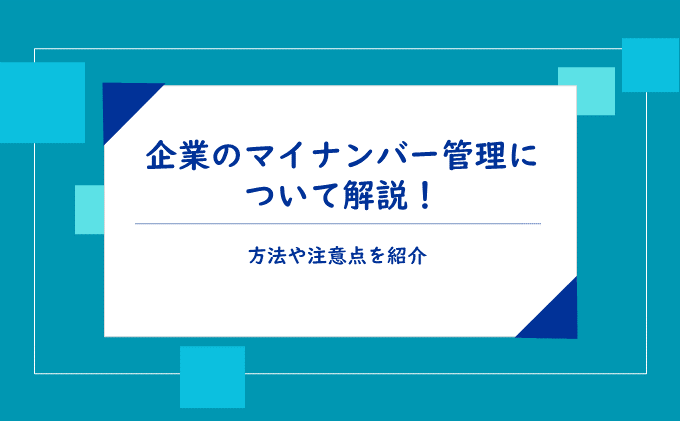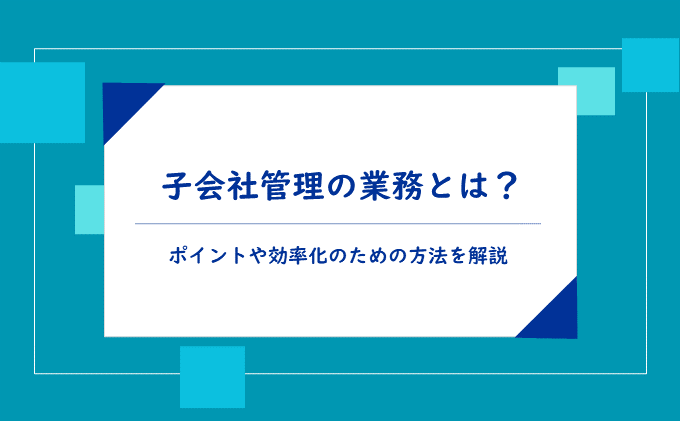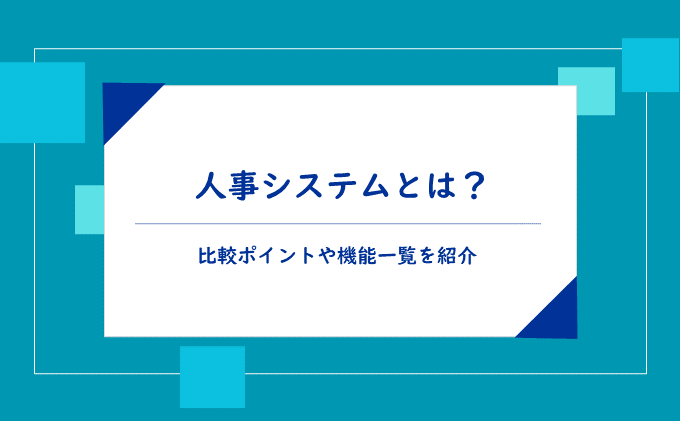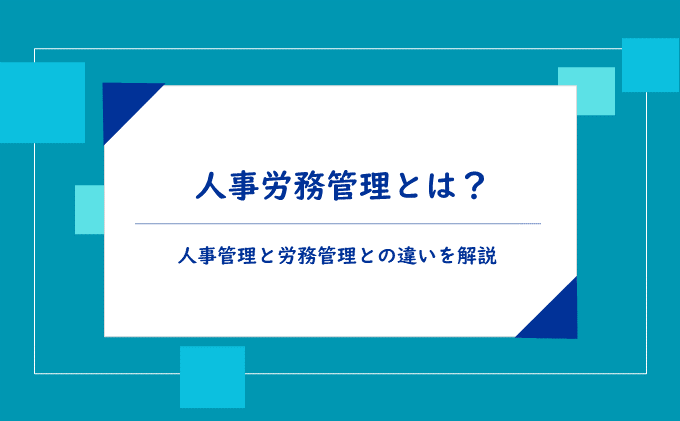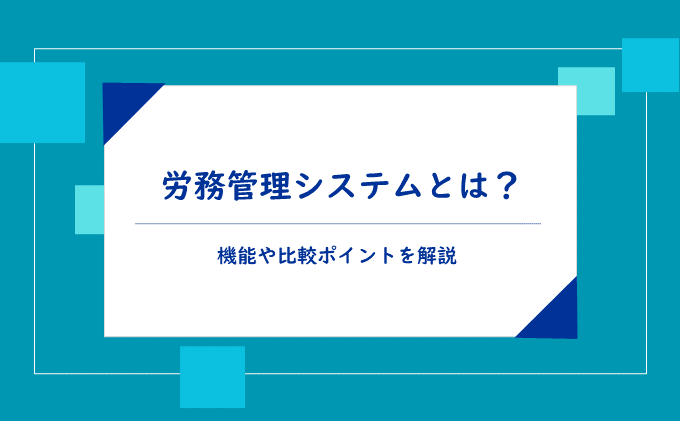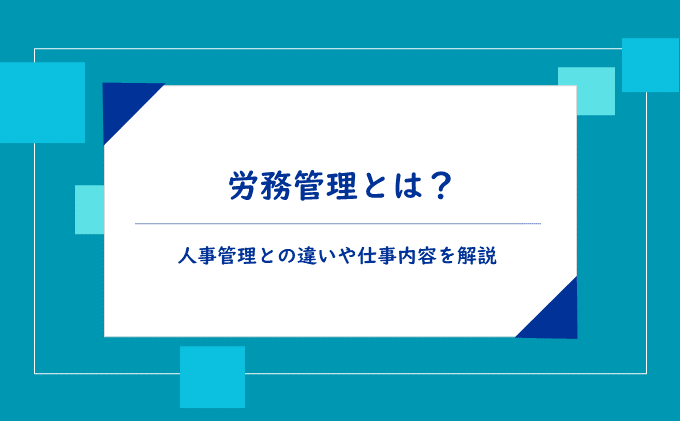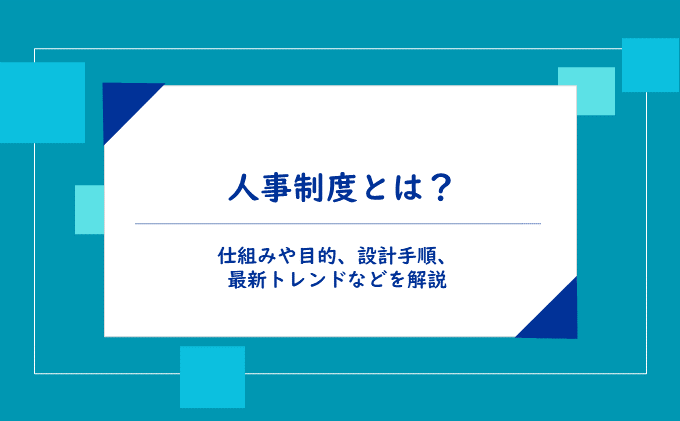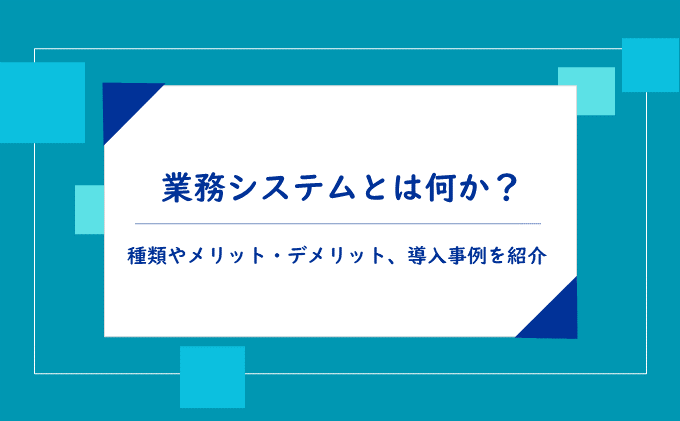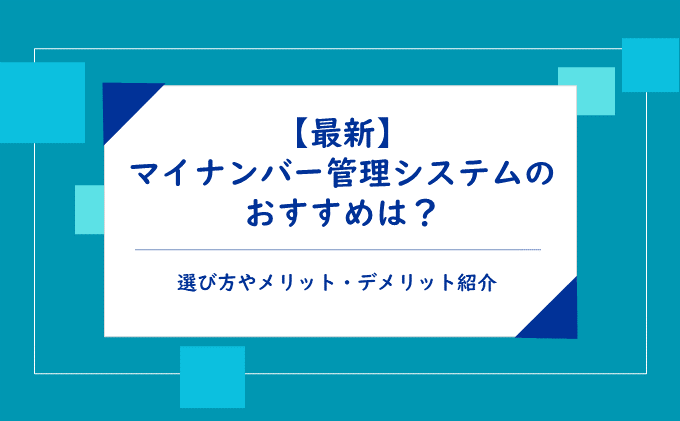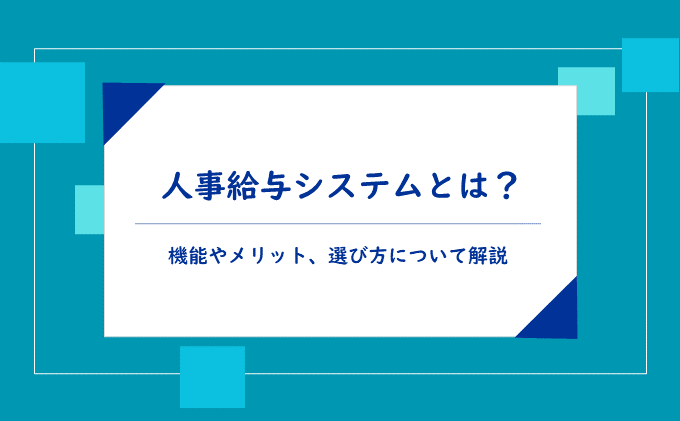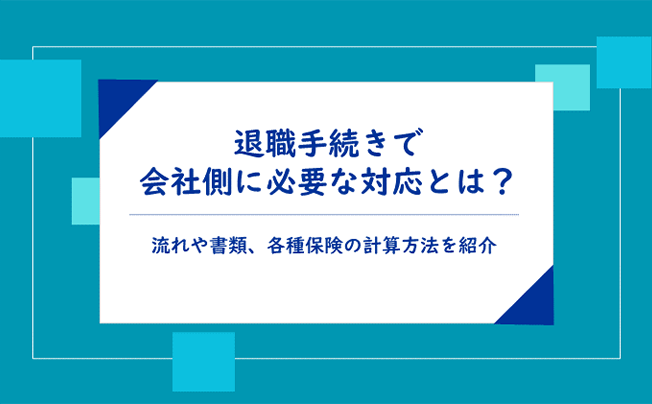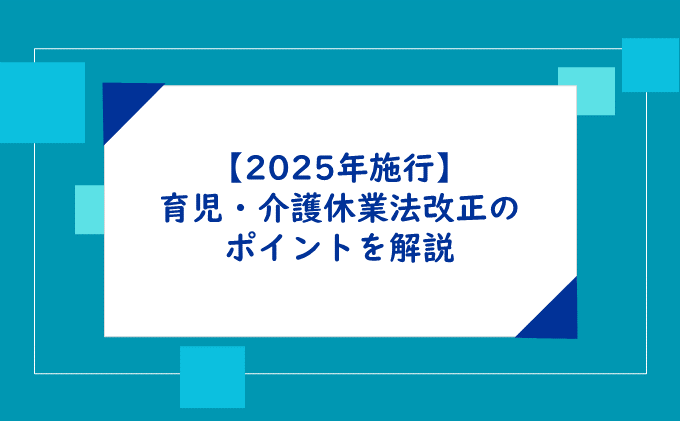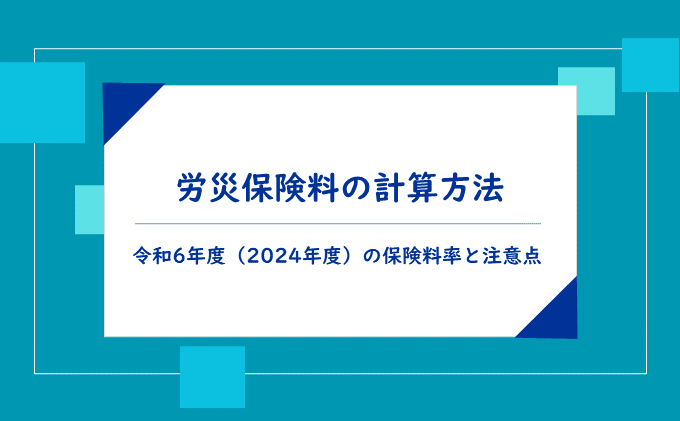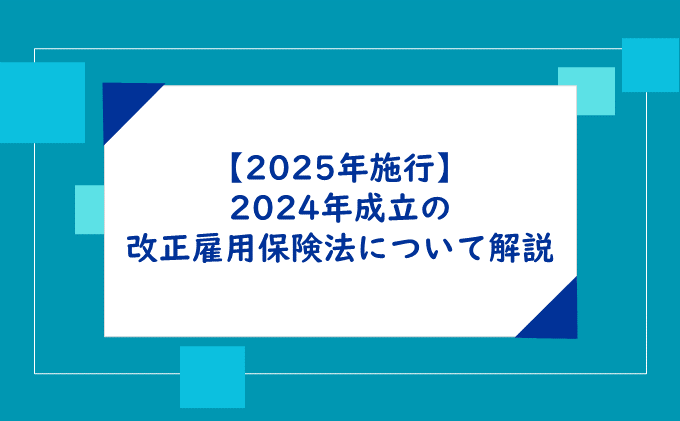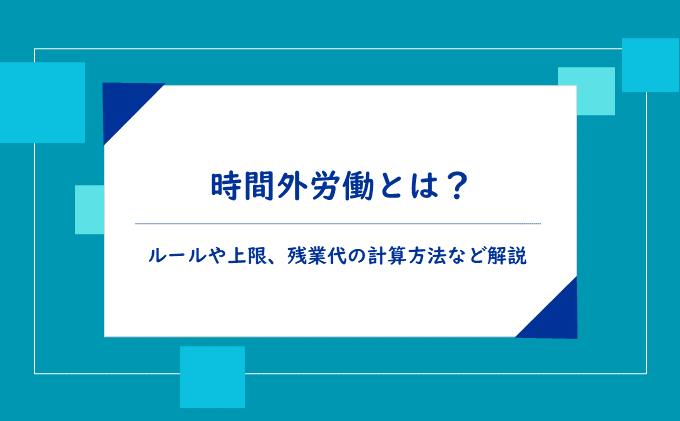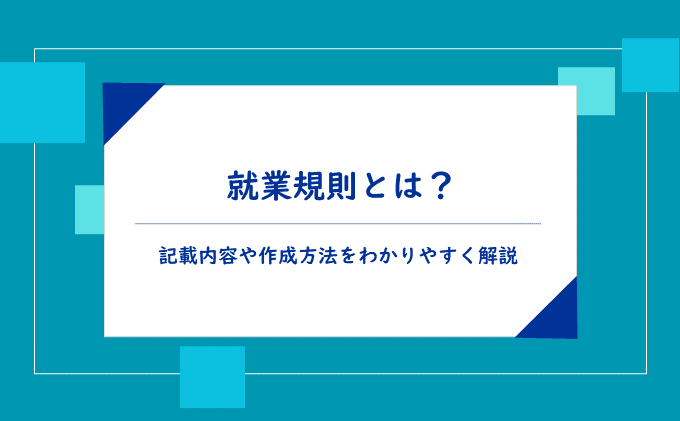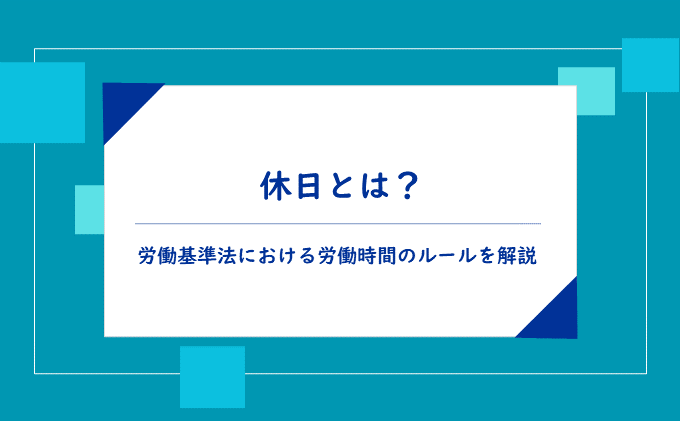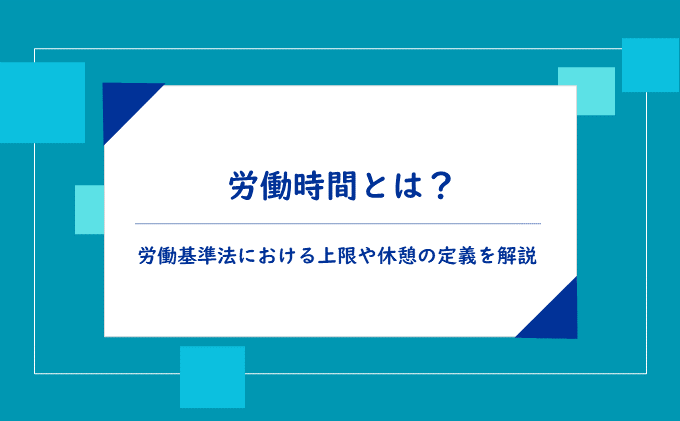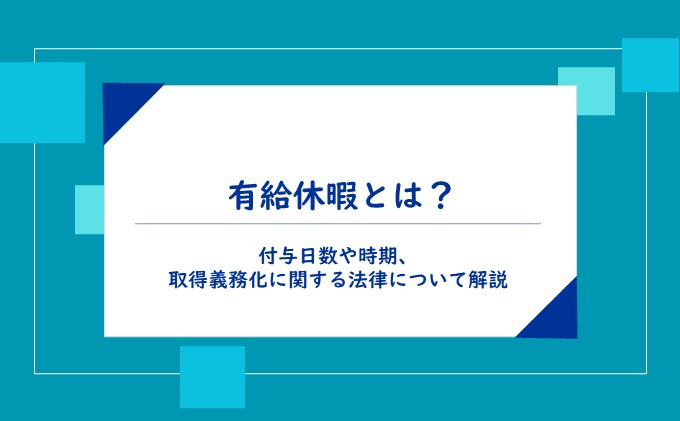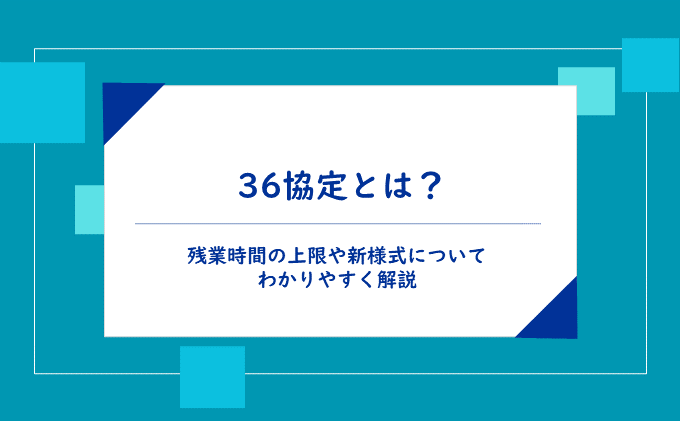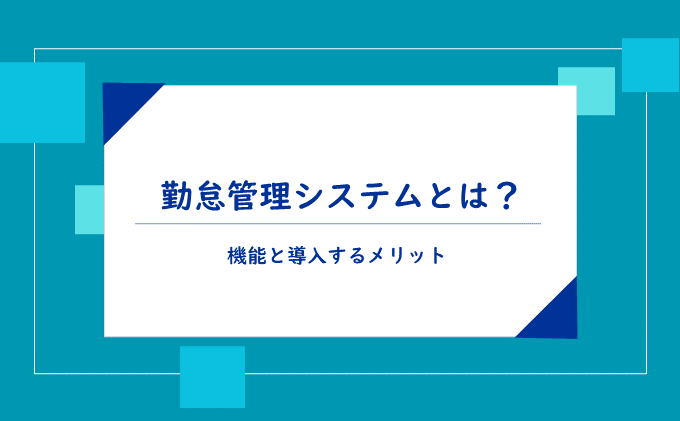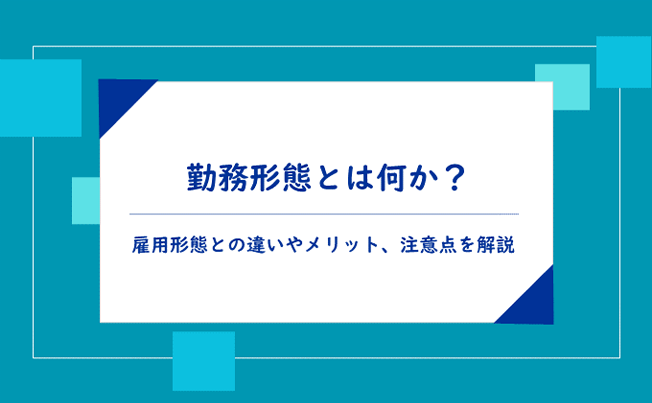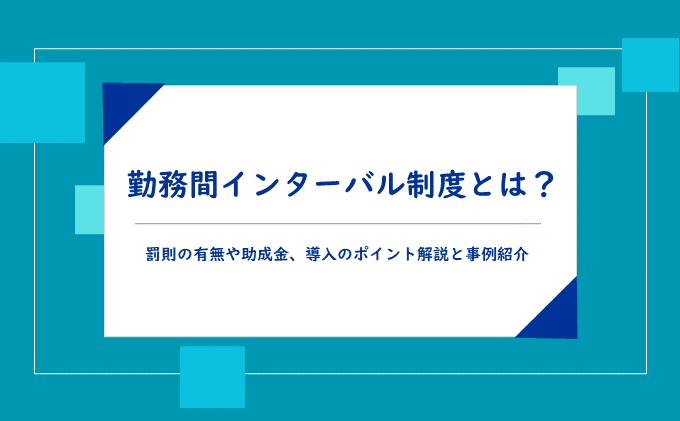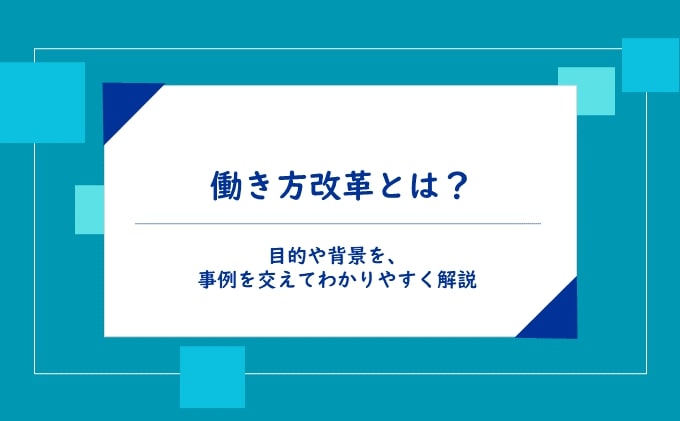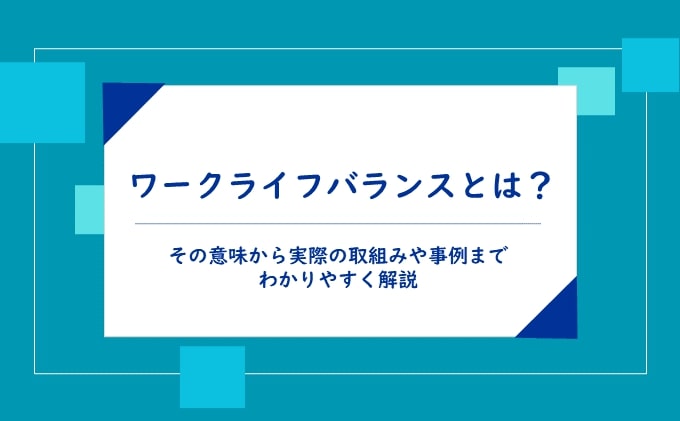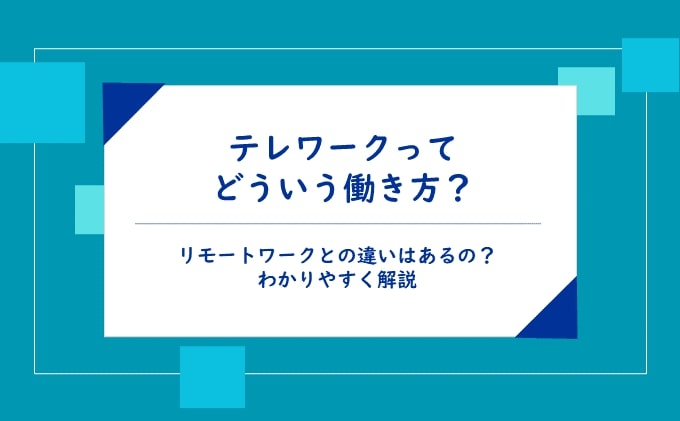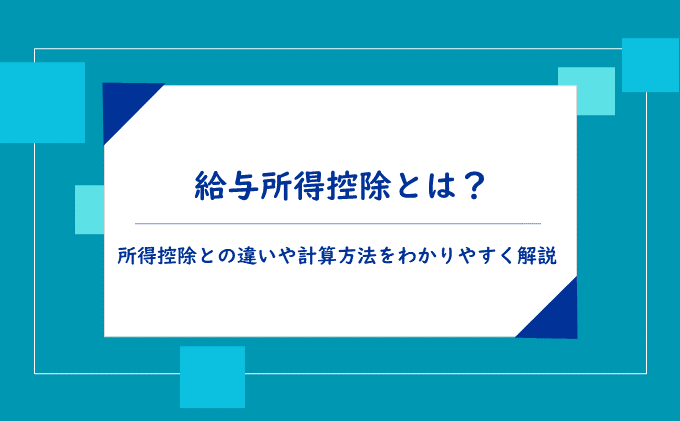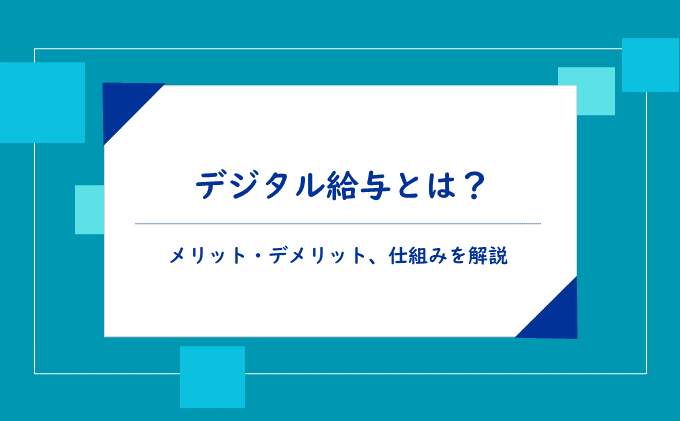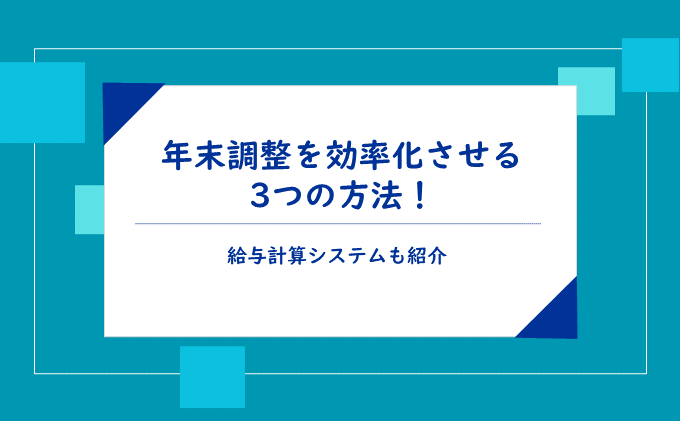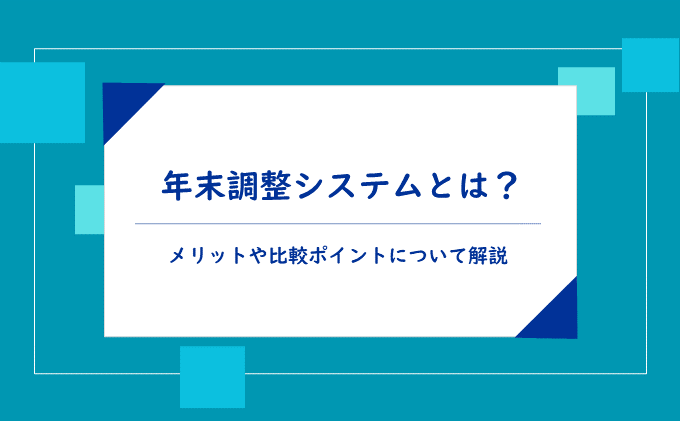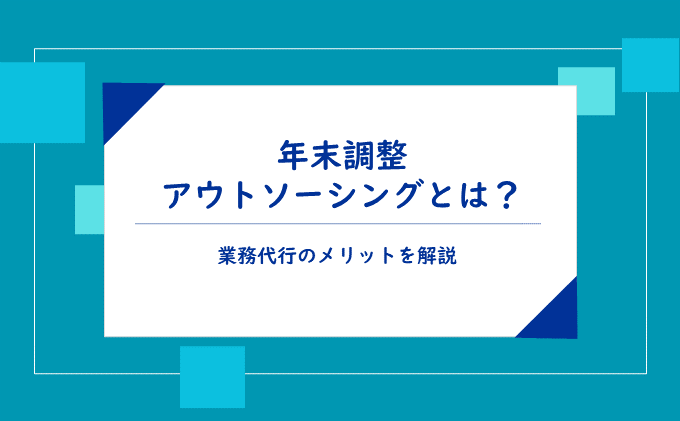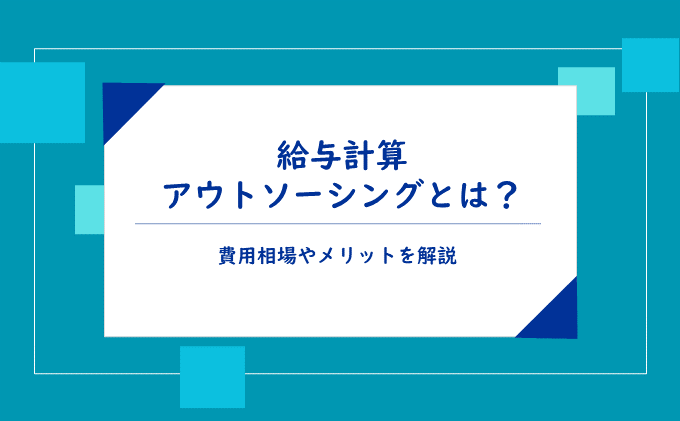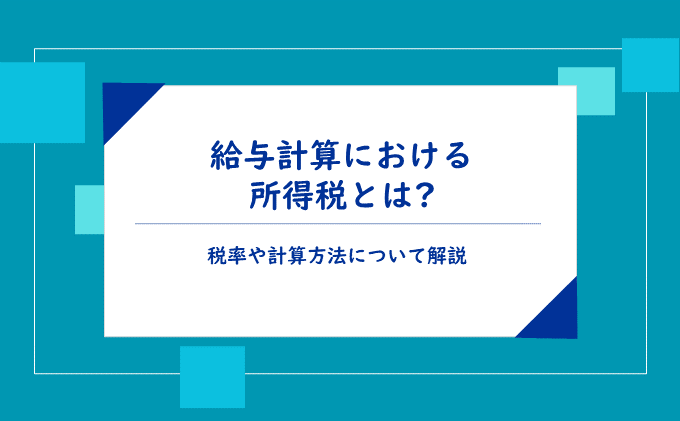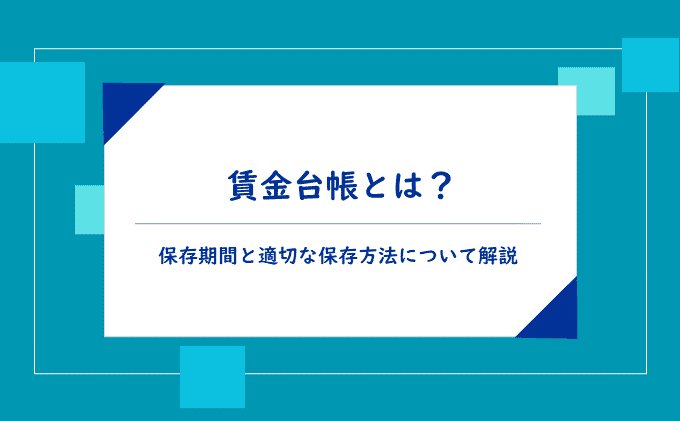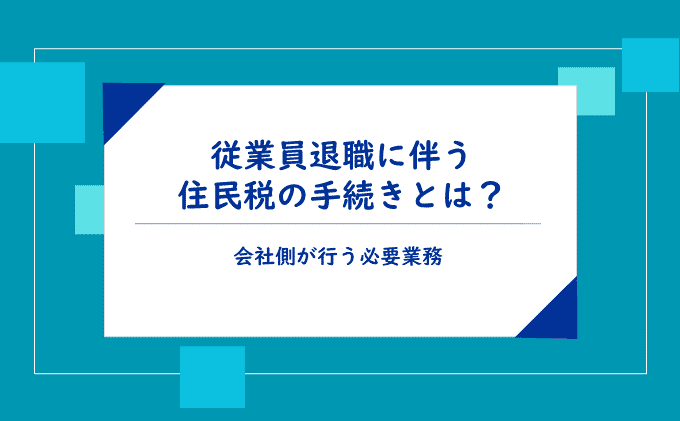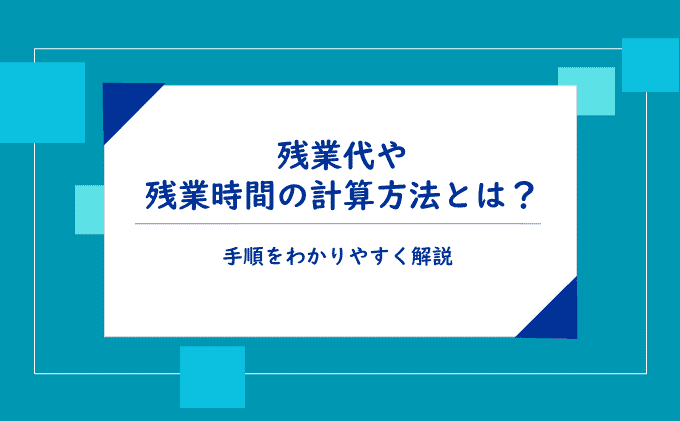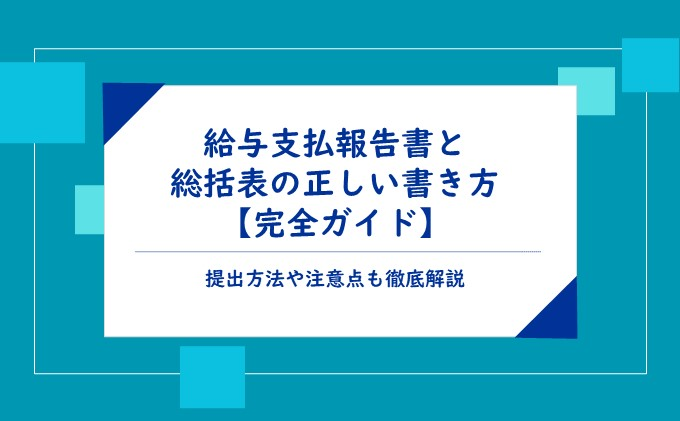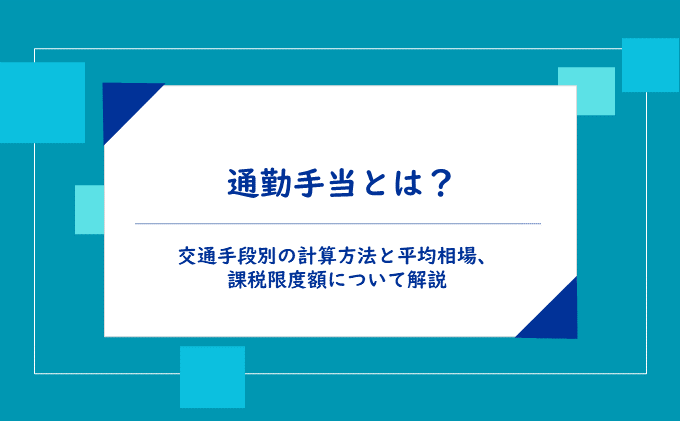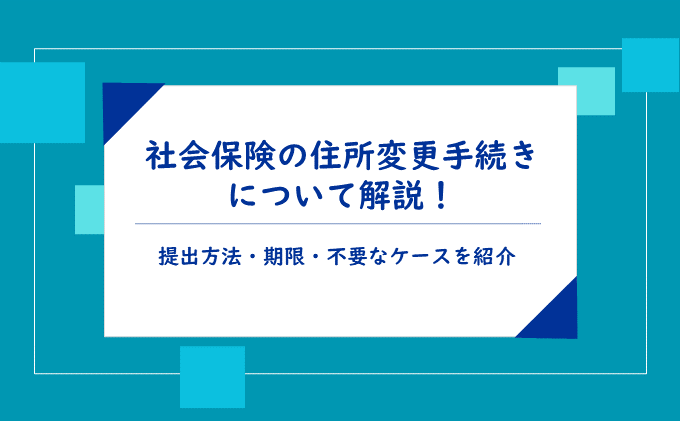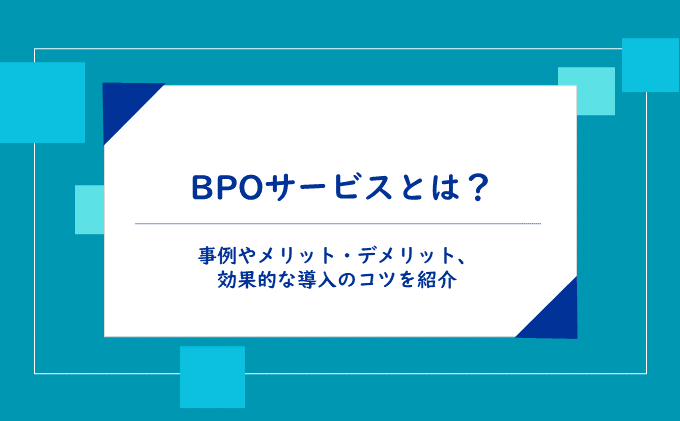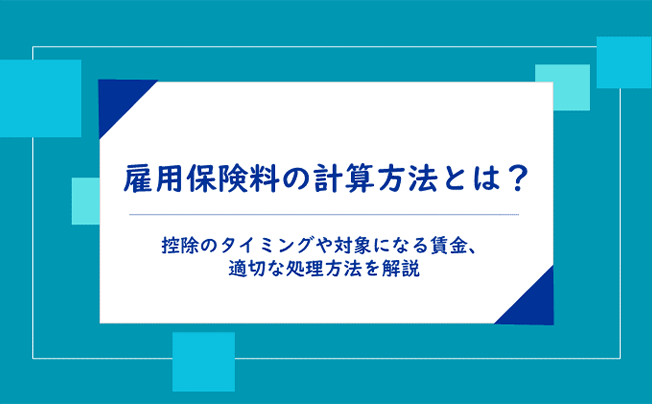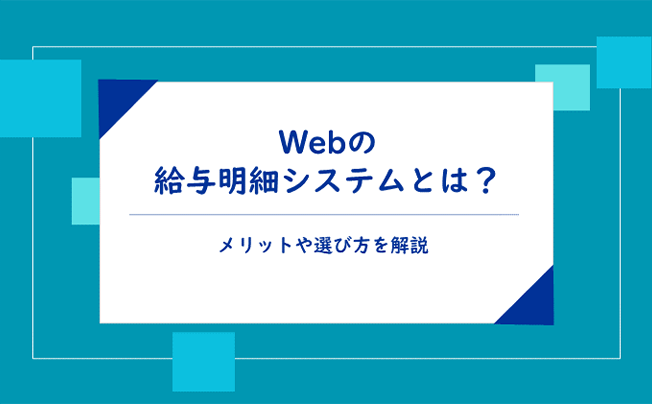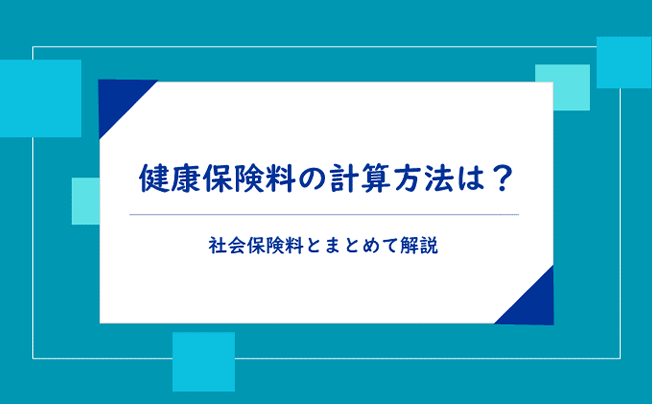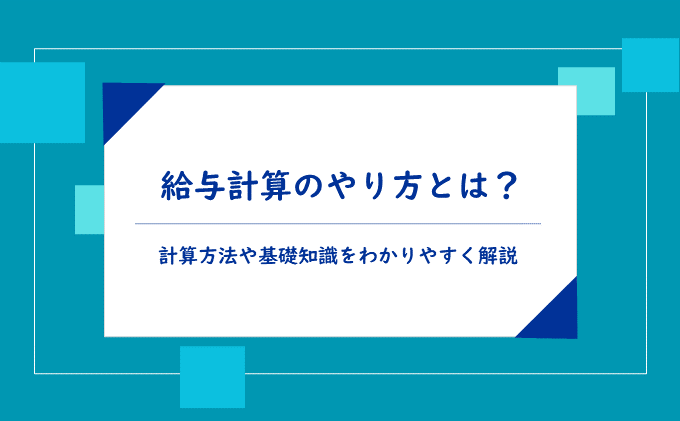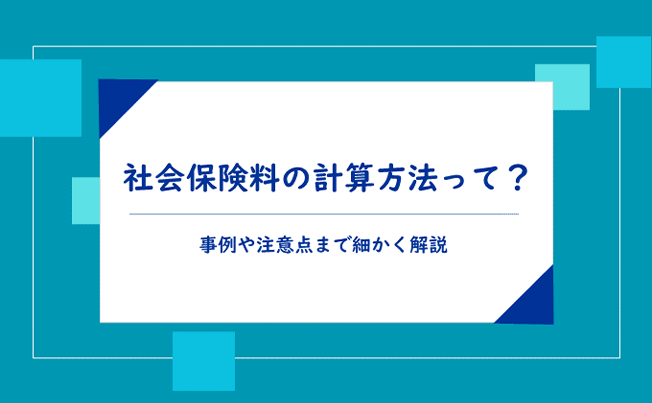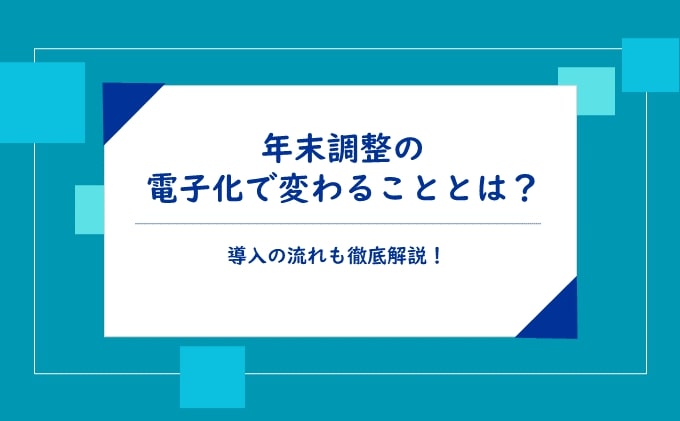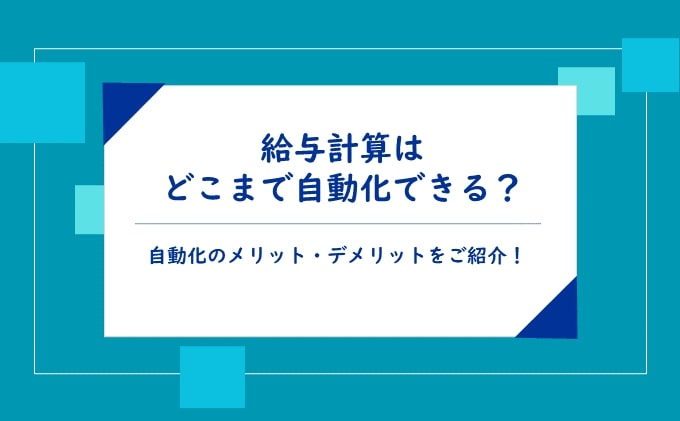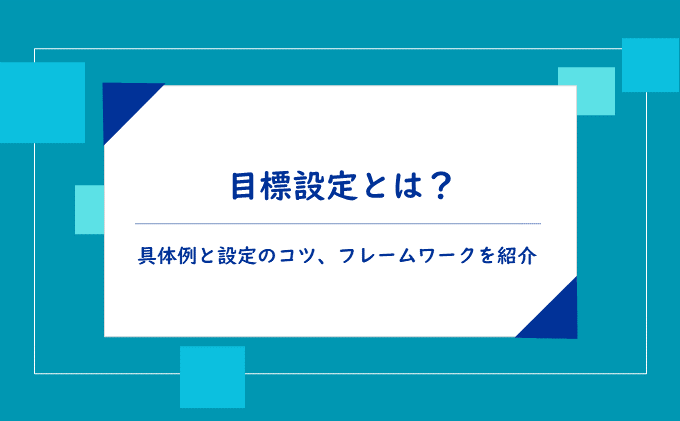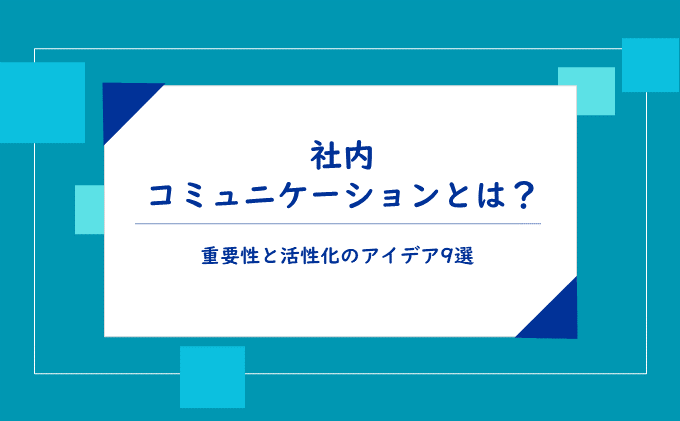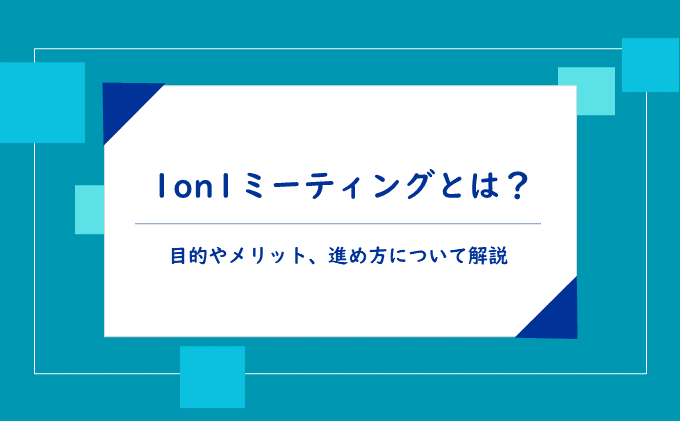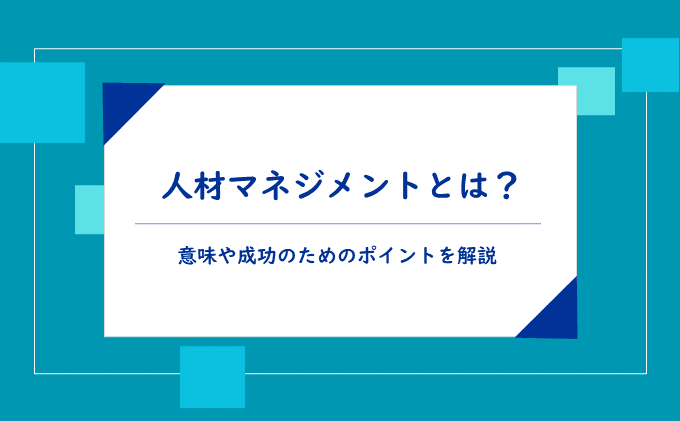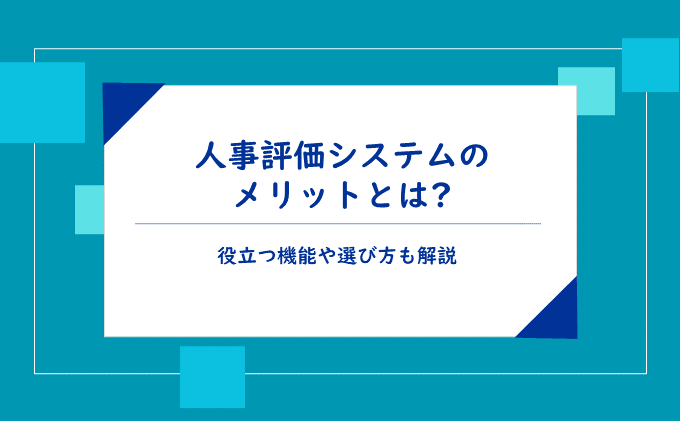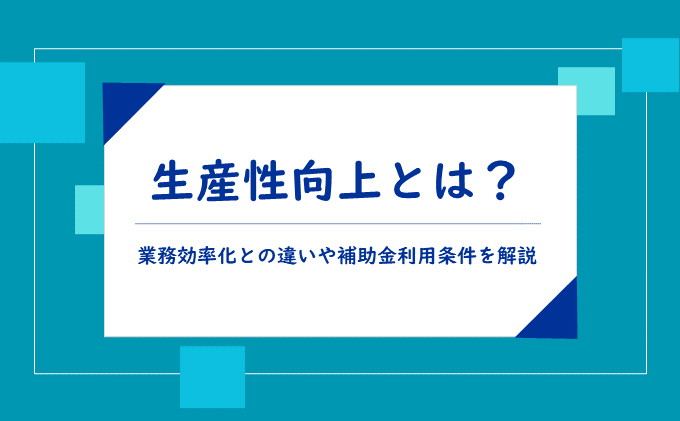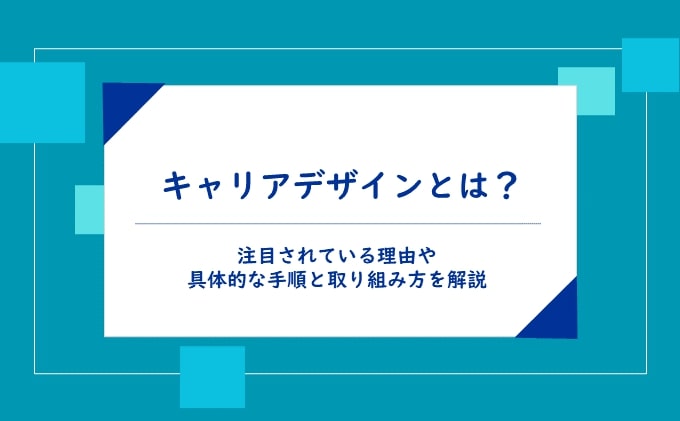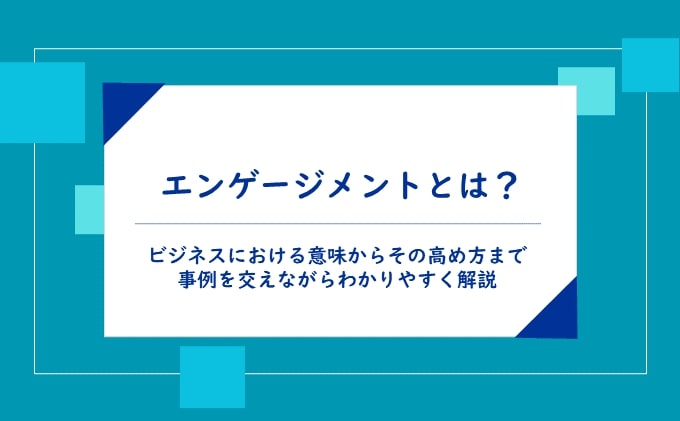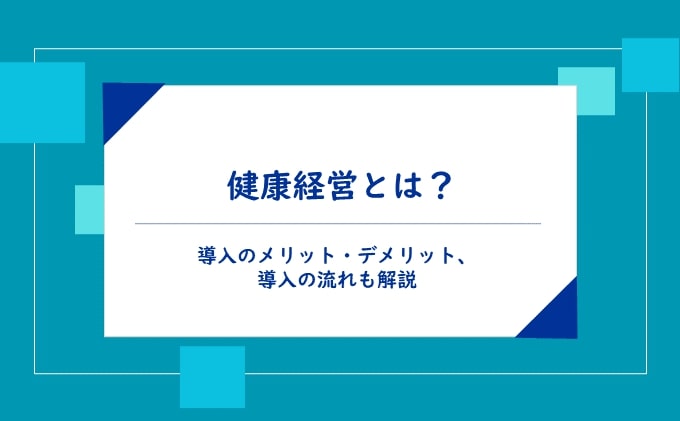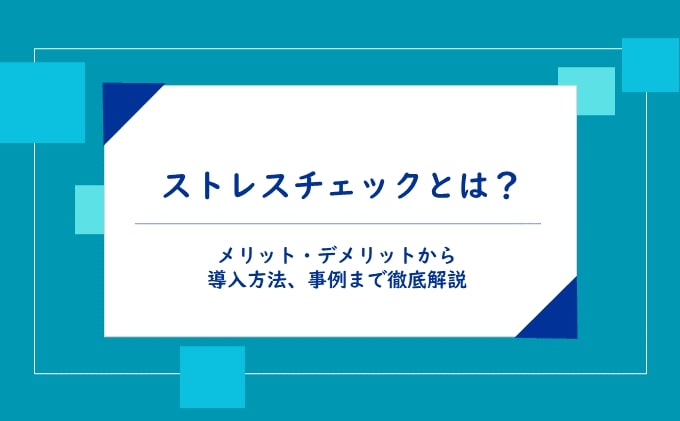勤怠管理とは?目的や必要性、方法などの基礎知識
2025.07.01
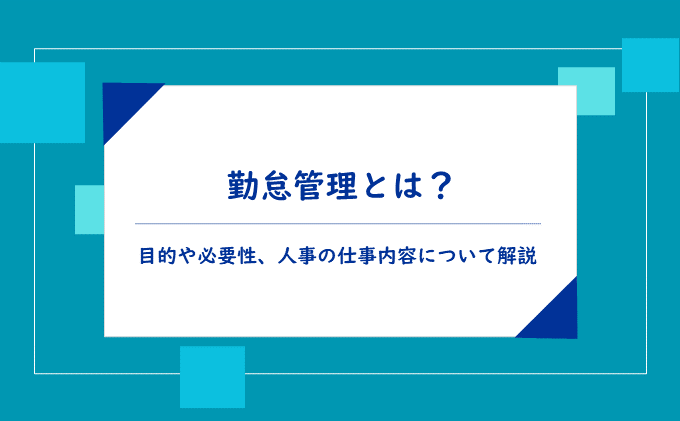
勤怠管理は人事・労務部門の重要な業務です。企業は従業員の勤務時間や日数などを記録し、働きすぎの防止や正確な給与の支払い行う必要があります。本記事では勤怠管理の基本から各種管理手法のメリット・デメリット、注意点などについて幅広く解説します。
目次
- 勤怠管理とは
- 勤怠管理の対象となる企業と従業員
- 勤怠管理の目的や必要性
- 勤怠管理で記録すべき項目
- 【手法別】勤怠管理のメリットとデメリット
- 【タイムカード】メリットとデメリット
- 【Excel管理】メリットとデメリット
- 【勤怠管理システム】メリットとデメリット
勤怠管理とは

勤怠管理とは、企業が従業員の出勤・退勤、休暇、欠勤などの出勤状況を正しく記録して、把握することです。労働関係の法令を守り、給与計算を正確に行うために必要な業務です。
勤怠管理は、企業の義務として労働基準法で定められています。同法に規定された以下の項目が勤怠管理に関連します。
- 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない(第32条)
- 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない(第34条)
- 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない(第35条)
勤怠管理の対象となる企業と従業員

勤怠管理の対象となるのは、労働基準法第4章(労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇)の規定が適用される企業です。ほとんどの企業が対象で、業種や業界、企業規模などは関係ありません。ただし、天候などの自然条件によって労働時間が左右される農業や水産業などの業種は、勤怠管理対象外とされています。
また、勤怠管理の対象は、労働基準法41条に定める例外を除くすべての労働者です。厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」では、「いわゆる管理・監督者及びみなし労働時間制が適用される労働者(事業場外労働を行う者にあっては、みなし労働時間制が適用される時間に限る)」とされています。
なお、管理・監督者以外では、農業や水産業に従事する従業員や、機密の事務を取り扱う従業員は勤怠管理の対象外です。
参考:厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
勤怠管理の目的や必要性

勤怠管理には、いくつかの目的があります。とくに、「従業員の健康を守る」「正確な給与計算を行う」「従業員のモチベーションを向上させる」の3点は重要な目的です。
労働時間を管理することで従業員の過重労働を防ぎ、健康の維持に結びつけられます。また、正確な給与計算には、労働時間の正確な把握が必要です。勤怠管理を確実に行うことで労働状況が改善されれば、従業員のモチベーションが上がり、生産性の向上に期待できます。
さらに、勤怠管理を着実に行うことは法令を遵守することでもあり、コンプライアンスを重視する健全な企業としてのイメージアップを図れます。勤怠管理の目的と必要性について、以下で項目ごとに解説しました。
長時間労働の防止
従業員の長時間労働を防ぐことは、勤怠管理の重要な目的の一つです。長時間労働の積み重ねは従業員の心身に支障をきたす懸念があり、過労死につながりかねません。労働時間を確実に管理し、長時間労働を防止して従業員の健康を守ることは、企業に課せられた責務です。
なお、長時間労働が認められる従業員に対して、業務量を減らしたり業務分担を変えたりするなどの対応を取る必要があります。
正確な給与の支払い
正確に給与を計算して支払うためには勤怠管理が欠かせません。労働時間が正確に把握できていなければ、時間外労働や休日出勤などを見落としてしまい、給与の未払いなどのトラブルが発生する可能性があります。
また、残業代は企業が給与天引きで徴収する税金や健康保険料などに影響します。勤怠管理が正確に行われていない場合、事務処理のやり直しなど、二度手間が生じかねません。従業員からの不満が出るなど、感情的な問題が起こる懸念もあります。従業員との信頼関係を構築し維持するためにも、勤怠管理を適切に行うことが重要です。
コンプライアンスの厳守
従業員の労働時間に対して、給与を支払うのは企業の義務です。残業や休日出勤などを給与に反映させていなければ、ブラック企業の汚名を着せられかねません。
労働基準法では、企業と従業員が36協定を締結していない場合、週に40時間を超えて労働させてはならないことが定められています。違反した場合には、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
刑事罰を受けなくても、長時間労働をさせたり給与の未払いがあったりすれば悪評が立ち、求人や取引先の開拓などに悪影響を及ぼしかねません。近年はSNSの普及により、悪い評判が短時間で拡散してしまう危険性があります。
勤怠管理を確実に行うことにより、問題の発生を防げるだけでなく、コンプライアンス意識の高い健全な企業であることをアピールできます。
従業員のモチベーション向上
従業員のモチベーションを維持、向上するためにも、勤怠管理は重要です。長時間労働が是正されなかったり残業代が支払われなかったりすれば、従業員のモチベーションは上がりません。従業員がモラルの低い労働をしたり、離職者が増えてしまったりする可能性があります。
厳密な勤怠管理は、従業員の満足度を向上させ、業務遂行に対して前向きな気持ちを持たせることにつながります。
勤怠管理で記録すべき項目
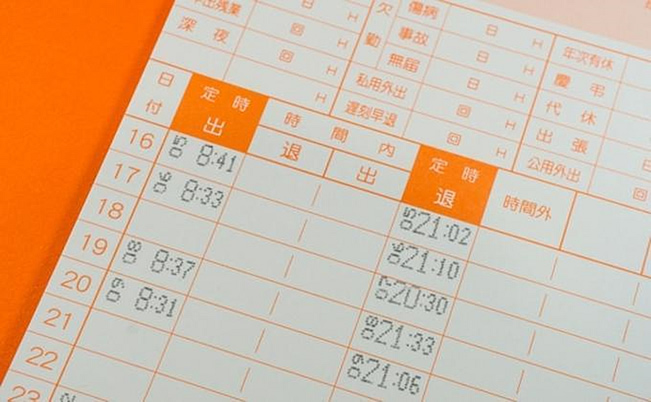
この項では、勤怠管理で記録すべき項目について解説していきます。記録すべき項目について、労働基準法では具体的な定めがありません。厚生労働省のガイドラインは、「使用者は、労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録すること」とし、労働時間の適正な管理を企業の責務と位置付けています。
項目ごとに詳しく説明します。
始業・終業時間および休憩時間
始業と終業の時間や休憩時間の把握は、1日の労働時間を正確に管理するために必要なことです。始業と終業は1分単位で記録して給与に反映させてください。また、従業員に休憩を取らせることも企業に課せられた義務であるため、休憩時間の把握も必須です。
始業と終業の時間を管理することで、従業員の遅刻や早退を確認できます。遅刻や早退が多い従業員がいれば、適切な指導や配置転換などの対応を検討してください。
時間外・深夜・休日労働時間
時間外労働や深夜業、休日出勤で働いた時間に対して、企業は割増賃金を支払わなければなりません。割増賃金が生じる時間についても、企業は正確に把握する必要があります。
厚生労働省のHPによると、時間外労働に対する割増賃金は「通常の賃金の2割5分以上」とされています。従業員の時給が1,000円だった場合、割増賃金は1時間あたり1,250円です。また、深夜業と休日労働の割増賃金の率は、深夜業が2割5分以上で休日出勤が3割5分以上です。
深夜業とは、午後10時から翌日午前5時までの間の労働を指します。一方の休日労働とは、労働基準法上の法定休日(週1日または4週のうち4日、曜日は問わない)に労働させることです。なお、割増賃金は重複して発生することがあります。たとえば、時間外労働が深夜に及んだ場合は、時間外労働分の2割5分以上と深夜業の分の2割5分以上が合算され、5割以上の割増率としなければなりません。
参考:厚生労働省「法定労働時間と割増賃金について教えてください」
出勤および欠勤日
勤怠管理で記録すべき項目には、時間だけでなく、出勤日と欠勤日もあります。どの程度休日を取得しているかは、従業員の健康管理にかかわる重要な情報です。適正に休みを取らせることで、健康維持や生産性向上に期待できます。
休日出勤した従業員については、代休や振替休日を取っているかどうかを確認することが必要です。就業規則にもよりますが、出勤や欠勤の日数は給与計算にも影響します。
有休の取得日数および残数
有給休暇の取得日数と残り日数の管理も、企業の責務です。2019年4月1日に施行された働き方改革関連法(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律)では、年5日の年次有給休暇を従業員に取得させることが義務付けられました。
同法施行以前は、有給休暇は従業員の申し出によって取得するものでしたが、そもそも取得の申し出がしにくいなどの問題があり、有給休暇の取得率は高まっていませんでした。同法により、企業は従業員の希望を踏まえて有給休暇の取得時季を指定することが定められています。
参考:厚生労働省「働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて~」
勤怠管理の方法とメリット・デメリット

勤怠管理の方法は、紙に手書きするものから、タイムカードで出退勤時刻を打刻するタイプ、システムで入力から分析まで一気通貫で行うものなど、さまざまです。この項では、主な勤怠管理の方法ごとにメリットとデメリットをまとめました。
【紙の出勤簿】メリットとデメリット
紙の出勤簿は、従業員が出勤と退勤の際に、用意された用紙に時間を書き込んでいくものです。手軽でコストもあまりかかりませんが、集計に手間がかかり、リアルタイムでの勤怠が確認できないなどの難点もあります。以下で、紙の出勤簿を使うメリットとデメリットを解説します。
メリット
紙の出勤簿を使うメリットは、必要なものが紙と筆記具だけのため、ランニングコストがほとんどかからない点です。従業員が数人しかいないなど、少人数の企業であれば「紙の出勤簿で十分」と考える経営者もみられます。
出勤時間、退勤時間のほか、休憩時間や有給休暇の取得といった勤怠に関連する情報を1枚の用紙にまとめられ、一覧性があることも紙のメリットです。
デメリット
勤怠管理を紙の出勤簿で行うデメリットは、以下のとおりです。
- 単純な間違いだけでなく、不正申告やサービス残業を見抜けない可能性がある
- リアルタイムで勤怠が確認できないこと
- 出勤簿の保管場所を確保しなくてはならない
厚生労働省のガイドラインでは、「タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること」が求められています。自己申告で労働時間を把握できますが、以下のような条件が付きます。
- 従業員や労働時間の管理者に対し、自己申告制の適正な運用などガイドラインに基づく措置について十分な説明を行う
- 自己申告の労働時間と、パソコンの使用時間などから把握した在社時間に著しい違いがある場合は実態調査を実施し、労働時間を補正する
- 自己申告できる時間数の上限を設定するなど適正な自己申告を阻害する措置を設けてはならない
こうしたガイドラインを満たすためのハードルの高さも、紙の出勤簿のデメリットです。
【タイムカード】メリットとデメリット
タイムレコーダーと呼ばれる機械に専用のタイムカードを差し込み、出勤や退勤の時刻などを打刻して記録する仕組みです。
出勤時と退勤時、早退時などにあわせて差し込み口をスライドさせ、タイムカード上のそれぞれのマスに時刻が打ち込まれるようにします。タイムカードのメリットとデメリットは、以下のとおりです。
メリット
タイムカードのメリットには、操作が簡単であることが挙げられます。操作は、タイムカードをレコーダーの差し込み口に入れ、打刻音がするまで押し込むだけです。ITリテラシーに左右されず、若年層からシニア層まで使いやすいという利点があります。
企業側にとっては、用意するものがレコーダー本体と毎月のタイムカードだけであり、コストが比較的低い点がメリットです。近年は紙のタイムカードではなく、ICカードをタッチするだけで出退勤時刻の入力ができるタイプもあります。ICカード型であれば、パソコンに取り込んで集計作業をするのも手軽です。
デメリット
タイムカードは原則として、手作業による集計処理が発生します。アナログ的な処理方法には、ケアレスミスがつきものです。集計処理には時間と人手を要する点も、デメリットとして数えられます。
タイムカードには、出退勤の時刻、営業担当者などが外回りに出て帰社した時刻などの打刻ができます。しかし、残業時間が何時間であったかの計算や、休日を何日取得したかなどの管理には別途処理が必要です。
営業担当者が直行直帰した場合や、リモートワークで出社しない従業員が多い企業などでは打刻そのものができません。他人のタイムカードを打刻する不正を防ぎにくい、打刻済みのカードを保管する場所を必要とするなどの点も、弱点に挙げられます。
【Excel管理】メリットとデメリット
表計算ソフトのExcel(エクセル)で管理するやり方も、広く使われています。従業員が自らExcelを開き、出退勤時刻などを入力する方法です。
パソコンを使う職場であれば、Excel活用のハードルはさほど高くないと考えられます。Excelで勤怠管理するメリットとデメリットを、以下の項で示しました。
関連記事:Excel(エクセル)で勤怠管理┃自動計算のメリットと注意点
メリット
Excelを業務で使っている企業の場合、パソコンにはすでにExcelがインストールされているため、導入コストは低廉です。タイムカードのように紙を保管する必要がなく、スペース効率の向上も見込めます。
Excelは表計算ソフトであり、関数や計算式を使うことで集計が手早くできることもメリットです。Web上には、Excelを勤怠管理に使う企業向けに、無料でダウンロードできるテンプレートが多数用意されています。紙をベースとした勤怠管理に比べ、集計や分析など後工程の処理が手軽です。
デメリット
Excelは便利で高機能ですが、入力は従業員本人が行うため、誤入力や誤操作といったミスの発生は懸念材料です。手入力であることから「客観的な記録」と認められず、別途タイムカードなどでの記録が必要な点は人事担当者の負担増につながります。
人事担当者側で、関数や計算式の設定を間違う可能性もあります。他人が入力する不正行為が起こり得る点も、リスクの一つです。
法改正や就業規則の改定などがあった場合、計算式を設定し直す必要があります。紙での管理と同様に、リアルタイムで従業員の出退勤を確認できない点もデメリットです。
【勤怠管理システム】メリットとデメリット
勤怠管理システムは、出退勤の時刻から休日の取得日数、残業時間の管理のほか、集計や分析など、あらゆる必要な処理をシステム上で一括管理するものです。自社でサーバーを設定する「オンプレミス型」や、クラウド上のシステムを活用する「クラウド型」などがあります。
勤怠管理システムのメリットとデメリットは、以下に示すとおりです。
メリット
紙ベースやExcelでは不可能だった、リアルタイムでの勤怠状況の把握が勤怠管理システムを使えば可能です。給与計算など、他のシステムと連携することにより、業務効率の一段の向上が期待できます。スマートフォンなどと連携できるシステムもあり、出張中やリモートワークの従業員などの勤怠入力と管理に便利です。
オンプレミス型のシステムを構築した場合、自社で使いやすいようにカスタマイズが可能です。クラウド型のサービスを活用すれば、法改正時にも自動対応してもらえるため、自社の担当者の負荷を軽減できます。
デメリット
システムの導入には、タイムカードやExcelとは比較にならない水準のコストがかかります。とくにオンプレミス型では、コストが高くなりがちです。
全従業員が間違いなく使えなくては、システム導入の効果が十分に上がりません。使い方の周知やマニュアル作成、研修などを行う必要があり、担当者の負担となります。
導入する際には、自社の必要とする機能を洗い出し、それを満たす製品を見極めて選定することが重要です。必要以上に高機能なシステムを導入すると、かえって機能を活かしきれないおそれがあります。操作性やセキュリティなど、ニーズを取りまとめる時間と手間が必要です。
【ケース別】勤怠管理の注意点
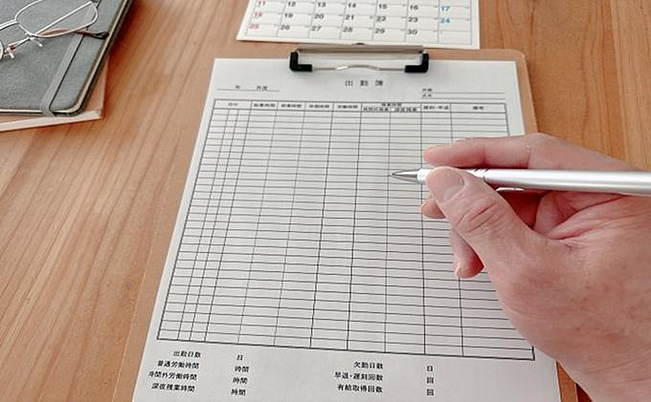
この項では、勤怠管理を行うにあたって注意すべき点をまとめています。以下のようなケースのそれぞれについて解説しました。
- 勤務日や勤務時間がまちまちなパート・アルバイト
- 正社員ではない契約社員
- テレワークの場合の対応
- 103万円や130万円の壁を意識した働き方をする扶養控除内勤務
【パート・アルバイト】勤怠管理の注意点
パート・アルバイトは、人によって勤務日や休日、勤務時間が異なることに注意が必要です。厳正な勤怠管理を行うためには、確実に勤務日や労働時間などを把握しておかなければなりません。
パートやアルバイトはシフト制の勤務体系が多く、シフト作成機能を備えた勤怠管理システムを活用すれば業務が効率的に進みます。また、時給は人によって異なるため、給与計算が複雑になりがちです。勤怠管理と給与計算を連携できるシステムの活用がおすすめです。
【契約社員】勤怠管理の注意点
契約社員にも、正社員と同等の勤怠管理が求められます。契約社員と正社員の差は、労働期間の定めの有無です。始業・終業の時刻や時間外労働、休日などを正確に記録し、適切に給与計算に結びつけることが重要です。
【テレワーク】勤怠管理の注意点
テレワークを採用している従業員は、勤怠管理がオンラインを経由した自己申告制になることが多くあります。自己申告による勤怠管理を行う際には、厚生労働省のガイドラインに準じて、従業員への十分な説明や、申告された時間と客観的な記録に乖離がないかチェックが必要です。
テレワークなど、多様で複雑な勤務スタイルが可能な企業であれば、柔軟な設定ができる勤怠管理システムの導入により生産性の向上が期待できます。
関連記事:テレワークってどういう働き方?リモートワークとの違いはあるの?わかりやすく解説
【扶養控除内勤務】勤怠管理の注意点
扶養控除の範囲内で働きたいという希望を持つ従業員への対応も欠かせません。扶養控除内には、所得税が発生する「103万円の壁」や、社会保険料が徴収される「130万円の壁」など、いくつかの種類があります。
企業は、扶養控除内での就労を希望する従業員が、自身の所得をどの水準までに抑えたいのか把握しなければなりません。確実な勤怠管理がされていなければ「壁」を越えてしまい、税や社会保険料に対して想定外の支払いが発生する可能性があります。
年末が近づくにつれ、扶養控除内に抑えるためのシフト調整など、煩雑な処理が増えます。扶養控除内で働きたい従業員がいる企業には、シフト作成機能を持つ勤怠管理ソフトの導入がおすすめです。
勤怠管理システムの種類と選び方

勤怠管理システムの導入により、勤怠管理を適正に行い、給与計算へのミスのない反映が期待できます。手作業による集計や確認などの手間が不要となり、業務効率の向上にも有効です。この項では、勤怠管理システムの種類と選び方についてまとめました。
勤怠管理システムの種類
勤怠管理システムには、大きく分けて以下の3種類があります。
- オンプレミス型
- クラウド型
- タイムレコーダー型
オンプレミス型とは、自社でサーバーを構築し、運用するタイプのシステムです。サーバー、ソフトウェア、ネットワークなどを自社で整備する必要があるため、コストが高くなりやすい傾向です。
ただし、自社でシステムを構築するため、強固なセキュリティの確保や細かなカスタマイズができます。自社でメンテナンスできる技術部門を擁する企業に向いています。
クラウド型は、自社にサーバーを置かず、インターネット上のシステムを各社で共有する方式です。以前はオンプレミス型が主流でしたが、近年はクラウド型を活用する企業が増えています。
クラウド型はオンプレミス型よりも導入費用が安く、導入にかかる時間が短いことがメリットです。また、法改正には提供ベンダーが対応するため、手間がかかりません。
従業員数が少ない企業や、シンプルな勤務体系の企業には、低コストで導入できるクラウド型がおすすめです。ただし、クラウド型はシステムを共有する性質上、カスタマイズには限界があります。
タイムレコーダー型は、専用のタイムレコーダーとICカードを使って、出退勤時刻を入力するシステムです。パソコン操作が苦手な従業員でも、従来のタイムレコーダーの延長線上で活用できる利点があります。
原則としてリモートでの入力ができず、テレワークや長期出張の従業員がいる企業には不向きです。
勤怠管理システムの選び方
勤怠管理システムを選ぶ際には、自社でよく使う機能が盛り込まれているかや、コストがかかりすぎないかなど、いくつかの観点から見ることが必要です。選び方として重要なポイントを、以下の項に示しています。
自社に必要な機能が備わっているか
勤怠管理システムには多様な製品があり、それぞれにセールスポイントが異なります。システムを選ぶ前に、自社で必要とする機能をピックアップしておくことが大切です。
勤怠時刻のリアルタイムでの管理、残業時間の把握、帳票印刷の容易さなど、企業によって求める機能はさまざまです。あれば便利でも、実際にはほとんど使わないことが想定される機能もあります。ピックアップした「必要とする機能」に優先順位をつけておくと、製品選択に役立ちます。
自社で活用している給与計算システムなどと連動させる場合は、システム連携がうまくいくかどうかの確認も必要です。
コスト面に問題はないか
勤怠管理システムの導入には、費用がかかります。導入コストだけでなく、継続的なランニングコストにも注意を払う必要があります。活用する年数を想定して、導入から運用までのトータルコストに対する費用対効果を検討することが不可欠です。
導入費用が安かったとしても、ランニングコストが高ければ、最終的には損をする可能性があります。法改正があった際のプログラム改修などが月々の管理費用に含まれるのか、別途費用が発生するのかなど、各システムのコストは入念な比較が肝要です。
セキュリティ対策は万全か
勤怠管理システムは、氏名や住所、生年月日などのほか、システムによっては給与などセンシティブな情報を扱います。漏えいや改ざんなどが発生してしまうと、企業への被害は甚大です。強固なセキュリティ性能が担保されているかどうか、十分に調査しましょう。
オンプレミス型のシステムを構築する場合は、自社内で閉じたシステム設計とすることも可能なため、高いセキュリティを確保しやすい利点があります。クラウド型ではインターネットを介してアクセスするため、通信の暗号化やデータのバックアップ体制などが不可欠です。
サポート体制は整っているか
システムは一般的に、導入しただけですぐ使えることはまれです。担当者が使い方を理解し、操作に習熟できるようになるまでの研修など、サポート体制が充実しているかはシステムの活用度合を左右します。
不具合や操作の問い合わせなどに24時間、365日体制で対応してもらえるのか、平日の日中だけなのかといった点も、チェックしておきたい部分です。サポートが手厚ければ安心ですが、その分費用が高くなる傾向があります。自社の業務に必要かどうかを検討したうえで、選択するのがおすすめです。
人事管理システム「ADPS」で勤怠管理を効率化!

カシオヒューマンシステムズ株式会社が提供する人事管理システム「ADPS(アドプス)」は、1990年の誕生以来、累計5,000社を超える企業への導入実績があります。勤怠管理だけでなく、人事管理、給与計算なども一括して扱えるシステムであり、複雑な業務手順がフローで表示されるため視覚的なオペレーションが可能です。
また、シンプルでわかりやすい操作性と高度なセキュリティを兼ね備えており、勤怠管理業務を初めて行う従業員からベテラン担当者まで安心して活用できます。「ADPS」の活用で勤怠管理業務の生産性を上げ、経営効率のさらなる改善につなげてください。
まとめ

勤怠管理とは、企業が従業員の労働状況を正確に把握し、記録することです。勤怠管理が確実なものでなければ、給与計算は不正確になりかねません。勤怠管理の方法には、紙の出勤簿やタイムカード、Excelなどもありますが、勤怠管理システムの導入がおすすめです。まずは自社の運用にあったシステムを選定し、適切な勤怠管理と業務の効率化を実現していきましょう。
カシオヒューマンシステムズコラム編集チームです。
人事業務に関するソリューションを長年ご提供してきた知見を踏まえ、
定期的に「人事部の皆様に必ず今後の業務に役立つ情報」を紹介しています。