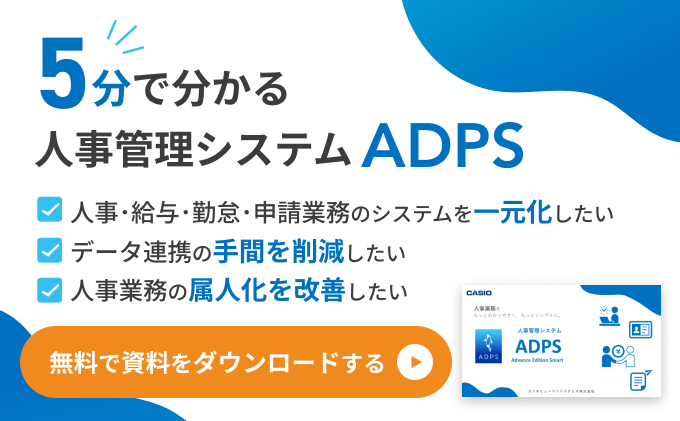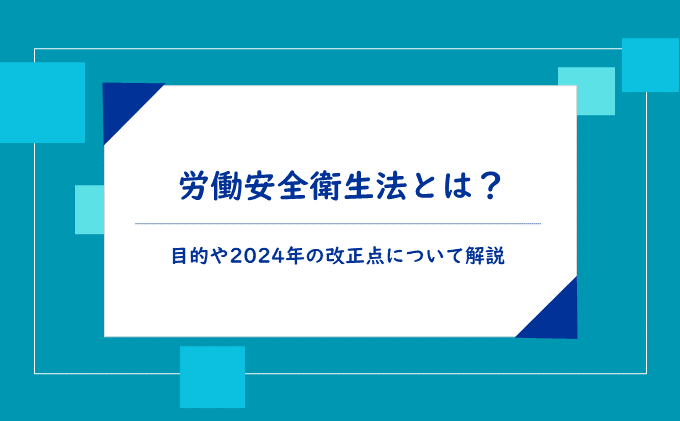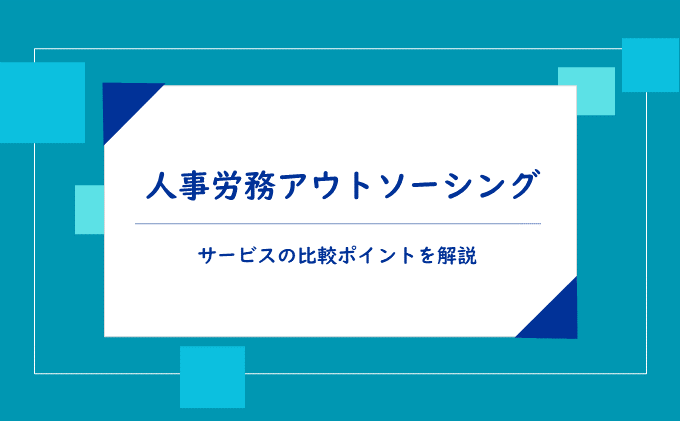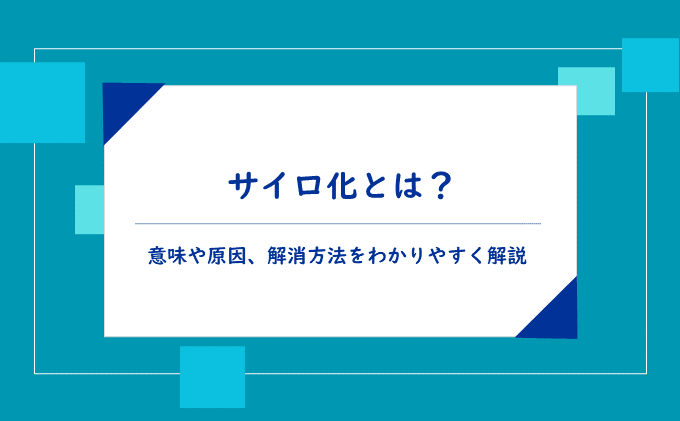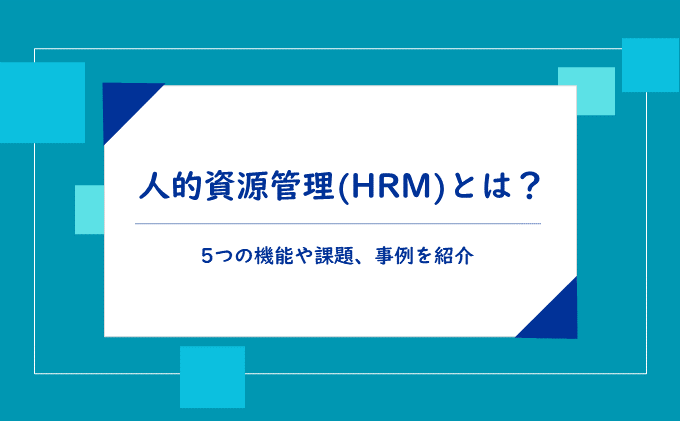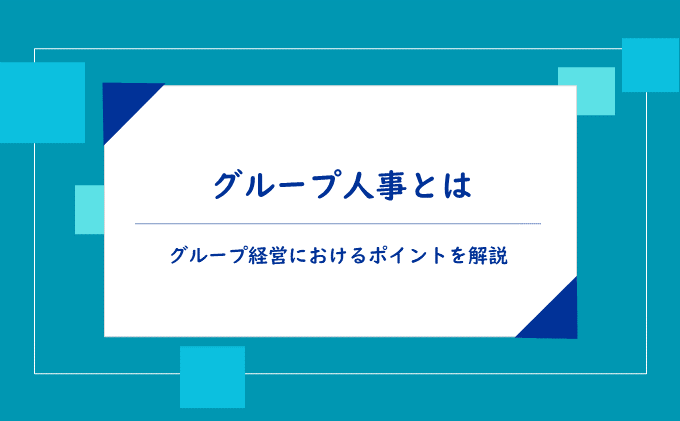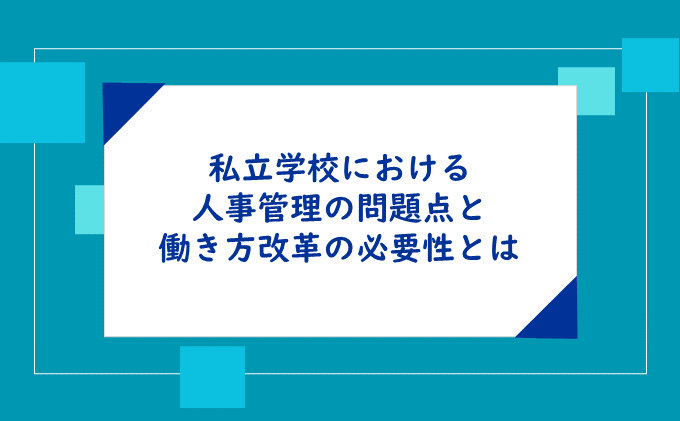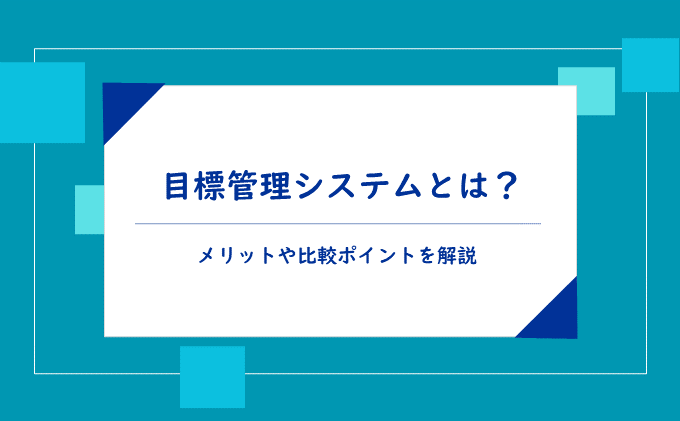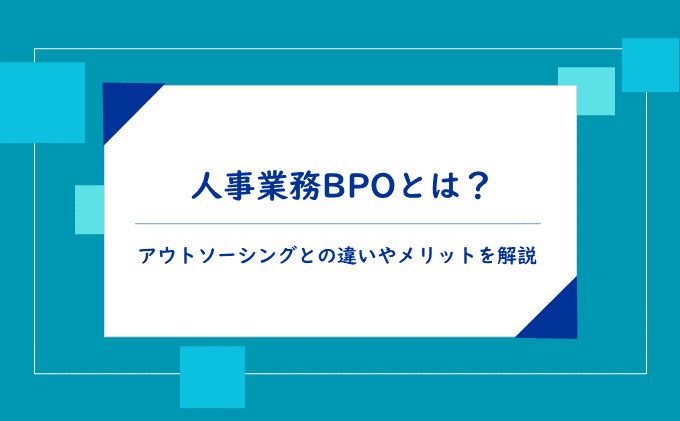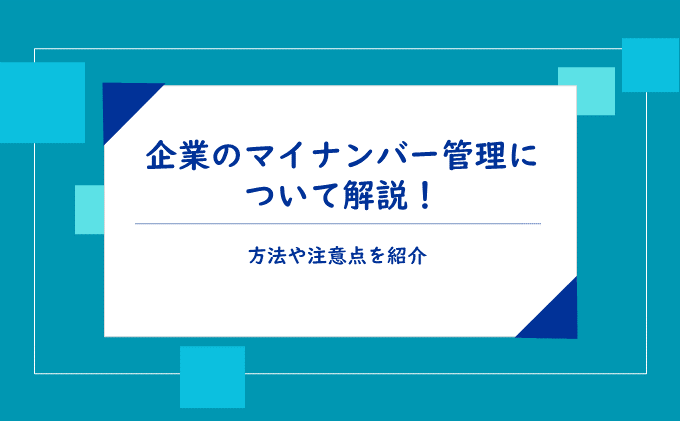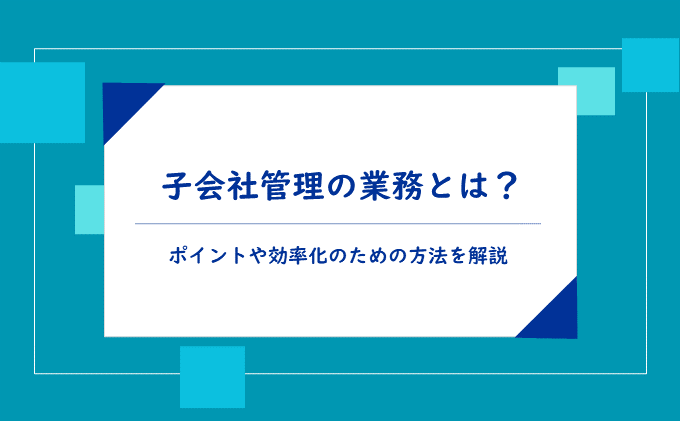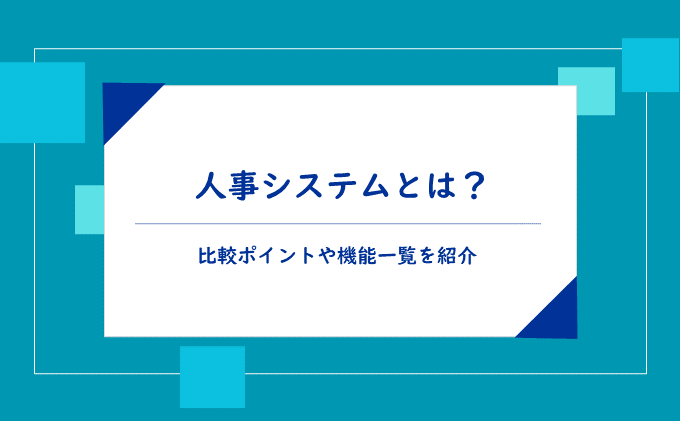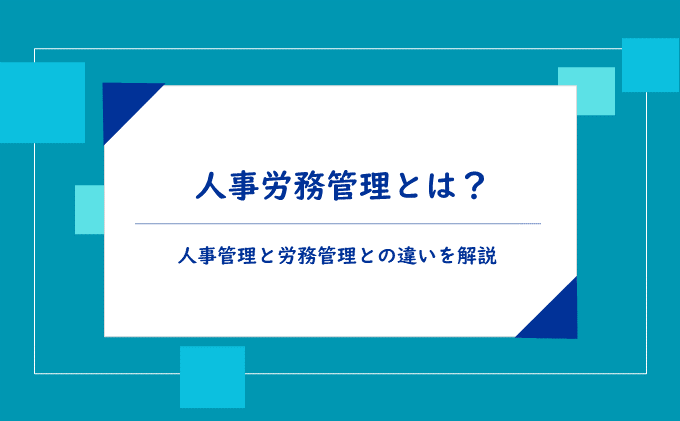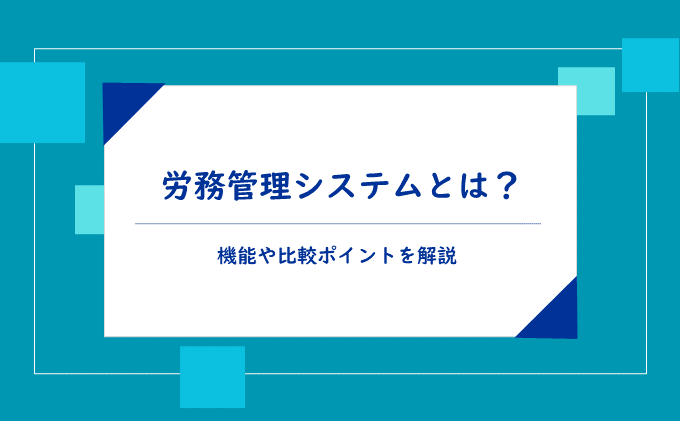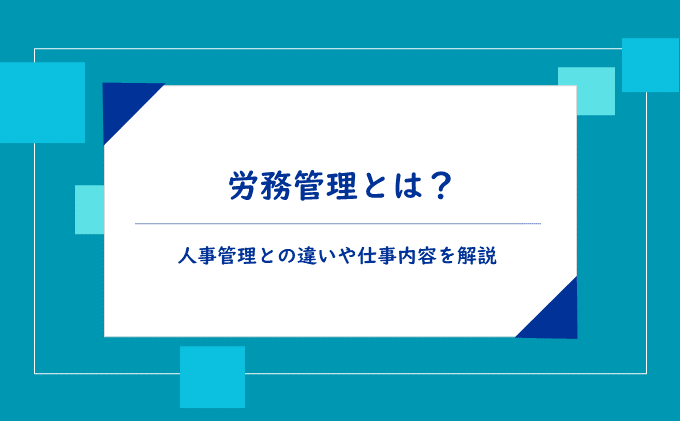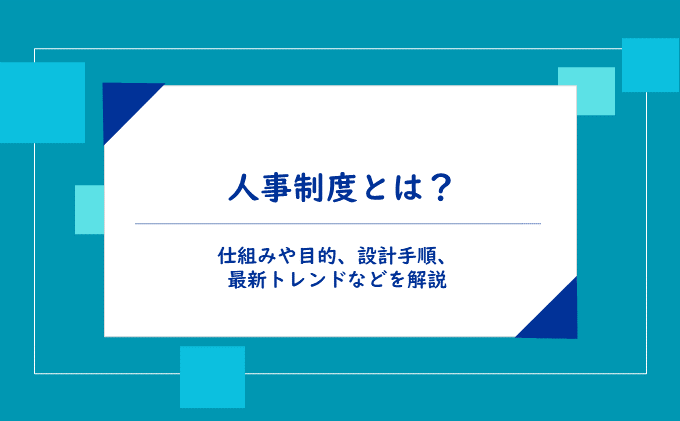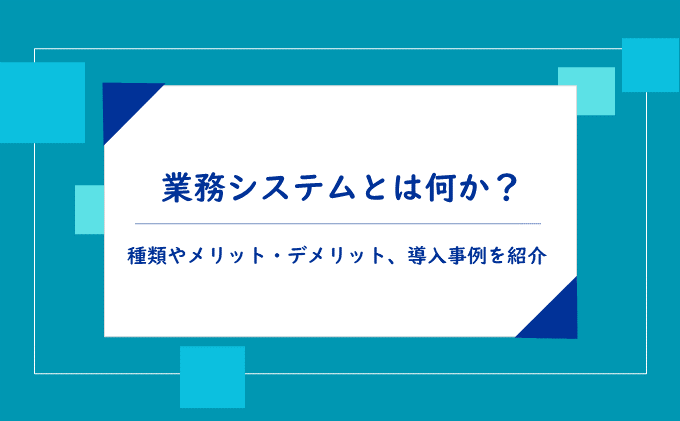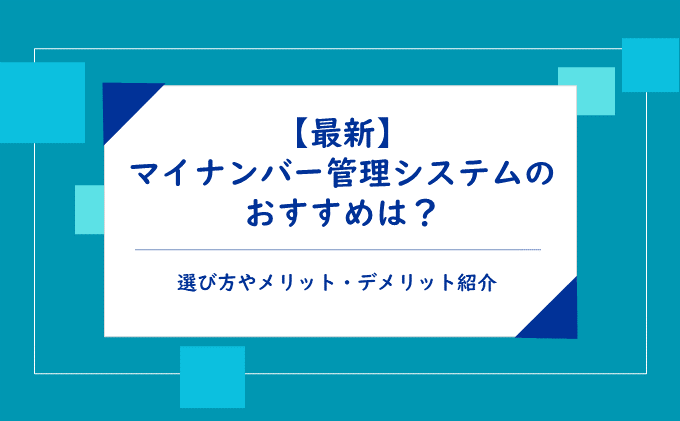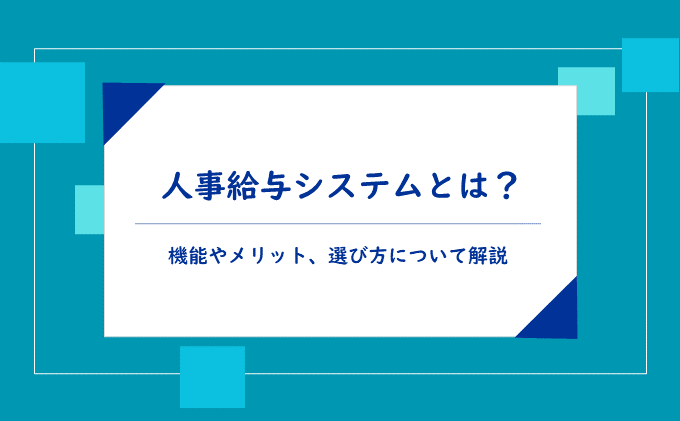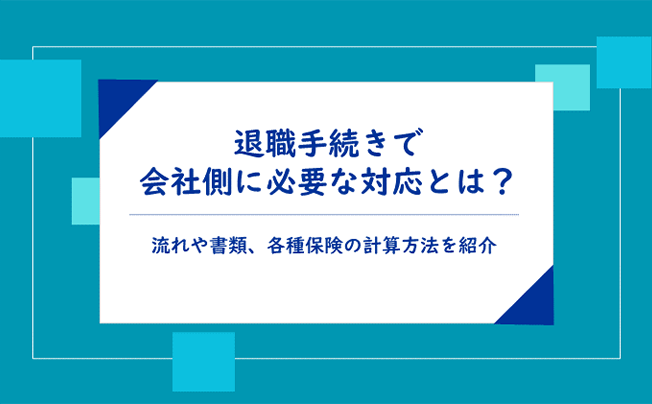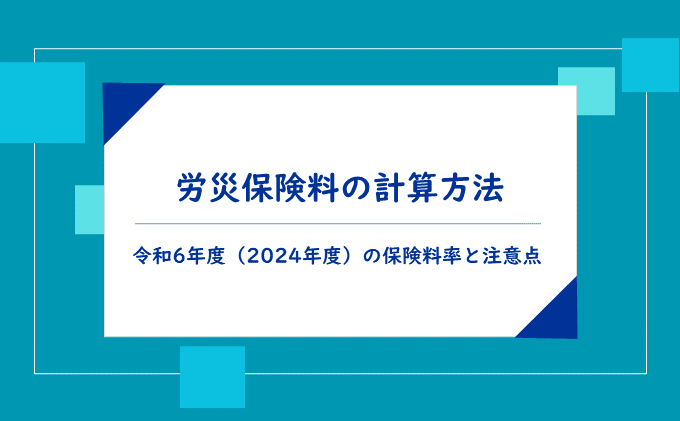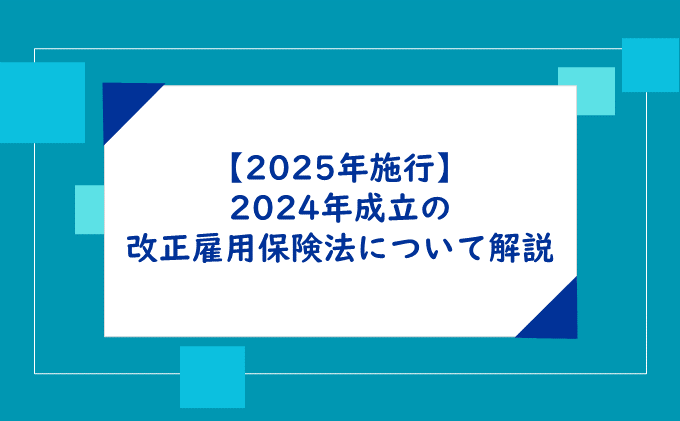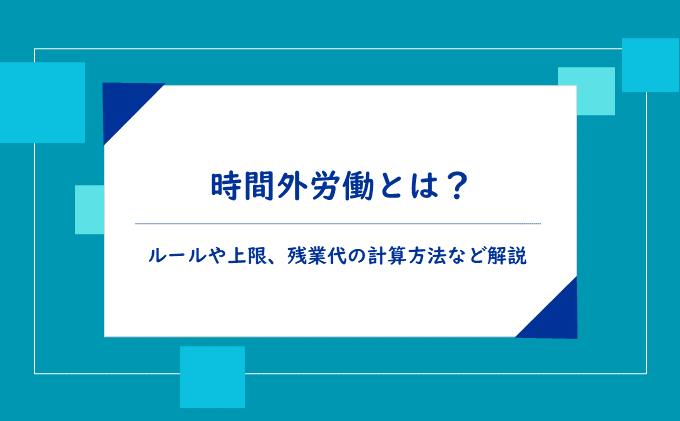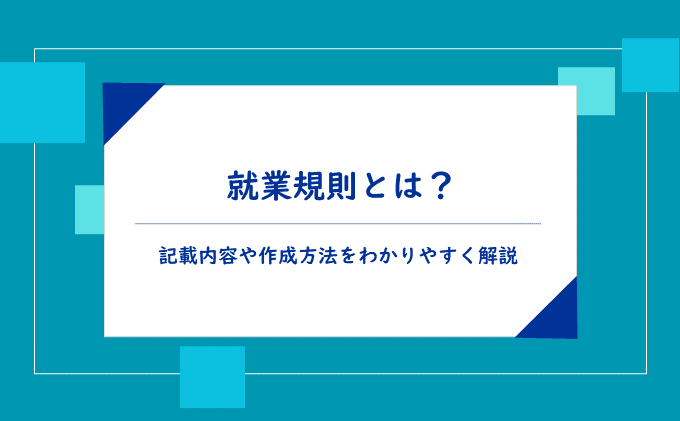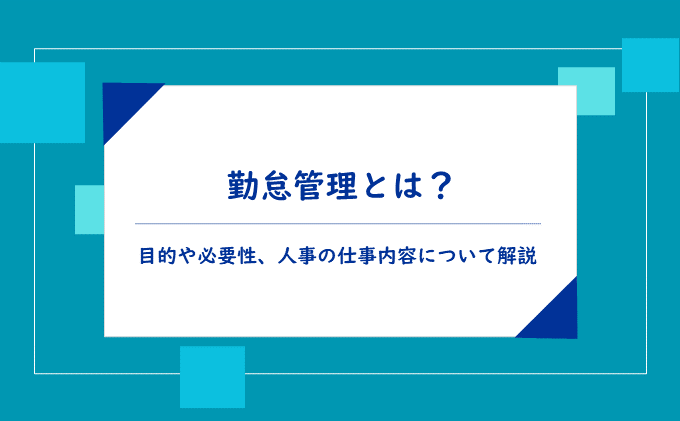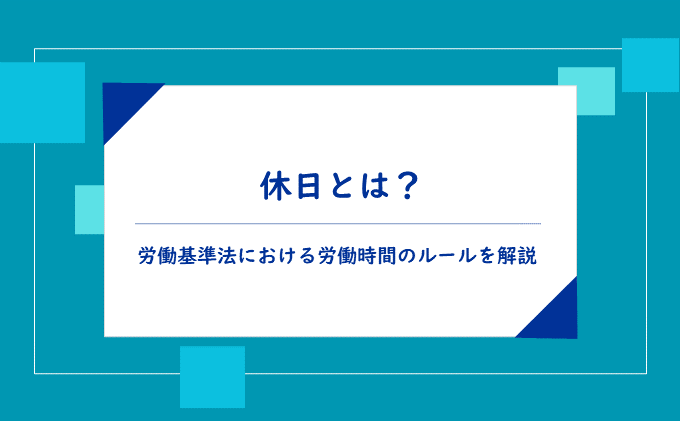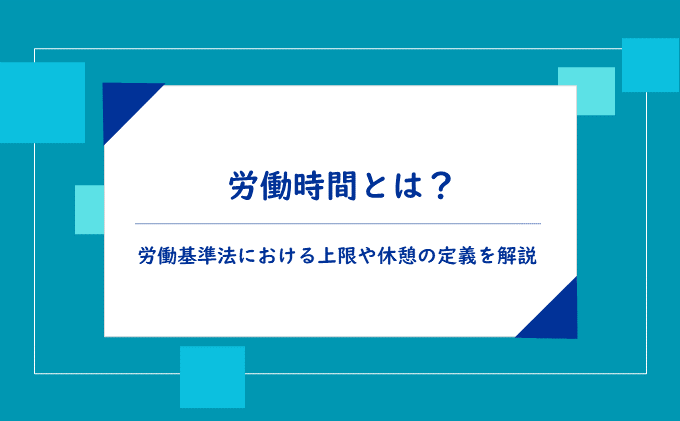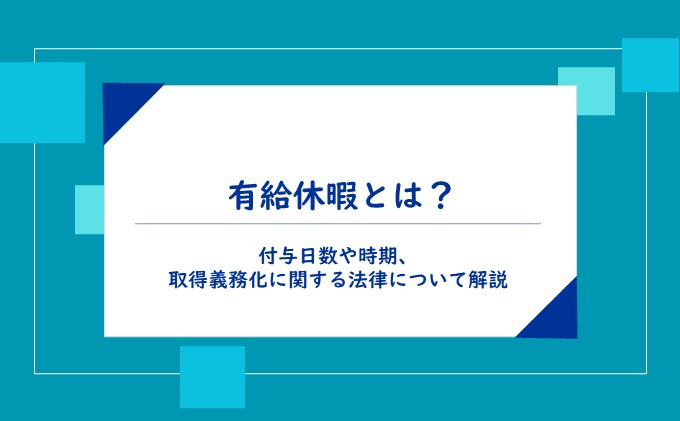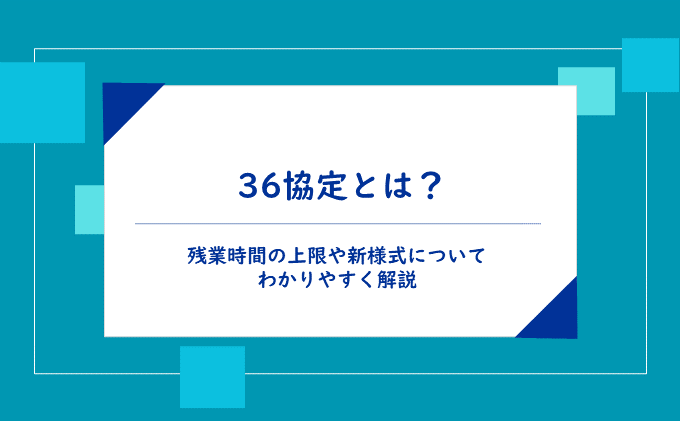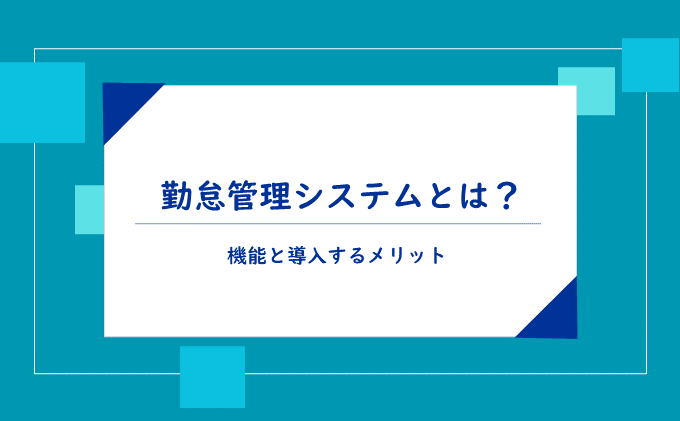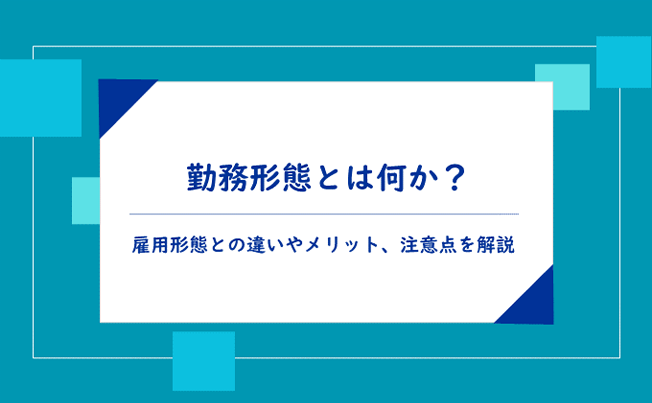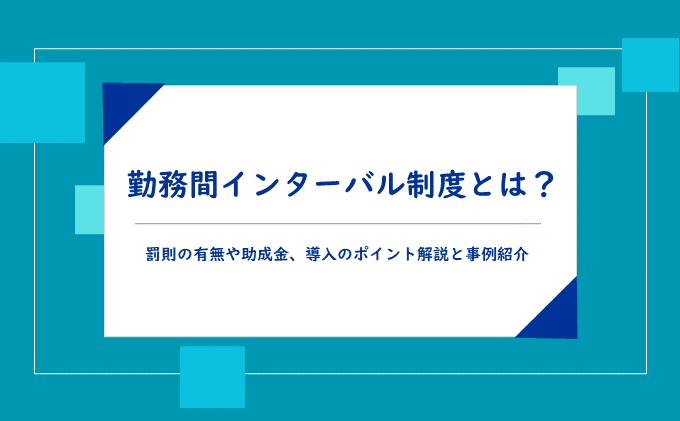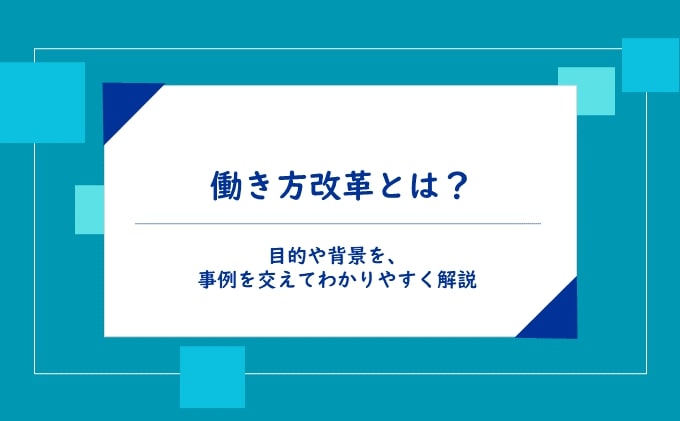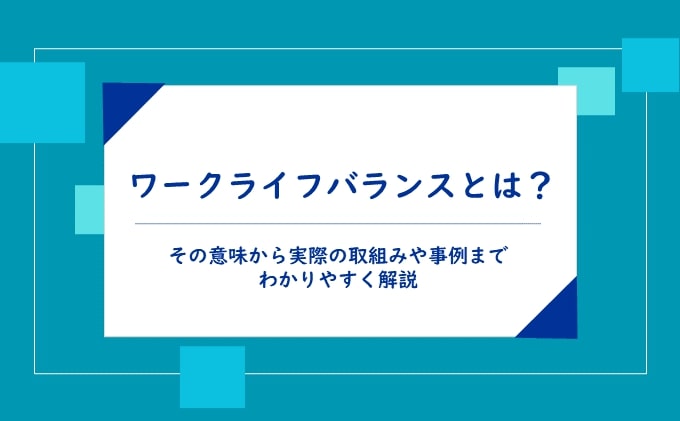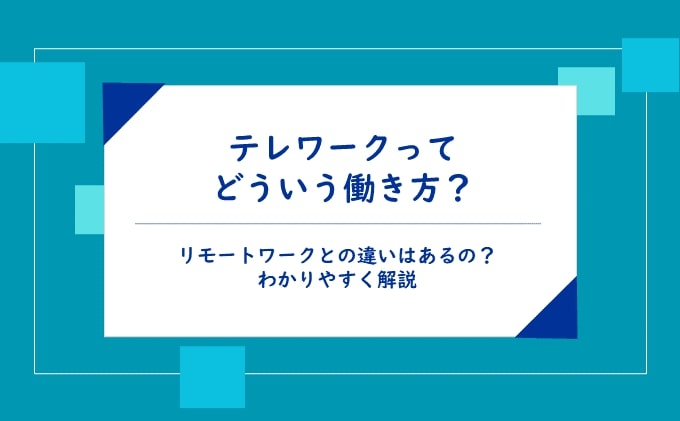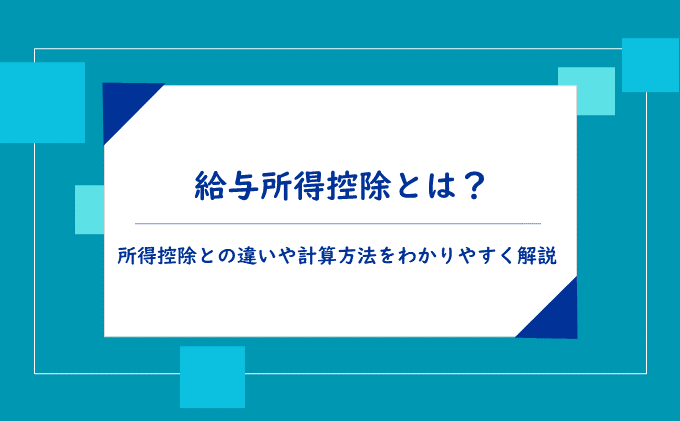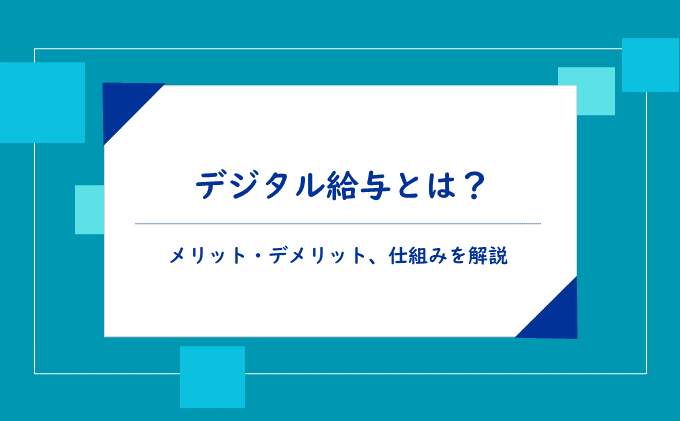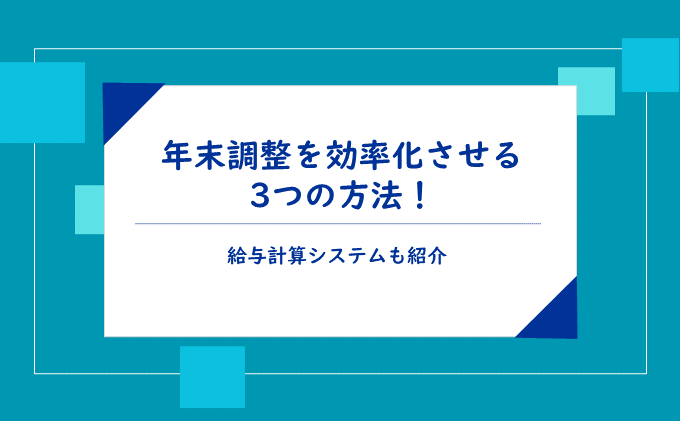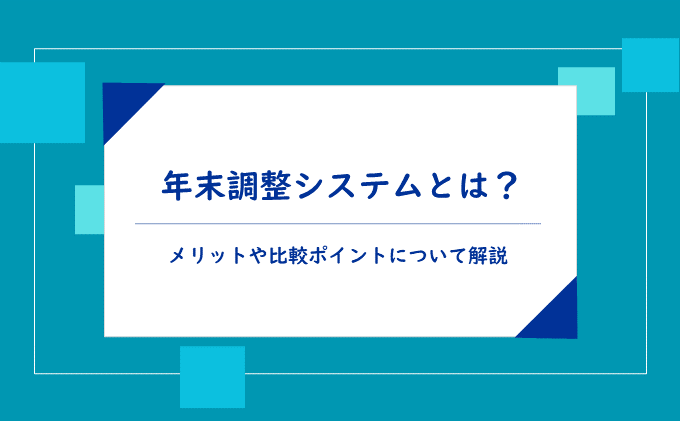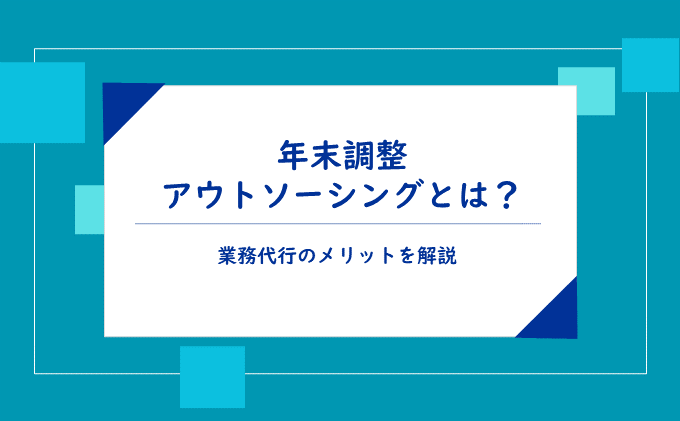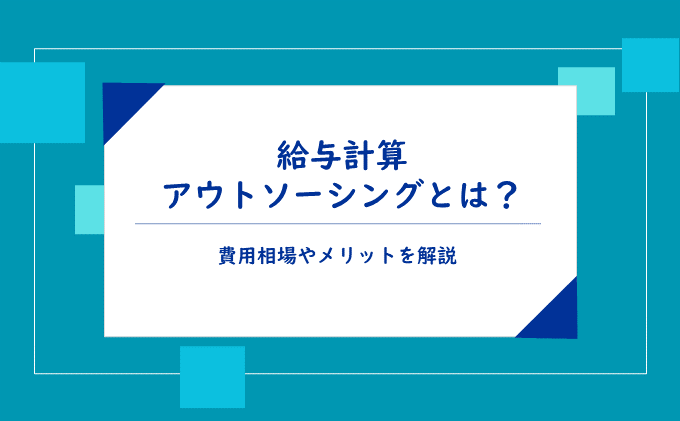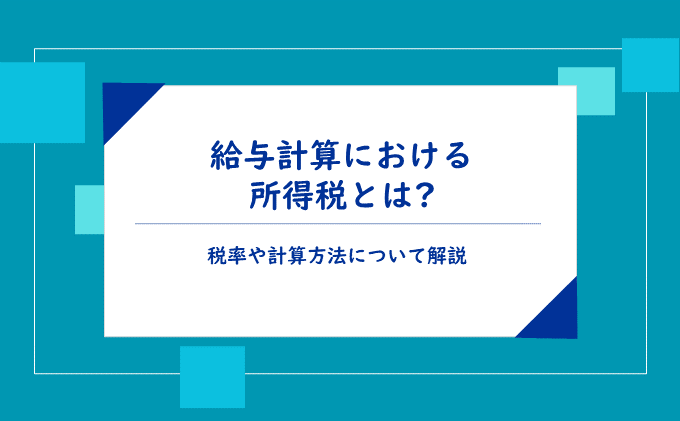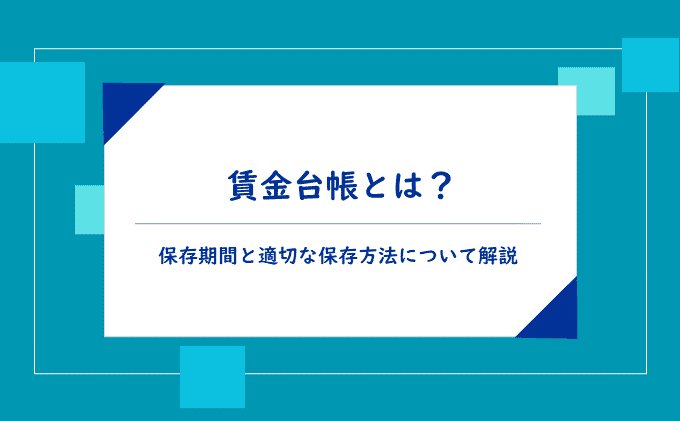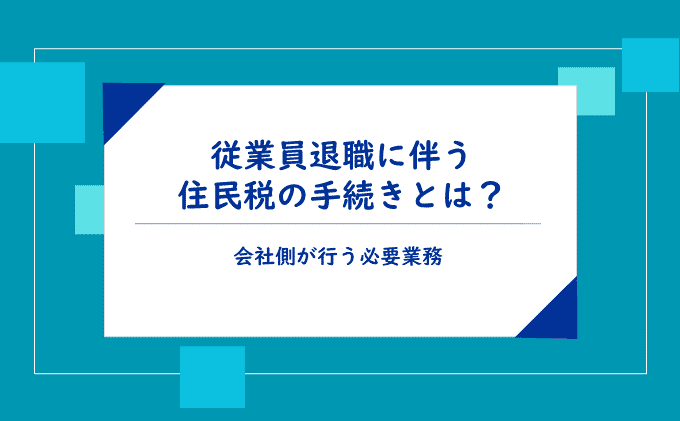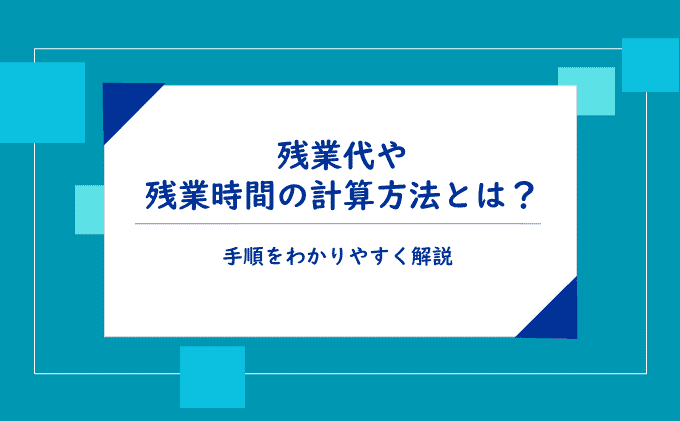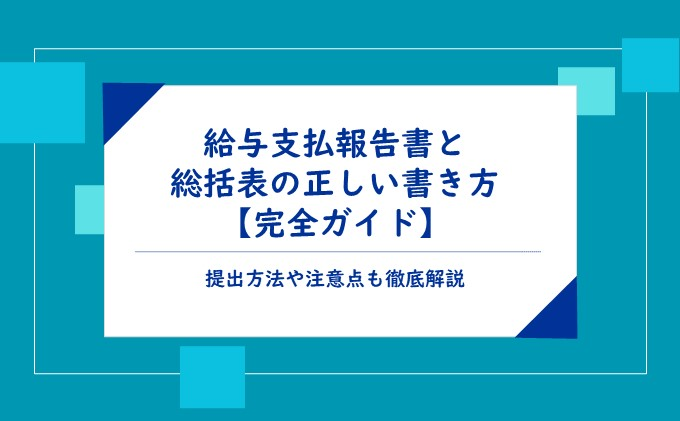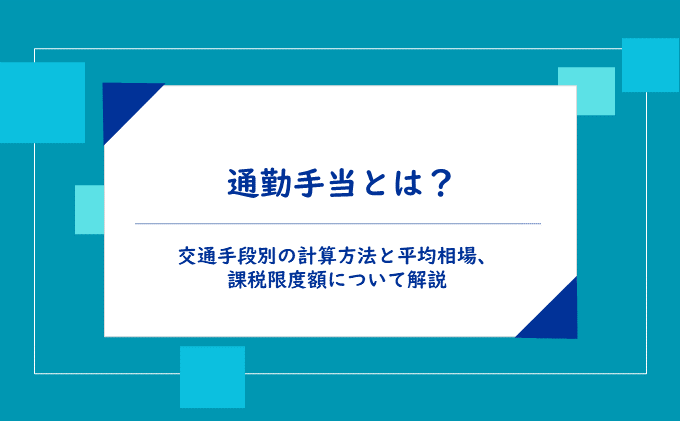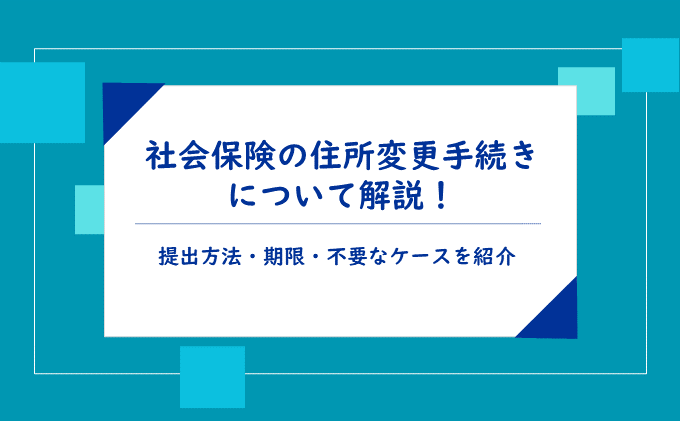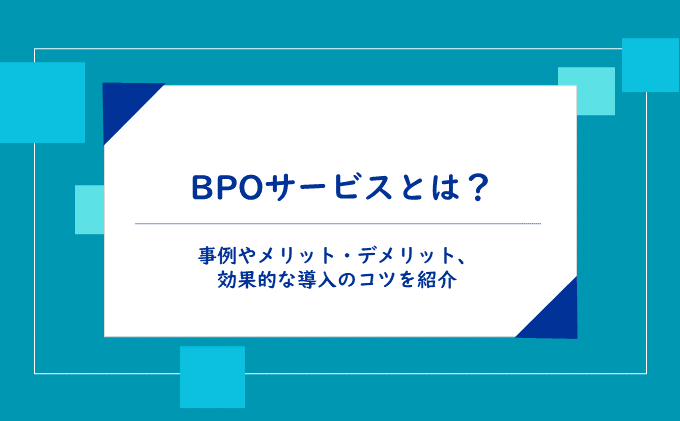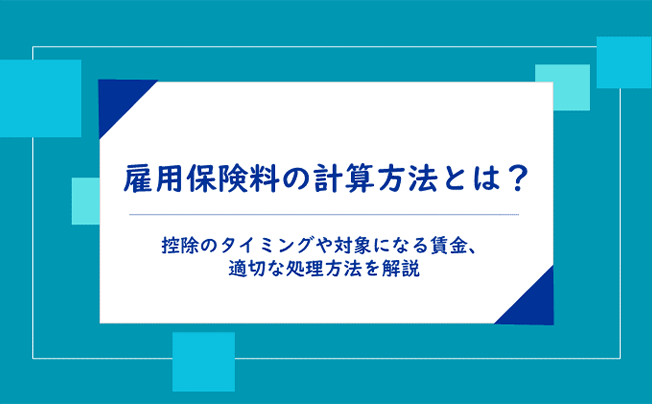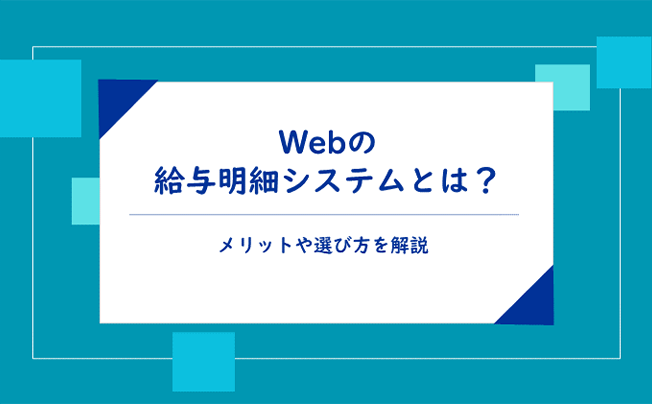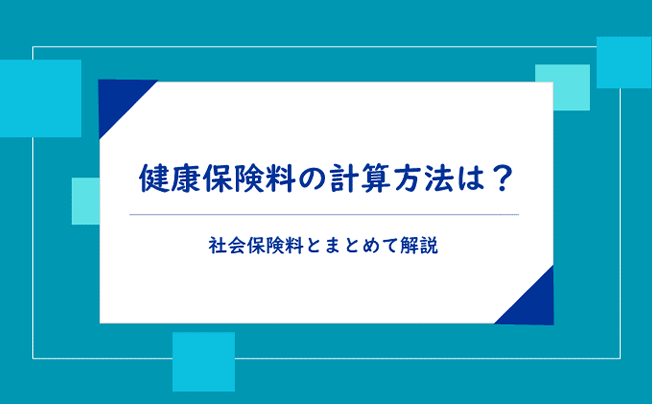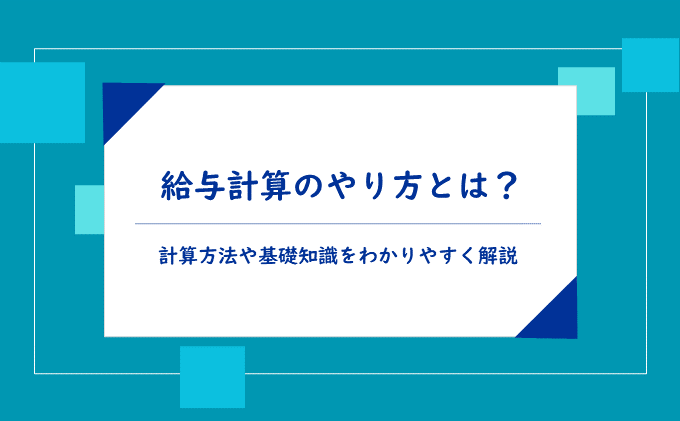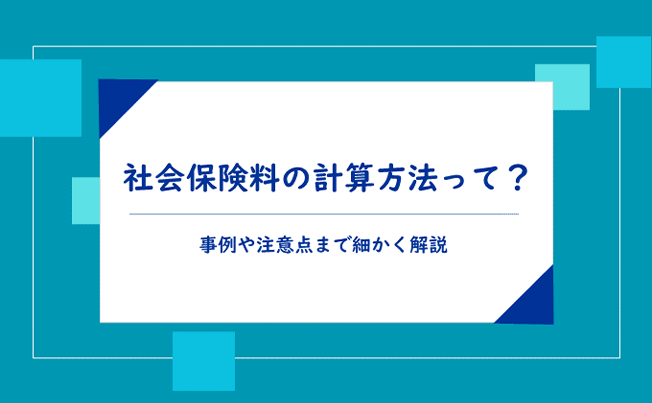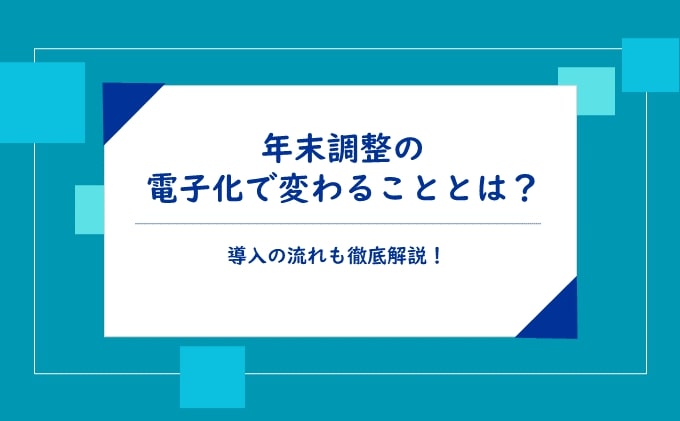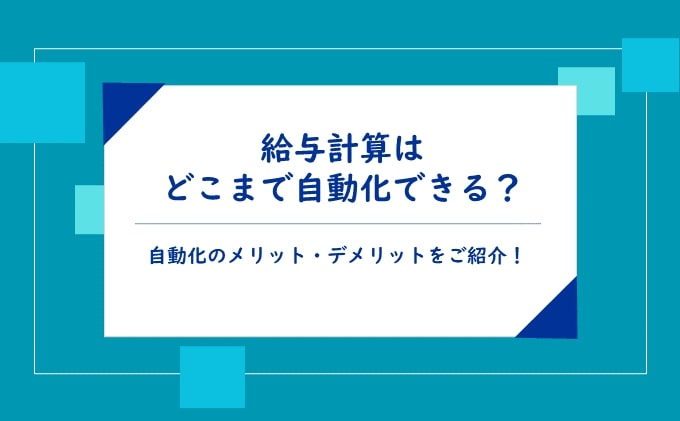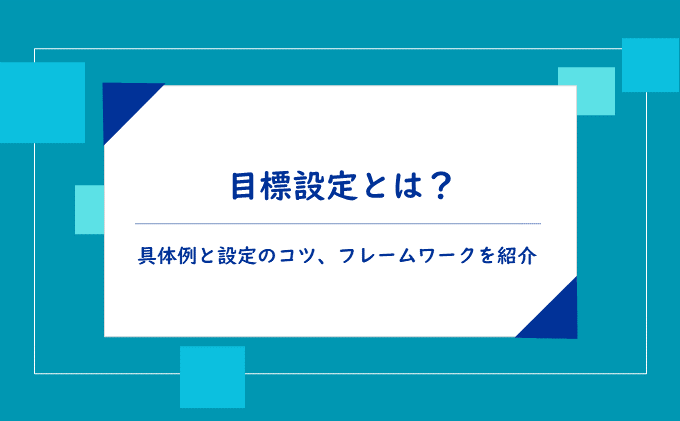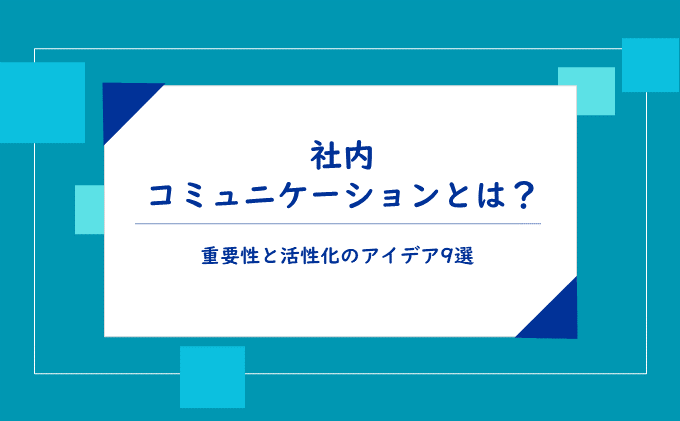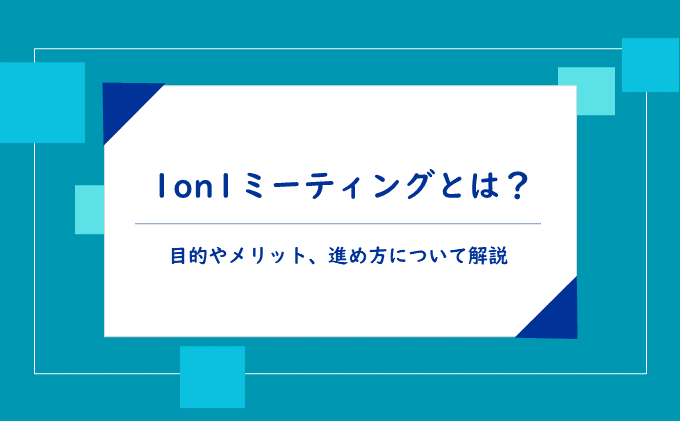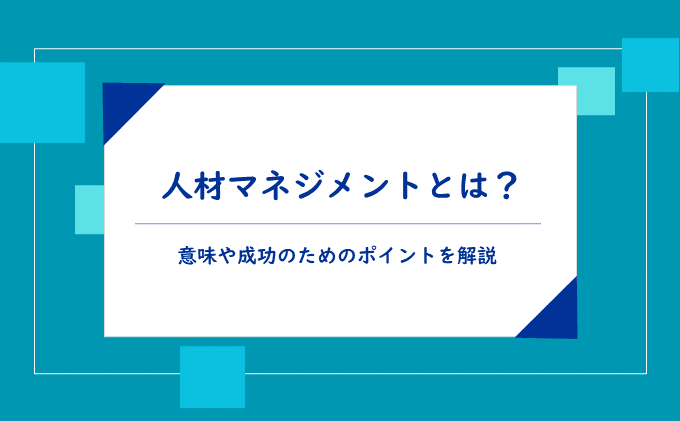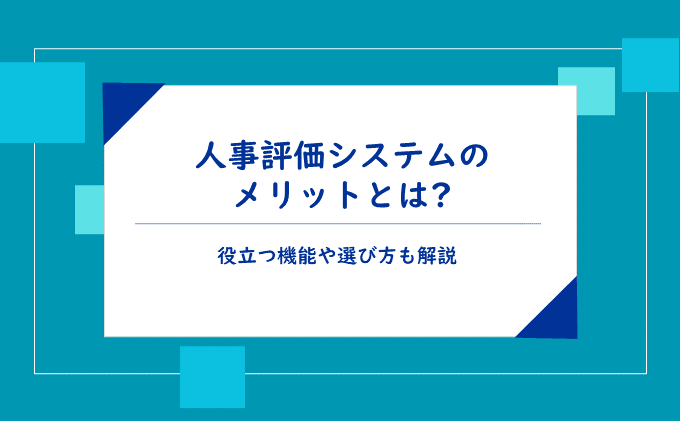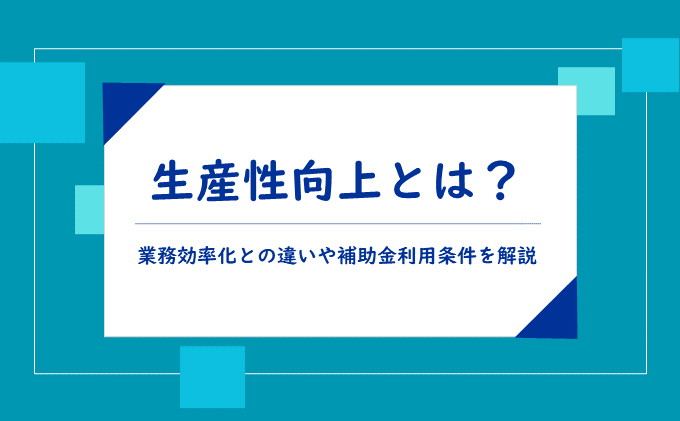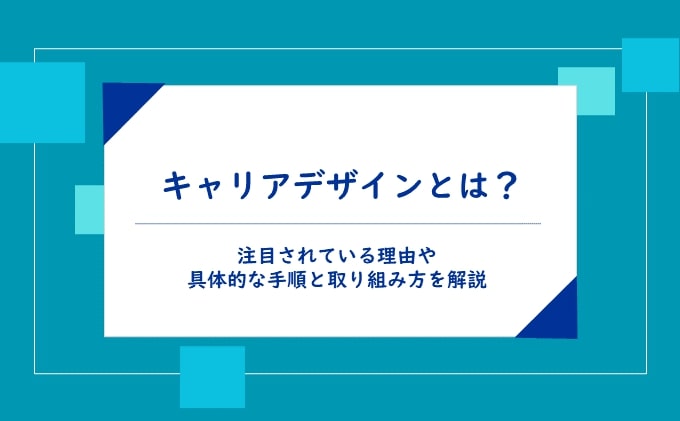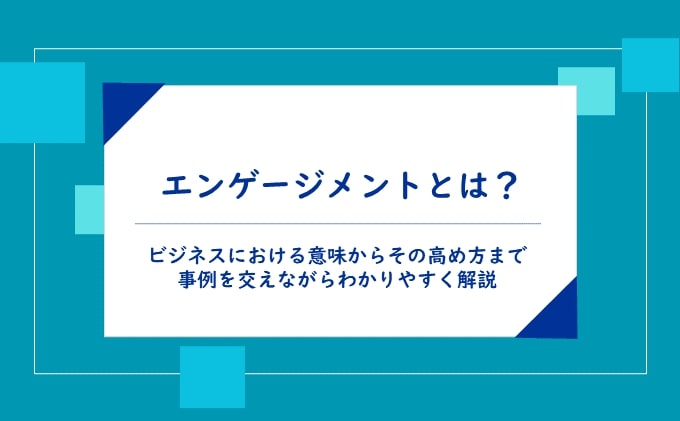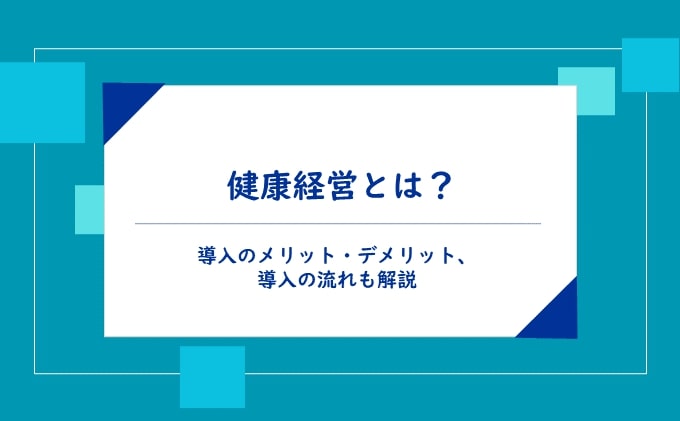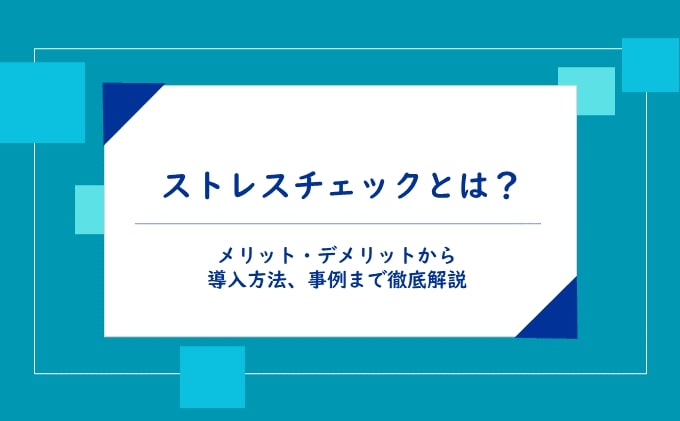【2025年施行】育児・介護休業法改正のポイントを解説
2025.06.11
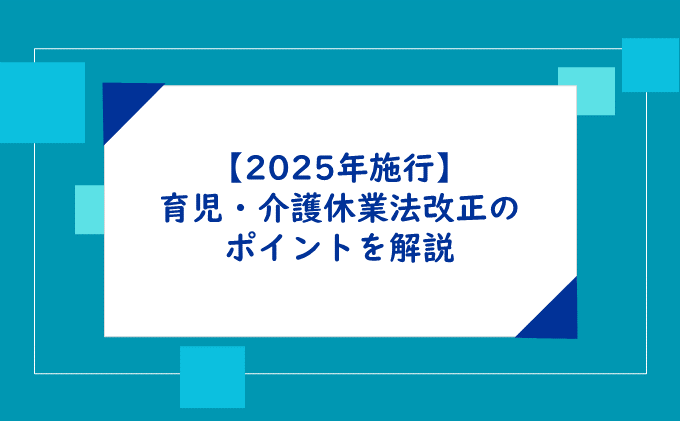
育児・介護休業法等の改正法が2025年4月1日と同年10月1日に施行されます。企業の人事・総務担当者としては、十分に把握して対応できるようにしておきたいところです。
本記事では、育児・介護休業法改正の変更点やポイントをまとめました。あわせて、育児・介護休業法改正へ対応するうえで役立つ人事管理システムについても解説します。
目次
【2025年4月・10月施行】育児・介護休業法改正の概要
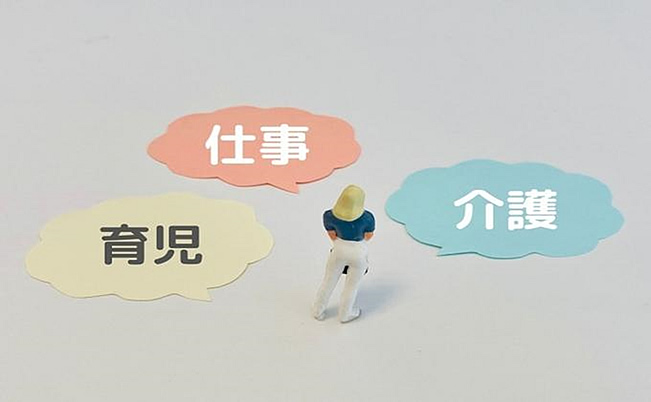
ここでは、育児・介護休業法改正の目的や内容について解説します。
育児・介護休業法とは、育児や介護を行う従業員が仕事と家庭生活を両立できるように支援する法律のことです。正式名称を「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」といいます。
育児・介護休業法改正の目的
育児・介護休業法改正の目的は、男女ともに仕事と育児、介護を両立できるようにすることです。今回の改正では、仕事と介護の両立支援や多様な働き方の選択、男性の育児参加の促進などに重点が置かれています。
仕事と家庭を両立できる環境が職場に整っていなければ、子育てや介護などを抱えた従業員が退職せざるを得ないケースが生じるかもしれません。企業が仕事と家庭の両立を支援できれば、子育てや介護をしながら働く従業員の退職防止にもつながります。
また、子育てや介護を理由に仕事を辞めた従業員の再就職促進効果も期待されています。過去に育児・介護休業法の改正で創設された育休制度については、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:育休手当(育児休業給付金)とは?計算方法や支給条件を解説
【2025年4月1日】施行の内容
2025年4月1日に施行される内容の一覧は次のとおりです。
- 子の看護休暇の見直し
- 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
- 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
- 育児のためのテレワーク導入
- 育児休業取得状況の公表義務適用拡大
- 介護休暇を取得できる従業員の要件緩和
- 介護離職防止のための雇用環境整備
- 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
- 介護のためのテレワーク導入
各施行内容の詳細については、次項で解説します。
【2025年10月1日】施行の内容
2025年10月1日に施行される内容の一覧は次のとおりです。
- 柔軟な働き方を実現するための措置等
- 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
各施行内容の詳細については、次項で解説します。
【2025年施行】育児・介護休業法改正のポイント

ここでは、育児・介護休業法改正のポイントを大きく3つに分けて紹介します。
- 「子の年齢に応じた柔軟な働き方」を実現するための措置の拡充
- 「育児休業取得状況の公表義務拡大」、「次世代育成支援対策の推進・強化」
- 仕事と介護の両立支援制度の強化等
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1.「子の年齢に応じた柔軟な働き方」を実現するための措置の拡充
改正法の変更ポイントのひとつに、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充があります。具体的な施策として、次の4つが挙げられます。
- 柔軟な働き方を実現するための措置の義務化
- 残業免除の対象が「3歳以上小学校就業前の子」を養育する従業員に拡大
- 子の看護休暇の対象や取得事由等の見直し
- 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置に努力義務としてテレワークが追加
柔軟な働き方を実現するための措置の義務化
改正によって、企業には3歳以上~小学校就学前の子を養育する従業員に対して、柔軟な働き方を実現するための措置を従業員が選択できるようにすることが義務付けられます。
柔軟な働き方を実現するための措置として、次のうち2つ以上を選択しなければなりません。
- 始業時刻等の変更
- 短時間勤務
- テレワーク(10日以上/月)
- 新たな休暇の付与(10日以上/年)
- その他働きながら子を養育しやすくするための措置(保育施設の設置運営等)
また、上記の措置を対象従業員に個別周知および意向確認を行うことも新たに義務付けられます。
残業免除の対象が「3歳以上小学校就業前の子」を養育する従業員に拡大
改正によって、残業免除の対象が「3歳以上小学校就業前の子」を養育する従業員に拡大されます。所定外労働の制限(残業免除)とは、対象従業員からの請求により所定労働時間を超える労働を禁止する制度のことです。
現行法では3歳になるまでの子を養育する者が対象でしたが、改正法では小学校就学前の子を養育する従業員まで対象範囲が拡大され、仕事と育児の両立がしやすくなることが期待されます。
子の看護休暇の対象や取得事由等の見直し
子の看護休暇の対象や取得事由等の見直しも変更点のひとつです。看護休暇とは、負傷または疾病にかかった子の世話などを行う際に取得する休暇を指します。
改正による、主な変更点は表のとおりです。
| 改正前 | 改正後 | |
| 名称 | 子の看護休暇 | 子の看護等休暇 |
| 対象 | 小学校就学の始期に達するまで | 小学校3年生修了まで |
| 取得事由 | 病気やけが 予防接種や健康診断 |
病気やけが 予防接種や健康診断 感染症にともなう学級閉鎖等 入園(入学)式、卒園式 |
| 労使協定締結で除外できる従業員 | 1:引き続き雇用された期間が6か月未満 2:週の所定労働日数が2日以下 |
週の所定労働日数が2日以下 ※左記の1を撤廃し、2のみに |
改正にともない、子の学校行事に参加する際や学級閉鎖が生じた際にも看護休暇の取得が可能になります。また、労使協定に基づいて、勤続6か月未満の従業員は看護休暇の取得対象外にできなくなるため、企業によっては労使協定の内容確認と見直しが必要です。
短時間勤務制度の代替措置に努力義務としてテレワークが追加
改正により、短時間勤務制度の代替措置に対する努力義務として、テレワークが新たに追加されます。具体的には、3歳未満の子を養育する従業員が育児休業を取得しない場合、企業には新たに努力義務として在宅勤務等(テレワーク)の措置を講じなければなりません。
措置を講じない場合でも罰則等はありませんが、従業員の仕事と育児の両立に対して積極的な対応が期待されています。
仕事と育児の両立に関する意向聴取・配慮の義務化
企業に対して、従業員の仕事と育児の両立に関しての意向聴取・配慮が義務付けられます。
個別の意向聴取は、妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の適切な時期に行う必要があります。子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立について、従業員の意向を確認しなければなりません。
聴取内容は、次のようなことです。
- 勤務時間帯(始業および終業の時刻)
- 勤務地
- 両立支援制度等の利用期間
- 仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)
聴取した従業員の意向に対して、自社の状況に応じた配慮が必要です。たとえば、勤務時間の変更や勤務地に対する配慮などです。
また、企業は従業員から聴取した意向を理由として、解雇その他不利益な取り扱いをしてはなりません。
2.「育児休業取得状況の公表義務拡大」、「次世代育成支援対策の推進・強化」
改正法の変更ポイントのひとつに、育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化があります。
ここでは、各変更点について解説します。
育児休業取得状況の公表義務適用拡大
育児休業取得状況の公表義務の対象となる企業が拡大されます。現行法では、従業員数1,000人超の企業が適用対象ですが、改正法では従業員数300人超の企業が対象です。公表義務の範囲拡大により、育児休業の取得促進が幅広い企業において期待されます。
次世代育成支援対策推進法に関する改正
今回の法改正では、次世代育成支援対策推進法に関する改正も盛り込まれています。次世代育成支援対策推進法とは、次世代育成支援対策の基本理念や行動計画策定指針などをまとめた法律のことです。
次世代の子どもを育成するうえでも、従業員による育児休業の取得促進や仕事と育児の両立は重要な問題です。今回の法改正では、従業員数100人超の事業主に対して、行動計画策定時に育児休業の取得状況等に係る状況把握および数値目標の設定が新たに義務付けられました。
また、2025年3月31日に失効する予定だった次世代育成支援対策推進法は、2035年3月31日まで10年間延長されます。
3.仕事と介護の両立支援制度の強化等
改正法の変更ポイントのひとつに、仕事と介護の両立支援制度の強化等があります。具体的な変更点は、次のとおりです。
- 介護離職防止に向けた雇用環境の整備
- 介護休暇取得に関する要件緩和
- 介護に直面した従業員に対する個別の周知および意向確認
- 家族を介護する従業員のためのテレワーク導入
各変更点について解説します。
介護離職防止に向けた雇用環境の整備
従業員が介護休業や介護両立支援制度等の申し出をしやすくなるように、企業に対して以下のいずれかの措置を講じることが努力義務として課せられます。
- 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
- 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
- 自社の従業員の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
- 自社の従業員の介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
介護休暇取得に関する要件緩和
介護休暇取得に関する要件も緩和されます。介護休暇取得の条件である「継続雇用期間6か月未満」が撤廃されます。
介護休暇とは、要介護状態の家族の世話をするために取得する休暇です。改正により、勤続6か月未満の従業員でも一律に介護休暇の取得が可能になります。
介護に直面した従業員に対する個別の周知および意向確認
介護に直面した旨の申出をした従業員に対して、企業は介護休業制度等に関する事項の周知と利用に関する意向の確認を個別に行うことが義務化されます。周知事項として、次のような内容が挙げられます。
- 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容)
- 介護休業・介護両立支援制度等の申出先
- 介護休業給付金に関すること
また、介護に直面する早い段階(40歳等)での情報提供が、努力義務として新たに設けられます。推奨されている情報提供期間や情報提供事項は、次のとおりです。
<情報提供期間>
- 従業員が40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度(1年間)
- 従業員が40歳に達する日の翌日(誕生日)から1年間 のいずれか
<情報提供事項>
- 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容)
- 介護休業・介護両立支援制度等の申出先
- 介護休業給付金に関すること
情報提供にあたり、介護に関連する休業制度の趣旨や目的を明確にと伝えることが重要です。また、介護保険制度の内容に対する十分な理解が必要です。
家族を介護する従業員のためのテレワーク導入
企業には、要介護状態にある対象家族を介護する従業員が介護休業をしていない場合、在宅勤務等(テレワーク)の措置を選択できるようにすることが、新たに努力義務として課されます。
在宅勤務等の措置を講じないことに対して、罰則等はありません。従業員の仕事と介護の両立をサポートするうえでも、積極的に措置を講じることが企業に対して求められます。
育児・介護休業法改正において事業者がとるべき対応

育児・介護休業法改正において事業者がとるべき対応について解説します。主な対応は、次の3つです。
- 就業規則および業務体制の見直し
- 従業員への改正内容の周知
- 取得対象者の把握と取得日数の管理
企業の人事担当者は対応策を把握しておきましょう。
就業規則および業務体制の見直し
企業には、法改正にあわせて自社の就業規則の見直しや追記・修正が求められます。また、労働時間の短縮や休業取得者の増加などによって、既存の従業員だけで対応できない場合は業務体制の再考も必要です。
見直す際は、改定が必要な項目の洗い出しから行いましょう。育児休業・介護休業の取得対象者の要件として「引き続き雇用された期間が1年以上」と記載されていれば、削除が必要です。
現状の就業規則に対して、多くの修正点が発生する企業もあるかもしれません。就業規則のおよび業務体制の見直しは時間がかかる作業です。施行開始時期が決定しているため、早めに取り組みましょう。
従業員への改正内容の周知
法改正が行われたことを従業員へ周知する必要もあります。育児・介護休業法の変更点を従業員が正しく理解しておかなければ、トラブルにつながる恐れがあります。
また、従業員に説明する立場である管理職等は、法律の変更点を十分に理解しておかなければなりません。理解が不足していれば、従業員に誤った説明をしてしまう可能性があります。
なお、法改正にともなう変更点を伝える際には、研修の実施が有効です。研修を通して、すべての階層の従業員に周知し、育児・介護休業についての理解を会社全体で深めましょう。
取得対象者の把握と取得日数の管理
育児休業取得率の公表義務が拡大されるため、法改正に向けて育児休業の取得対象者や取得日数などを正確に把握することが重要です。また、公表内容や公表方法もあわせて検討する必要があります。
厚生労働省では、自社ホームページのほか、厚生労働省の「両立支援のひろば」での公表を推奨しています。両立支援のひろばとは、仕事と家庭の両立の取り組みを支援するサイトです。企業や従業員向けに役立つ情報が掲載されています。
なお、公表時期の目安は決算時期からおおむね3か月以内です。事業年度末が2025年9月であれば2025年12月末となります。今から公表の準備を進めましょう。
勤怠管理に役立つ人事管理システム「ADPS(アドプス)」

育児・介護休業法により、企業の人事・総務部門は、就業規則の見直しや修正、従業員の育児休業取得状況の確認などの作業が必要です。従業員の休暇状況を自動的に把握できる勤怠管理システムを導入すれば、作業漏れやミスを防止できるだけでなく、担当者の負担も軽減できます。
1990年に誕生した、カシオヒューマンシステムズ株式会社が提供する人事管理システム「ADPS」は、累計5,000社を超える導入実績を誇ります。法令遵守はもちろん、従業員の休暇や出退勤の管理などを手軽に行える点が魅力です。
また、ADPSは時短勤務取得にともなう労働時間や勤務シフトの変更など、複数の勤務体制の管理にも対応しています。育児・介護休業法改正による就業規則および業務体制の見直しにも役立ちます。
勤怠管理をスムーズに行えるように、人事管理システム「ADPS」の導入を検討しましょう。
まとめ

育児・介護休業法等の改正法が2025年4月1日と同年10月1日に施行されます。法改正の目的は、仕事と育児、介護を男女がいずれも両立できることで、関連した項目が主な変更点です。
企業は法改正に沿って、就業規則や業務体制の見直しをはじめ、従業員への改正内容の周知、育児休業取得対象者の把握と取得日数の管理などが求められます。多くの変更点があるため、本記事を参考にして確実に対応しましょう。
カシオヒューマンシステムズコラム編集チームです。
人事業務に関するソリューションを長年ご提供してきた知見を踏まえ、
定期的に「人事部の皆様に必ず今後の業務に役立つ情報」を紹介しています。