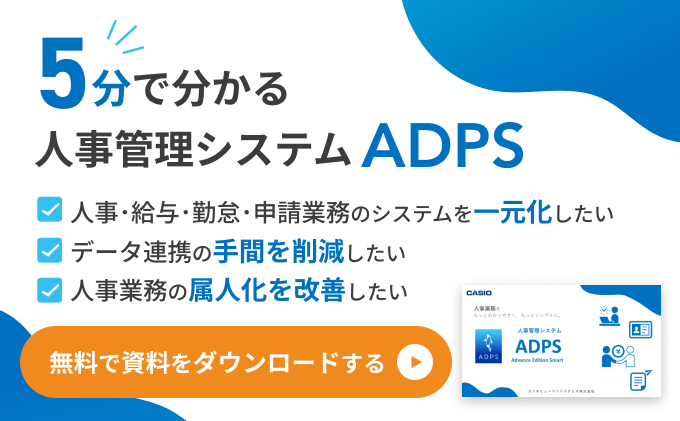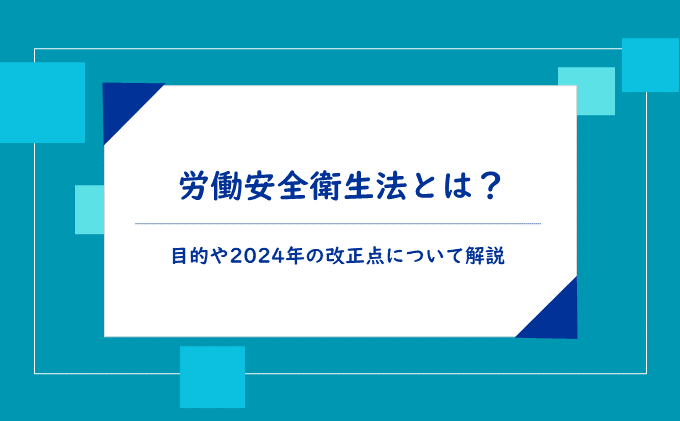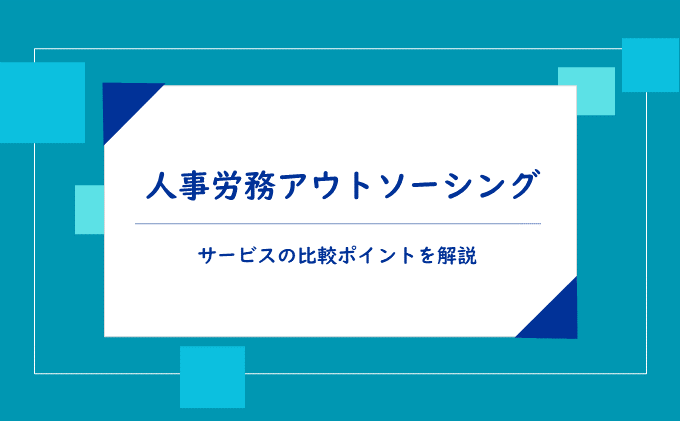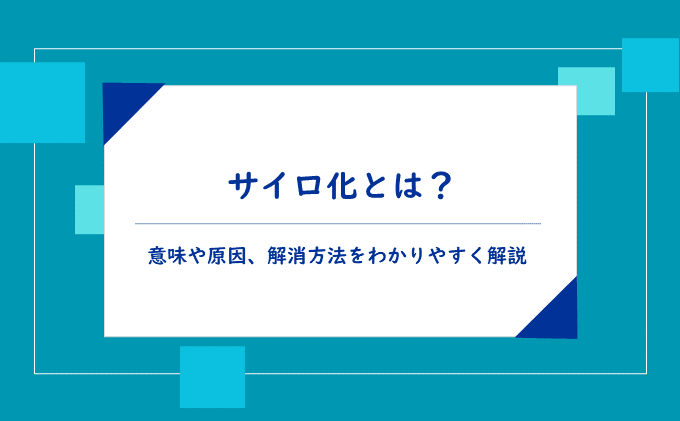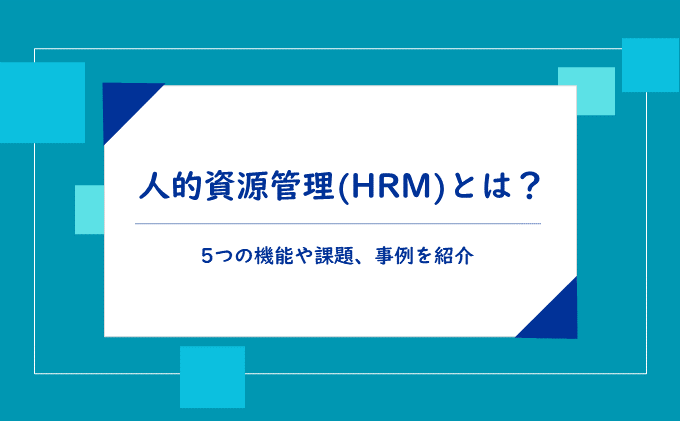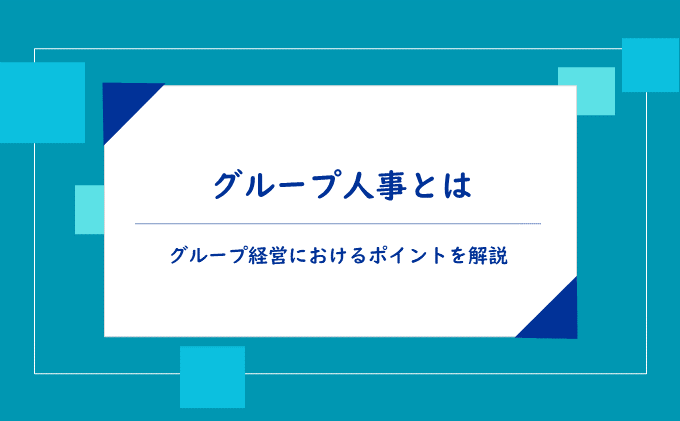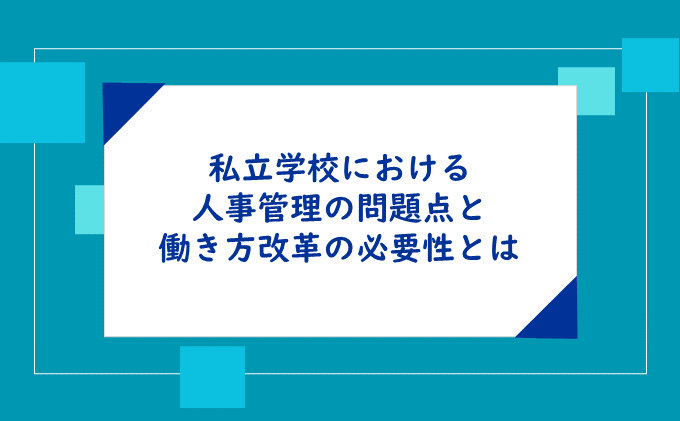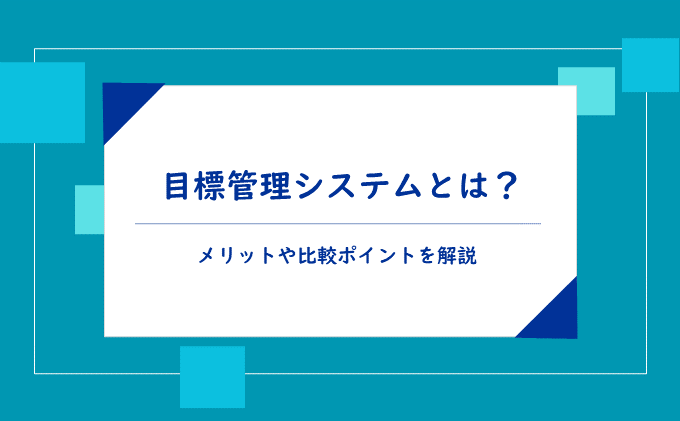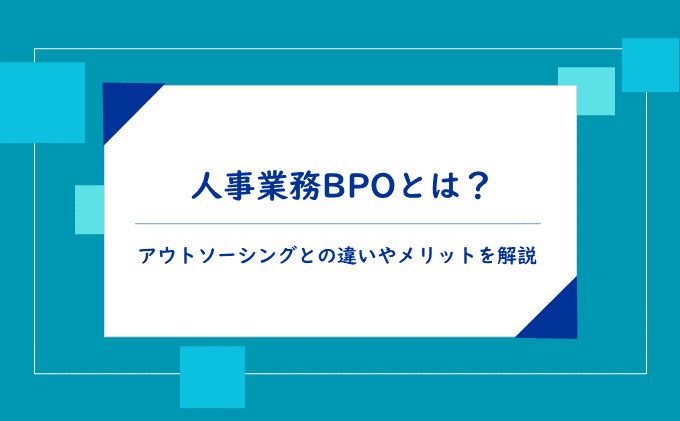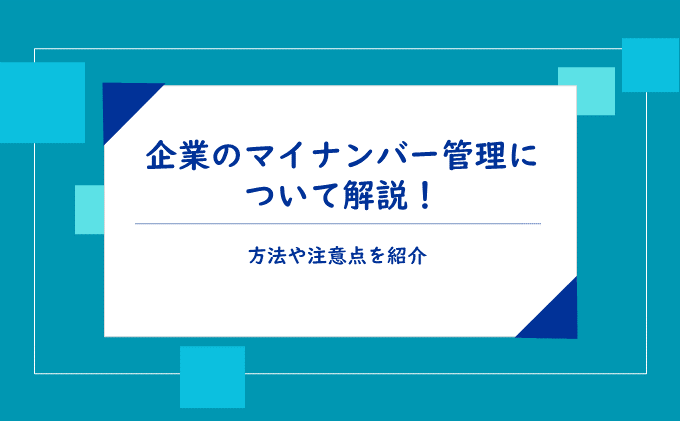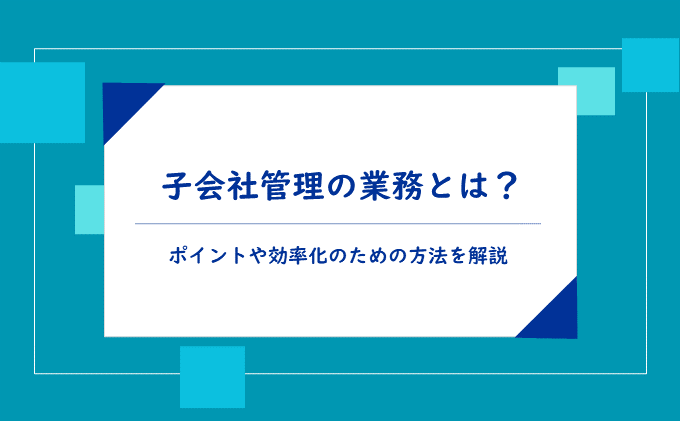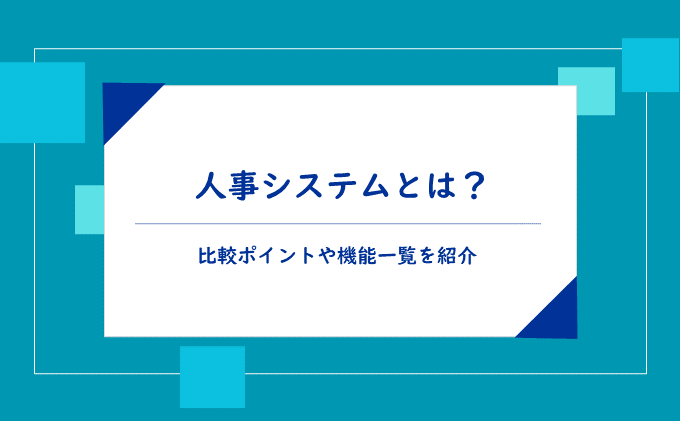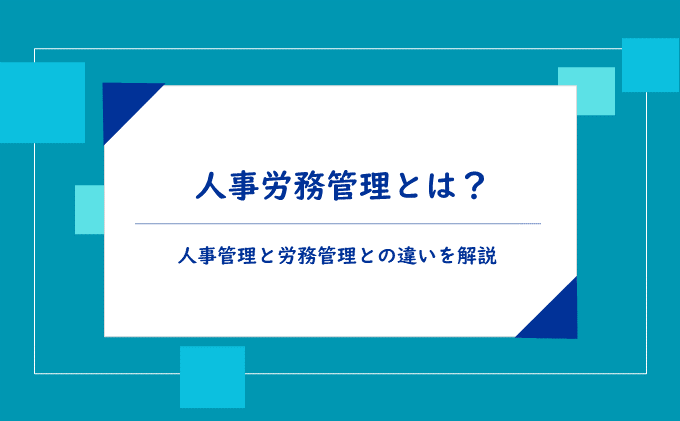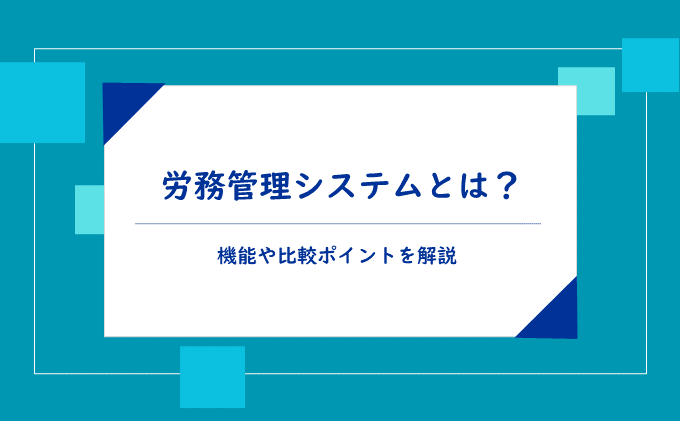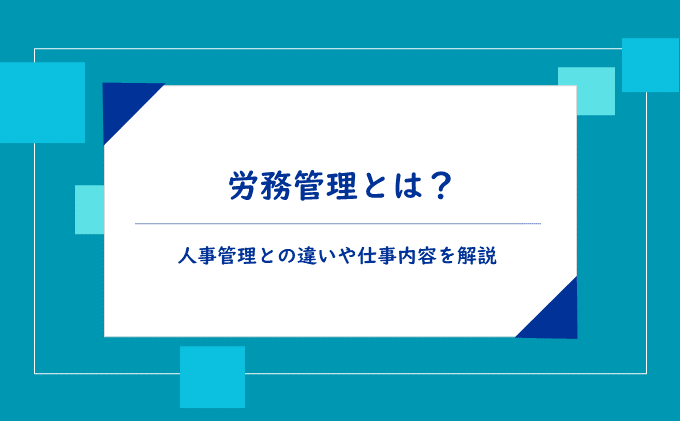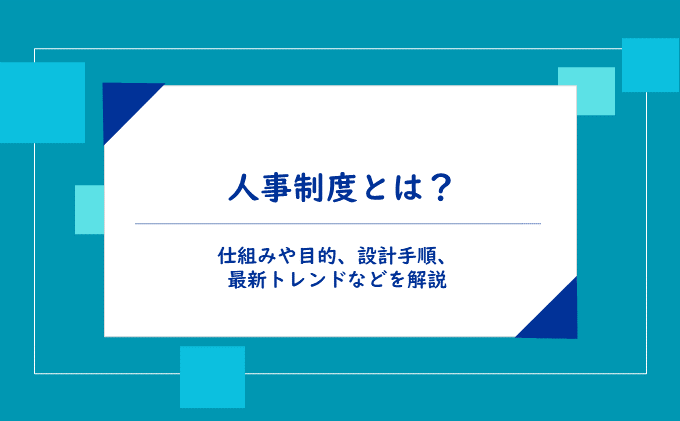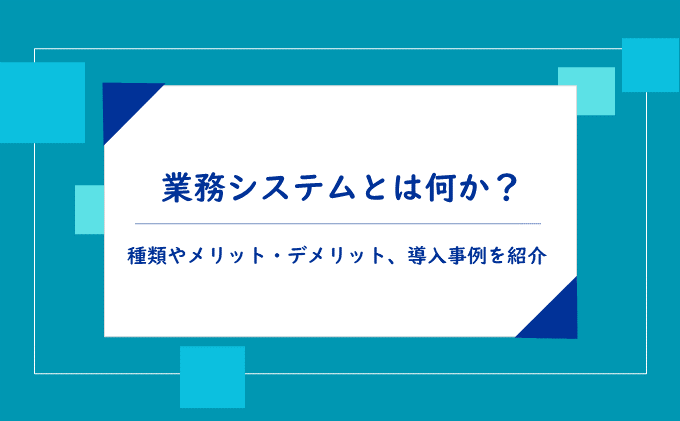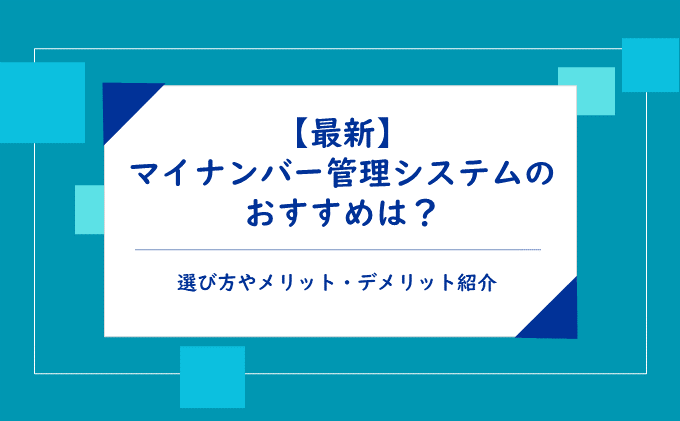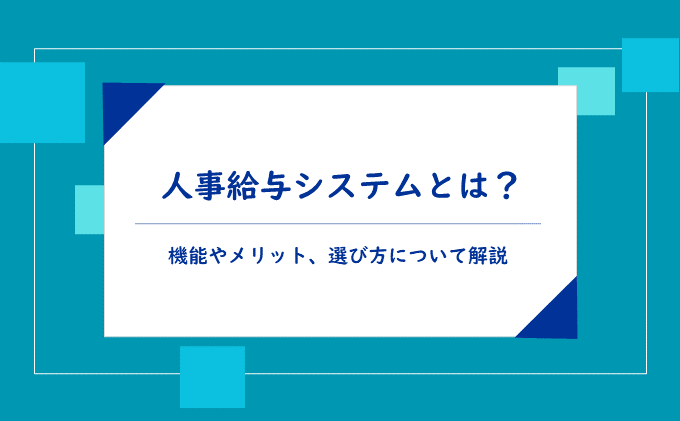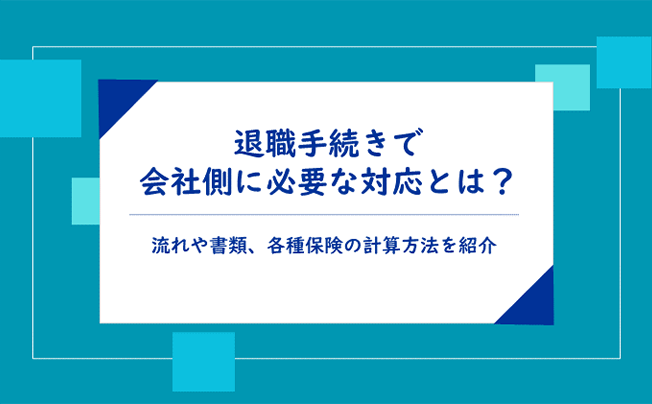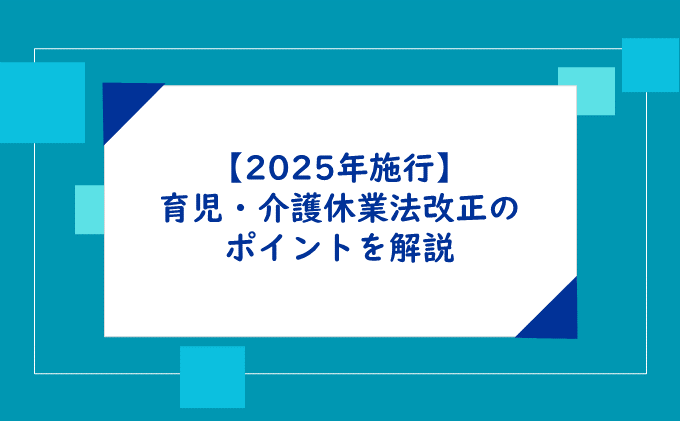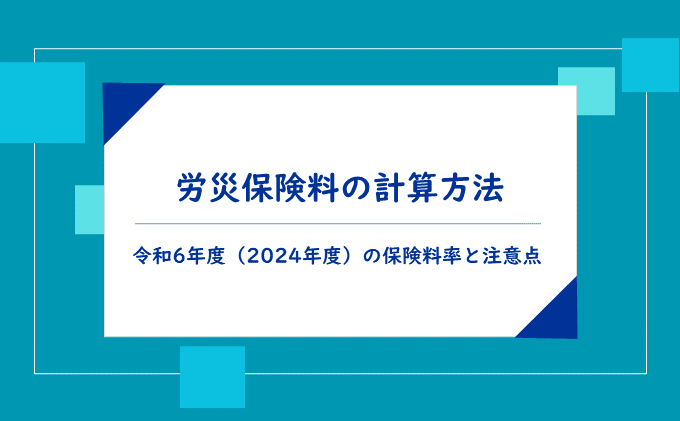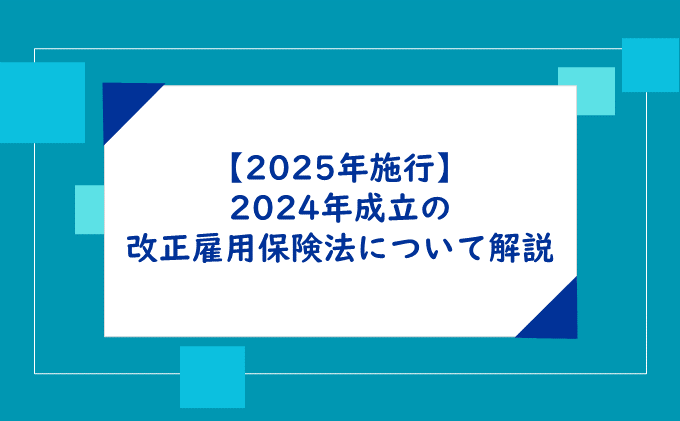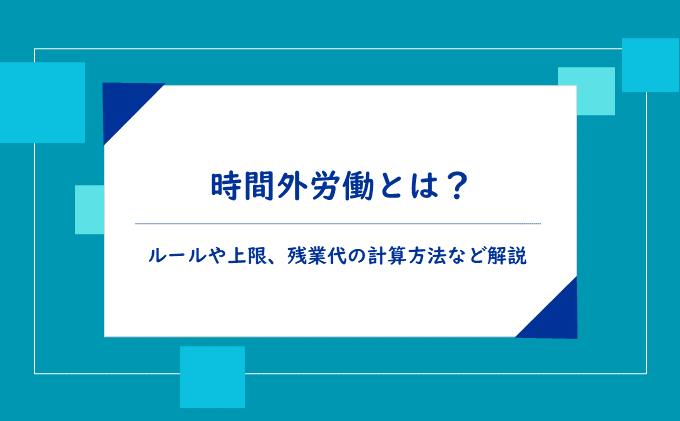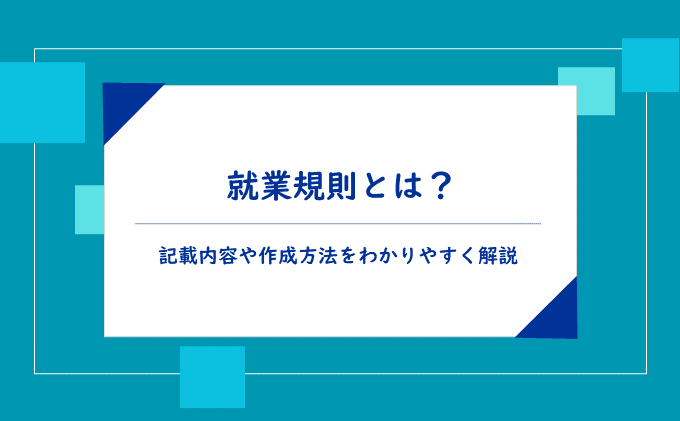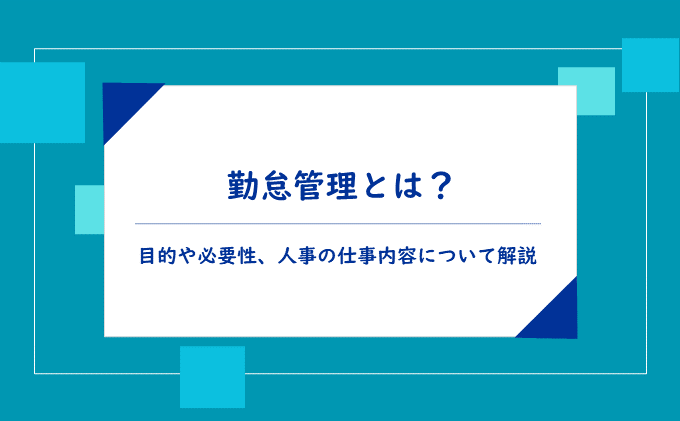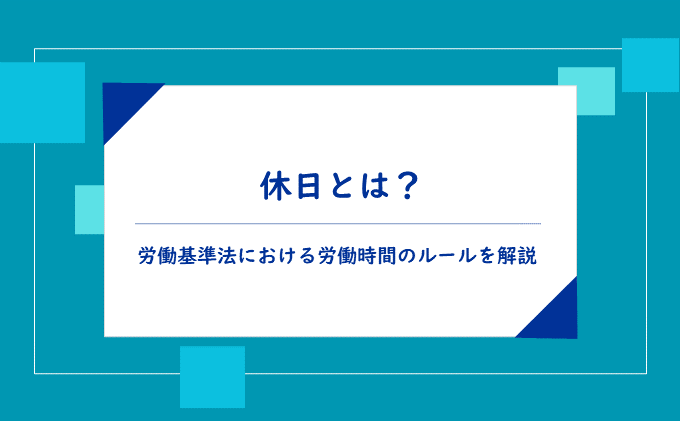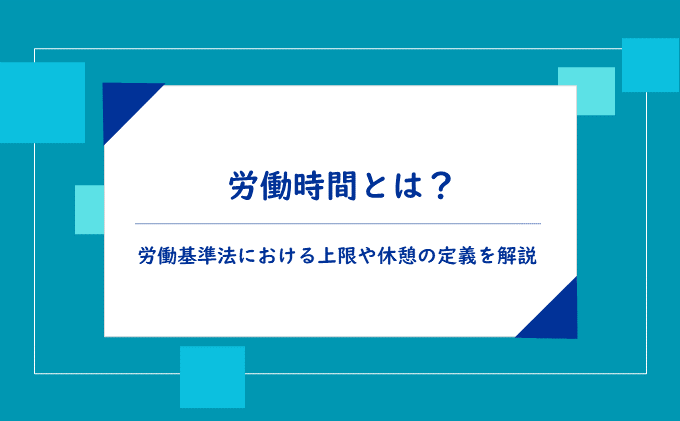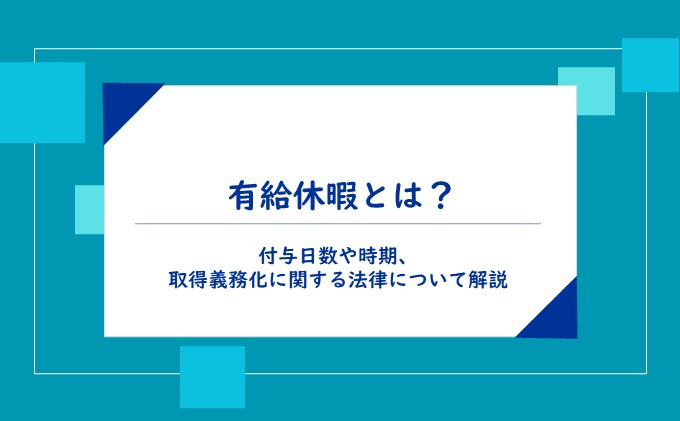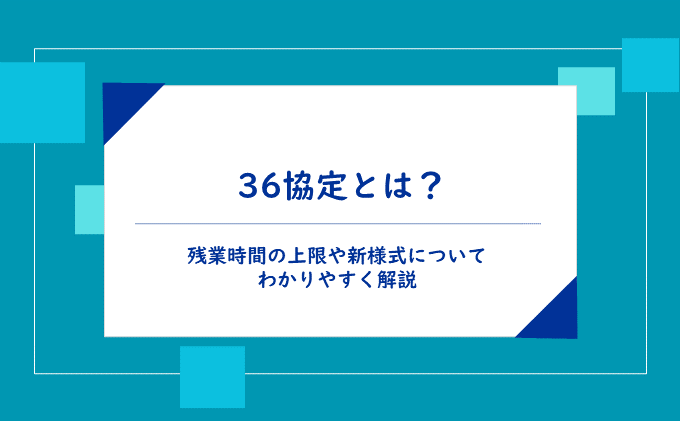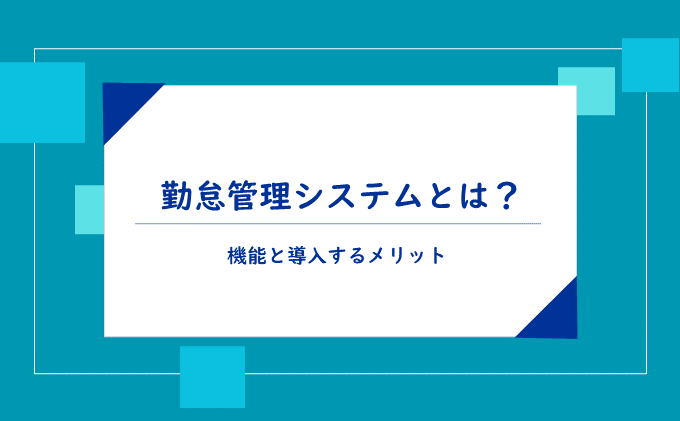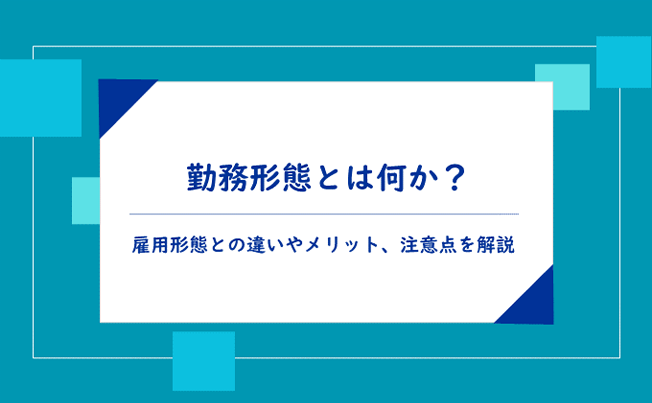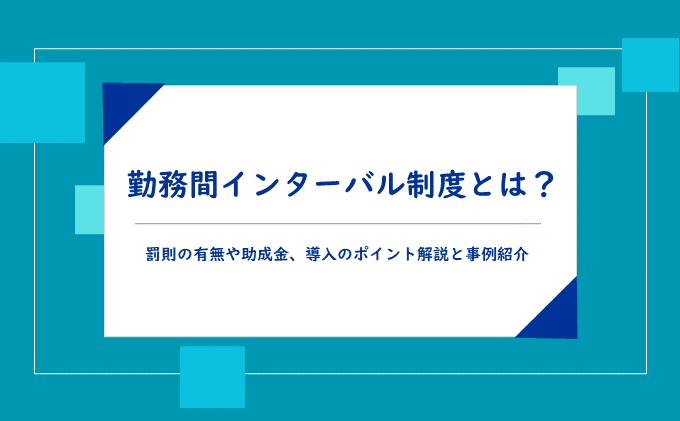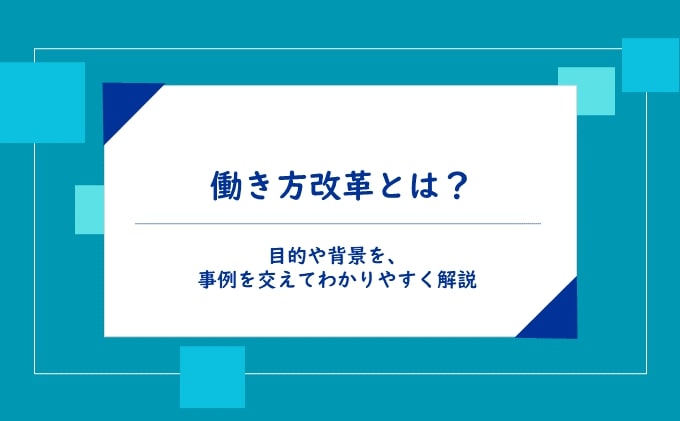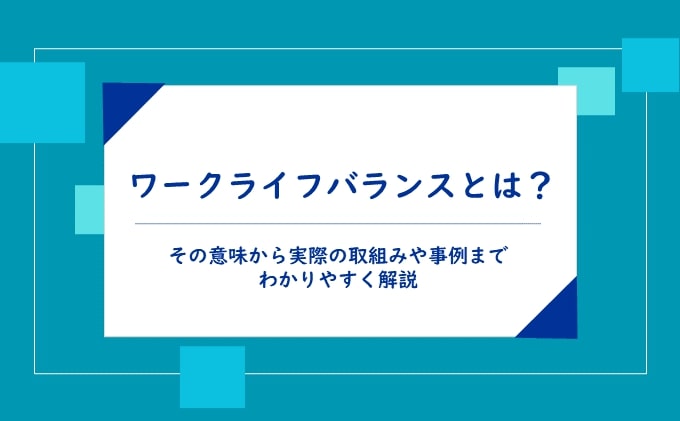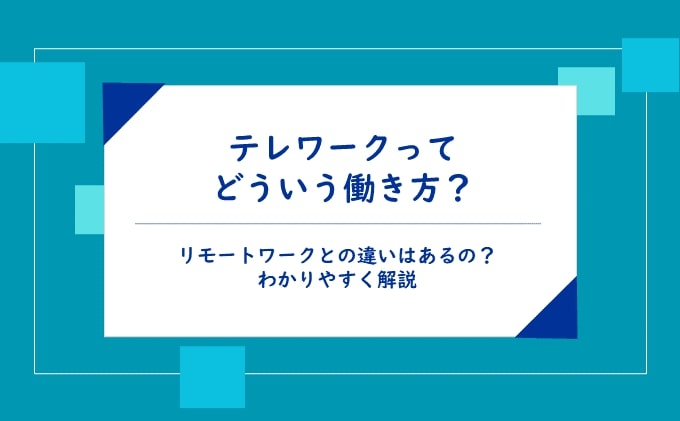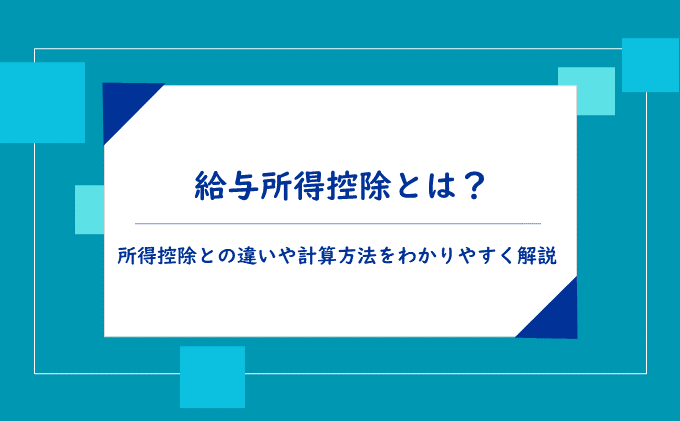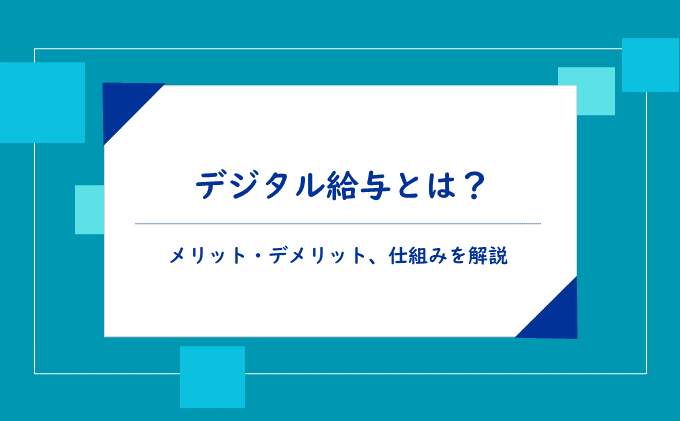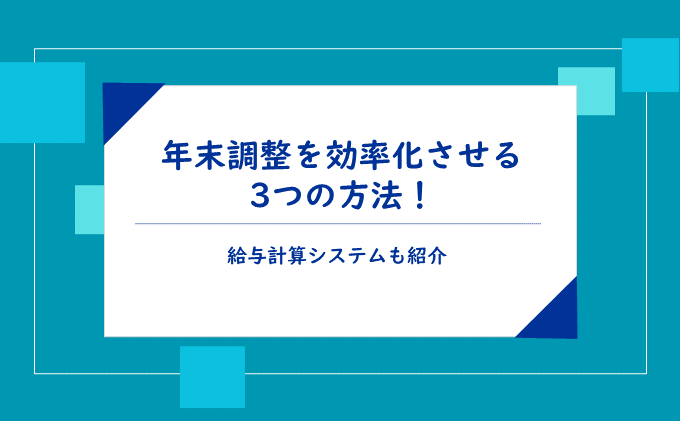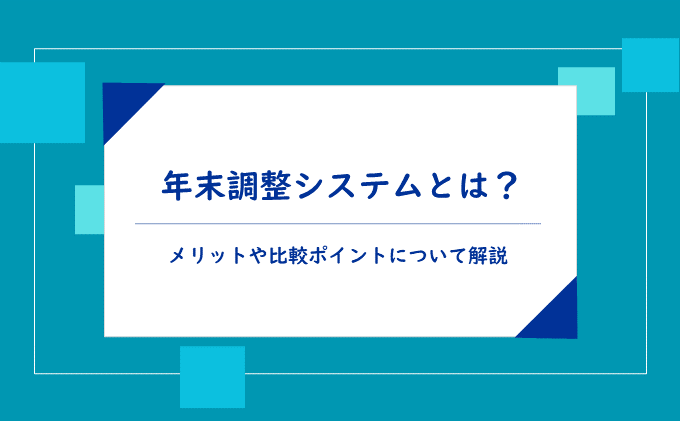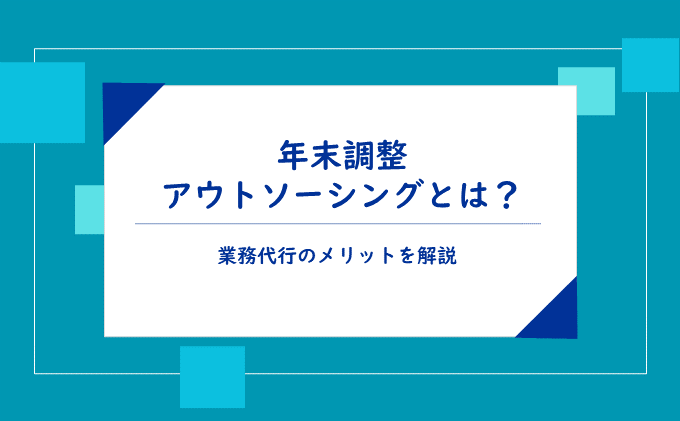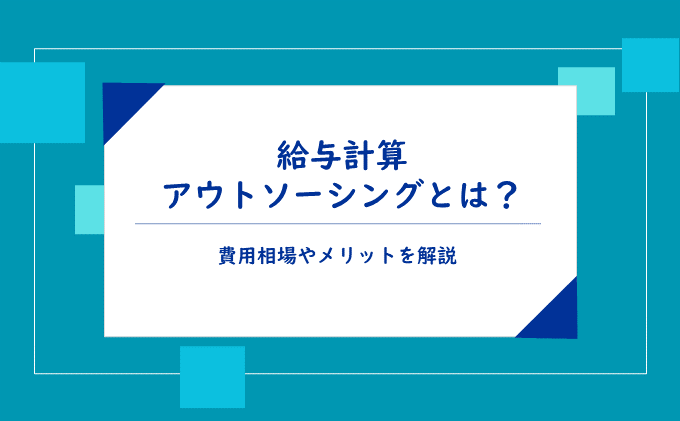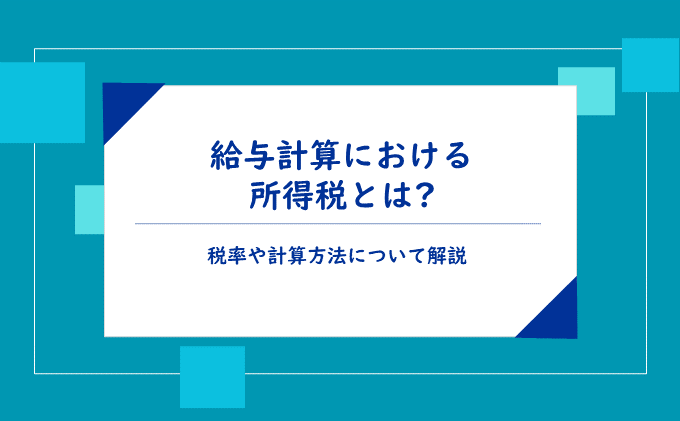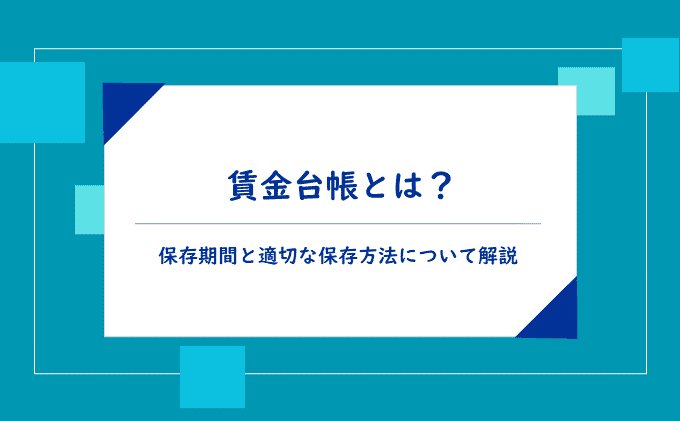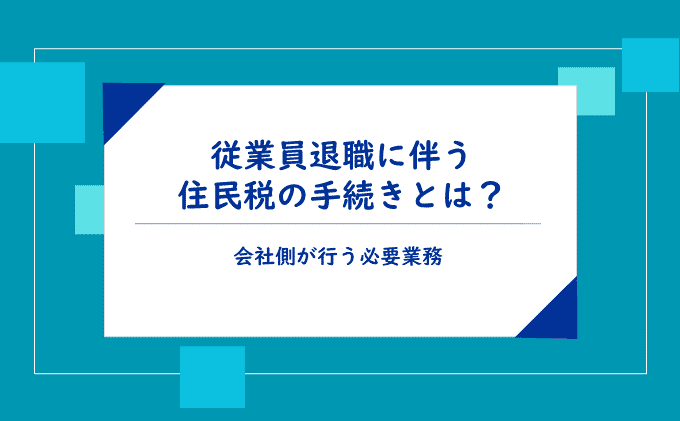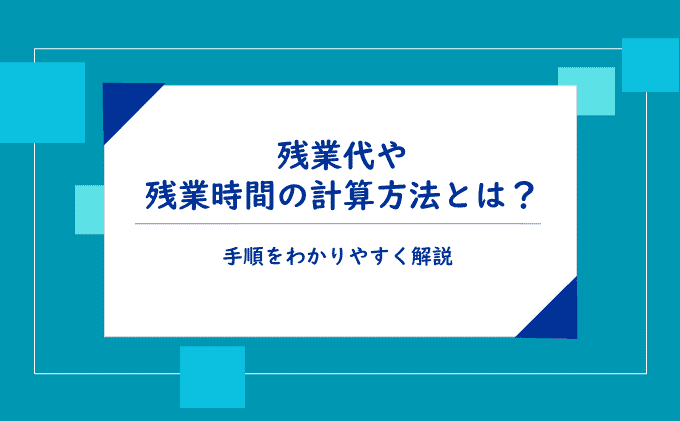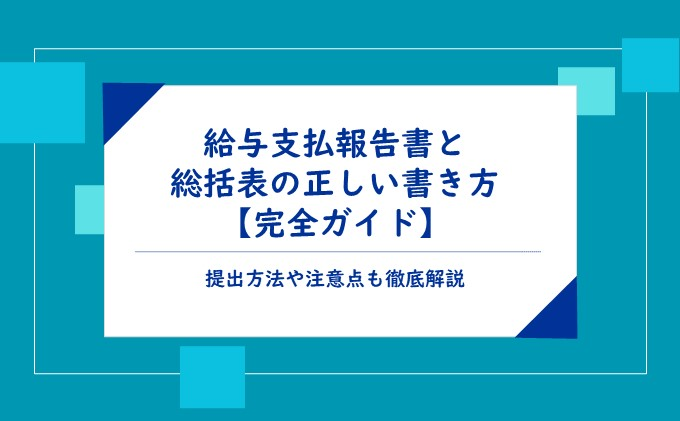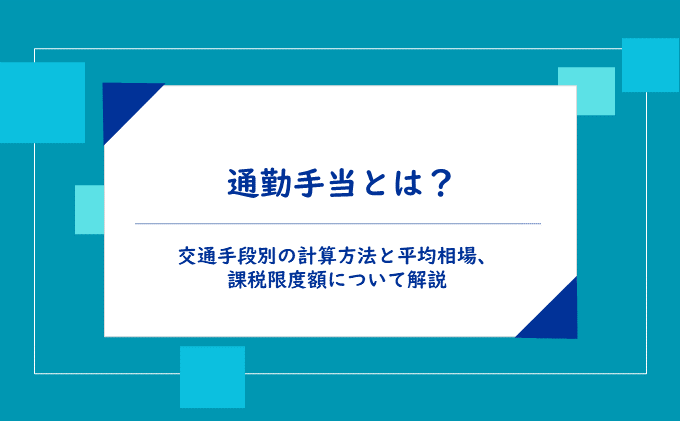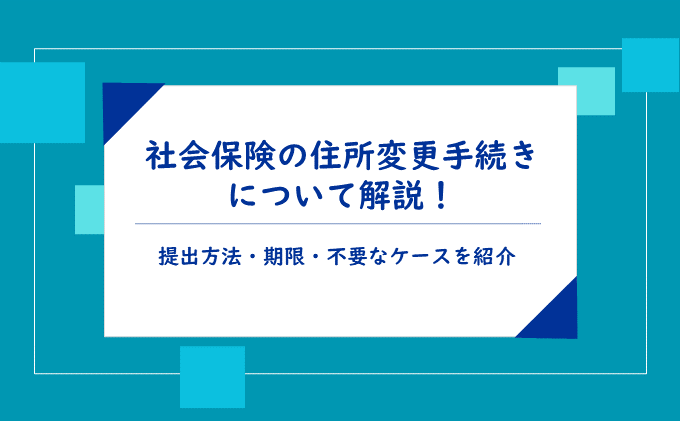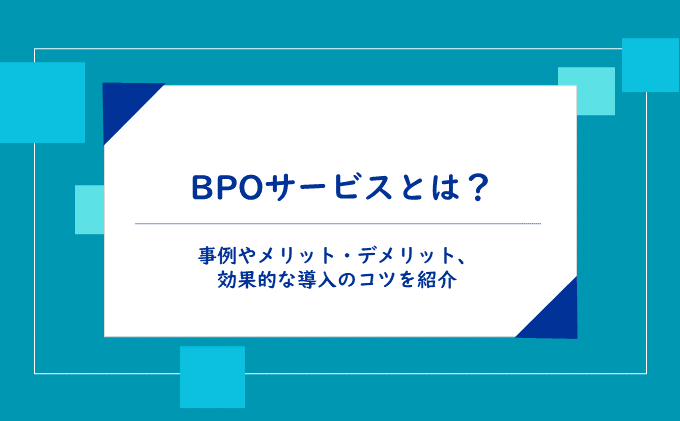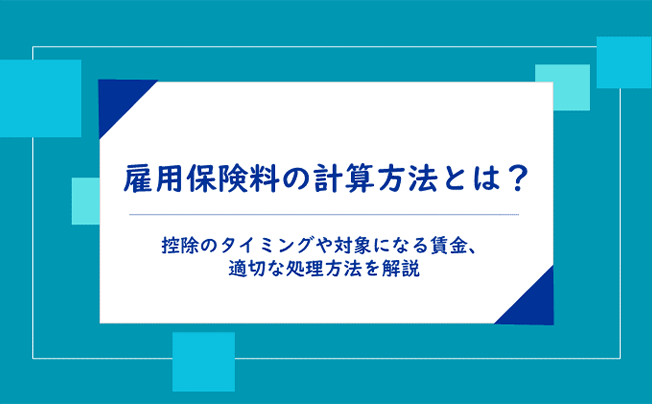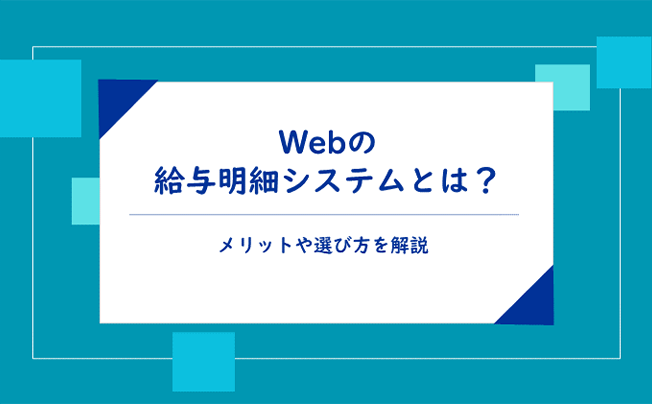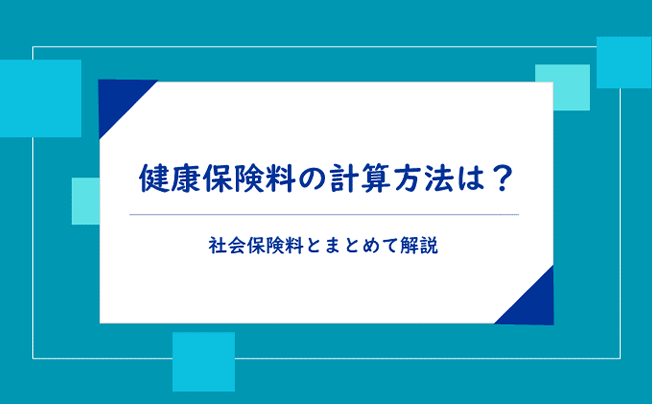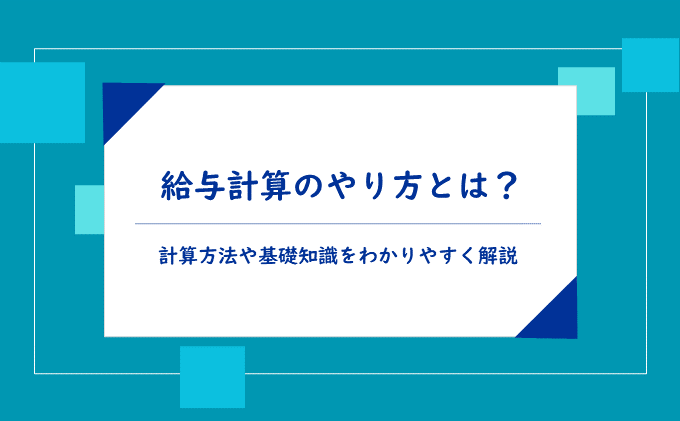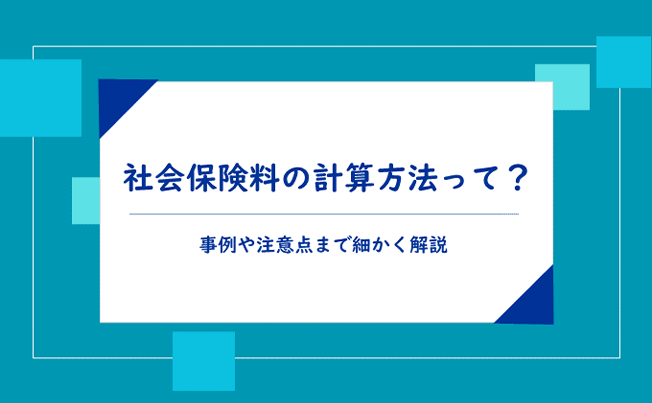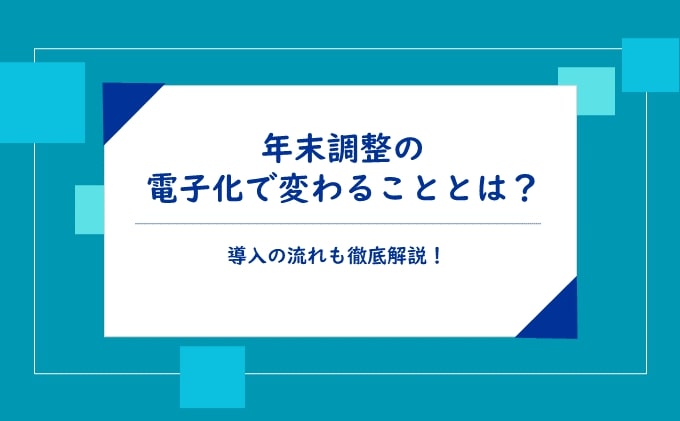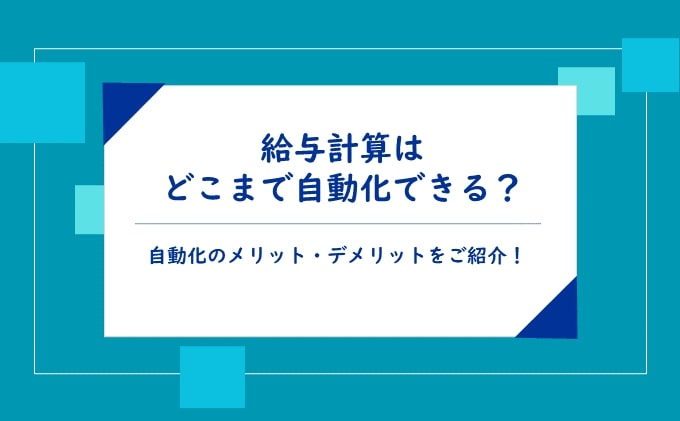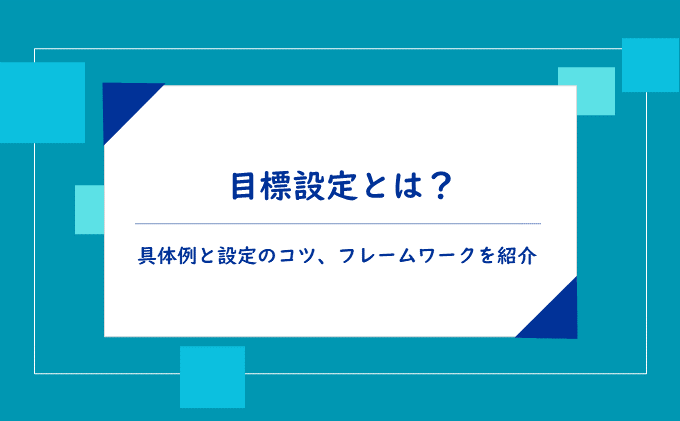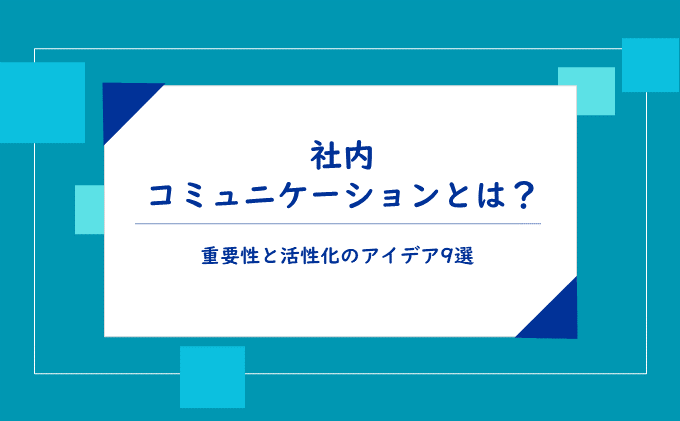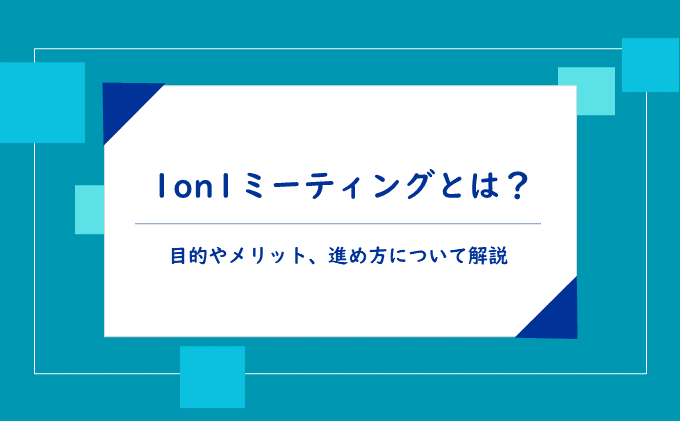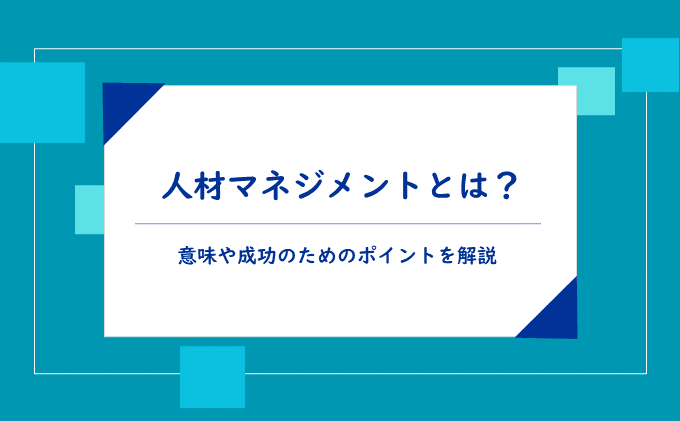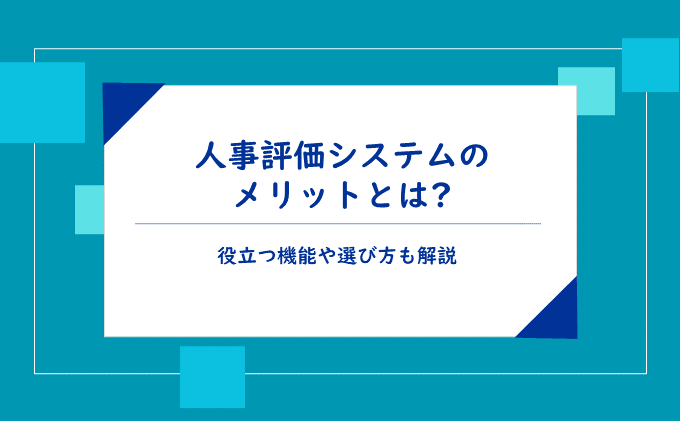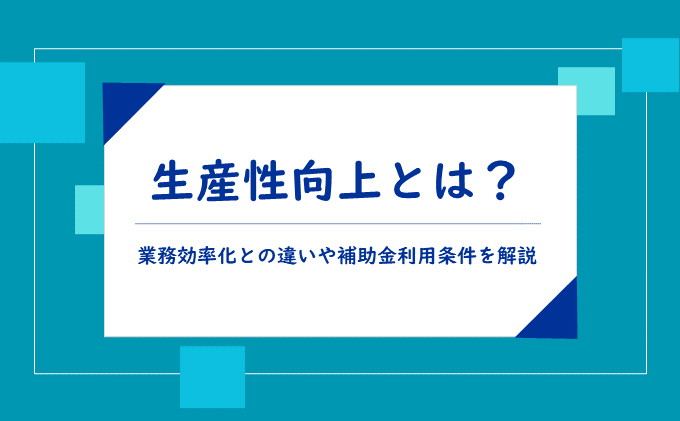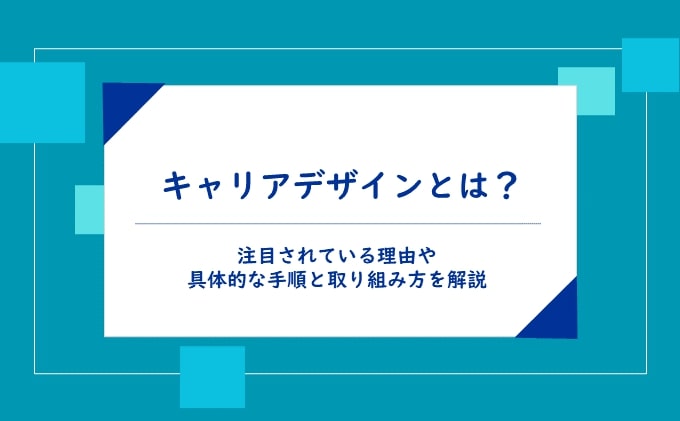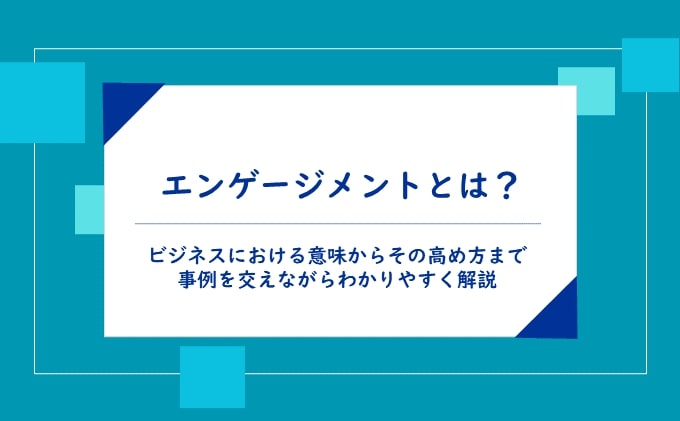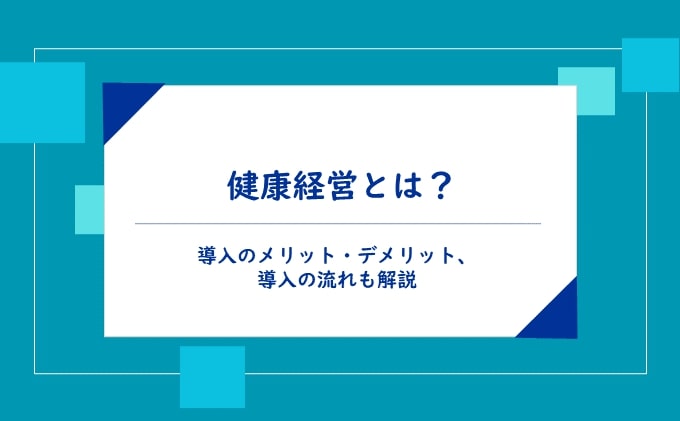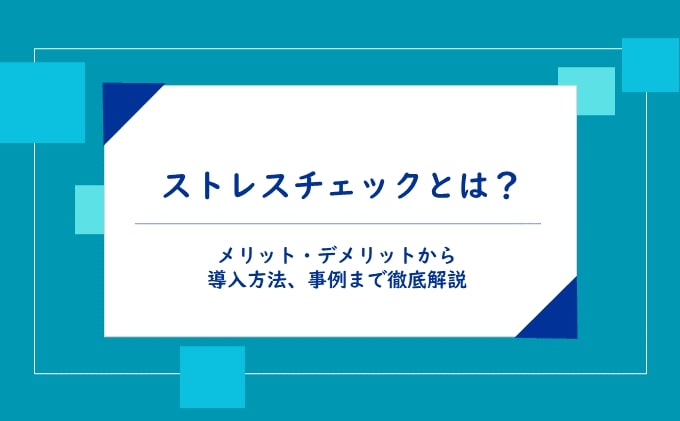子ども・子育て支援金制度とは?対象者や給付金の種類などわかりやすく解説
2025.08.20
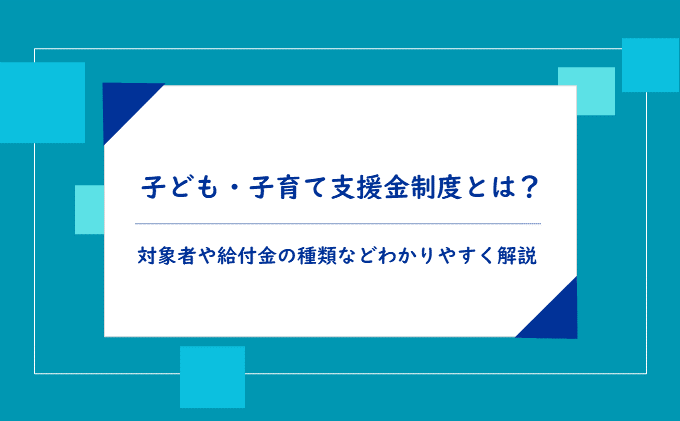
子ども・子育て支援金制度とは、少子化対策の強化を目的とした特定財源を確保するための仕組みです。令和8年度から、全世代・全経済主体を対象に支援金の徴収が始まります。今回は、子ども・子育て支援金の対象者や企業への影響や対策について解説します。
目次
「子ども・子育て支援金制度」とは

子ども・子育て支援金制度とは、子育て世帯を支えるために必要な特定財源を確保するための仕組みです。
政府は、少子化対策の根本強化を図る「こども未来戦略(令和5年12月22日閣議決定)」において、予算規模3.6兆円の「こども・子育て支援加速化プラン」を取りまとめました。この財源を確保するために新設されたのが、子ども・子育て支援金制度です。
子ども・子育て支援金は令和8年度から徴収が始まります。対象者は高齢者や事業者を含む全世代・全経済主体で、被保険者が加入する社会保険料に上乗せされて徴収されます。徴収額は、令和8年から令和10年にかけて段階的に引き上げられる予定です。
関連記事:こども未来戦略とは│背景や加速化プランの内容について解説
子ども・子育て支援金制度導入の背景
子ども・子育て支援金制度の導入背景には、以下のことが挙げられます。
- 少子化・人口減少対策
- 子育て世帯や若年層の支援
それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。
少子化・人口減少対策
日本は、深刻な少子高齢化に直面する危機的な状況です。2030年代には若年人口が急激に減少するため、このまま放置すると歯止めが利かない状況に陥る可能性があります。少子化傾向を反転させるために閣議決定されたのが、「こども・子育て支援加速化プラン」です。
「こども・子育て支援加速化プラン」の予算規模は、3.6兆円と見込まれています。こども・子育て支援加速化プランに必要な財源を確保するため、令和10年度までに徹底した歳出改革の実施や子ども・子育て支援金制度の創出等に取り組む予定です。
子育て世帯や若年層の支援
子ども・子育て支援金は、子育て世帯や若年層への経済的支援に充てられます。日本の出生率の低下は、少子高齢化社会における喫緊の課題です。支援制度により、経済的な理由で出産や結婚を諦める子育て世帯や若者が減り、出生率の改善につなげる目的があります。
子ども・子育て支援金制度の創設により、子ども一人当たりの給付改善額(高校生年代まで)は約146万円です。現行の平均的な児童手当額と合わせると給付改善額は合計約352万円で、子育て世帯や若い世代を支える制度に構築されています。
令和8年度(2026年度)から徴収スタート
子ども・子育て支援金は令和8年度に創出し、令和10年度までに段階的に導入されます。被保険者・事業主の拠出額の目安は、以下のとおりです。
| 年度 | 被保険者・事業主の拠出額の目安 |
|---|---|
| 令和8年度 | 約6,000億円 |
| 令和9年度 | 約8,000億円 |
| 令和10年度 | 約1兆円 |
令和6年〜10年度のみ、子ども・子育て支援特例公債が充てられます。特例公債とは、特例公債法に基づいて国が一般会計の歳入不足を補填するために発行する国債です。
令和8年度からは、子ども・子育て支援金の拠出額も充てられます。
参考:e-GOV「財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律」
子ども・子育て支援金の対象者と負担額

子ども・子育て支援金の徴収が開始するにあたって確認すべき点は、対象者と負担額です。とくに、負担額は企業や従業員の金銭的な負担に直結します。従業員に周知する際にも納得感のある説明が必要になるため、しっかり確認しておきましょう。
子ども・子育て支援金の対象者
子ども・子育て支援金の対象者は、以下に該当する全世代・全経済主体です。
- 被用者保険(協会けんぽ・健保組合・共済組合)の加入者
- 国民健康保険の加入者
- 後期高齢者医療制度の加入者
子ども・子育て支援金は、全世代で子育て世帯を支援する仕組みです。会社員・公務員は労使折半が前提のため、企業は従業員の負担額を折半して支払う必要があります。
子ども・子育て支援金の負担額
子ども・子育て支援金に関する一人当たりの負担見込み額を、以下の表にまとめました。
| 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | |
|---|---|---|---|
| 被用者保険 | 300円 | 400円 | 500円 |
| 国民健康保険 | 250円 | 300円 | 400円 |
| 後期高齢者医療制度 | 200円 | 250円 | 350円 |
| 全制度平均 | 250円 | 350円 | 450円 |
子ども・子育て支援金は、被保険者が加入する医療保険料に上乗せして徴収される仕組みです。会社員や公務員の場合は、加入する医療保険で負担額が異なります。
被用者保険の負担額の目安は、以下のとおりです。
| 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | |
|---|---|---|---|
| 健保組合 | 300円 | 400円 | 500円 |
| 協会けんぽ | 250円 | 300円 | 450円 |
| 共済組合 | 350円 | 450円 | 600円 |
中小企業が加入する「協会けんぽ」と比較すると、大企業が加入する「健保組合」や公務員が加入する「共済組合」の負担額のほうが高く設定されています。
子ども・子育て支援金の使い道

全世代・全経済主体から徴収された支援金は、以下のような事業に使われます。
- 児童手当の抜本的拡充(令和6年10月~)
- 妊婦支援給付金(令和7年4月~)
- 出生後休業支援給付金(令和7年4月~)
- 育児時短就業給付金(令和7年4月~)
- こども誰でも通園制度(令和8年4月~)
なお、支援金拠出が満額となる令和10年度まで発行される子ども・子育て支援特例公債の償還金等にも充当される予定です。
それぞれの事業内容について詳しく確認していきましょう。
関連記事:こども未来戦略とは│背景や加速化プランの内容について解説
児童手当の抜本的拡充(令和6年10月~)
子ども・子育て支援金は、子どもの生活を安定させるために児童手当の拡充に使われます。
| 拡充前(令和6年9月まで) | 拡充後(令和6年10月以降) | |
|---|---|---|
| 支給対象 | 国内に住所を有する児童(中学高修了まで) | 国内に住所を有する児童(高校生年代まで) |
| 所得制限 | 所得制限あり(960万円未満) ※年収1,200万円以上は対象外 |
所得制限なし |
| 支給額 | 3歳未満:一律1万5,000円 3歳~小学校修了まで:第1子・第2子は1万円、第3子以降は1万5,000円 中学生:一律1万円 所得制限以上:5,000円 |
3歳未満:1万5,000円 3歳~高校生年代まで:第1子・第2子は1万円、第3子以降は3万円 |
拡充後は従来の所得制限が撤廃されており、支給対象は高校生年代まで延長されました。支給額も第3子以降は金額が引き上げられ、子ども世帯に手厚い支援が提供されます。
参考:こども家庭庁「全国こども政策主管課長会議」令和6年3月
妊婦支援給付金(令和7年4月~)
妊婦支援給付金は、すべての妊婦さんが安心して出産・子育てできる環境を提供するために給付金が給付される制度です。
| 対象者 | 妊娠している方 |
| 支給額 | 妊婦給付認定後:5万円 こどもの人数の届出後:こどもの人数 × 5万円 流産・死産・人工妊娠中絶:妊娠していた胎児の人数 × 5万円 |
給付金を受け取るには、市区町村の窓口で申請することが必要です。妊婦支援給付金では、医療機関で胎児心拍を確認できた状態を「妊娠」と定義しています。胎児心拍確認後に、お住まいの市区町村の「妊婦のための支援給付」担当窓口で申請を進めましょう。
なお、給付と合わせて面談も実施しており、妊娠や出産の不安や困りごとを相談可能です。相談を通して利用できる制度やサービスを紹介してくれます。
参考:こども家庭庁「全国こども政策主管課長会議」令和6年3月
出生後休業支援給付金(令和7年4月~)
出生後休業支援給付金は、共働き・共育ての推進や経済的不安を解消するための制度です。
出生時育児休業給付金や育児休業給付金等の出産や育児に関する給付に新たに加わり、共働きで子育てする世帯の支援が拡充しています。
| 支給要件 | ・被保険者である ・育児休業を通算して14日以上取得している |
| 支給額 | 【計算式】支給額 = 休業開始時賃金日額 × 休業期間の日数 × 13% ※休業開始時賃金日額は、出生時育児休業または育児休業の開始前直近6か月間に支払われた賃金の総額から出した額 |
| 支給申請手続 | 出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給申請と併せて申請手続きを進める |
参考:厚生労働省「2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設します」
関連記事:育休手当(育児休業給付金)とは?計算方法や支給条件を解説
育児時短就業給付金(令和7年4月~)
仕事と育児を両立する世帯に柔軟な働き方を選択できる環境を確保するための制度です。
| 支給要件 | ・2歳未満の子を養育するために育児時短就業する雇用保険の被保険者 ・育児休業に続いて育児時短就業を開始した者 ・被保険者期間(育児時短就業開始日前の2年間)が12か月間 |
| 支給額 | 育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額が支給 |
| 支給対象 | フレックスタイム制・変形労働時間制・裁量労働制・シフト制など、特別な労働時間制度で就業する者 |
| 支給対象期間 | 育児時短就業の開始月から終了月まで |
育児時短就業給付金の支給対象は従業員ですが、申請は企業が行う必要があります。
参考:厚生労働省「2025年4月から「育児時短就業給付金」を創設します」
関連記事:育休手当(育児休業給付金)とは?計算方法や支給条件を解説
こども誰でも通園制度(令和8年4月~)
こども誰でも通園制度は、すべての子育て世帯に良質な成育環境を整備するための制度です。保護者の就労有無や理由など勤労要件は問わず、保育所や認定こども園、幼稚園等に通園していない0歳6か月から満3歳未満の未就園児が利用できます。
ただし、利用可能時間は子ども一人当たり月10時間が上限です。初めて利用する事業所では、まず保護者と事前面談を実施し、子どもの特徴や保護者の意向等を確認します。環境に慣れるまで時間がかかる子どもには、親子通園を許可する事業者もあるため安心です。
こども誰でも通園制度を利用するには、お住いの市区町村が定める方法で申請する必要があります。申請方法を知りたい方は、市区町村に問い合わせましょう。
国民年金第1号被保険者の育児期間中保険料免除(令和8年10月~)
自営業者・フリーランス等の国民年金第1号被保険者の育児期間における保険料が免除されます。
従来の制度では、会社員などが加入する厚生年金保険と比較すると国民年金第1号被保険者における育児期間中の支援は不十分な状況でした。国民年金第1号被保険者も安心して子育てできるよう、子が1歳になるまで保険料免除措置が創設されます。
| 対象者 | 子を養育する国民年金第1号被保険者(自営業者・フリーランス、無職の方等) |
| 対象期間 | 原則として子が1歳になるまで |
免除対象期間中の基礎年金額は満額で受け取れます。保険料を給付しなくても加入期間と認められるため、将来の年金給付への影響はありません。財源は社会全体で子育て世代を支援する考え方に基づいて、こども・子育て支援納付金が充てられます。
子ども・子育て支援金と「拠出金」の違いとは

子ども・子育て支援金と名称が似た制度に「子ども・子育て拠出金」があります。どちらも子育て世帯の金銭的な負担を減らすための制度ですが、下表のように対象者や負担者等が異なります。
| 子ども・子育て支援金 | 子ども・子育て拠出金 | |
|---|---|---|
| 導入時期 | 令和8年 | 昭和46年度 |
| 負担者 | 企業と従業員で折半 | 事業主が負担 |
| 対象者 | 全世代・全経済主体 | 厚生年金保険の加入者全員 |
「子ども・子育て拠出金」制度は今後、段階的に「子ども・子育て支援金」制度に統合・移行していく予定です。
子ども・子育て拠出金の概要を確認しましょう。
子ども・子育て拠出金は全額事業所負担
子ども・子育て拠出金は、子育て支援に必要な資金を確保するために昭和46年度に創設された制度です。対象者は厚生年金保険に加入する被保険者で、子どもの有無や世帯構成等は関係なく、全従業員に例外なく納付義務があります。
ただし、全額が事業所負担となるため、被保険者個人に支払い負担はありません。
子ども・子育て拠出金の使い道
子ども・子育て拠出金は、以下の子育てに関する幅広い事業の財源に使われています。
| 制度・事業内容 | 概要 |
|---|---|
| 児童手当 | 子育て支援の適切な実施を図るために児童を養う世帯に支給される手当です。児童とは、0〜18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を指します。 |
| 延長保育事業 | 保育時間を超える場合の延長保育事業の経費を補助するための事業です。保育時間を延長して児童を預けられる環境を確保する目的があります。 |
| 病児保育事業 | 病気など自宅での保育が困難な場合に、看護師等が児童を一時的に保育する事業です。安心して子育てができる環境整備を図る目的があります。 |
| 企業主導型保育事業 | 柔軟かつ多様な保育を提供する企業等が設置した保育施設を支援する事業です。待機児童対策に貢献することを目的としています。 |
| 放課後児童健全育成事業 | 授業終了後等に児童に適切な遊びや生活の場を与えて健全な育成を図るための事業です。小学校に就学している児童を対象としています。 |
| ベビーシッター利用者支援事業 | 雇用される従業員がサービスを利用した場合に利用料金を助成する事業です。本事業は、乳幼児または小学3年生までの児童を対象としています。 |
| 中小企業子ども・子育て支援環境整備事業 | 子ども・子育て支援に積極的に取り組む事業主に助成金を支給する事業です。企業数に比して認定企業数の割合が低い中小企業に支援が行われます。 |
| 子どものための教育・保育給付 | 子どもの年齢や保育の必要性に応じて、幼稚園や保育所等の費用を一部負担する制度です。給付対象施設の利用を希望する児童全員が使用できます。 |
令和7年度の拠出金率は0.36%
子ども・子育て拠出金は、被保険者の標準報酬月額・標準賞与額に拠出金率を掛けて計算します。
標準報酬月額は厚生年金保険料や健康保険料の金額を算出する際の基準、標準賞与額は賞与にかかる保険料を計算する際に使われる基準となる金額です。令和7年度の拠出金率は令和6年度と同じ0.36%、法定上限額は0.40%と定められています。
子ども・子育て支援金制度による企業への影響と対策

子ども・子育て支援金の徴収は、令和8年度から開始されます。支援金は企業と従業員の折半で負担するため、以下の影響が出る可能性があります。
- 固定費の負担が増加する
- 働き方の多様化を実現できる
それぞれの内容を確認していきましょう。
固定費の増加
子ども・子育て支援金は、企業と従業員での折半が必要です。事業主のみが負担する子ども子育て拠出金に加えて、支援金の徴収が開始されると固定費の増加が懸念されます。固定費の負担を軽減するには、コスト管理の徹底や助成金の利用等が挙げられます。
コスト管理の徹底としては、固定費を見直して無駄な支出を減らすことが重要です。企業の経費において人件費の負担割合は大きいため、ITツールを導入して業務効率化を図る方法もあります。従業員の残業時間が減り、人件費削減につながる可能性があります。
また、IT導入補助金や両立支援助成金など助成金を活用するのも有効です。子育て支援に活かせる助成金は多くあるため、経済的負担を軽減できます。結果的に企業のイメージアップにもつながるため、優秀な従業員が集まりやすいです。
働き方の多様化
子ども・子育て支援金は、企業と従業員が負担額を折半して支払うことが必要です。従業員にも金銭的負担は生じますが、令和7年から開始される「出生後休業支援給付金」や「育児時短就業給付金」など子育て世帯が利用できる給付金制度は多くあります。
これらの制度を従業員が利用すれば、多様な働き方を実現することが可能です。創設したばかりの制度のため、存在を知らない従業員もいます。子ども・子育て支援金への理解を深めるためにも、従業員への徹底した周知が求められます。
また、少子高齢化に伴う労働人口減少に対応するため、子ども・子育て支援金の周知徹底と合わせて業務効率化に向けた対策も必要です。
人事管理システム「ADPS(アドプス)」が人事業務の効率化を実現

子ども・子育て支援金は、社会保険料に上乗せされて徴収されます。計算業務には正確性の保持が求められますが、法改正の対応や従業員情報の管理など複雑な要素が絡み合うため、担当者の心理的負荷や業務負担が増す可能性が高いです。
カシオヒューマンシステムズ株式会社では、人事管理システム「ADPS」を提供しています。従業員の情報を一元管理できるため、子ども・子育て支援金にも柔軟に対応可能です。また、法改正に応じた自動アップデート機能も搭載されているため、改正後の内容を確認して都度修正する手間も省けます。
詳しくは、以下をご確認ください。
まとめ

子ども・子育て支援金の徴収が始まり、その徴収金は児童手当の抜本的拡充、出生後休業支援給付金や育児時短就業給付金等の事業に充てられます。これらの支援制度の活用を周知徹底すれば、企業は子育て世帯の従業員が働きやすい環境を整えられます。
一方で、支援金は社会保険料に上乗せして徴収されるため、計算の煩雑さが担当者の負担になる可能性が高いです。また、各支援制度の申請手続きは原則企業が対応しなければいけません。担当者の業務負担を軽減するためにも、煩雑な人事業務を効率化できる人事管理システムの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
カシオヒューマンシステムズコラム編集チームです。
人事業務に関するソリューションを長年ご提供してきた知見を踏まえ、
定期的に「人事部の皆様に必ず今後の業務に役立つ情報」を紹介しています。