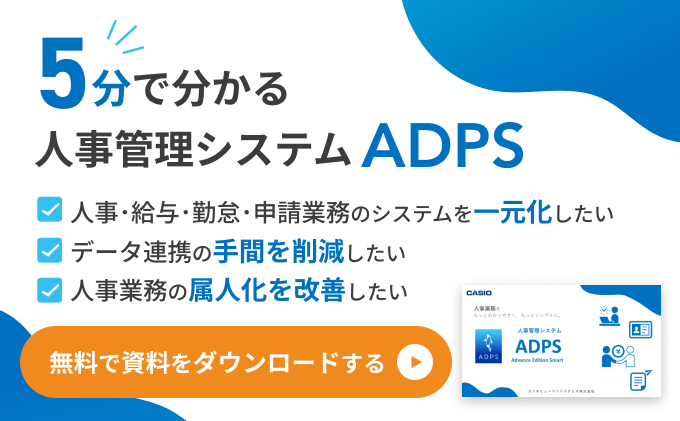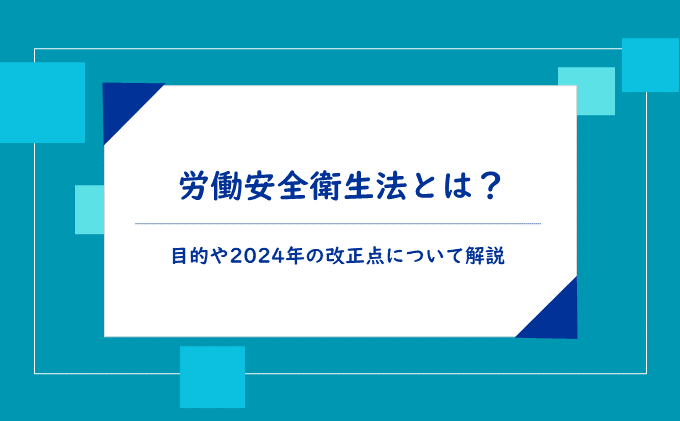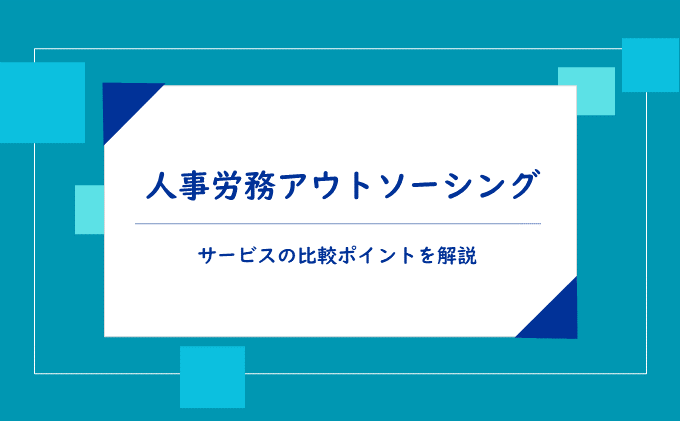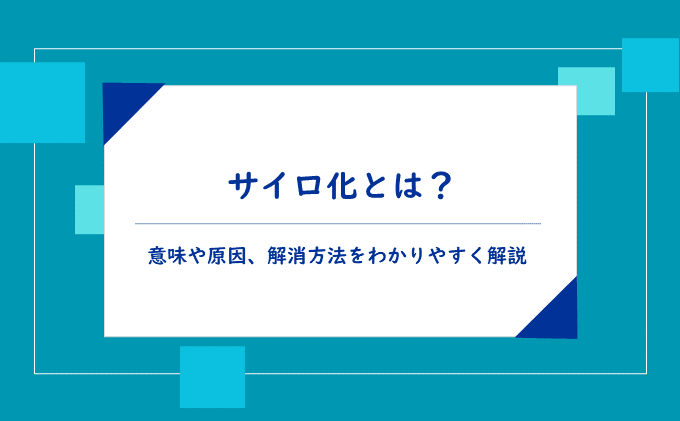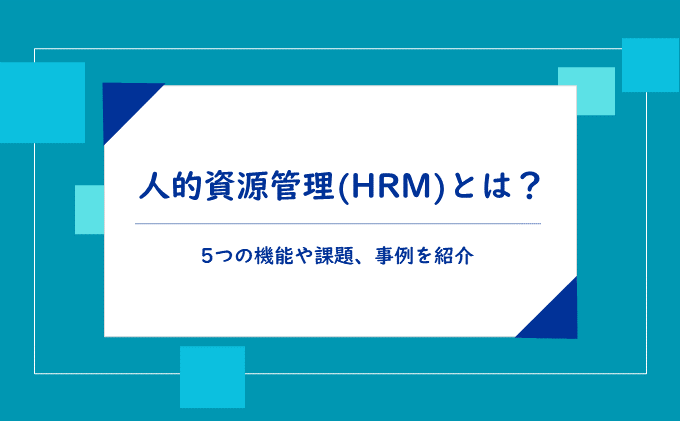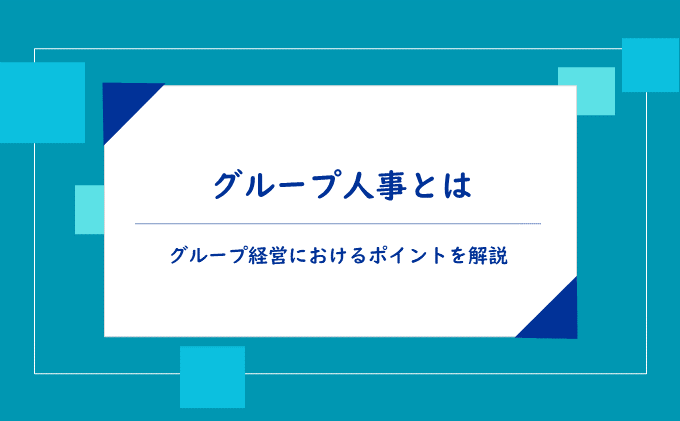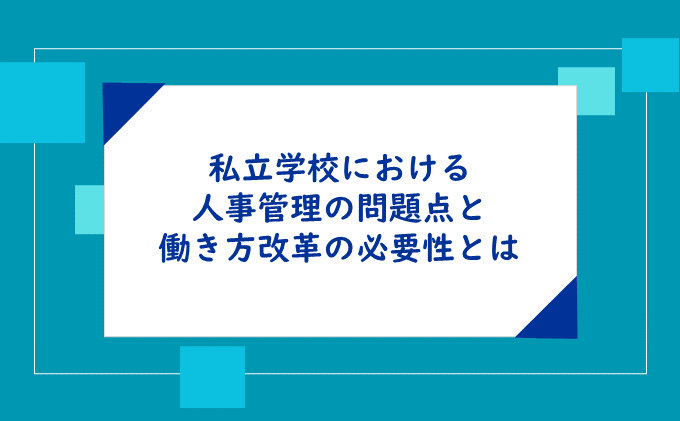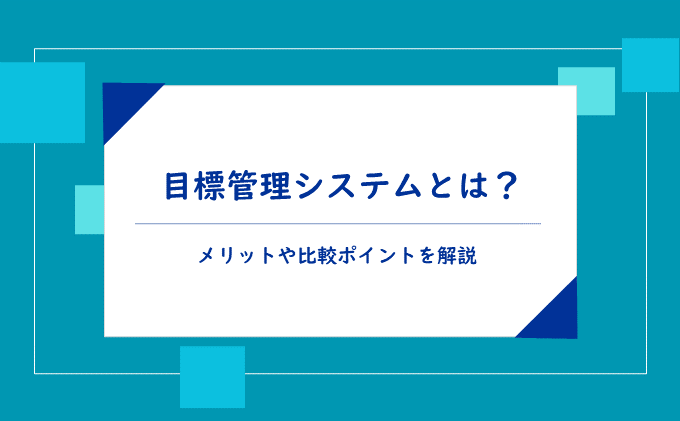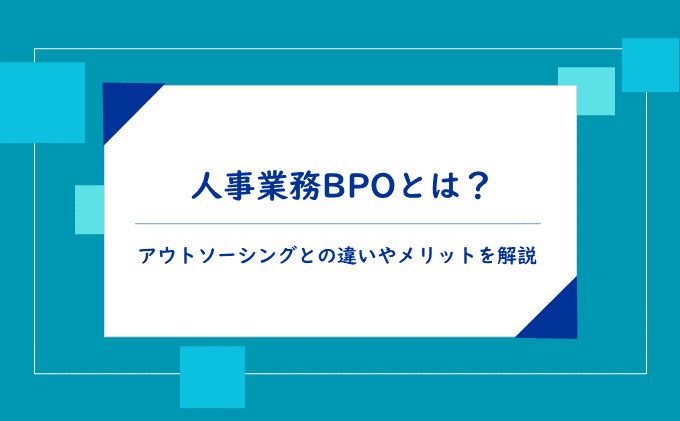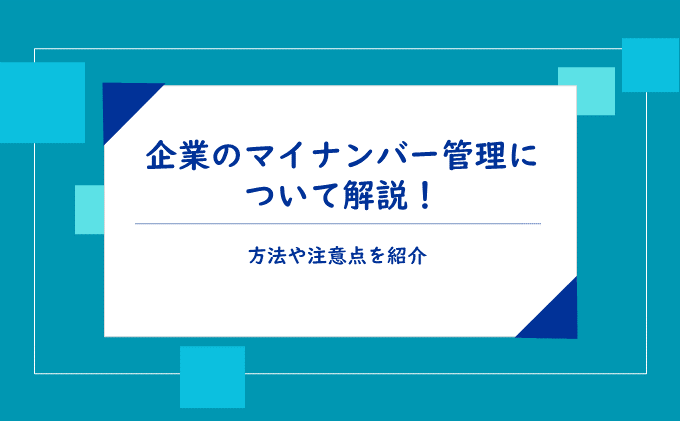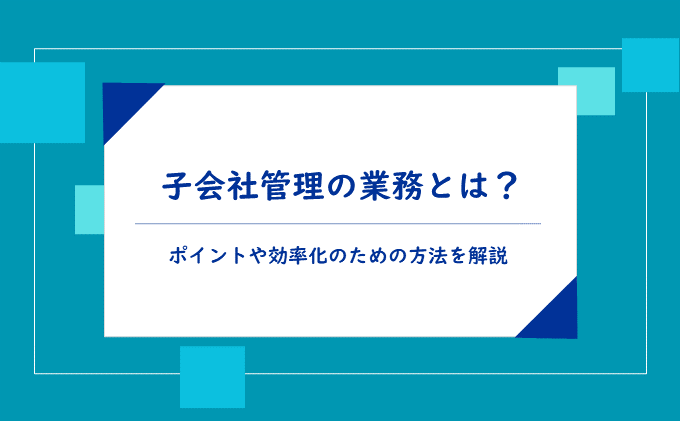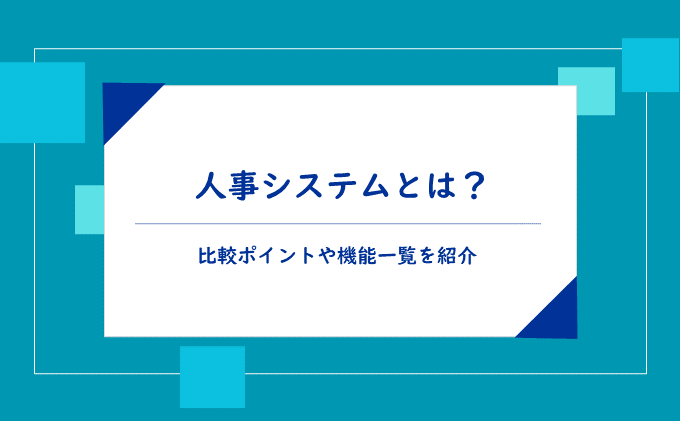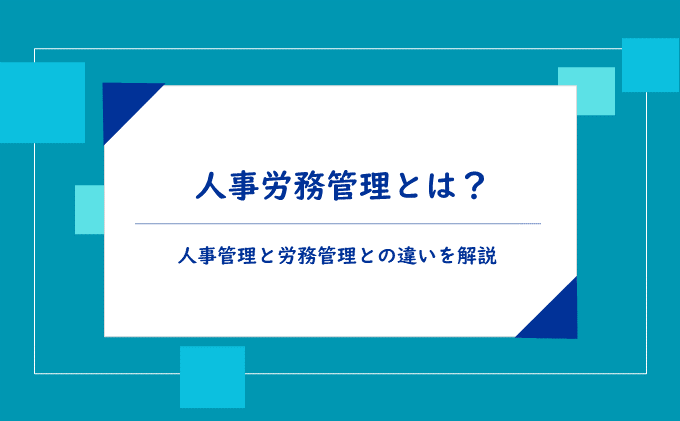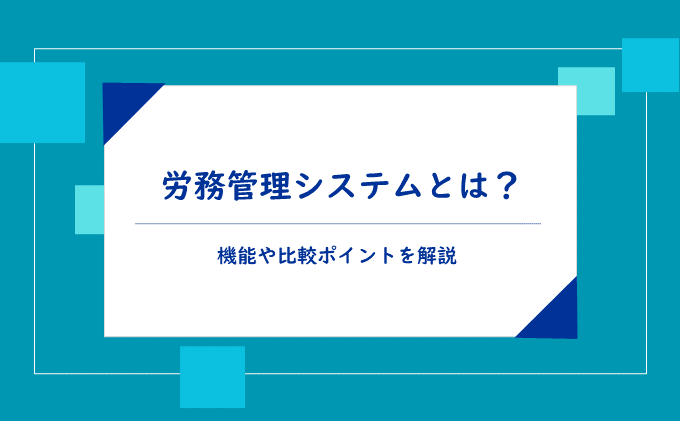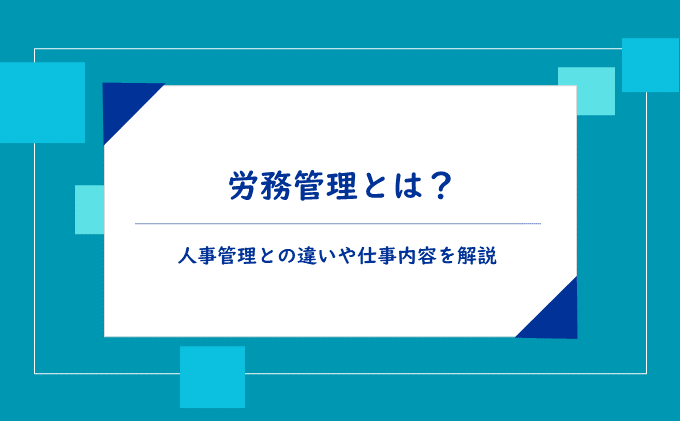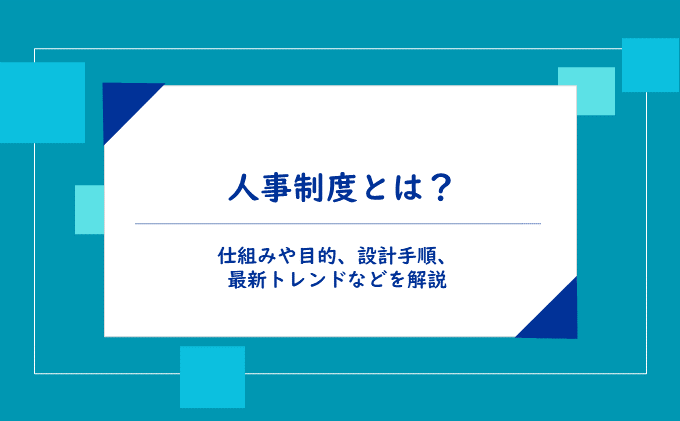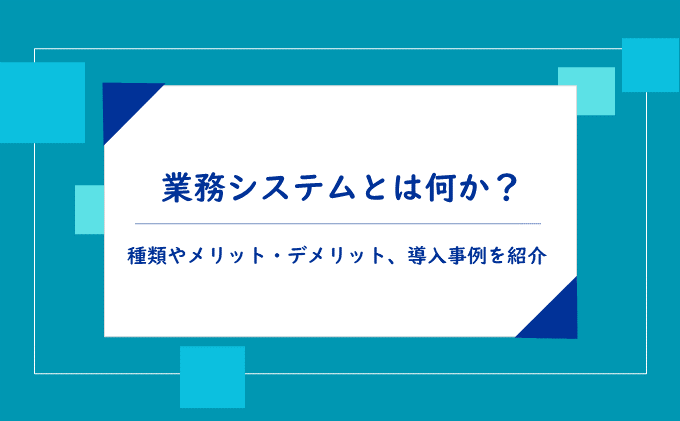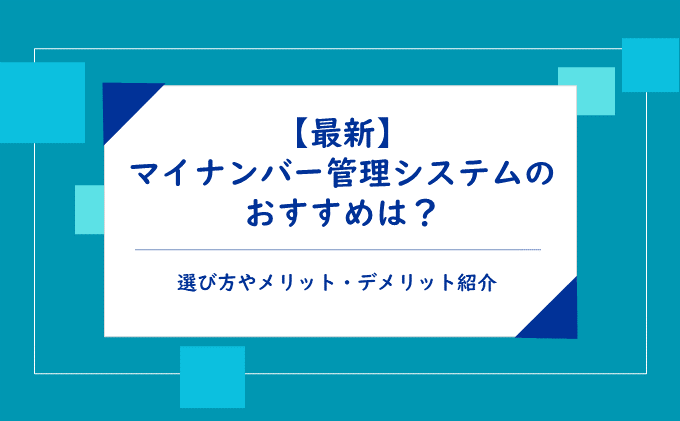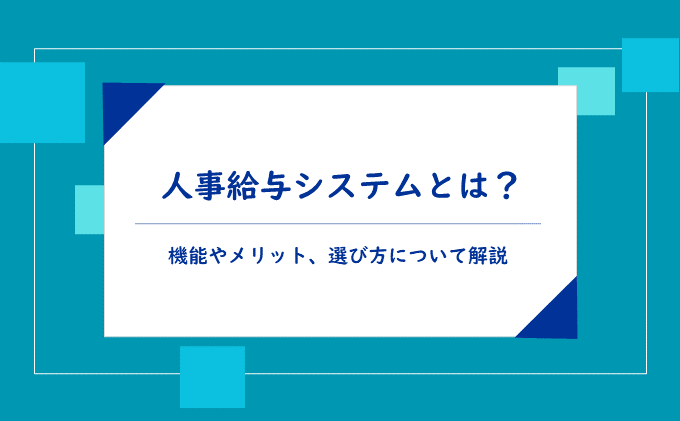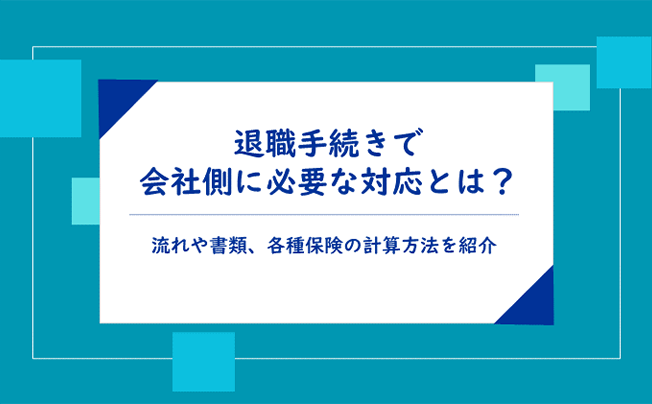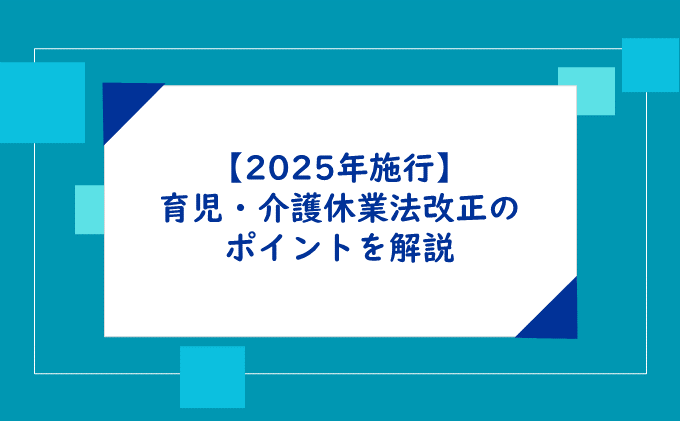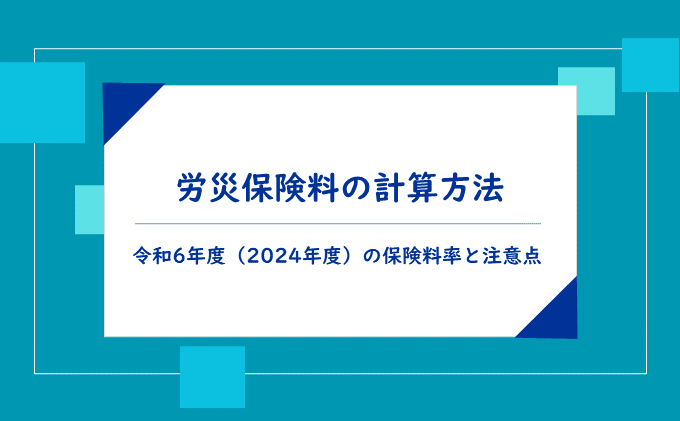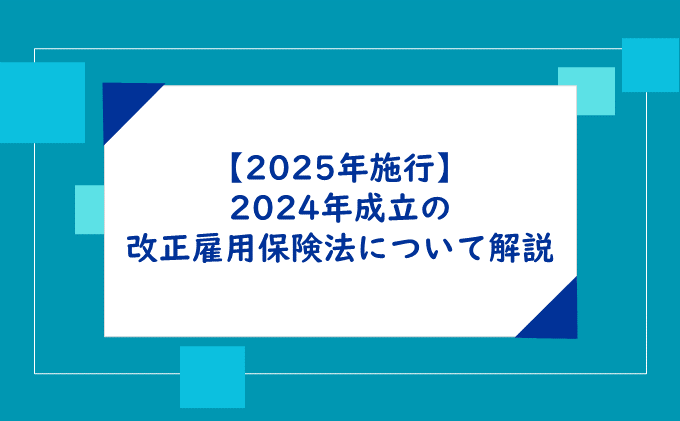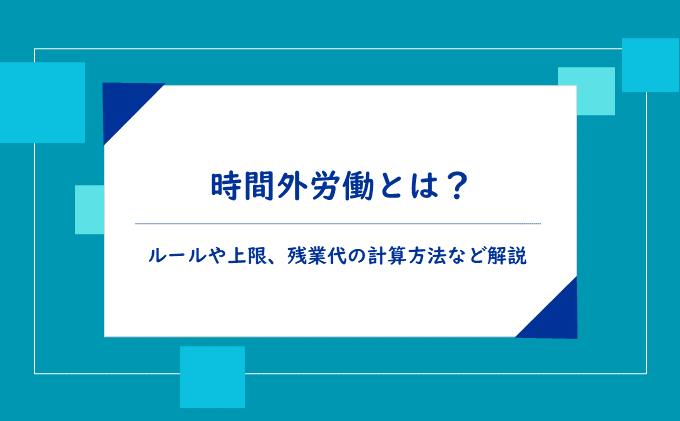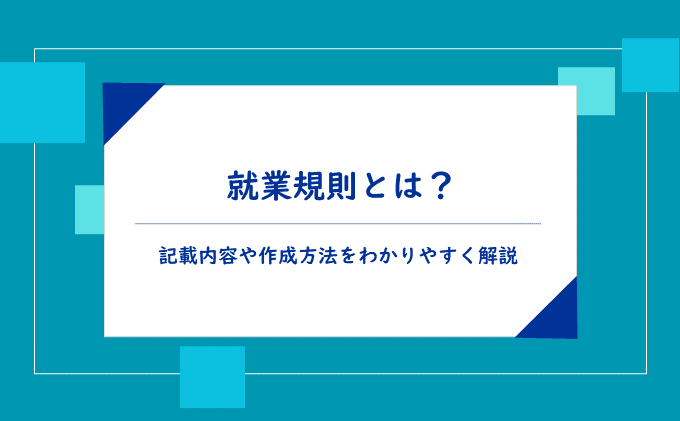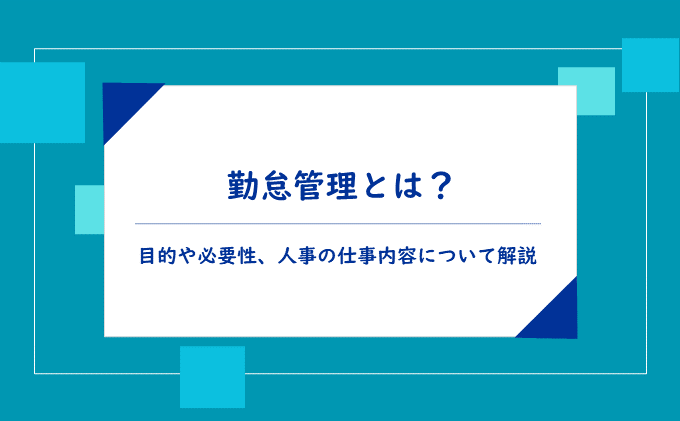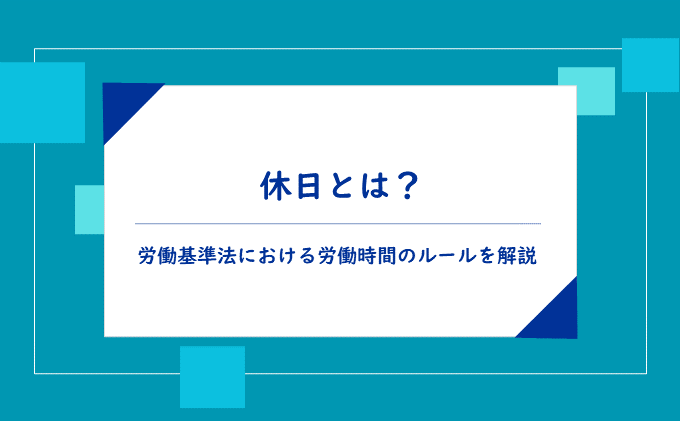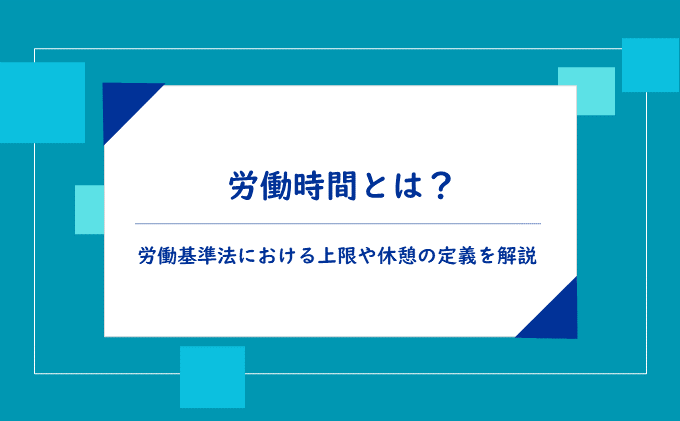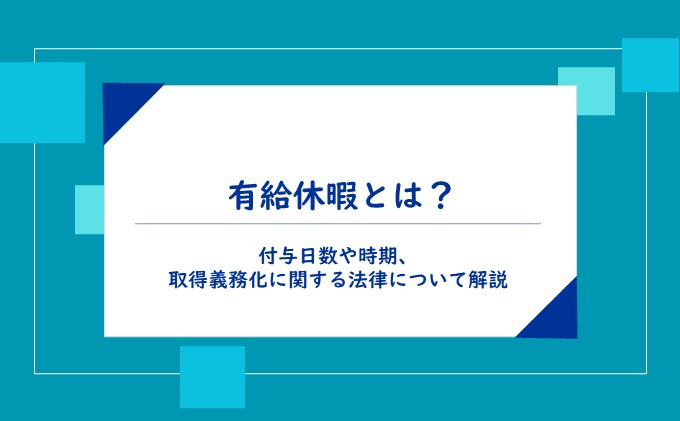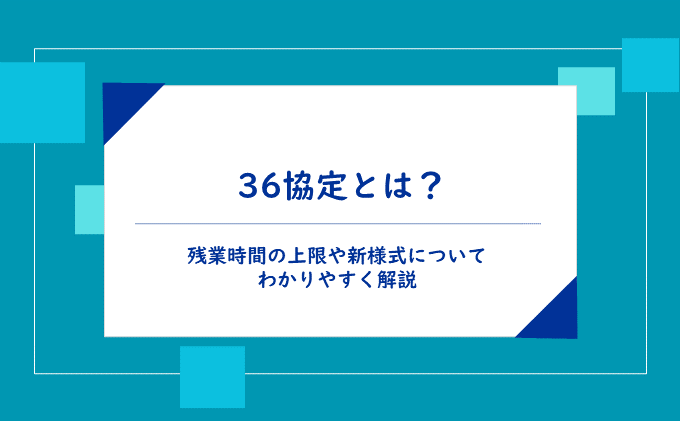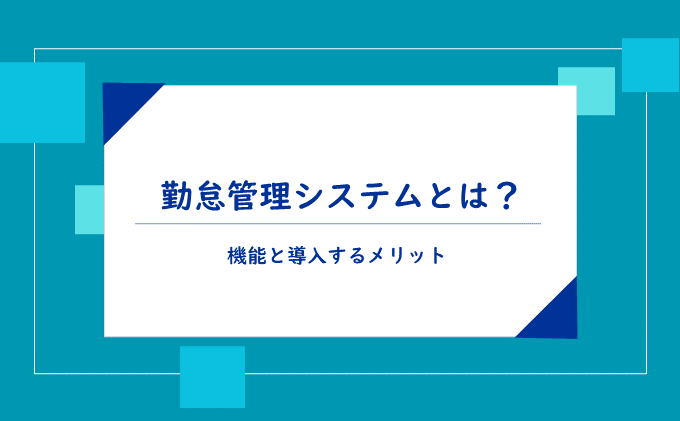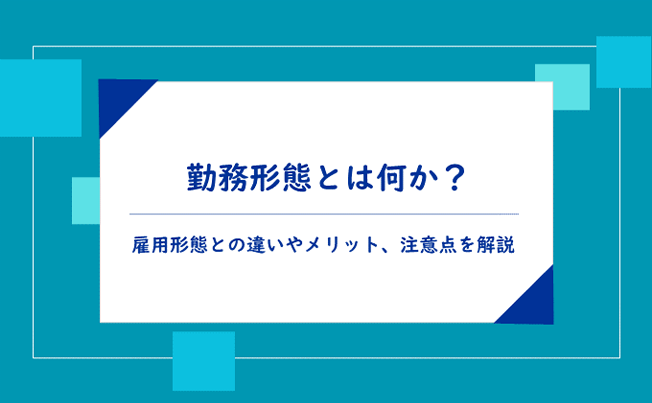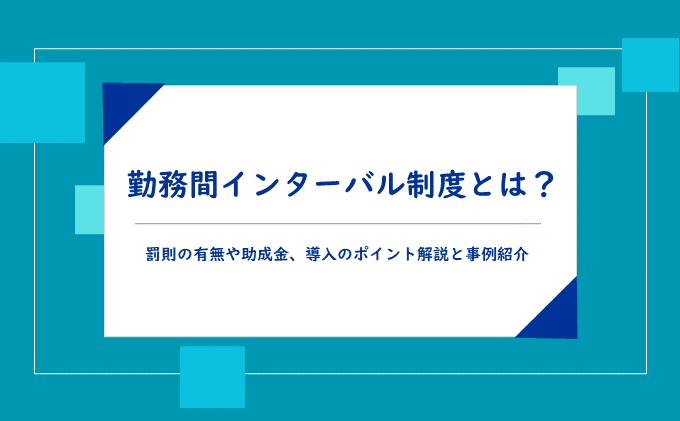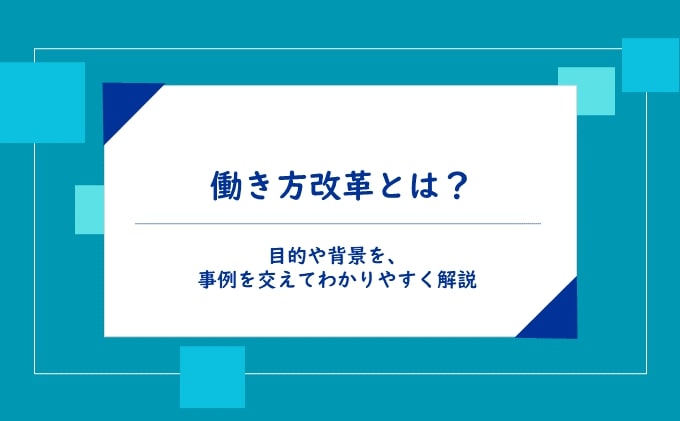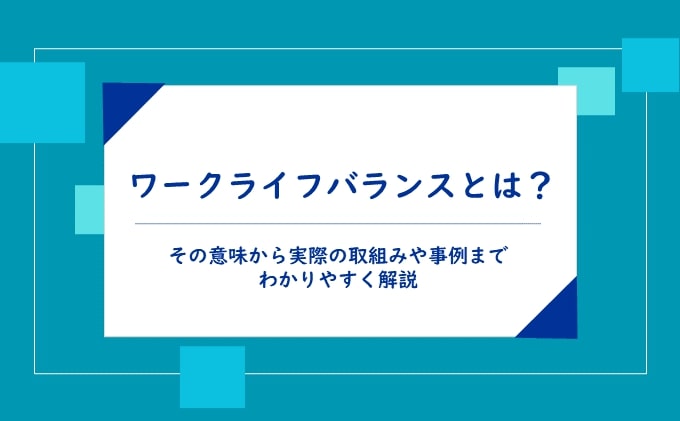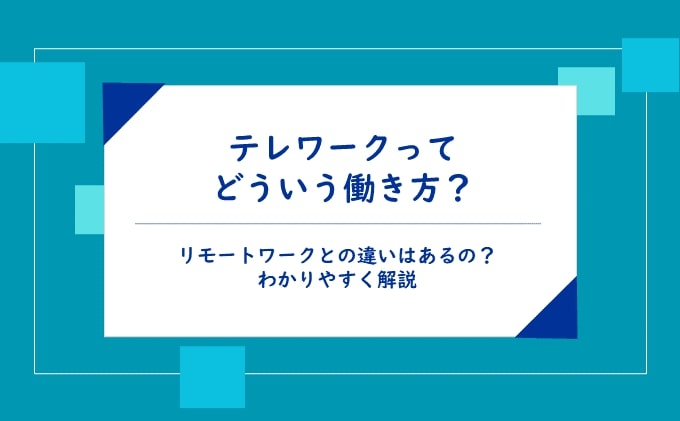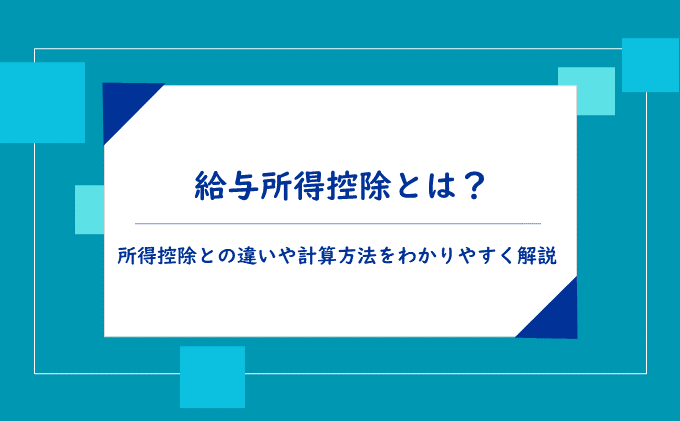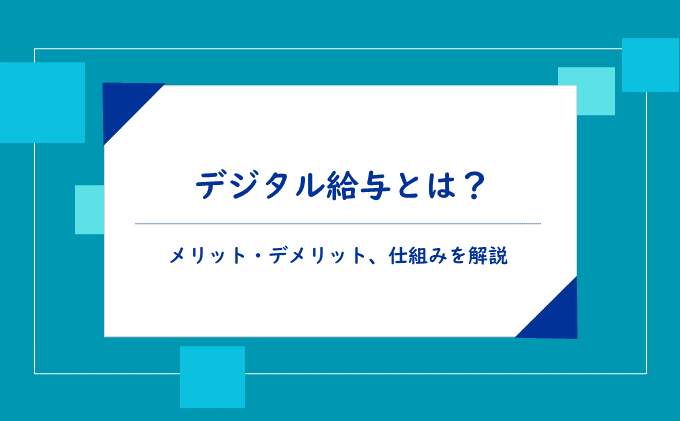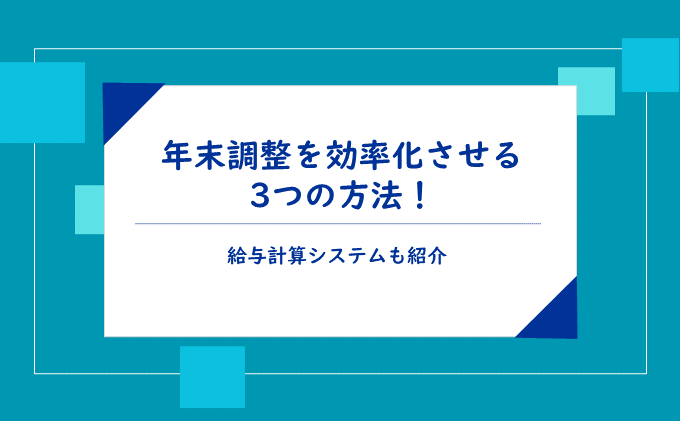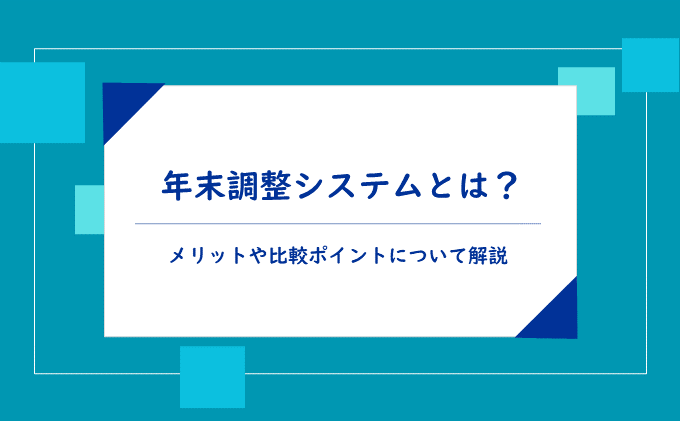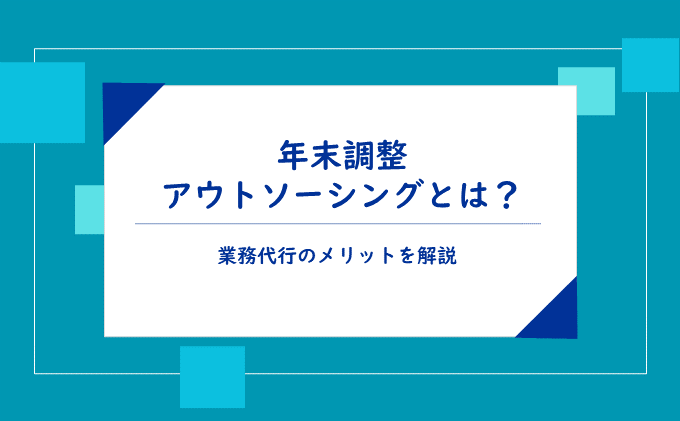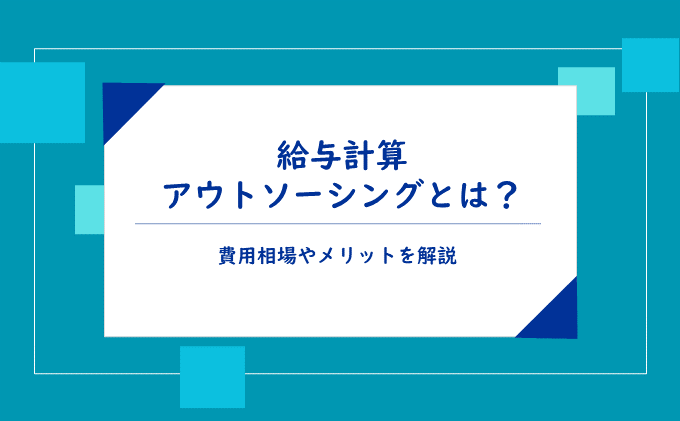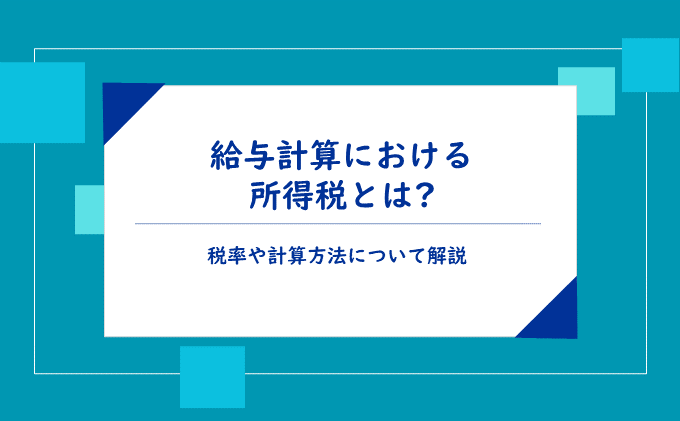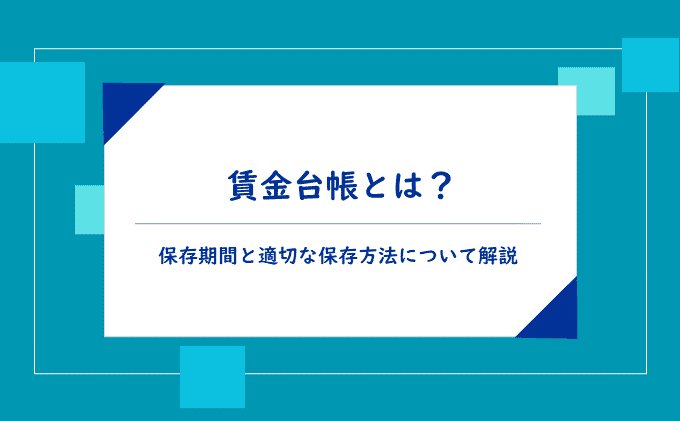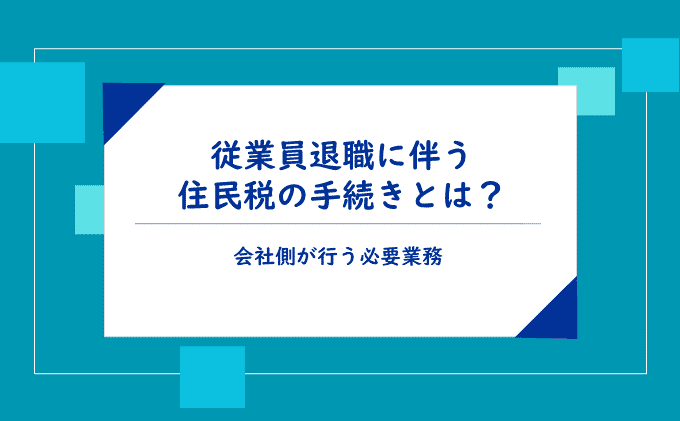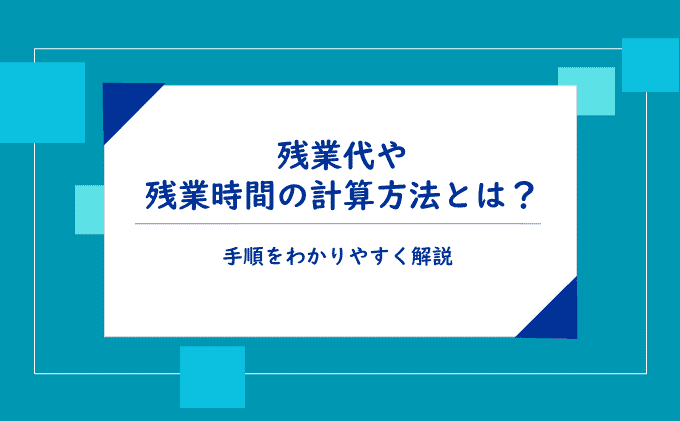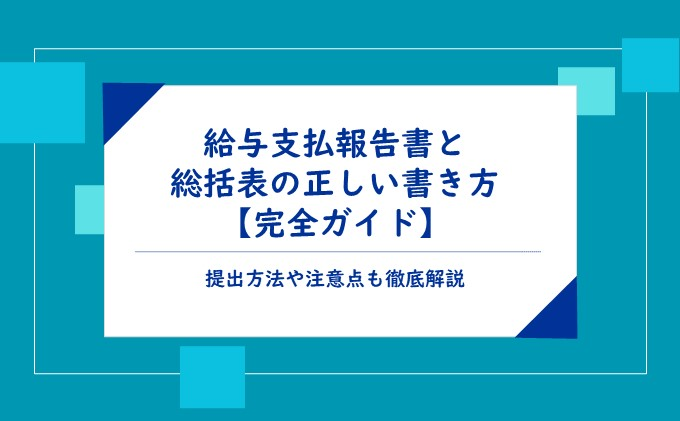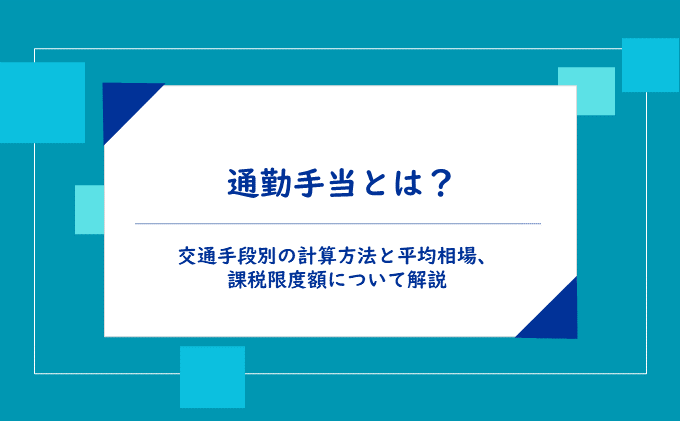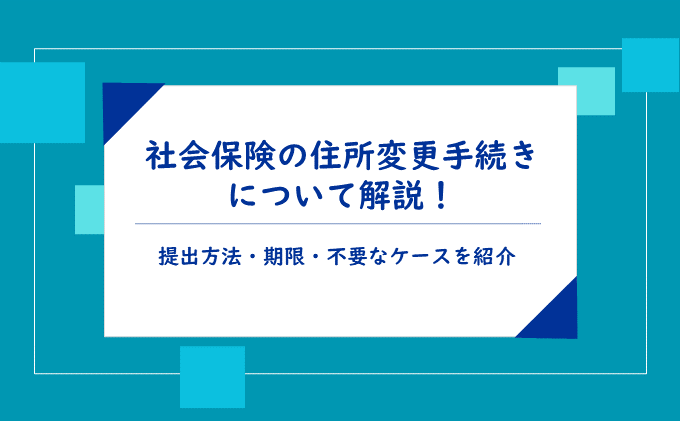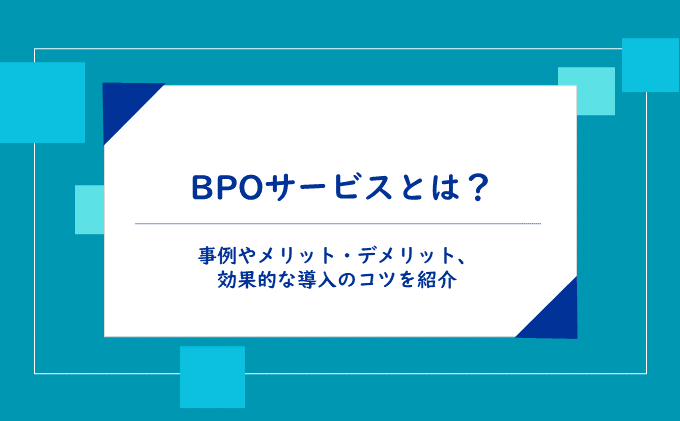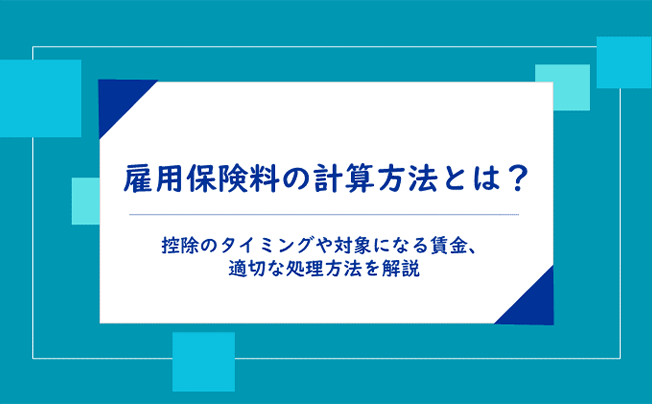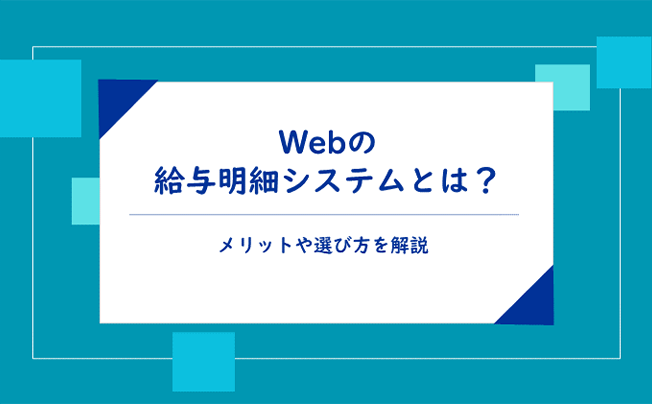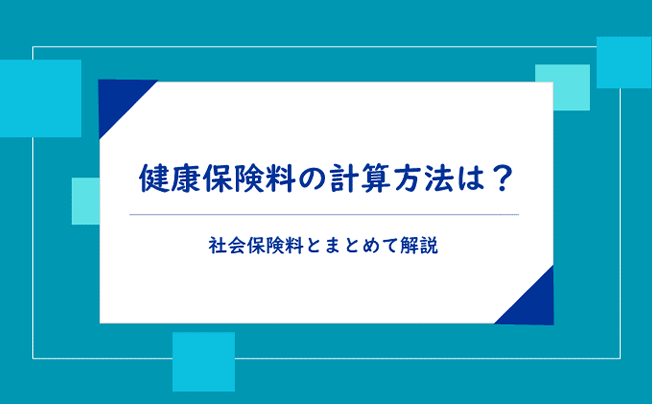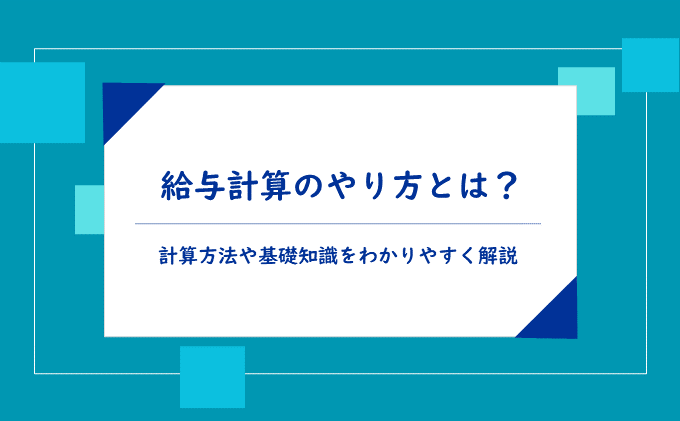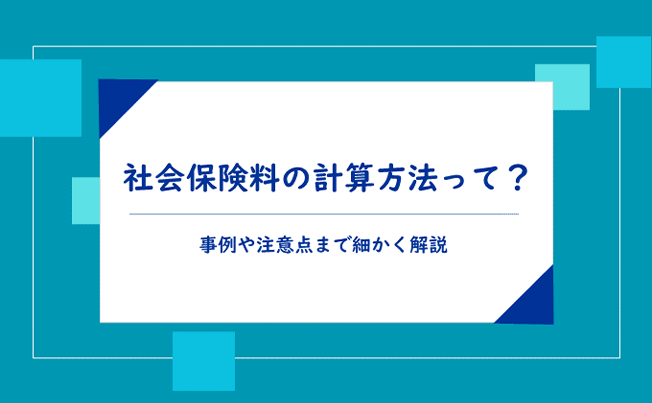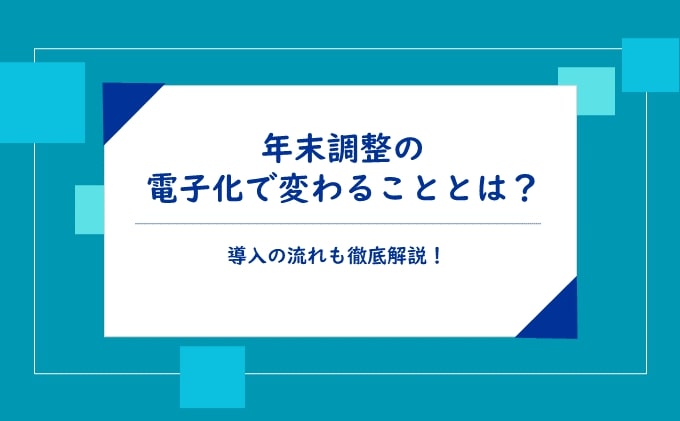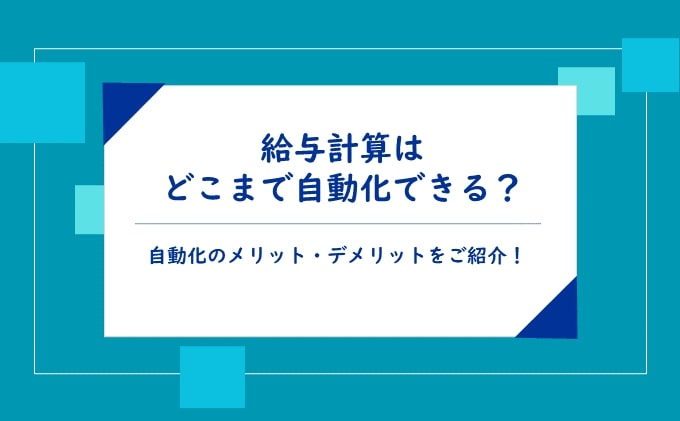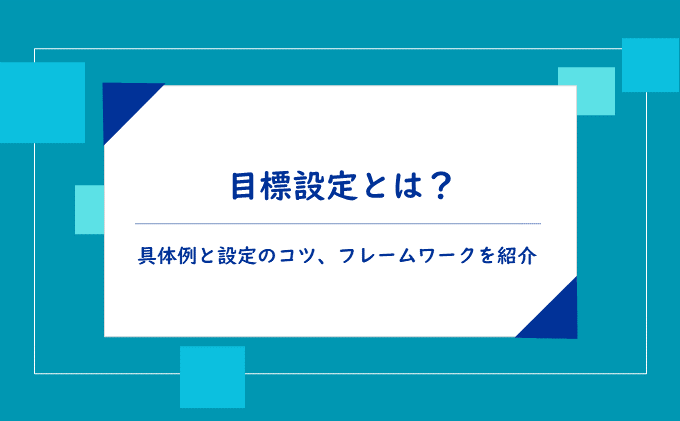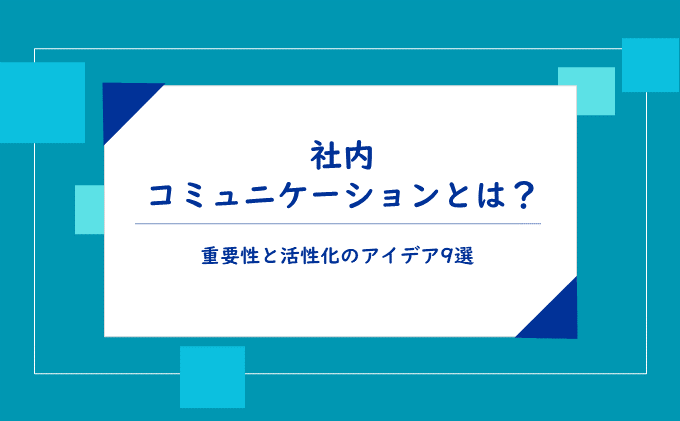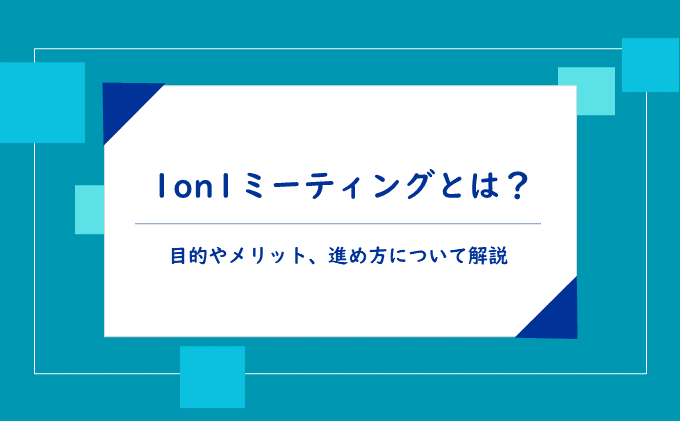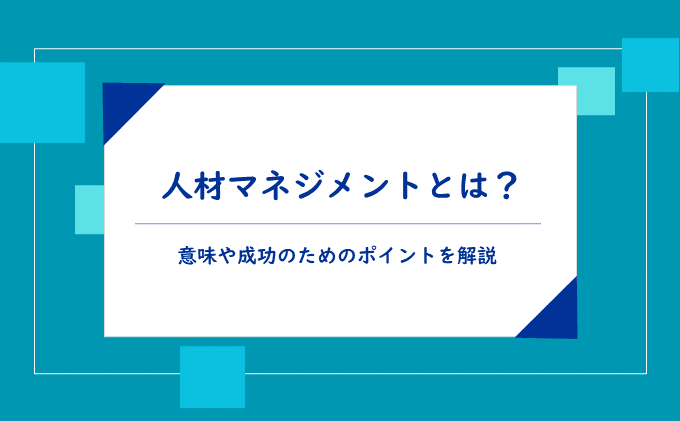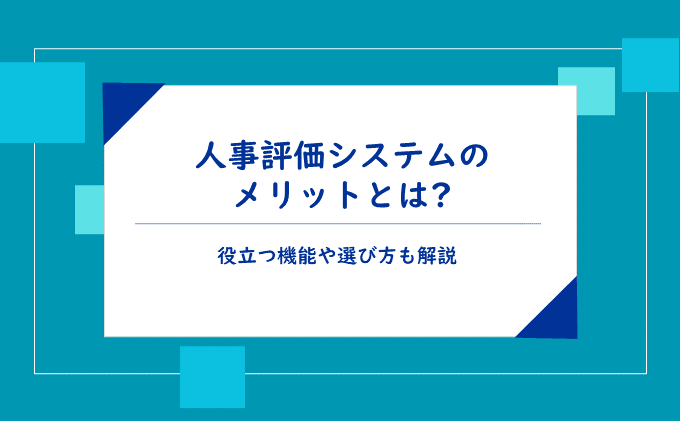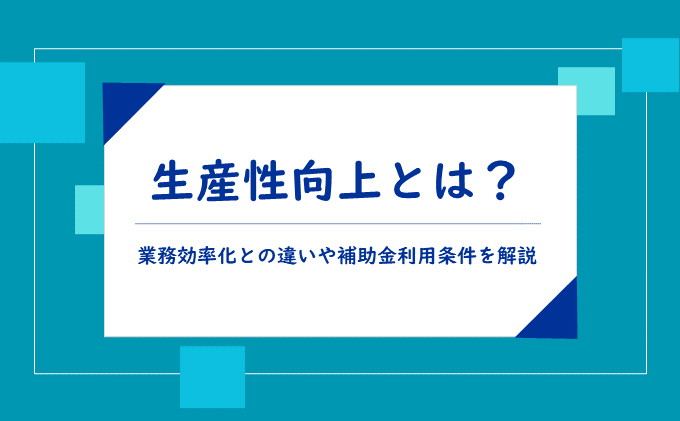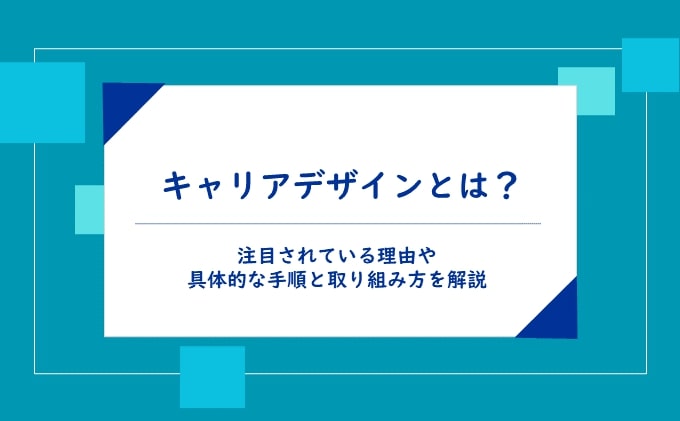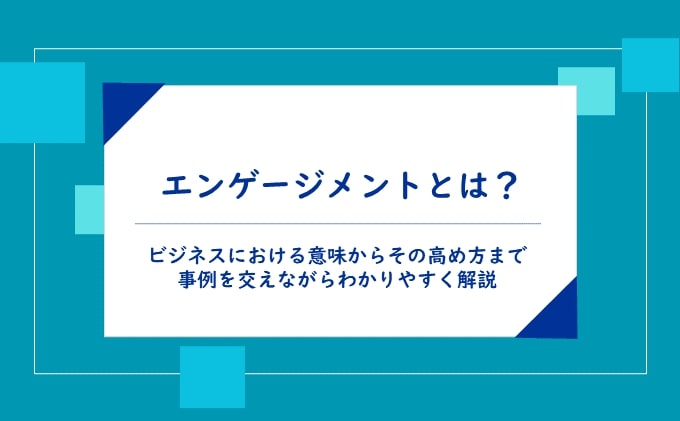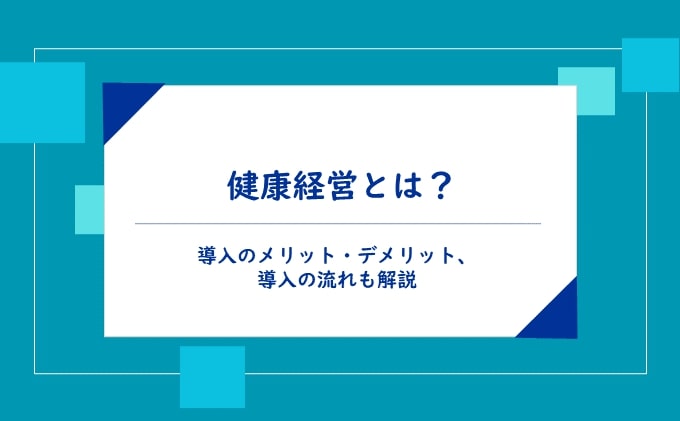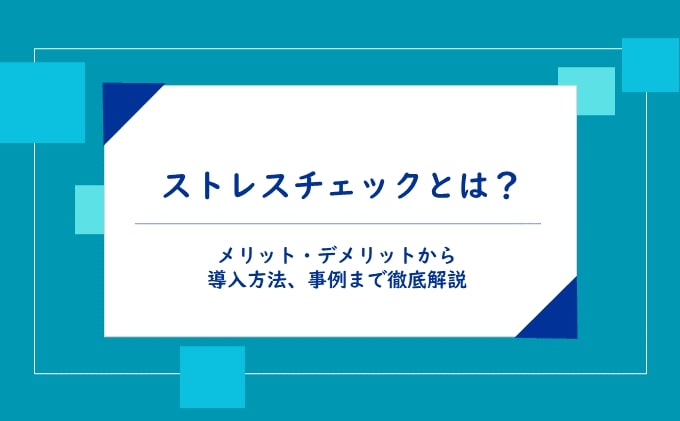年末調整の計算方法は?計算の流れや計算例も紹介
2025.08.20
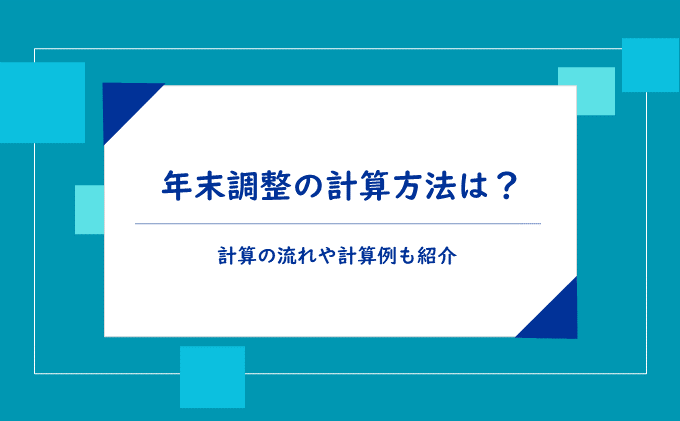
年末調整とは、源泉徴収した税額の年間合計額と年税額を一致させるための計算業務です。
年末調整の計算は年々複雑化しており、税制改正や控除制度等に応じて対応しなければいけません。今回は、年末調整の計算方法について詳しく解説します。
目次
「年末調整の計算」とは

年末調整の計算とは、従業員の1年間の所得税額を計算し、毎月給与から天引きしている源泉徴収税額との過不足分を算出する業務を指します。
所得税額と源泉徴収税額に過不足が生じる理由、毎月の従業員の給与から徴収される源泉所得税が概算額であるためです。年末調整の計算業務は、実際に支払うべき所得税の過不足金を調整するために必須の業務です。過納額がある場合は給与に上乗せして還付し、不足分はその差額を徴収します。
例年の法改正で提出書類が複雑化しており、年末調整業務にかかる時間や手間が増えているのが現状です。年末調整の間違いが放置された場合、お金と手間の両面で従業員に迷惑をかけるため、効率的かつ正確に計算業務を進める必要があります。
年末調整の計算方法

年末調整の計算方法は年々複雑化しています。計算間違いを防ぐためには、正しい手順で進めることが重要です。
どのような手順で計算していくのか詳しく確認していきましょう。
1.年間の給与総額・社会保険料・源泉徴収税額を計算する
年末調整を進めるためには、従業員一人ひとりの年間の給与総額、毎月の給与から天引きされている社会保険料・源泉徴収税額を計算します。
給与総額
1年間の給与総額を計算します。
給与とは、1月1日~12月31日までに従業員に支給した給与・賞与・各種手当等の合計額です。つまり、社会保険料や源泉徴収税等を差し引いていない金額を指します。年末までの給与・賞与の金額が未確定の場合は、これまで支払われた額に基づいて算出しましょう。
また、各種手当には、残業手当や家族手当、住宅手当等が含まれます。ただし、電車やバス等の公共交通機関を利用して通勤する従業員に支給される通勤手当は集計対象に含まれません。その理由は、1か月あたり15万円まで非課税の対象になるためです。
社会保険料
毎月の給与から天引きされている社会保険料の額を計算します。
社会保険とは、病気や怪我等に備えるためにすべての従業員の加入が義務付けられている社会保障制度です。社会保険加入者は、社会保障制度を維持するために保険料を納付しなければいけません。
具体的には、以下のような保険料が含まれます。
| 社会保険の種類 | 概要 |
|---|---|
| 健康保険 | 病気や怪我、またはそれが原因による休業や出産等に備える公的な医療保険制度です。 |
| 介護保険 | 介護サービスの利用時に費用負担を軽減するための公的な介護保険制度で、40歳以上の健康保険に加入するすべての従業員が対象です。 |
| 厚生年金保険 | 会社員や公務員の人が国民年金に上乗せして加入する公的な年金制度です。老後や障害、死亡などに備えるために保険料を納付します。 |
| 雇用保険 | 失業や育児休業等に備えるための公的な雇用保険制度です。1週間あたりの所定労働時間は20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある従業員が対象です。 |
| 労災保険 | 労災に備えるための公的な労災保険制度です。従業員を雇用する企業の場合、雇用形態にかかわらず、すべての従業員に適用されます。 |
健康保険・厚生年金保険・介護保険は従業員と企業が折半しますが、労災保険は企業が全額負担し、雇用保険は雇用保険料率に基づいて従業員と企業の双方が負担します。
源泉徴収税額
毎月の給与から差し引かれる源泉徴収税額を計算します。源泉徴収税は、納税者本人の代わりに、企業が国に納めている税金のことです。中途入社者の場合は、前年の収入に関する情報が記載されている源泉徴収票を含めて計算する必要があります。
2.給与所得額を計算する
給与所得額は、給与総額から給与所得控除を引いて計算します。給与所得控除は、所得税の負担を軽減するために、年間の給与収入額に応じた額が控除されることです。
給与所得控除額の算出表(令和6年分)
| 給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 1,625,000円まで | 550,000円 |
| 1,625,001円から1,800,000円まで | 収入金額 × 40% - 100,000円 |
| 1,800,001円から3,600,000円まで | 収入金額 × 30% + 80,000円 |
| 3,600,001円から6,600,000円まで | 収入金額 × 20% + 440,000円 |
| 6,600,001円から8,500,000円まで | 収入金額 × 10% + 1,100,000円 |
| 8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
引用:国税庁「給与所得控除」
給与所得控除は収入金額が増えるほど増加しますが、控除額は195万円が上限です。
また、所得金額調整控除には2種類の控除がありますが、年末調整で適用されるのは「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」のみです。
参考:国税庁「給与所得控除」
3.所得控除額を計算する
所得税法には、税負担を軽減するための所得控除制度があります。
要件に当てはまる場合、各種所得の合計額から各種所得控除の額の合計額を差し引くことが可能です。控除を受けると所得金額が減り、従業員の納税額を抑えられます。
所得控除には以下の種類があり、納税者の生活状況に応じて適用されます。
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寄附金控除
- 障害者控除
- 寡婦控除
- ひとり親控除
- 勤労学生控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 基礎控除
所得控除額は、従業員から提出された申告書に基づいて各種所得控除額を合計したものです。
4.課税給与所得額を計算する
課税給与所得は、給与所得額から「所得金額調整控除」と「所得控除額」を引いて算出します。
【計算式】課税所得額 = 給与所得額 - 所得控除の合計
この課税所得額に対して所得税が課されます。なお、1,000円未満は切り捨てて問題ありません。
参考:国税庁「給与所得者と税」
5.所得税額を計算する
所得税額は、課税給与所得額に所得税率を掛け、控除額を引いて算出します。
【計算式】所得税額 = 課税所得額 × 所得税率 - 控除額
所得税率は、所得税の計算に必要な税率です。所得税率は所得が多いほど段階的に税率が高くなる「超過累進課税」が採用されています。ただし、所得額全体に高い税率が適用されるのではなく、一定の額を超えた分だけ税金が課されるのが特徴です。
所得金額に対する税率や控除額は、以下の速算表で確認できます。
年末調整のための算出所得税額の速算表
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
関連記事:給与所得控除とは?所得控除との違いや計算方法をわかりやすく解説
6.所得税額から住宅ローン控除額を差し引く
住宅ローン控除は、個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築や改築等をした場合、住宅ローン利用者が所得税の減税を受けられる制度です。
住宅ローン控除を受ける従業員がいる場合は、「所得税額」から「控除額」を差し引きます。住宅ローンの控除額は、住宅ローン残高を証明する残高証明書に記載されている残高に控除率を掛けた金額です。計算には「住宅借入金等特別控除申告書兼住宅借入金等特別控除計算明細書」が必要になるため、従業員から回収しましょう。
なお、住宅ローン控除は2年目以降の年分が適用されます。控除を受ける初年分は、必要な書類を確定申告書に添付して提出する必要があるためです。
参考:国税庁「No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
7.年調年税額を計算する
年調年税額は、年末調整で算出した本来納めるべき所得税、および復興特別所得税です。「所得税額」に「復興特別所得税」を加算して年調年税額を算出します。
復興特別所得税は、東日本大震災の復興に必要な財源を確保するための特別措置法です。所得税を納める義務がある方は、復興特別所得税も納めなければなりません。
なお、復興特別所得税の納付義務は2037年まで継続される予定です。
【計算式】年調年税額(所得税および復興特別所得税)= 所得税額 × 102.1%(復興特別所得税率)
上記の計算式を用いて最終的な年調年税額を確定します(100円未満の端数は切り捨て)。
8.年調年税額と源泉徴収税額を比較し差額を清算する
確定した年調年税額源泉徴収税額と源泉徴収税額の差額を算出します。
【計算式】差額 = 年調年税額 - 源泉徴収税額
過納額がある場合は差額分を還付し、不足額がある場合は追加徴収で精算します。
なお、過納額が多額であり、期間内の還付が難しいと見込まれる場合、指定の明細書と添付書類を従業員の所轄税務署長に提出しなければなりません。
ケースに応じた年末調整の計算例

ここからは、従業員の家庭状況に応じた年末調整の計算例を確認していきます。
ケース1:配偶者(収入なし)と17歳の子どもがいる従業員
以下の条件をもとに計算例を解説します。
- 年間の給与支給額が480万円の従業員
- 配偶者(収入なし)と17歳の子どもがいる
1.給与支給額・社会保険料・源泉徴収税額の集計
年間の給与支給額と、毎月天引きされている社会保険料・源泉徴収税額を集計します。
| 項目 | 額 |
|---|---|
| 給与支給額 | 480万円 |
| 社会保険料 | 52万1,092円 |
| 源泉徴収税額 | 9万5,375円 |
2.給与所得額を計算
給与所得額は、給与総額から給与所得控除を差し引いて算出します。
給与支給額が480万円の場合、給与所得控除額は「収入金額 × 20% + 44万円」で計算します。給与所得控除額は、以下の計算式で求めることが可能です。
【計算式】
給与所得控除額(480万円の場合) = 収入金額 × 20% + 44万円
給与所得額 = 給与支給額 - (給与支給額 - 収入金額 × 20% + 44万円)
140万円 = 480万円 × 20% + 44万円
340万円 = 480万円 - 140万円
給与所得額 = 340万円
3.所得控除額を計算
適用される所得控除は以下の6つと仮定して、所得控除額を計算します。
| 所得控除 | 控除額 |
|---|---|
| 社会保険料控除 | 52万1,092円 |
| 基礎控除 | 48万円 |
| 配偶者控除 | 38万円 |
| 扶養控除 | 38万円 |
| 生命保険料控除 | 12万円 |
| 地震保険料控除 | 5万円 |
| 所得控除額 | 193万1,092円 |
4.課税給与所得額を算出
「給与所得額」から「所得控除額」を差し引いて課税給与所得額を算出します。
【計算式】
課税給与所得額 = 給与所得額 - 所得控除額
146万8,908円 = 340万円 - 193万1,092円
1,000円未満は切り捨てるため、課税給与所得額は146万8,000円です。
5.所得税額を計算
所得税額は、「課税給与所得額」に「所得税率」を掛けたものから「控除額」を差し引いて算出します。給与所得額が146万8,000円の場合、所得税率は5%、控除額は0円です。
【計算式】
所得税額 = 課税給与所得額 × 所得税率 - 控除額
7万3,400円 = 146万8,000円 × 5% - 0円
所得税額 = 7万3,400円
6.年調年税額を計算
年調年税額は、「所得税額」に「復興特別所得税」を加えて算出します。
【計算式】
年調年税額(所得税および復興特別所得税)= 所得税額 × 102.1%(復興特別所得税率)
7万4,941円 = 7万3,400円 × 102.1%
100円未満の端数は切り捨てるため、年調年税額は7万4,900円です。
7.源泉徴収税額との差額
「年調年税額」と「源泉徴収税額」の差分を算出します。
【計算式】
差額 = 年調年税額 - 源泉徴収税額
- 2万475円 = 7万4,900円 - 9万5,375円
差額 = - 2万475円
年調年税額が源泉徴収済税額よりも少なければ、税金を納め過ぎている状態です。超過分は従業員に還付する必要があります。
ケース2:配偶者(収入なし)と21歳、17歳の子どもがいる従業員
以下の条件をもとに計算例を解説します。
- 年間の給与支給額が480万円の従業員
- 配偶者(収入なし)と21歳(収入なし)、17歳(収入なし)の子どもがいる
1.給与支給額・社会保険料・源泉徴収税額の集計
年間の給与支給額、毎月天引きされている社会保険料・源泉徴収税額を集計します。
| 項目 | 額 |
|---|---|
| 給与支給額 | 480万円 |
| 社会保険料 | 52万1,092円 |
| 源泉徴収税額 | 9万5,375円 |
2.給与所得額を計算
給与所得額は、「給与総額」から「給与所得控除」を差し引いて算出します。給与支給額が480万円の場合、給与所得控除額は「収入金額 × 20% + 44万円」で計算します。
給与所得控除額は、以下の計算式で算出可能です。
【計算式】
給与所得控除額 = 収入金額 × 20% + 44万円
給与所得額 = 給与支給額 - (給与支給額 - 収入金額 × 20% + 44万円)
140万円 = 480万円 × 20% + 44万円
340万円 = 480万円 - 140万円
給与所得額 = 340万円
3.所得控除額を計算
適用される所得控除は以下の6つと仮定して、所得控除額を計算します。
| 所得控除 | 控除額 |
|---|---|
| 社会保険料控除 | 52万1,092円 |
| 基礎控除 | 48万円 |
| 配偶者控除 | 38万円 |
| 扶養控除(17歳の子) | 38万円 |
| 扶養控除(21歳の子) | 38万円 |
| 生命保険料 | 12万円 |
| 地震保険料 | 5万円 |
| 特定扶養親族加算額(21歳の子) | 25万円 |
| 所得控除額 | 256万1,092円 |
1つ目のケースと異なるのは、控除扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の人に適用される「特定扶養親族控除」が加算される点です。
4.課税給与所得額を算出
「給与所得額」から「所得控除額」を差し引いて課税給与所得額を算出します。
【計算式】
課税給与所得額 = 給与所得額 - 所得控除額
83万8,908円 = 340万円 - 256万1,092円
1,000円未満は切り捨てるため、課税給与所得額は83万8,000円です。
5.所得税額を計算
所得税額は、「課税給与所得額」に「所得税率」を掛けた金額から「控除額」を差し引いて算出します。課税給与所得額が83万8,000円の場合、所得税率は5%、控除額は0円です。
【計算式】
所得税額 = 課税給与所得額 × 所得税率 - 控除額
4万1,900円 = 83万8,000円 × 5% - 0円
所得税額 = 4万1,900円
6.年調年税額を計算
年調年税額は、「所得税額」に「復興特別所得税」を加算して算出します。
【計算式】
年調年税額(所得税および復興特別所得税)= 所得税額 × 102.1%(復興特別所得税率)
4万2,779円 = 4万1,900円 × 102.1%
100円未満の端数は切り捨てるため、年調年税額は4万2,700円です。
7.源泉徴収税額との差額
年調年税額と源泉徴収税額の差分を算出します。
【計算式】
差額 = 年調年税額 - 源泉徴収税額
- 5万2,675円 = 4万2,700円 - 9万5,375円
差額 = - 5万2,675円
年調年税額が源泉徴収済税額より少ない場合、税金を納め過ぎている状態です。超過分は従業員に還付しなければなりません。
ケース3:17歳の子ども(収入なし)がいるひとり親の従業員
以下の条件をもとに計算例を解説します。
- 年間の給与支給額が480万円の従業員
- 17歳の子ども(収入なし)がいるひとり親
1.給与支給額・社会保険料・源泉徴収税額の集計
年間の給与支給額、毎月天引きされている社会保険料・源泉徴収税額を集計します。
| 項目 | 額 |
|---|---|
| 給与支給額 | 480万円 |
| 社会保険料 | 52万1,092円 |
| 源泉徴収税額 | 9万5,375円 |
2.給与所得額を計算
給与所得額は、「給与総額」から「給与所得控除」を差し引いて算出します。
給与支給額が480万円の場合、給与所得控除額は「収入金額 × 20% + 44万円」で計算します。給与所得控除額は、以下の計算式で算出可能です。
【計算式】
給与所得控除額 = 収入金額 × 20% + 44万円
給与所得額 = 給与支給額 - (給与支給額 - 収入金額 × 20% + 44万円)
140万円 = 480万円 × 20% + 44万円
340万円 = 480万円 - 140万円
給与所得額 = 340万円
3.所得控除額を計算
適用される所得控除は以下を仮定して、所得控除額を計算します。
| 所得控除 | 控除額 |
|---|---|
| 社会保険料控除 | 52万1,092円 |
| 基礎控除 | 48万円 |
| 扶養控除(17歳の子) | 38万円 |
| ひとり親控除 | 35万円 |
| 所得控除額 | 173万1,092円 |
4.課税給与所得額を算出
課税給与所得額は、「給与所得額」から「所得控除額」を差し引いて算出します。
【計算式】
課税給与所得額 = 給与所得額 - 所得控除額
166万8,908円 = 340万円 - 173万1,092円
1,000円未満は切り捨てるため、課税給与所得額は166万8,000円です。
5.所得税額を計算
所得税額は、「課税給与所得額」に「所得税率」を掛けたものから「控除額」を差し引いて算出します。課税給与所得額が166万8,000円の場合、所得税率は5%、控除額は0円です。
【計算式】
所得税額 = 課税給与所得額 × 所得税率 - 控除額
8万3,400円 = 166万8,000円 × 5 % - 0円
所得税額 = 8万3,400円
6.年調年税額を計算
年調年税額は、所得税額に復興特別所得税を加算して算出します。
【計算式】
年調年税額(所得税および復興特別所得税)= 所得税額 × 102.1%(復興特別所得税率)
8万5,151円 = 8万3,400円× 102.1%
100円未満の端数は切り捨てるため、年調年税額は8万5,100円です。
7.源泉徴収税額との差額
「年調年税額」と「源泉徴収税額」の差分を算出します。
【計算式】
差額 = 年調年税額 - 源泉徴収税額
- 1万275円 = 8万5,100円 - 9万5,375円
差額 = - 1万275円
年調年税額が源泉徴収済税額より多い場合、納税額が足りていない状態です。その差額は、従業員から追加徴収する必要があります。
年末調整の流れと対象期間

年末調整は、10月頃から1月にかけて行われます。
| スケジュール | 業務内容 |
|---|---|
| 10月・11月 |
|
| 12月 |
|
| 1月 |
|
年末調整の計算に必要な各種申告書を従業員に配布し、必要事項を記入してもらいます。申告書を従業員から回収し、その内容をもとに年末調整業務を始めましょう。
なお、年末調整は、原則1月1日から12月31日に支払われた給与が対象となります。12月に働いた分は翌年1月に支給されるため、当年の年末調整の対象外です。
12月に行う年末調整の対象者

年末調整は、年間を通して会社などで勤務している人や、年の途中に就職して年末まで勤務している人が対象です。
また、正社員のみでなく、パートやアルバイト等の非正規社員も対象に含まれます。ただし、年の途中で退職した人は、転職先の会社で年末調整が行われるため対象外です。
なお、複数の場所から給与支払いを受けたり、副業の所得が一定額を超えたりする場合には、年末調整と確定申告の両方の手続きが必要です。
年末調整の計算に必要な申告書

扶養控除や保険料控除など、従業員の税負担を軽減するための控除を受ける場合、年末調整の計算業務には各種申告書が必要です。
どのような申告書が必要なのか詳しく確認していきましょう。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
扶養控除等(異動)申告書は、控除の有無にかかわらず、年末調整対象の従業員は提出が必要となる書類です。申告書の提出により、扶養控除やひとり親控除、寡婦控除等の適用が判断されます。扶養控除等(異動)申告書は、従業員本人の個人情報や扶養家族の情報を記入する必要があるため、できるかぎり早めに配布しましょう。
参考:国税庁「A2-1 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」
給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書は、基礎控除・配偶者(特別)控除・所得金額調整控除を受けるための書類です。
基礎控除の対象者は、納税者本人の合計所得金額が2,500万円以下の従業員です。すべての従業員が、基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書を提出する必要があります。なお、2024年には定額減税の申告書も結合されました。
参考:国税庁「A2-4 給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告」
給与所得者の保険料控除申告書
保険料控除申告書は、社会保険料や生命保険料等の保険料控除を受けるための書類です。
毎月の給与から天引きされる社会保険料には、保険料控除申告書による社会保険料控除の申告は不要です。なお、社会保険料控除が適用されるには、国民年金保険料等の支払金額を証明する書類を提出する必要があります。
給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 兼(特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書
給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 兼(特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書は、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けるために必要な書類です。
従業員の居住地を管轄する税務署から従業員宛に交付されます。対象となる従業員は、金融機関から発行された年末残高等証明書の情報を記載した申告書の提出が必要です。年末残高等証明書は、11月下旬頃に金融機関等から送付されます。
参考:国税庁「年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受ける方へ」
年末調整の計算に関する注意点

年末調整の計算に関する注意点は、以下の3つです。
- スケジュールに余裕をもつ
- 端数処理の誤りに気を付ける
- 扶養控除の人数変更の漏れに気を付ける
効率的に業務を進めるためにもしっかり確認しておきましょう。
スケジュールに余裕をもつ
年末調整の計算には、従業員からの回収が必要な書類があります。
従業員からの書類回収が遅れると年末調整の作業も遅れます。年末調整の提出期限までに必要な書類が揃わない場合、従業員自身が確定申告しなければ控除は受けられません。期限に間に合うように早い段階から従業員に周知し、余裕を持ったスケジュールで進めましょう。
端数処理の誤りに気を付ける
年末調整の計算時に注意したいのが、端数処理の仕方です。
課税所得金額は「1,000円未満」、年調年税額は「100円未満」でそれぞれ切り捨てる必要があります。対応を間違えると合計金額に誤差が生まれるため、年末調整の計算を始める前に端数処理の仕方を確認しておくことが重要です。
扶養控除の人数変更の漏れに気を付ける
結婚や離婚、子どもの独立などで扶養家族の人数に増減が生じた場合、扶養控除の人数変更が必要です。扶養人数が変わると、還付ではなく追加徴収になる場合があります。記載漏れがあれば修正対応にも時間を取られるため、正しく記載するように周知しましょう。
年末調整の計算業務を効率化する方法

年末調整の計算は年々複雑化しており、担当者の業務負担が増しています。担当者の業務負担を減らすためには、計算業務を効率的に進められる対策が必要です。
計算業務を効率的に進める方法として、以下のようなものがあります。
- しっかりと事前準備する
- 外部に年末調整業務を依頼する
- 給与計算システムを導入する
それぞれの概要を確認していきましょう。
しっかりと事前準備する
年末調整は年に一度の業務であり、業務フローを思い出すのに時間がかかることも少なくありません。
早めに対策しなければ、作業スケジュール全体に影響が出る可能性があります。年末調整が近づく早い段階で従業員に周知徹底し、効率的に業務を進めましょう。
なお、記入漏れやミスが多ければ修正対応に時間が取られるため、年末調整の記入マニュアルを作成しておくことも有効です。
外部に年末調整業務を依頼する
年末調整には、書類作成や複雑な計算処理が多く、担当者の負担は大きなものです。
年末調整業務に多くの人員を割けない場合は、税理士やアウトソーシング会社への委託を検討しましょう。外部委託することで、担当者は年末調整に関する業務負担を軽減でき、本来注力すべき業務に集中することが可能です。ただし、外部委託する場合には一定の費用が発生するため、費用対効果を踏まえて検討する必要があります。
関連記事:年末調整アウトソーシングとは?業務代行のメリットを解説
給与計算システムを導入する
年末調整業務の負担を軽減したい場合は、給与計算システムを導入しましょう。
給与計算システムとは、勤怠情報をもとに自動で給与を計算できるシステムです。システム導入により、給与計算業務の効率化や人的ミスを減らす効果が期待できます。機能が充実したシステムは年末調整にも対応しているため、担当者の負担軽減にも効果的です。
なお、国税庁は、年末調整手続の電子化に向けた年調ソフトを提供しています。ただし、年末調整の書類提出に関する業務のみが対象で、計算業務は対象外です。業務効率を図るためには、給与計算システムの導入が有効です。
関連記事:年末調整システムとは?メリットや比較ポイントについて解説
関連記事:年末調整を効率化させる3つの方法!給与計算システムも紹介
参考:国税庁「年末調整手続の電子化について ~年調ソフト編~」
年末調整にも対応!人事管理システム「ADPS(アドプス)」

年末調整は年々複雑化しており、とくに計算業務の負担が増しています。従業員不足の企業も多く、担当者の負担や人的ミスを軽減するためには業務効率化に向けた取り組みが必須です。
カシオヒューマンシステムズ株式会社では、労働時間管理や給与計算、人事管理を一元化できる人事管理システム「ADPS」を提供しています。年末調整にも対応しており、計算業務の自動化や書類作成の簡素化等で担当者の負担を大幅に軽減できます。
詳しくは、以下をご確認ください。
まとめ

年末調整の計算業務は年々複雑化しており、担当者の負担は増しています。
担当者の負担や人的ミスの軽減を図るためには、業務効率化に向けた取り組みが欠かせません。近年は、給与計算や年末調整等に対応するシステムが多く存在します。年末調整業務の課題を解消したい場合には、システムの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
カシオヒューマンシステムズコラム編集チームです。
人事業務に関するソリューションを長年ご提供してきた知見を踏まえ、
定期的に「人事部の皆様に必ず今後の業務に役立つ情報」を紹介しています。