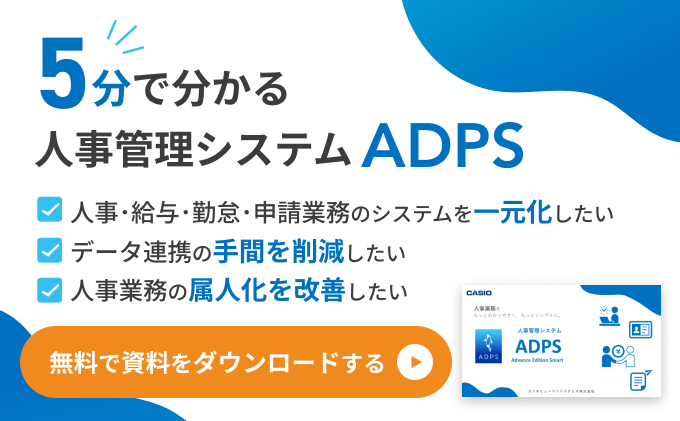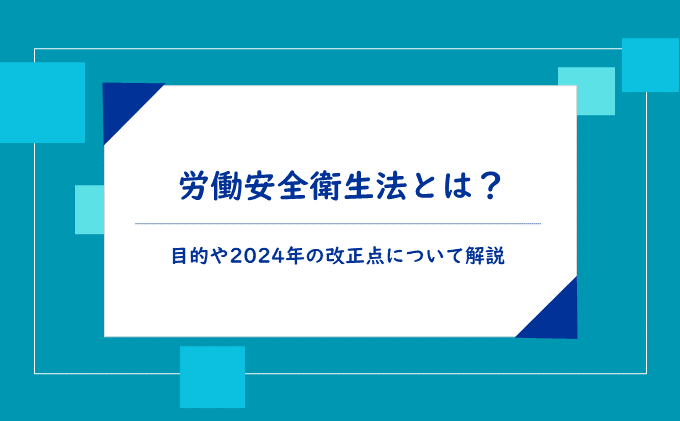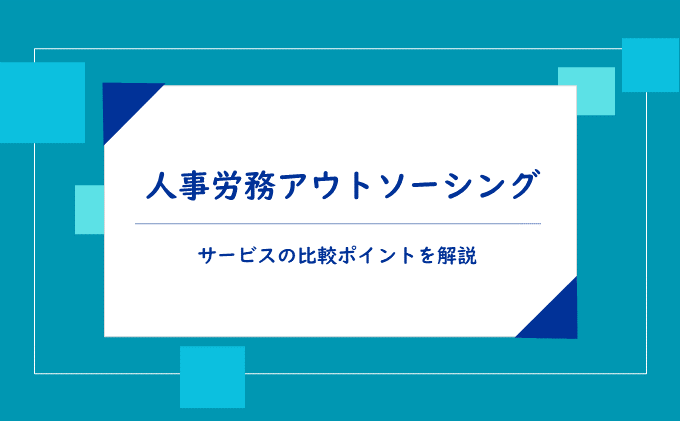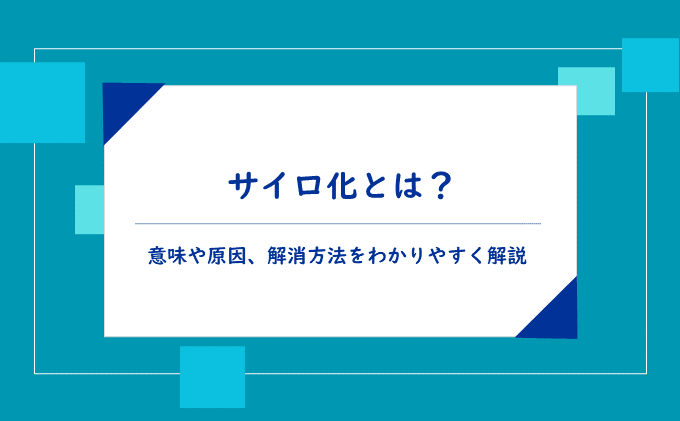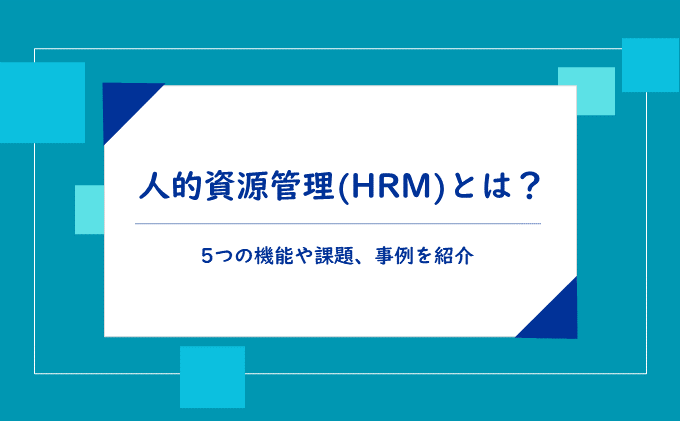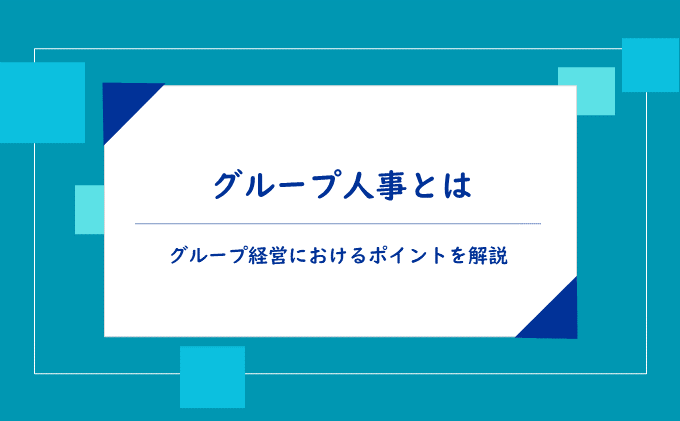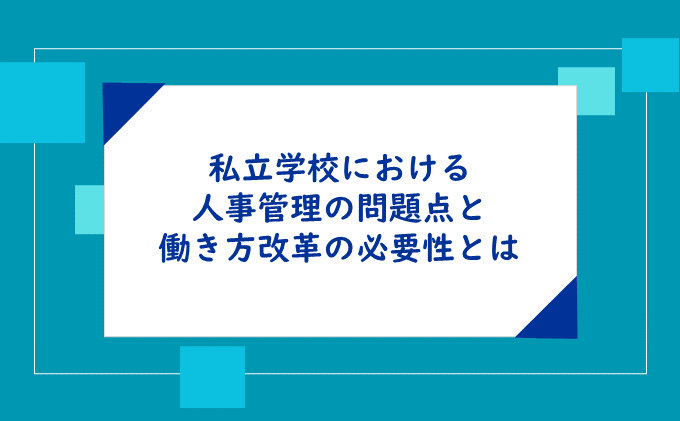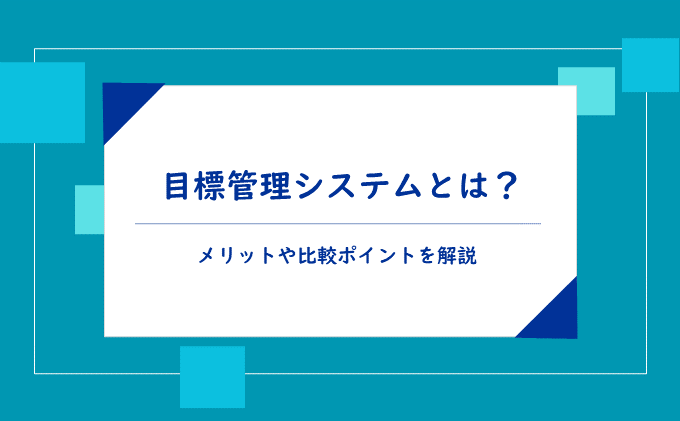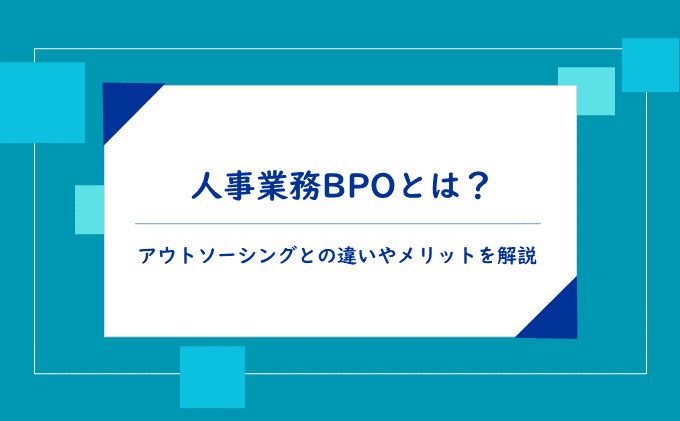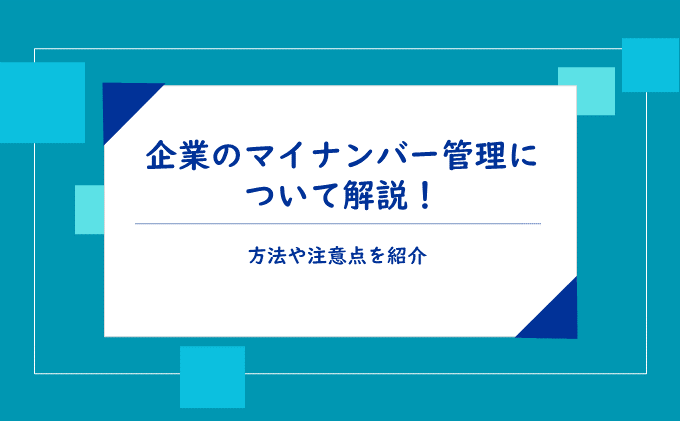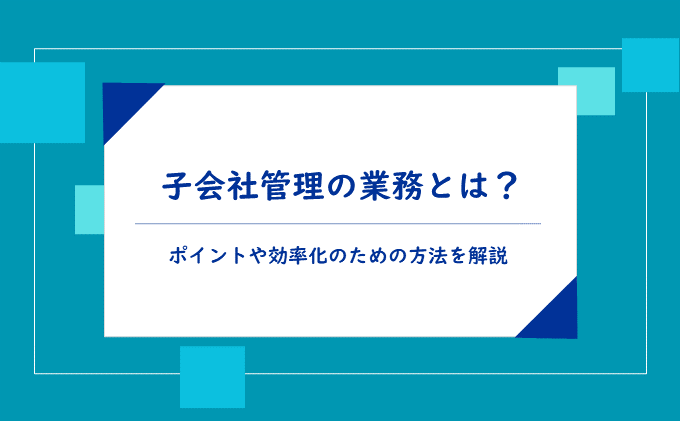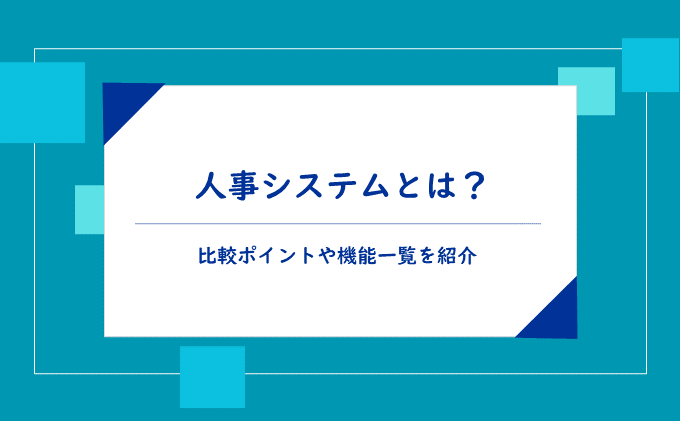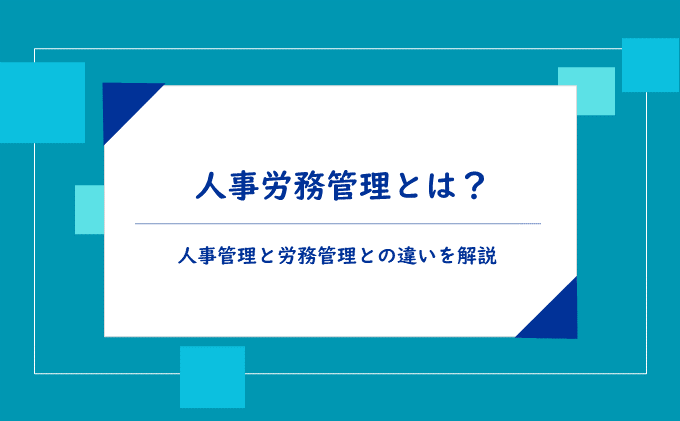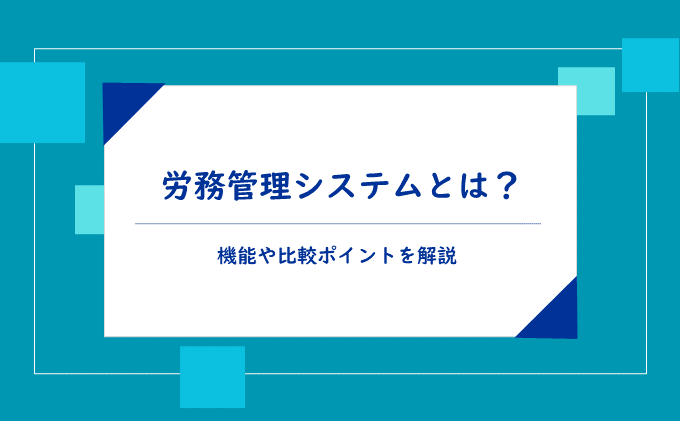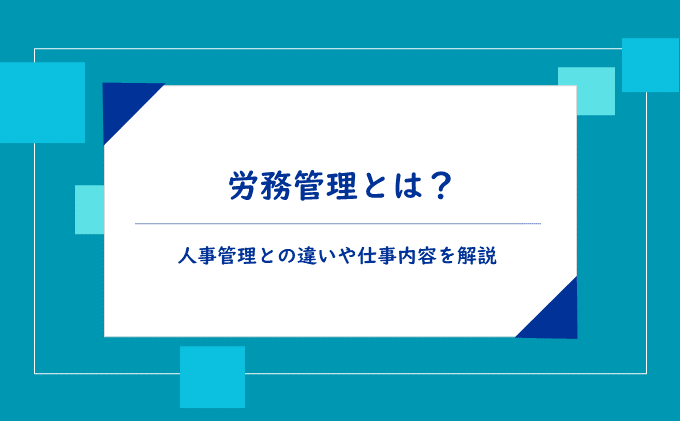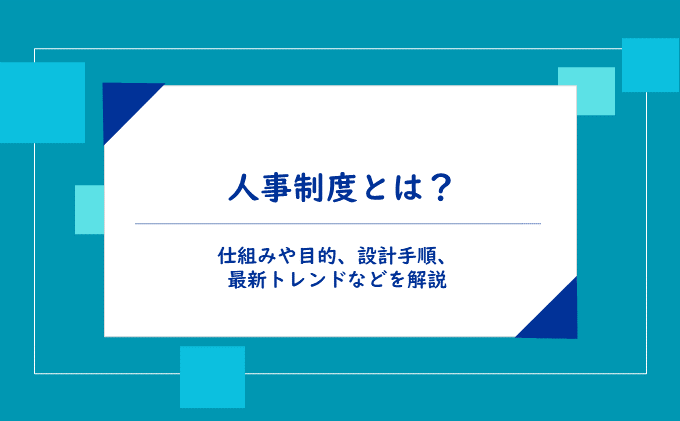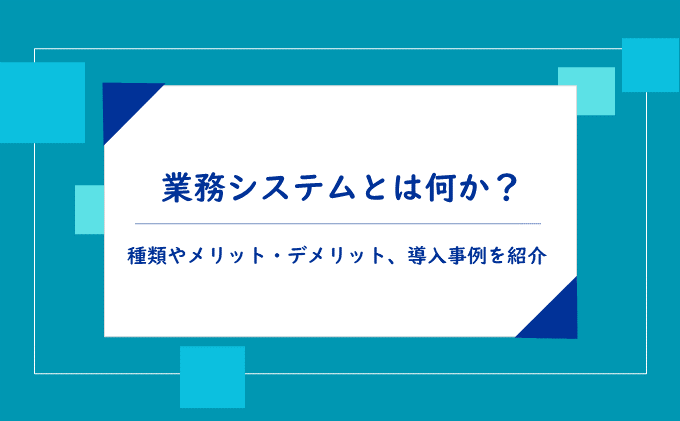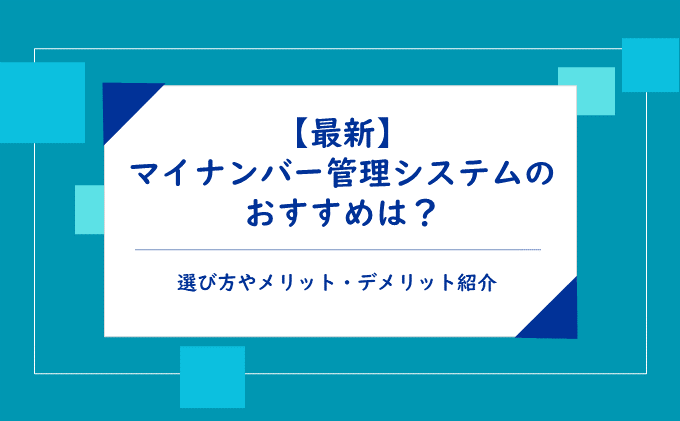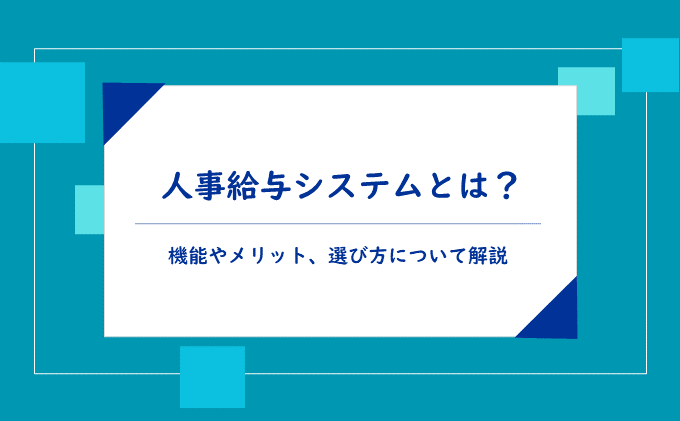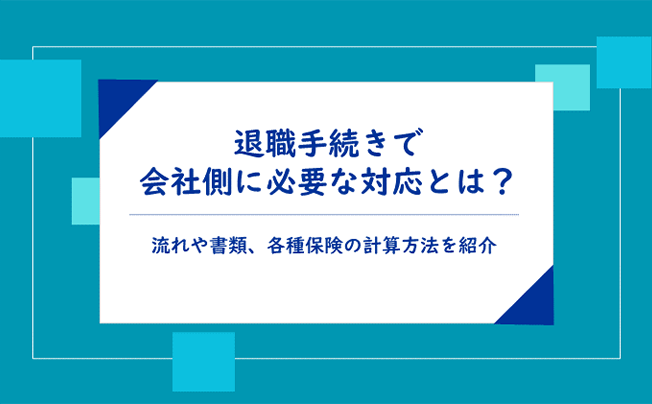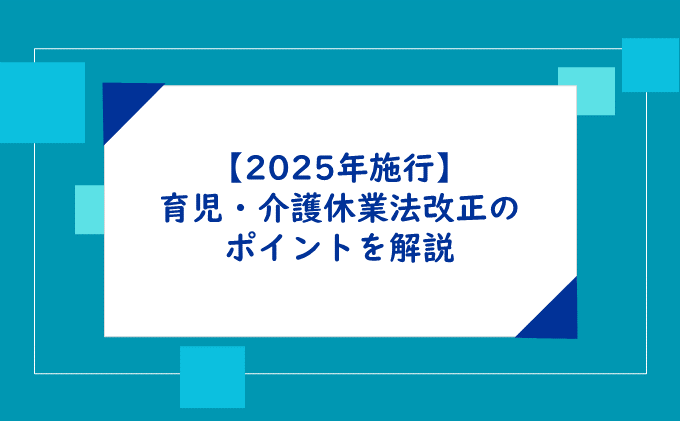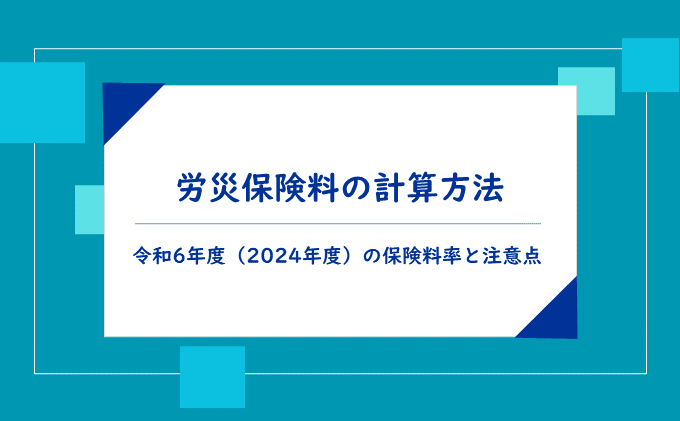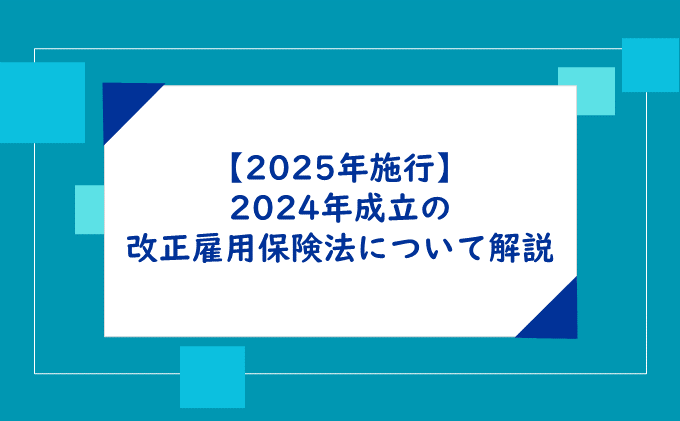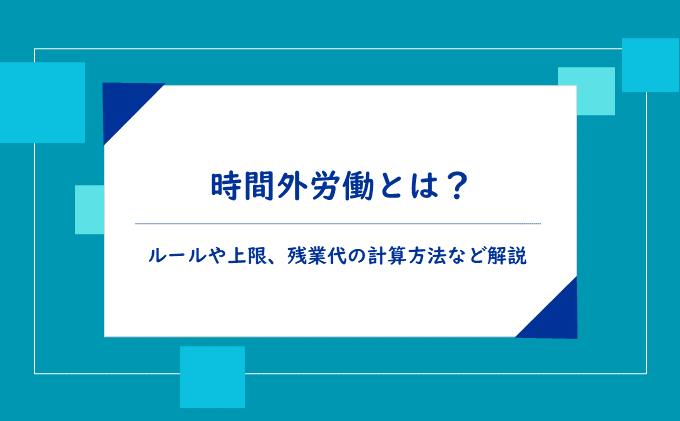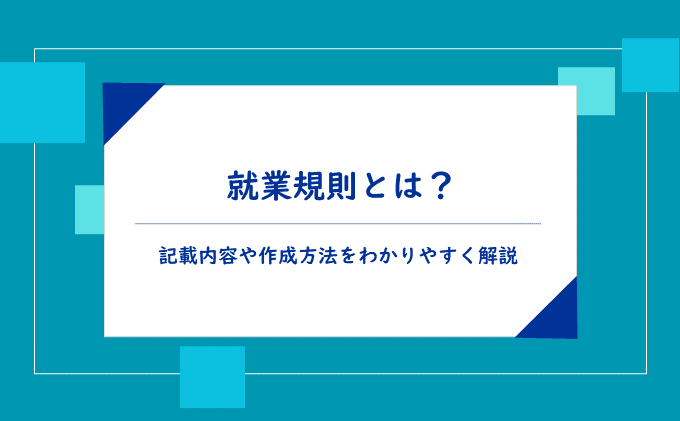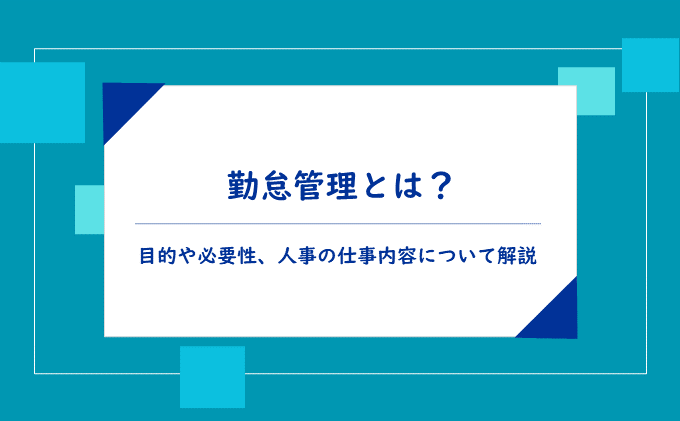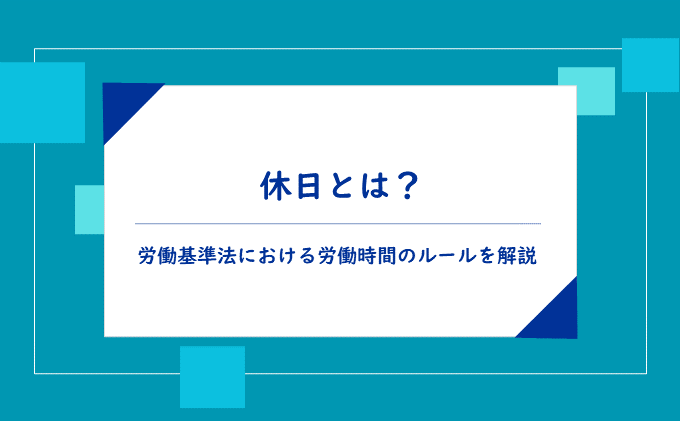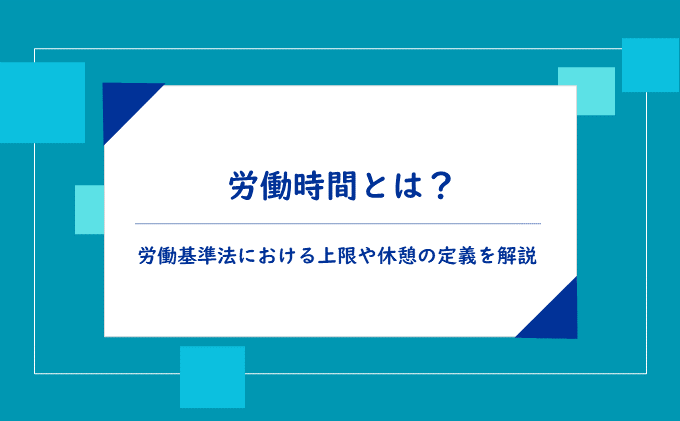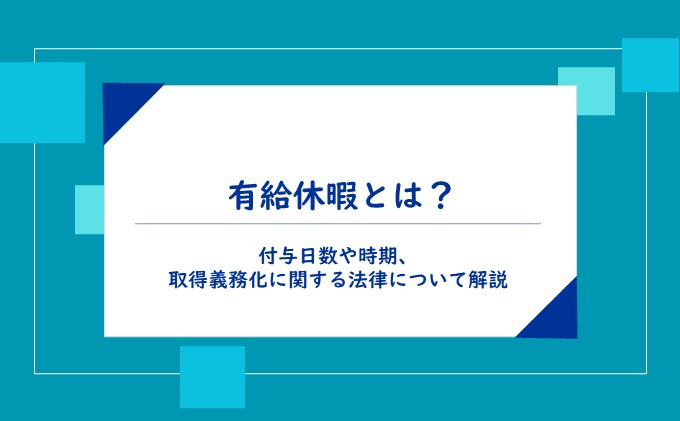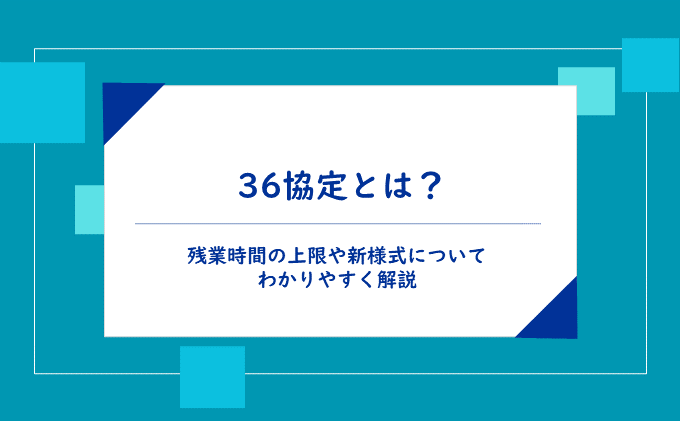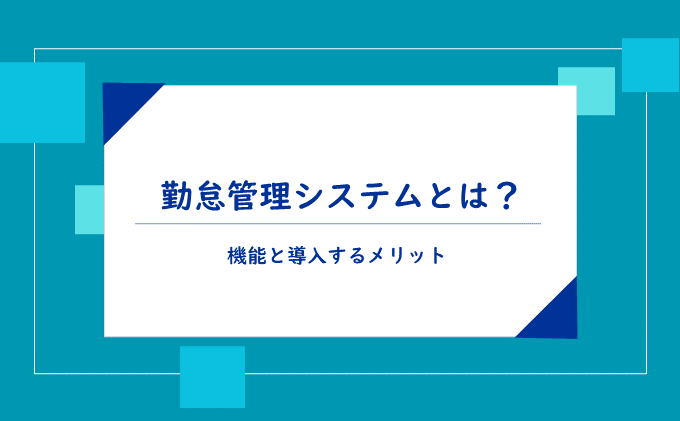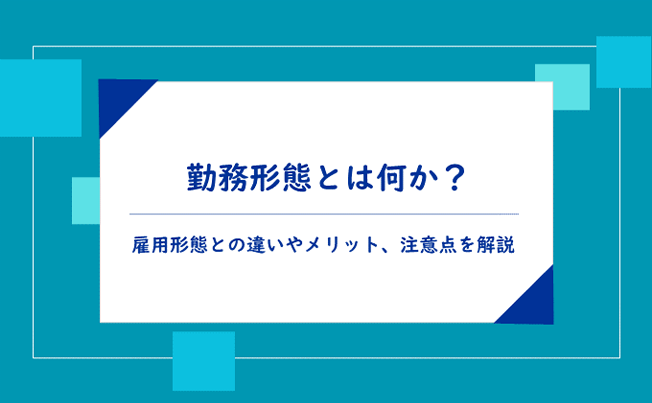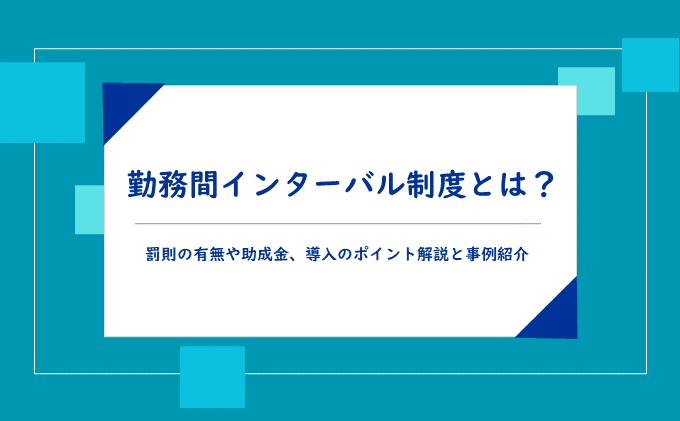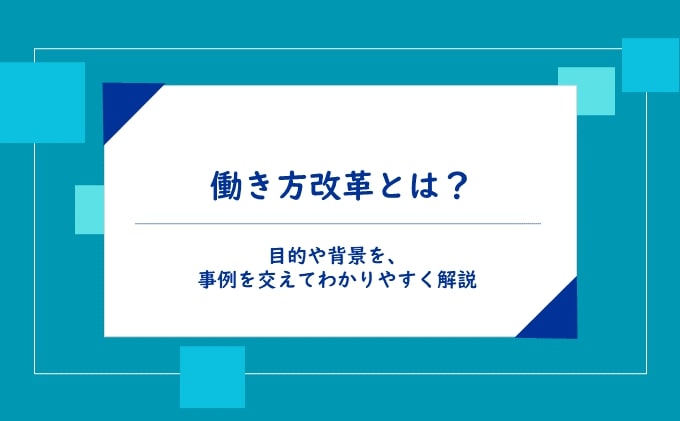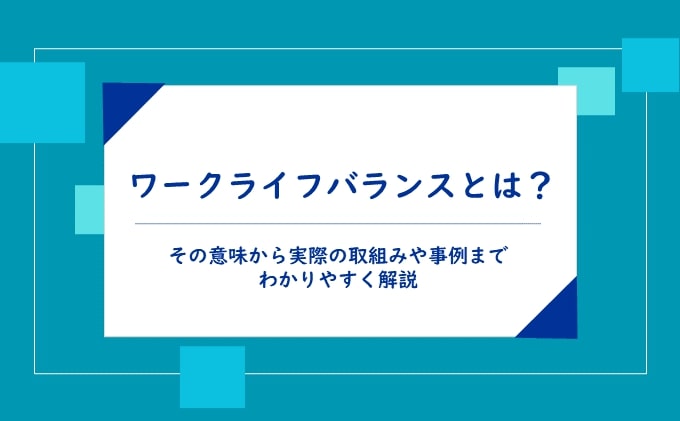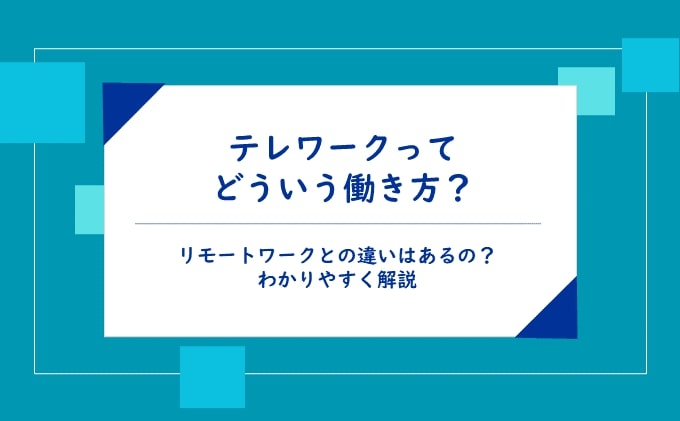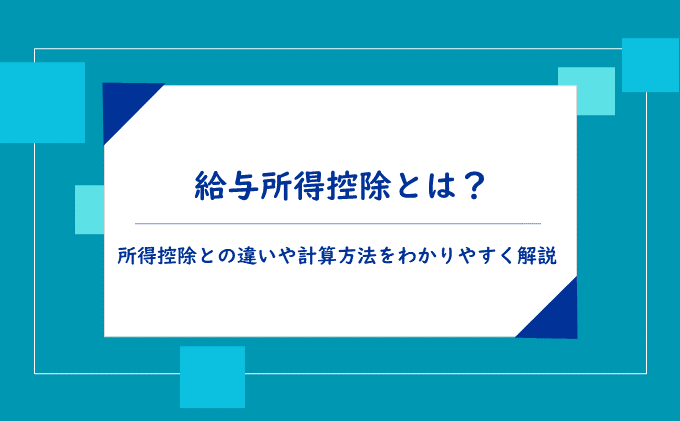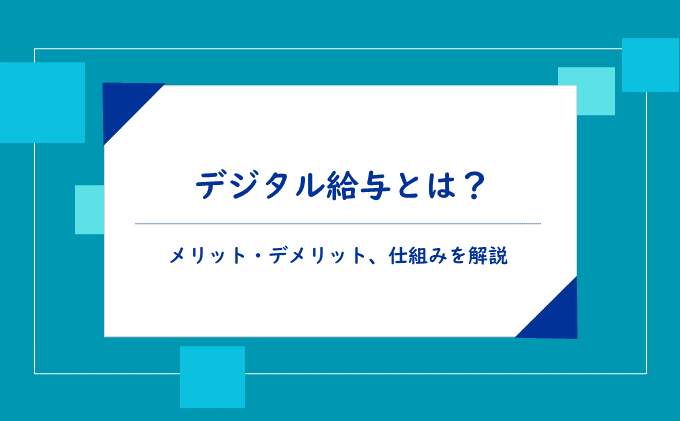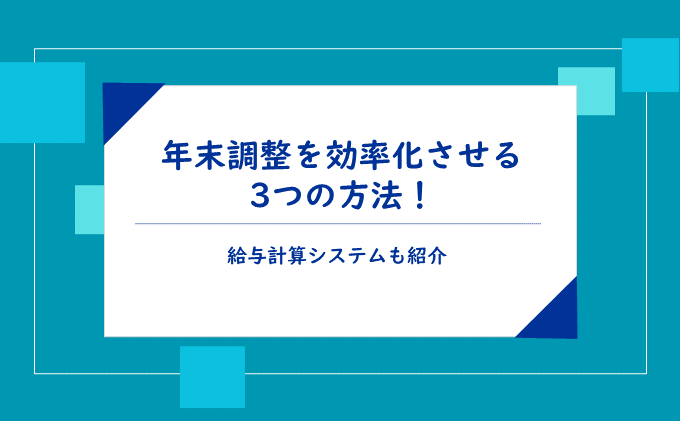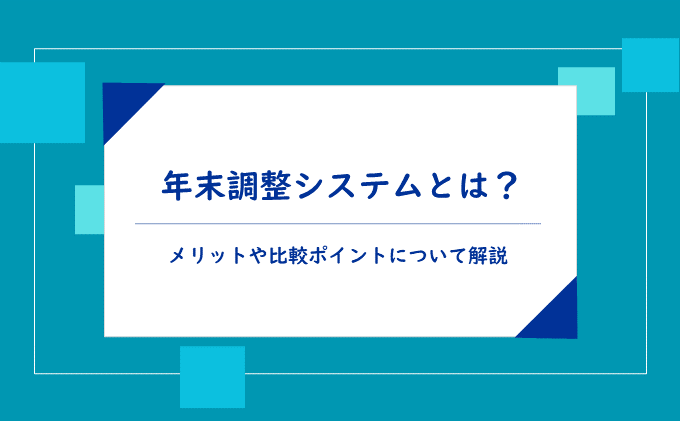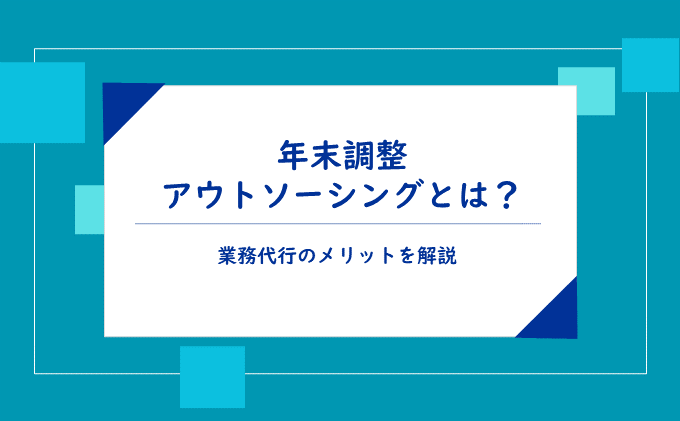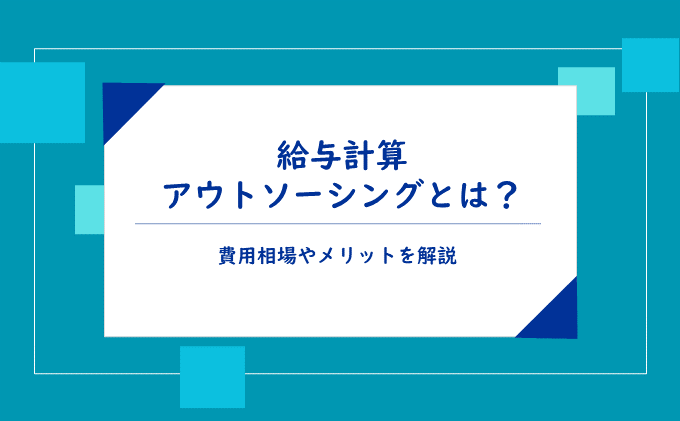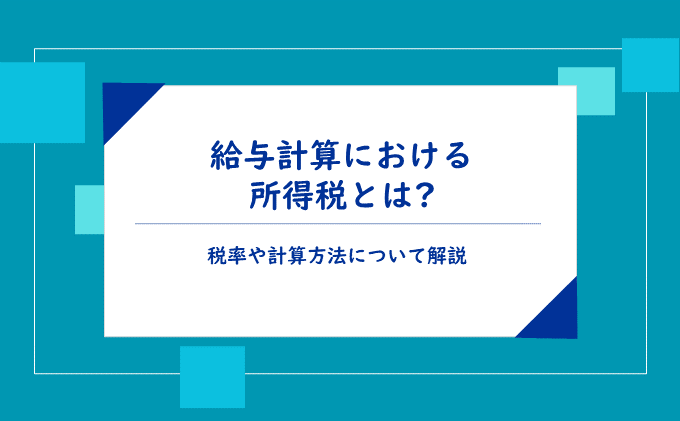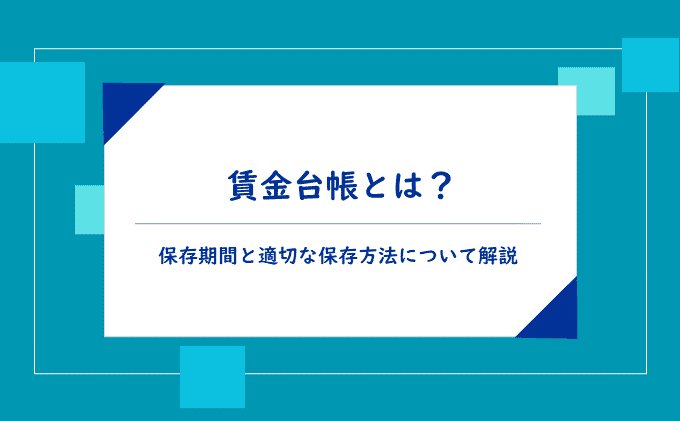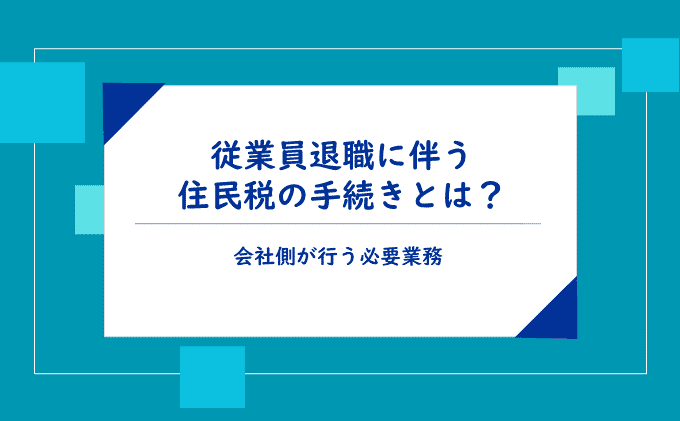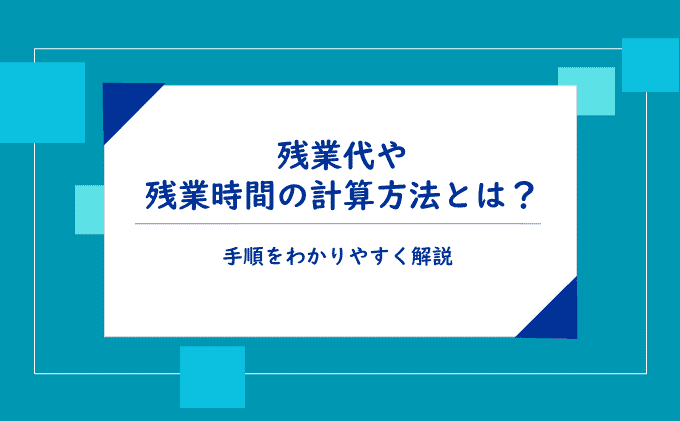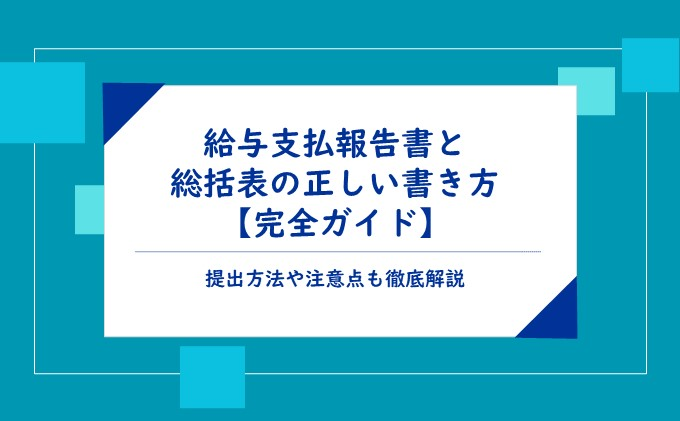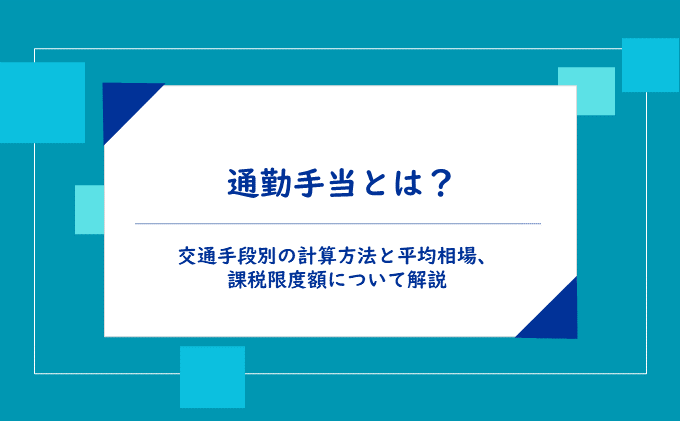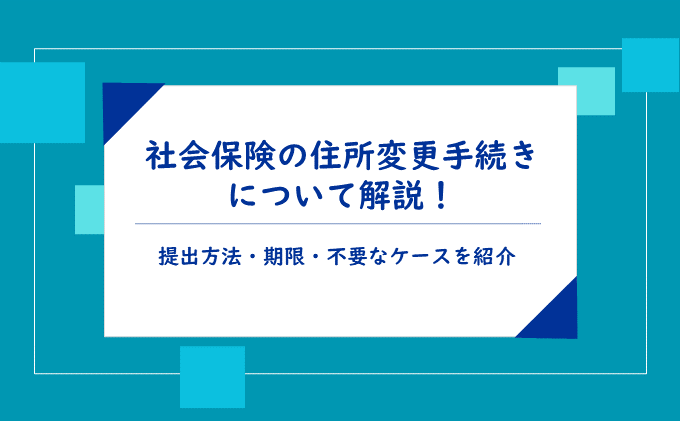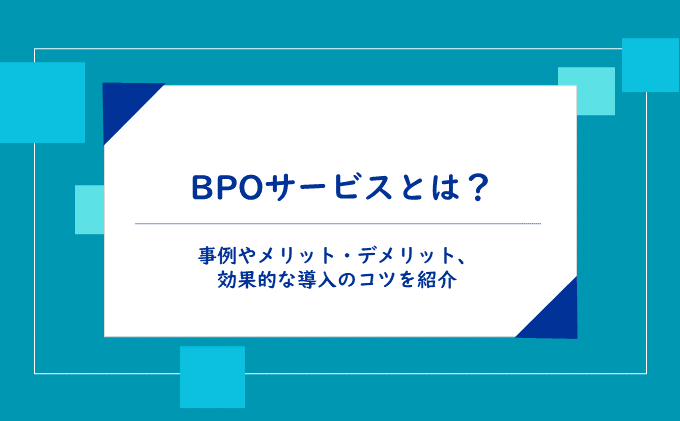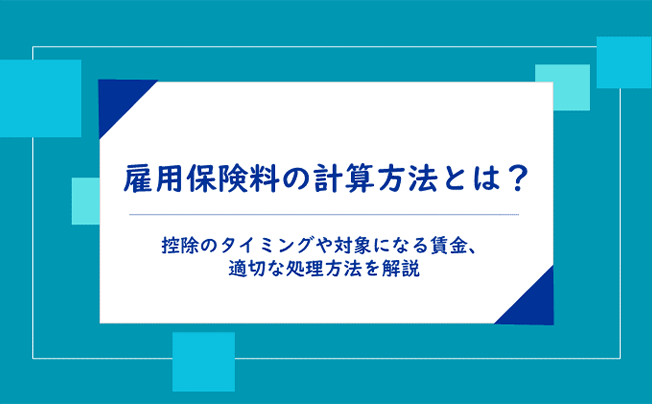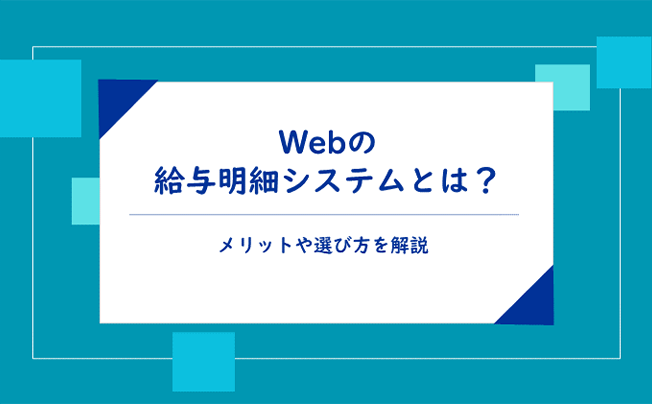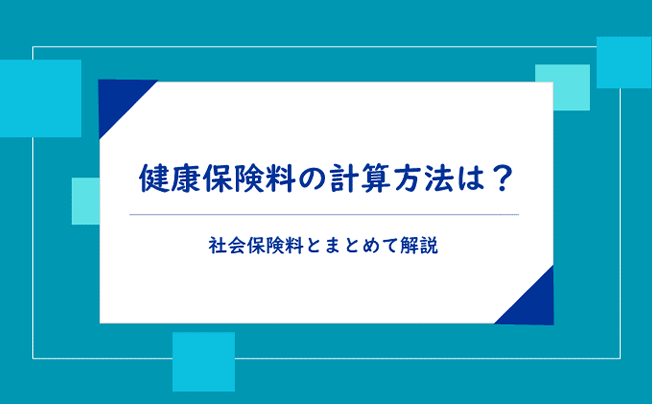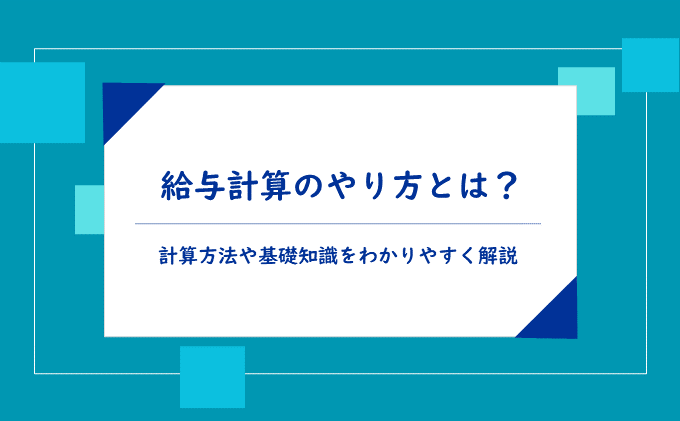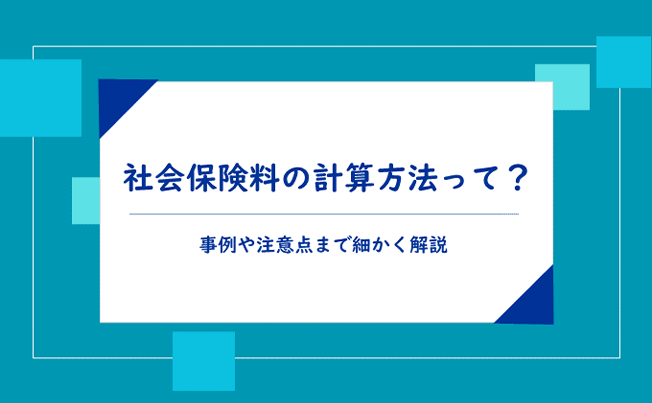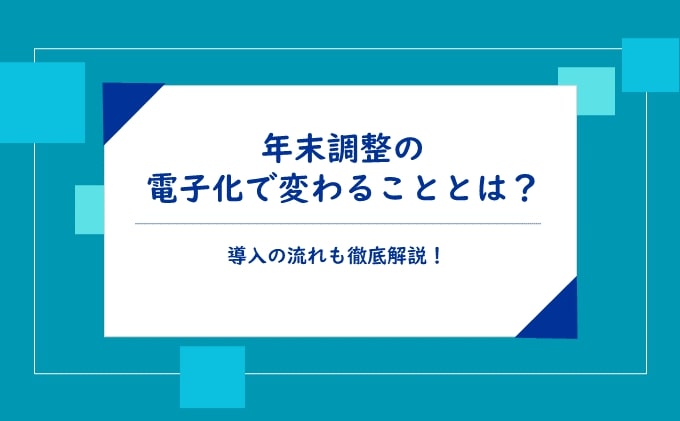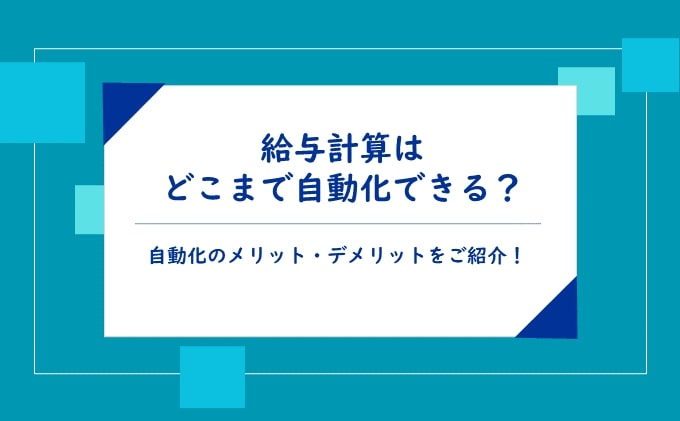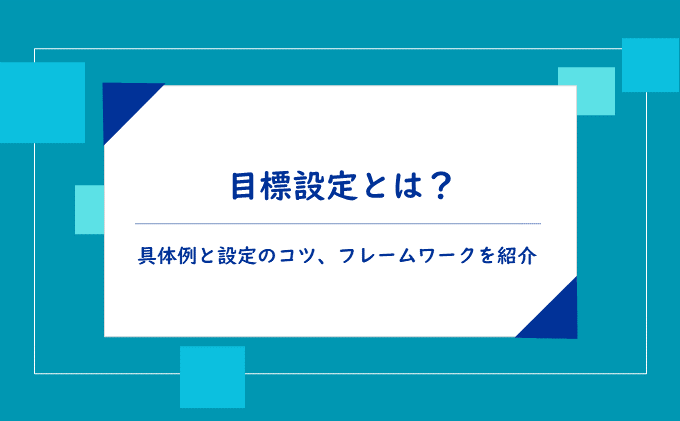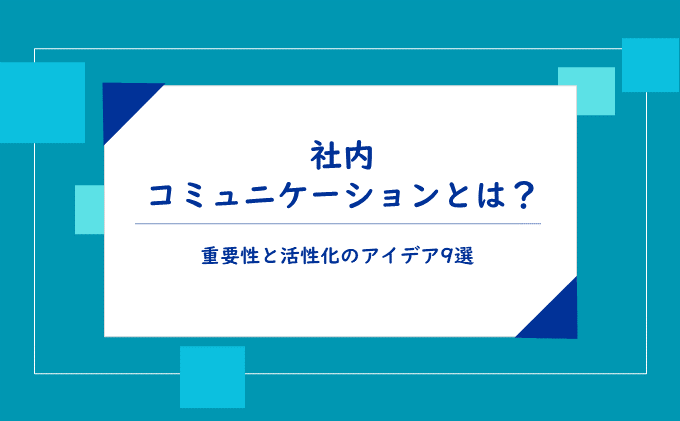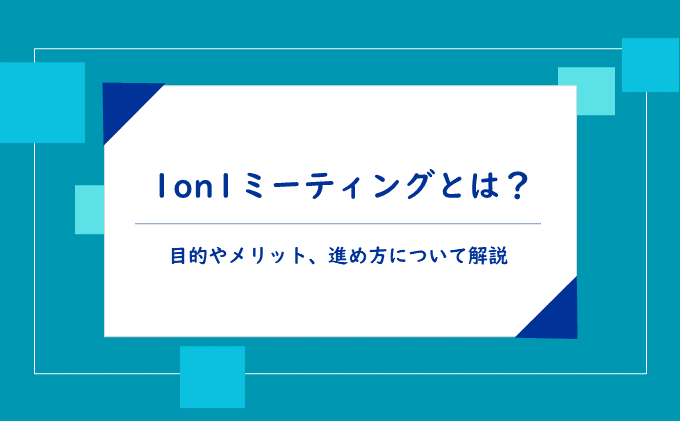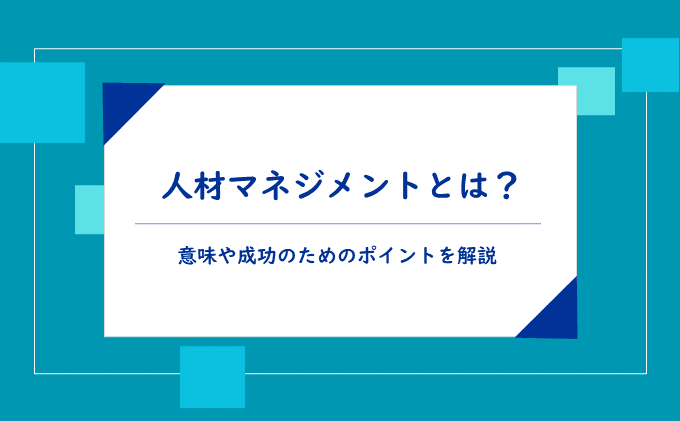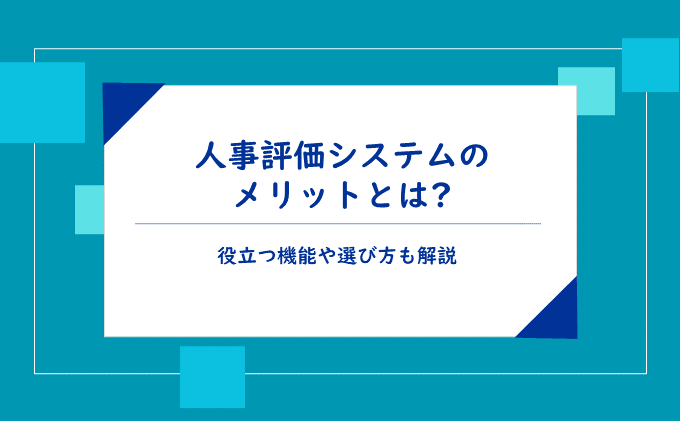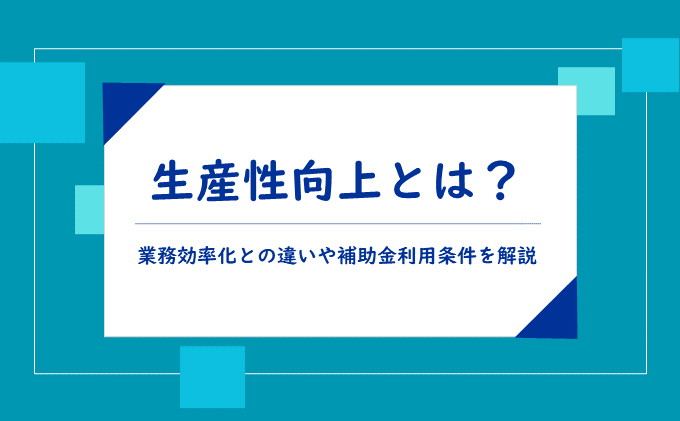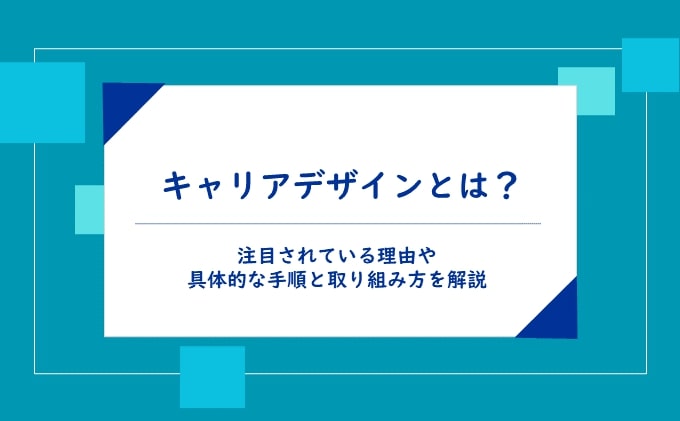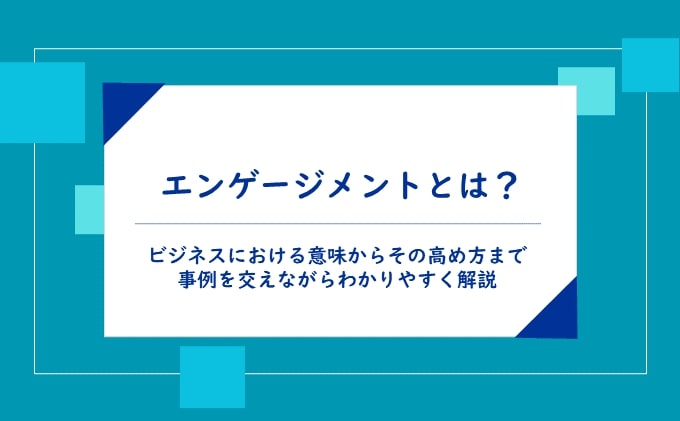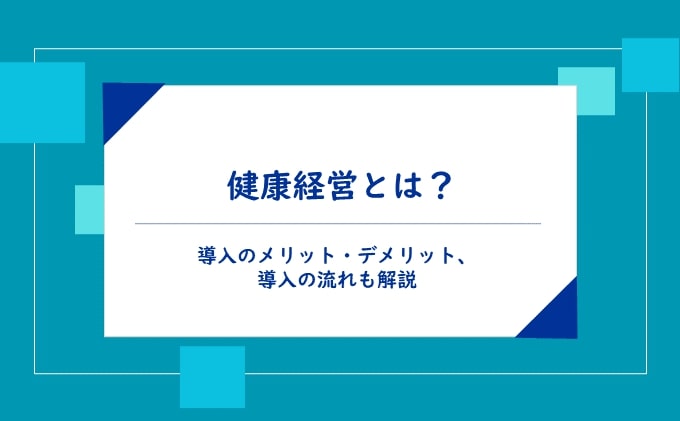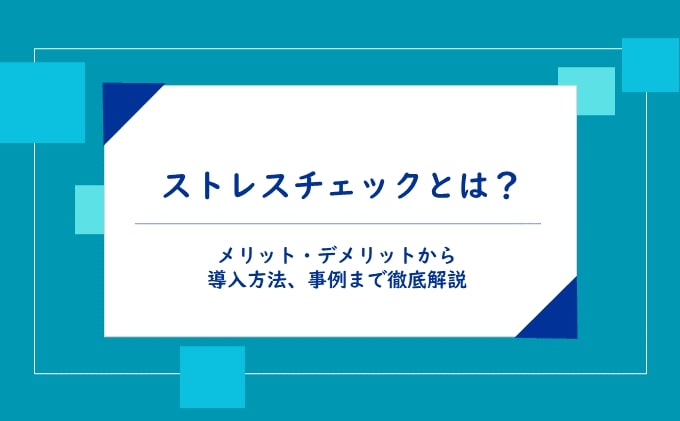令和7年度(2025年度)税制改正大綱についてわかりやすく解説
2025.08.20
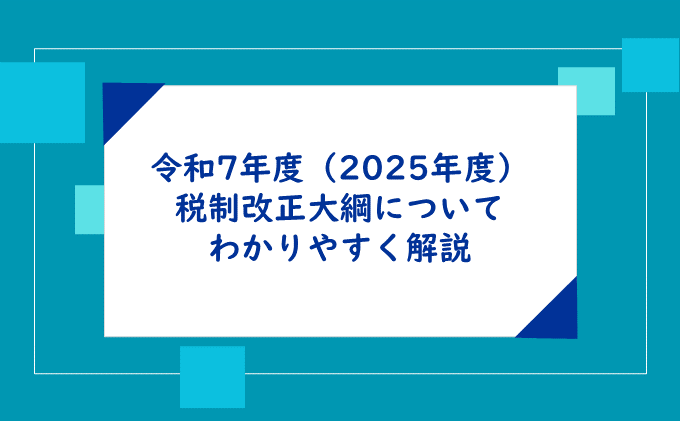
2024年12月27日に閣議決定された令和7年度の税制改正大綱には、いわゆる「103万円の壁」に対する上限や所得税の基礎控除引き上げなど、生活に直接関わる改正が多く盛り込まれました。本記事では、個人所得課税をはじめ、法人課税や資産課税に対する改正点について幅広く解説します。
目次
令和7年度(2025年度)税制改正大綱の概要

税制改正大綱は、次年度の具体的な税制改正項目を取りまとめたものです。例年、年末に公表されます。与党税制調査会が要望項目を審議し、与党税制改正大綱を作成した後に、税制改正大綱として閣議に提出され、閣議決定される流れです。
2025年度の大綱では、個人所得課税に対して以下の点に力点が置かれました。
- 納税者の負担軽減
- 働き控えの解消
- 税制面からの子育て支援
法人課税では、中小企業の経営強化が眼目とされています。また、資産課税には、円滑な事業承継や子育て世帯を支援する意味合いの改正が含まれました。さらに、納税環境整備の一環として、電子帳簿等保存制度の見直しが行われます。
以下で、「個人所得課税」「法人課税」「資産課税」「電子帳簿等保存制度」について、それぞれの主な改正点を解説します。
令和7年度税制改正「個人所得課税」

個人所得課税とは、個人の所得にかかる所得税のことです。税制改正の議論では、いわゆる「103万円の壁」の引き上げが焦点となりました。
物価上昇傾向にあることを踏まえて、所得税の基礎控除額の引き上げが行われます。また、生命保険料控除の拡充や子育て世帯を対象にした住宅ローン減税なども盛り込まれました。
各項目の詳しい内容は、以下のとおりです。
「103万円の壁」が実質123万円まで拡大
報道でもしばしば取り上げられて話題になった「103万円の壁」とは、年収が103万円を超えると所得税の支払いが生じることを指した言葉です。税負担を避ける目的で年収103万円を超えないように労働時間を調整する人がいることは、人手不足とも相まって問題化していました。
103万円は、基礎控除48万円と給与所得控除の最低保障額55万円の合計です。今回の改正では、基礎控除が58万円に、給与所得控除の最低保障額は65万円にそれぞれ引き上げられました。その結果、大綱では給与所得者の非課税限度額である「壁」が実質123万円に拡大されました。
企業の給与支払いや源泉徴収の実務では、2025年末に行う年末調整の際に対応が必要です。同年11月までは改正前の控除額に基づいて源泉徴収を行い、年末調整の段階で改正後の控除額に基づく再計算と精算が行われます。
令和7年度の税制改革大綱は令和6年(2024年)12月27日に閣議決定されました。政府は2025年2月に「壁」を123万円に拡大する法案を提出しましたが、国会審議を経て、さらなる引き上げが決定します。
年収200万円以下の人の基礎控除は37万円増えて95万円になりました。所得税の課税最低限は、給与所得控除の最低保障額の65万円と合わせると160万円です。
参考:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
所得税の基礎控除が48万円から最高58万円まで引き上げ
税制改正大綱の段階では、48万円だった基礎控除が58万円に引き上げられています。物価上昇による税負担の軽減が背景にあります。これまでは、合計所得金額2400万円以下の場合、固定で48万円でした。
基礎控除が固定されていると、物価の上昇局面では実質的な税負担が高まってしまいます。消費者物価が上昇傾向にあるため、低所得者の税負担に対して配慮する観点から、今回の引き上げが行われました。なお、低中所得者層に対しては、所得階層ごとに控除の上乗せが行われました。
参考:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
扶養親族の所得要件の改正
扶養親族の所得要件が、収入103万円以下から123万円以下に改正されました。
例えば、19歳以上23歳未満の大学生年代の子を持つ親の場合、特定扶養控除は63万円となりますが、アルバイトなどで子に103万円を超える収入があると、特定扶養控除を受けられませんでした。今回の改正で、収入123万円を超えない範囲までは扶養親族として控除を受けることができます。
特定親族特別控除の新設
今回の改正では、「特定親族特別控除」が新設されました。19歳以上23歳未満の子について、給与収入が123万円を超えた場合(扶養親族でなくなった場合)でも、150万円以下であれば、親は63万円の控除を受けられる制度です。年収が150万円を超えた場合でも、控除額は段階的に減少する仕組みで、親の負担が急激に増大しないよう配慮されています。
これらの見直しは、人手不足の影響によるものです。年収が103万円を超えないように就労調整する人は一定数存在し、そのような状況を踏まえた対応です。
新しい控除が制度化されたため、企業の人事・総務部門においては、対象者の確認や給与計算システムの設定変更が必要といえます。
参考:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
生命保険料控除の拡充
税制改正大綱には、生命保険料控除の拡充も盛り込まれました。改正により、23歳未満の扶養親族がいる場合には、一般生命保険料控除の適用限度額が4万円から6万円に拡大されます。子育て世帯に対する支援として導入されました。
生命保険料控除は、一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払っている場合に適用されます。生命保険は、契約が締結された時期によって新制度と旧制度に分かれます。2012年以降に契約されたものが新制度で、2011年以前のものが旧制度です。
控除の拡大は、新制度の契約が対象です。拡大の対象となった契約と旧制度の契約が混在する場合には、6万円の所得控除を受けられます。改正前後の比較を、以下の表で示します。
・現行
| 一般生命保険料 | 介護医療保険料 | 個人年金保険料 | |
|---|---|---|---|
| 所得税控除額 | 4万円 | 4万円 | 4万円 |
| 地方税控除額 | 2.8万円 | 2.8万円 | 2.8万円 |
| 所得控除限度額 | 所得税12万円、地方税7万円 | ||
・改正後
| 一般生命保険料 | 介護医療保険料 | 個人年金保険料 | |
|---|---|---|---|
| 所得税控除額 | 6万円 | 4万円 | 4万円 |
| 地方税控除額 | 2.8万円 | 2.8万円 | 2.8万円 |
| 所得控除限度額 | 所得税12万円、地方税7万円 | ||
なお、この控除の拡充は2026年分のみの時限措置です。所得控除全体の限度額は、12万円のまま変わっていません。地方税も同様です。
参考:厚生労働省「令和7年度 税制改正の概要(厚生労働省関係)」
子育て世帯等への住宅ローン減税
子育て世帯や若者夫婦世帯に対する住宅ローン控除は、2024年の特別措置として借入限度額が上乗せされていましたが、2025年も継続されます。
子育て世帯とは、19歳未満の扶養親族がいる世帯を指します。また、若者夫婦世帯とは、夫婦のいずれかが40歳未満であることが要件です。
新築や買取再販で住宅を取得した場合には、住宅の種別によって500万円または1,000万円の住宅ローンの借入限度額が上乗せされます。借入限度額の目安は以下の表のとおりです。
| 認定住宅 | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 | ||
|---|---|---|---|---|
| 借入限度額 | 子育て世帯など | 5000万円 | 4500万円 | 4000万円 |
| それ以外 | 4500万円 | 3500万円 | 3000万円 | |
認定住宅とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅として証明された住宅のことです。また、ZEH水準省エネ住宅は、認定住宅以外でエネルギー使用の合理化に著しく資すると証明された住宅を指します。一方、省エネ基準適合住宅は、認定住宅とZEH水準省エネ住宅以外の、エネルギー使用の合理化に資すると証明された住宅です。
なお、ZEHとは「Net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)」の略称で、「ゼッチ」と読みます。住宅の断熱性能を大幅に高め、省エネ機器や太陽光発電装置などの導入により年間のエネルギー消費量の収支をゼロ以下にすることを目指した住宅のことです。住宅ローン減税には、政府が2050年までに温室効果ガスの排出をゼロにすることを目指す背景があります。
令和7年度税制改正「法人課税」

法人課税では、中小企業関連の改正が目立ちました。代表的なものとして、中小企業の法人税に関する軽減税率の特例の延長や、設備投資減税の拡充が挙げられます。
ほかにも、世界各地で発生している紛争や、アジア地域における地政学的リスクの高まりを背景に、防衛力強化に必要な財源を手当てするための「防衛特別法人税」が創設されました。
以下では、主なポイントを解説します。
中小企業者等の法人税率を17%へ引き上げ
中小企業に対する法人税率の軽減を17%に引き上げる措置が新設されました。
2008年のリーマン・ショックの際に導入された特例はそのまま延長されてきました。中小企業に対する法人税率の軽減は、本則が19%であるのに対し、特例では15%とされています。
15%の特例の期限は2年間延長されますが、所得が年10億円を超える「極めて所得が高い中小企業」に対して、その事業年度の税率を17%に引き上げる措置が新設されました。税率の引き上げではありますが、グループ通算制度の適用を受けている法人は対象外です。
なお、財務省は、17%の税率が対象となる中小企業は全体の0.1%程度と見積もっています。多くの中小企業には影響がないといえます。
中小企業経営強化税制の延長
「中小企業経営強化税制」が延長されました。中小企業や従業員1000人以下の個人事業主が対象の制度です。一定以上の投資収益率が見込める設備投資を行った場合に、投資額の10%の税額控除または即時償却のいずれかを選択できます。
また、資本金3000万円以上の企業は、税額控除率が7%に抑制されます。2027年3月末までに取得した設備が対象です。対象の物品と投資額などの例は、以下のとおりです。
- 機械、設備 1台160万円以上
- 測定工具、検査工具 1台120万円以上、1台30万円以上で合計120万円以上
- ソフトウェア 1本70万円以上、複数合計で70万円以上
- 貨物自動車 重量3.5トン以上
防衛特別法人税の創設
創設された防衛特別法人税は、法人税、所得税、たばこ税の増税によって不足が見込まれる約1兆円の財源を手当てする方針に沿うものです。
2026年4月1日以後に開始する事業年度から、企業の利益に4%の法人税を上乗せするもので、全額が防衛力整備に充当される予定です。所得に法人税を課されている企業は、防衛特別法人税の納税義務者となります。
なお、企業側は新たに、防衛特別法人税確定申告書の提出が必要です。税額がゼロでも申告は必要となるため、対応を忘れないようにしてください。
令和7年度税制改正「資産課税」

資産課税に対して、事業承継税制の特例措置の見直しや、結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置の延長などが行われました。詳細は以下のとおりです。
事業承継税制の特例措置の見直し
事業承継税制は、非上場企業の株式を贈与、相続した場合に、贈与税や相続税の納税を猶予する制度です。特例措置として、猶予割合が100%になります。
これまで特例措置の適用を受けるためには、株式贈与日に後継者が役員に就任してから3年以上経過していることが要件でした。この要件が事実上撤廃され、贈与の直前に役員になっていればよいことになりました。
経営環境の急激な変化に対応し、迅速で円滑な事業承継を促すことが改正の目的です。
参考:経済産業省「令和7年度(2025年度)経済産業関係 税制改正について」
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の延長
結婚や子育ての資金を祖父母や両親から一括で贈与された場合に、贈与税を非課税とする制度はすでに創設されていましたが、今回の改正では適用期限が2027年3月末まで2年間延長されます。
結婚は300万円、子育てでは1,000万円が非課税の範囲です。なお、適用を受けるためには、以下のような条件があります。
- 受贈者は18歳以上50歳未満の子、孫
- 贈与者は祖父母や両親
- 贈与者は受贈者名義の金融機関の口座に資金を一括して拠出
- 子や孫が50歳に達する日に口座は終了し、使い残しがあれば贈与税を課税
結婚・子育て資金にあたるものの例は、以下のとおりです。
- 挙式や結婚式会場の費用
- 結婚を機に移り住む住居にかかる家賃や敷金、礼金など
- 結婚を機に移り住むための引越し費用
- 人工授精など不妊治療にかかる費用
- 出産に必要な費用
- 保育園や幼稚園、ベビーシッターなどへの支払い
資金の使用に対して、金融機関による領収書のチェックを受けることと、書類の保管が定められています。
参考:子ども家庭庁「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について」
令和7年度税制改正「電子帳簿等保存制度」

税制改正に盛り込まれた「電子帳簿等保存制度」は、企業にとって重要な制度です。一定の要件を満たしたシステムで送受信や保存された電子取引データには、隠蔽・改ざん行為に対して生じる10%の重加算税を除外します。
適用を受けるためには、国税庁長官が定める基準に適合した以下のようなシステムを活用する必要があります。
- データの送受信と保存を訂正・削除できないシステムや、訂正・削除履歴が残るシステムで行う
- 金額の訂正・削除を行った電子取引データを電子帳簿に記録できない、または訂正・削除の事実が確認できる
- 電子取引データと電子帳簿との関連性を相互に確認できる
システムを導入すれば、人手での入力作業が不要になり、事務負担の軽減が可能です。また、データの削除や訂正ができないことで、税務調査で問題点を指摘されるリスクの低減に期待できます。
参考:国税庁「請求書等を帳簿に⾃動連携する仕組みに対応した制度が新設されました」
令和7年分の年末調整における注意点

令和7年(2025年)の税制改正の範囲は広く、年末調整の実務を担当する企業の担当者は細心の注意が必要です。以下で、年末調整における注意点を解説します。
新たに扶養控除等の対象となった親族等の確認
今回の税制改正を受けて、新たに扶養控除の対象となった親族を持つ従業員がいる可能性があります。そのような事例がないかどうかを確認し、ある場合は「扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けてください。
徴税事務を着実に進めるために、従業員に対する注意喚起が重要です。
特定親族特別控除の適用の有無の確認
大学生年代の子を持つ従業員は、子が特定親族特別控除の適用対象となる可能性があるため、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出が必要です。
従業員への周知を行うことをおすすめします。
基礎控除額・給与所得控除額の確認
今回の税制改正では、基礎控除や給与所得控除が見直されています。2025年11月までの給与にかかる源泉徴収事務は、これまでと同様です。基礎控除、給与所得控除の見直しにともなう調整は、12月の年末調整時に行います。
年末調整時の事務作業では、基礎控除、給与所得控除の額が改正内容に沿って正しく計算されているかを確認したり、11月分までの精算が誤りなく行われているかどうか確認したりすることが必要です。以下に、具体的な注意点を示します。
- 従業員が提出した「給与所得者の基礎控除申告書」が正しく記載されていることを確認
- 従業員の配偶者に収入がある場合、配偶者(特別)控除額が正しく記載されていることを確認
- 年末調整の計算をする際には、改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を使用
令和8年分以降の源泉徴収に関する注意点

令和8年(2026年)分以降の源泉徴収に対しても注意が必要です。「源泉控除対象親族」にかかわるものなど、主な項目を以下に示しました。
「源泉控除対象親族」の記載の確認
税制改正による特定親族特別控除の創設にともない、令和8年(2026年)分以降の扶養控除等申告書には「源泉控除対象親族」を記載しなければなりません。源泉控除対象親族とは、以下の人のことです。
- 控除対象扶養親族(配偶者以外で従業員本人に扶養されている16歳以上の親族)
- 従業員本人と生計を一にする親族のうち、19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超100万円以下の人
源泉控除対象親族の記載に漏れがないよう、従業員に注意喚起してください。
新たな源泉徴収税額表に基づいた業務の実施
毎月の給与から天引きされる源泉徴収税の金額は、「源泉徴収税額表」を基準に決定されますが、扶養親族などの数によっても異なります。
扶養親族などの数は、令和7年(2025年)までは、「源泉控除対象配偶者」及び「控除対象扶養親族」が計算のベースでした。令和8年(2026年)からは、「源泉控除対象配偶者」と「源泉控除対象親族」を基に計算されます。申告書の様式も変更されます。
なお、2026年は「令和8年分」の税額表を用いて源泉徴収税額を求めなければならない点に注意が必要です。
人事管理システム「ADPS(アドプス)」なら年末調整業務がよりスムーズに

カシオヒューマンシステムズ株式会社が提供する人事管理システム「ADPS(アドプス)」を活用すれば、煩雑で確認事項も多い年末調整業務をスムーズに処理できます。年末調整をデジタル化することで、従業員も総務・人事部門の担当者にかかる負荷の軽減が可能です。
ADPSは1990年の誕生以来、累計で5000社を超える導入実績を持っています。年末調整業務だけでなく、給与明細の作成や勤怠管理、センシティブな人事情報の蓄積と検索など、搭載されている機能は多彩です。
まとめ

令和7年(2025年)の税制改正では、「103万円の壁」の引き上げや子育て世帯への住宅ローン減税延長など、多岐にわたる見直しが行われました。基礎控除の底上げや特定親族特別控除の新設は、企業側の源泉徴収業務にも影響を及ぼします。
給与計算や源泉徴収を正しく行うためには、人事管理システムの導入が一つの策です。総務・人事部門の担当者の負荷軽減につながり、生産性の向上にも期待できます。複雑な税制を着実にフォローするためにも、人事管理システムの導入を検討してはいかがでしょうか。
カシオヒューマンシステムズコラム編集チームです。
人事業務に関するソリューションを長年ご提供してきた知見を踏まえ、
定期的に「人事部の皆様に必ず今後の業務に役立つ情報」を紹介しています。