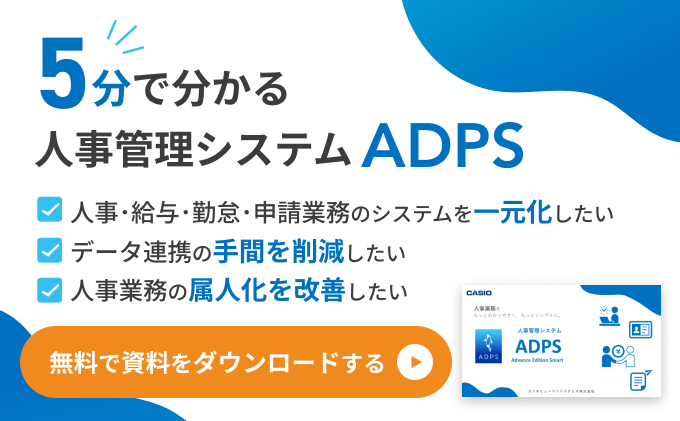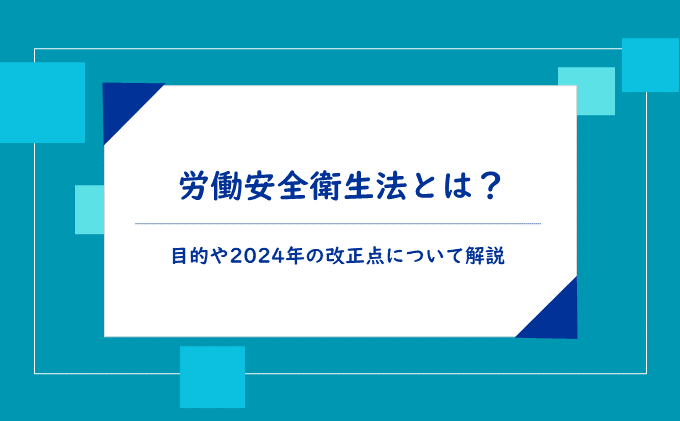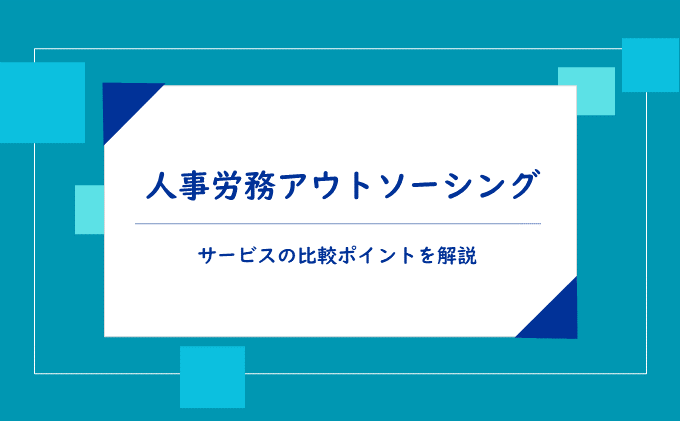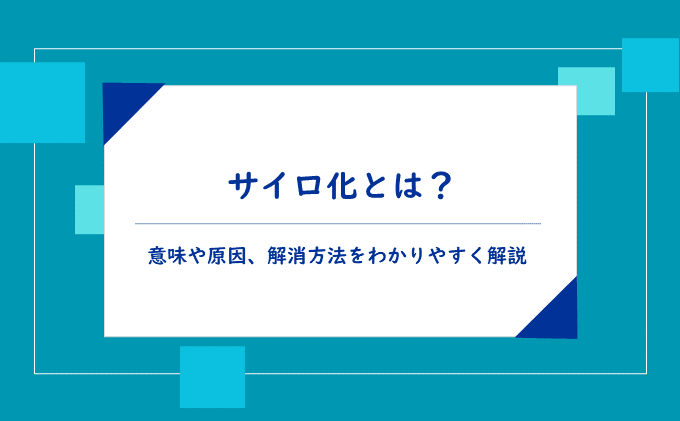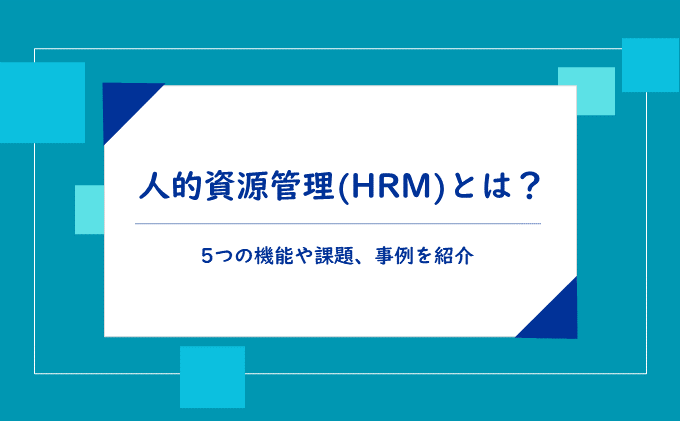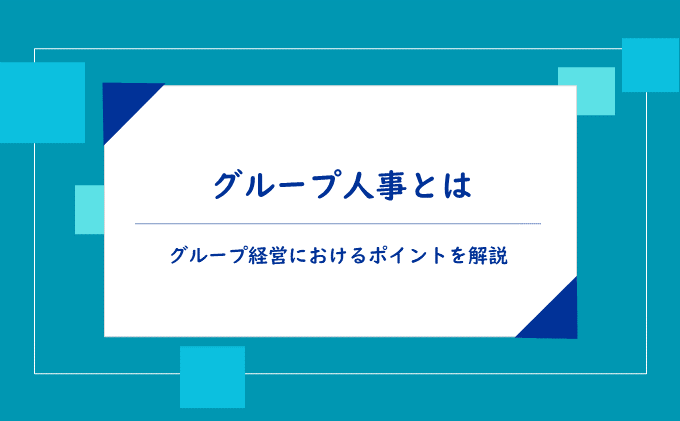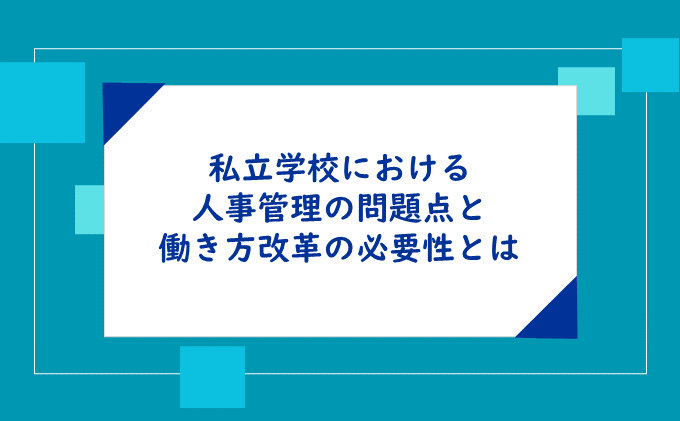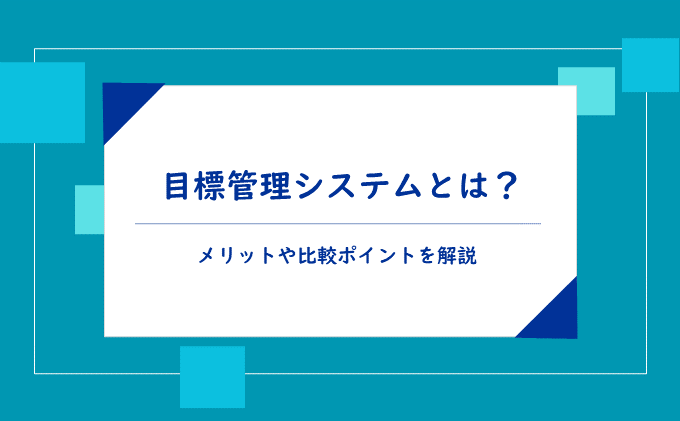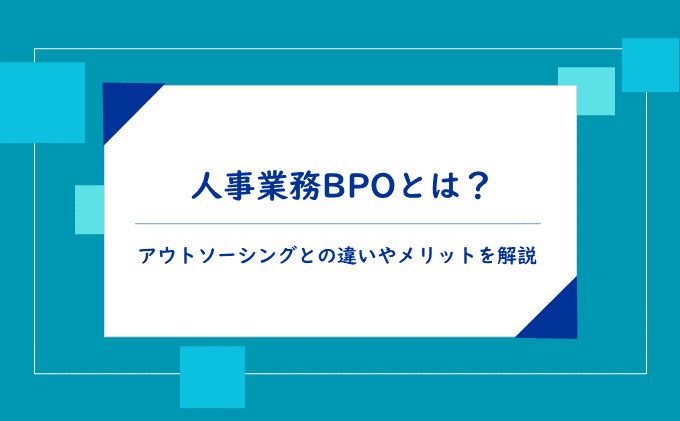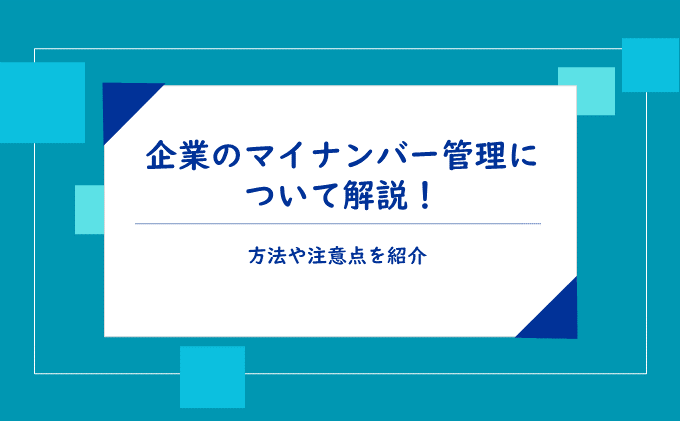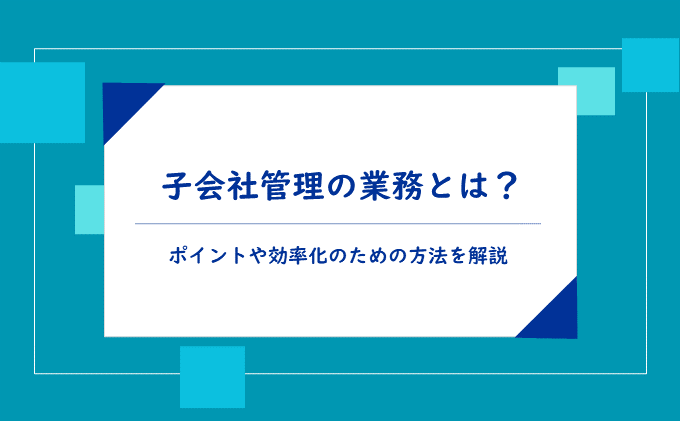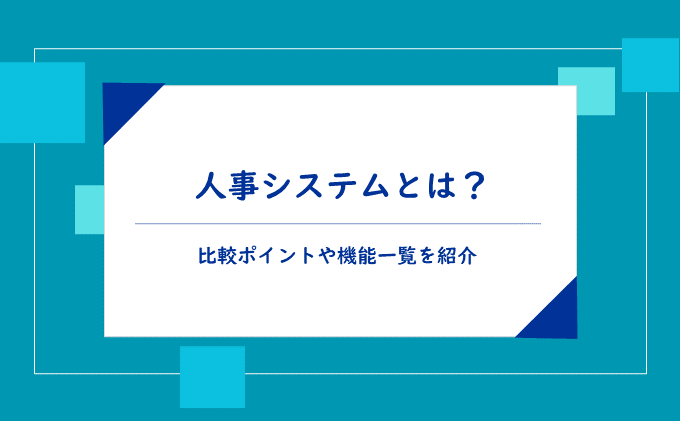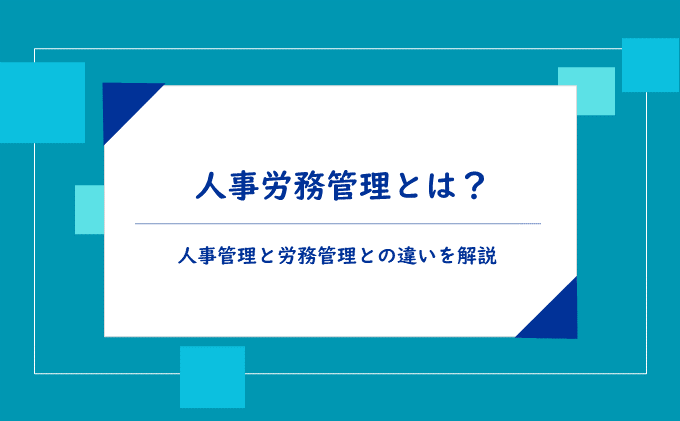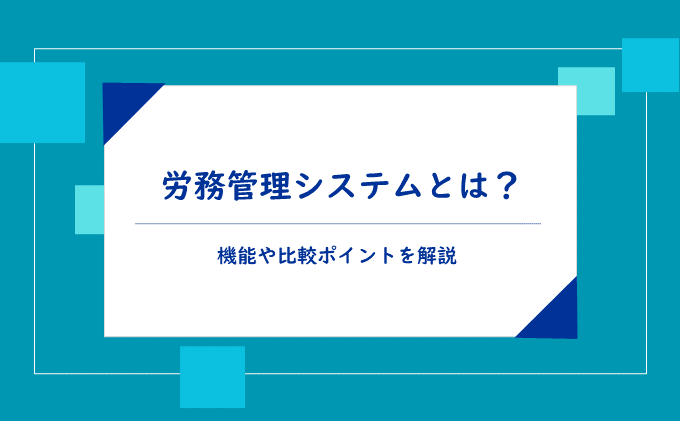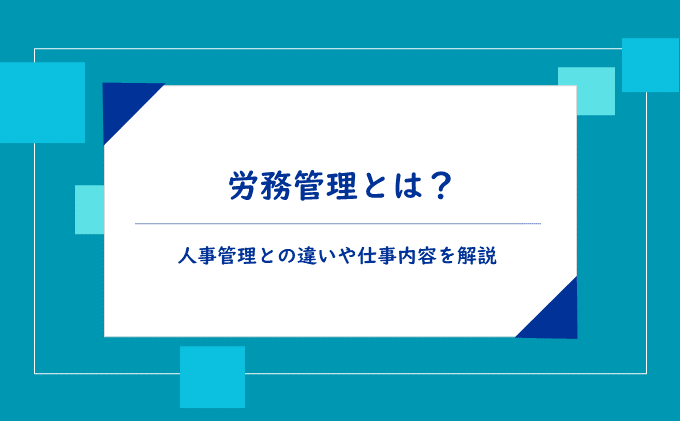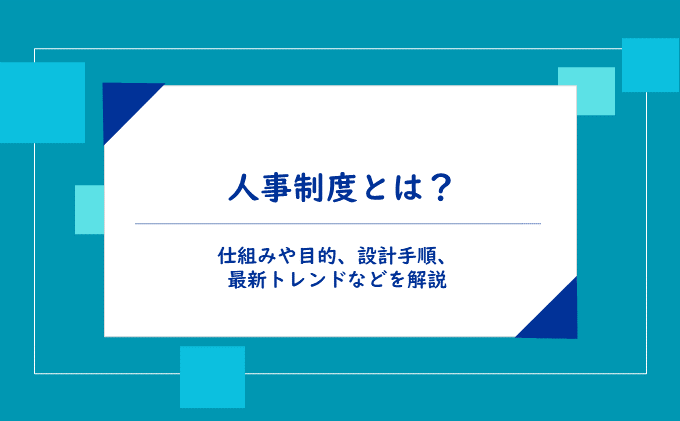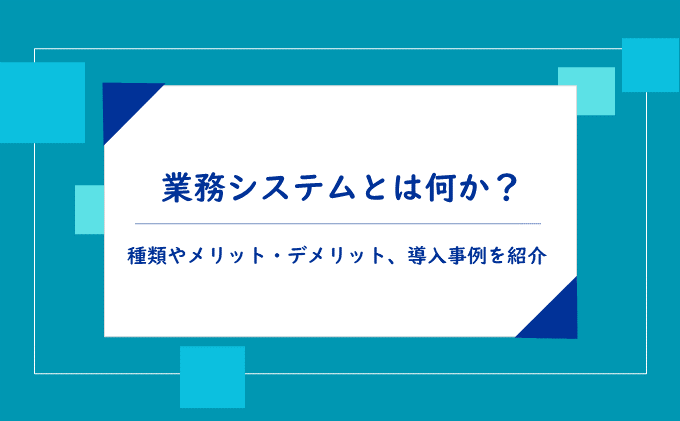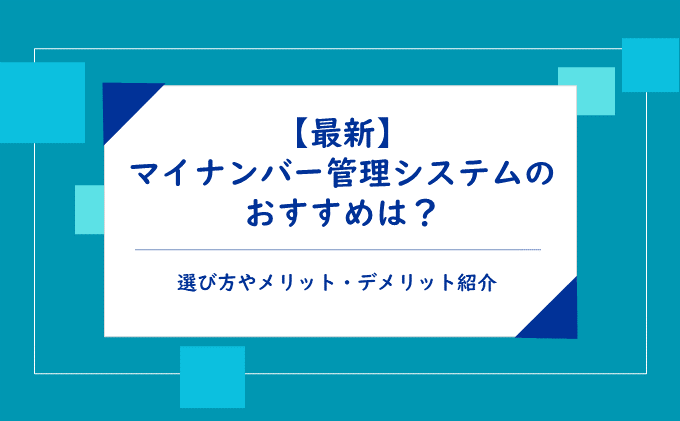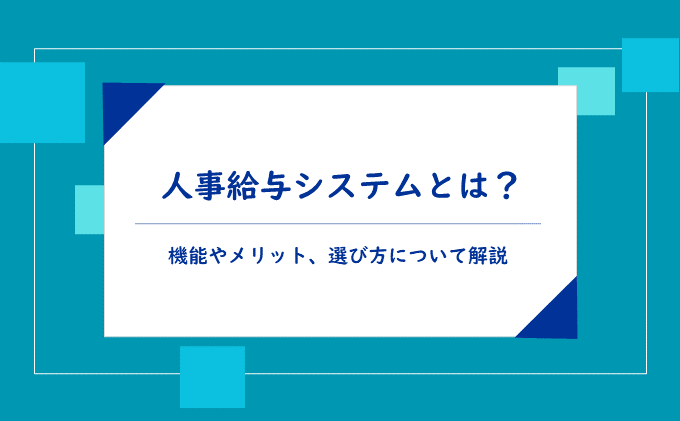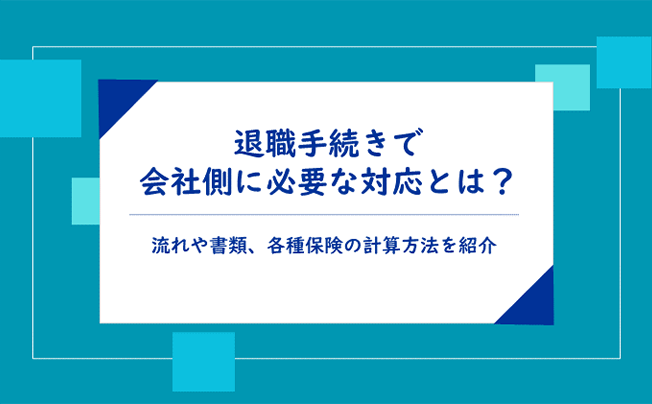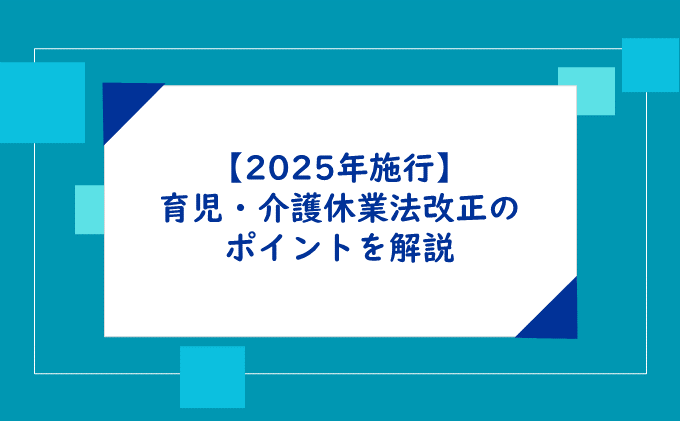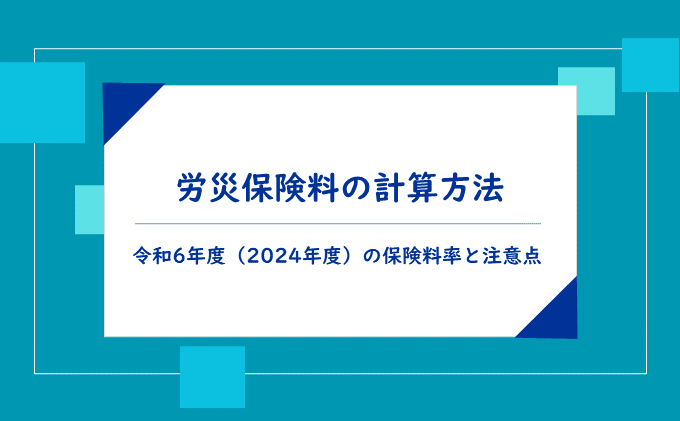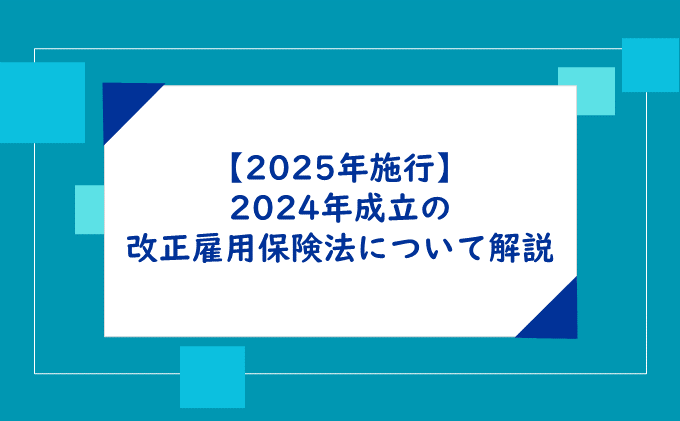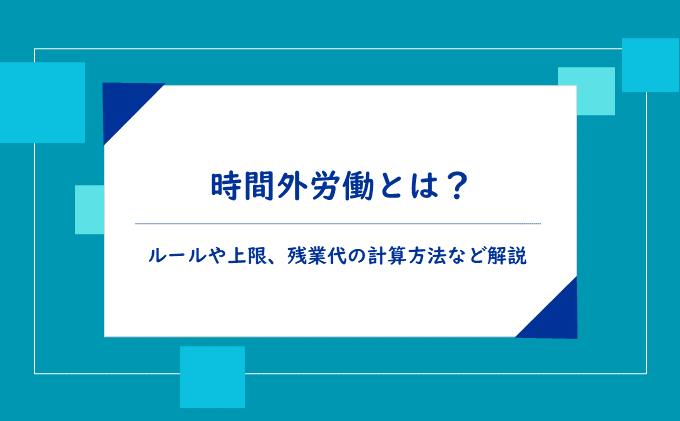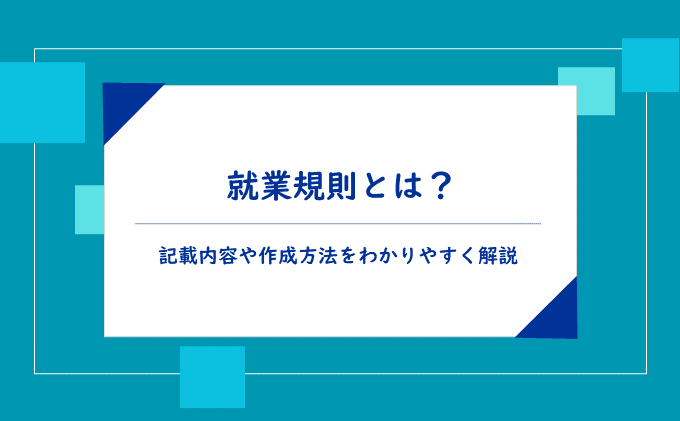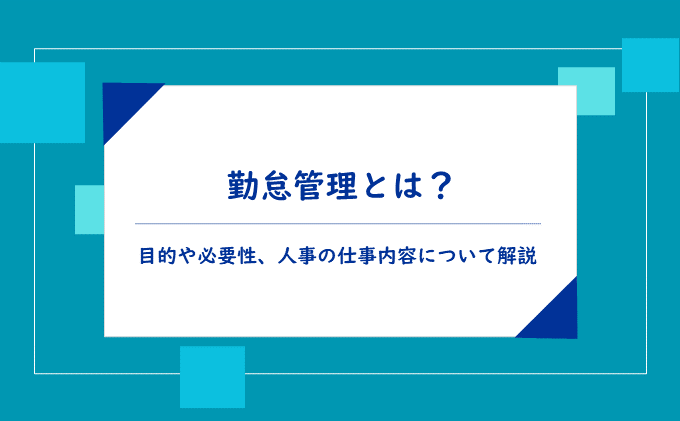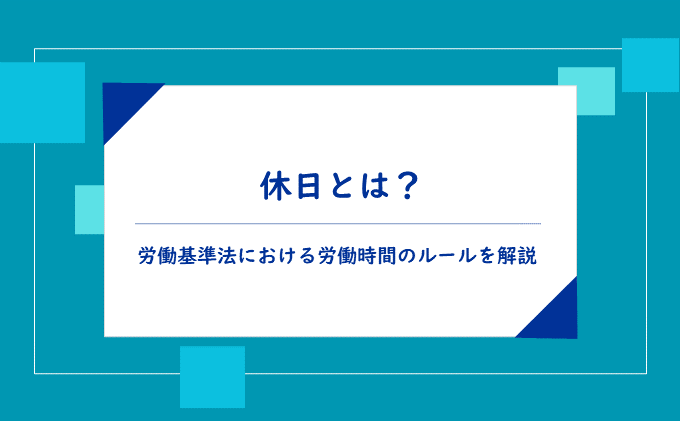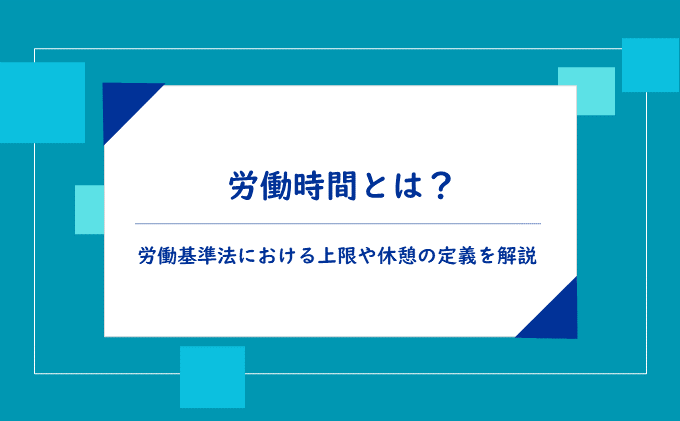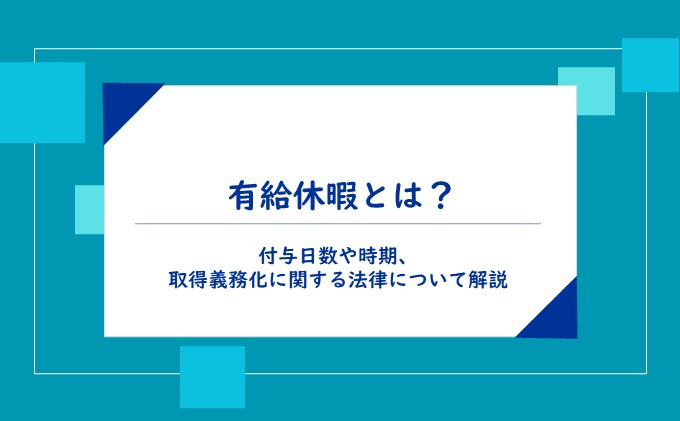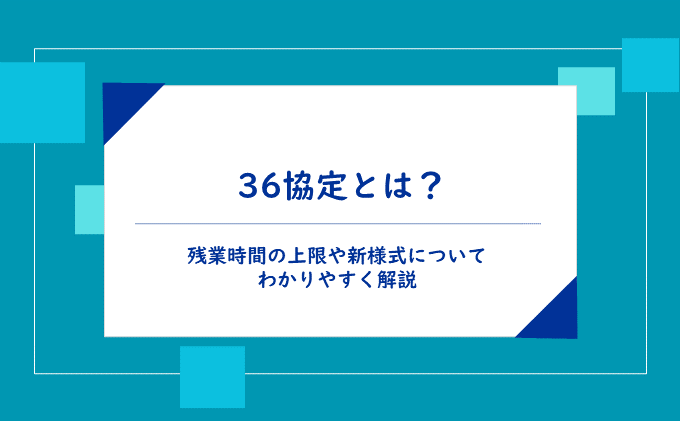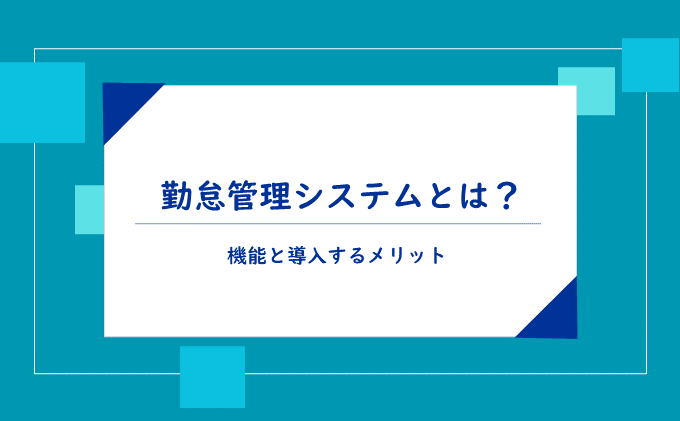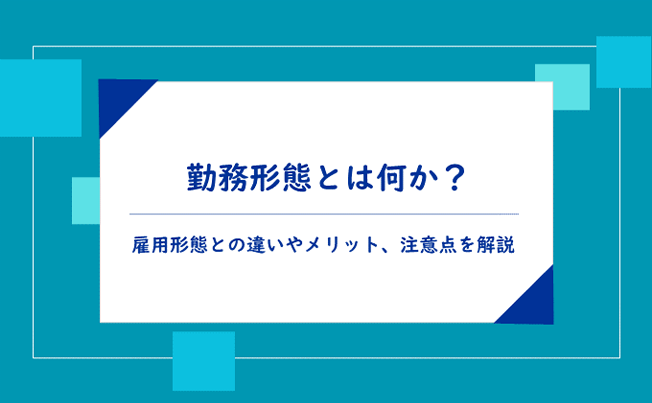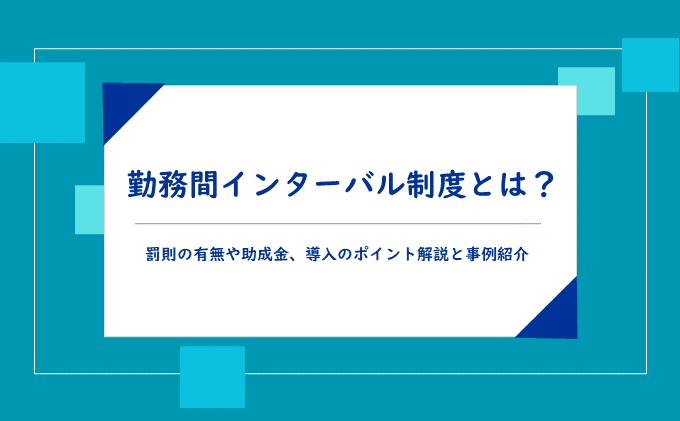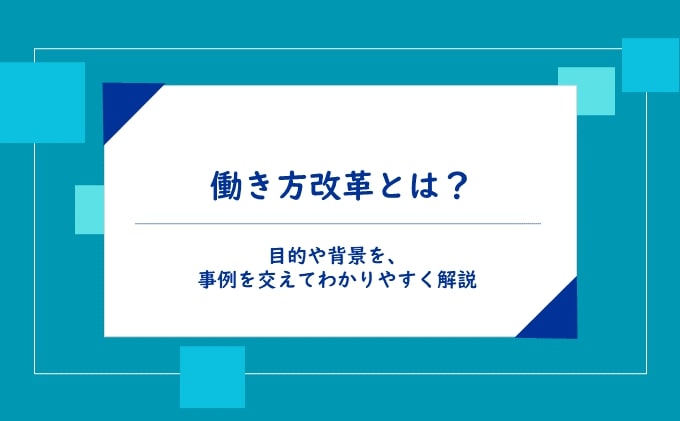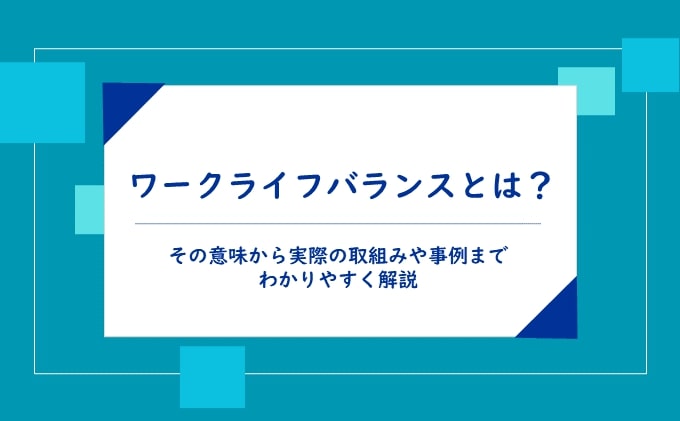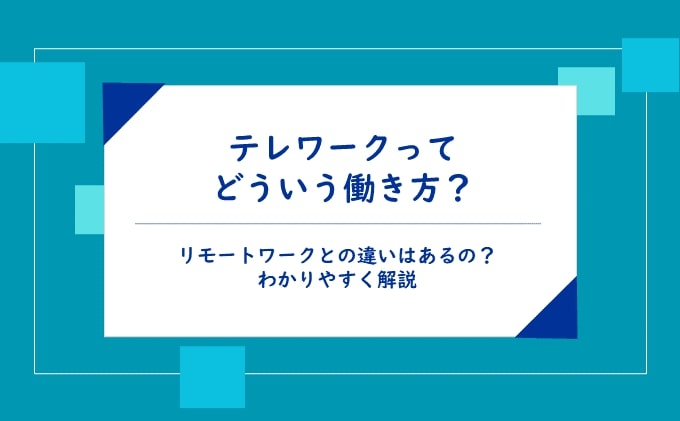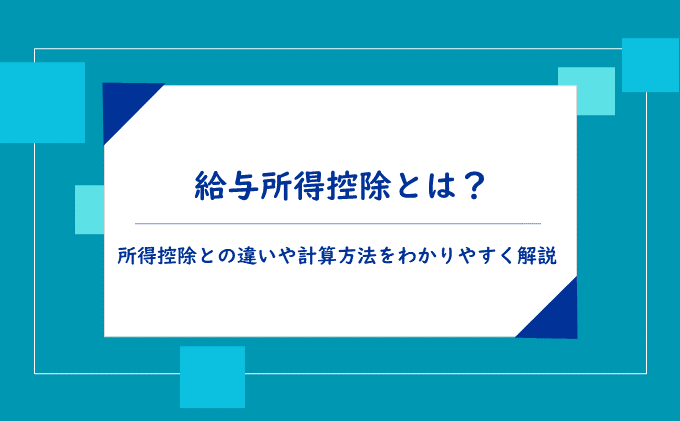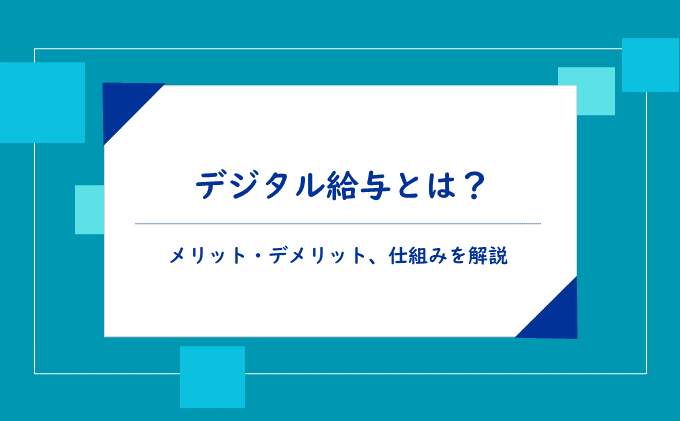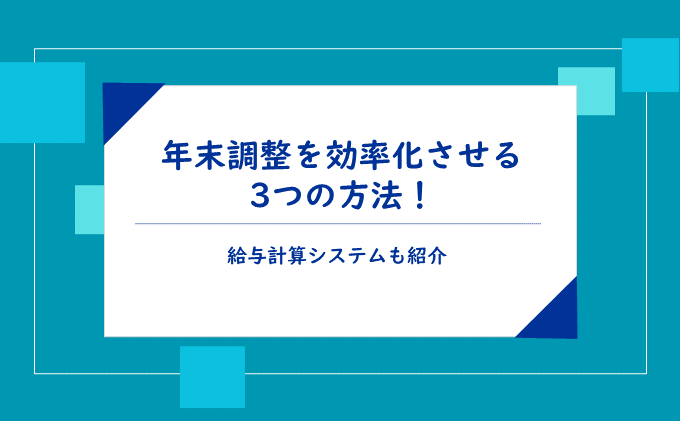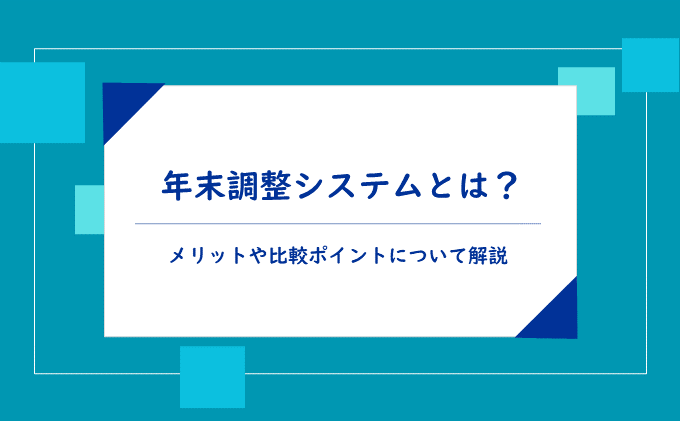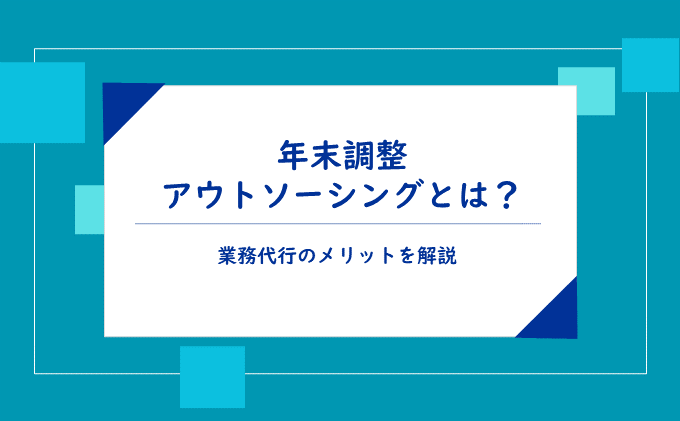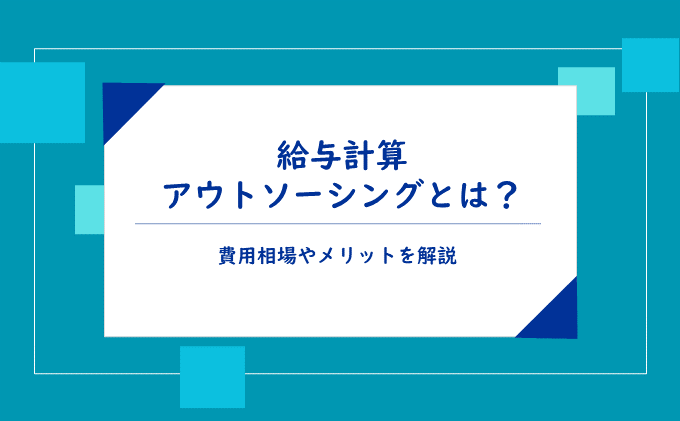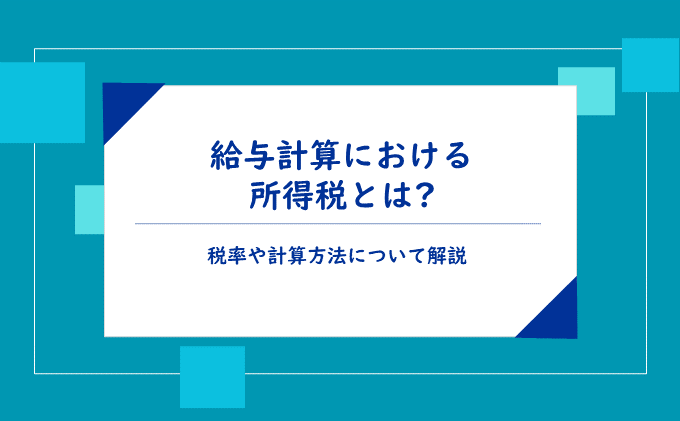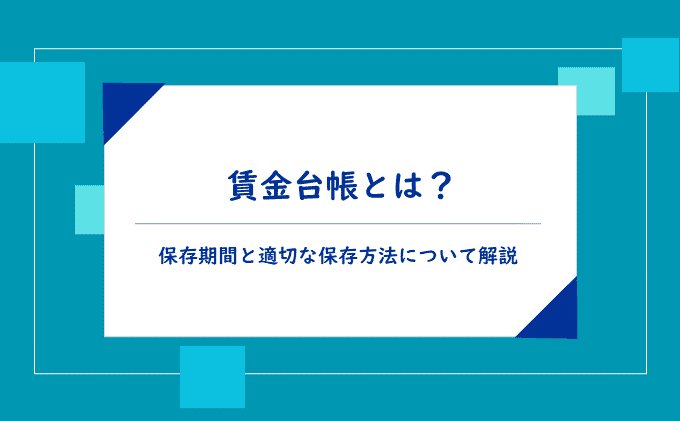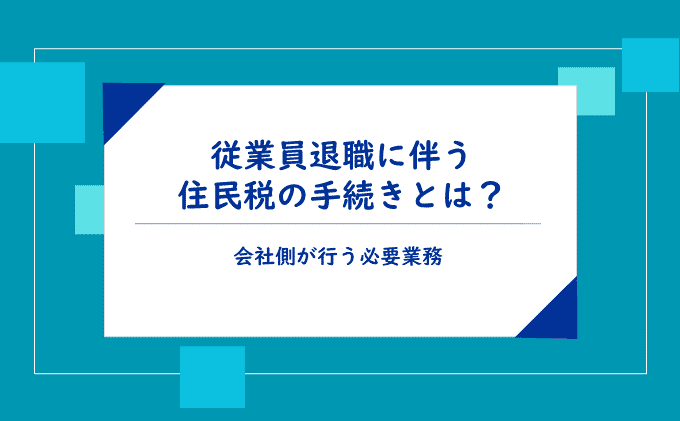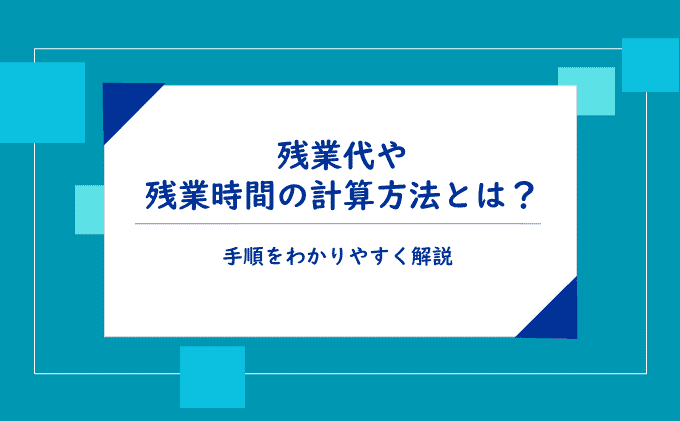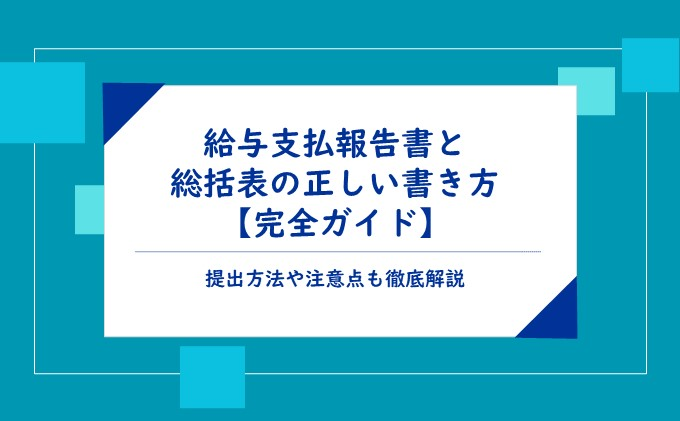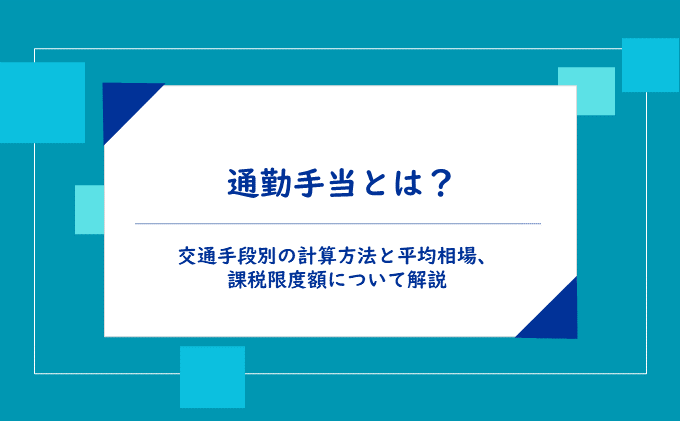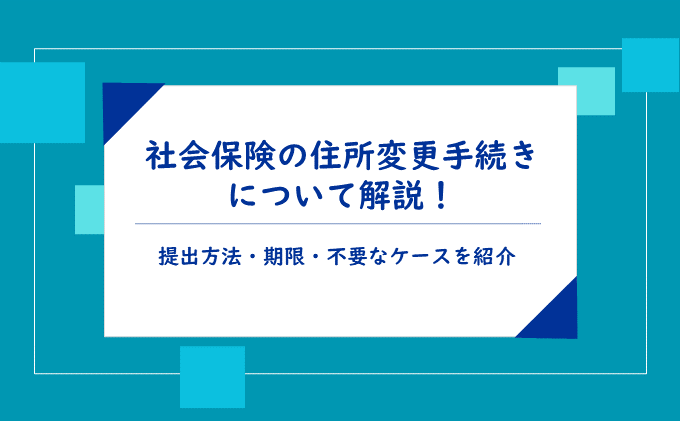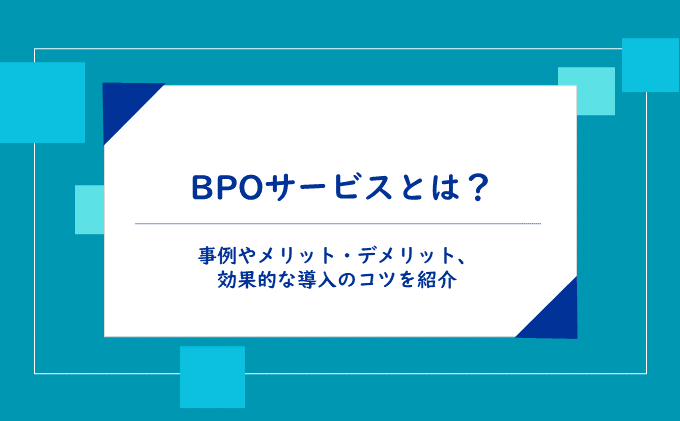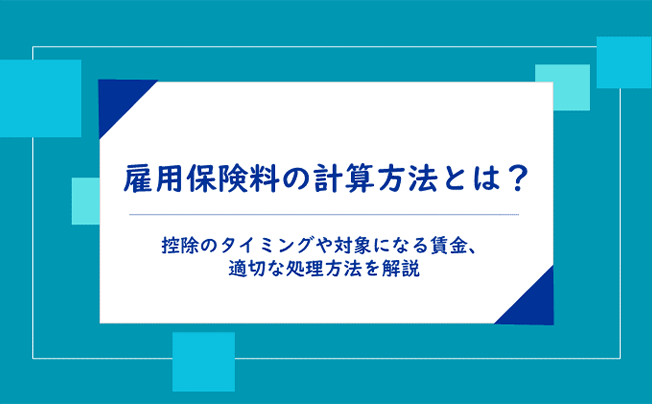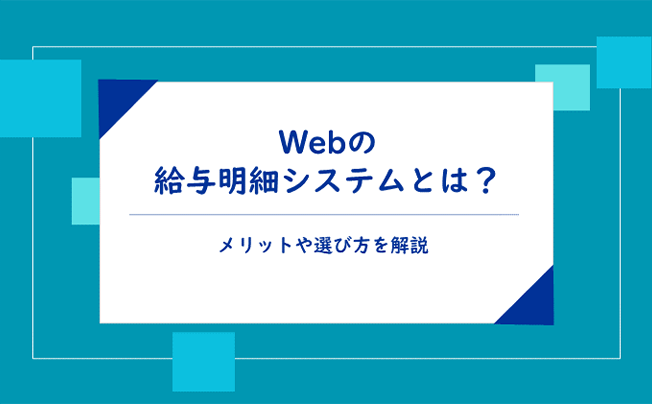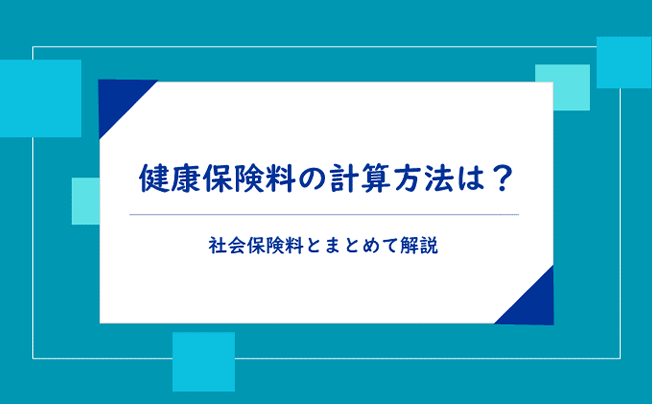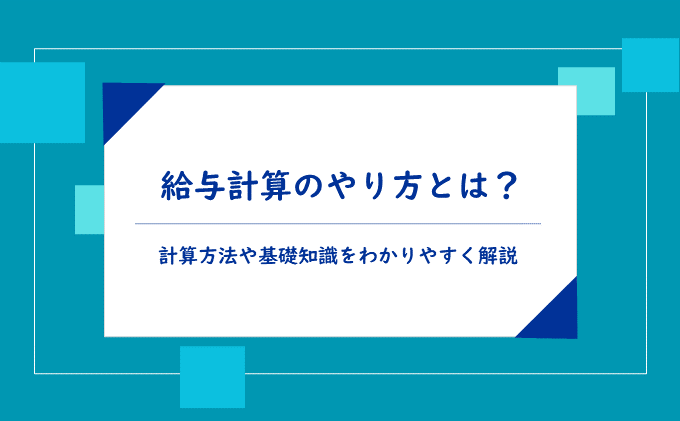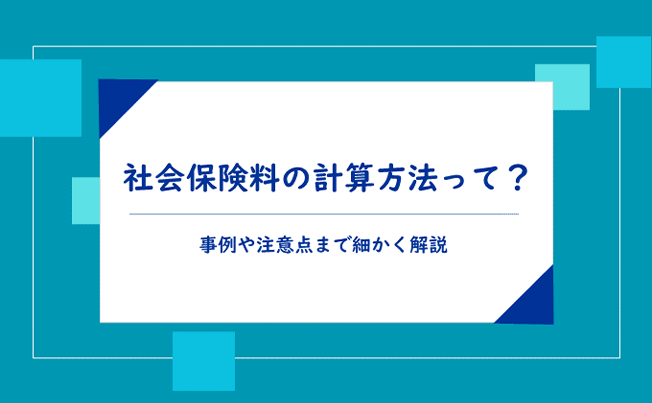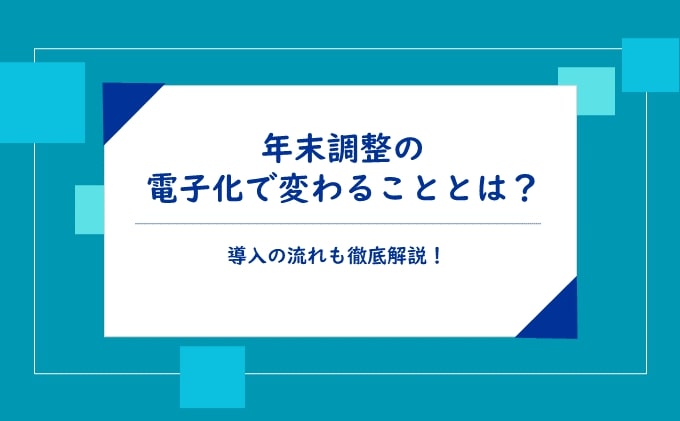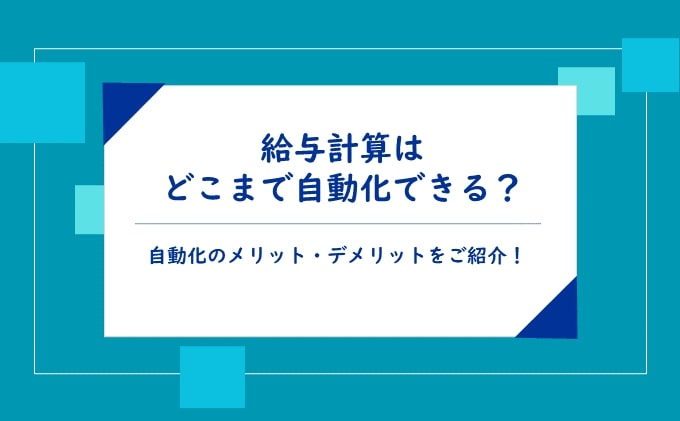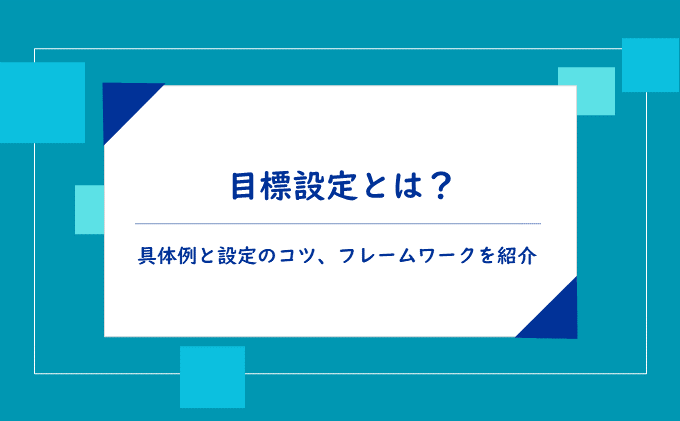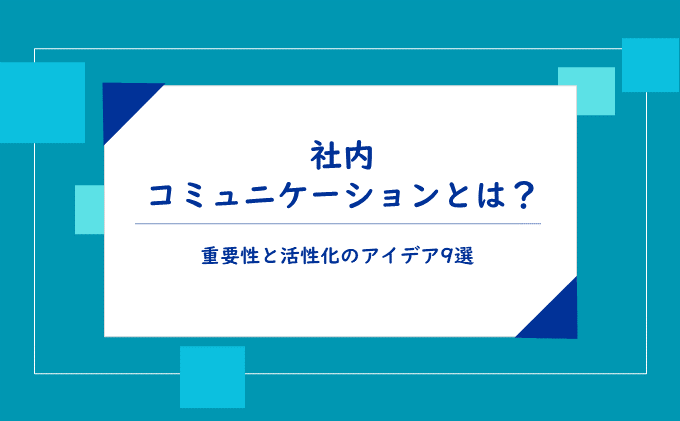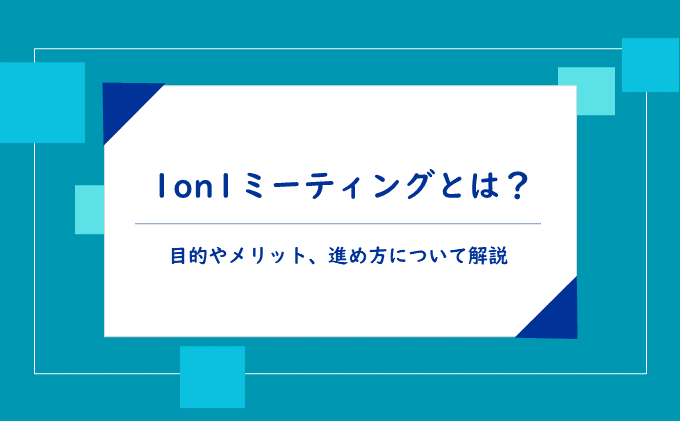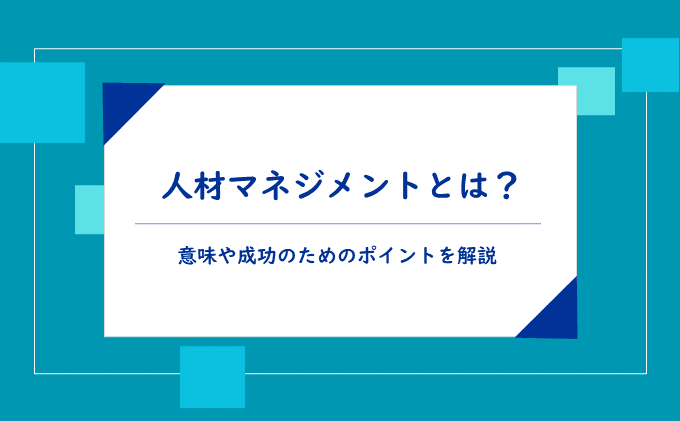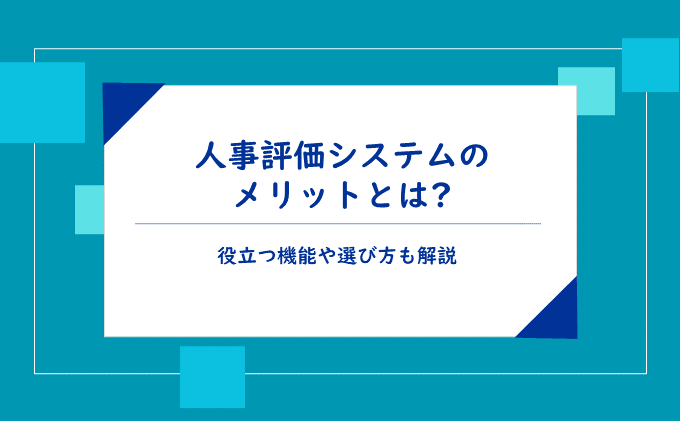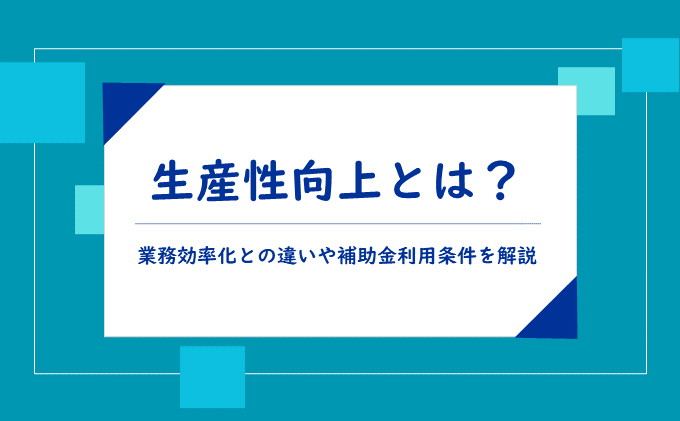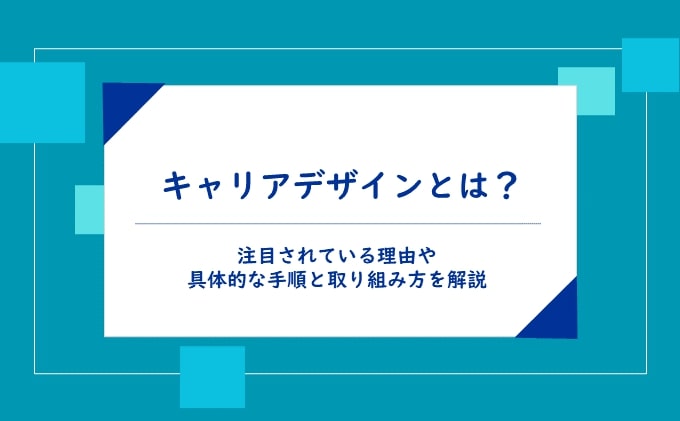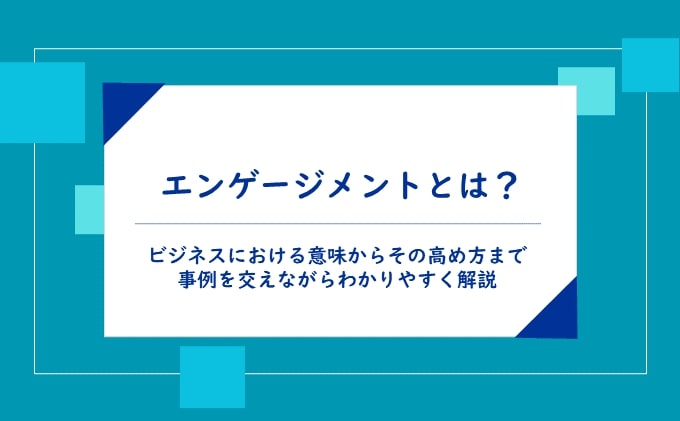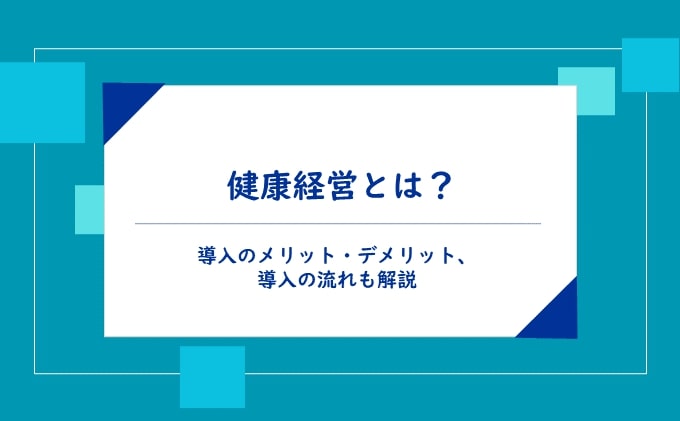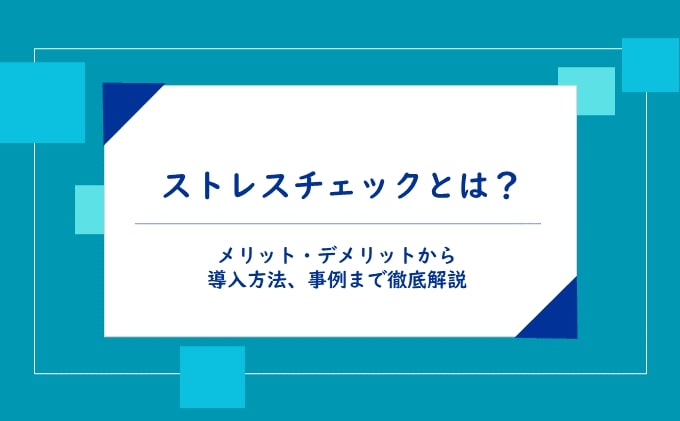こども未来戦略とは│背景や加速化プランの内容について解説
2025.09.22
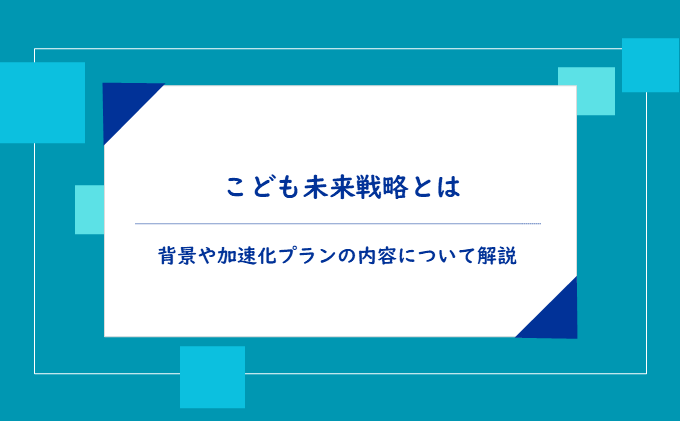
少子化対策として国が掲げた「こども未来戦略」および「加速化プラン」では、すべての子どもと子育て世帯を切れ目なく支援する体制づくりが進められています。本記事では、具体的な支援内容とその狙いをわかりやすく解説します。
目次
「こども未来戦略」とは?決定の背景

政府が2023年12月に発表した「こども未来戦略」は、若年層や子育て世代が直面する不安を解消する目的で制定された政策です。若い世代が希望通りに結婚し、安心して子育てを行える社会を目指すために、総額3.6兆円もの予算が組まれています。
「こども未来戦略」が組まれた背景には、深刻な少子化問題による人口減少があげられます。厚生労働省の統計によると、2024年の出生数は68万6,061人となっており、1899年の統計開始以来、過去最低を記録しました。
一方、2024年の死亡数は160万5,298人と出生数の2倍以上多く、昭和50年代後半から増加傾向が続いています。出生数を大きく上回る死亡数がこのまま続けば、日本の人口は2060年には9,000万人を割り込み、高齢化は40%に近い水準になるとも言われています。
現在の日本の人口は約1億2,500万人であるため、わずか半世紀で国の規模が3分の2近くまで縮小される計算です。子どもが減る現象は単なる家庭の問題にとどまらず、経済や社会保障、地域社会の存続にまで波及する深刻な国家課題です。
人口減少による危機的な状況を受けて政府は、「2030年代に入るまでを少子化傾向を反転できるかのラストチャンス」と位置づけ、「こども未来戦略」を策定しています。
参考:厚生労働省「令和6年(2024)人口動態統計月報年計(概数)の概況」
こども未来戦略における基本理念

こども未来戦略は、単なる出生数の増加を目指すものではありません。若い世代の経済的安定を後押しし、子育てがしやすい社会環境を整えることを全体の方向性としています。ここでは、その中核となる3つの理念について解説します。
理念1.若者・子育て世代の所得を増やす
「こども未来戦略」の基本理念としてまずあげられるのは、若者や子育て世代の所得を増やすことです。公益財団法人 日本財団が2024年に行った調査によると、子どもを持ちたくない理由として「経済的な負担が大きい」が全体の42.8%と最も多く占めています。
就職や結婚、出産や育児といったライフイベントが重なる時期を経済的不安なく過ごすためにも、「こども未来戦略」では若い世代の所得を増やすための施策を打ち出しています。
例えば、成長分野の投資や人材流入の促進、物価の上昇を賃金に反映させる仕組みづくりが進行中です。また、「同一労働同一賃金」の徹底や非正規雇用の方々の正規化など、雇用の安定と質向上の取り組みも行われています。
さらに注目されるのが、「雇用保険の適用拡大」や「年収の壁」への対策です。雇用保険の拡大では、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の従業員にも雇用保険を適用するための法整備が進められており、短時間労働者も安心して働ける環境づくりを目指しています。
年収の壁に対しては繁忙期などで収入が一時的に上がっても、事業主がその旨を証明できれば引き続き扶養に入れるといった「年収の壁・支援強化パッケージ」を提供しています。
参考:公益財団法人 日本財団「少子化に関する意識調査 報告書」
参考:厚生労働省「こども未来戦略(令和5年12月22日閣議決定)(抜粋①)」
理念2.社会全体の構造・意識を変える
「こども未来戦略」では、社会全体の構造や意識を変えることも理念として掲げられています。「育児は母親が担うもの」「男性が長時間働くのが当然」という、時代に即さない性別役割意識が若い世代の出産や子育てを妨げていると考えられるためです。
例えば、育児が女性に偏りがちな「ワンオペ育児」を是正するために、男性育休取得率の向上やテレワークの導入など夫婦で協力して子育てできる体制づくりが進められています。企業においては、出産・育児支援を「コスト」ではなく「未来への投資」として捉えるよう求め、男性も女性も気兼ねなく育児休業を取得できる職場文化の構築を呼びかけています。
また、働き方改革による長時間労働の是正も重要です。長時間労働を是正することで、子育て世代が育児や家事に充てる時間を十分に確保できるだけでなく、企業の生産性向上や延長保育ニーズの減少など、コストの抑制効果も期待できます。
理念3.すべてのこども・子育て世帯を切れ目なく支援する
「こども未来戦略」の3つ目の理念は、すべての子どもや子育て世帯をライフステージの切れ目なく支援することです。
これまで政府は、保育所の整備や幼児教育・保育の無償化といった施策を通じて子育て支援を強化してきました。しかし近年、社会経済の変化や家族のあり方の多様化により、従来の枠組みでは対応しきれない課題が浮き彫りになっています。
例えば、今まで手薄であった0~2歳児や妊娠期への支援強化やヤングケアラー、ひとり親世帯など、特別な支援を要する子どもにも柔軟に対応する体制づくりが不可欠です。
また、申請を待つのではなく、行政が必要な家庭に積極的にアプローチする「伴走型・プッシュ型支援」への移行や、DXの活用による手続きの簡素化も重視されます。
事実、東京都のデジタルサービス局ではスマホアプリから、子育てや給付金といった必要な情報が先回りで届く仕組みが作られています。自治体側がプッシュ型で情報提供を行うことで、知りそびれや申し込みそびれ、貰いそびれの防止が可能です。
「こども未来戦略」では、デジタル機器の活用などを行って、すべての子どもや子育て世代に切れ目ない支援が行き届くことを目指しています。
こども未来戦略・加速化プラン(妊娠~子育て)

こども未来戦略は2024年からさらなる拡充を目指して加速化プランを提供しています。なかでも妊娠や子育てに関する支援は大きな変容を見せていると言っても過言ではありません。ここでは、こども未来戦略の妊娠や子育てに関する制度拡充や新制度の設立を解説します。
妊婦のための給付・伴走型相談支援の制度化
妊娠や子育て領域におけるこども未来戦略では、妊娠から出産後まで期間に次のような支援を受けられる制度が新設されました。
- 妊婦のための支援給付
- 妊婦等包括相談支援事業
妊婦のための支援給付では妊娠を届け出ることで、届出時に5万円、さらに妊娠後期以降では妊娠している子どもの人数に応じて5万円を給付する仕組みです。例えば、双子を妊娠している場合は、妊娠時の5万円に追加して妊娠後期に10万円が支給されるため、妊娠期間の経済的な負担を軽減できます。
さらに、経済的支援と並行して、妊婦等包括相談支援事業と呼ばれる伴走型の相談支援が全国的に導入されました。妊婦等包括相談支援事業は、妊婦やその配偶者に対して面談を実施して、妊娠や出産、育児に関する悩みを継続的にフォローする仕組みです。
妊婦のための支援給付や相談事業は、妊娠や子育ての経済的な不安感の解消だけでなく、妊婦の孤立や不安感を未然に防ぐうえでも役立ちます。
「こども誰でも通園制度」の制度化
こども未来戦略・加速化プランでは、「こども誰でも通園制度」が2025年度から始まります。本制度は親の就労状況に関わらず、すべての子どもが保育サービスを柔軟に利用できる新たな仕組みとして位置づけられており、2026年度からは全国の自治体で本格実施される予定です。
導入の背景にはこれまでの保育制度が就労要件に基づいていたため、育児の負担が大きくても制度の支援を受けにくい家庭が一定数存在していたという課題があります。育児疲れや孤立を感じる保護者にとって、保育の利用が就労条件で制限されるのは大きなハードルでした。
本制度では就労していない保護者の子どもにおいても、月10時間までの枠内で保育園の一時利用が可能です。時間単位で利用が可能なうえ、スマホで簡単に申請ができるため、急な通院や休息などの時間を確保したい家庭にとって大きな助けとなります。
「産後ケア事業」の拡大
こども未来戦略・加速化プランでは、出産後の母子を支える産後ケア事業の拡充が明確に打ち出されています。産後ケア事業が拡充された背景には、出産直後の母親が抱える身体的疲労や精神的な不安、そして育児の孤立といった課題があります。
産後うつや、十分な支援を得られずに悩みを抱え込んでしまうケースも少なくなく、早期にケアの手を差し伸べる体制が急務となっていました。本制度では出産後の母子に対して心身のケアを行うことを目的に、以下3つの形態で支援が実施されます。
- 宿泊型:病院や助産院に宿泊して休養の機会を得る
- デイサービス型:個別や集団で支援を受けられる施設に来所する
- アウトリーチ型:担当者が自宅に赴き支援を実施する
上記のように状況に応じたさまざまな形で産後の母親が休養を取ることが可能です。とくに実家などからのサポートが得にくい核家族やひとり親家庭にとっては、心身を休められる心強い存在といえます。
「保育士の配置基準」の見直し
こども未来戦略では、児童に対する保育士の配置ルールが約76年ぶりに変更されました。具体的には4・5歳児のクラスで、従来は子ども30人に対して保育士1人だったものが、25人に対して1人に改められています。また、2025年からは、6人につき1人の配置が求められていた基準も5人に対して1人に変更される予定です。
保育士の配置基準を変更する理由は、「一人の保育士にかかる負担が重すぎる」「子どもに十分な目配りができない」といった現場の課題に対応するためです。保育士の現場では、長時間勤務や事故のリスク軽減の観点からも、適正な人員配置が求められてきました。
今回の見直しによって保育環境の改善が進み、子どもたちへのより丁寧な関わりが可能になると期待されます。保育を「量」から「質」に転換を掲げるこども未来戦略において、非常に重要な取り組みです。
「出生後休業支援給付」の創設
こども未来戦略・加速化プランでは、2025年4月から「出生後休業支援給付金」が導入されます。出生後休業支援給付金は出生直後に両親ともが計14日以上の育児休業を取得した場合に、最大28日間の追加支給を受けられる制度です。
支給額は既存の育児休業給付金や出生時育児休業給付金と併せて、休業開始時の賃金の日給 × 支給日数(上限28日) × 13%相当分が支給されます。つまり、休業開始時賃金日額が仮に10,000円で14日間育休を取った場合、約18,200円が支給され、休業給付と併用して実質的に手取りがほぼ維持される仕組みです。
出生後休業支援給付が創設されることにより、育児休業中の収入源がほぼ解消されることで、共働き家庭での育休取得への心理的・経済的ハードルを大きく下げられます。
「育児時短就業給付」の創設
こども未来戦略・加速化プランにおいては、2025年4月から「育児時短就業給付」が新設され、子育て中の働き方を後押しする新たな支援制度がスタートしました。
育児時短就業給付とは、2歳未満の子どもを育てながら時短勤務を選択している雇用保険の被保険者に対し、勤務中の給与額の10%相当が国から給付される制度です。
例えば、育児休業前に月収30万円だった方が時短勤務によって月収が20万円になった場合、10%にあたる2万円が給付され、減収分の一部をカバーできます。育児時短就業給付を利用することで収入面での不安を軽減しながら、子育てを中心とした柔軟な働き方が実現しやすくなります。
柔軟な働き方の実現
こども未来戦略の加速化プランにおいて、2025年10月から育児中の従業員に対する職場の柔軟な働き方制度が義務化されました。本法改正は、育児と仕事を両立しやすい環境を企業が主体的に整備することを目的としています。
具体的には次の4つの事業が改正され、より多くの人にとって利用しやすくなります。
| 改正・新設される制度 | 改正前内容 | 改正後・新設内容 |
|---|---|---|
| 子の看護休暇 | 【対象範囲】 | 【対象範囲】 |
| 小学校就学まで 【取得事由】 病気やケガ、予防接種など 【労使協定の締結により除外できる従業員】 ・雇用された期間が6か月未満 ・週の所定労働日数が2日以下 |
小学校3年生修了まで 【取得事由】 ・病気やケガ、予防接種 ・感染症による学級閉鎖や卒園式 【労使協定の締結により除外できる従業員】 週の所定労働日数が2日以下 |
|
| 残業免除 | 3歳未満の子どもを養育する従業員が申請可能 | 小学校就学前の子を養育する従業員が申請可能 |
| 育児を目的としたテレワーク導入の努力義務化 | 3歳未満の子を養育する従業員に対して短時間勤務制度が適用できない場合、テレワークで代替えする。 または3歳未満の子を養育する従業員がテレワークを選択できるような措置を行う努力義務 |
|
| 育児休業取得状況の公表義務範囲を拡大 | 従業員1,000人以上の企業に公表が義務化 | 従業員300人以上の企業に公表が義務化 |
2025年10月1日からは、3歳から小学校就学前の子を養育する従業員がより柔軟な働き方を実現する施策も始まります。具体的には事業者が、次の措置から2つ以上を選択して措置を講じることが必要です。
- 始業・終業時刻の変更(フレックスタイムや時差出勤)
- テレワークの導入(月10日以上の実施が努力義務)
- 保育施設の設置
- 新たな休暇制度の設立(年10日以上)
- 短時間勤務制度の設立
上記のような制度があることで、働きながらも子育てしやすい社会の実現が期待されます。また、柔軟な労働環境の整備は従業員の離職率低下に好影響を与えるケースもあり、企業にとってもメリットがあります。
こども未来戦略・加速化プラン(教育)

こども未来戦略の加速化プランは、教育支援についても新しい試みが行われています。教育支援について抑えておくことで、今後の子育て負担をより軽減可能です。ここではこども未来戦略における教育支援について解説します。
こどもの学習・生活支援の充実
こども未来戦略の加速化プランでは、子どもの学習や生活支援の充実も掲げられており、とくにひとり親家庭や低所得世帯に対する支援が拡充されます。ひとり親家庭や低所得世帯では学習環境が十分確保されないケースが多く、学びの格差が広がる懸念があるためです。
具体的には次のような事業が展開されます。
- 生活習慣や生活指導の場の提供
- 自習室提供などの学習支援
- 長期休暇期間の生活指導や支援日数の増加
- 大学や専門学校の受験料の支援
- 中学校や高校の受験に向けた模擬試験受験料の支援
- 学習支援員の場に個別支援員を配置する費用の支援
生活支援強化事業では複雑な家庭環境や困難に対応する子どもたちに対して、地域のさまざまな場を活用して、食事が提供できる場の設置も進められています。また、こども食堂の運営を「ひとり親家庭等のこどもの食事等支援事業」として国側が支援する枠組みも取り決められました。
学習の場や食事の提供を通じて、子どもの貧困や孤立への支援を地域で行う体制も整えられています。
教育費のさらなる支援拡充
こども未来戦略の加速化プランでは子どもを3人以上同時に扶養する家庭を対象に、大学等の入学金・授業料が一定額まで無償化されます。所得に関する基準や制限はないため、3人以上の子どもを同時に扶養するすべての家庭が利用可能です。
子どもは第一子目から支援の対象となるため、子ども同士の年齢差によっては教育費用を大幅に削減できる可能性があります。例えば、3人の子を育てていて、そのうち2人が大学生であれば、その2人とも支援を受けられます。ただし、1人が卒業するなどして扶養から外れ、扶養している子が2人だけになった場合、その時点で支援が打ち切られる制度です。
こども未来戦略による教育費の無償化は、子どもたちが多様な未来を選び取る力を後押しする重要な制度です。教育関連の支援が拡充されることを通じて、家庭の経済的負担が減るだけでなく、将来的な社会の活力にもつながると期待されます。
多様なワークスタイルに対応・人事管理システム「ADPS」

こども未来戦略・加速化プランにより、柔軟な働き方の推進が求められる中、職場の人事管理にも大きな変化が求められています。
そうした中で注目されているのが、カシオヒューマンシステムズ株式会社が提供する人事管理システム「ADPS」です。勤怠・給与・申請・従業員情報などを一元管理できるADPSは、企業の人事業務の効率化と働き方改革の実現を後押しする人事管理システムです。
近年、育児・介護・副業・テレワークなど、働き方の多様化が進み、企業の人事部門には柔軟かつ正確な対応が求められています。しかし、制度が複雑化する一方で、アナログな管理や属人的な運用に限界を感じている企業も少なくありません。
ADPSは、柔軟な人事制度が求められる課題に応える形で、給与や社会保険、勤怠やマイナンバー管理といった主要な人事業務をすべてカバーできる設計となっています。
例えば、時短勤務やフレックス、在宅勤務といった個別の勤務形態にも対応可能な勤怠管理機能が搭載されており、複雑な計算や就業ルールもパターン登録により自動化可能です。多様な働き方を支えるには、制度設計だけでなく、それを現場で実行する「しくみ」が必要です。
ADPSを導入することでシステムを通じて柔軟な労働環境を整備し、従業員が安心して働ける職場づくりを実現できます。
まとめ

こども未来戦略と加速化プランは、少子化対策と子育て支援を社会全体で進めるための実行計画です。妊娠・出産から教育までを切れ目なく支援し、所得向上や柔軟な働き方の実現を目指しています。
多くの人が仕事と子育てが両立できる社会の実現には、企業側の対応力も欠かせません。カシオヒューマンシステムズの「ADPS」は、人事業務の一元化によって、職場の柔軟性を高めながら運用負担を軽減できるシステムです。
制度と現場をつなぐ仕組みづくりを行って従業員の持続可能な子育て支援を行うためにも、人事システムの導入を検討しましょう。
カシオヒューマンシステムズコラム編集チームです。
人事業務に関するソリューションを長年ご提供してきた知見を踏まえ、
定期的に「人事部の皆様に必ず今後の業務に役立つ情報」を紹介しています。