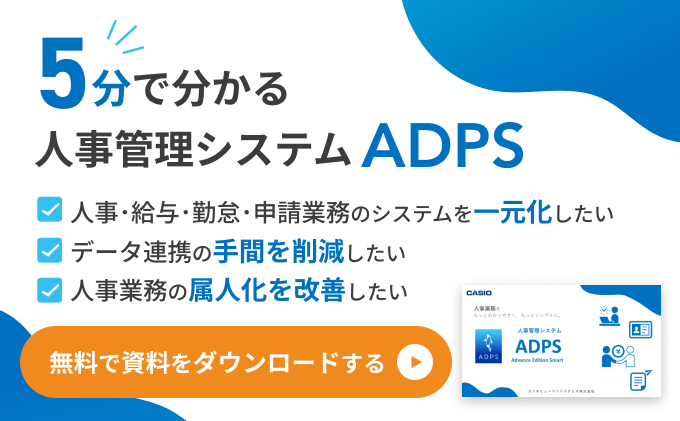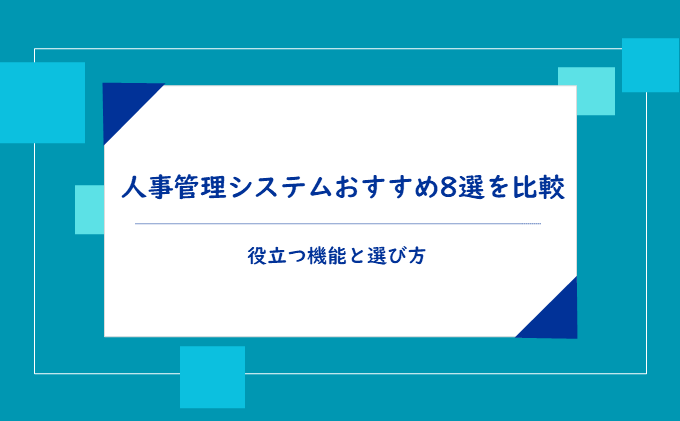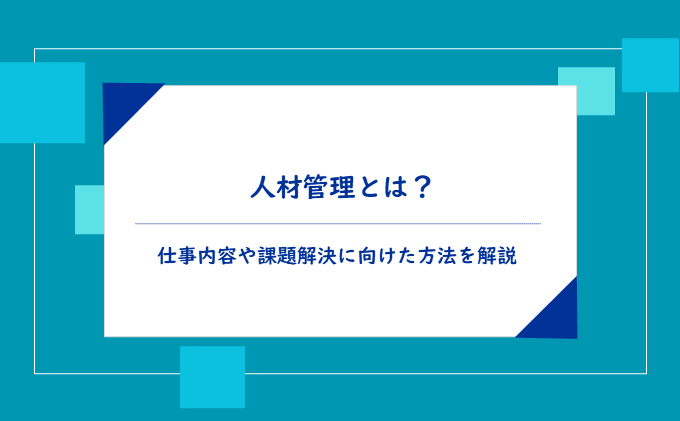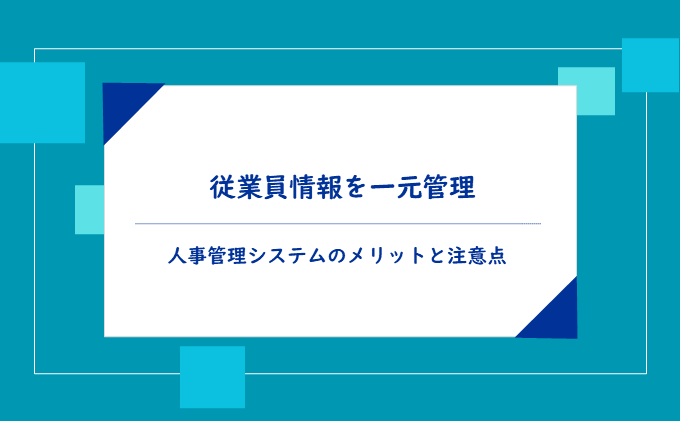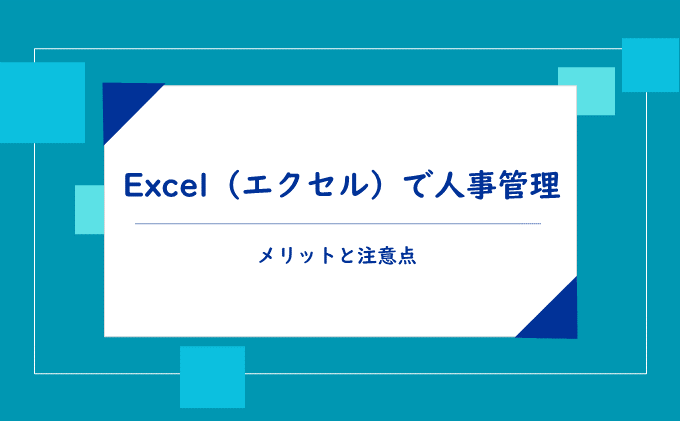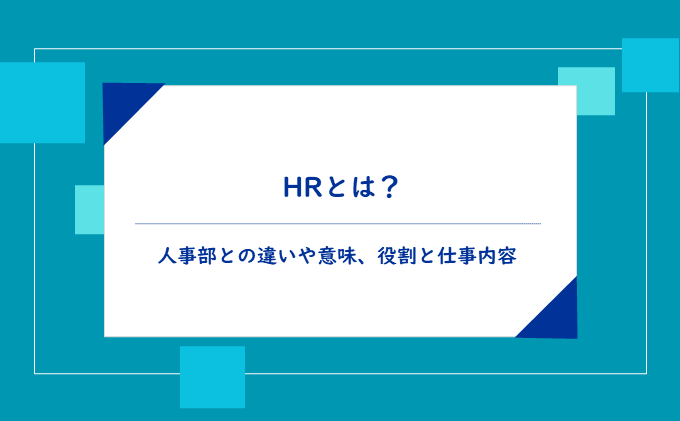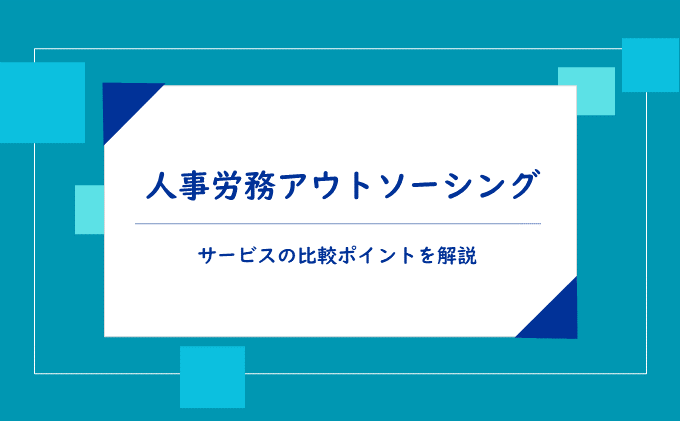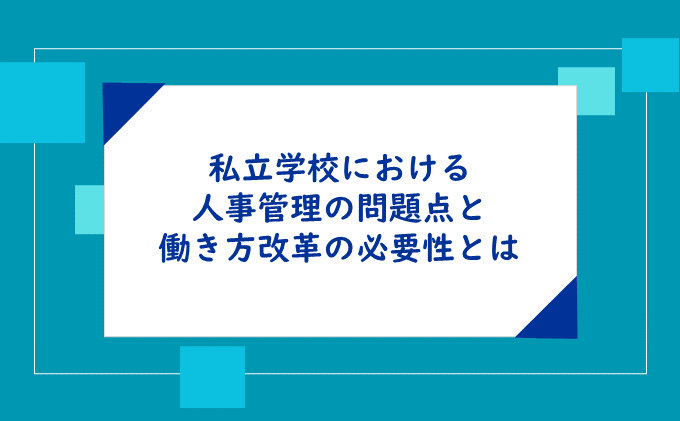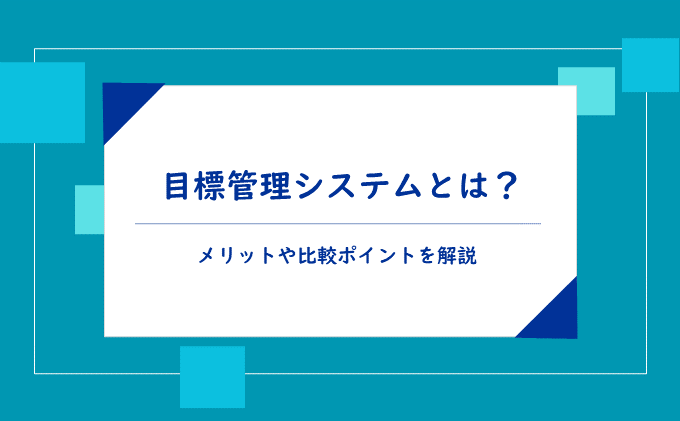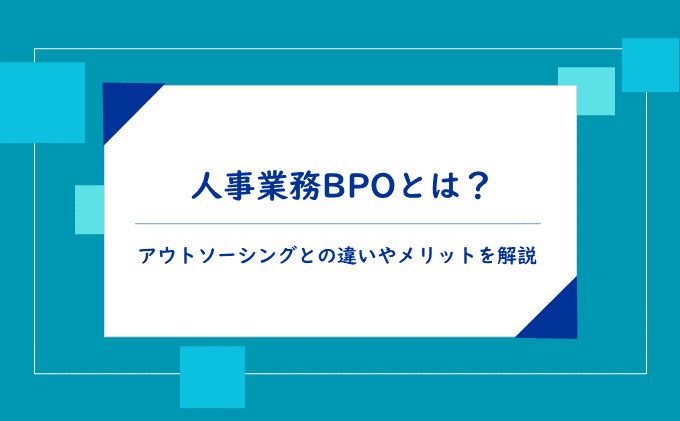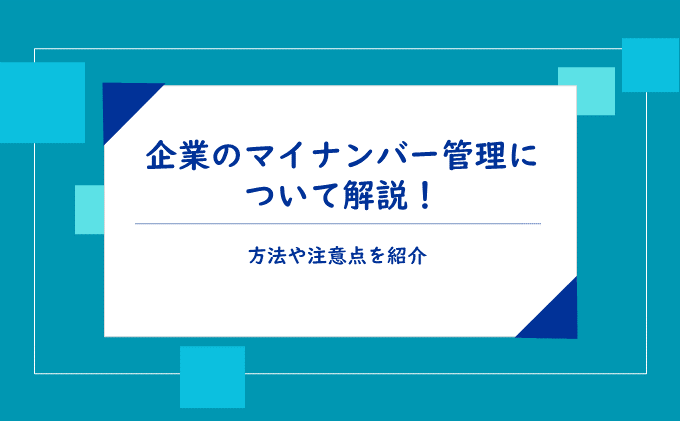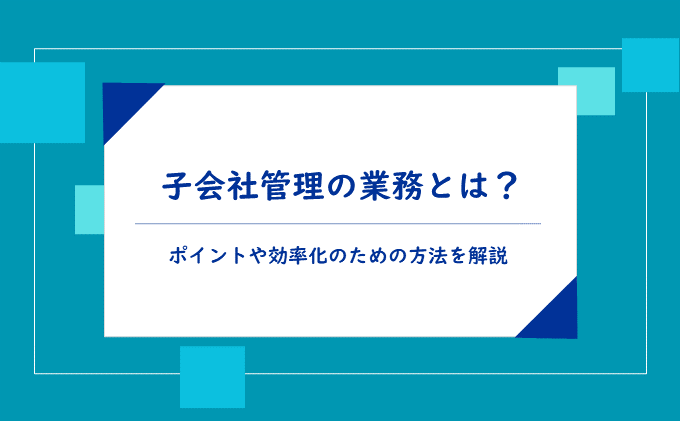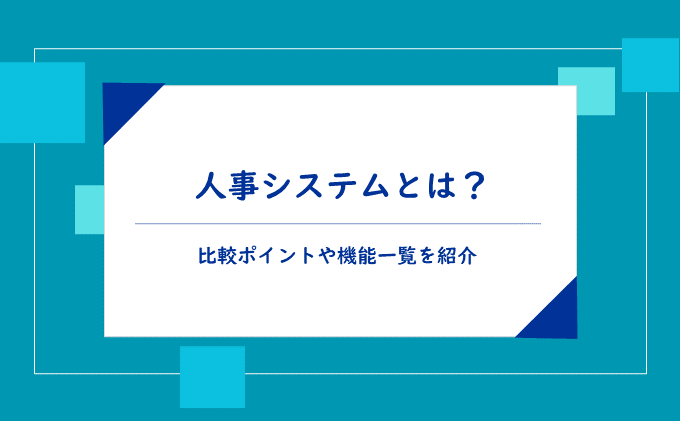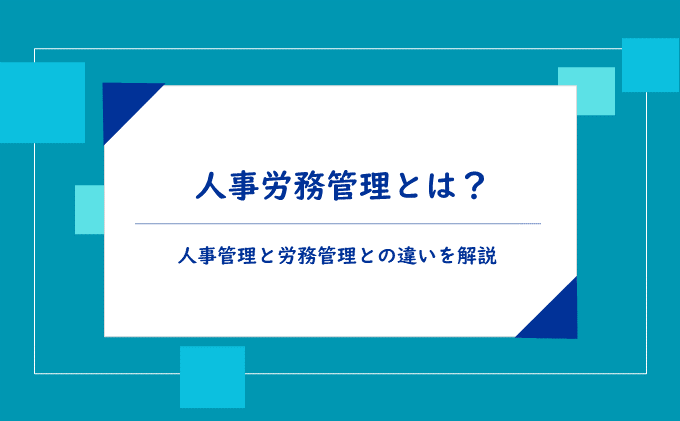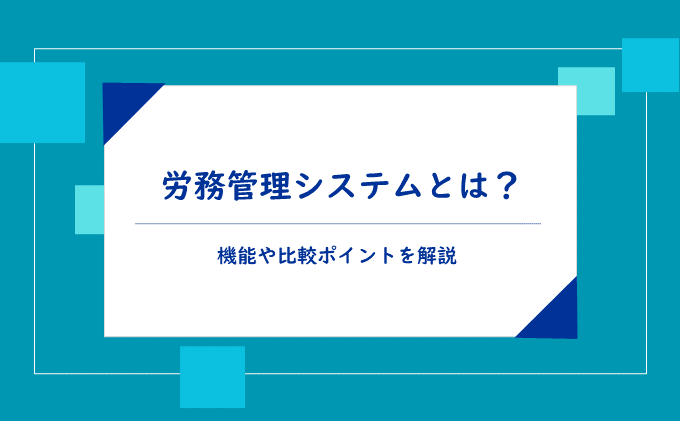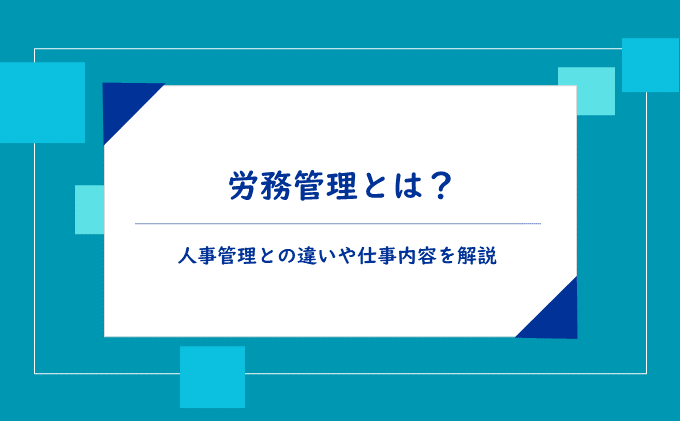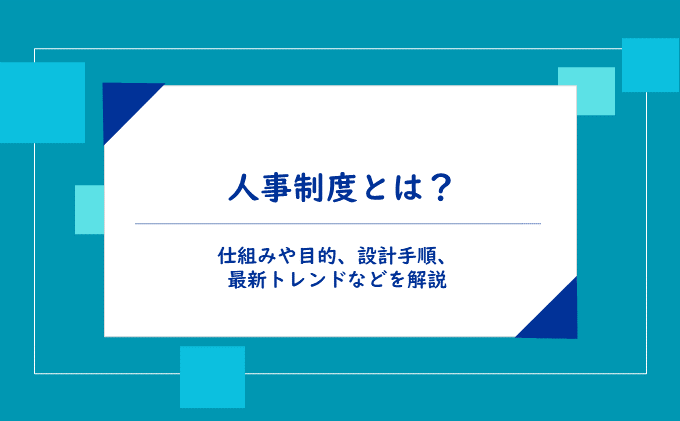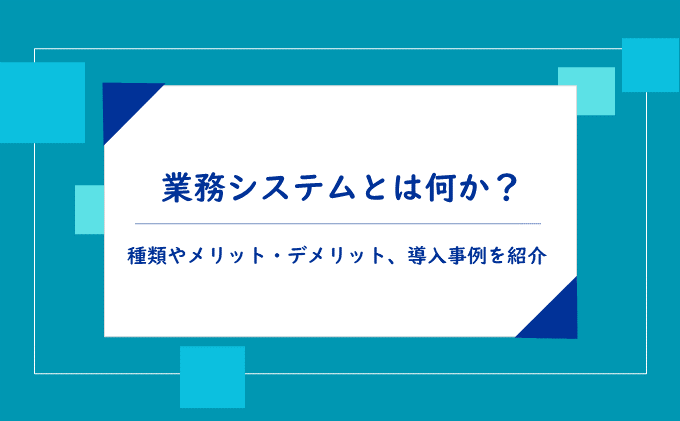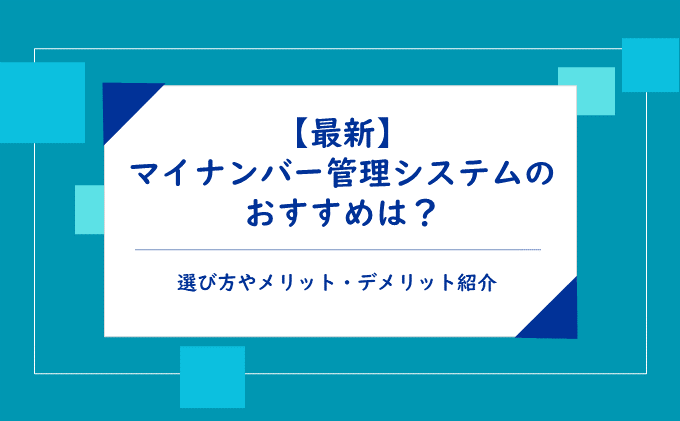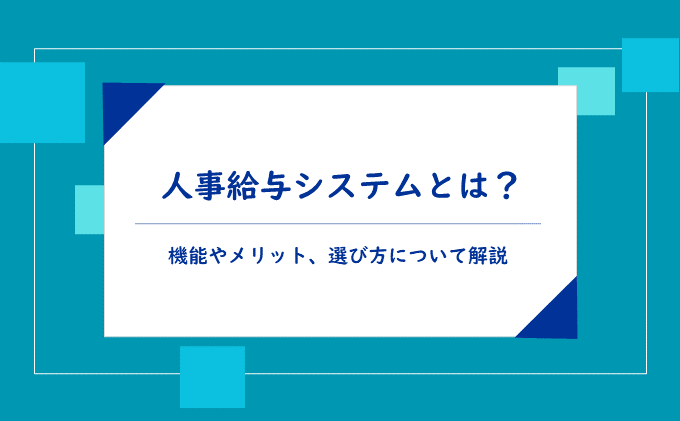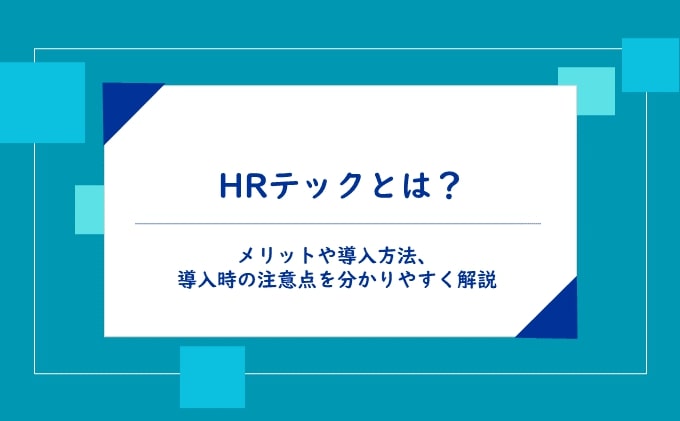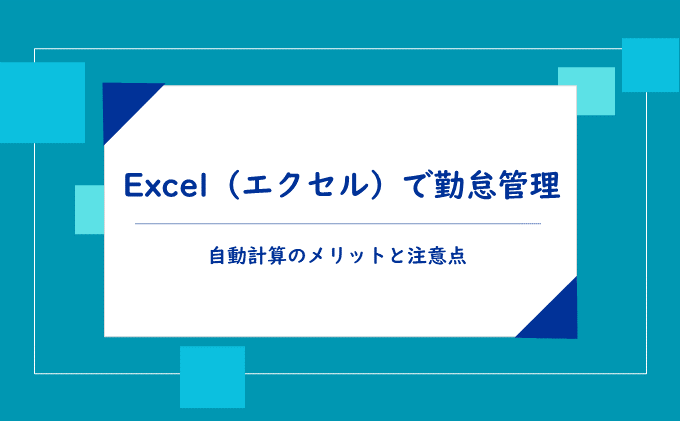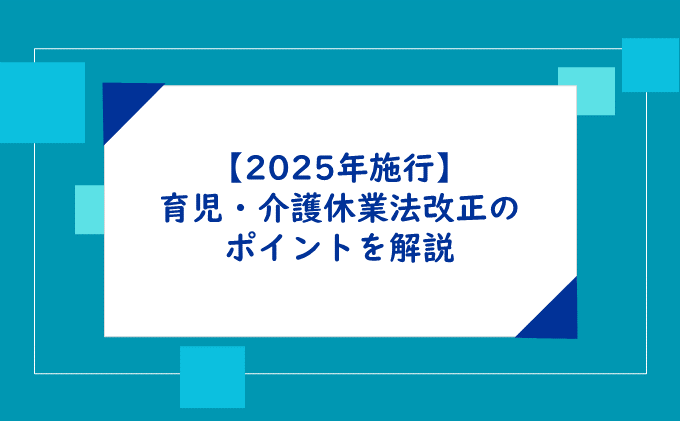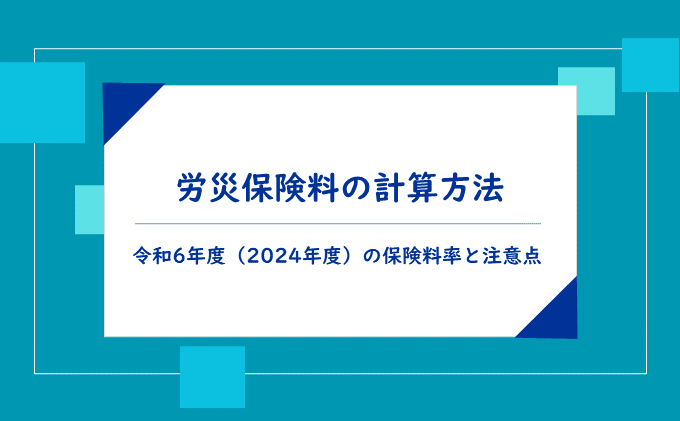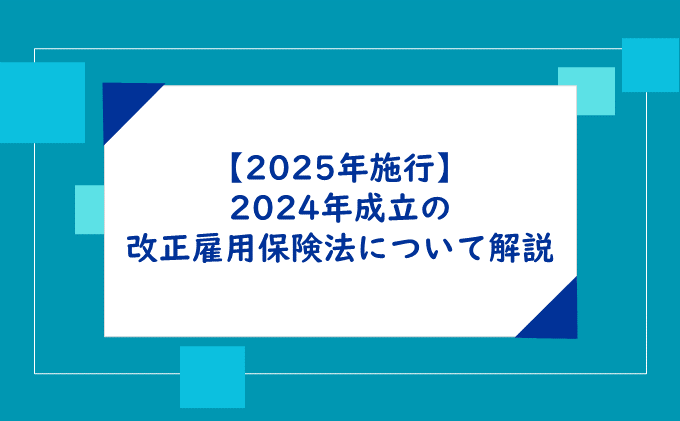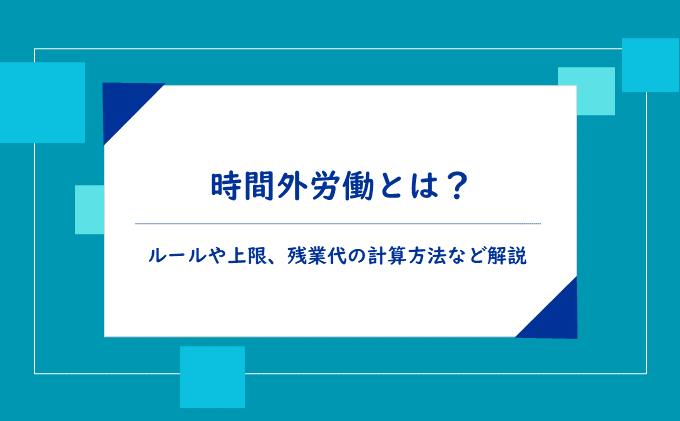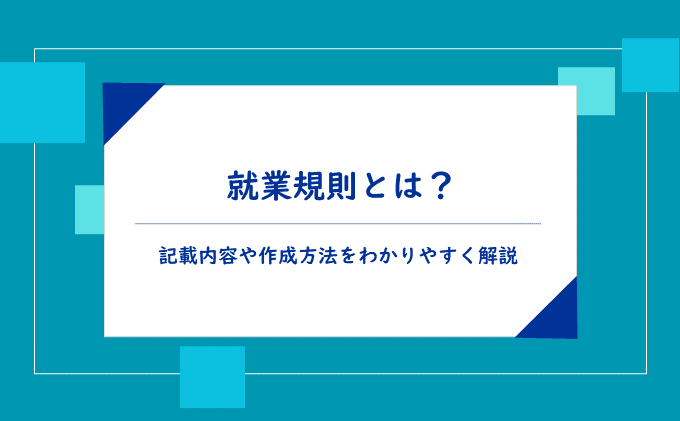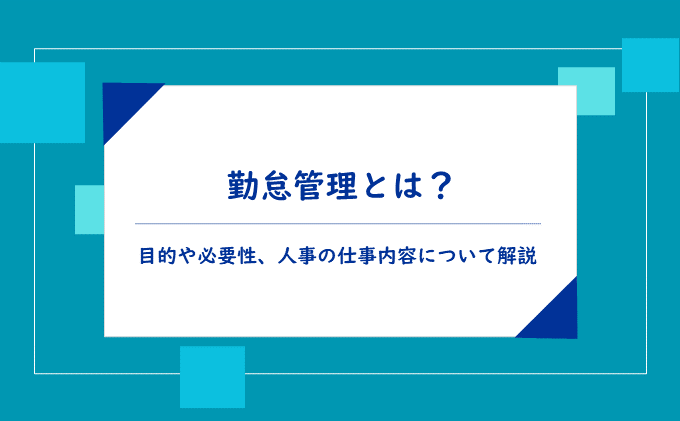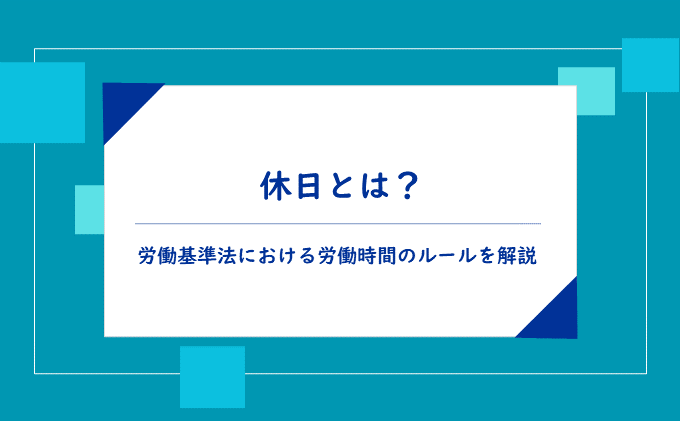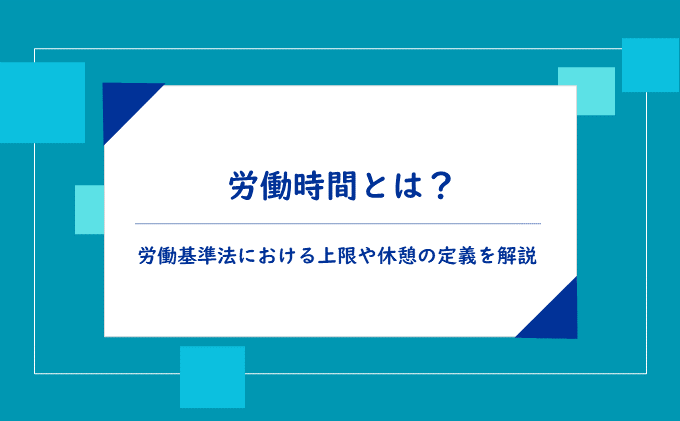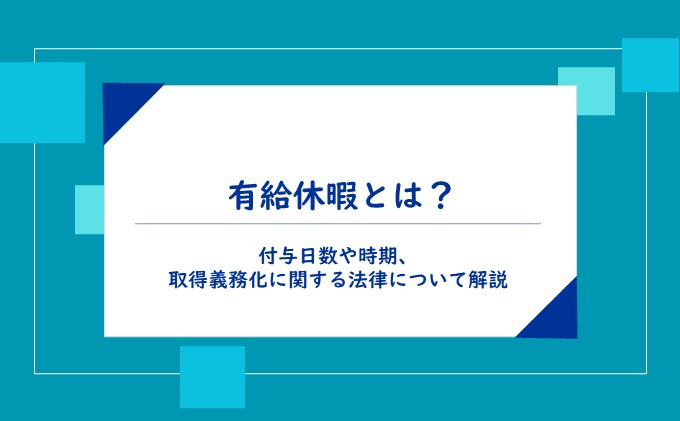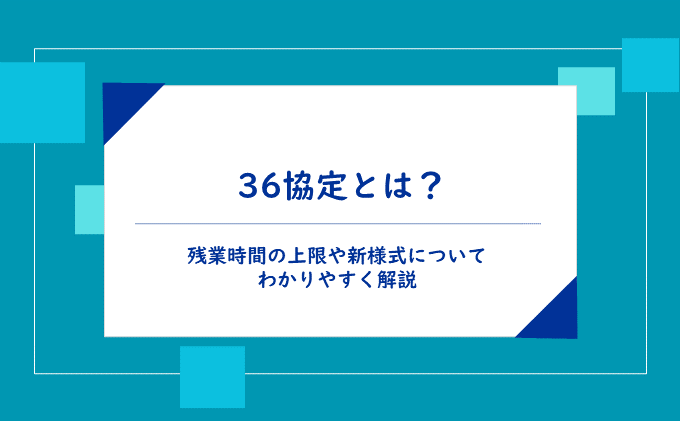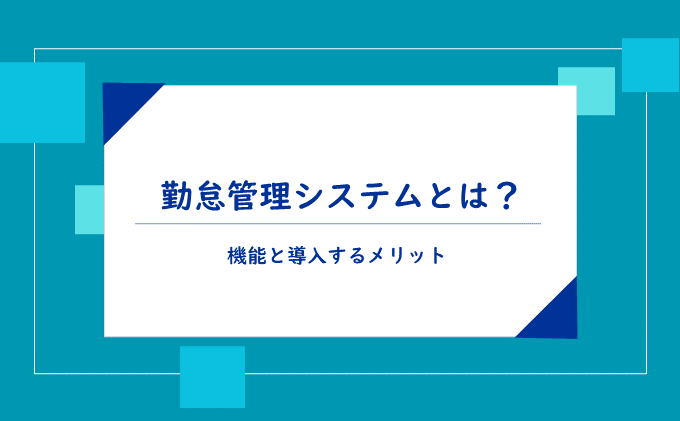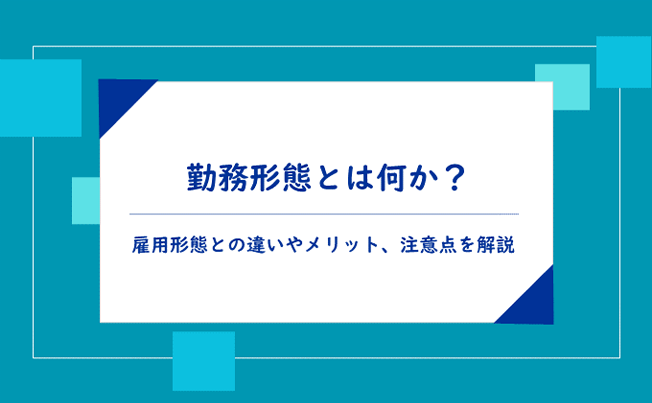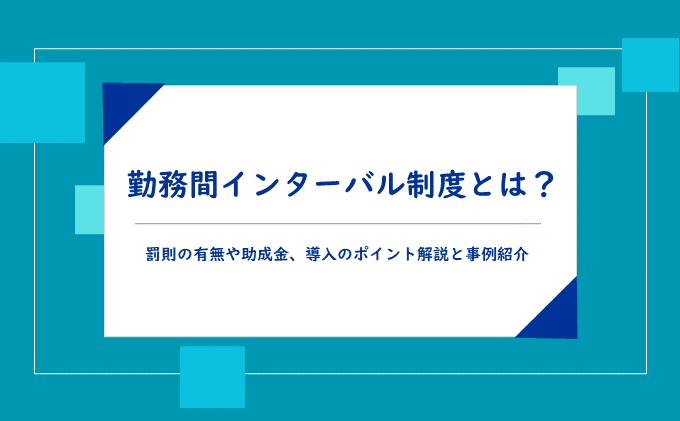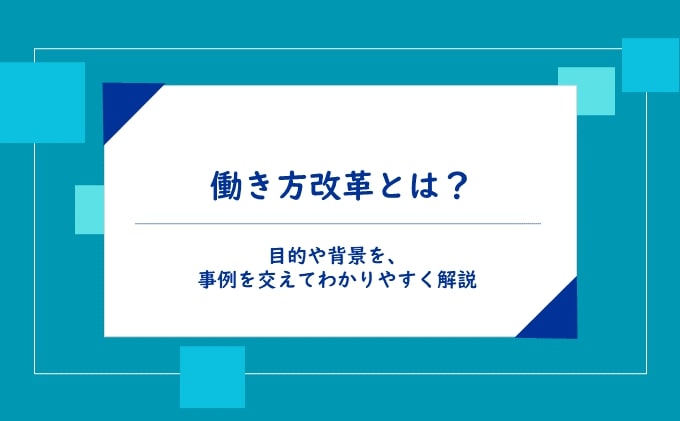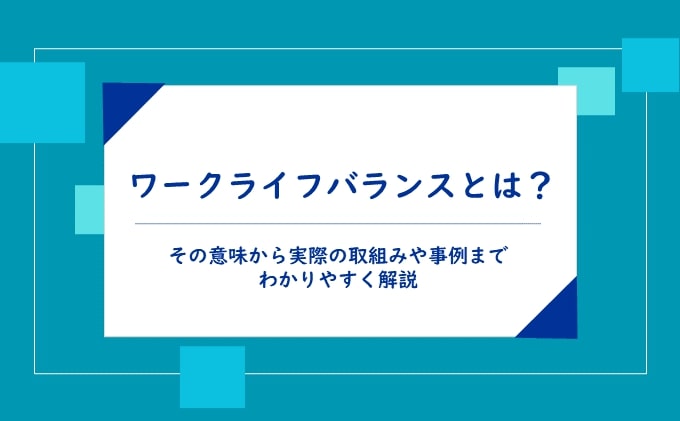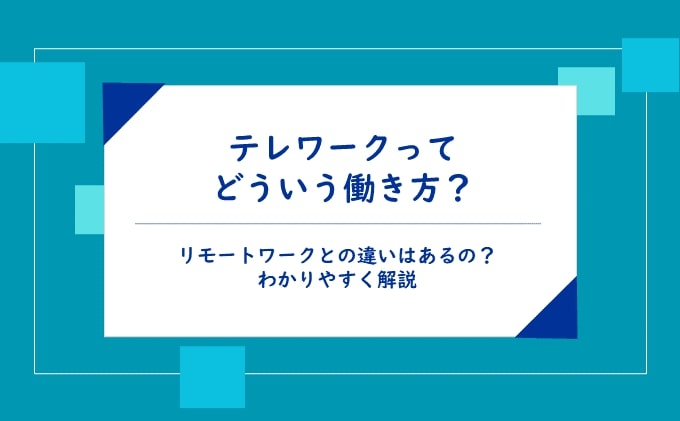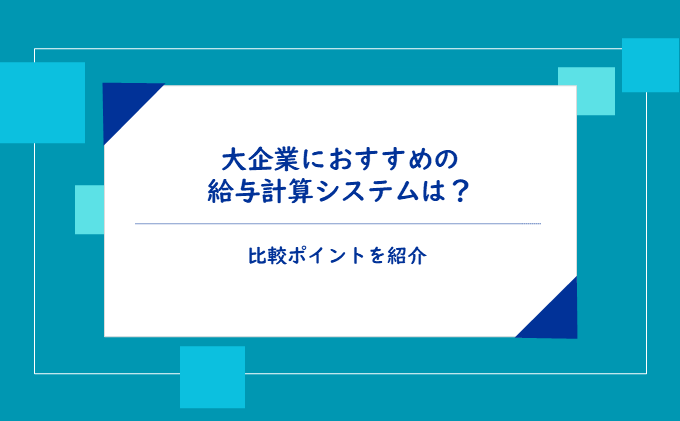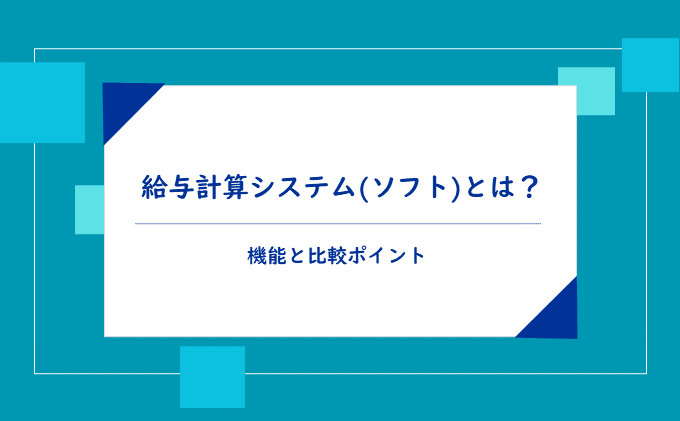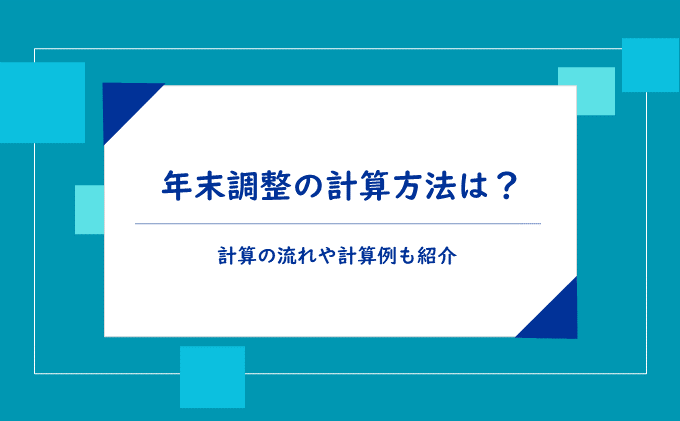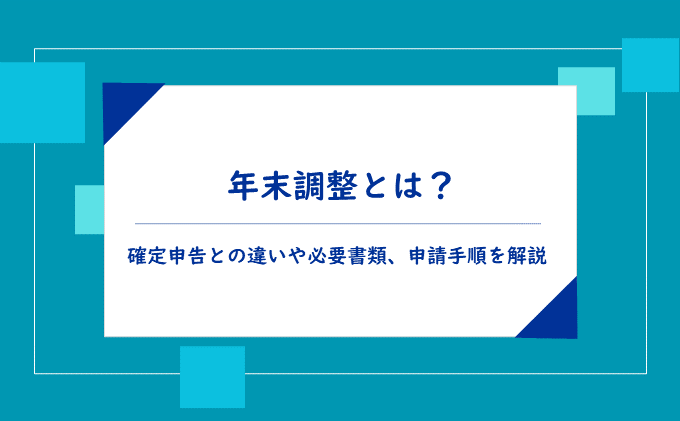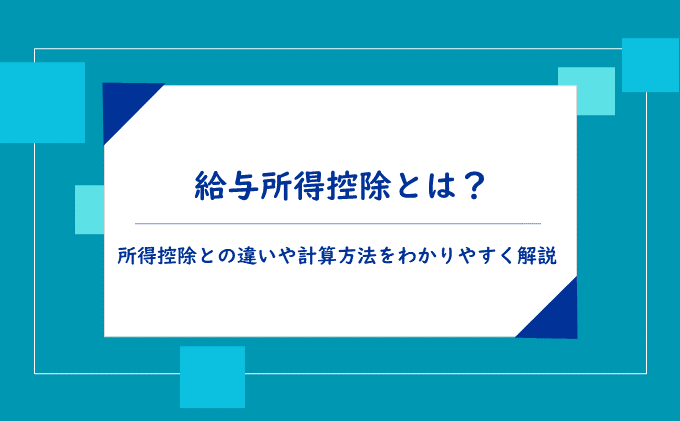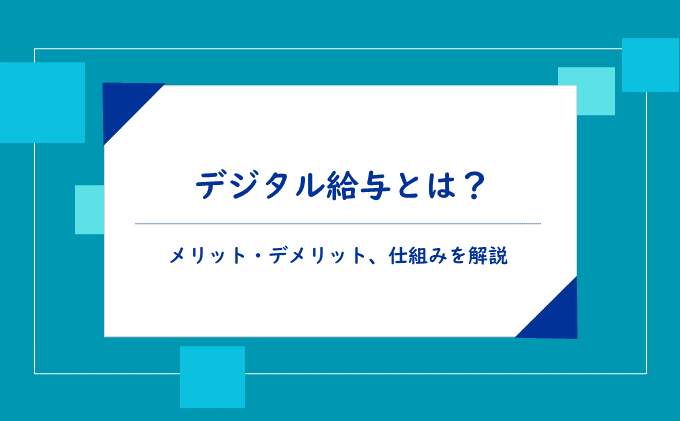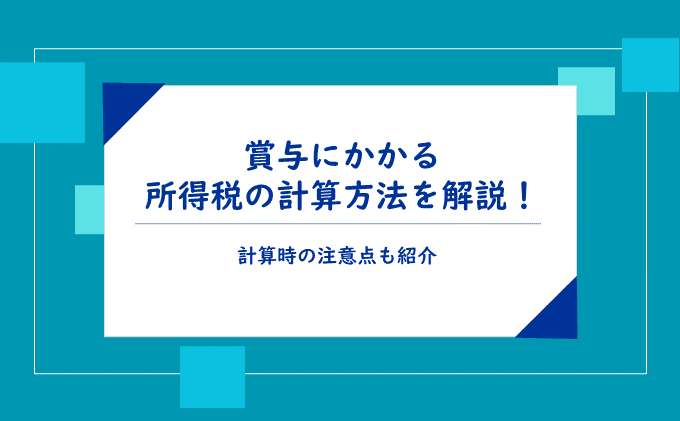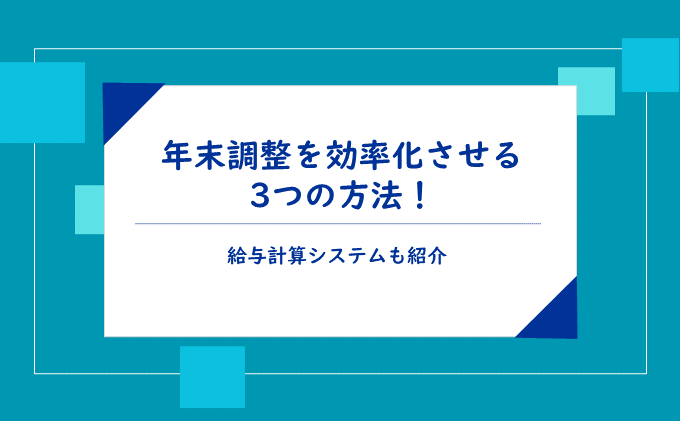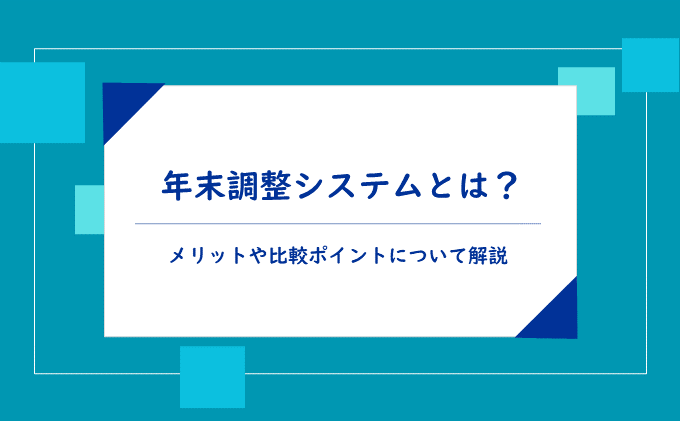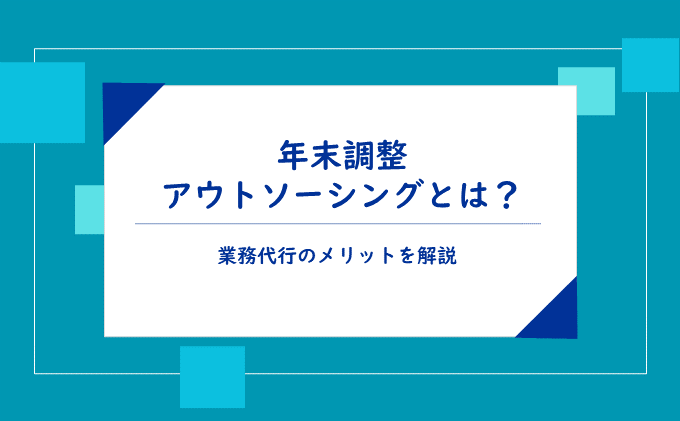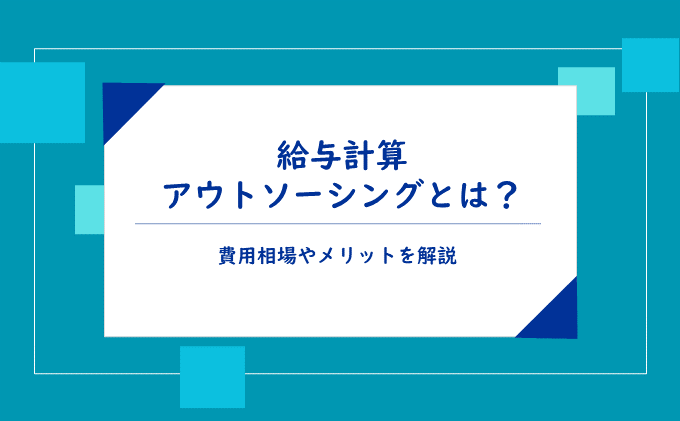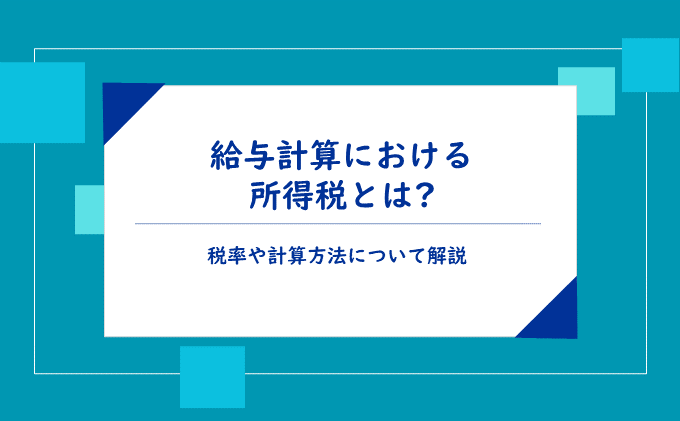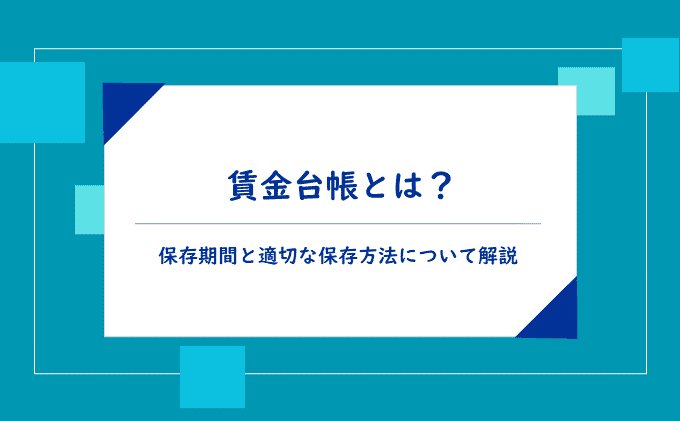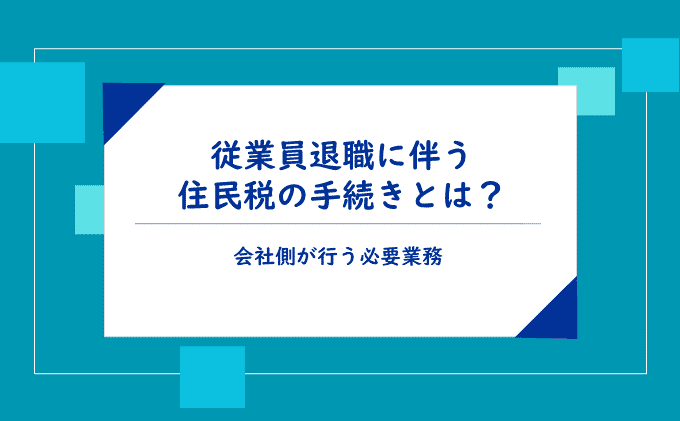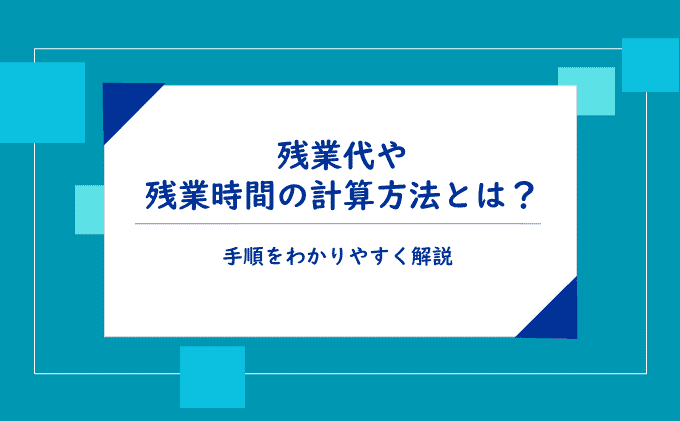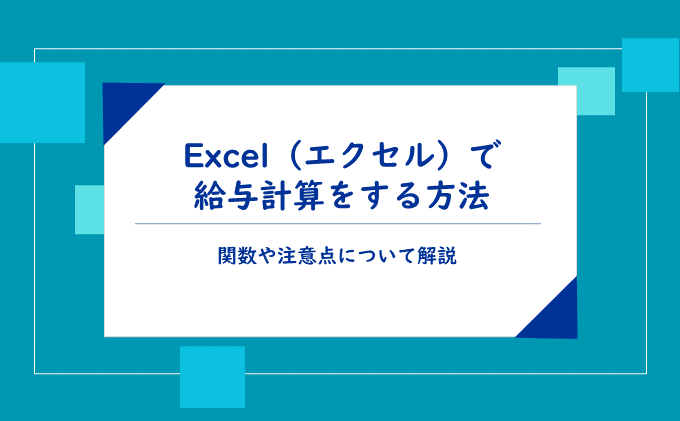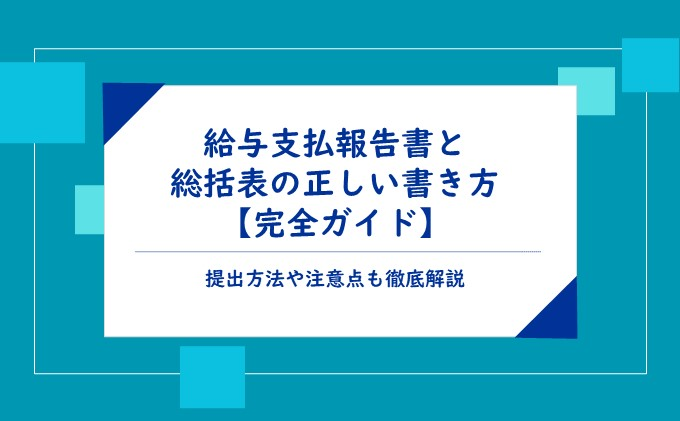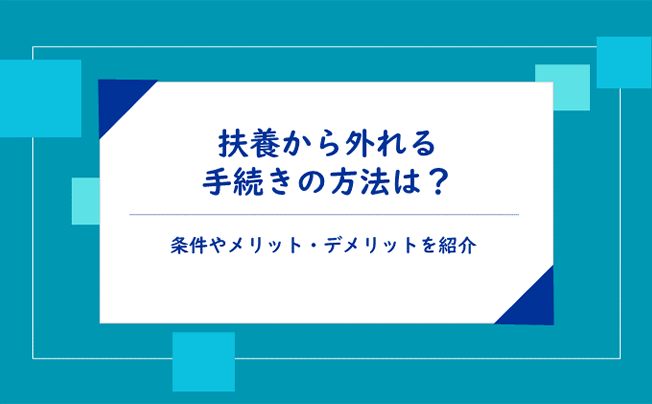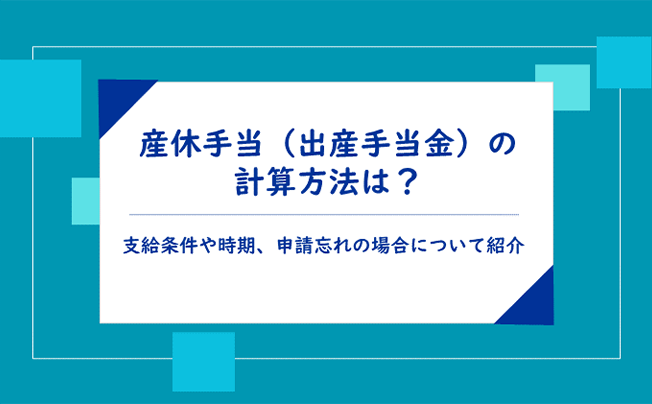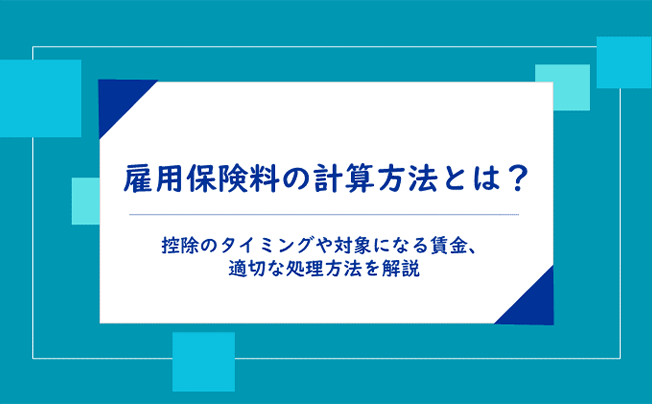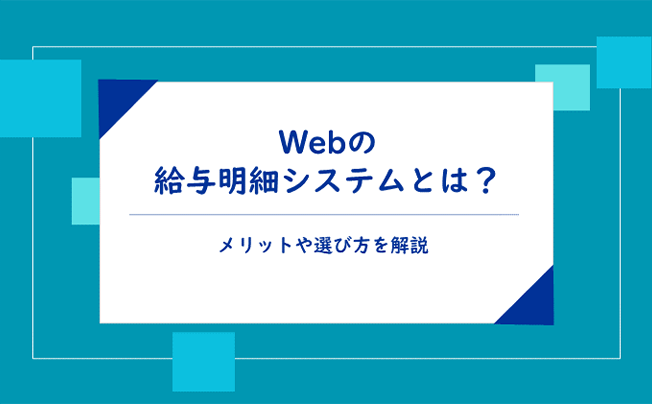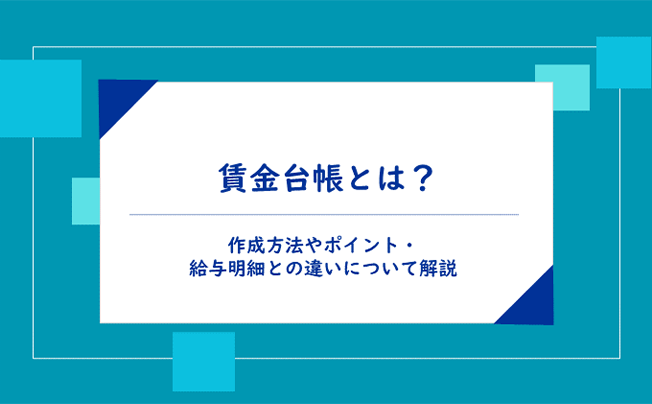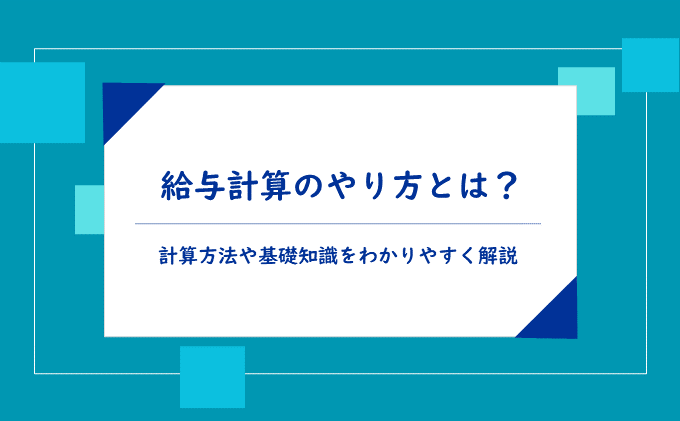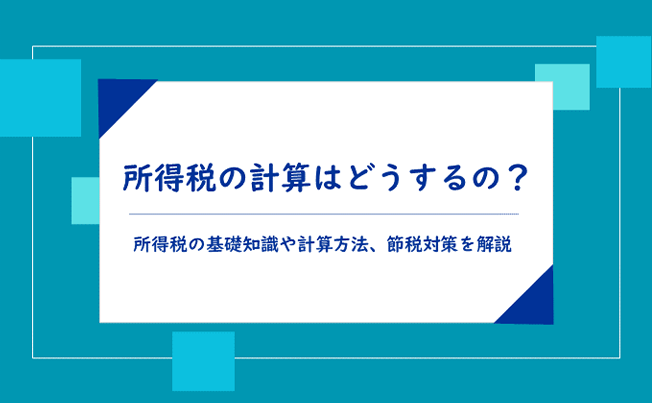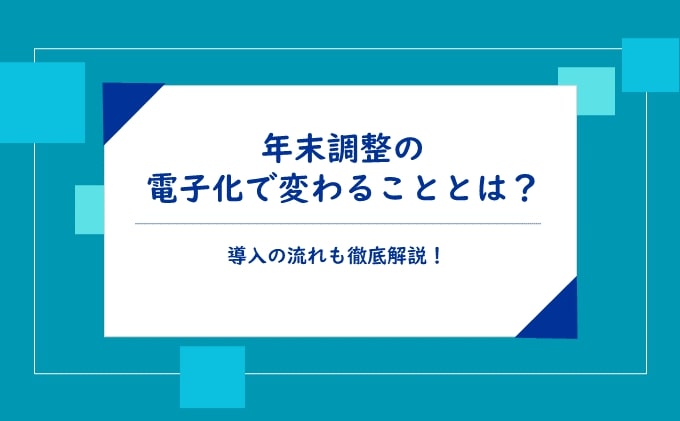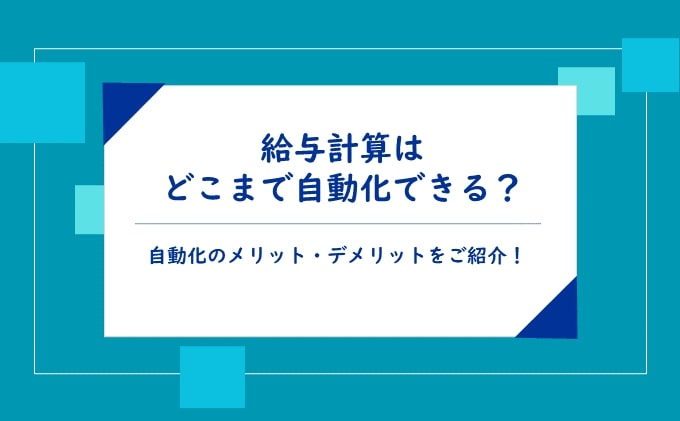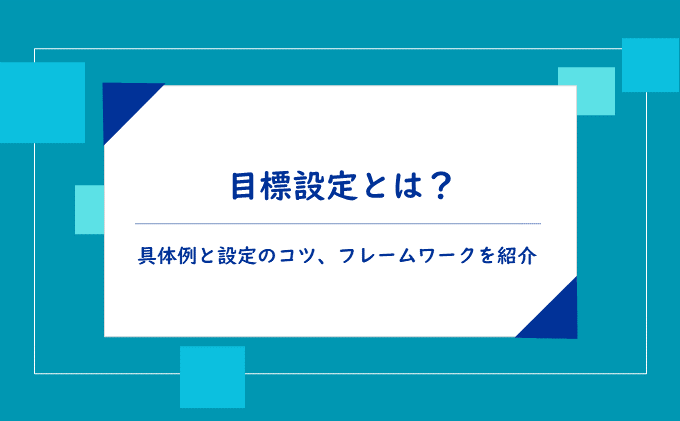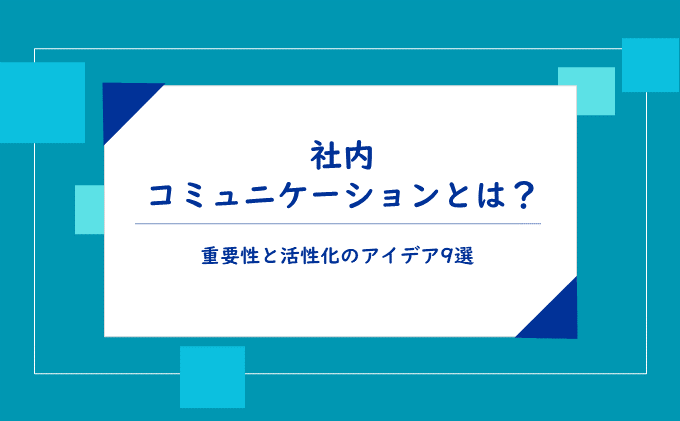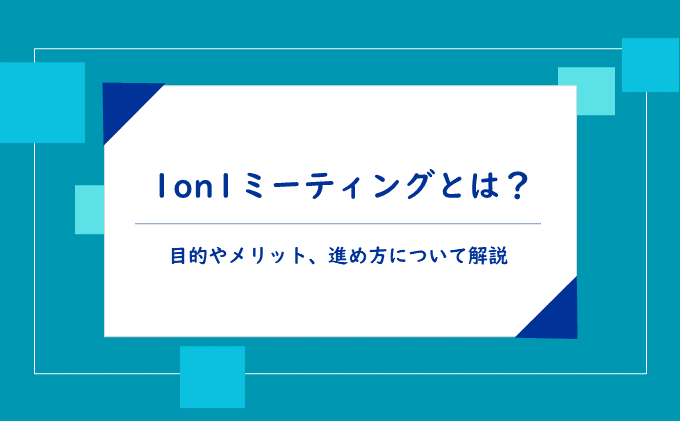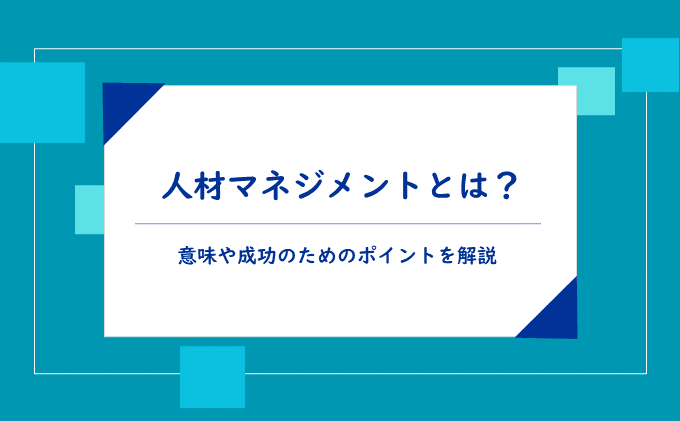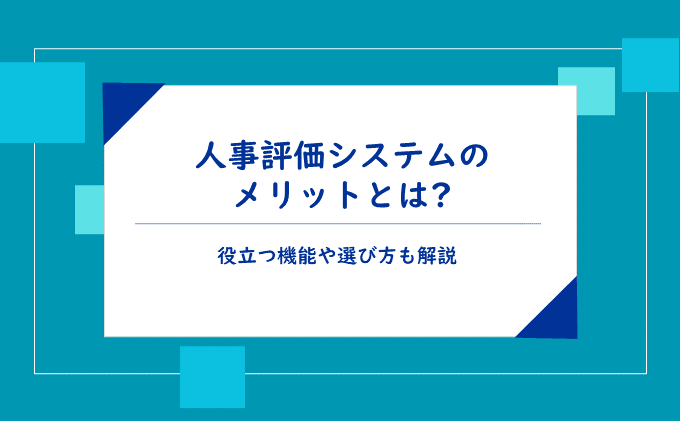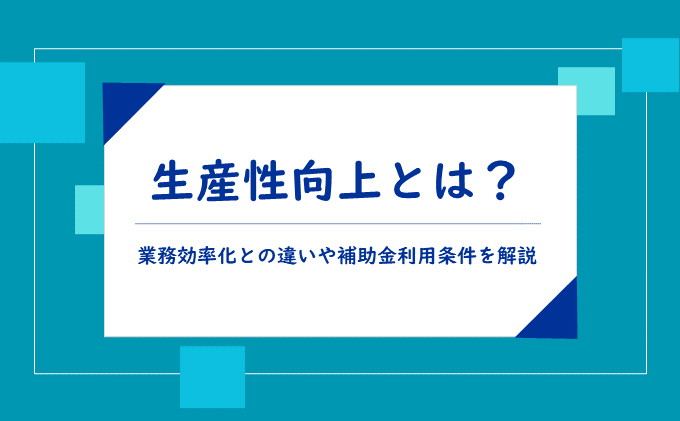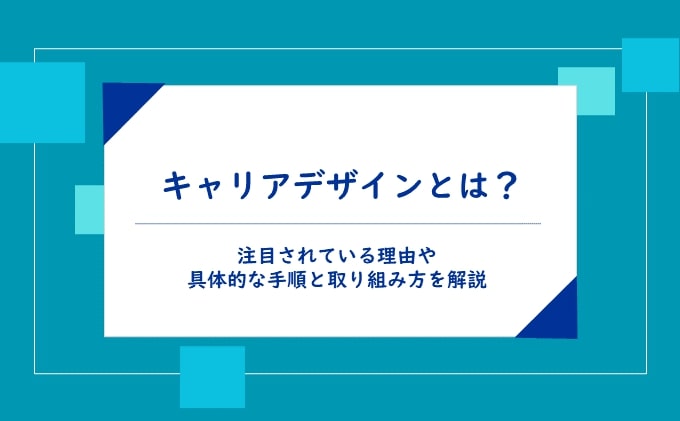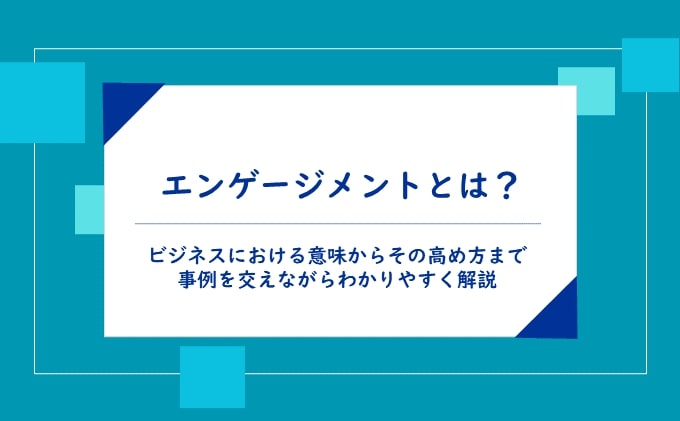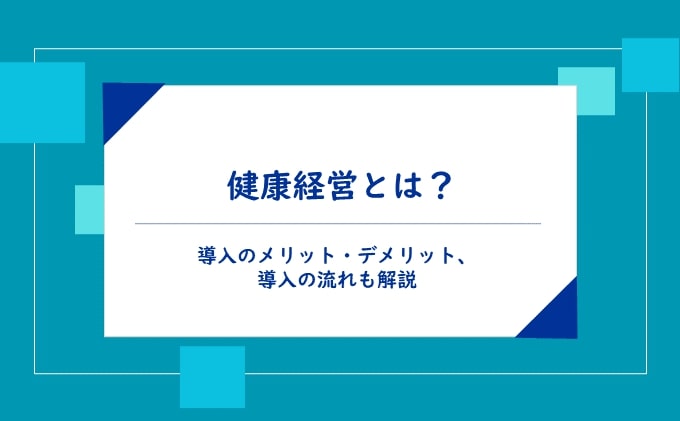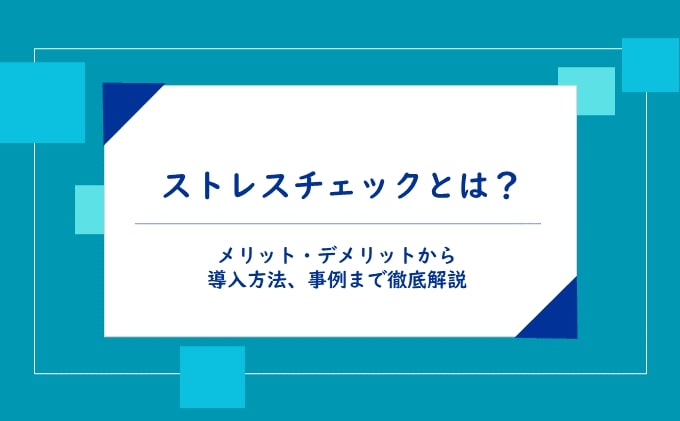2026年3月JR東日本が運賃改定┃通勤手当業務における注意点
2025.10.30
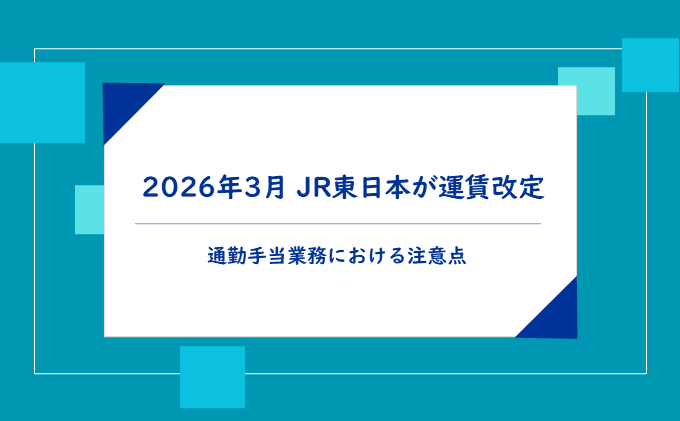
2026年3月にJR東日本が予定している運賃改定は、多くの企業にとって通勤手当業務へ大きな影響を及ぼす出来事です。とくに従業員数の多い企業では、処理の遅れや誤支給がトラブルにつながる可能性も否定できません。本記事では、運賃改定が企業の通勤手当業務に与える影響と、担当者が押さえておくべき注意点をわかりやすく解説します。
目次
【2026年3月】JR東日本が運賃改定を実施

2026年3月にJR東日本が運賃を改定することが発表されています。今回の改定は普通運賃にとどまらず、通勤定期の料金にも影響を及ぼすため、事前に改定率や対象範囲を確認しておくことが重要です。
ここでは、運賃改定に至った背景や具体的な改定率についてわかりやすく解説します。
運賃改定の背景
JR東日本が全エリアで運賃改定を実施する背景には、社会環境の大きな変化があります。コロナ禍によるテレワークやオンライン会議の普及で鉄道利用者は減少し、加えてエネルギー価格や物価の上昇により運営コストが増大しました。
さらに、人口減少に伴う人材確保の難しさも課題です。待遇改善の必要性に加え、安全対策やサービス品質の維持、老朽化した設備の更新、災害対策やカーボンニュートラルへの投資など、社会的責任を果たすための費用も避けられません。
こうした状況を踏まえ、JR東日本は経営努力を前提としつつ、鉄道事業を持続可能にするために運賃改定を決断しました。
通勤定期の改定率(値上げ率)は12.0%
2026年3月の改定では、通勤定期の平均値上げ率が12.0%と公表されています。普通運賃の7.8%、通学定期の4.9%と比較して大きな上昇幅となっているため、通勤手当を支給する企業に大きな影響を及ぼすことは間違いありません。
具体的な改定率の内訳は次のとおりです。
| 運賃区分 | 普通運賃 | 通勤定期 | 通学定期 |
|---|---|---|---|
| 幹線 | 4.4% | 7.2% | 改定なし |
| 地方交通線 | 5.2% | 10.1% | 改定なし |
また、電車特定区間や山手線内は、競合路線があることで特定区分として料金が安価に設定されていました。しかし、2026年3月の改定によってこの特定区分は廃止され、実質的な大幅値上げが実施される予定です。
電車特定区間や山手線内の具体的な改定率は次のとおりです。
| 運賃区分 | 普通運賃 | 通勤定期 | 通学定期 |
|---|---|---|---|
| 電車特定区間 | 10.4% | 13.3% | 8.0% |
| 山手線内 | 16.4% | 22.9% | 16.8% |
企業は、各区分の値上げ率を考慮したうえで、通勤手当業務を進める必要があります。
運賃改定による通勤手当業務への影響

運賃改定による通勤手当業務の影響は非常に大きいです。改定に伴う処理は単純ではなく、対象となる従業員の特定から通勤経路・改定後の運賃確認まで、多くの工数を要します。
まず、どの従業員が影響を受けるのかを洗い出し、それぞれの経路や運賃を確認することが必要です。表計算ソフトで手作業管理をしている場合、入力や転記といった細かな作業が積み重なり、担当者の負担は一層大きくなります。
また、今回のような運賃改定は消費税増税時の一斉改定とは異なり、鉄道会社ごとに実施時期がずれることもあります。そのため路線ごとに処理が必要となり、従業員数が多い企業ほど対応に追われやすい点も課題です。
さらに、通勤手当の支給方法が「定期代の前払い」と「実費精算の後払い」で混在している場合は注意が必要です。支給するタイミングによって、どの時点の運賃を基準に支給するかを正しく判断しなければならず、チェック体制が不十分だと誤支給のリスクが高まります。
このように、運賃改定への対応には事前準備と正確な情報管理が不可欠です。
従業員数が多い企業ほど、通勤手当業務の担当者負担は大きくなります。
その解決策としておすすめなのが、人事管理システム「ADPS」です。通勤手当業務を効率化し、正確かつ迅速な給与計算を実現し、大規模な企業の課題解決をサポートします。
詳しくは資料をご覧ください!
関連記事:通勤手当とは?交通手段別の計算方法と平均相場、課税限度額について解説
運賃改定による通勤手当変更のタイミング

運賃改定に伴う通勤手当の変更は、支給時期に合わせて行う必要があります。2025年9月7日時点では、改定実施日の詳細はまだ公表されていません。
ここでは仮に2026年4月1日に料金改定が実施されると想定し、支給方法別に必要な対応タイミングを確認します。
前月に交通費を一括で前払いしている企業の場合は、2026年3月の支給段階で改定後の定期代を反映することが必要です。一方、出社日数に応じて交通費を後払いしている企業の場合は、5月の支給時点で新しい運賃を適用します。
このように、前払いと後払いでは処理のタイミングが異なるため、従業員の通勤形態に応じて正しく対応することが重要です。
運賃改定への対応方法

運賃改定は、企業の通勤手当業務に直接影響を与えるため、正確かつ迅速な対応が求められます。とくに従業員数が多い企業では、準備不足や処理の遅れがトラブルにつながりかねません。
ここからは、実務担当者が押さえておくべき具体的な対応方法について順を追って解説します。
従業員が自分で申請する
運賃改定に伴い通勤手当の金額が変わる場合、多くの企業では従業員本人が改定後の運賃を調べて申請する方式を採用しています。
基本的な流れは以下のとおりです。
- 従業員が現行の経路をもとに、新しい運賃を確認し紙やメールなどで申請
- 上長が申請内容を承認
- 管理担当者が申請内容をもとに経路や金額を再確認し、表計算ソフトなどに入力
- 最終的に給与システムへ反映し、通勤手当を支給
この方法は、申請した従業員ごとに順次対応できるため、担当者が作業に取り掛かりやすいメリットがあります。一方で、全従業員が申請を済ませているかを把握しにくい点はデメリットです。
申請漏れが発生したり、担当者が全員分の経路・金額を一つひとつ確認したりするなど、結果的に負担が多くなるケースも少なくありません。
管理部門が対応する
一部の企業では、管理部門が一括で通勤手当を変更処理する方法をとっています。この方式では、申請や承認といったプロセスを省略できるため、従業員側の手間を削減できる点が特徴です。
基本的な流れは以下のとおりです。
- 運賃改定の対象路線を確認する
- 対象となる従業員を抽出する
- 公表された料金表をもとに、新運賃を適用する
- Excelや一覧データに入力し、給与システムへ再登録またはCSVで取り込み
この方法では、従業員からの申請を待つ必要がないため、処理を主体的に進められるメリットがあります。
しかし、対象路線や駅名をすべて把握しておかなければならず、データが一覧化されていない場合は確認作業が膨大になります。乗り継ぎが含まれるケースでは検索ツールでの確認も必要となり、入力や転記の手間も避けられません。
また、鉄道会社によって改定月が異なる場合、3月・4月と複数回の改定に対応する必要があり、業務負担は長期化します。さらに、定期券支給と実費精算の従業員が混在している場合には、前払い・後払いの区分確認や、旧運賃と新運賃の差額調整なども発生し、管理部門の負担はさらに大きくなります。
2026年3月の運賃改定に向けた通勤手当業務の流れ

2026年3月に予定されている運賃改定に向け、企業は通勤手当の見直しから支給まで一連の対応を進める必要があります。改定の影響を正しく把握し、誤りのない処理を行うためには、業務の流れを段階的に確認しておくことが重要です。
ここからは、実際の通勤手当業務の進め方をステップごとに解説します。
改定後の運賃を把握する
改定後の通勤手当業務を行う際は、事前に運賃を把握しておくことが大切です。直前になってから確認すると、差額精算などの追加対応が発生し、業務が煩雑化するリスクがあります。
理想的には、1月後半から改定後運賃の確認作業を始めるのが望ましいです。早めに情報を集めておけば、給与計算スケジュールに余裕をもてるため、担当者の負担を軽減できます。
具体的な運賃を把握するには、以下3つの方法があげられます。
- 経路検索ツールの活用
- JR東日本の改定率表をもとに算出
- 従業員からの申請をもとに収集
経路検索ツールの活用
改定後の運賃を把握する方法のひとつが、経路検索ツールを活用する方法です。経路検索ツールは、全国の路線データと運賃情報が掲載されているため、従業員の通勤経路を自動で検索できます。
また、改定前後の運賃を比較できる点も大きなメリットです。従業員数が多い企業では、手作業で路線や料金を調べるよりも、はるかに正確かつ効率的に手当額を確認できます。
ただし、改定直後は検索結果に新しい運賃が反映されていない場合もあるため、最新データへの更新状況を確認しながら利用することが重要です。
改定率表をもとにした算出
経路検索ツールに改定後の運賃がまだ反映されていない場合は、JR東日本が公表している改定率表を使って算出する方法があります。従業員ごとの現在の定期代や運賃に改定率を掛け合わせれば、おおよその新料金を把握することが可能です。
ただし、発表資料では「電車特定区間」や「山手線内」などの区分が幹線に統合されて記載されており、確認を怠ると誤差が生じる恐れがあります。とくにこれらの区分は改定率が高めに設定されているため、慎重にチェックすることが重要です。
経路検索ツールと併用すれば、データ反映の遅れにも柔軟に対応でき、給与計算前に必要な情報を確実に揃えられます。
従業員の申請
改定後の運賃を把握する方法として、従業員が各自で利用経路の新しい運賃を調べ、その内容を通勤手当申請に記載してもらうのもおすすめです。
この際、JR東日本が公開する運賃表や経路検索ツールの結果を添付してもらえば、担当者側でも金額の妥当性をスムーズに判断できます。
また、運賃改定後に購入した定期券のコピーを提出してもらう方法もあります。ただし、その場合はいったん改定前の定期代で支給し、後から値上げ分の差額を追加精算する必要がある点に注意が必要です。
従業員申請方式は、利用者自身が最新の情報を確認するため正確性が高い反面、担当者には申請内容のチェックや差額精算などを丁寧に行う体制づくりが求められます。
従業員の通勤手当データを更新する
改定後の運賃を把握したら、通勤手当を管理している表計算ソフトや人事・経理システムのデータを更新します。
このとき、とくに注意すべきポイントは次の2点です。
- 給与計算システムとの連携を忘れないこと
- 連携のタイミングに注意すること
まず、管理データを修正しても給与システムに反映されなければ誤支給につながります。必ず両者を正しく連携させることが重要です。
次に、反映のタイミングにも注意が必要です。改定後の運賃を早く上書きしすぎると、前払い分や直前の給与に誤った金額を適用してしまう恐れがあります。例えば、4月1日に改定がある場合、2月や3月の給与で改定後の定期代を誤って支給してしまうケースです。
こうしたミスを防ぐには、自社の通勤手当データがどのように管理されているのかを再確認し、更新の手順やスケジュールを明確にしておくことが欠かせません。
通勤手当を支給する
改定後の金額をデータに反映したら、実際の支給業務に移ります。この際は、改定前の支給額と比較し、誤りがないかを必ず確認することが重要です。金額のズレがあれば、従業員とのトラブルや差額精算の手間につながるため、最終チェックは欠かせません。
通勤手当の支給方法は、従業員の勤務形態によって異なります。
正社員など月20日前後出勤する従業員には、長期的な勤務を前提として定期代をまとめて支給する方法が主流です。多くの企業では6か月定期を基本としますが、3か月定期や1か月定期に合わせて支給するケースもあります。
一方、パート・アルバイトなど勤務日数が限られている従業員には、往復日額に実際の出勤日数を掛けて月ごとに後払いで精算する方法が一般的です。定期代を支給するよりも合理的となる場合が多いためです。
このように、運賃改定後の通勤手当は勤務形態や就業規則に応じて処理方法が異なります。従来の支給額との比較と勤務形態ごとの正確な計算方式を徹底し、誤りのない支給を行うことが求められます。
運賃改定による通勤手当業務の注意点

運賃改定に伴う通勤手当の処理では、通常の給与計算とは異なる特有のリスクが潜んでいます。対応を誤ると、誤支給や従業員とのトラブルにつながる可能性もあるため注意が必要です。
ここからは、担当者がとくに意識しておくべきポイントについて解説します。
自社の規定を再確認する
運賃改定に対応する際には、まず自社の通勤手当規定を確認することが大切です。通勤手当は労働基準法で義務付けられているものではなく、法律上は必須の手当ではありません。多くの企業が慣習的に導入していますが、実際の支給条件や範囲は就業規則や賃金規程によって定められています。
具体的には、利用経路が「経済的かつ合理的」であるかを基準に支給額を判断する必要があります。とくに最寄駅が複数ある場合、最安経路を優先するのか、時間短縮を考慮するのかなど、社内ルールを明確にしておくことが欠かせません。
さらに、新幹線や特急の利用をどの条件で認めるかといった長距離通勤者への対応も、あらかじめ規定しておけば従業員への説明がスムーズになります。
対応方法について従業員に通知する
運賃改定の対応方法を従業員に通知することも重要です。対応方法を明確に通知しておかなければ、申請方法やタイミングなどで誤解が生じ、申請漏れや支給遅延につながる恐れがあります。
具体的には次の内容を周知しておくと安心です。
- 申請や手続きを行う対象者
- 定期券コピーなど、申請や確認に必要な書類や情報
- 変更に伴う社内処理のスケジュール
とくにスケジュールについては、給与計算のタイミングや差額精算の可能性も含めて具体的に示すことで、従業員との相互理解が深まり、円滑な業務進行につながります。
余裕をもって業務に取り組む
運賃改定に伴う通勤手当業務は、余裕をもって準備することで不測の事態に備えられます。2025年9月7日時点では、JR東日本から具体的な実施日はまだ公表されていません。そのため、給与計算のタイミングによっては正確な料金を事前に把握できない場合も想定されます。
とくに定期代を前払いで支給するケースでは、新料金が不明のまま適用できず、後日差額を追加で支給するといったイレギュラー対応が必要になる可能性があります。
したがって、詳細なスケジュールの発表を待つだけでなく、あらかじめ想定されるシナリオを洗い出すことが重要です。給与計算や申請処理の流れを事前に確認しておくことで、混乱を最小限に抑えられます。
必要に応じて随時改定の手続きをとる
通勤手当は「固定的賃金」に含まれるため、運賃改定によって金額が増減した場合、社会保険の標準報酬月額を変更するための随時改定(月額変更届)の対象となる可能性があります。随時改定とは、昇給などで賃金が大きく変動した際に、定時決定を待たずに標準報酬月額を見直す仕組みです。
随時改定の要否を判断する流れは、次のとおりです。
- 通勤手当が変更された月を「変動月」とする
- 変動月から3か月間の給与を確認する
- 標準報酬月額において2等級以上の増減があるかを確認する
- 条件を満たした場合、4か月目に「月額変更届」を作成し、日本年金機構に届け出る
なお、定期代を3か月や6か月分まとめて支給している場合は、1か月あたりに換算した額を各月の報酬として扱います。また、自動車通勤者についても、ガソリン単価を基準に支給額を算出している場合、単価の変動によって支給額が大きく変わるときは随時改定の対象です。
このように、運賃改定による通勤手当の変動は、給与計算だけでなく社会保険の手続きにも影響があります。改定の発生月と支給月を正確に把握し、条件を満たす場合は速やかに対応することが求められます。
専用ツールを活用し業務効率化を図る
運賃改定に対応する際には、専用ツールを活用することで処理が格段にスムーズになります。従業員数が多い企業ほど通勤手当の確認や更新作業は複雑化し、担当者の負担やヒューマンエラーのリスクが高まります。
専用ツールを導入すれば、こうした煩雑な作業を効率化し、正確かつ迅速な処理が可能です。とくに大企業など従業員が多い場合は、その効果がより大きく発揮されます。
さらに、給与計算も可能なシステムを利用すれば、通勤手当だけでなく役職手当や残業手当、社会保険料の算出なども自動化できます。勤怠管理システムと連携できるタイプであれば、運賃改定といったイレギュラーな対応にとどまらず、日々の労務管理全般も効率化可能です。
人事管理システム「ADPS」が正確かつ迅速な給与計算業務を実現

運賃改定のたびに必要となる通勤手当の見直しは、担当者にとって負担の大きい業務です。従業員ごとの経路や金額を確認し、表計算ソフトやシステムのデータを修正したうえで給与計算に反映させる必要があり、処理が遅れれば誤支給や差額精算につながる恐れがあります。
こうした課題に対応できるのが、カシオヒューマンシステムズ株式会社が提供する人事管理システム「ADPS(アドプス)」です。
ADPSは累計5,000社以上の導入実績を持つ人事管理システムで、通勤手当を含む各種手当を自動計算し、給与計算システムと連携して正確に反映できます。運賃改定後の新料金をデータに組み込むことで、従業員一人ひとりの通勤手当を迅速に再計算でき、入力や転記の手間を減らせます。
さらに、従業員情報を一元管理する仕組みを備えているため、通勤手当の変更に限らず給与や社会保険の手続きともスムーズに連動し、業務の効率化を実現可能です。通勤手当業務の負担を軽減し、正確で迅速な給与計算を実現したい企業にとって、ADPSは信頼できる選択肢のひとつです。
通勤手当業務のポイントを把握し運賃改定に備えよう

2026年3月に予定されているJR東日本の運賃改定は、企業の通勤手当業務に少なからず影響を及ぼします。改定率や実施時期を正しく把握し、前払いと後払いの違いを理解したうえで、従業員への案内やデータ更新を早めに進めることが重要です。対応を後回しにすると、誤支給や差額精算のトラブルにつながり、担当者の負担が増す原因にもなりかねません。
自社の規定を確認し、従業員との認識を揃えることで混乱を防ぎ、必要に応じて随時改定の手続きを行うことも求められます。さらに、専用ツールや人事システムを活用すれば、改定時の処理を効率化し、正確性とスピードの両立が可能になります。
運賃改定は避けられないものだからこそ、早めに準備し、自社に適した体制を整えることが、円滑な通勤手当業務のためにも重要です。
カシオヒューマンシステムズコラム編集チームです。
人事業務に関するソリューションを長年ご提供してきた知見を踏まえ、
定期的に「人事部の皆様に必ず今後の業務に役立つ情報」を紹介しています。