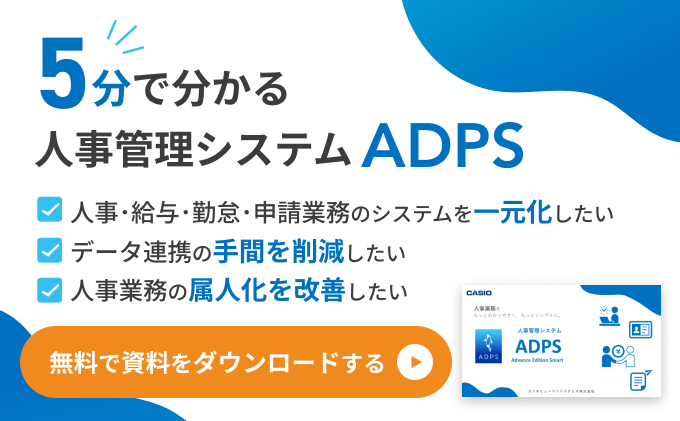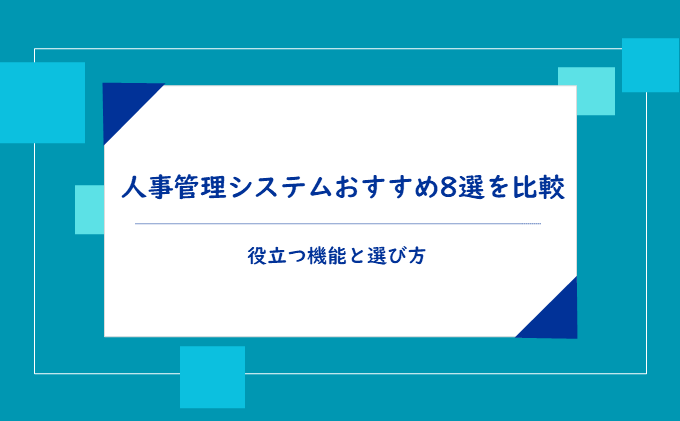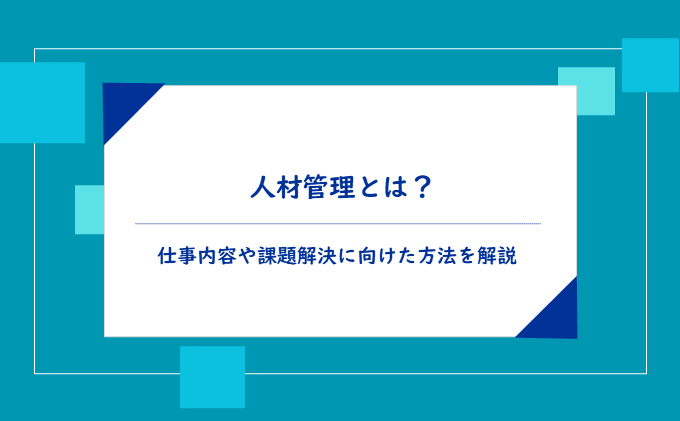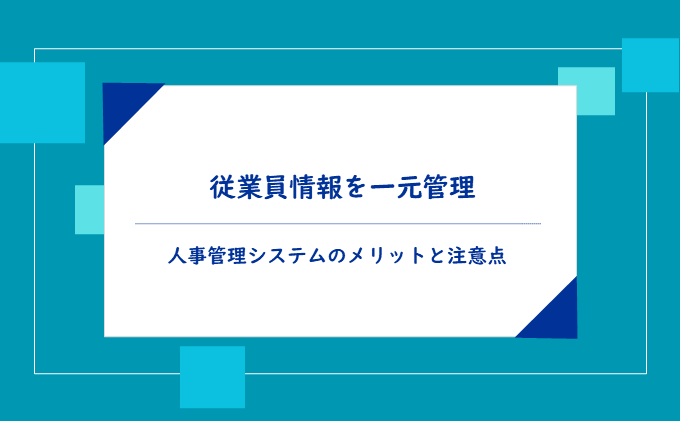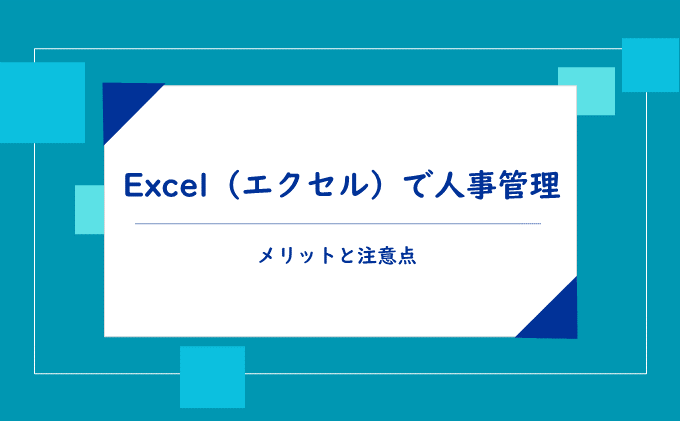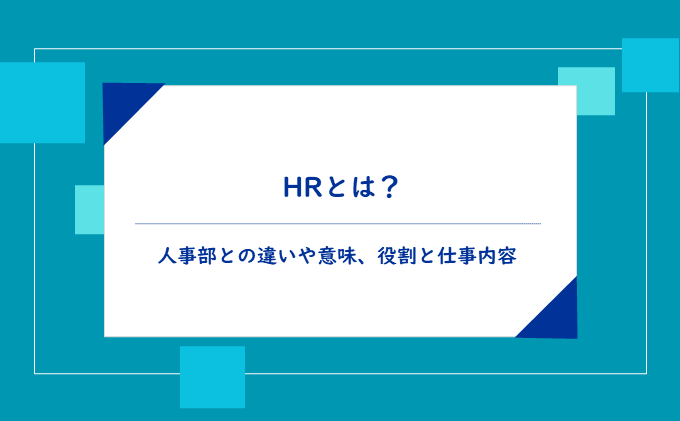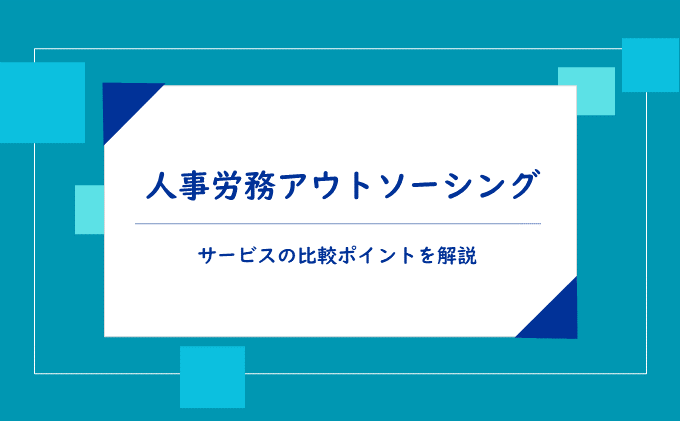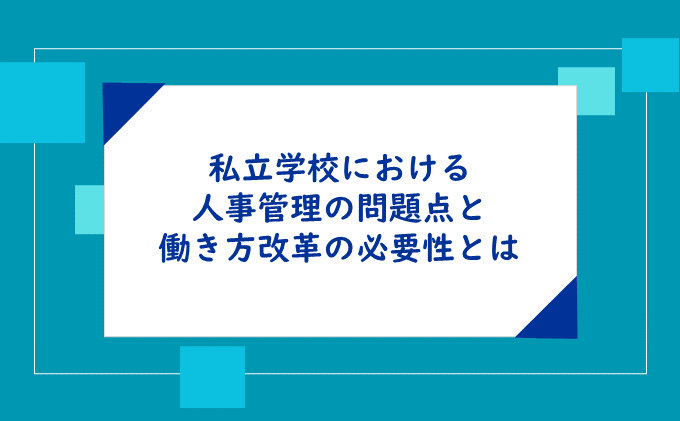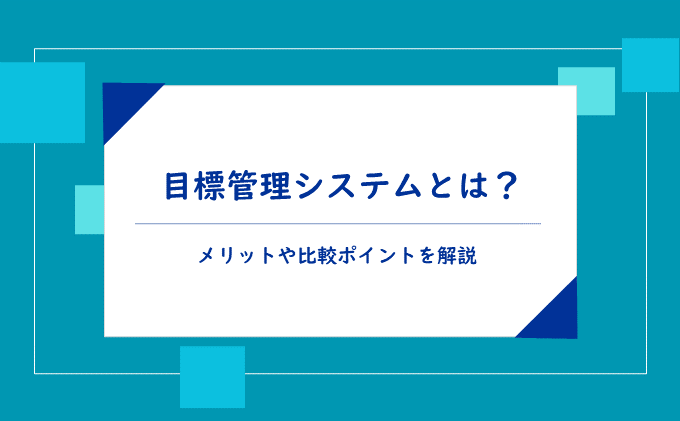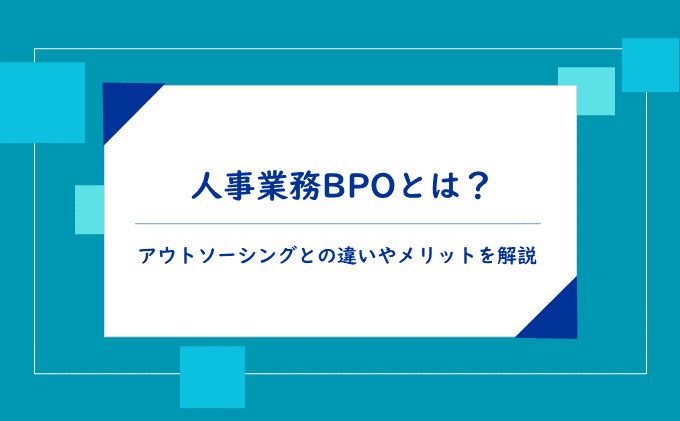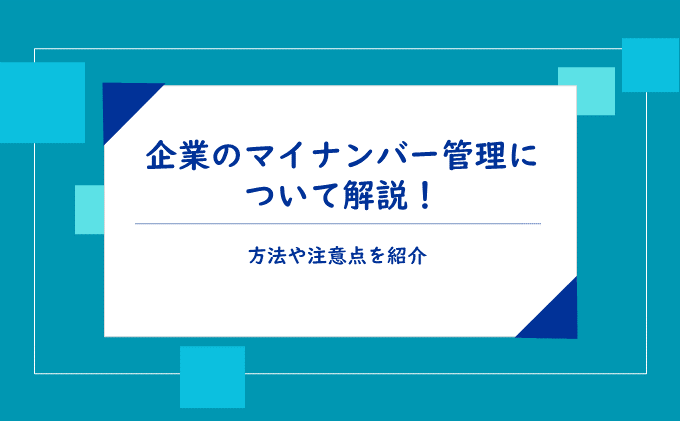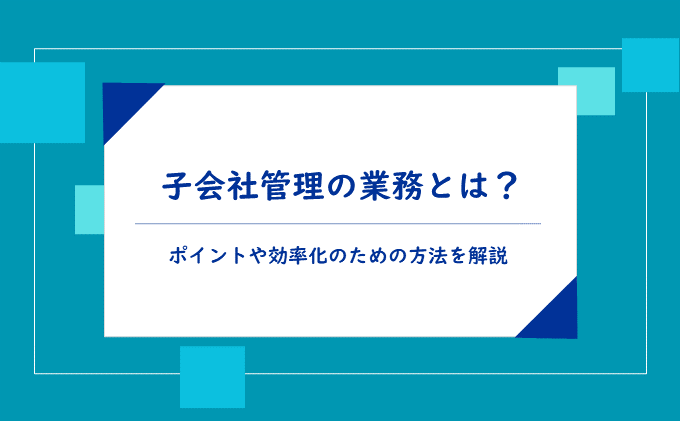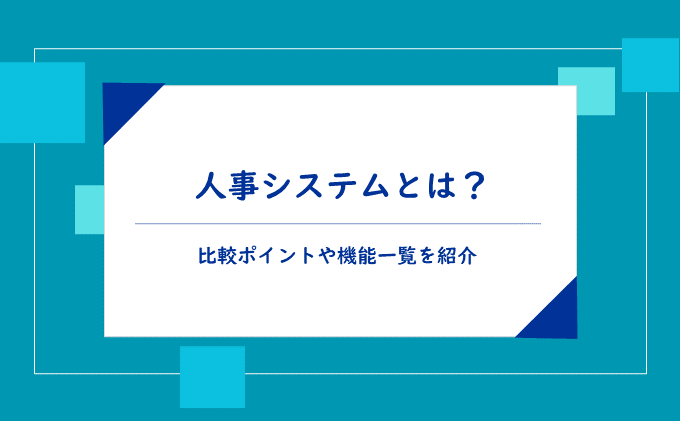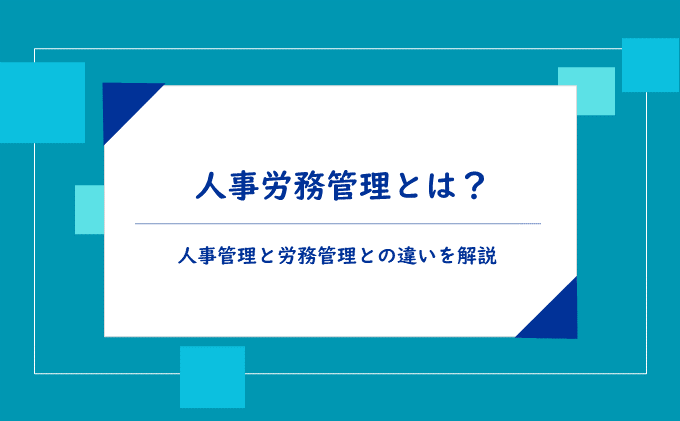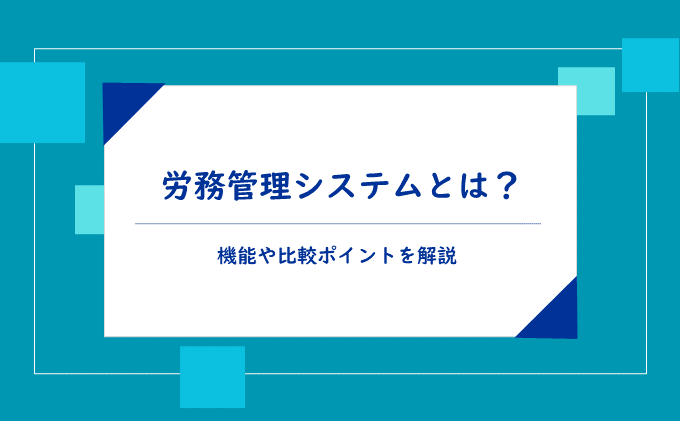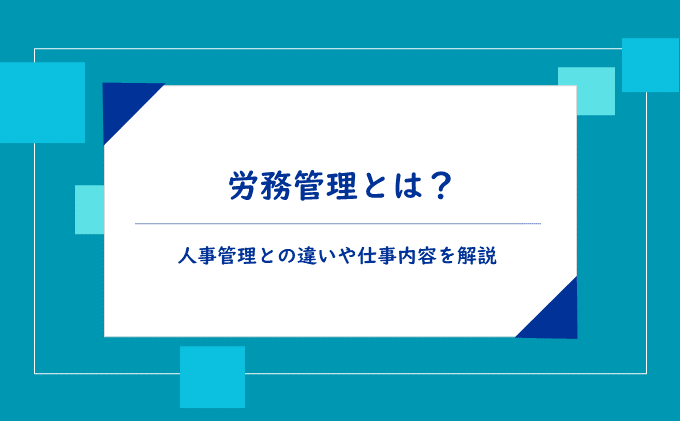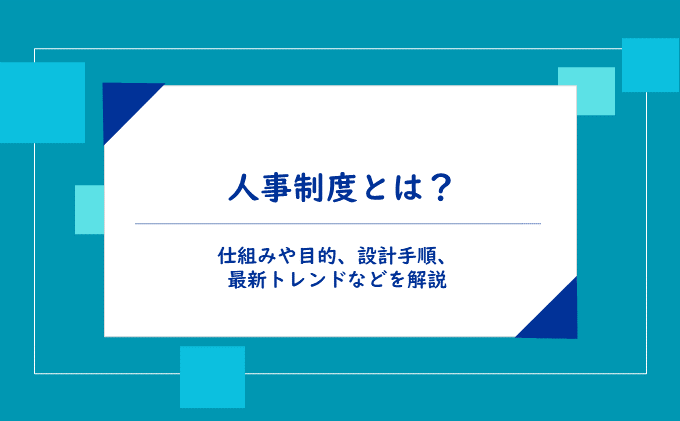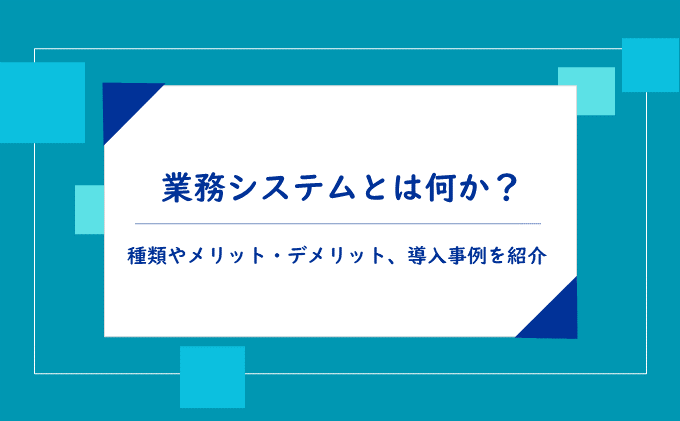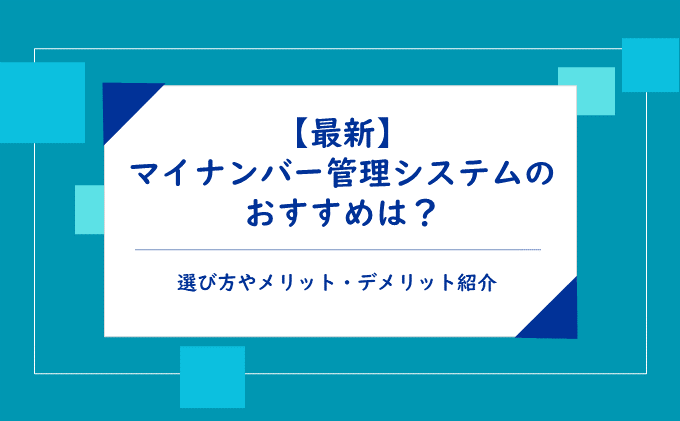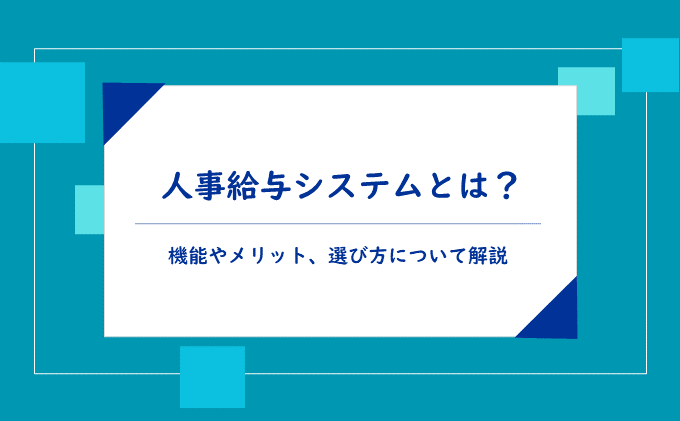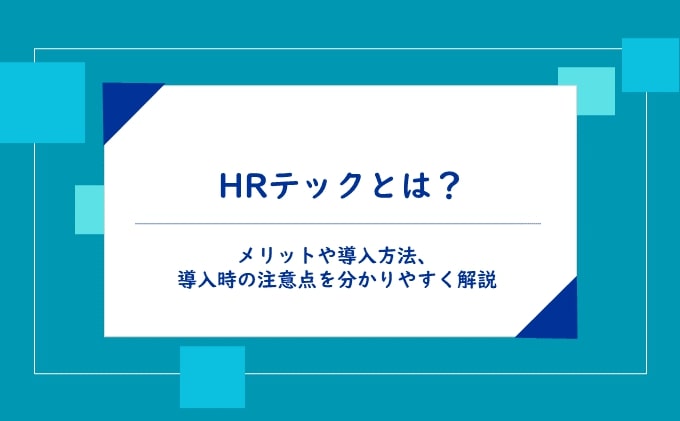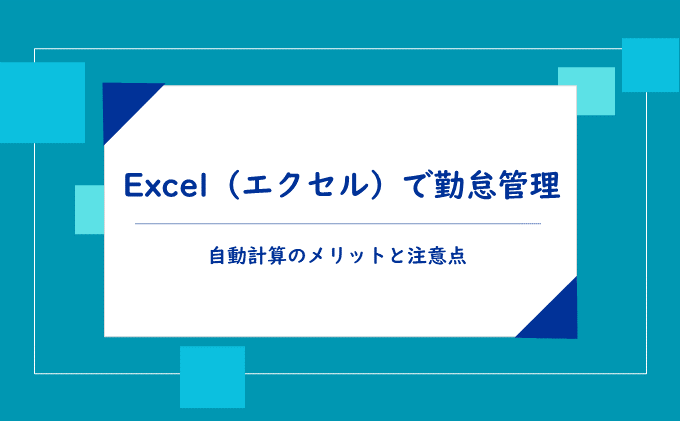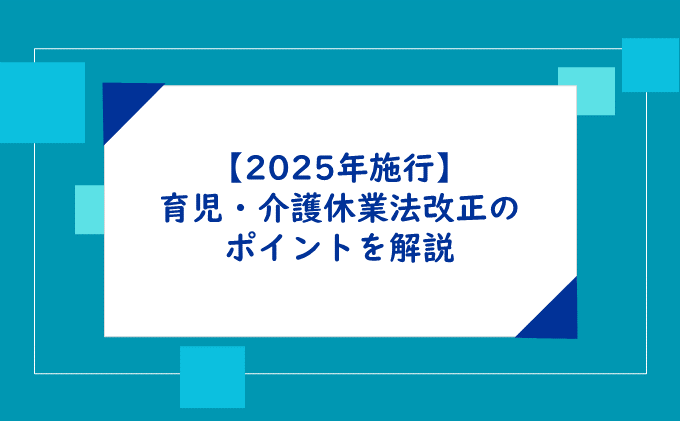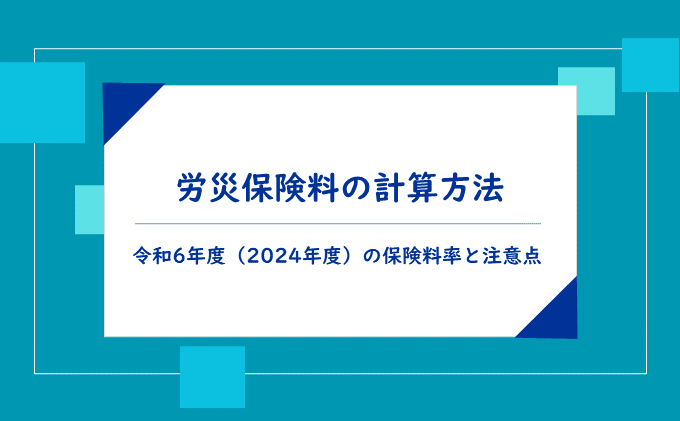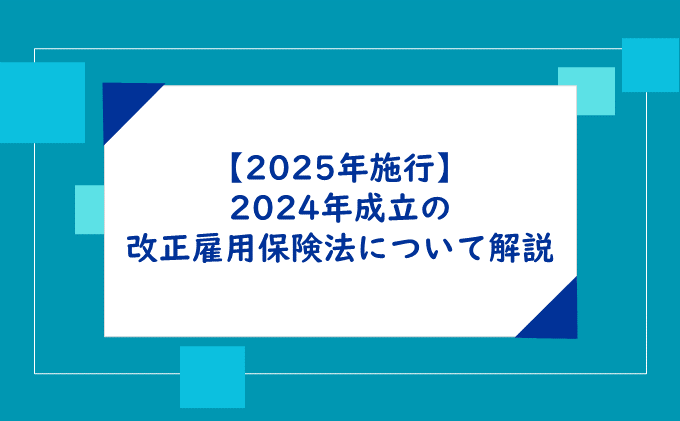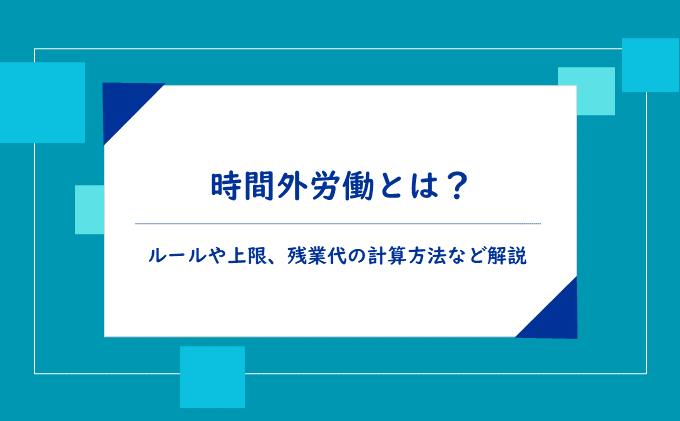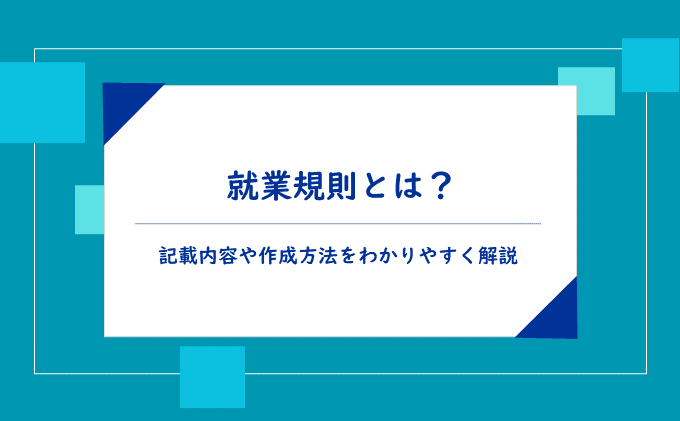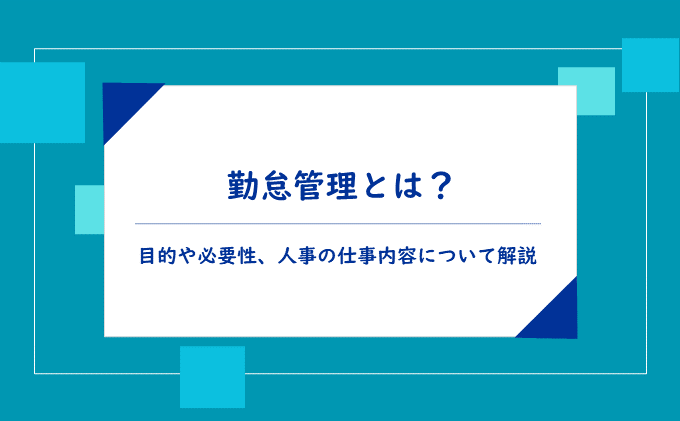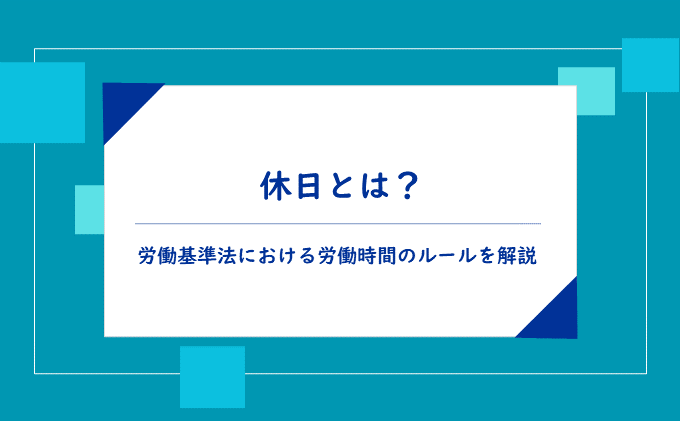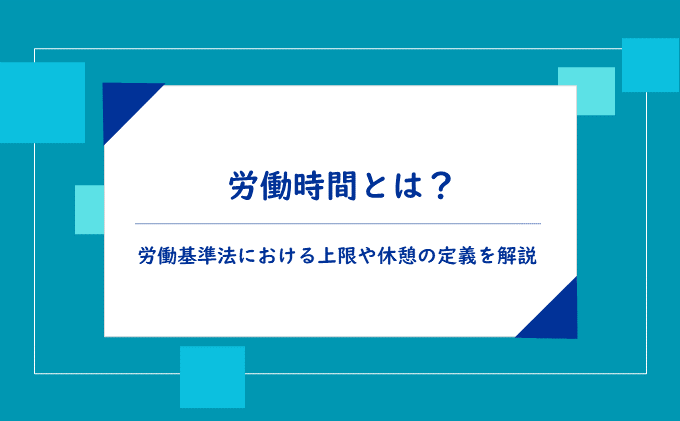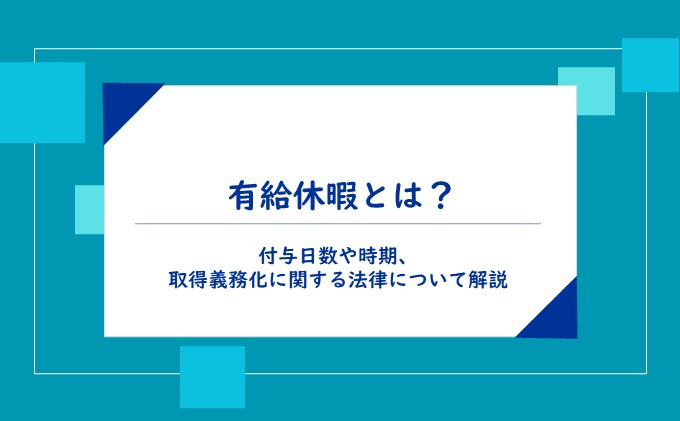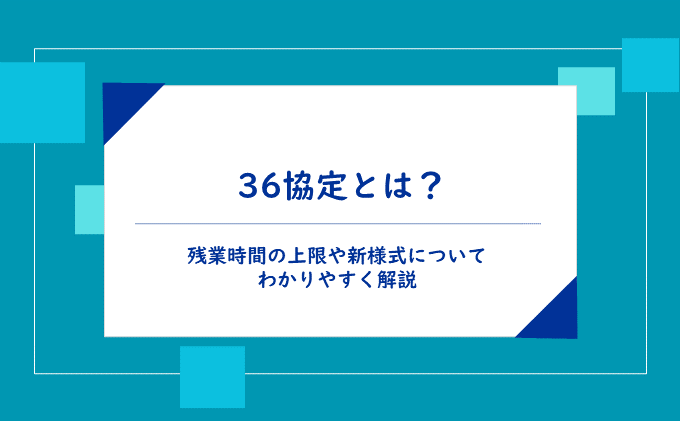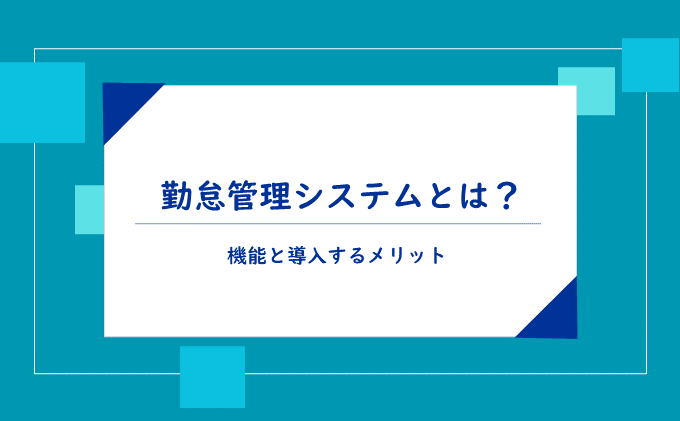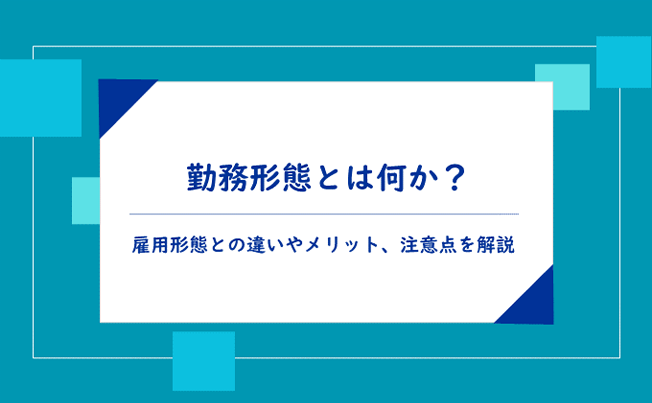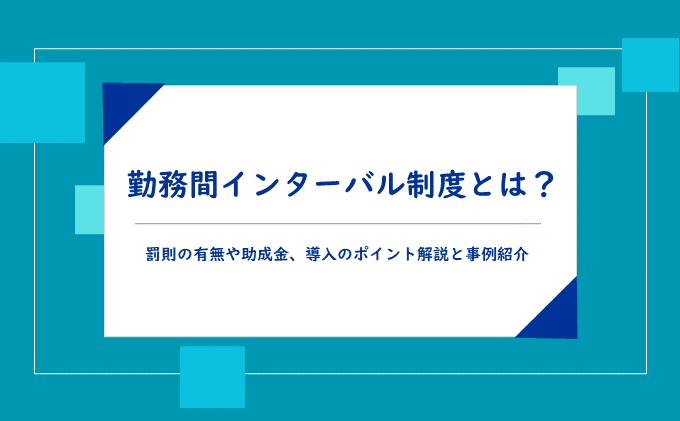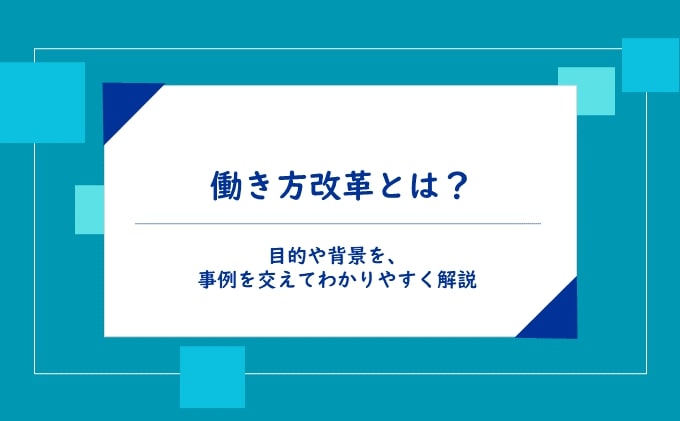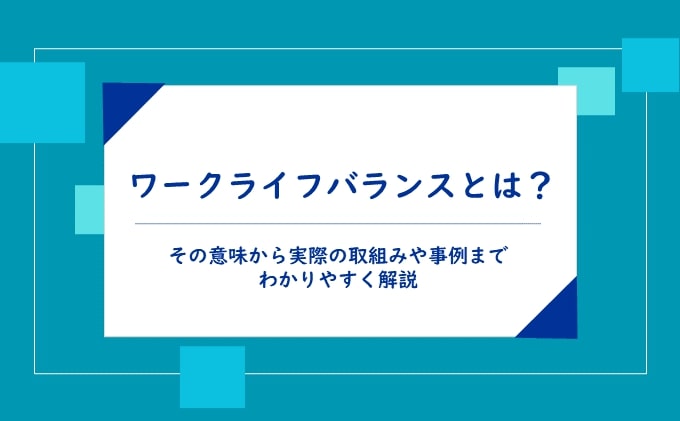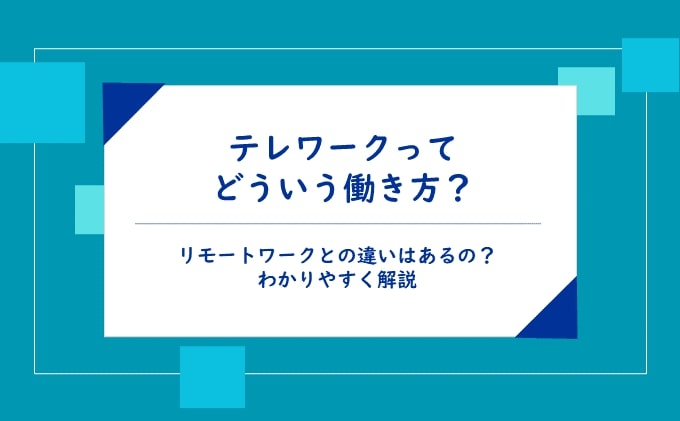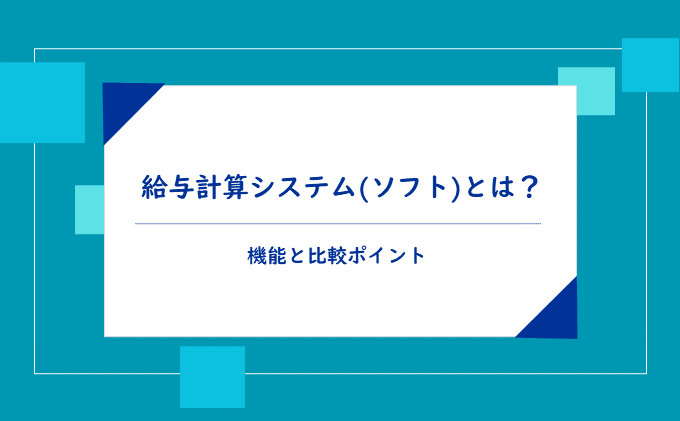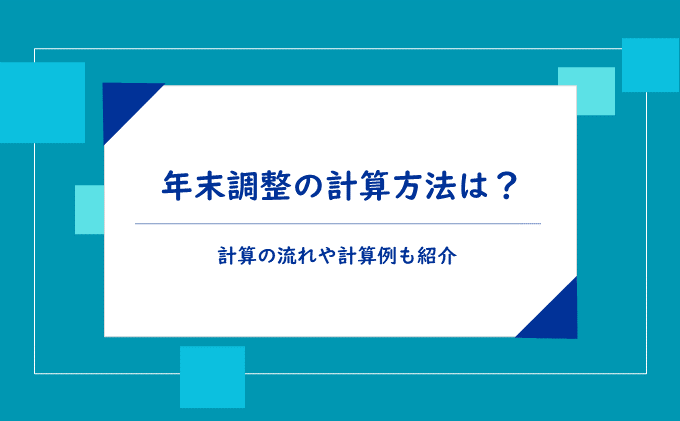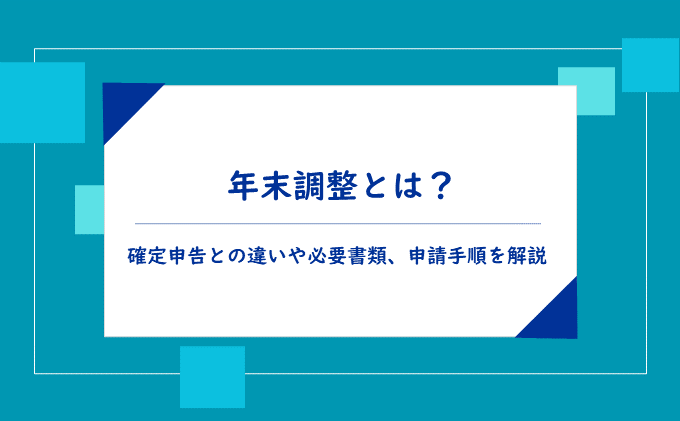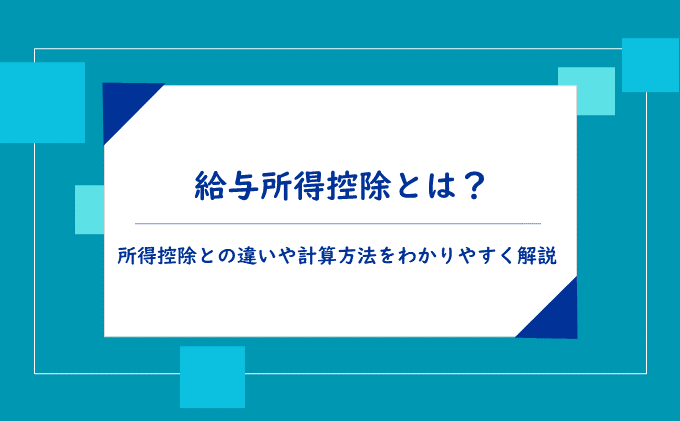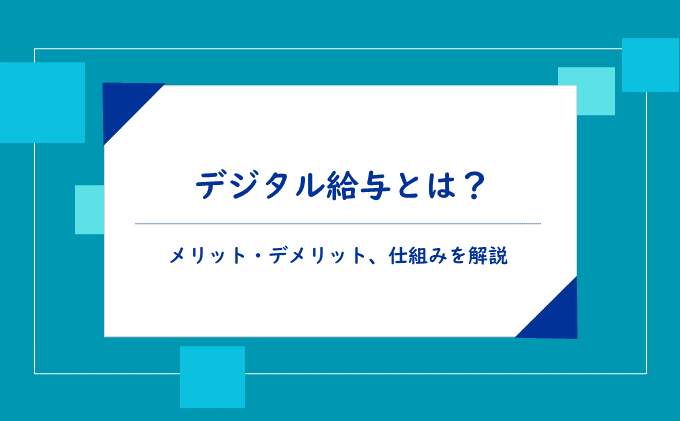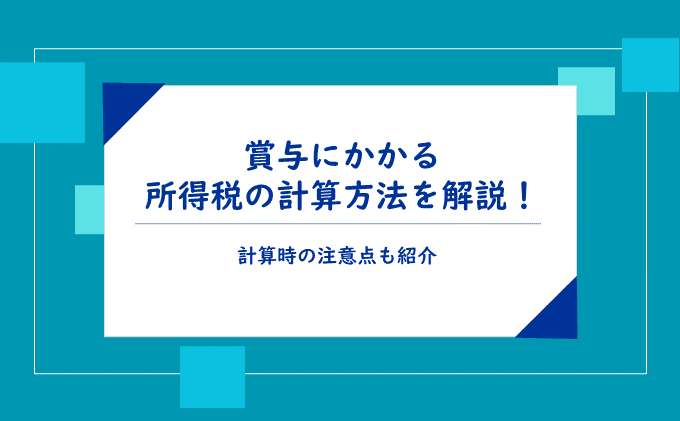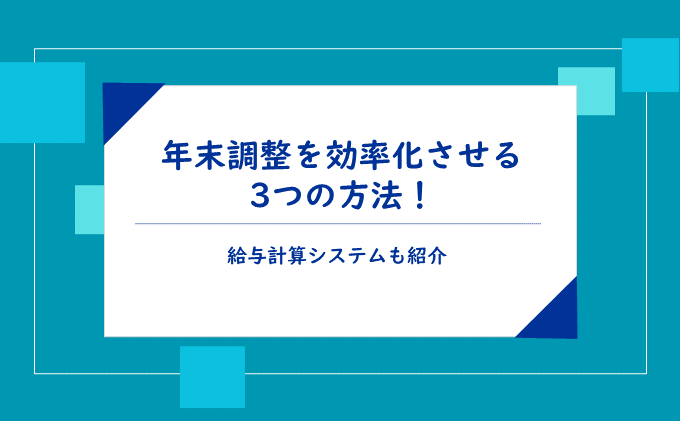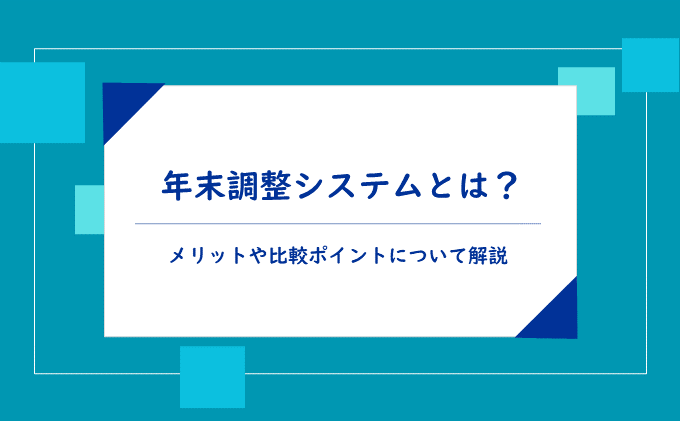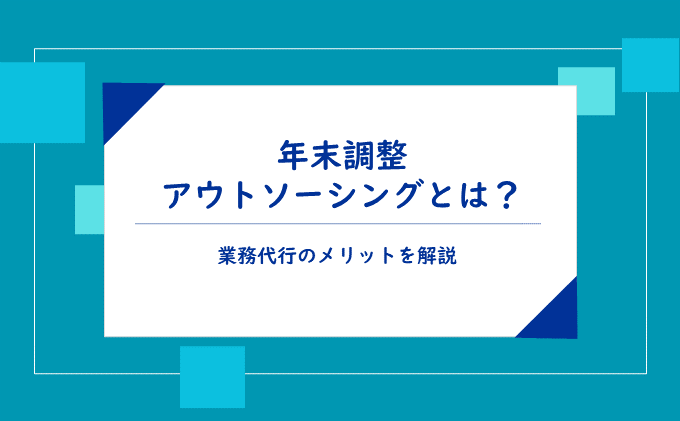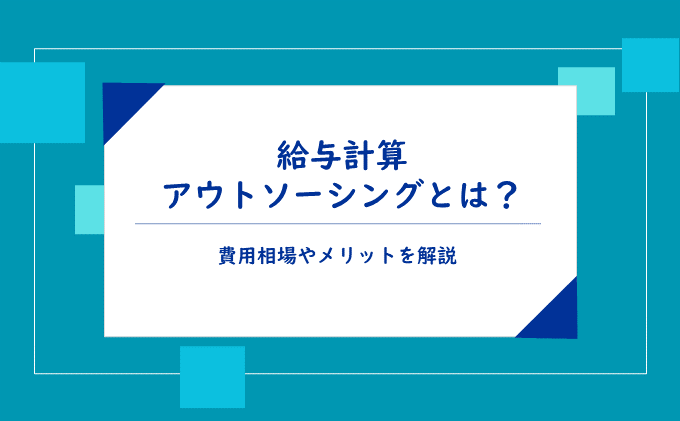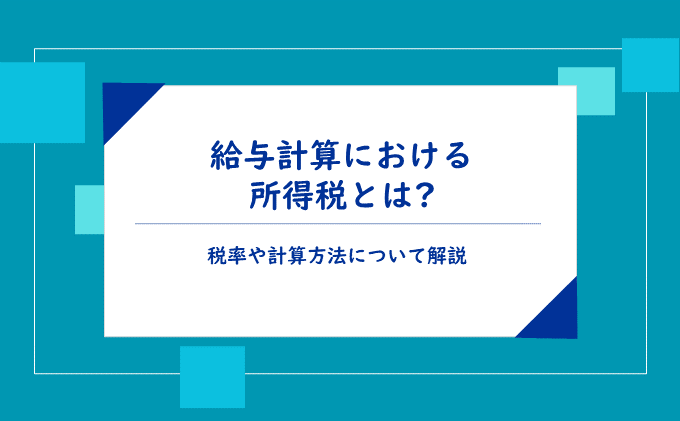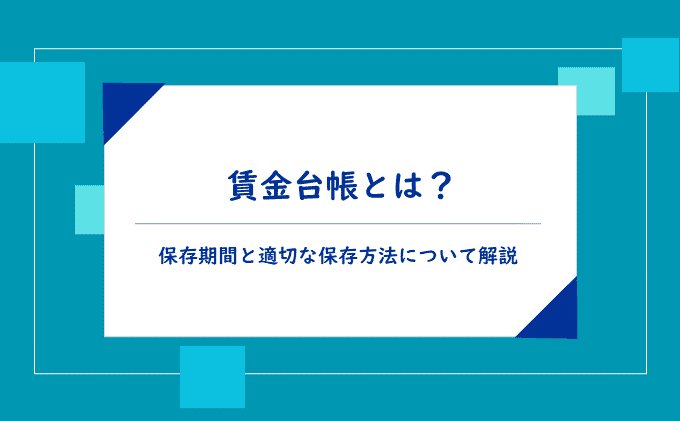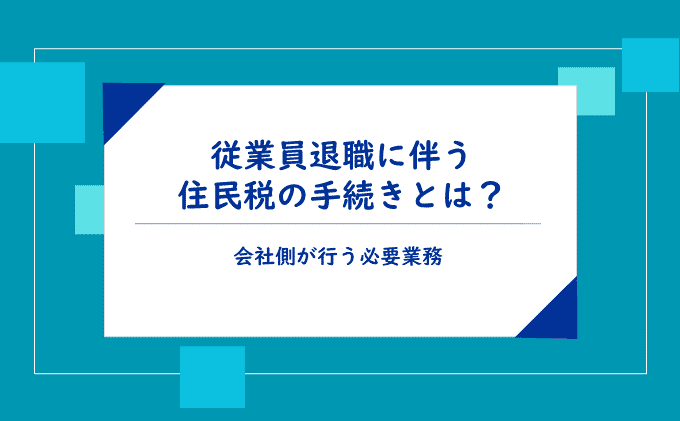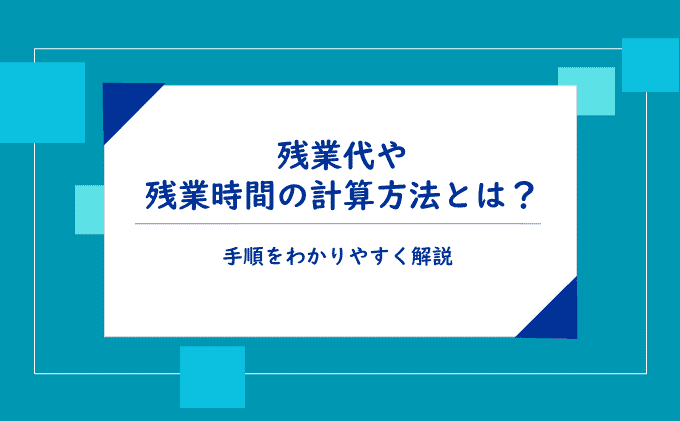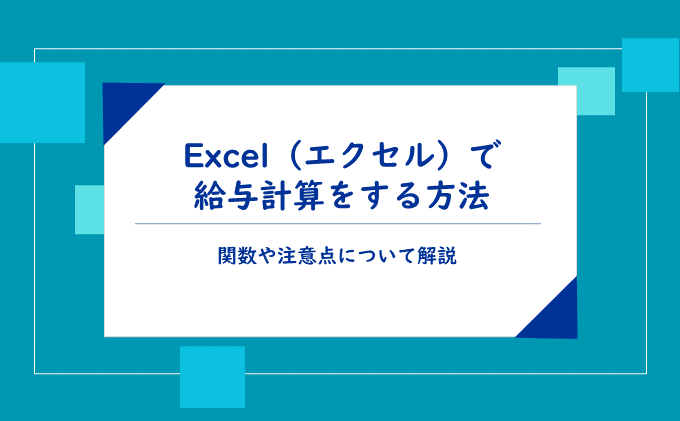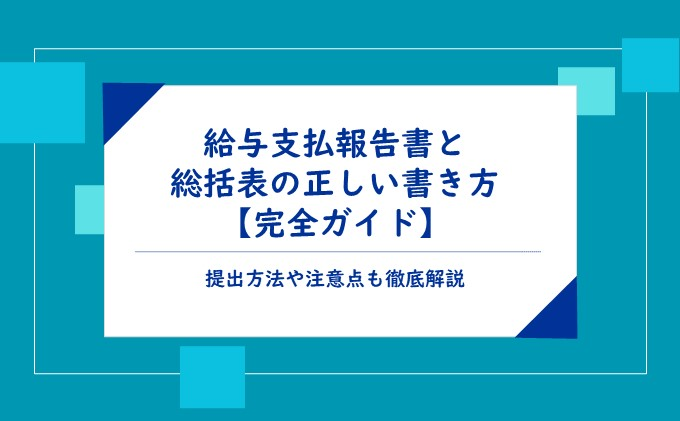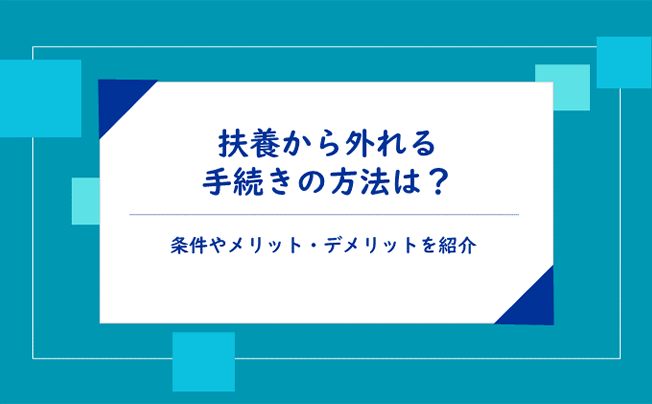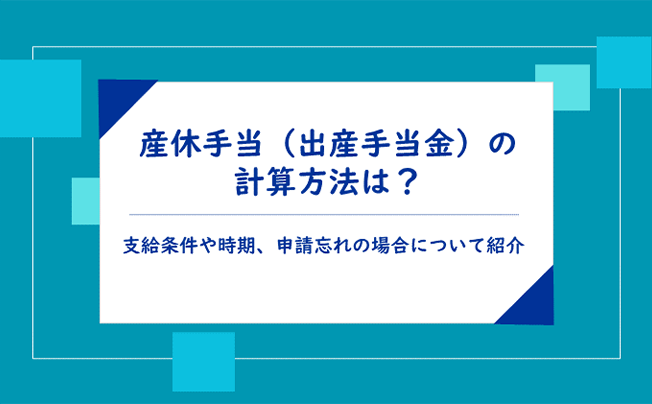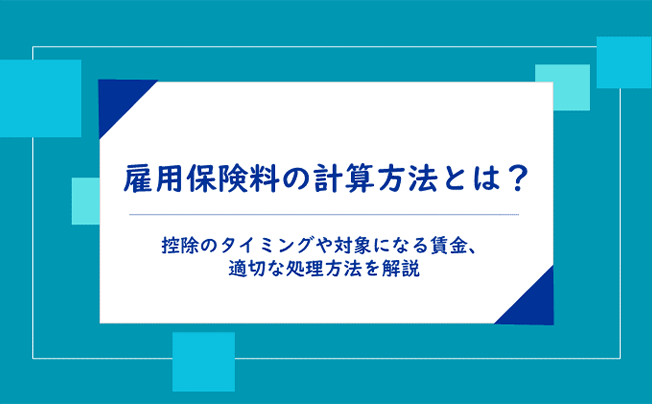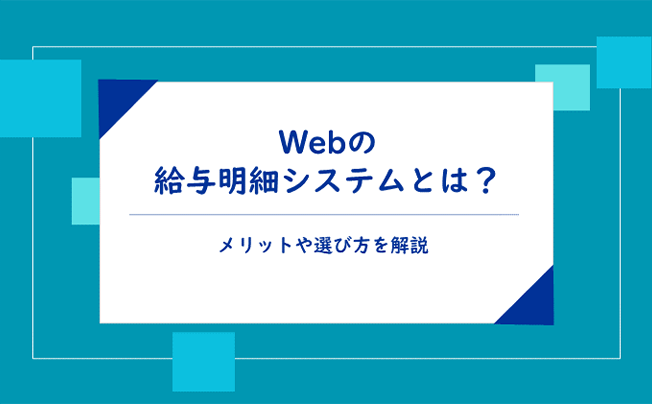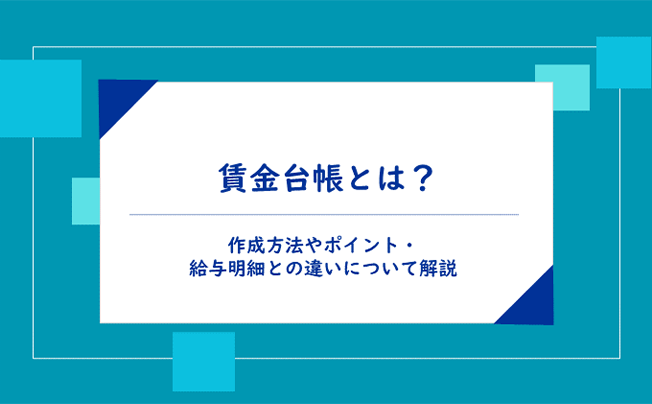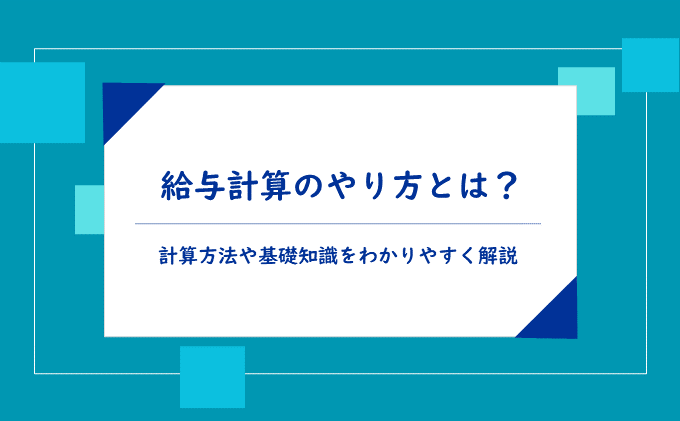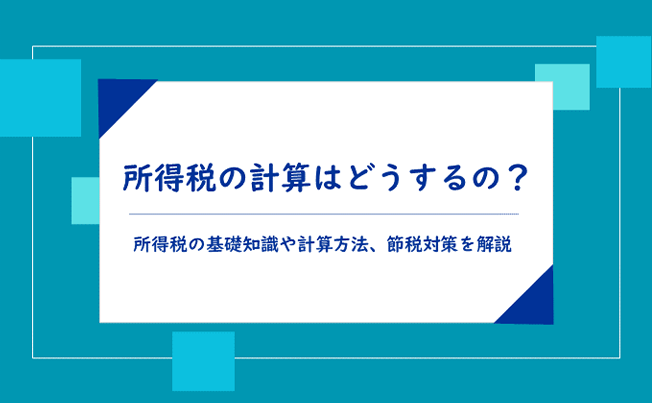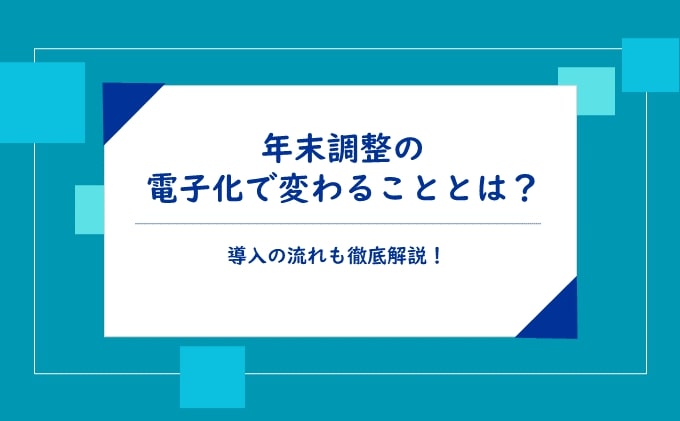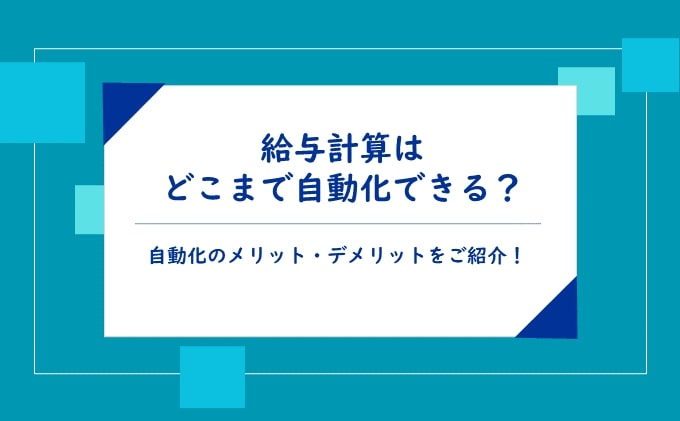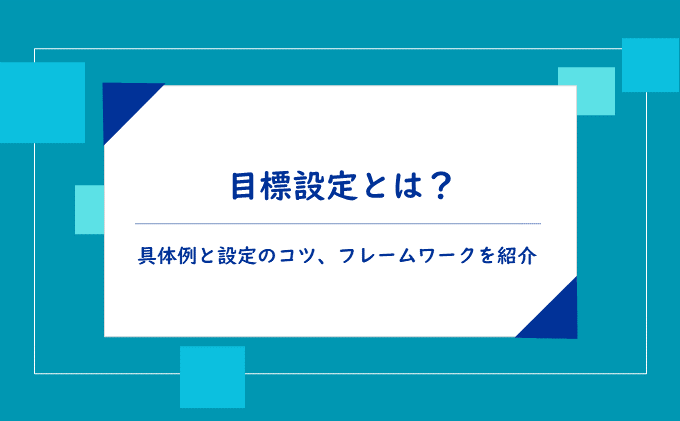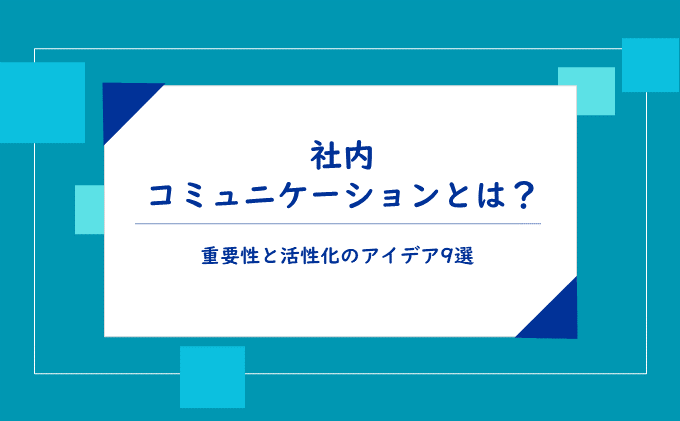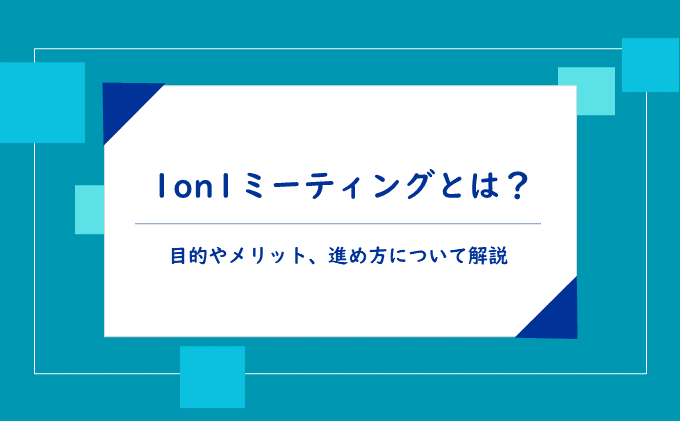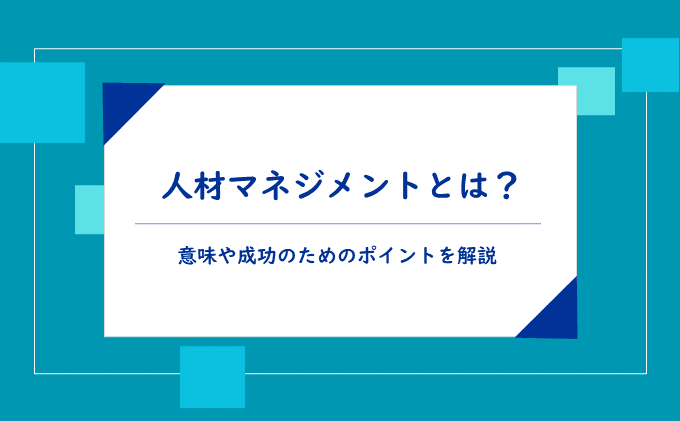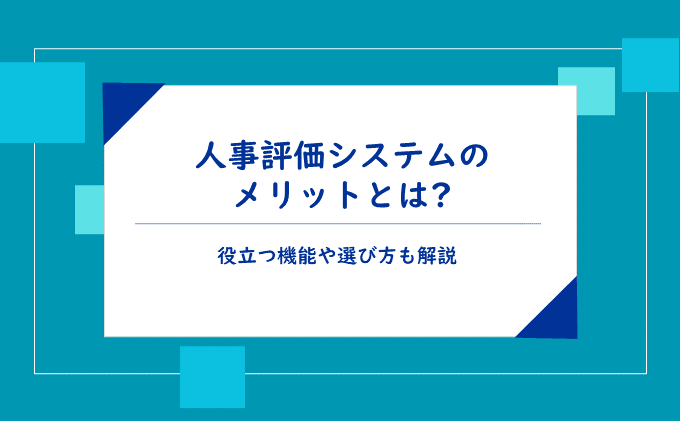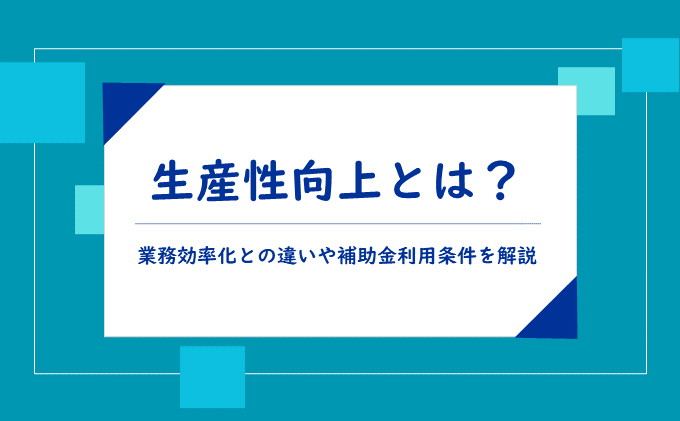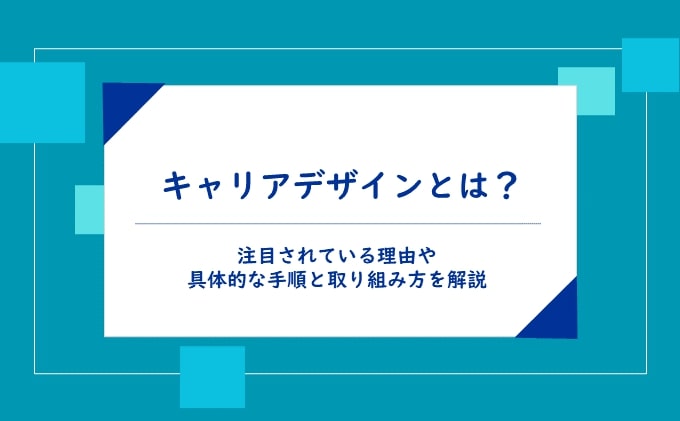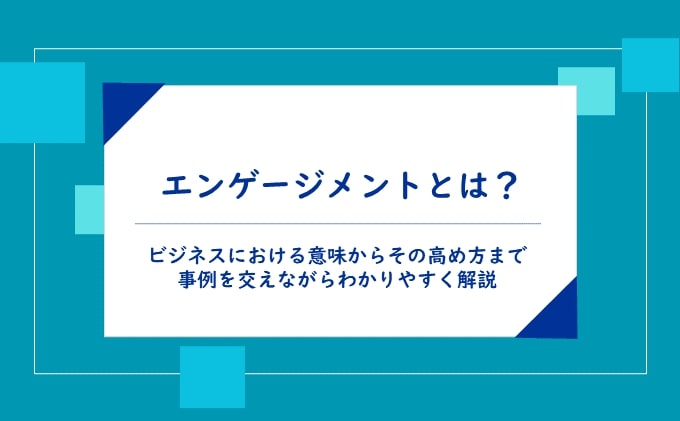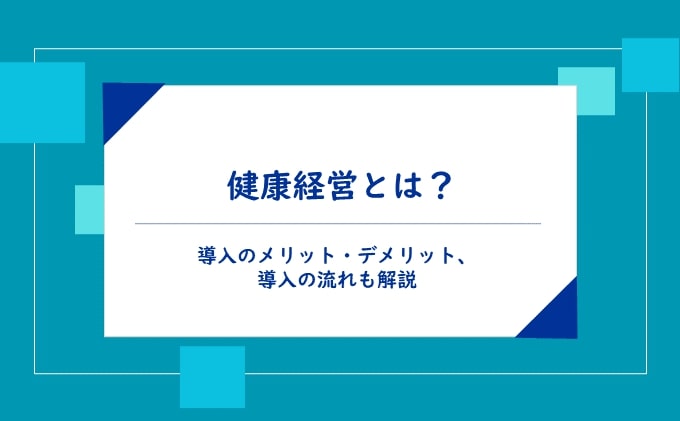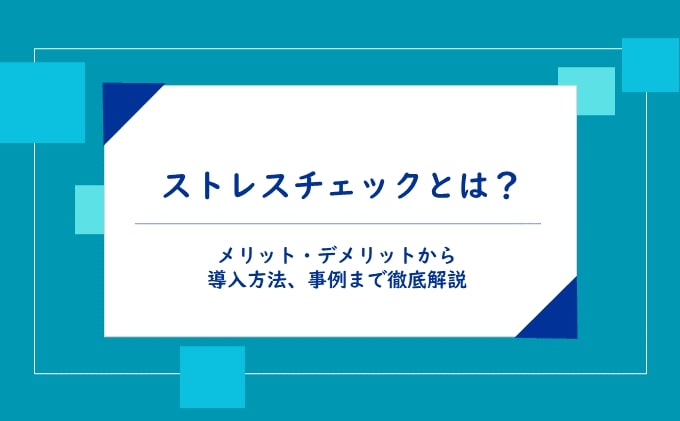大企業におすすめの給与計算システムは?比較ポイントを紹介
2025.10.30
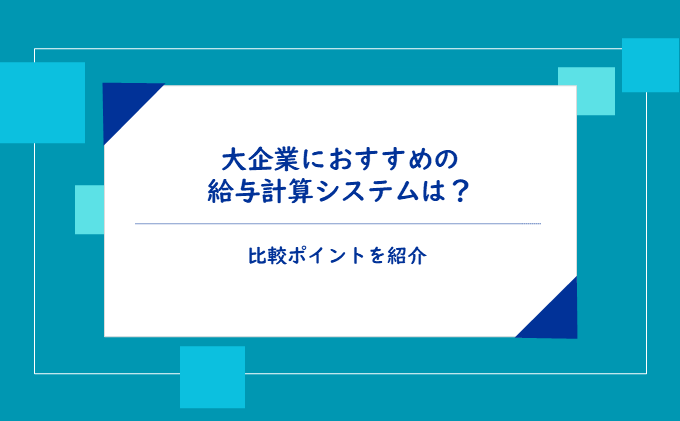
従業員数や拠点数が多い大企業は、人事管理が複雑になる傾向があります。人事業務の効率化には、給与計算システムの導入が一策です。本記事では、大企業向けの給与計算システムについて、比較ポイントや導入事例などを交えて解説します。
目次
給与計算システム(給与計算ソフト)とは

給与計算とは、従業員に支払う給与を正確に計算する業務のことです。支払金額の計算のみでなく、時間外労働や欠勤をした分の調整や、税金や社会保険料の控除なども行うことが一般的です。
給与計算には、手書きやExcelなどの表計算ソフトを使用する場合があります。しかし、従業員数が多かったり拠点が複数あったりする大企業では、給与計算システムが活用されていることが一般的です。
なお、「大企業」には法的な定義はありません。中小企業基本法が定める中小企業者の定義を超えるものを大企業と呼びます。同法による中小企業者の定義は以下のとおりです。
| 製造業その他 | 資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社、常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 |
|---|---|
| 卸売業 | 資本金の額または出資の総額が1億円以下の会社、常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
| 小売業 | 資本金の額または出資の総額が5,000万円以下の会社、常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 |
| サービス業 | 資本金の額または出資の総額が5,000万円以下の会社、常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
給与計算システムとは、給与の総額や各種の控除などの計算を自動で行うシステムのことです。給与計算ソフト、給与システム、給与管理システムなどと呼ばれることもあります。
残業代や社会保険料の計算、各種手当の付与など、給与計算業務は煩雑です。給与計算システムを導入することで、業務の効率化が期待できます。
なお、給与計算システムはサーバーを自社で持つかどうかで「オンプレミス型」と「クラウド型」に分かれます。それぞれにメリットとデメリットがあるため、自社に合う方式を選ぶことが重要です。
機能面で分けると、給与計算に絞り込んだ「給与計算特化タイプ」、基幹系情報システム(ERP)を搭載した「ERPタイプ」、給与計算に加えて勤怠管理などもあわせてできる「人事給与タイプ」に大別できます。以下で、それぞれについて解説します。
種類は「オンプレミス型」と「クラウド型」
オンプレミス型は、サーバーやネットワーク環境、ソフトウェアなどを自社で保有し、管理する形式です。「プレミス(Premises)」とは、「建物」や「構内」を意味します。
自社内で構築から運用まで行うため、設計の自由度が高い特徴があります。インターネットを使わず、社内で閉じた環境にできるため、セキュリティを強固にできる点もメリットです。
ただし、導入コストは高くなりがちです。また、運用に必要な人員を確保しなくてはならないこともデメリットとして挙げられます。ただし、セキュリティ性能を高くすれば外部からのアクセス設定が煩雑になり、パートナー企業などと連携が難しくなる可能性もあります。
一方のクラウド型は、インターネットを介してベンダーの用意したサーバーやソフトウェアなどを利用する形式です。サーバーや運用担当者などを自社で用意する必要がなく、迅速に利用を開始できます。
インターネットに接続できる環境があればどこでも使える点がクラウド型のメリットです。また、法改正などでプログラムに更新が必要になった場合も、ベンダー側が対応してくれます。さらに、導入コストが低いこともメリットです。
ただし、クラウド型は自社でシステムを構築しないため、カスタマイズ性は高くありません。セキュリティ性能はサーバーなどを管理するベンダー側の対応に左右されます。
また、初期コストは低く済む一方、月額や年額などの使用料がかかる点には確認が欠かせません。使用料は利用人数ごとに決められているケースがあり、その場合は人数が増えるほどランニングコストがかかります。
給与計算システムの主なタイプと機能
給与計算システムやソフトの主なタイプは以下のとおりです。
- 機能を給与計算に絞ったタイプ
- 企業内の情報を一元管理するタイプ
- 給与と勤怠のデータを連携させたタイプ
それぞれの特徴やメリット、デメリットを順に説明します。
給与計算特化タイプ
機能を給与計算に絞り込んだものが給与計算特化タイプです。機能が限定されているため、比較的低コストで運用できます。シンプルな操作性を求める企業や、小規模な企業におすすめのタイプです。
システムによっては、マイナンバーの管理や社会保険関連の書類作成を支援する機能なども搭載されています。ただし、勤怠管理など、他のシステムとの連携が必要な点に注意が必要です。給与計算システムの導入前に、稼働中の他のシステムとのデータ連携が可能かどうかの確認が欠かせません。
関連記事:給与計算のやり方とは?計算方法や基礎知識をわかりやすく解説
ERPタイプ
ERPとは「Enterprise Resource Planning」の略で、直訳すると「企業資源計画」ですが、通常は「基幹系情報システム」と訳されます。ERPは、人事給与だけでなく、会計や販売、物流など、企業内で部門ごとに管理されていた情報資源を一元的に連携させようとするものです。
企業が持つ各種データを全体として管理し、リアルタイムに連携して効率的に運用しようとするシステムで、複雑な給与体系や福利厚生制度などにも対応可能です。生産や契約の管理など、人事給与以外の業務効率化にも期待できます。
ERPの目的は、縦割りで管理されていた各種データに横串を刺し、効率的な連携を進めることです。システムに合わせて業務フローを修正する手間がデメリットになる可能性があります。
また、コストが高くなることにも注意が必要です。給与計算システム導入の際には、自社で求める機能と費用のバランスを検討してください。
人事給与タイプ
人事給与タイプは、給与計算に加えて勤怠管理や税金の計算など、人事まわりの関連業務をあわせて処理できるシステムです。給与計算と勤怠管理が別システムになっている場合、従業員を個別に登録しなければならず、システムの連携に手間がかかります。
なお、人事給与タイプは従業員の情報をひとつに集約できるため、人事関連の業務を他システムと連携せずに処理できます。また、拡張性を備えており、段階的に機能を増やしていくことが可能です。雇用形態の多様化など、大企業が抱える給与計算業務の課題解決に期待できます。
関連記事:人事給与システムとは?機能やメリット、選び方について解説
大企業が抱える給与計算業務の課題

大企業は従業員数や支店などの拠点が多いことがありますが、給与計算業務の課題につながりがちです。大企業が抱える主な給与計算業務の課題は以下のとおりです。
- 雇用形態の多様化
- 多拠点管理の複雑化
- 法改正への随時対応
これらの課題について、順に説明します。
雇用形態の多様化
多くの従業員を擁する大企業では、雇用形態が多様化している事例が少なくありません。フルタイムとパートタイムの従業員が混在していたり、テレワークを中心に働く従業員がいたりすることも一般的です。
同じパートタイムの従業員でも職種や勤続年数が違えば時給は異なります。また、フレックスタイム制を採用している場合は、残業代の計算が特殊です。テレワークが常態化している従業員に通勤手当を支給するかどうかは、ケースによって判断が分かれます。
多様な働き方をする従業員がいる大企業の給与計算業務は複雑化することが通例です。複雑な業務を手作業で行っていると、数字の転記などで人的ミスが発生するリスクが高まります。ミスが起これば修正処理に時間がかかるため、給与計算システムの導入は有力な選択肢です。
多拠点管理の複雑化
正確に給与計算を行うためには、勤務時間や残業時間、休日などの把握が重要です。国内外に多数の拠点を持つ大企業では、支店や工場などごとに勤怠を管理している場合があります。
とくに、タイムカードや従業員の申告による管理方式を採っていると、勤怠情報の管理がリアルタイムでできません。人事担当者が各拠点の情報をリアルタイムに把握できない場合、過重労働の覚知や給与計算事務の遅れなどが起こる可能性があります。
なお、海外拠点がある場合は、現地の法規制や労働慣行との調整、為替レートの確認なども必要になるため、業務がさらに煩雑になります。
法改正への随時対応
労働や給与に関係する法令が改正された場合、企業側は迅速に対応しなければなりません。近年、建設業などでの労働時間の上限規制が適用されたり、短時間労働者に対する社会保険の強制適用が拡大されたりしています。
大企業にはコンプライアンス(法令遵守)が強く求められます。法改正への対応を怠ると企業のイメージダウンにもつながりかねません。
大企業の複雑な給与計算も、システム導入で正確かつ効率的に。数百人、数千人規模の従業員データを一括管理し、人為的ミスや法改正対応の不安を解消できます。
詳しい内容はこちらからご確認ください!
大企業におすすめ┃給与計算システム(ソフト)の導入メリット

従業員や拠点数が多く、複雑な処理が必要になりがちな大企業の給与計算には、給与計算システムの導入がおすすめです。メリットとしては、以下のようなものがあります。
- 業務効率化に期待できる
- 幅広い業務に対応できる
- 多拠点の情報を一元管理できる
- 法改正に正確かつスムーズに対応できる
- 情報セキュリティの強化につながる
それぞれのメリットについて、以下で説明します。
業務効率化に期待できる
大企業が給与計算システムを導入するメリットのひとつが、業務効率化です。多様な働き方をする従業員がいる場合でも、条件を設定すれば職種や部署ごとに計算ルールを適用することが可能です。
アルバイト、正社員、定年退職後の嘱託契約など、幅広い雇用形態に対応できます。給与計算システムの特徴は、大量のデータを一括処理できることです。また、勤怠管理システムと連携することで、多数の従業員の勤務時間などを正確かつ効率的に処理できます。
幅広い業務に対応できる
幅広い機能を備えるERPタイプを導入すれば、給与計算以外の業務効率化にも対応可能です。勤怠管理システムや経理システムとの連携により、給与計算から支給までがスムーズに進められます。
また、人事や労務に関する定型業務も効率化できれば、担当者に生産性が高い業務を割り当てられます。さらに、保有資格や経験職種などの人材データと給与データを連携することで、キャリアパスと昇給スピードの関係性の分析なども可能です。
多拠点の情報を一元管理できる
国内外に拠点を多数持つ大企業は、各拠点の情報を本社で一元管理することが重要です。海外拠点がある場合は、国ごとに異なる税制や法規制、為替レートなどの扱いに神経を使うことがあります。
他国の税制や為替レートの動きなどにも対応できる柔軟な給与計算システムを導入すれば、各拠点の情報を一括して管理し、全社の給与計算業務が円滑になります。
法改正に正確かつスムーズに対応できる
法改正に対して迅速に対応でき、正確な給与計算を行える点も給与計算システム導入のメリットです。クラウド型のシステムの場合、法改正や税率変更などの対応はベンダー側で行います。
労働法制や税制などは、毎年のように改正されています。税率などの計算式を修正し忘れるなどのミスがあると、計算のやり直しや再確認などが必要になり、現場が混乱するかもしれません。
また、ミスの発生は法律違反につながりかねません。行政指導を受けたりSNSで拡散されたりすると、企業のイメージダウンに直結します。コンプライアンス重視の観点からも、給与計算システム導入がおすすめです。
情報セキュリティの強化につながる
大企業には多くの従業員が所属しているため、多くの個人情報を管理しなければなりません。個人情報には、氏名や住所はもとより、給与データのようなセンシティブなものもあります。情報漏洩やデータ損壊などがあった場合、自社に与える悪影響は計り知れません。
セキュリティ機能が充実したシステムを採用すれば、漏洩などのリスクは軽減されます。また、データのバックアップをしっかり保存できるシステムであれば、担当者が安心して業務に専念できます。
大企業におすすめの人事給与システムADPSの詳しい内容はこちらからご確認ください!
大企業向け給与計算システム(ソフト)の比較ポイント

数多くある給与計算システムやソフトを比較する際のポイントとして、機能やコストが挙げられます。以下で、選び方を比較ポイントごとに解説します。
搭載している機能
自社で必要とする機能が備わっているかどうかは、重要なポイントです。給与計算に特化したシステムが必要なのか、全社的なデータ連携を見据えたシステム構築を検討しているのかで、選ぶシステムやソフトは異なります。
必要以上に機能が多いタイプを導入すると、機能面やコスト面に無駄が生じるおそれがあります。自社がどのような機能を必要としているかを、導入前に精査することが大切です。
他システムとの連携性
他システムとの連携を前提に検討している場合は、データのスムーズなやり取りができるか、連携に必要なソフトウェアのインターフェースが用意されているかなどの比較も必要です。勤怠管理システムと連携すれば、勤怠データを自動で取り込んで給与計算に反映できます。また、人事管理システムと連携することで、人事データの登録が一度で済みます。
なお、連携による利便性の向上を享受するためには、既存システムとの互換性の確認が重要です。データ連携するために別のコストがかかったり業務フローが増えたりしないか、注意が必要です。
コストパフォーマンス
給与計算システムにかかるコストは直接的な利益を生み出さないため、コストパフォーマンス(費用対効果)を慎重に見積もる必要があります。
オンプレミス型とクラウド型で、導入にかかるコストは異なります。クラウド型は、月額や年額でランニングコストが発生する点に注意が必要です。従業員数が増えると使用料が高くなる従量料金制のシステムもあります。
導入したシステムは、数年使い続けることが一般的です。コストパフォーマンスが悪いものを採用すると、数年単位でムダを生み続けることになります。
そのため、導入の際には、経営計画を検討のベースにする必要があります。将来的な従業員数増減の見込みや事業拡大の計画を組み込んだコストの見積もりが重要です。
大企業での導入実績
給与計算システムの導入にあたっては、自社の規模と同程度の企業が採用しているかどうかも比較のポイントです。他社の導入実績も参考にしてみてください。
なお、大企業で導入実績があるシステムは、複雑な条件の給与計算に対応できます。システムによっては導入事例を公表しているものもあります。
大企業向け給与計算システムの導入事例

近畿圏を中心に、全国でホームセンターを展開するコーナン商事株式会社は、1999年に給与計算システムを導入しました。同社が採用したのはカシオヒューマンシステムズの「ADPS(アドプス)」です。
コーナン商事の店舗数は641か所あり、アルバイトやパートタイマーを含めた雇用者数1万1,562人(いずれも2025年2月末、雇用者数は期中平均)を擁する大企業です。店舗が多く雇用形態もさまざまなため、管理業務の負担が重かったといいます。
同社がADPSを導入する決め手になったのは以下の2点です。
- 専任チームによるサポートがあり、システム移行で本来業務が圧迫されない
- 旧システムの独自機能やカスタマイズをそのまま生かせる
同社はADPSの導入により、1時間かかっていた人事情報の取り込みが15分に、30分かかっていた計算が5分ほどにそれぞれ短縮できました。大幅な業務効率化を実現できたようです。また、資格や履歴などの従業員データも連携させることで、幅広い活用を図っています。
「ADPS(アドプス)」が大企業の複雑な業務をサポート

カシオヒューマンシステムズ株式会社が提供する人事管理システム「ADPS」は、1990年の登場以来、累計5,000社を超える企業に採用されてきた実績を持ちます。給与、就業、マイナンバー関連などの煩雑な人事業務を効率的にサポートできる点が特徴です。
蓄積された人事データを基に、さまざまな角度から従業員検索が可能なほか、給与明細の電子化にも対応しており、業務コストの削減や従業員の利便性向上をバックアップできます。
給与計算システムで大企業の幅広い業務を効率化

給与計算業務には迅速さと正確性が求められます。従業員数や拠点数が多く、雇用形態が多岐にわたる大企業であれば、給与計算システムの導入が有効です。
給与計算システムには、計算に特化したタイプや、他のシステムと連携して幅広い業務に対応できるタイプなど、複数の種類があります。業務の効率化だけでなく、情報の一元管理やセキュリティ強化にも期待できます。
なお、給与計算システムを導入する際には、自社で必要とする機能の洗い出しや、コスト面での検討が必要です。人事業務の効率化や従業員の生産性向上を求めるのであれば、給与計算システムの導入を検討してはいかがでしょうか。
カシオヒューマンシステムズコラム編集チームです。
人事業務に関するソリューションを長年ご提供してきた知見を踏まえ、
定期的に「人事部の皆様に必ず今後の業務に役立つ情報」を紹介しています。