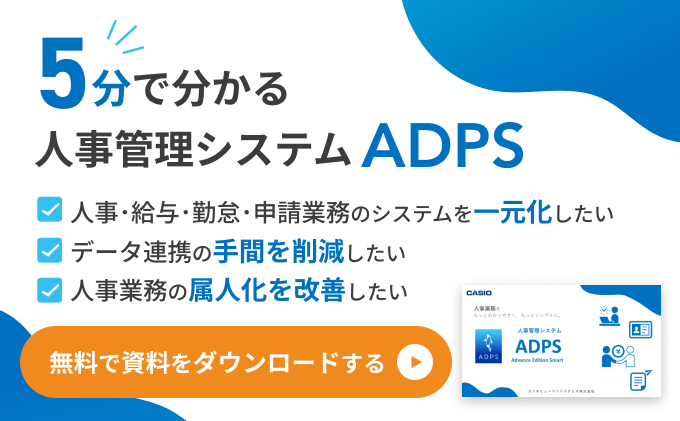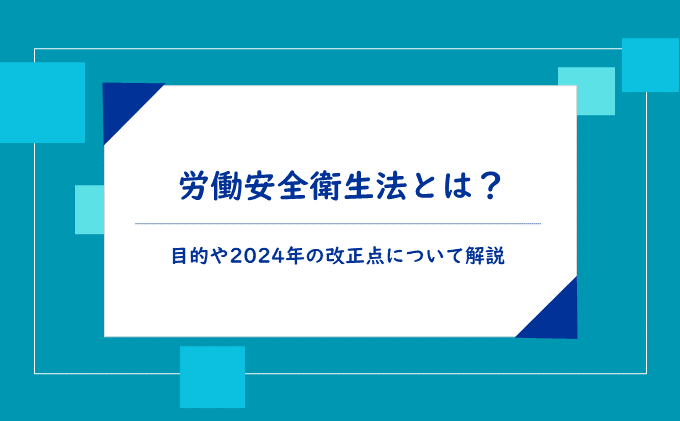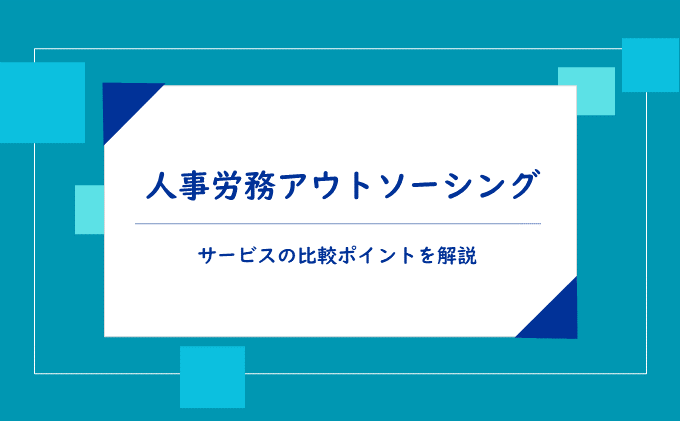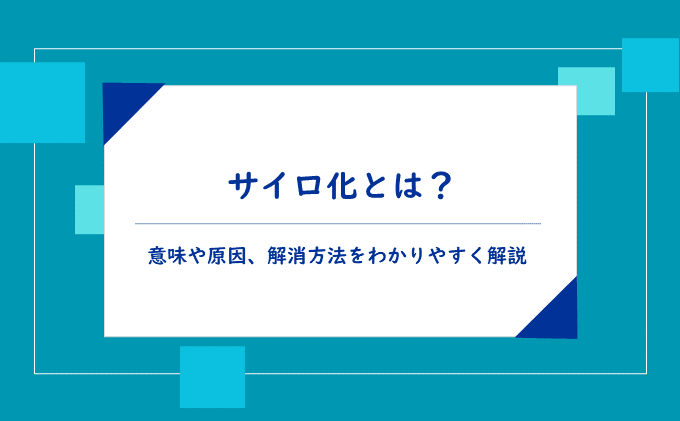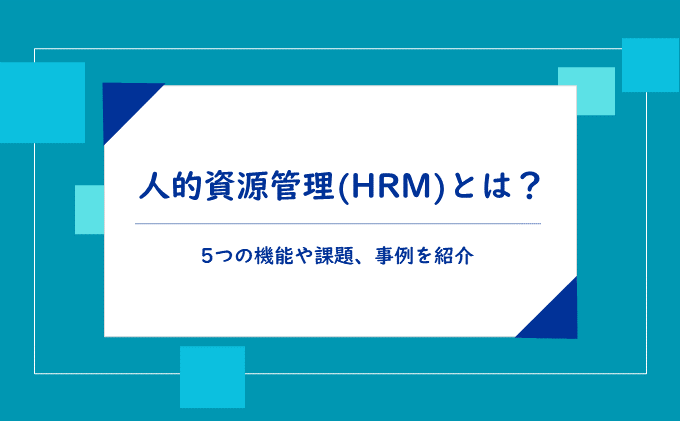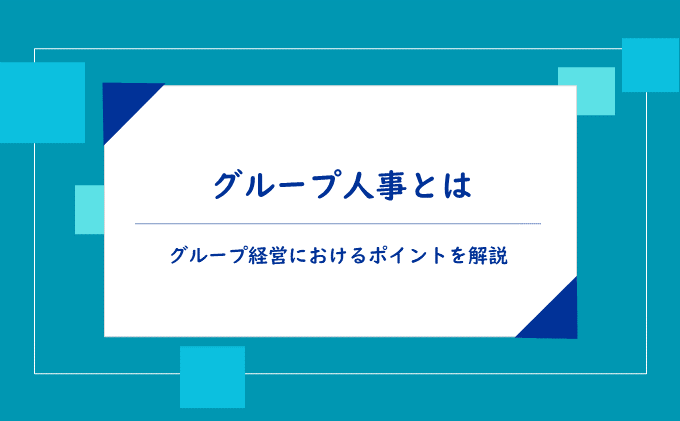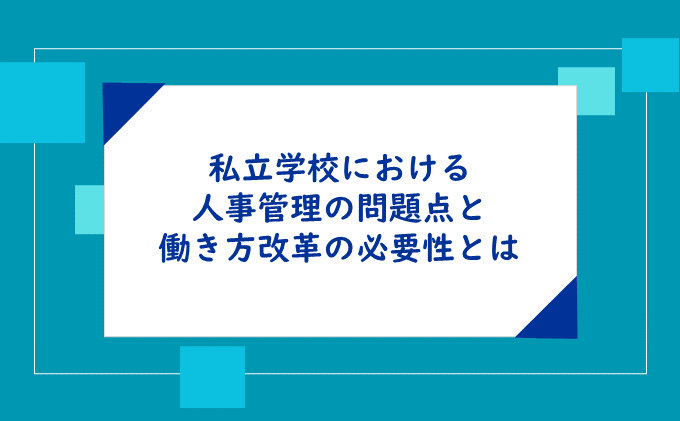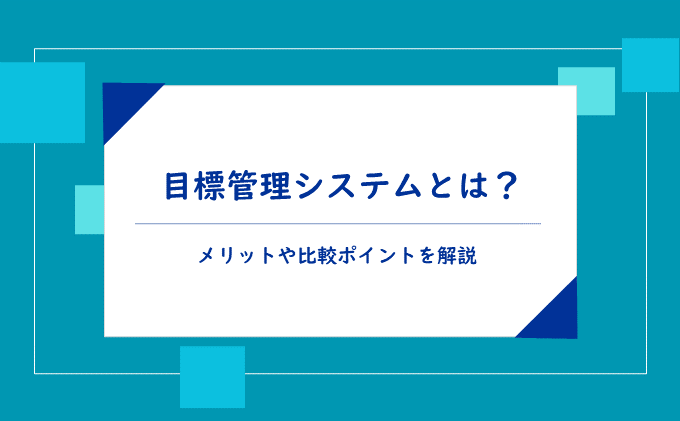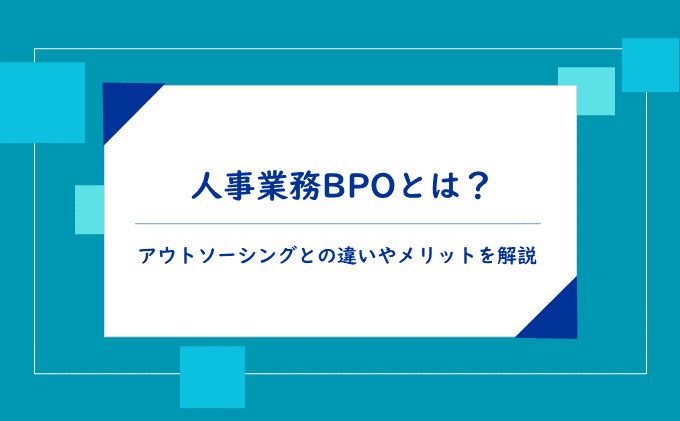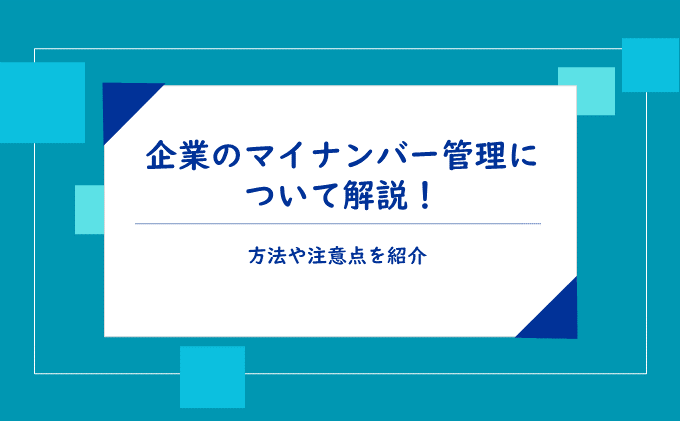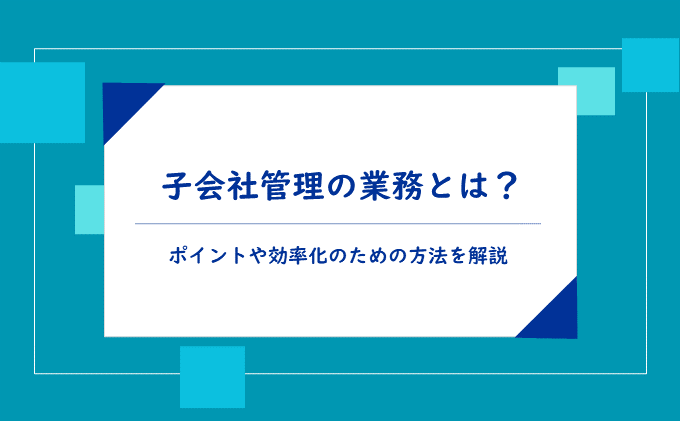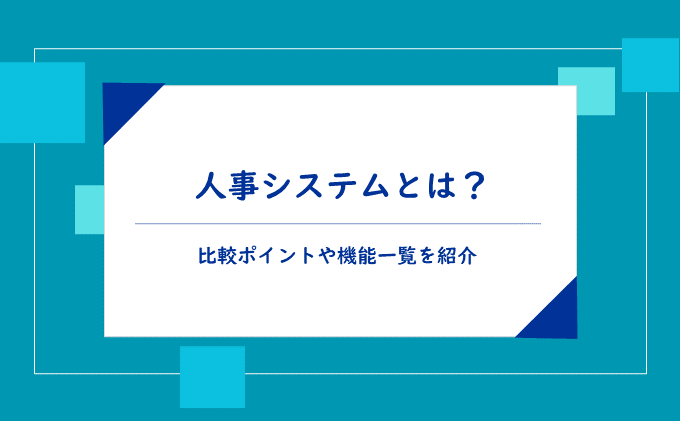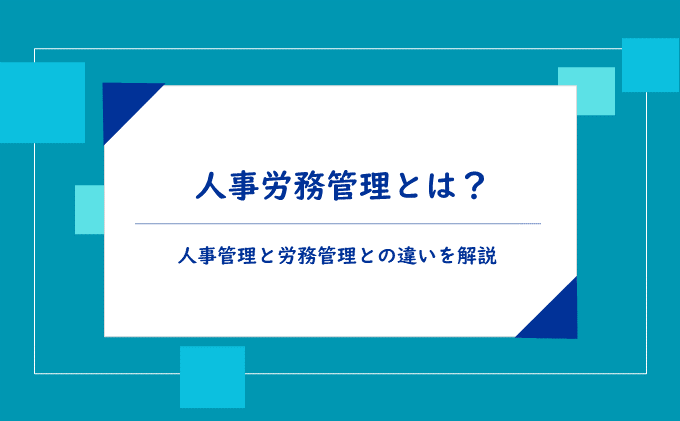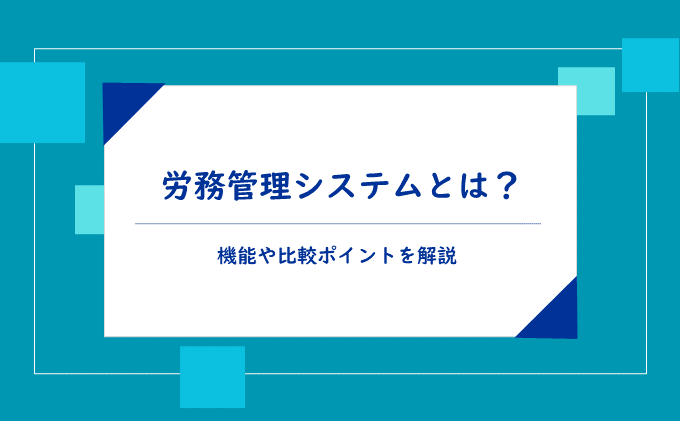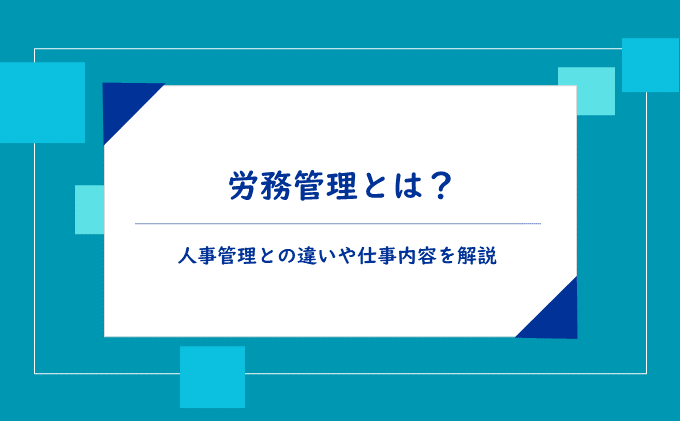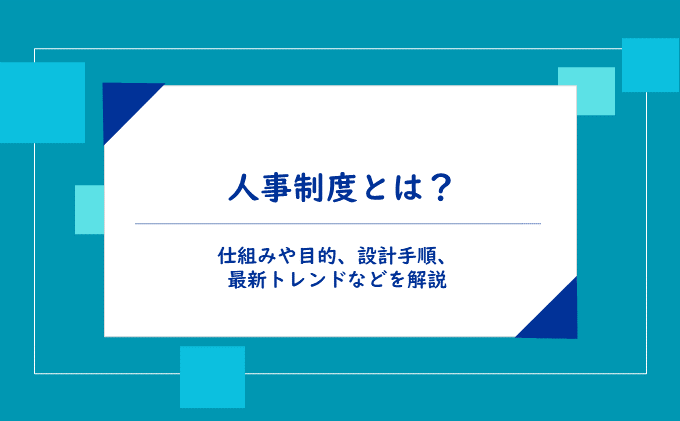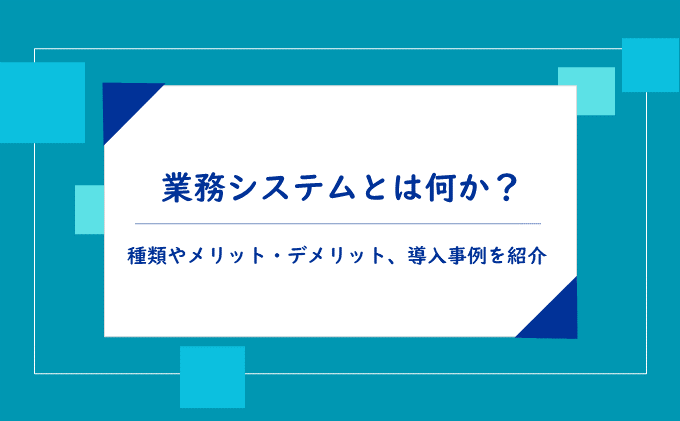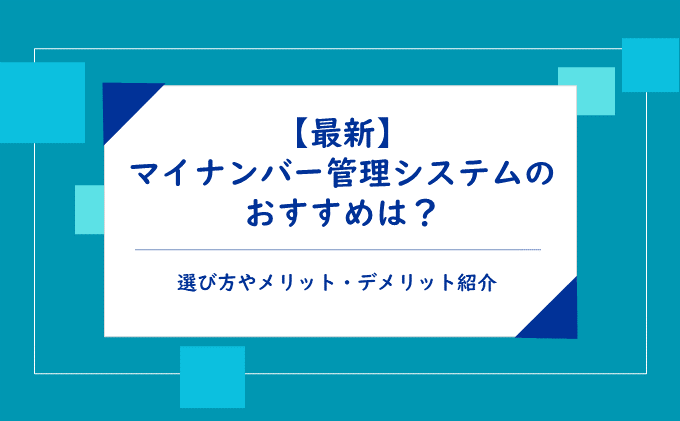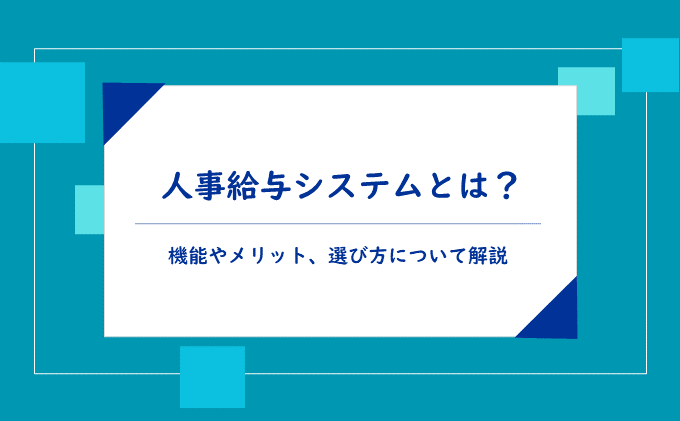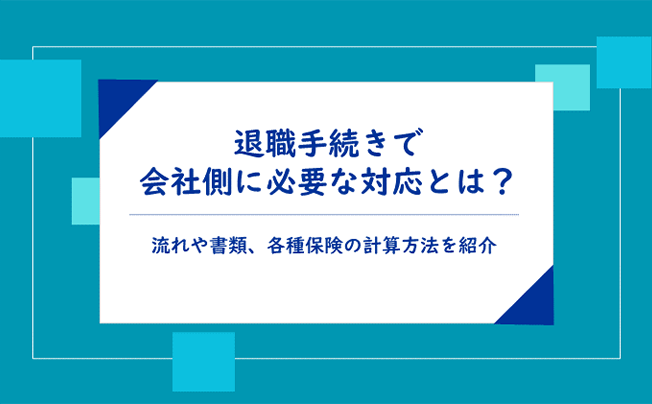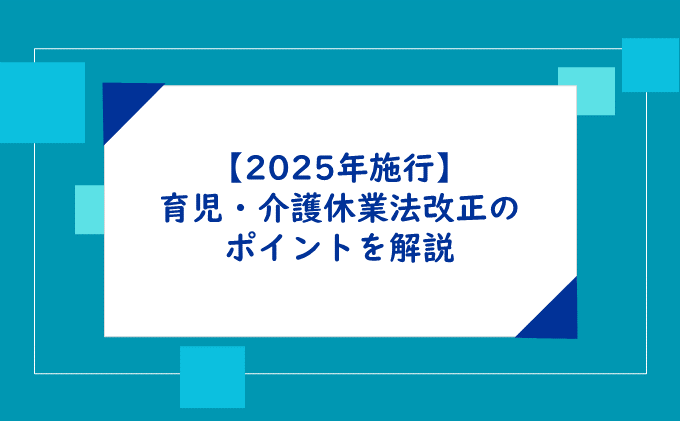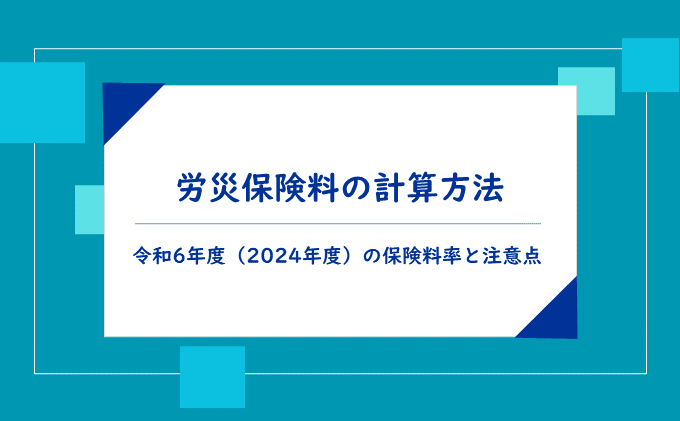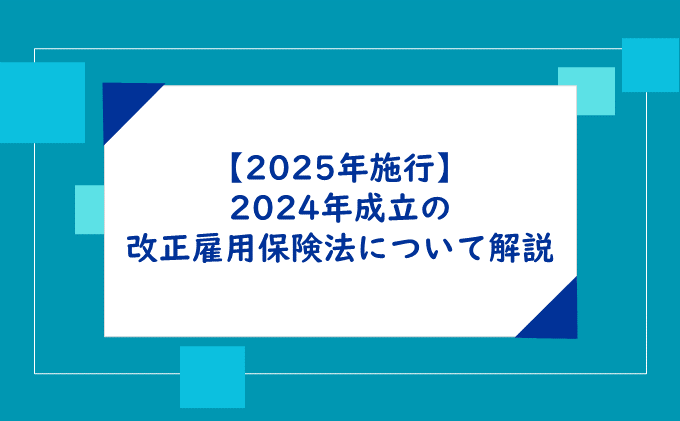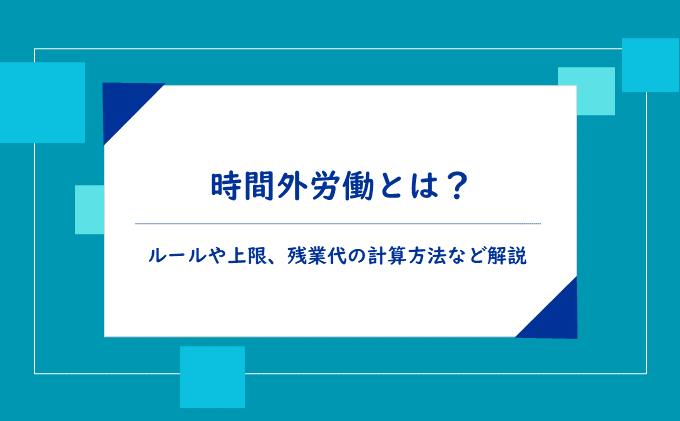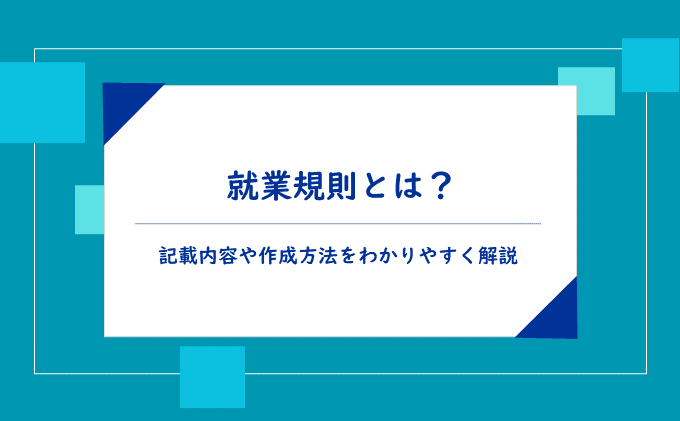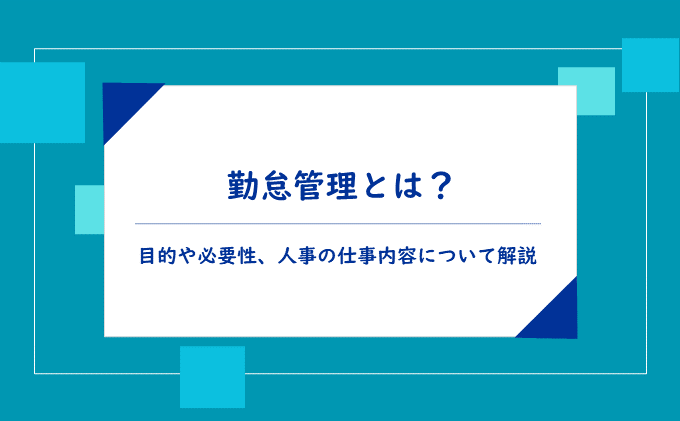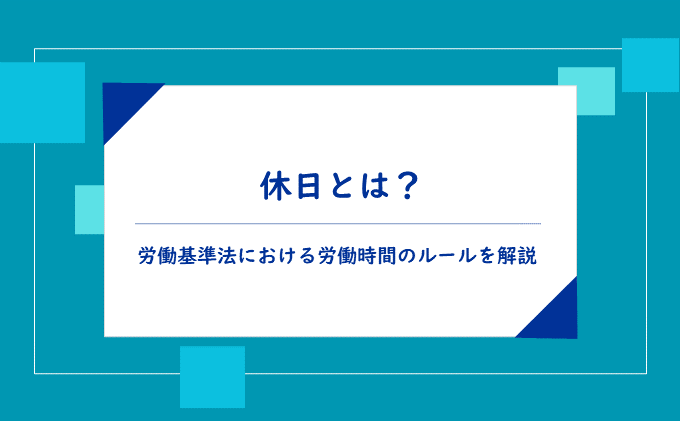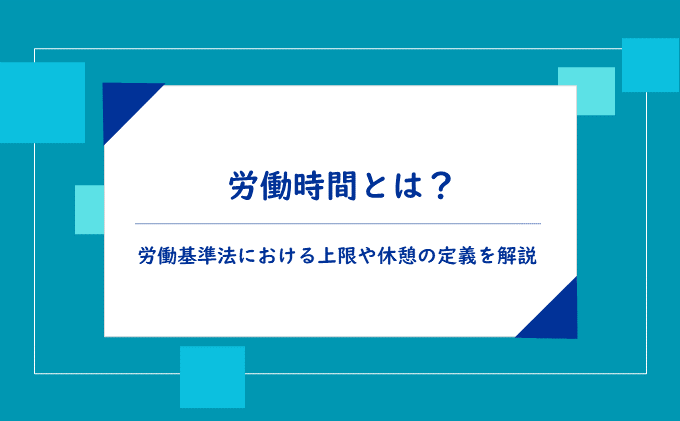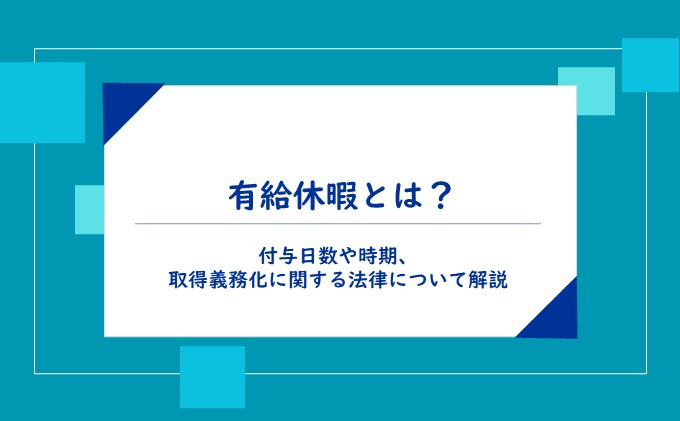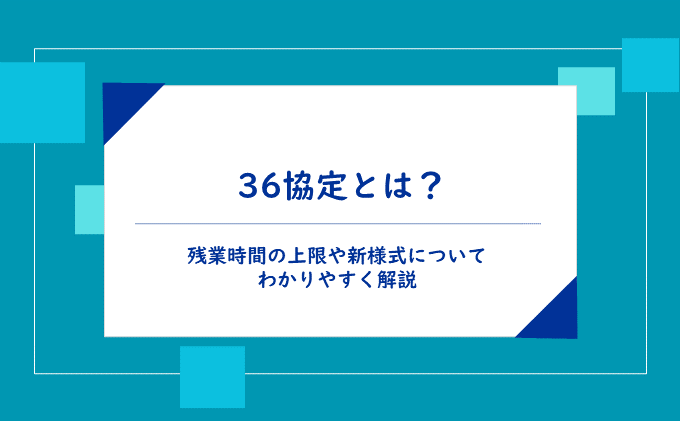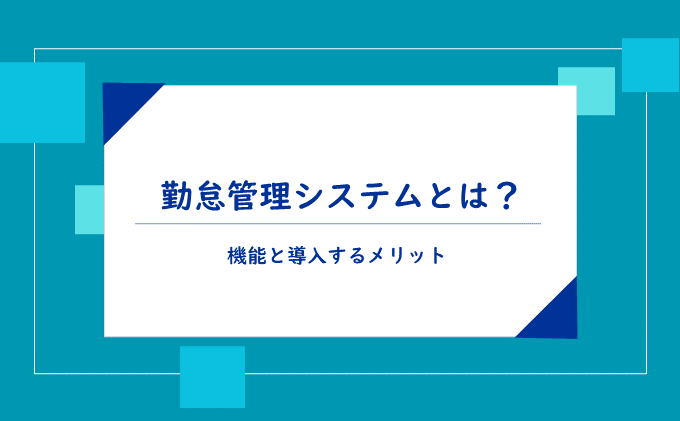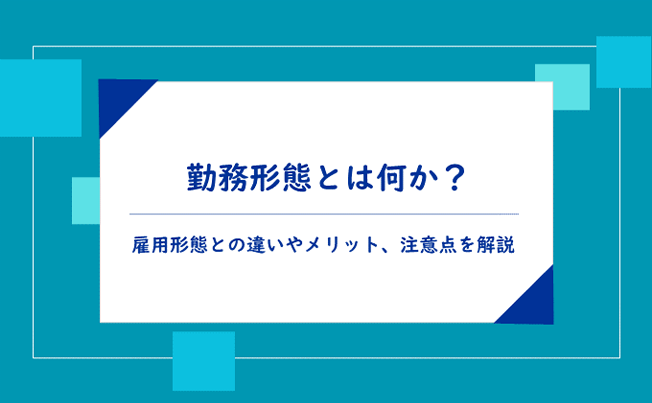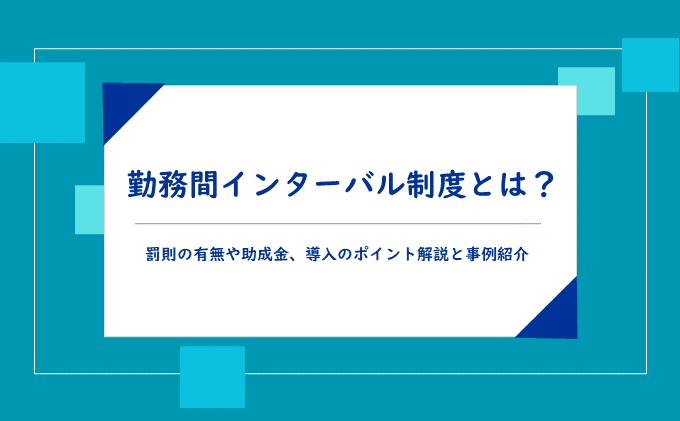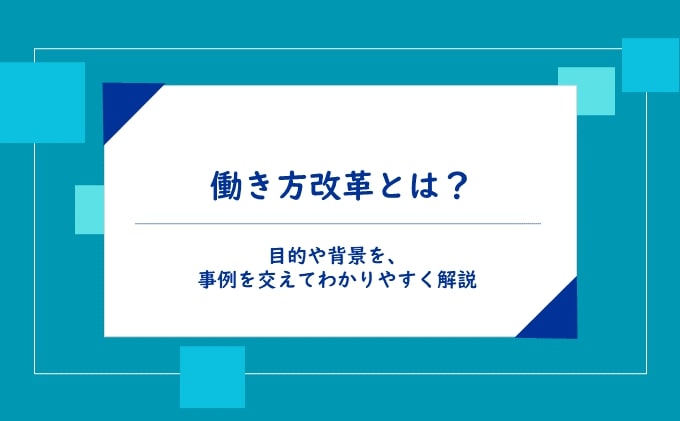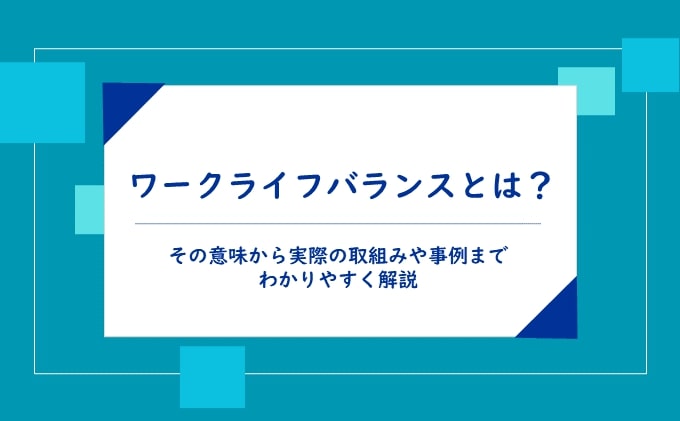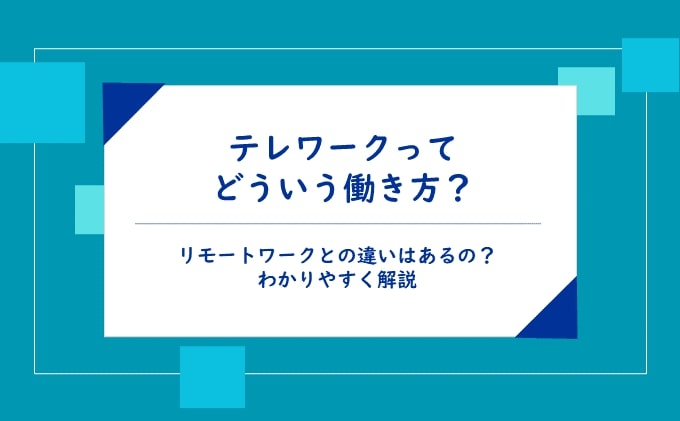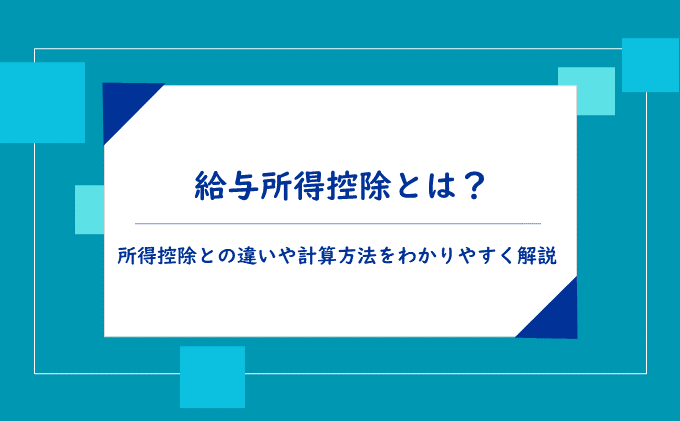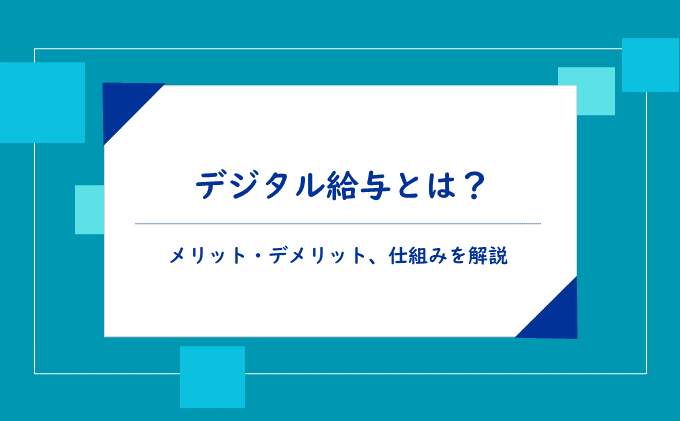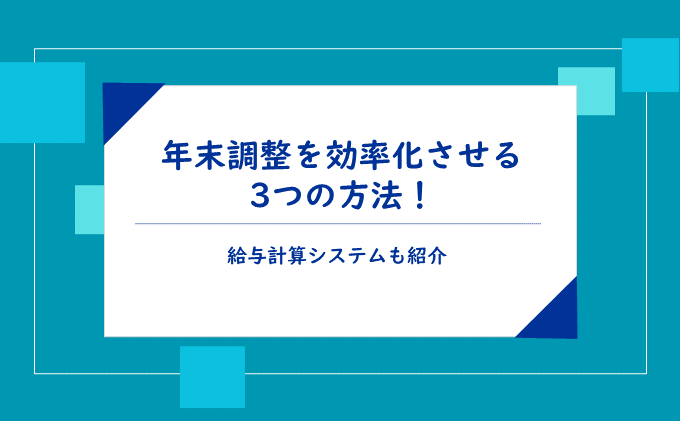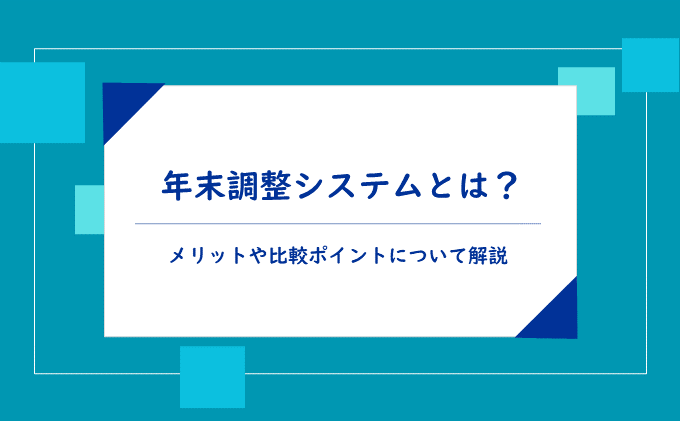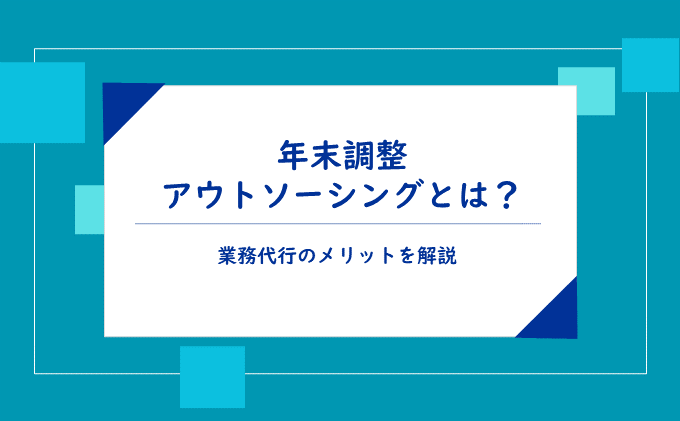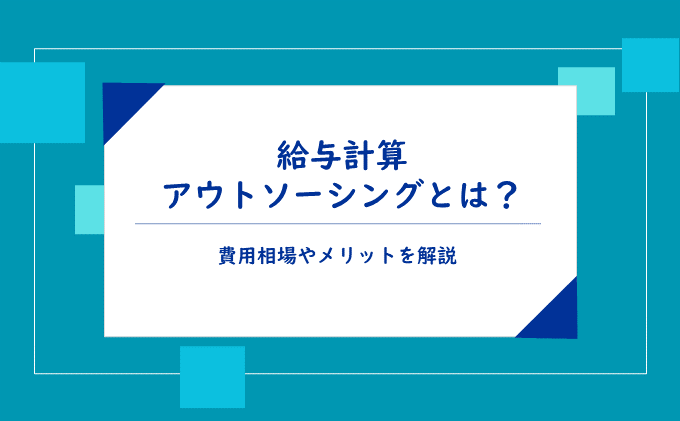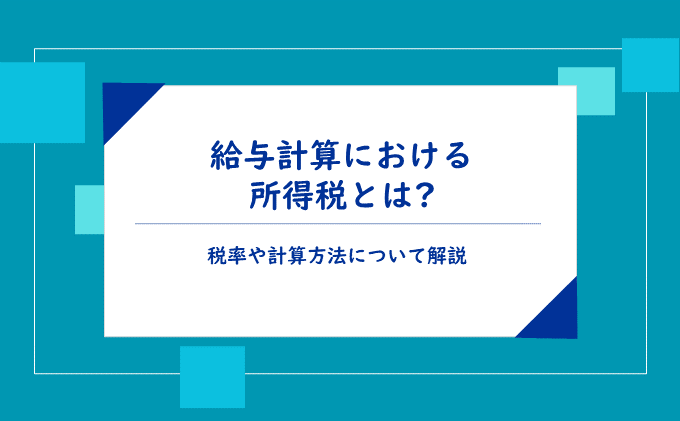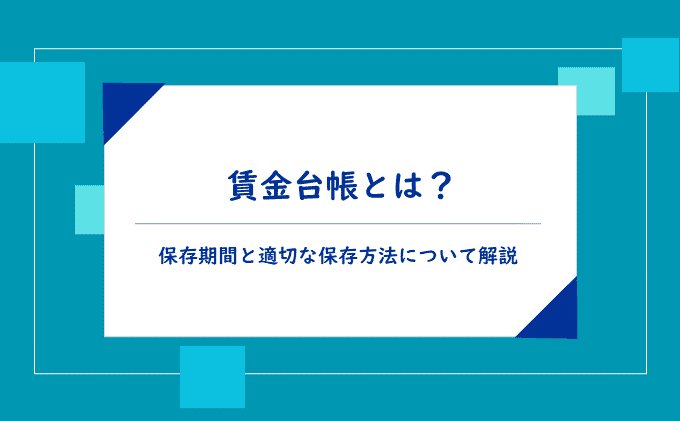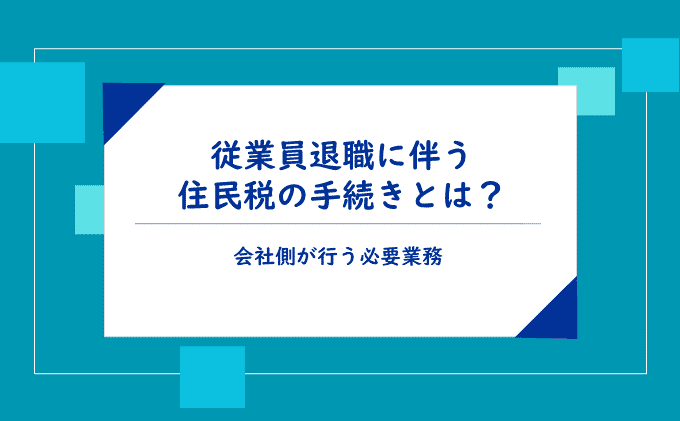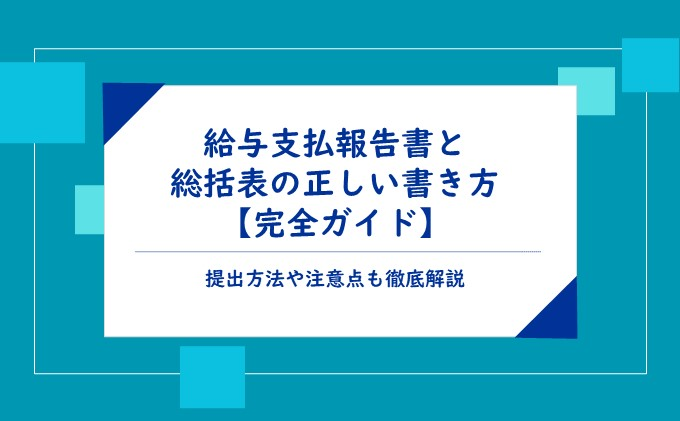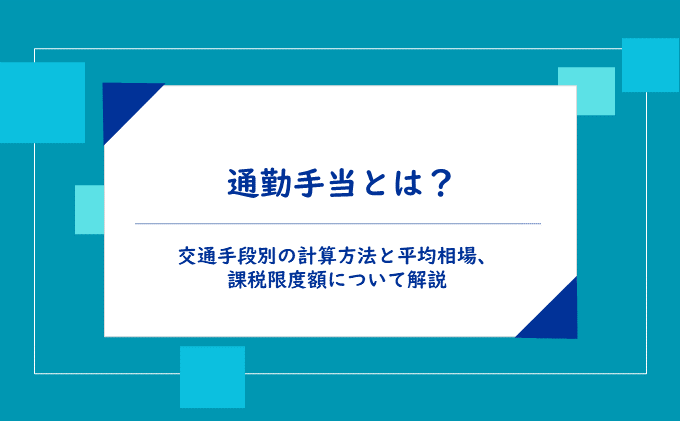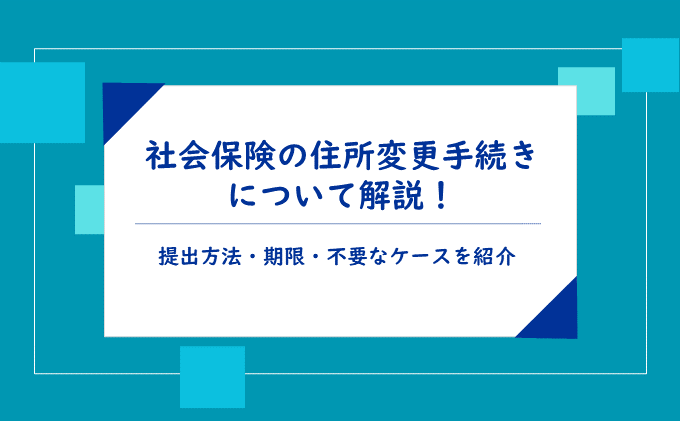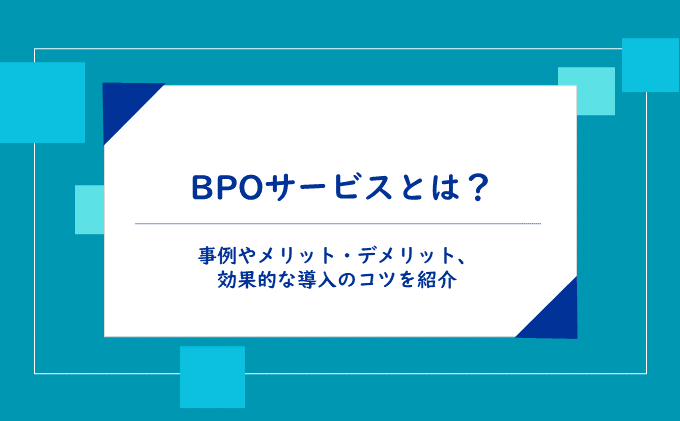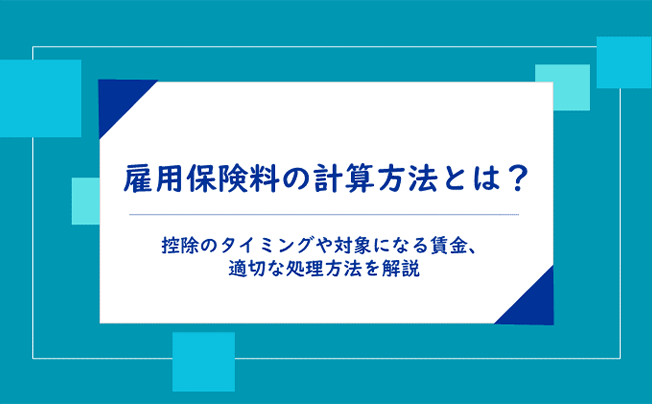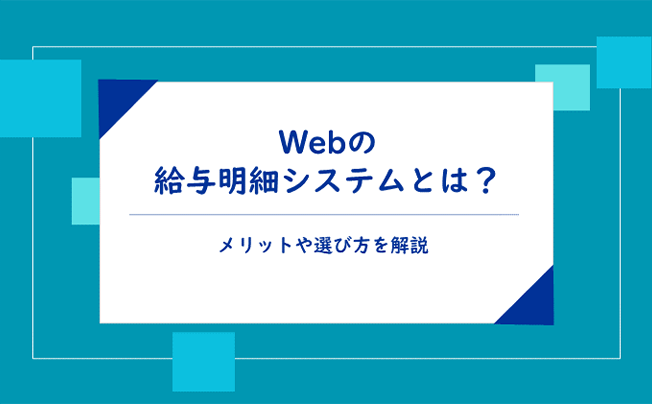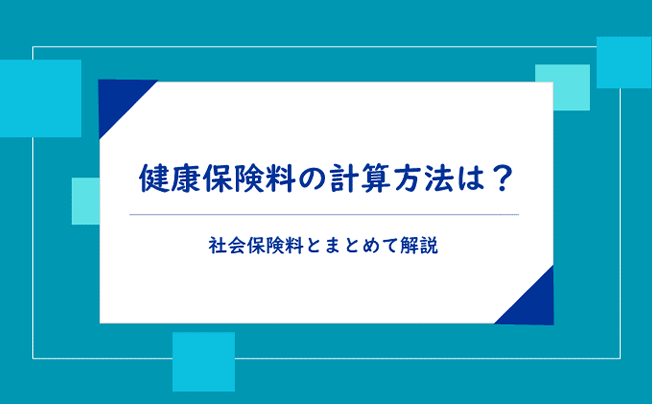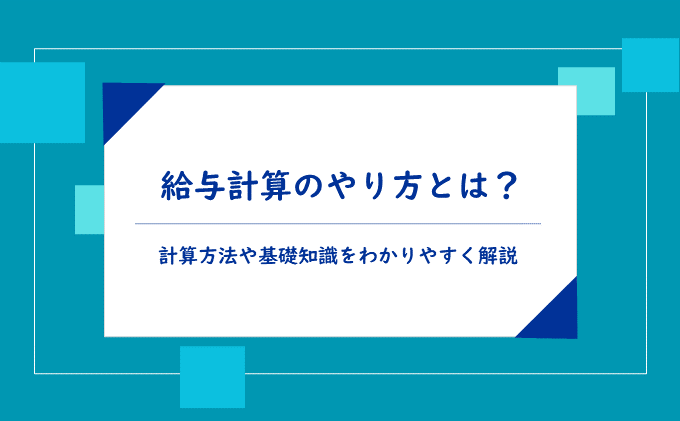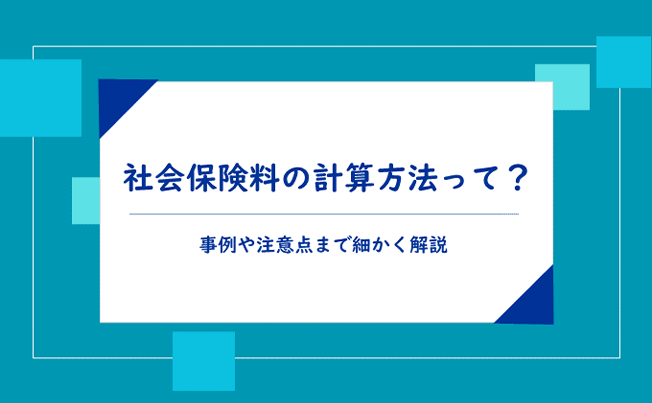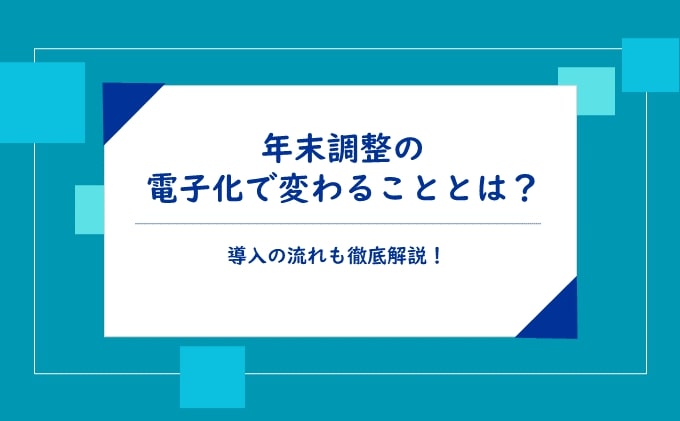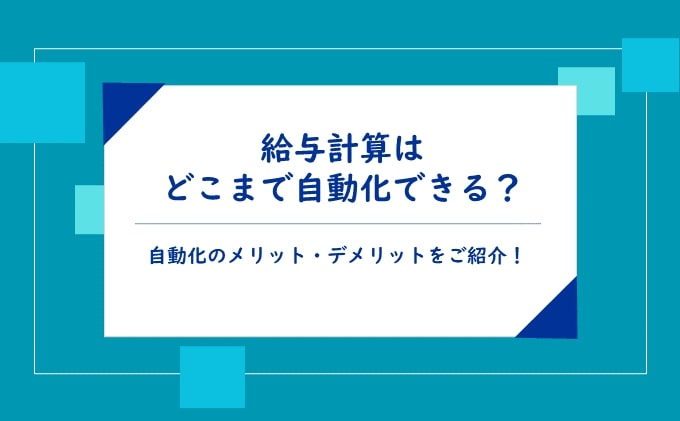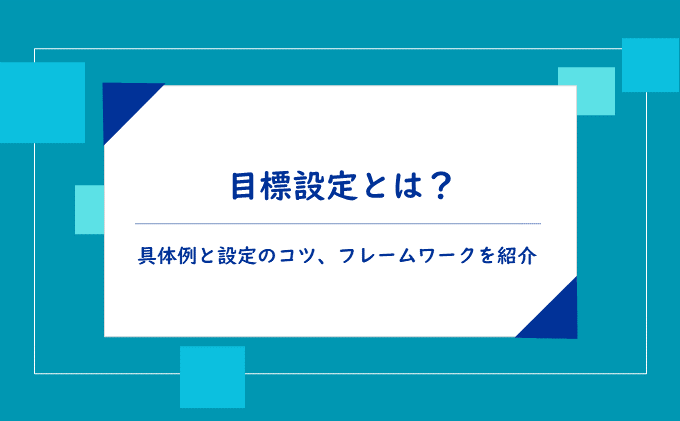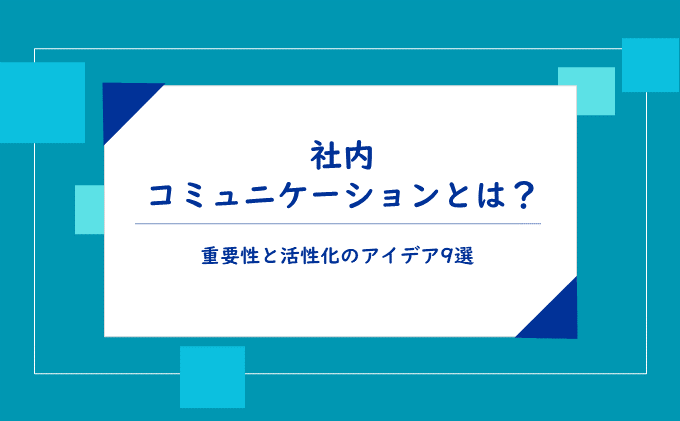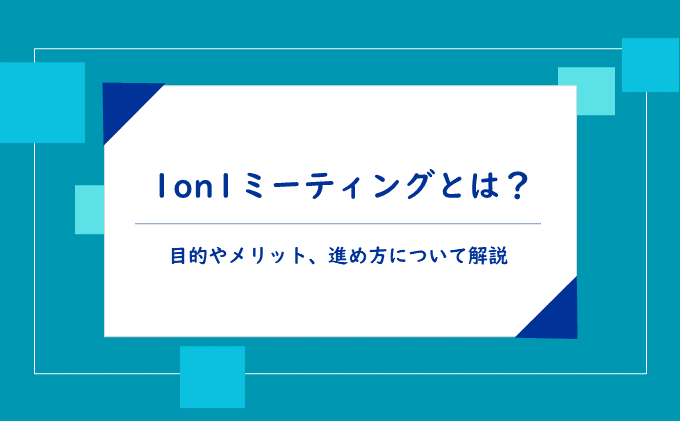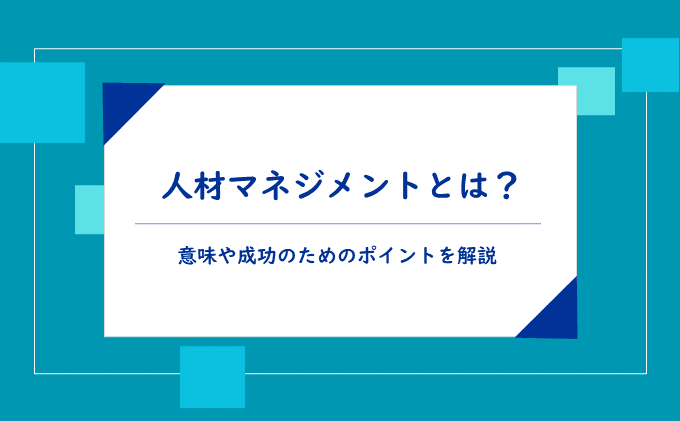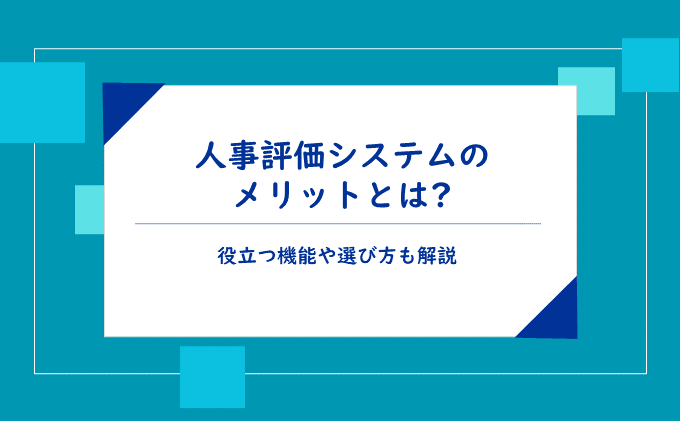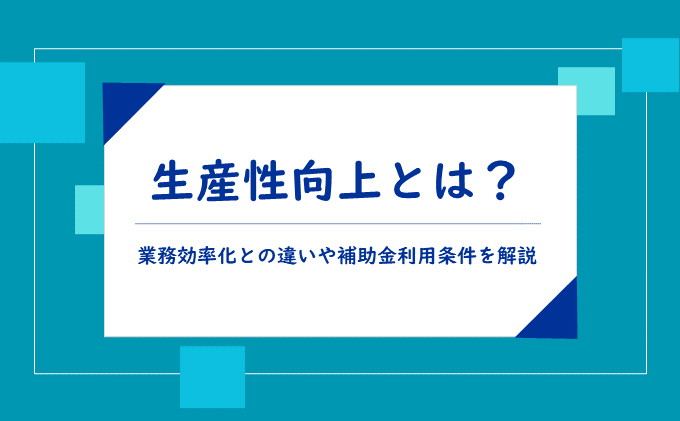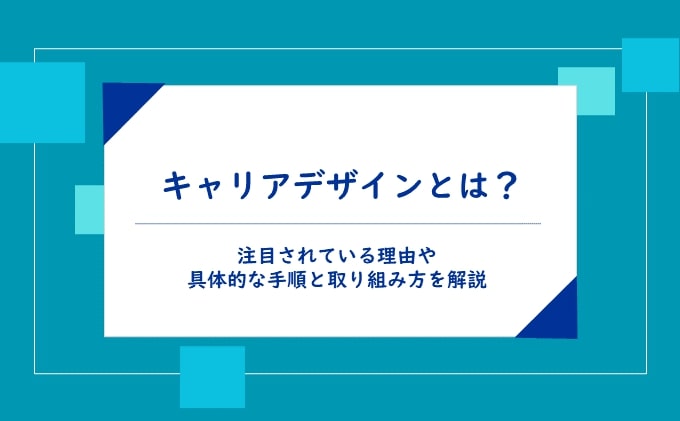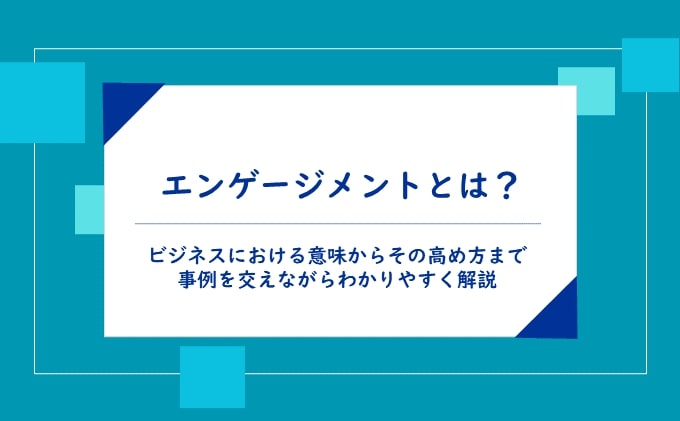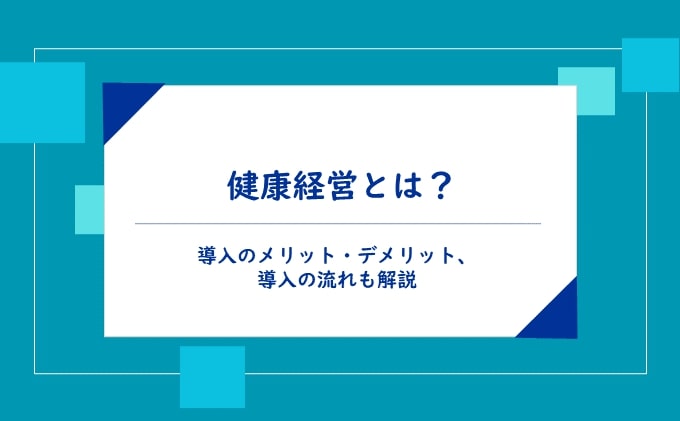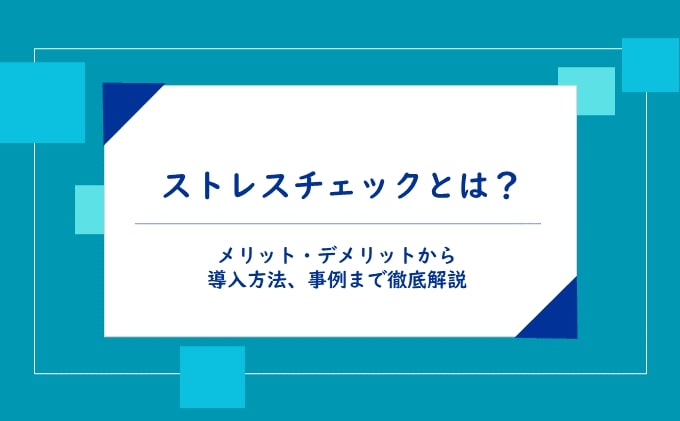残業代や残業時間の計算方法とは?ツールの選び方も紹介
2025.11.28
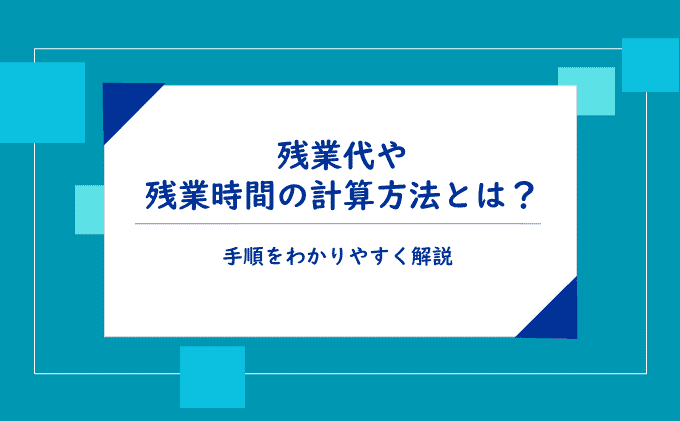
企業は、残業した従業員に対して残業代を支払わなくてはなりません。残業時間や残業代の計算方法は勤務体系などによっては複雑なため、注意が必要です。本記事では、間違いやすい残業代の計算方法や、計算に役立つツールの選び方などについて解説します。
目次
残業代とは?時間外手当との違い

残業代とは、法定労働時間を超えて働いた時間分の賃金のことです。残業には2つの種類があり、割増賃金を支払うか否かが異なります。
企業は、残業代を正しく計算し、従業員に支払わなければなりません。残業代の未払いが発生した場合は、従業員とトラブルになり、本来の残業代以上の金額を請求される可能性があります。
残業代を適切に支払うためには、残業や労働時間の定義を正しく理解することが欠かせません。
ここでは、残業とは何か、残業代と時間外手当との違いについて解説します。
そもそも「残業」とは
そもそも残業とは、法定労働時間、あるいは所定労働時間を超えて働くことです。
法定労働時間とは、労働基準法で定められている労働時間の上限のことです。労働基準法第32条では、「1日8時間以内、1週間40時間以内(10人未満のサービス業や医療などの一部業種は、44時間以内)」という上限が定められています。法定労働時間を超えて従業員に働かせることは、原則認められていません。
一方、所定労働時間とは、企業が独自に定めた労働時間の上限のことです。休憩時間を除いた始業時間から終業時間までの時間が該当し、就業規則や雇用契約書などに記載されます。所定労働時間は、法定労働時間の範囲内であれば企業が自由に定められるのが特徴です。
残業には、所定労働時間を超えて行う「法内残業」と、法定労働時間を超えて行う「法外残業(時間外労働)」があります。いずれの場合も、残業を行った従業員に対しては適切な賃金を支払わなければなりません。
以下では、法内残業と法外残業(時間外労働)について解説します。
参考:e-Gov法令検索「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)」
参考:e-Gov法令検索「労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)」
法内残業
法内残業とは、就業規則で定められた所定労働時間を超えており、かつ労働基準法で定められた法定労働時間の範囲内で行う労働のことです。
たとえば、就業規則で「1日7時間」という上限が定められていたとしましょう。このとき、1日の労働時間が7時間30分であった場合は、所定労働時間を30分オーバーしたことになります。しかし、法定労働時間はオーバーしていません。このような残業のことを、法内残業と呼びます。
後述のとおり、法内残業についても残業代を支給する必要があるものの、割増賃金を支払う必要はありません。
関連記事:就業規則とは?記載内容や作成方法をわかりやすく解説
法外残業(時間外労働)
法外残業(以下、時間外労働)は、労働基準法で定められた法定労働時間の上限を超えて行う労働のことです。
たとえば、所定労働時間が7時間で1日の労働時間が10時間だった場合、所定労働時間を3時間、法定労働時間を2時間超過しています。これを時間外労働と呼び、時間外労働に対しては割増賃金を支払わなければなりません。割増率については後述します。
関連記事:時間外労働とは?ルールや上限、残業代の計算方法など解説
残業代と時間外手当との違い
残業代と時間外手当は、意味が似ているものの厳密には異なります。
時間外手当は、時間外労働に対して支払う残業代のことです。一方、残業代は、所定労働時間あるいは法定労働時間を超えた場合に支払う賃金のことを指します。
たとえば、所定労働時間が7時間で1日の労働時間が8時間だった場合、1時間分の残業代を支払う必要があります。しかし、法定労働時間の範囲内であるため、時間外手当を支払う必要はありません。
このように、時間外手当は残業代の一部であり、残業代の方が範囲が広いのがポイントです。
残業時間の種類で異なる「割増率」
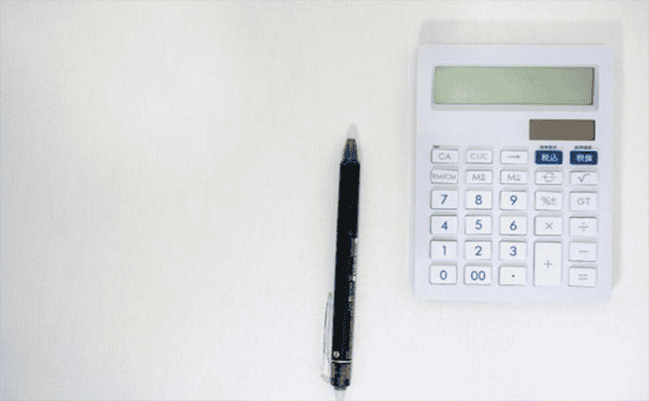
残業代を正しく計算するためには、割増率について理解する必要があります。
時間外労働に対しては、通常の賃金よりも割り増した割増賃金を支払わなければなりません。通常よりも何%割り増すかについては、残業の種類によって異なります。
ここでは、残業の種類ごとの割増率について見ていきましょう。なお、ここで紹介するのは法律で定められている割増率の基準です。企業が独自に基準を超える割増率を設定し、割増賃金を支払っても問題ありません。
法内残業:0%
法内残業については、割増率は0%、つまり割増賃金の対象外です。基本的には、割増賃金を支払う必要はありません。
ただし、就業規則や雇用契約書などで「所定労働時間を超えた分については◯%の割増率で賃金を支払う」というような内容を定めている場合は、規定に従って割増賃金を支払う必要があります。
また、割増賃金の対象外であるからといって、残業代を支払わなくてよいというわけではありません。所定労働時間を超えた分については、必ず然るべき賃金を支払いましょう。
深夜労働・時間外労働:25%
深夜労働や時間外労働については、割増率は25%と定められています。
深夜労働とは、労働基準法第37条で定められた22時〜翌5時までの時間帯に行う労働のことです。たとえば、22時〜翌3時まで働いた場合、労働時間の合計は5時間と法定労働時間の範囲内です。しかし、深夜労働に該当するため、割増賃金を支払う必要があります。
時間外労働については通常の賃金より25%高い額を、深夜労働については更に割増率を25%加算(計50%)した額を支払いましょう。
参考:厚生労働省 東京労働局「しっかりマスター労働基準法 割増賃金編」
参考:e-Gov法令検索「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)」
休日労働:35%
休日労働については、割増率は35%と定められています。
休日労働とは、労働基準法第35条で定められた法定休日に命じられる労働のことです。労働基準法では、企業は従業員に対して、週に少なくとも1回(または4週間で4日以上)の休日を与えなければならないと定められています。このルールに従って、週に1回与えられるのが法定休日です。
この法定休日に労働を命じた場合は、通常の賃金より35%高い額を支払いましょう。
なお、土日休みの場合は、土曜日と日曜日のうちどちらかが法定休日、どちらかが所定休日です。この場合、法定休日に行った労働の割増率は35%、所定休日に行った労働の割増率は25%で計算しましょう。
参考:厚生労働省 東京労働局「しっかりマスター労働基準法 割増賃金編」
参考:e-Gov法令検索「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)」
1か月に60時間を超える時間外労働:50%
1か月に行う時間外労働の合計が60時間を超える場合、割増率は50%になります。60時間までは25%、60時間を超えた分は50%の割増率で残業代を支払いましょう。
このルールはこれまで大企業のみに適用されていましたが、2023年4月からは中小企業にも適用されています。
なお、法定休日に行う労働は時間外労働の算定には含まれず、割増率は35%です。一方、所定休日に行う労働は、月60時間の時間外労働の算定に含まれます。つまり、60時間を超えた分については、割増率50%が適用されます。
参考:厚生労働省 東京労働局「しっかりマスター労働基準法 割増賃金編」
残業代の基本的な計算方法
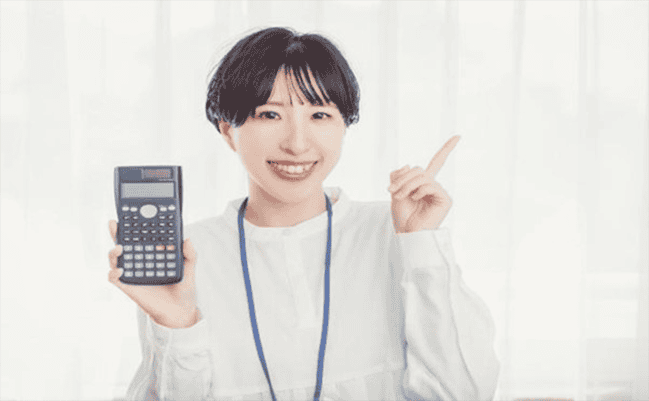
残業代の基本的な計算方法は以下のとおりです。
残業代=1時間当たりの賃金(時給) × 割増率 × 残業時間
月給制の場合、時給は以下の計算で求められます。
月給制の時給 = 月間給与(基本給 + 諸手当) ÷ 月平均所定労働時間
月平均所定労働時間は、以下で求められます。
月平均所定労働時間 = 年間所定労働日数 × 1日の所定労働時間 ÷ 12
実際に例をあげて計算してみましょう。
例)月給24万円(諸手当を含む)、1日の所定労働時間8時間、年間所定休日125日のAさんが、月10時間の時間外労働をした場合
まずは、Aさんの1時間当たりの賃金を求めるため、月平均所定労働時間を計算しましょう。年間所定労働日数は、365日から年間所定休日125日を引いて、240日と求められます。
月平均所定労働時間は、以下のとおりです。
240日 × 8時間 ÷ 12=160時間
ここから、Aさんの1時間当たり賃金は以下のように求められます。
24万円 ÷ 160時間=1,500円
次に、残業代を求めます。時間外労働の割増率は基本的には25%であるため、計算式は以下のとおりです。
1,500円 × 1.25 × 10時間=18,750円
Aさんの1か月の残業代は18,750円と求められました。
関連記事:給与計算はどこまで自動化できる?|自動化のメリット・デメリットをご紹介!
関連記事:エクセルを使った給与計算方法を解説!役立つ関数も紹介
【時給~歩合制】残業代の計算方法

ここでは、時給や日給制、年俸制、歩合制の場合の残業代の計算方法について見ていきましょう。
【時給制】残業代の計算方法
パートやアルバイトなど時給制で働いている従業員については、時給をそのまま1時間当たりの賃金として計算しましょう。計算式は以下のとおりです。
残業代=時給 × 割増率 × 残業時間
時間帯ごとに時給が異なる場合は、時間外労働が発生した時間帯の時給をもとに計算しましょう。
ただし、1日の勤務時間が8時間を超えていない場合は、割増賃金は発生しません。たとえば、5時間のシフトで働いていたアルバイトが1時間残業をした場合、1時間分については時給と同額を支払いましょう。
【日給制】残業代の計算方法
日給制の場合は、1時間当たりの賃金は以下のように求められます。
1時間当たりの賃金=日給 ÷ 1日の所定労働時間
たとえば、日給8,000円で1日の所定労働時間が8時間の場合、1時間当たりの賃金は1,000円です。
残業代の計算方法は、時給制と同様です。
【年俸制】残業代の計算方法
年俸制の場合、1時間当たりの賃金は以下のように求められます。
1時間当たりの賃金=年俸額 ÷ 12か月 ÷ 月平均所定労働時間
残業代の計算方法は、時給制や日給制と同様です。
【歩合制】残業代の計算方法
歩合制の場合は、固定給と歩合給を分けて計算する必要があります。
そもそも歩合制とは、従業員の成果や業績によって給与が変わる、成功報酬型の給与形態です。歩合制には、以下の2つの種類があります。
- インセンティブ制:固定給にプラスして成果に応じた歩合給を与える
- フルコミッション制:固定給がなく、歩合給のみを与える
フルコミッション制は、雇用契約を結んでいる従業員に対しては適用できません。最低賃金が保障されないためです。そのため、ここではインセンティブ制における残業代の計算方法を解説します。
歩合制では、まずは固定給と歩合給それぞれの1時間当たりの賃金を求める必要があります。計算式は以下のとおりです。
1時間当たりの固定給 = 月給額 ÷ 月平均所定労働時間
1時間当たりの歩合給 = 歩合給額 ÷ 残業分を含めた総労働時間
それぞれに割増率と残業時間をかけて、残業代を算出しましょう。
このとき、1時間当たりの歩合給にかける割増率は、1.25ではなく0.25である点に注意が必要です。歩合制の場合、時間外労働に対する1時間当たりの賃金は、すでに給与総額に含まれているためです。
労働形態別の計算方法
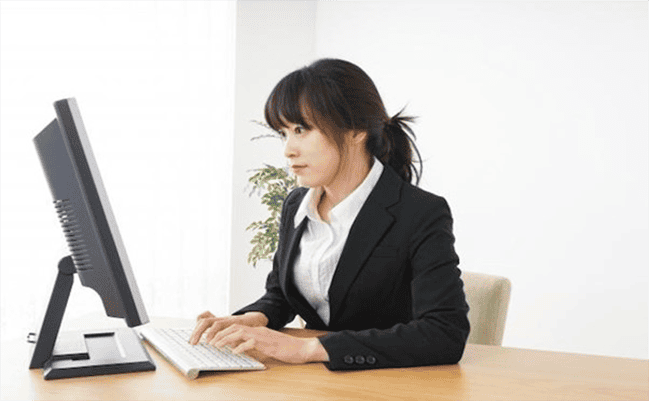
近年、変形労働時間制やフレックスタイム制、裁量労働制など、多様な働き方を取り入れる企業が増えています。ここでは、労働形態別の残業代の計算方法を見ていきましょう。
関連記事:大企業におすすめの給与計算システムは?比較ポイントを紹介
「変形労働時間制」の計算方法
変形労働時間制とは、忙しい時期に長く働き、手が空く時期には働く時間を短くするなど、業務の性質にあわせて調整する制度です。労働時間が1日8時間を超えても、1週40時間の枠で調整できることが特徴です。
同制度を採用する全期間で、1週あたりの「平均の労働時間」が40時間を超えてはなりません。また、所定労働時間が8時間未満の場合には注意が必要です。所定労働時間が6時間で、実労働時間が7時間の場合、「1日8時間」を超えないため残業は0と計算されます。
一方、「1週40時間」の枠を超えた分は残業にあたります。同制度における残業代計算の複雑さが生じる点です。
同制度で時間外となる範囲は以下のとおりです。
| 1日について | 8時間超の労働時間が設定された場合は、それを超えて働いた時間。それ以外は8時間を超えた時間。 |
| 1週について | 40時間を超える労働時間が設定された場合は、それを超えて働いた時間。それ以外は40時間を超えた時間。ただし、「1日について」の基準で残業時間となった分は除く。 |
| 全変形期間について | 全変形期間の法定労働時間の総枠を超えて働いた時間。ただし、「1日について」「1週について」の基準で残業時間となった分は除く。 |
この制度には、労働基準法の定めにより「1か月単位」「1年単位」と「1週間単位の非定型的」の3種類があります。それぞれについて、具体例を用いて残業代の計算方法を説明します。
参考:e-Gov法令検索「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)」
1か月単位の変形労働時間制の場合
1か月単位の変形労働時間制は、月初や月末、特定の週のみが忙しい職場などで採用される方式です。この制度を導入するためには「対象期間」と「起算日」を決めなければなりません。「毎⽉1日を起算日とし、1か⽉を平均して1週間当たり38時間以内とする」など、就業規則などに具体的な形で定める必要があります。
残業代は、「1日について」「1週について」「全変形期間について」の基準にしたがい、それぞれ算出します。
【表1 1日について】
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 所定労働時間 | 8 | 10 | 8 | 4 | 10 |
| 実労働時間 | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 |
| 時間外労働 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
上表のケースで注意が必要になるのは、木曜日です。4時間の所定労働時間に対して7時間働いており、3時間の時間外労働が発生しているように見えますが、実労働時間は8時間を超えていないため、時間外労働時間は0とカウントされます。水曜日の1時間のみが残業時間にあたります。
【表2 1週について】
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 計 |
| 所定労働時間 | 8 | 10 | 8 | 4 | 10 | 40 |
| 実労働時間 | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 | 44 |
| 時間外労働 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4-1=3 |
同じ1週間を、「1週について」の基準で計算すると、上表のとおりになります。右端の枠にあるように、実労働時間は「1週40時間」を超える44時間です。時間外が4時間発生しているように見えますが、「1日について」の基準で残業扱いとなった1時間は差し引かれるため、この週の残業時間は3時間です。
【表3 全変形期間について】
| 曜日 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 計 |
| 所定労働時間 | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 |
| 実労働時間 | 44 | 44 | 44 | 44 | 176 |
| 時間外労働 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16-4-12=0 |
1か月(暦日数28日)の所定労働時間と実労働時間が、表1、表2とそれぞれ同様である場合、この1か月を全変形期間とする時間外労働は、表3のとおりです。
残業代が発生するのは「全変形期間の法定労働時間の総枠を超えて労働した時間」であり、総枠は以下の式により計算できます。
総枠 = 40時間 × 期間中の暦日数 ÷ 7
表3の例では、40時間 × 28日 ÷ 7となり、総枠は160時間です。実労働が176時間であるため、総枠に対して16時間の時間外労働が発生しているように見えますが、「1日」「1週」基準での時間外労働は除外します。
どの週においても、「1日」基準による時間外労働は1時間です。同様に、「1週」基準による時間外労働は3時間です。全変形期間が4週で構成されるため、それぞれ4倍にします。
なお、全変形期間における時間外労働の計算では、「1日」基準で時間外労働扱いとなった4時間と、「1週」基準による12時間はカウントしません。計算すると16-4-12=0となり、「全変形期間について」の基準では時間外労働は0でした。
残業代の計算は、以下の3つの合計です。
「1日について」の基準による残業時間の合計 × 1時間あたりの賃金 × 1.25
「1週について」の基準による残業時間の合計 × 1時間あたりの賃金 × 1.25
「全変形期間について」の基準による残業時間の合計 × 1時間あたりの賃金 × 0.25
「全変形期間」では割増率が異なる点に注意が必要です。
1年単位の変形労働時間制の場合
1年単位の変形労働時間制は、スキー場やプール、百貨店など、年間を通じて繁忙期と閑散期の差が大きい業種に多く採用されています。変形期間は1か月を超えて1年未満です。1年と決まっているわけではありません。
期間が長ければ心身に与える影響も大きくなるため、1か月単位では求められていない「労使協定の締結」が必要です。なお、労使協定は、労働基準監督署に提出する必要があります。
1年単位の場合でも、基本的な残業代の計算は1か月単位と同様です。「1日について」「1週について」の基準による計算を行った後に、「全変形期間について」の基準で計算したものを合算します。全変形期間を365日と定めた場合、上限労働時間は40時間 ×365日 ÷ 7 = 2085.7時間です。
1年単位の場合には、1日10時間、1週52時間の労働時間の上限が設けられています。ただし、期間が3か月を超える場合、以下のような制限が課されることに注意が必要です。
- 全期間で労働時間が48時間を超える週が連続する場合は3週連続以下とする
- 1年あたり280日を労働日の上限とする(3か月超1年未満の場合は280日 × 期間中の暦日数 ÷ 365とする)
1週間単位の非定型的変形労働時間制の場合
1週間単位の非定型的変形労働時間制は、「従業員数30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店」に対して適用可能です。規模の大きな企業には適用されません。労働時間は1日10時間以内、1週40時間以内の範囲で、週単位で調整できます。
労使協定の締結が必要で、1週あたり40時間を超えた分が時間外労働です。各日の労働時間は、1週間単位で前週末までに書面で通知します。
関連記事:労働時間とは?労働基準法における上限や休憩の定義を解説
「フレックスタイム制」の計算方法
フレックスタイム制は、あらかじめ設定された総労働時間の範囲内で、従業員が出退勤時刻を自由に決められる制度です。総労働時間を超えなければ10時間働いても残業は発生せず、5時間のみ働いても早退にはなりません。3か月を上限とする清算期間ごとに設定を行います。
1日の中で、全従業員が出勤しなければならない「コアタイム」と、それ以外の「フレキシブルタイム」に分けて運用されるのが一般的です。この制度を採用した場合、清算期間が1か月か1か月を超えるかにより、残業代の計算方法は異なります。具体例を以下で見ていきます。
清算期間が1か月の場合
清算期間が1か月の場合、計算はシンプルです。まず、1か月の労働時間の総枠を計算します。計算式を以下に示します。
総枠 = 40時間 × 期間中の暦日数 ÷ 7
実労働時間が総枠を超えた分が時間外労働です。暦日数30日の1か月を清算期間とし、期間内の実労働時間が192時間だった場合の例は以下のとおりです。
総枠 40時間 ×30日 ÷ 7 = 171.4時間
実労働時間 192時間
時間外労働 192時間 - 171.4時間 = 20.6時間
この場合の残業代は「20.6時間 × 1時間あたりの賃金 × 1.25」で計算できます。
清算期間が1か月を超える場合
清算期間が1か月を超える場合は、計算が複雑になります。1か月ごとに「週平均50時間を超えた労働時間」があれば、その分も時間外労働となるためです。
総枠を超えた労働時間も時間外労働にカウントされます。各月に週平均50時間を超えた部分があった場合は差し引きます。
また、清算期間を3か月とした場合、残業代の計算には以下のような2段階の作業が必要です。
- ①各月について「週平均50時間を超えた労働時間」があるかを確認
- ②全期間の実労働時間から上記①の合計を減算し、総枠を超えているか確認
以下の3か月を例にとって、残業代の計算を説明します。
| 月 | 暦日数 | 実労働時間 | 週平均50時間の労働時間 | 週平均50時間超の時間 | 清算期間の労働時間総枠 |
| 4月 | 30 | 220 | 214.2 | 5.8 | |
| 5月 | 31 | 130 | 221.4 | 0 | |
| 6月 | 30 | 230 | 214.2 | 15.8 | |
| 計 | 91 | 580 | 21.6 | 520 |
週平均50時間となる労働時間の計算式は「50時間 × 暦日数 ÷ 7」ですが、この期間の労働時間の総枠は「40時間 ×清算期間の 暦日数 ÷ 7」の式で計算できます。
週平均50時間を超えた月は、4月の5.8時間と6月の15.8時間で、計21.8時間でした。実労働時間の580時間から減算すると558.2時間となり、総枠の520時間を38.2時間上回っています。
時間外労働は38.2時間となるため、残業代は9月分の給与に上乗せして支払われます。計算式は以下のとおりです。
38.2時間 × 1時間あたりの賃金 × 1.25
「裁量労働制(みなし残業)」の計算方法
裁量労働制(みなし残業)とは、実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ定めた時間分労働したとみなす制度です。みなし労働時間を8時間と決めた場合は、実際の労働時間が7時間であっても8時間働いたとみなされ、その分の賃金が支払われます。
裁量労働制では、残業についてもみなし残業時間を定め、毎月その分の固定残業代を支払います。実際は残業が0時間だった場合でも、固定残業代を支払うのがポイントです。
裁量労働制において、残業代の計算が必要になるのは以下のようなケースです。
- みなし労働時間が法定労働時間を超える場合
- 休日労働や深夜労働を行った場合
みなし労働時間が法定労働時間を超える場合は、超えた分が時間外労働として扱われるため、割増率25%の割増賃金を支給しなければなりません。
また、休日労働を行った場合は割増率35%、深夜労働を行った場合は割増率25%の割増賃金を支給しましょう。
勤務形態については、以下のコラムで詳しく解説しています。併せて参考にしてください。
「裁量労働制(みなし残業)」の計算方法
裁量労働制とは、実際に働いた時間にかかわらず、事前に設定した時間分の労働をしたものとみなして給与を支払う制度です。多くの場合、あらかじめ一定時間の残業があったとみなして固定残業代を上乗せする「みなし残業」の形で運用されます。
ほかにも、深夜勤務や休日出勤をした場合などには、裁量労働制であっても割増賃金を支払わなければなりません。以下で、ケースごとに分けて説明します。
みなし労働時間が8時間を超えた場合
1日のみなし労働時間を10時間と定めた場合、法定労働時間(8時間)を超えた2時間が残業扱いとなります。
裁量労働制を採用した場合でも、労働基準法の定める時間外労働の原則的な上限「月45時間、年360時間」は適用されます。したがって、月45時間を超える残業が発生するような労働時間は設定できません。
1日分の残業代の計算式は、以下のとおりです。
2時間 × 1時間あたりの賃金 × 1.25
深夜勤務をした場合
午後10時から翌日午前5時までの時間に労働させることを「深夜業」といいます。深夜業に対する賃金の割増率は25%以上です。裁量労働制を採用していても、深夜業に対する割増は発生します。
裁量労働制を適用されている従業員に深夜勤務を行わせた場合の割増賃金(割増率25%の場合)の計算式は、以下のとおりです。
深夜業の時間数 × 1時間あたりの賃金 × 1.25
参考:e-Gov法令検索「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)」
法定休日に勤務した場合
法定休日に勤務させた場合も、割増賃金の対象です。労働基準法では、週に1日以上または4週間で4日以上の休日を与える必要があると定められています。
法定休日に勤務させた場合は、その時間に対して35%以上の割増賃金を支払わなければなりません。裁量労働制で働く従業員であっても、休日勤務に対する割増賃金は発生します。割増率35%の場合の計算式は、以下のとおりです。
法定休日における労働時間数 × 1時間あたりの賃金 × 1.35
残業代の計算時に気を付けたい3つのポイント
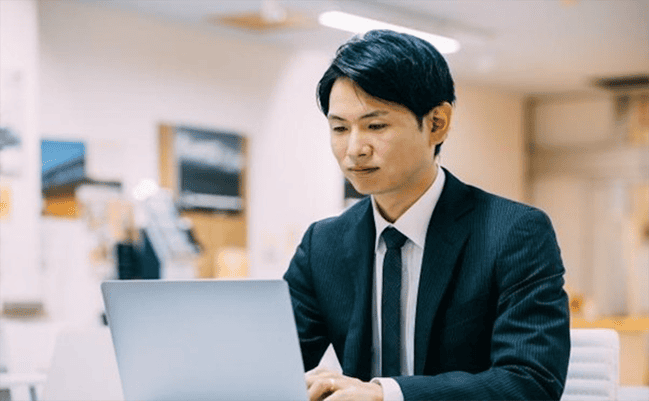
残業代を計算する際は、以下の3つのポイントに注意しましょう。
- 従業員に残業させるには「36協定」の締結が必要
- 残業代は1分単位で計算する
- 残業代請求には時効がある
トラブルを防ぐためにも、正しい方法で残業代を計算することが欠かせません。
ここでは、それぞれのポイントについて解説します。
関連記事:36協定とは?残業時間の上限や新様式についてわかりやすく解説
1.従業員に残業させるには「36協定」の締結が必要
従業員に時間外労働をさせるためには、事前に使用者と従業員の間で「36(サブロク)協定」を締結することが必要です。
36協定とは、時間外労働や休日労働に関する取り決めのことです。36協定を締結せずに時間外労働を課した場合は、残業代を適切に支払ったとしても労働基準法違反に該当します。
36協定を締結することで、時間外労働の上限は、「月45時間以内、年360時間以内」に変更されます。
36協定と同時に押さえておきたいのが「特別条項付き36協定」です。36協定を締結した場合でも、「月45時間、年360時間」を超える時間外労働を課すことは原則認められていません。繁忙期や深刻な人手不足に悩んでいるなど、やむを得ず基準を超えてしまう場合は、事前に労使間で特別条項付き36協定を締結しましょう。
関連記事:36協定とは?残業時間の上限や新様式についてわかりやすく解説
参考:厚生労働省「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」
参考:厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」
2.残業代は1分単位で計算する
残業代は、原則1分単位で計算しましょう。残業時間が1時間35分だからといって、キリのよい1時間30分に切り捨てて残業代を計算してはなりません。
ただし、月の合計残業時間については、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げることが例外として認められています。
また、残業代を算出した際に1円未満の端数が発生した場合は、50銭未満は切り捨て、50銭以上は切り上げることが可能です。ただし、端数処理を行う場合は、その旨を就業規則に定めておく必要があります。
3.残業代請求には時効がある
残業代請求には3年という時効があります。2020年の民法改正により、賃金請求権の消滅時効が2年から5年(当面の間は3年)に延長されました。
従業員は過去3年分にさかのぼって未払い残業代の支払いを請求できます。請求内容が正しい場合は、支払いに応じなければなりません。
残業代請求に対応する際は、時効の援用に注意しましょう。時効の援用とは、時効の完成によって利益を得る者(残業代請求の場合は企業側)が時効の完成を主張することです。
民法では、当事者が時効を援用しないかぎり、時効の効果は完成しないとされています。つまり、3年が過ぎたからといって自然に残業代請求権が消滅するわけではありません。企業側が「この請求は時効期間を経過しているため、支払えません」と主張しなければ、時効を過ぎている分についても支払いに応じる必要があります。
もちろん、そもそも未払い残業代が発生しないよう、労務管理を徹底することが大切です。
参考:厚生労働省「未払賃金が請求できる期間などが延長されています」
参考:e-Gov法令検索「民法(明治二十九年法律第八十九号)」
残業時間の計算に役立つツール

残業時間の計算は複雑になる場合があり、集計や計算にミスが生じる可能性もあります。実務では、ミス防止や効率向上を図れるツールを利用することが一般的です。以下では、残業時間の計算に役立つツールについて解説します。
人事管理システム
人事管理システムは、企業が従業員の残業時間を効率的に管理できるツールです。従業員の出退勤時刻や残業時間などが自動で記録され、労働管理の負担を軽減できます。
クラウド上で提供される多くのツールには、法改正に自動で対応するサービスが付帯しています。自社で対応する必要はなく、手間の削減やミス防止にも有効です。デメリットとして、費用が発生する点が挙げられます。
カシオヒューマンシステムズが提供する人事管理システム「ADPS(アドプス)」は、残業時間の計算をはじめ、人事や給与、各種申請などの関連業務を一括して効率的にサポートするツールです。裁量労働制などの複雑な勤務体制にも対応しており、適正な労務管理に力を発揮します。
Excel
Excelやグーグルのスプレッドシートなどの表計算ツールを使用して、残業時間の計算をする方法もあります。パソコン1台で対応できるため、手軽に利用できるのが利点です。
残業時間や残業代の計算に使えるテンプレートが、ネット上で数多く配布されています。テンプレートを自社の就業規則などにあわせてカスタマイズすることで、使い勝手の向上が可能です。
リモートワークやフレックスタイム制など、多様な働き方を認めている企業の場合、カスタマイズが複雑になる懸念があります。法改正や就業規則変更があった際には、自社で修正しなければならない点にも注意が必要です。
残業代計算ツール
残業代の計算に特化したツールも提供されています。基本給や割増賃金率などの基礎的な情報を入力するのみで、従業員の残業時間を自動的に計算できます。クラウド上で提供されているものであれば、法改正への対応が自動で行われるため便利です。
残業時間の計算に使うツールの選び方

この項では、残業代の計算に使うツールの選び方について解説します。
自社の勤務形態、業務フローに適したツールを選ぶ
少人数で勤務形態がシンプルな企業であれば、Excelを使った残業時間の計算にも対応可能です。フレックスタイム制や裁量労働制、在宅勤務など、勤務形態が複雑な場合には人事管理システムの活用をおすすめします。
また、給与計算や帳票類の発行など、人事労務まわりの業務を連携させたい場合にも人事管理システムが役立ちます。自社の規模や要件に合わない高機能システムを導入すると、費用の無駄になりかねません。自社の人員規模や勤務形態、求める機能、費用対効果などを考慮して、適切なツールを選択してください。
他システムと連携できるツールを選ぶ
既存の給与システムなど、他のシステムと連携できるかどうかも選択のポイントです。システム連携ができれば、データ入力などがスムーズに進められ、業務フローの効率化につながります。他システムと連携できないツールを導入すると、データの読み込みに外部記憶媒体を使わなければならないなどの手間がかかってしまう可能性があります。
時間外勤務減!「ADPS」勤怠管理システムの活用事例

残業代を正しく支払うためには、勤怠管理を効率化できるシステムを活用するのがおすすめです。
カシオヒューマンシステムズ株式会社が提供する人事統合システム「ADPS」は、給与計算や人事情報管理などを効率化できます。
東京センチュリー株式会社様
ここでは、ADPSを導入して時間外労働の減少に成功した、東京センチュリー株式会社の事例を紹介します。
東京センチュリー株式会社(以下、東京センチュリー)は、ADPSを導入し、従業員の勤務時間への意識向上を実現しました。具体的には、時間外労働を行う前にシステムで申請し、管理者の指示や承認を受けることを義務付けました。
ADPSを導入して時間外労働に対するルールを設けた結果、従業員の約82%が時間管理を意識して業務を行うようになったそうです。
詳細は、以下をご覧ください。
参考:ADPS導入事例 東京センチュリー株式会社様
カシオ計算機株式会社様
カシオ計算機株式会社では、全社の人事情報を一元管理できる統合パッケージ「ADPS」を導入し、月末の勤怠集計業務の手間を大幅に削減。従来は人事部門がExcelで集計していた残業時間や勤怠情報も、各拠点の入力を自動集約・可視化することで、リアルタイムな残業状況の把握と抑制が可能になりました。
人事ご担当者様からは「部門長が部下の残業実態をすぐ確認でき、業務配分や是正指導がしやすくなった」との声もあり、未払い残業リスクの低減と業務効率の両立を実現しています。
詳細は、以下をご覧ください。
参考:ADPS導入事例 カシオ計算機株式会社様
まとめ

企業には、残業代の支払い義務が課せられています。
残業には、所定労働時間を超えて行う法内残業と、法定労働時間を超えて行う時間外労働があり、後者については割増賃金を支払わなければなりません。割増率は残業時間の種類によって異なります。また、残業代の計算方法は、給与形態や労働形態によってさまざまです。
残業代を正しく支給できるよう、残業時間の定義を理解し、残業時間を適切に把握しましょう。
管理職でも残業代は出ますか?
固定残業代を超えた場合、どうなりますか?
残業代の時効はありますか?
カシオヒューマンシステムズコラム編集チームです。
人事業務に関するソリューションを長年ご提供してきた知見を踏まえ、
定期的に「人事部の皆様に必ず今後の業務に役立つ情報」を紹介しています。