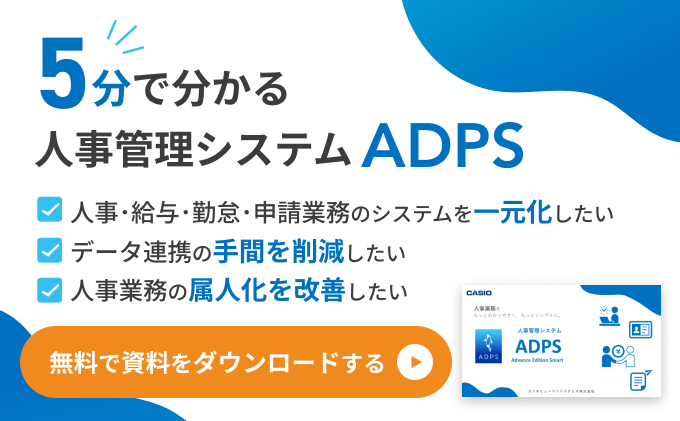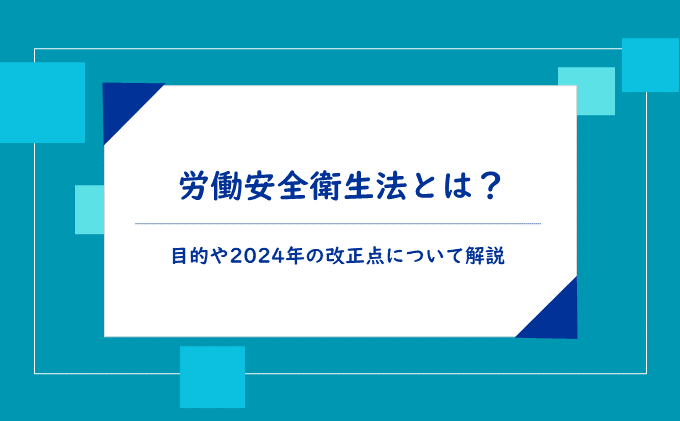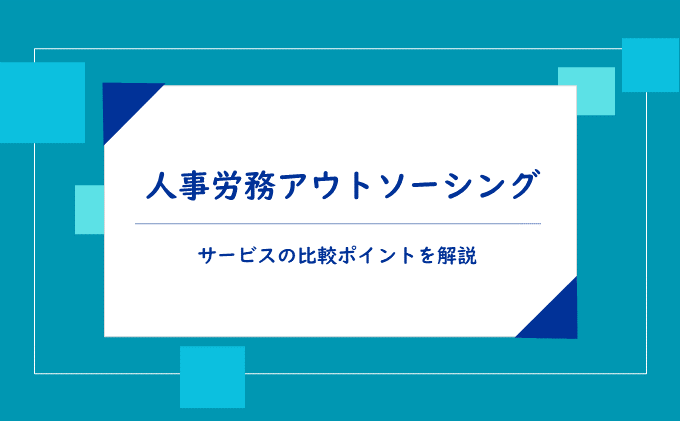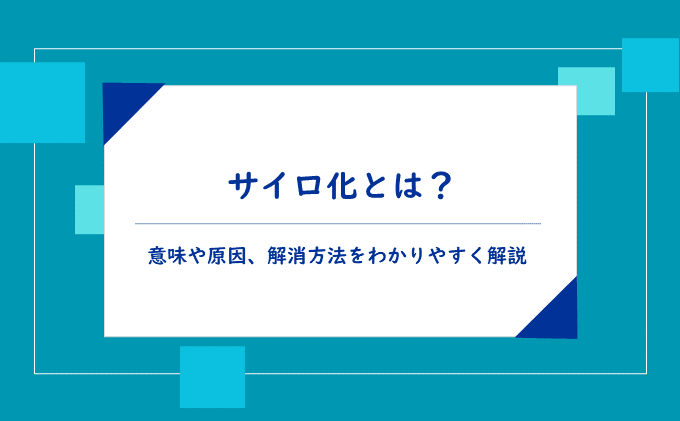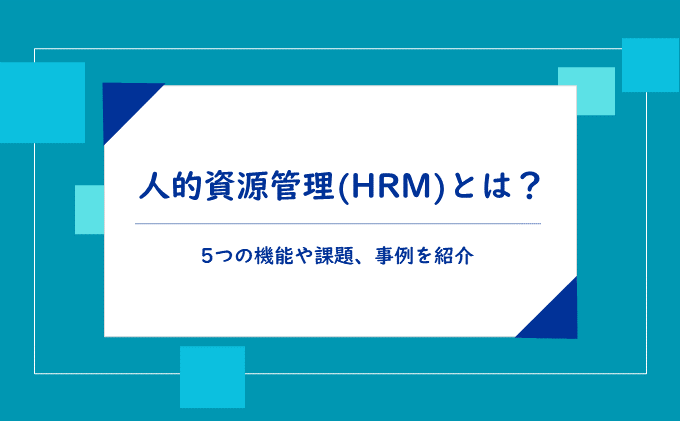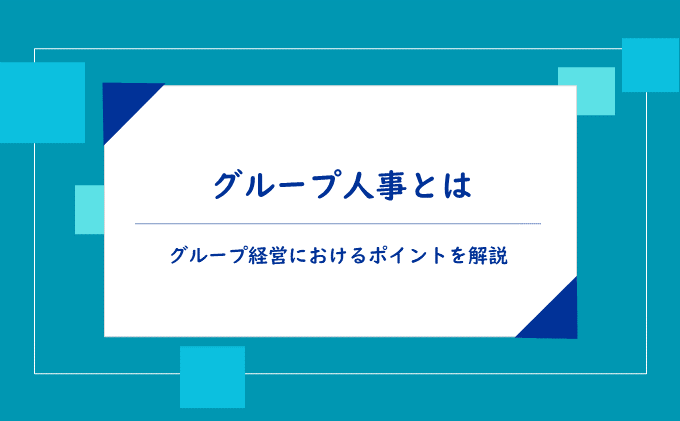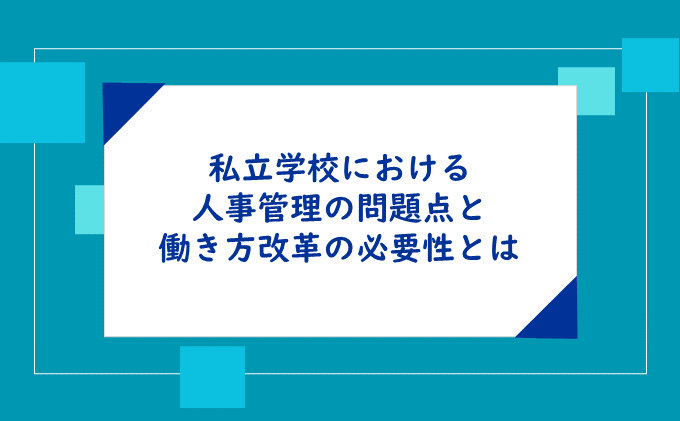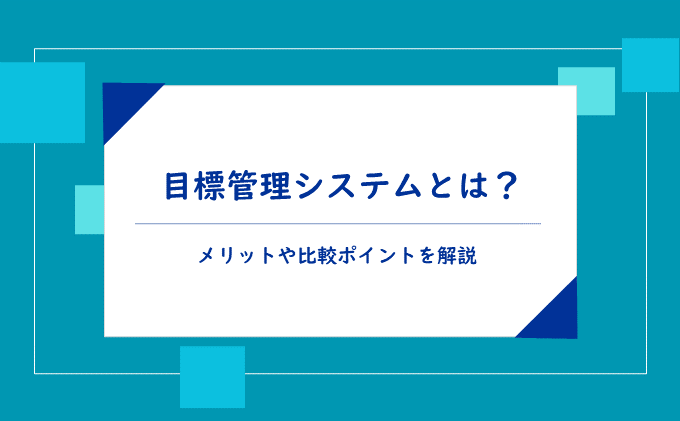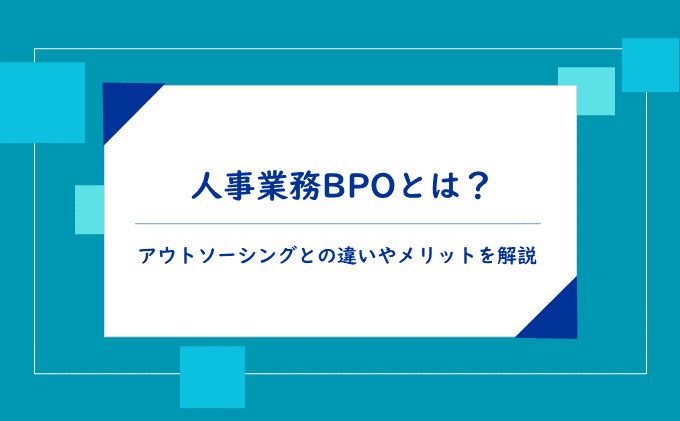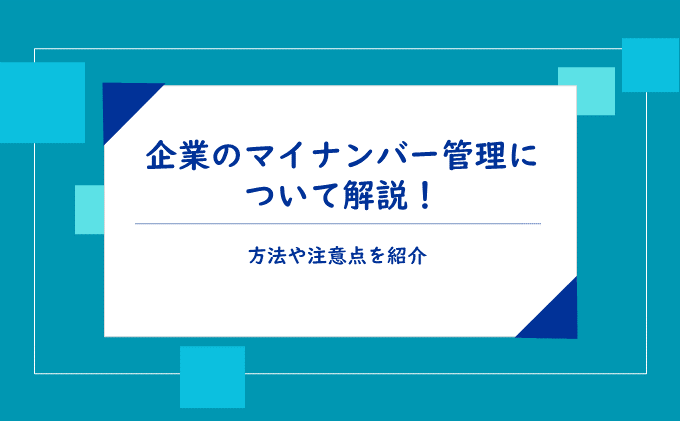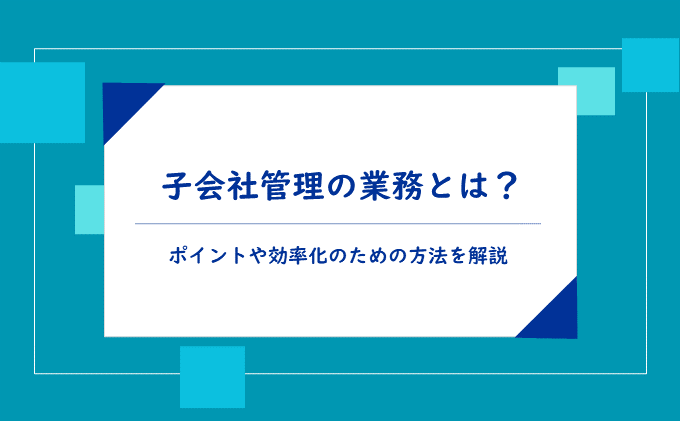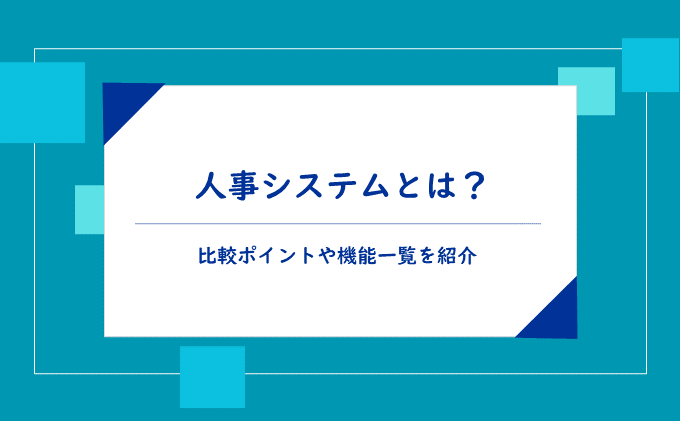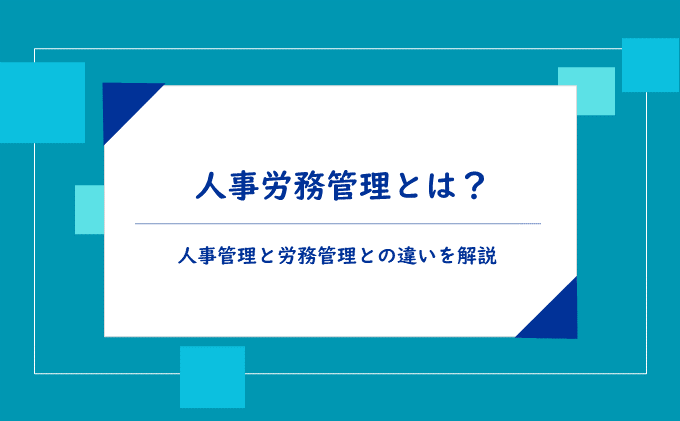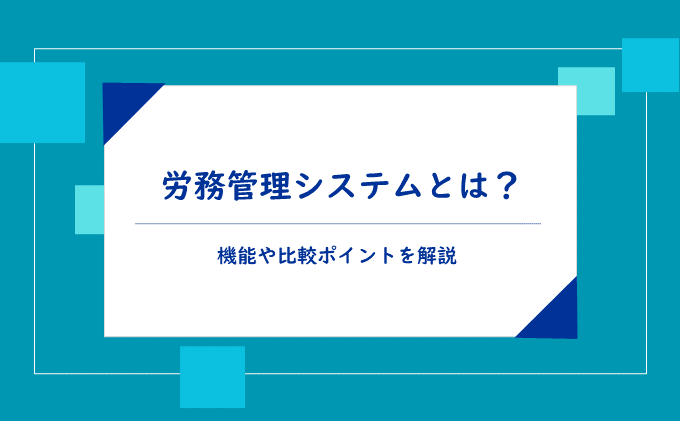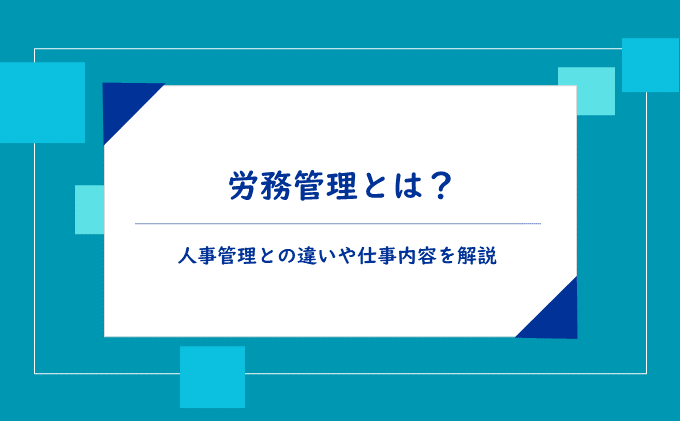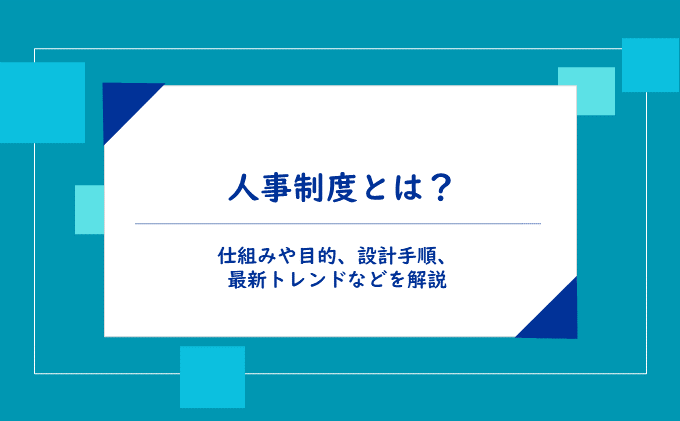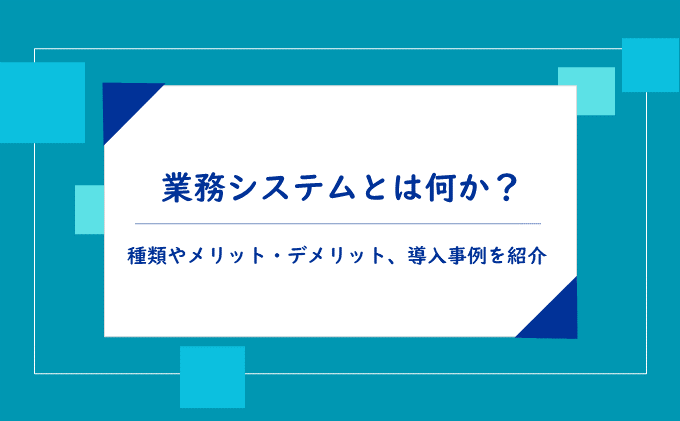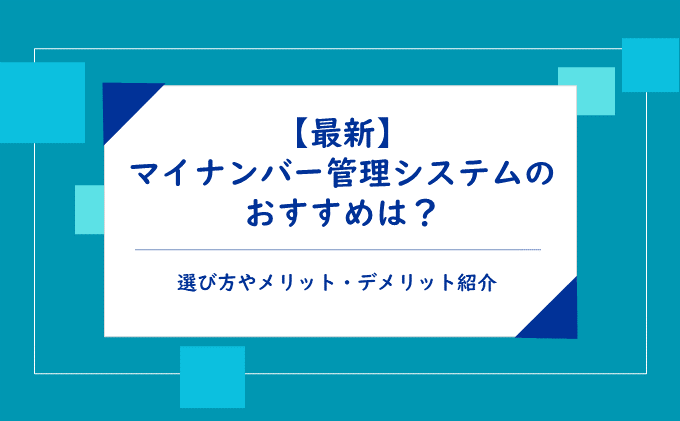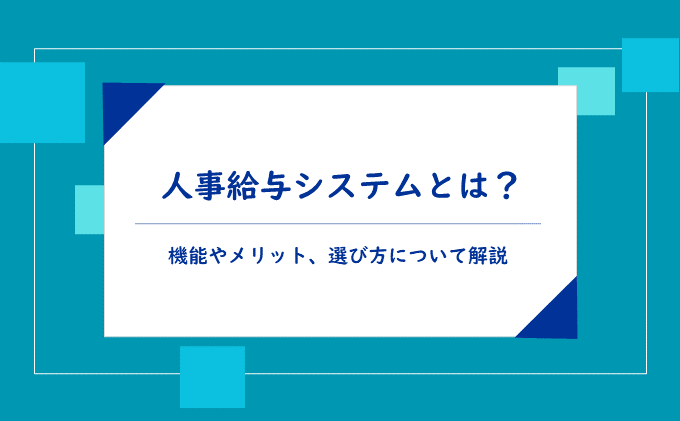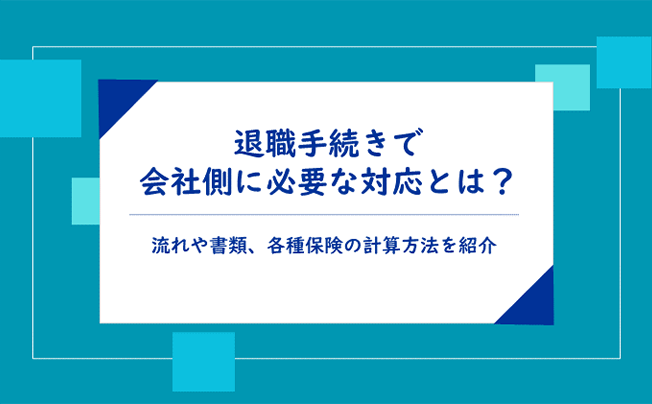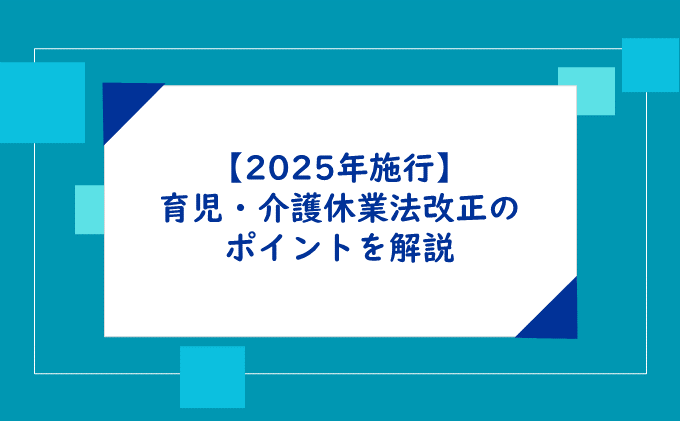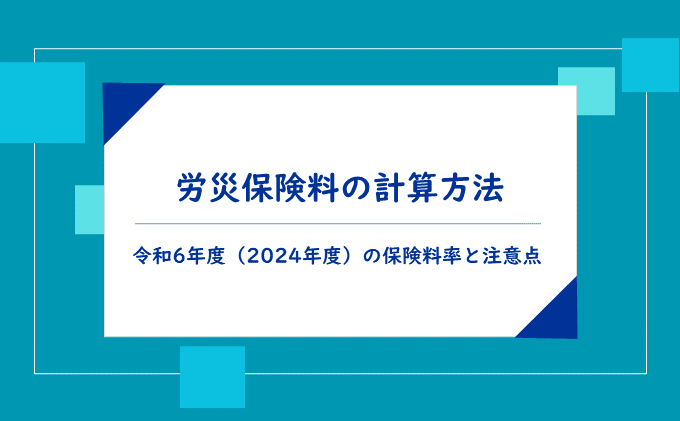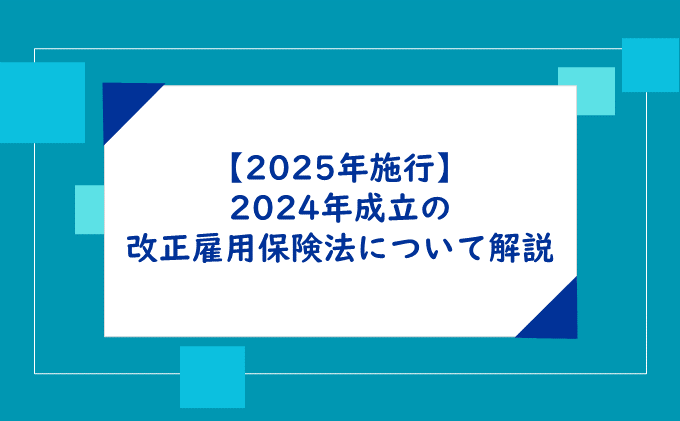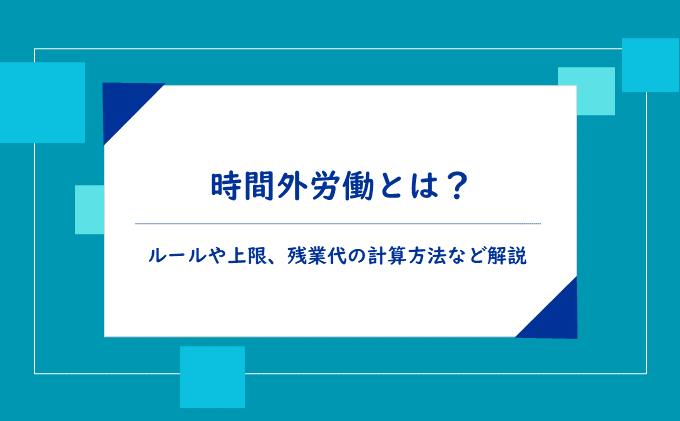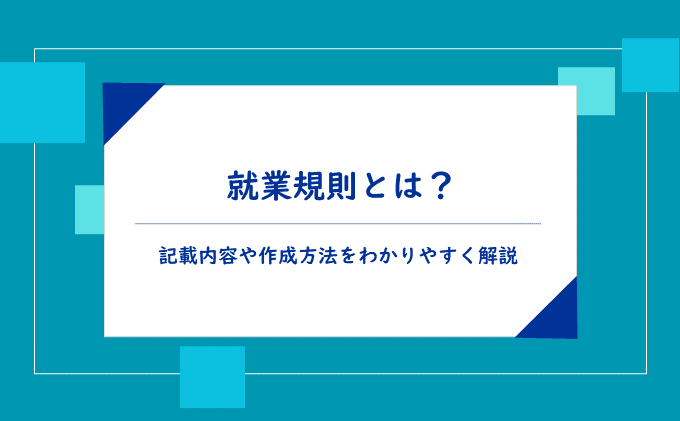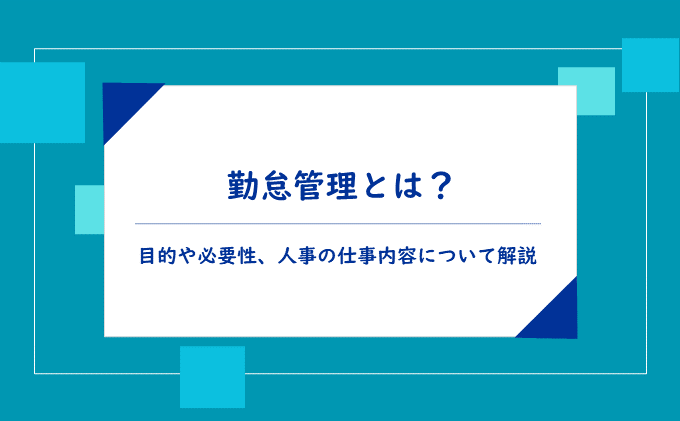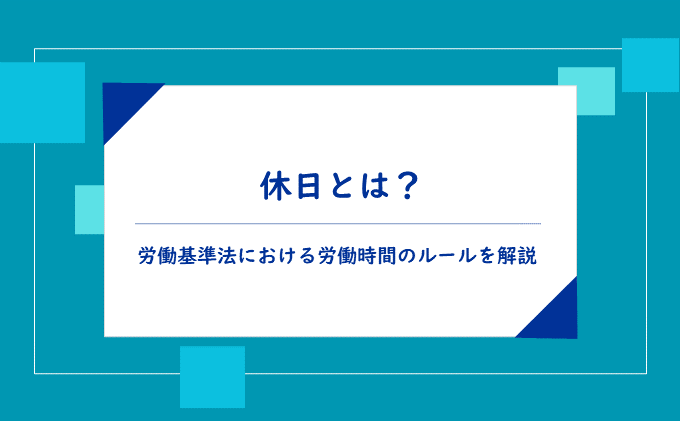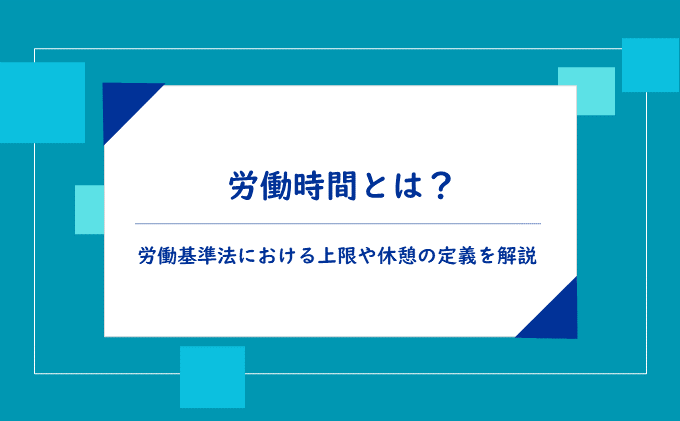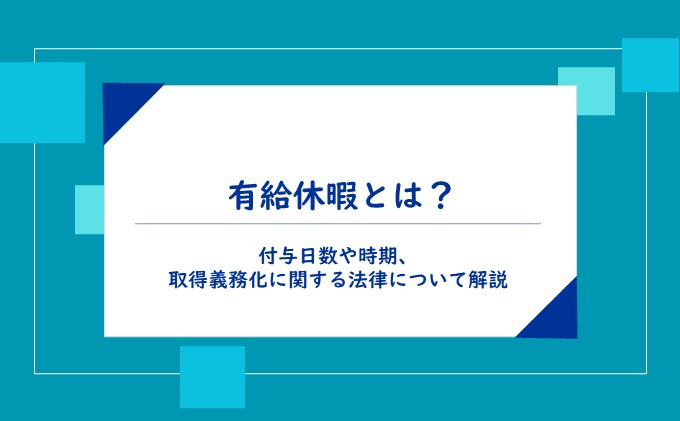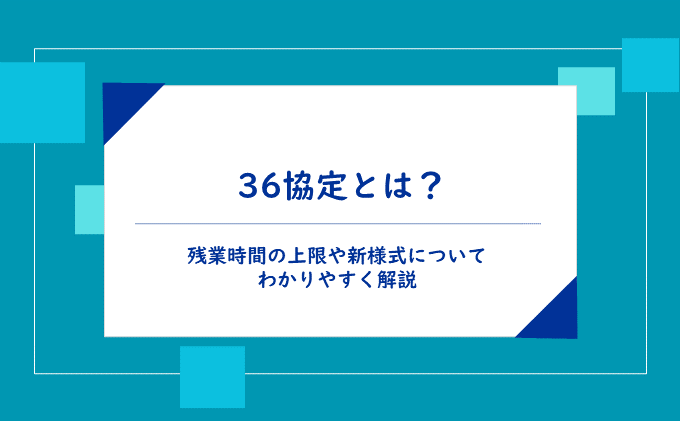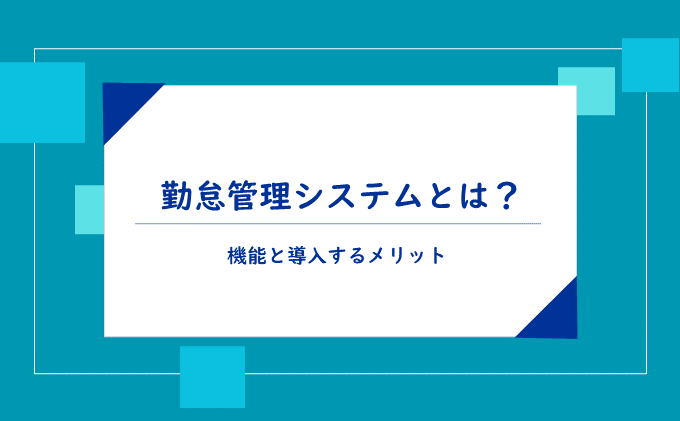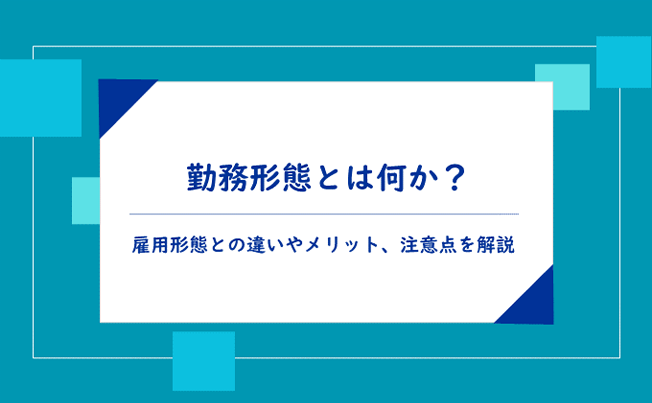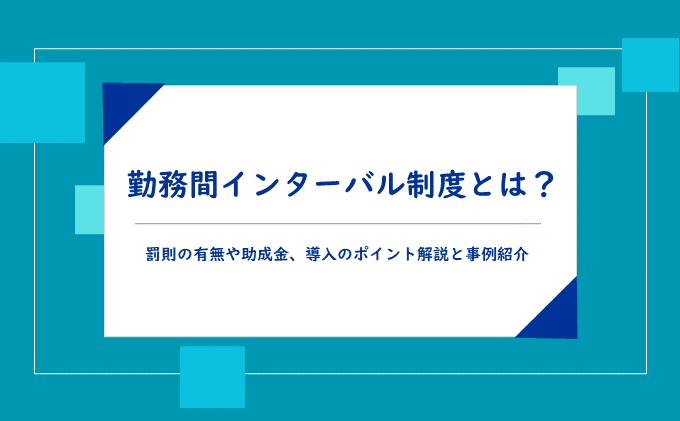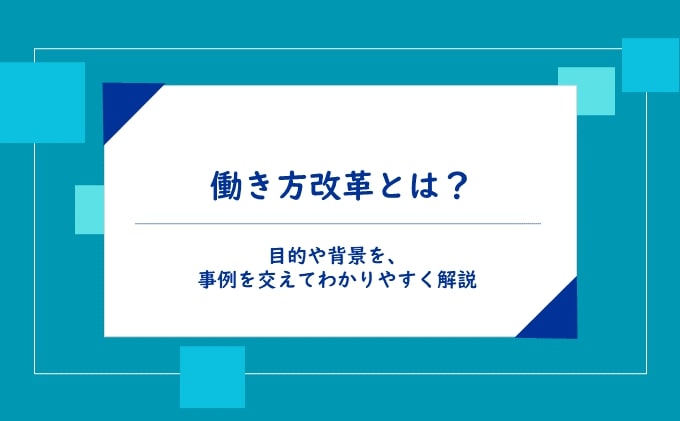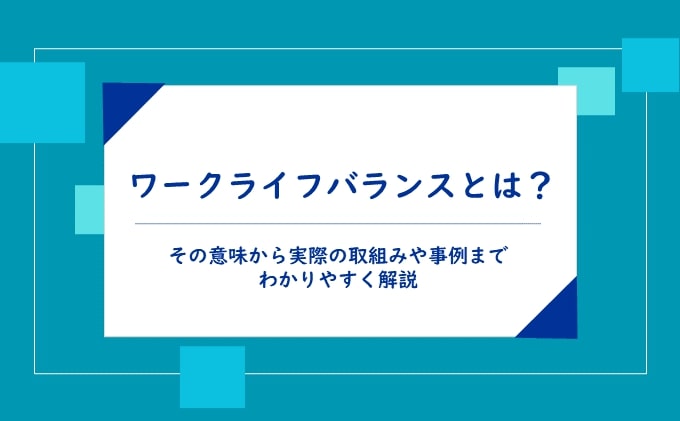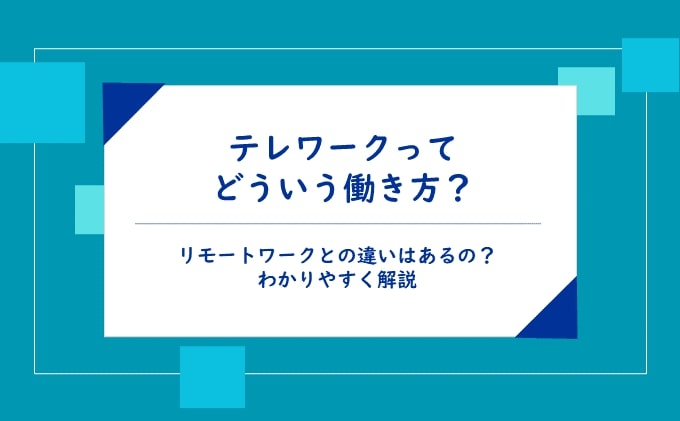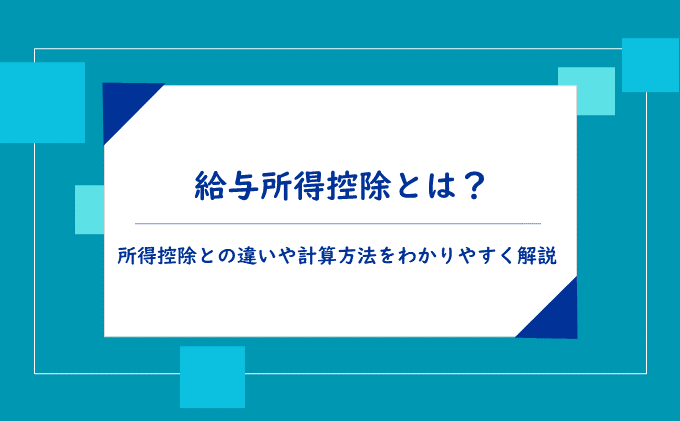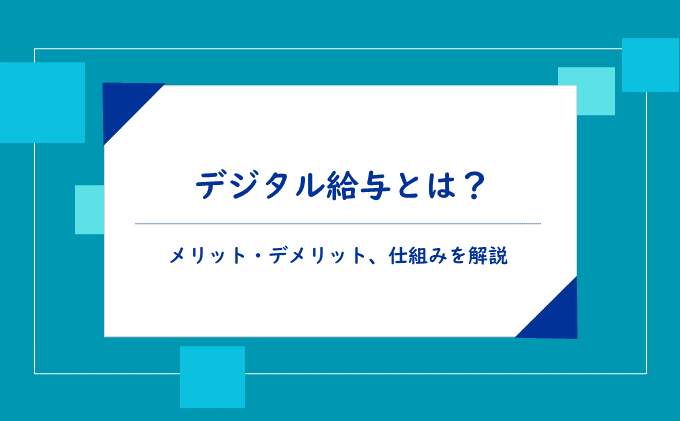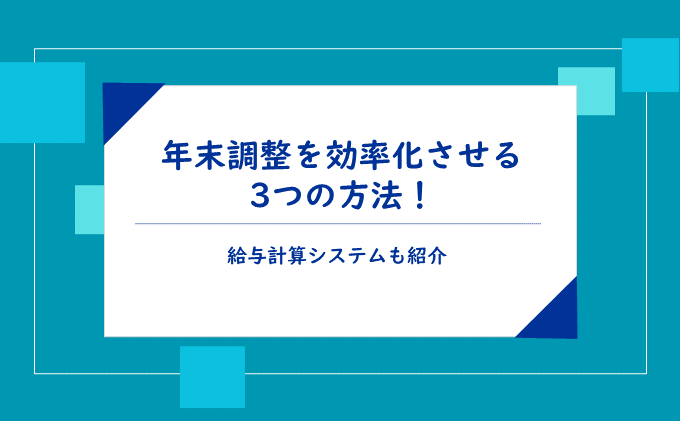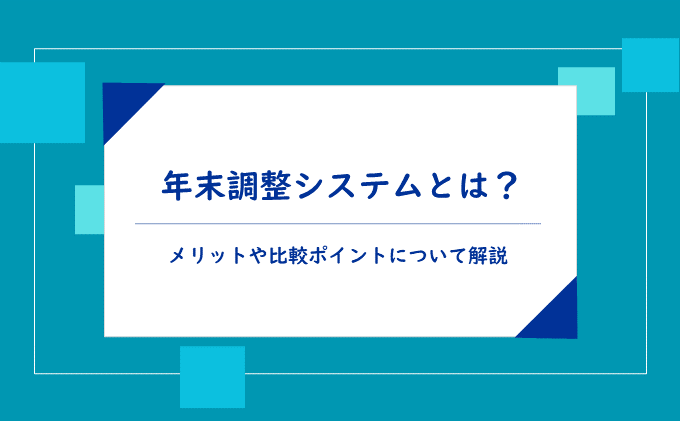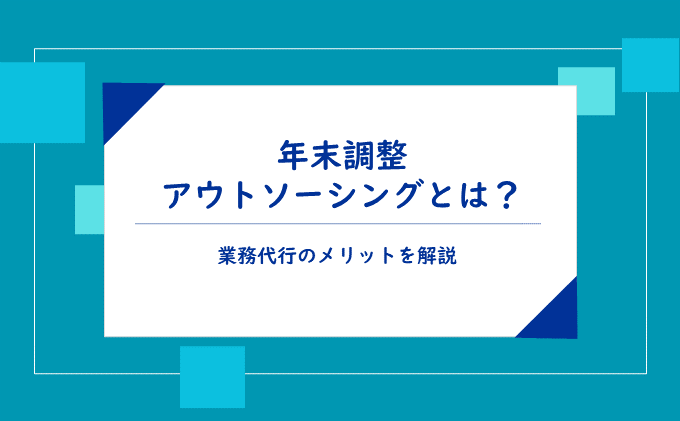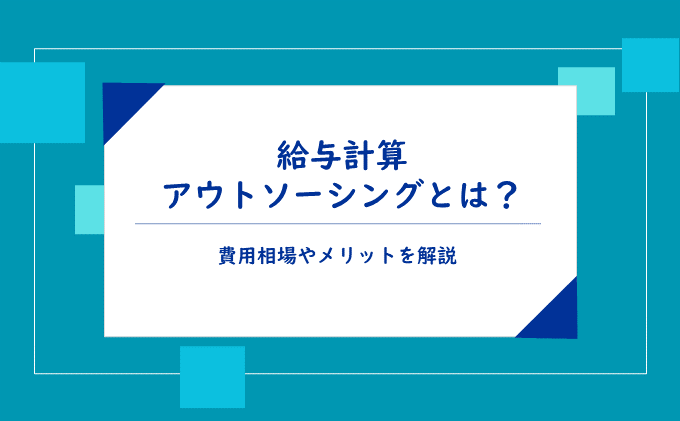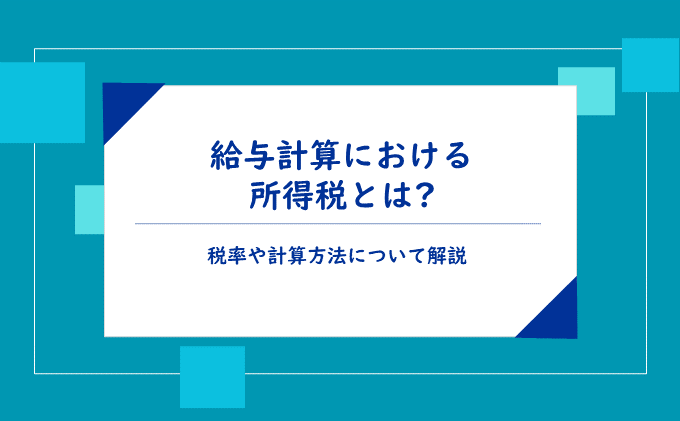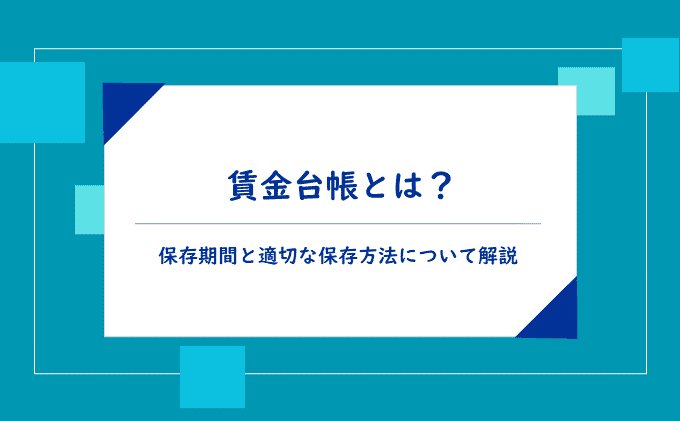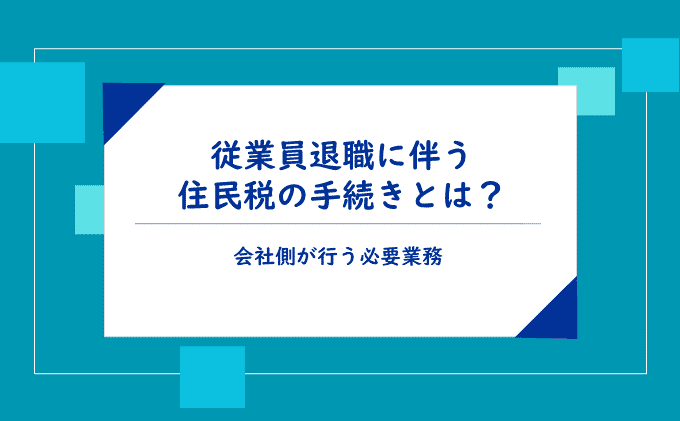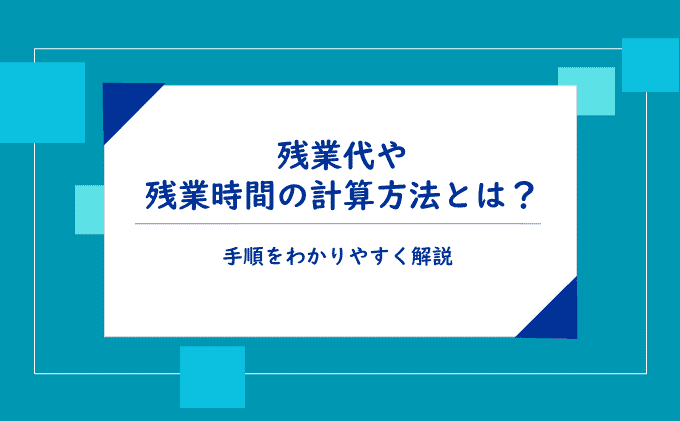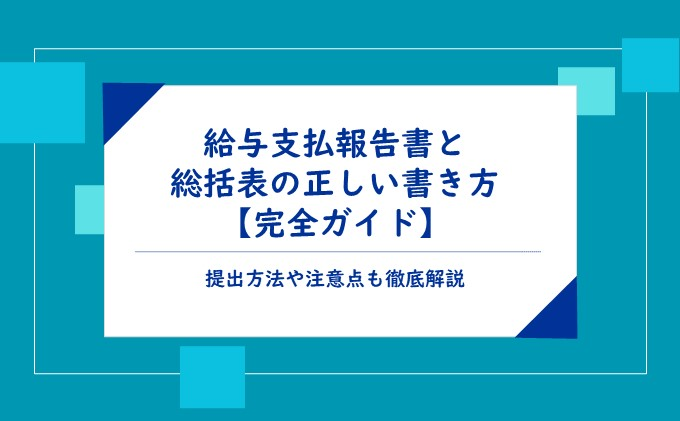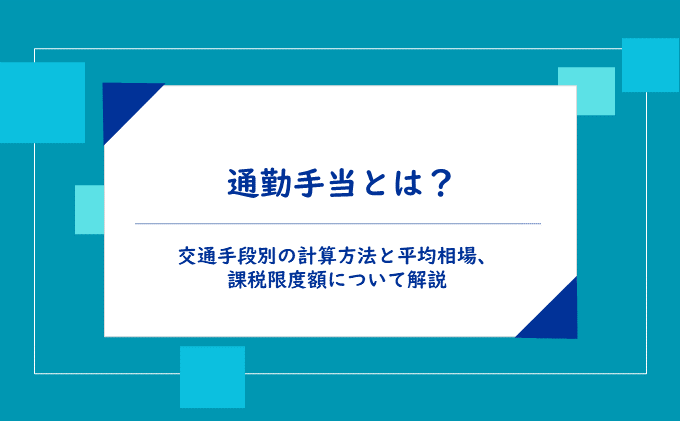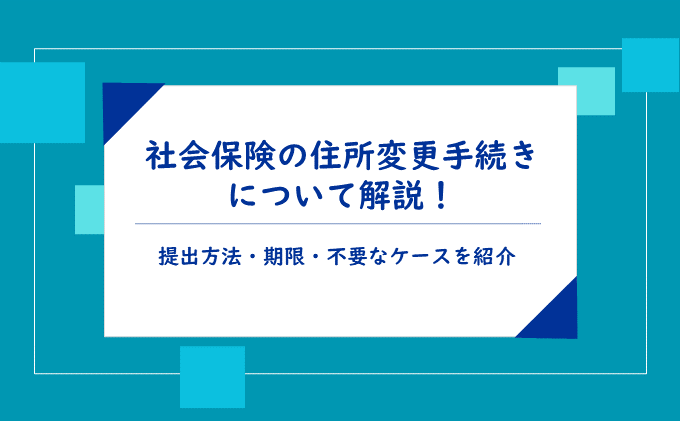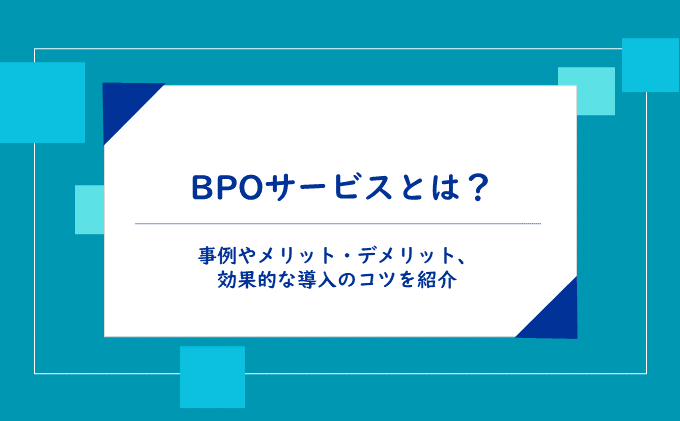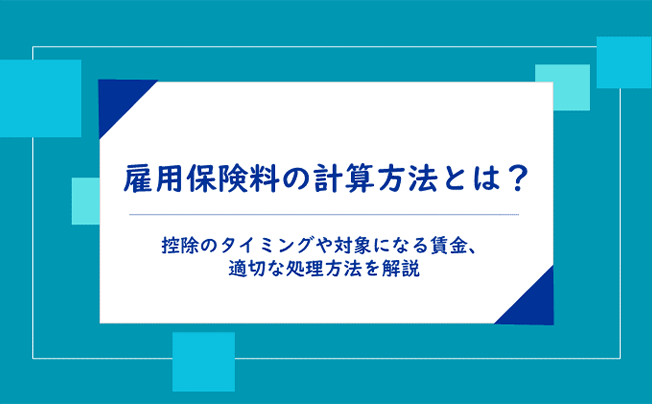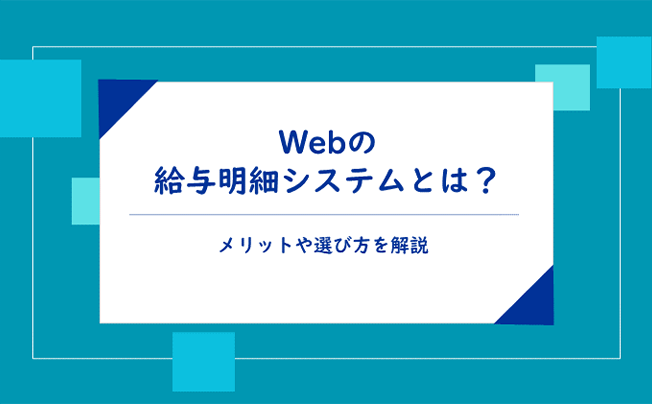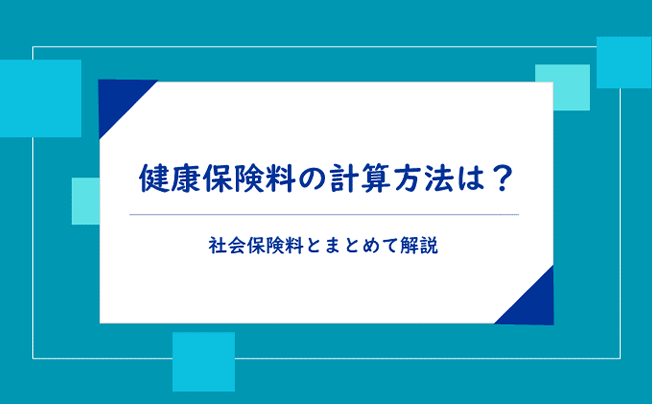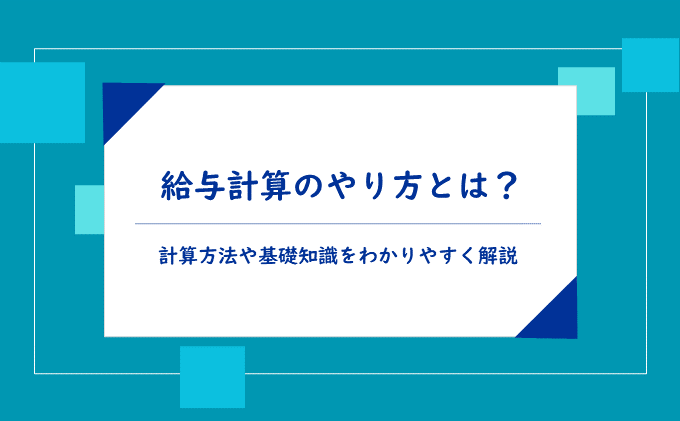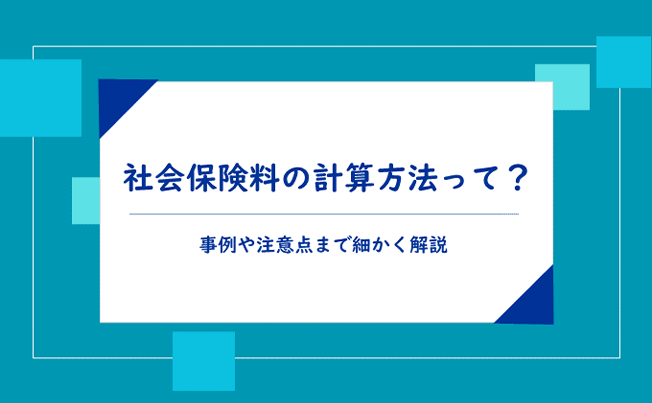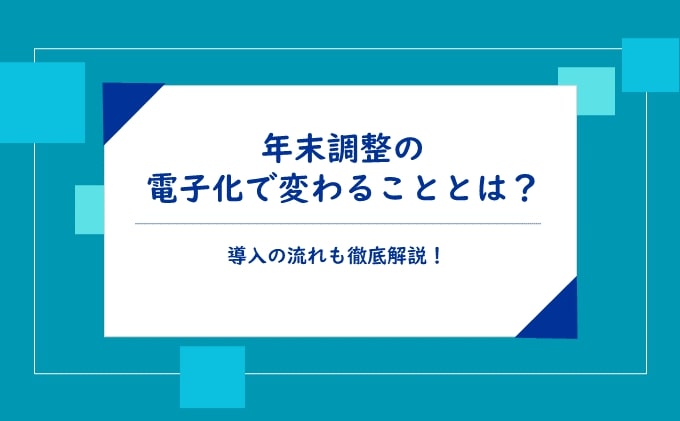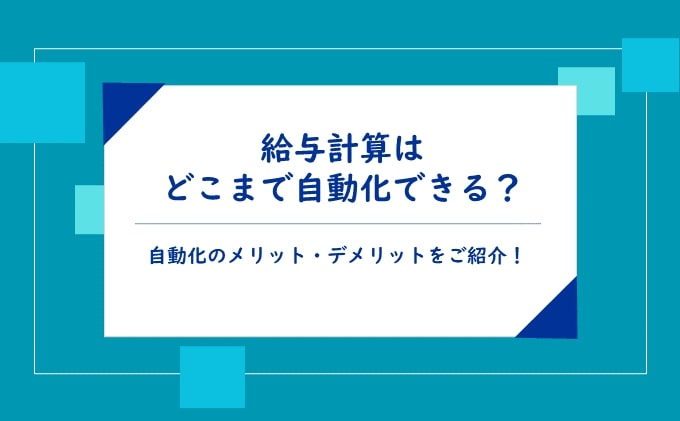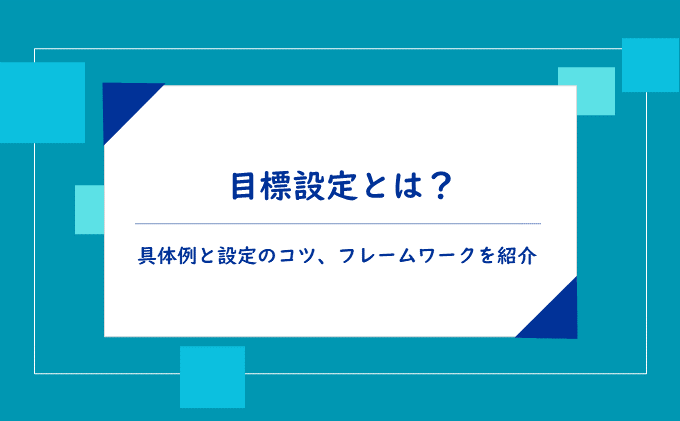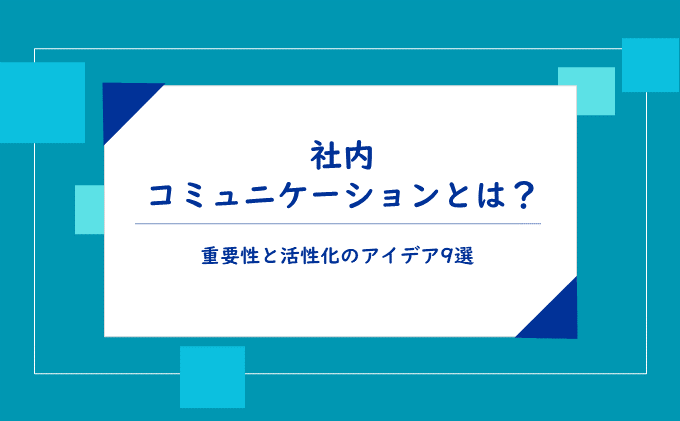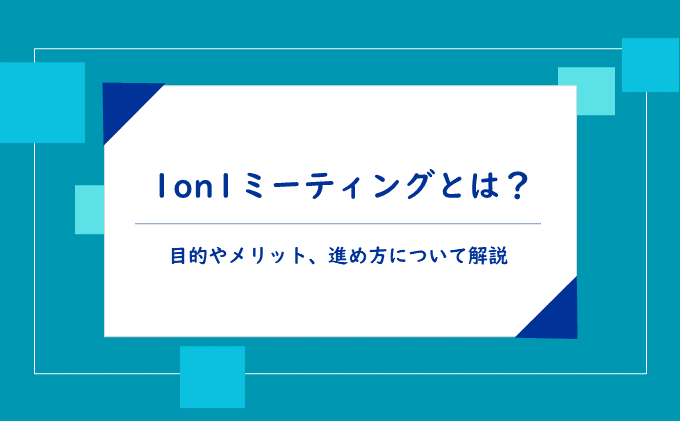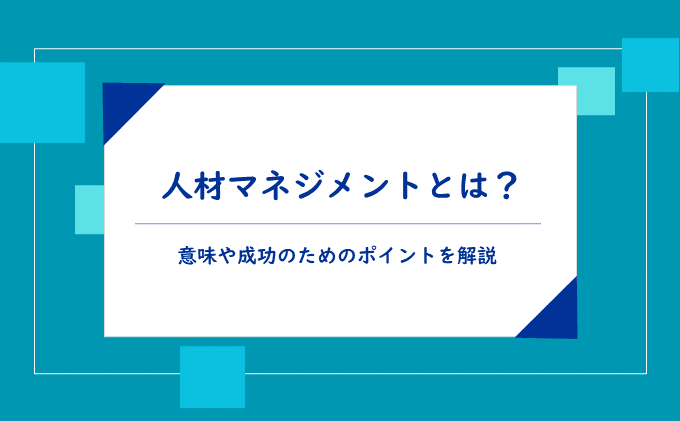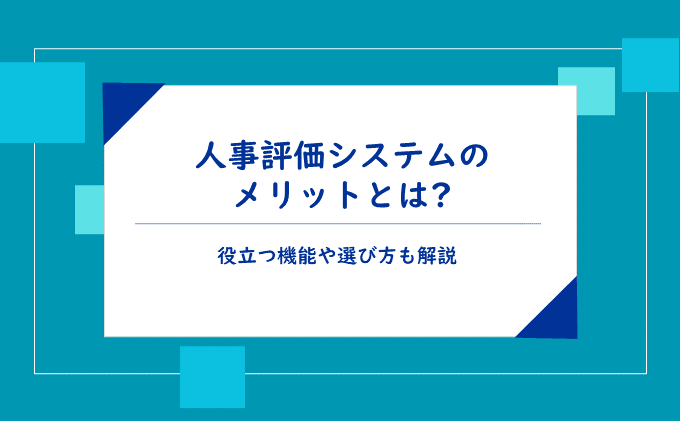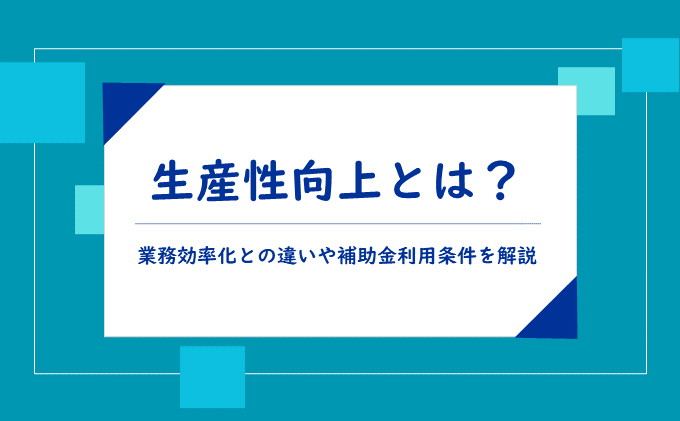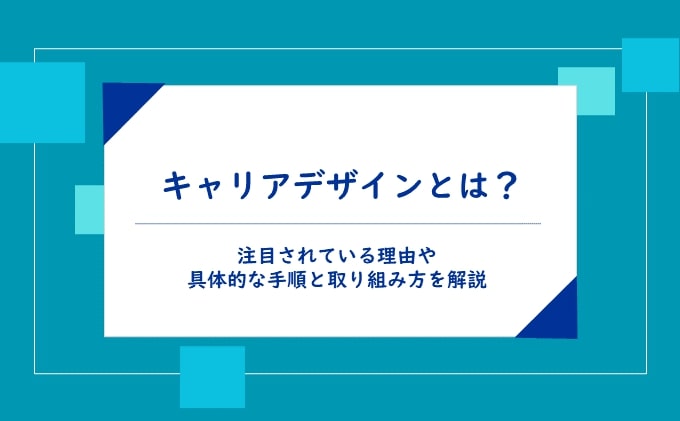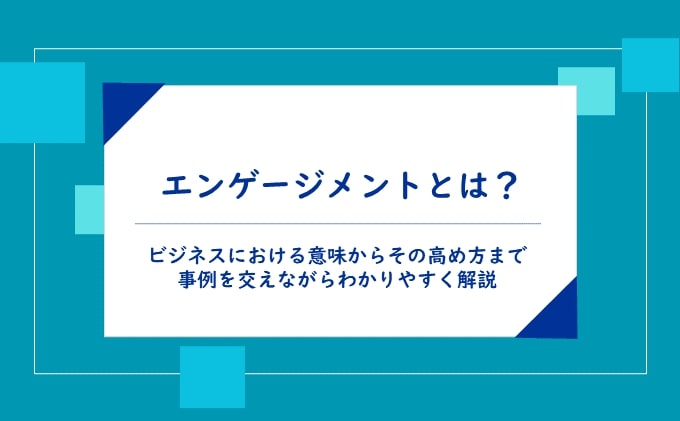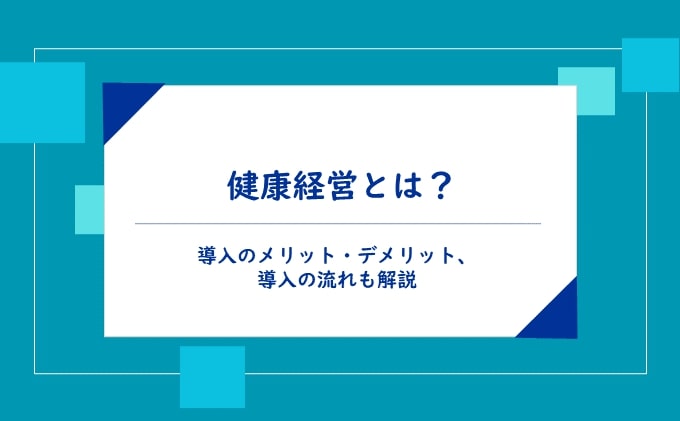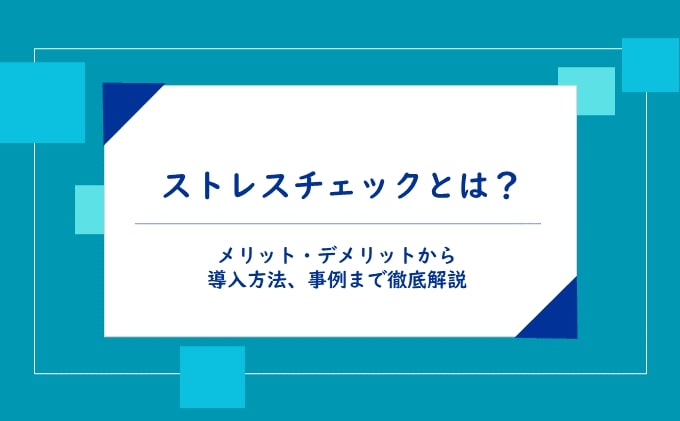年末調整とは?確定申告との違いや必要書類、申請手順を解説
2025.07.17
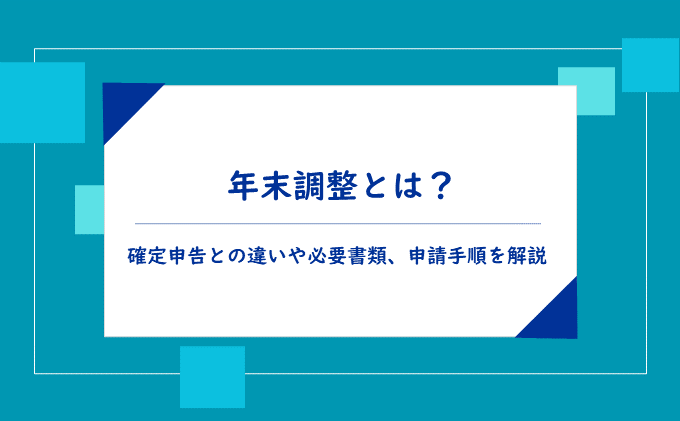
企業の人事部や経理部に所属している方にとって、「年末調整」の時期は繁忙期といえます。年末調整の手続きは煩雑で、締め切り日まで気が抜けません。本記事では、年末調整と確定申告の違いをはじめ、必要書類や申請手順、効率化する方法などについても解説します。
目次
年末調整と確定申告の違いとは

会社勤めの方であれば、「年末調整」という言葉は耳になじみがあるでしょう。毎年11月ごろから作業が開始され、各種書類の提出などを求められます。
年末調整の時点で所得税の徴収額に不足があれば追加徴収が行われますが、所得税を納めすぎている場合には還付されます。年末調整は、1年分の納税額の精算と捉えることも可能です。
なお、所得税の支払いや還付に関する手続きには「確定申告」もあります。両者の違いを、以下の項で見ていきます。
年末調整は企業が行う手続き
年末調整とは、所得税の過不足を企業が調整する手続きのことです。企業は給与やボーナスを支払う際に、所得税を概算して天引きして納税しています。年末に1年分の所得と納税額がまとまる年末に、概算で支払った所得税と、確定した年間の所得税額を合致させる手続きが年末調整です。
年末調整と確定申告の大きな違いは、「誰が主体で行うか」です。年末調整は企業が行う手続きである一方、確定申告は本人が行います。
企業には、従業員に給与やボーナスを支払う際、所得税を本人の代わりに徴収して納税する義務があります。本人の代わりに企業が納税する手続きが「源泉徴収」です。
毎月の給与や半期ごとなどに支給されるボーナスから源泉徴収している所得税額は概算であり、正確なものではありません。概算で徴収を行う理由は、年間の所得がいくらになるかが年末まで確定しないためです。
年末調整の手続きは毎年10月ごろから翌年1月にかけて行います。勤務先の企業から申告書の提出を依頼されるのは、おおむね10~11月ごろです。
確定申告では、年末調整では対応しきれない納税や還付の手続きを従業員本人が行います。申告の時期は、翌年の2月中旬から3月中旬です。
年末調整は、企業や団体に勤める人の給与所得のみが対象ですが、確定申告は企業に勤めていない自営業者や、事業所得など給与以外の所得も対象になります。企業に勤めている人でも、一定の条件に当てはまる場合には確定申告が必要です。
関連記事:源泉徴収票の作成方法と手順とは?記入例や所得税の計算方法も紹介
年末調整の対象者
年末調整の対象になるのは、会社から給与の支払いを受けていて、所得税を源泉徴収されている人で、形式的には「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が条件です。
また、年間を通じてその企業に勤めているか、その年の途中から勤め始めて年末まで勤めた人が対象です。正社員以外にも、アルバイトやパート、契約スタッフなども含まれます。
その年の途中で退職した場合でも、以下のようなケースでは年末調整が必要です。
- 年の途中で死亡した
- 年の途中で非居住者(海外赴任等)となり、その後(12月まで)は国内分の給与や賞与の支給を行わなくなる
- 心身の障害が著しく、年末までに再就職の見込みが立たない
- 12月に支払われる、年の最後の給与や賞与を受けてから退職した
- アルバイトやパートの従業員で、退職した際に年間の給与の合計が103万円未満である
アルバイトやパートであれば、ダブルワークの場合や、退職後に他の企業に勤めて年末まで給与が支払われる場合は除外されます。
年末調整の前に退職した従業員に対しては、転職先の企業が年末調整を行います。そのため、転職前の企業の源泉徴収票を転職先の企業に提出しなくてはなりません。
また、退職していなくても、海外転勤などで非居住者になった場合は、年の途中で年末調整を行います。非居住者とは、国税庁の定義では「居住者(国内に「住所」を有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人)ではない人」のことです。「居所」は、「生活の本拠ではないが現実に居住している場所」を意味します。
確定申告が必要な人
源泉徴収が義務付けられている企業に勤めている人のなかで、以下のどちらかに当てはまる人は確定申告が必要です。
- 年末調整の対象にならない
- 自分で確定申告することが必要な控除を受ける
以下のような場合は、年末調整の対象外になるため、自分で確定申告を行う必要があります。
- 1年間の主たる給与の合計額が2000万円を超える人
- ダブルワークなどで2か所以上から給与を受け取っている人で、自社ではない勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人
- 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が未提出の人
- 非居住者
- 日雇い労働者など同一の企業などに継続して雇用されない人
- 年の途中で退職した従業員のうち、前述の「年の途中で退職した場合でも年末調整が必要」なケースに該当しない人
- 災害減免法の適用を受けて所得税の徴収猶予や還付を受けた人
ダブルワークを行っている人は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出先はメインの勤め先1社のみです。メインの勤め先が年末調整を行い、他の勤め先では年末調整が行われないため、所得税の徴収に過不足がある場合には自分で確定申告する必要があります。
なお、自営業やフリーランスの人は確定申告が必要です。
年末調整で受けられる控除の種類

年末調整で受けられる控除の種類は多岐にわたります。以下の項で、各種の控除について詳細に解説します。
給与所得控除
所得税は、給与所得を基に課税される税金です。給与所得は、給与などの収入金額に応じた一定額を「給与所得控除」として差し引いて計算します。
給与所得控除は、所得税を計算する前段階で差し引かれるものです。自営業者などの「経費」に相当するものと考えられます。収入金額に応じた給与所得控除の額は、以下の表のとおりです。【※1】
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 162万5,000円まで | 55万円 |
| 162万5,000円超180万円まで | 収入金額の40% - 10万円 |
| 180万円超360万円まで | 収入金額の30% + 8万円 |
| 360万円超660万円まで | 収入金額の20% + 44万円 |
| 660万円超850万円まで | 収入金額の10% + 110万円 |
| 850万円超 | 195万円 |
※1:2025年3月、税制改正案が国会で可決されました。2025(令和7)年分の年末調整より、所得要件が変更となります。
参考:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
所得金額調整控除
所得金額調整控除は、2020年分から新設されました。「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」と「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」の2通りがあり、年末調整で対応できるのは前者です。
子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除が適用される対象は、自身の給与などの収入金額が850万円超で、以下の条件のいずれかを満たしている場合です。
- 本人が特別障害者に該当する
- 23歳未満の扶養親族がいる
- 特別障害者である同一生計の配偶者または扶養親族がいる
所得金額調整控除は世帯を対象とするものではないため、夫婦それぞれの収入が850万円超で、上記の条件のいずれかを満たしている場合には、夫婦いずれにも適用されます。
特別障害者とは、障害者のなかでもとくに重度の障害を持つ人を指します。国税庁の資料によれば、具体的には以下のような場合です。
- 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
- 重度の知的障害者と判定された人
- 精神障害者保健福祉手帳を交付され、障害等級が1級と記載されている人
- 身体障害者手帳に障害の程度が1級または2級と記載されている人
- 原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている人
- 寝たきりの状態で複雑な介護を受けなければならない人
参考:国税庁「障害者と税」
所得控除
所得控除は給与所得控除と似た呼称ですが、内容や性質は大きく異なります。給与所得控除は勤め人の「経費」に相当するものであるのに対し、所得控除は納税者の個人的な事情に応じて税負担を軽減するものです。
所得控除は、給与所得控除とは別に収入金額から差し引かれ、所得税を計算するベースになります。所得控除には15種類あり、そのうち年末調整で対応できるのは以下の12種類です。【※2】
| 控除の名称 | 概要 |
|---|---|
| 基礎控除 | 本人の合計所得金額が2400万円以下の場合は48万円、2400万円超2450万円以下の場合は32万円、2450万円超2500万円以下の場合は16万円が控除される。2500万円超になると控除はない。【※2】 |
| 配偶者控除 | 本人の合計所得金額が1000万円以下で、所得税法上の控除対象配偶者がいる場合、一定額の所得控除が受けられる。控除額は所得金額や配偶者の年齢によって異なる。 |
| 配偶者特別控除 | 配偶者控除の適用が受けられない場合に、配偶者の所得金額に応じて一定額の所得控除が受けられる場合がある。配偶者の所得金額が48万円超133万円以下などの条件がある。 |
| 扶養控除 | 本人に16歳以上の控除対象扶養親族がいる場合に適用される。控除額は年齢や同居の有無などにより38万~63万円。 |
| 生命保険料控除 | 本人が生命保険、介護保険、個人年金保険の保険料を支払った場合に一定額の所得控除を受けられる。控除額の最大は12万円。 |
| 地震保険料控除 | 本人が特定の損害保険などにかかる地震保険部分の保険料や掛金を支払った場合に、一定額の所得控除を受けられる。控除額の最大は5万円。 |
| 社会保険料控除 | 本人や生計を一にする親族の社会保険料を支払った場合、全額を控除できる。対象となる社会保険料は健康保険料、国民年金保険料、厚生年金保険料、国民健康保険料または国民健康保険税、介護保険料など。 |
| 障害者控除 | 本人や同一生計配偶者、扶養親族が所得税法上の障害者にあたる場合、一定額の所得控除を受けられる。控除額は障害者が27万円、特別障害者が40万円、同居特別障害者は75万円。 |
| ひとり親控除 | 本人がひとり親である場合、一定の条件に当てはまれば33万円の控除が受けられる。 |
| 勤労学生控除 | 本人に勤労による所得があり、合計所得金額が75万円以下などの条件を満たす学生である場合、27万円の控除が受けられる。 |
| 寡婦控除 | 本人が夫と離婚または死別した後婚姻せず、扶養家族がいて合計所得金額が500万円以下などの条件を満たす場合、扶養家族の有無により27万~35万円の控除が受けられる。 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 本人が小規模企業共済法に規定された共済契約に基づき掛金などを支払った場合には、掛金の全額が控除される。 |
ひとり親控除は、男女を問いませんが、寡婦控除は女性のみが対象であるため、注意が必要です。
※2:2025年3月、税制改正案が国会で可決されました。2025(令和7)年分の年末調整より、計算方式が変更となります。
また、新たに「特定親族特別控除」が創設されます。
参考:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
税額控除
給与所得控除や所得控除は「所得税を計算するベース」から差し引かれる控除であるのに対し、税額控除は計算された所得税額から控除分を差し引くものです。税額から直接差し引くため、節税効果は高いといえます。
税額控除にあたるものには、2年目以降の「住宅借入金等特別控除」があります。一般的に「住宅ローン控除」と呼ばれるもので、年末調整が行われる企業に勤めている人でも、1年目は確定申告が必要です。2年目以降は年末調整で対応できます。
住宅購入以外にも、条件を満たしていればリフォームでも適用されます。
年末調整ではなく自分で確定申告が必要な控除
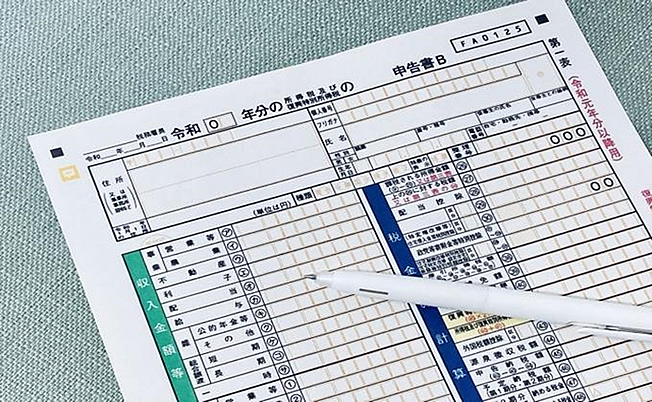
年末調整で対応できない医療費控除と寄附金控除、雑損控除を受けるためには、確定申告が必要です。また、「住宅借入金等特別控除」は、1年目は確定申告が必要です。
以下の項でそれぞれの控除について解説します。
医療費控除
医療費控除は、本人および生計を一にする親族が支払った医療費が一定額を超えた場合、所得控除を受けられる制度です。対象となる医薬品の購入費が一定額を超えた場合にも適用されます。
医療費については、年間10万円を超えた部分が所得控除されます。また、医薬品は、セルフメディケーション税制の対象となる一般用医薬品の購入費が1万2,000円を超えた場合です。
控除の上限は、医療費が200万円、医薬品は8万8,000円です。医療費と医薬品の両方の控除は受けられません。両方とも条件を満たしている場合には、確定申告の際にどちらかを選ぶ必要があります。
なお、生命保険から支払われた入院給付金や、健康保険などで支給される高額療養費などがあった場合は、医療費から差し引かなくてはならない点に注意が必要です。
総所得金額が200万円未満の人は、医療費が総所得金額等の5%の金額を超えた場合に控除の対象となります。そのため、医療費が10万円以下でも控除が適用されることがあります。
寄附金控除
本人が国や地方公共団体、公益性の高い法人などに寄付をしたときに利用できる控除が、寄附金控除です。寄附金控除の対象となる寄付は「特定寄附金」と呼ばれます。特定寄附金とは、以下のような団体などへの寄付金のことです。
- 公益社団法人
- 公益財団法人
- 日本赤十字社
- 自動車安全運転センター
- 社会福祉法人
- 更生保護法人
寄附金控除では、「特定寄附金の額 - 2,000円」または「その年の総所得金額の40% - 2,000円」が総所得金額から控除されます。
ふるさと納税も寄付金控除の対象です。自分が選んだ自治体に寄付を行うことをふるさと納税といい、専用のポータルサイトが複数運営されています。ふるさと納税を行う場合には、「ふるさと納税額 - 2,000円」が控除されます。
雑損控除
雑損控除は、盗難や災害などにより資産に損害を受けた場合に受けられる所得控除です。損害の原因は、以下の場合に限られます。
- 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
- 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
- 害虫などの生物による異常な災害
- 盗難
- 横領
横領の被害にあった場合は雑損控除の対象となりますが、詐欺や恐喝の被害は対象とならないことに注意が必要です。
控除を受けられるのは、以下の2つのうち多い方の金額です。
- (損害金額 + 原状回復などに支出した金額 - 保険金等の額)-(総所得金額等)× 10%
- (原状回復などに支出した金額 - 保険金等の額)- 5万円
住宅ローン控除(1年目)
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、1年目のみ確定申告を行わなければなりません。控除額は年末時点の住宅ローン残高の0.7%相当です。住宅の省エネルギー対応がどのレベルかによって、控除を受けられる住宅ローン残高の上限は変わります。子育て世帯・若者夫婦世帯(19歳未満の子どもがいる、または夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が長期優良住宅・低炭素住宅をローンで購入した場合、年間の控除額の上限は35万円です。
住宅ローン控除の適用期間は、最長で13年です。住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として以下のような条件があります。
- 住宅の床面積が50平方メートル以上で、床面積の2分の1以上が居住用
- 控除を受ける年分の合計所得金額が3000万円以下
- 10年以上にわたる返済期間の住宅ローンがある
リフォームや増改築の場合の適用条件は以下のとおりで、いずれかを満たす必要があります。
- 増改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または大規模な模様替えの工事
- マンションの専有部分の床、階段などについて行う一定の修繕・模様替えの工事
- リビング、キッチン、浴室、トイレなどの床、または壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
- 耐震改修工事
- バリアフリー改修工事
- 省エネ改修工事
リフォームや増改築では、改修工事費用から補助金などの額を差し引いた金額が100万円を超えている場合のみ控除されることに注意が必要です。
参考:国税庁「認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」
年末調整に必要な書類

年末調整が近づく10月中旬ごろになると、企業は必要書類を従業員に配布します。源泉徴収されている従業員が提出しなければならない書類があれば、対象となる従業員以外は提出が不要なものもあります。
年末調整は企業の義務であるため、督促して未提出者がないようにしてください。年末調整に必要な主な書類について、以下の項で説明します。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、12月31日時点での従業員の扶養親族に関する情報を記載する書類です。扶養親族がいない場合には、空欄のまま提出します。
個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」と統合された形式になっており、従業員は提出が必須です。記載する項目は、以下の控除に関する情報です。
- 扶養控除
- 障害者控除
- 寡婦控除
- ひとり親控除
- 勤労学生控除
該当する扶養親族の氏名、フリガナ、個人番号、その年の所得の見積額などを記載して提出することで控除が受けられます。
給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書
「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」は、4種類の申告を1枚にまとめた書式です。【※3】以下の所得控除に関して、適用されるかどうかが確認できます。
- 基礎控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 定額減税
- 所得金額調整控除
※3:2025年3月、税制改正案が国会で可決されました。2025(令和7)年分の年末調整より、「特定親族特別控除」が創設されます。これに伴い、同申告書に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の欄が追加される予定です。
このうち定額減税は、政府の経済対策の一環として2024年に限って実施されました。2024年6月1日以降、最初に支払われる給与や賞与の源泉徴収税額から、定額減税分を控除するという内容です。
所得税分として、従業員と同一生計配偶者、扶養親族の1人あたり3万円、個人住民税分としてはそれぞれ1万円が控除されています。従業員、同一生計配偶者、扶養親族の1人あたりの減税額は、合計4万円です。
6月1日以降の最初の給与や賞与で控除しきれない場合は、その後に支払う給与などから順次控除していき、2024年12月までに完了させます。2025年1月以降の給与などから天引きする源泉所得税からは控除できない仕組みでした。
なお、定額減税は1年のみの制度とされましたが、与党の「令和6年度税制改革大綱」には「今後、賃金、物価等の状況を勘案し、必要があると認めるときは、所要の家計支援の措置を検討する」との文言が盛り込まれています。定額減税の再実施があり得ることに留意しておく必要があります。
関連記事:定額減税4万円(所得税3万、住民税1万)2024年の概要を解説
給与所得者の保険料控除申告書
給与所得者の保険料控除申告書は、本人が支払った社会保険料や生命保険料などの控除額を計算するための書類です。この申告書に関連する控除は、以下のとおりです。
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
生命保険料控除は、「新保険料」と「旧保険料」に分かれています。保険会社から送られてくる保険料控除証明書には、申告書に記入すべき内容が記載されていることを従業員に周知することも大事です。
生命保険料(一般の生命保険、介護医療保険、個人年金保険)、地震保険料、小規模企業共済等掛金の各控除と、社会保険料控除のうち国民年金保険料等については、支払金額を示す書類を添付する必要があります。
控除のために必要な書類
控除を受ける対象者のみ、提出が必要な書類もあります。住宅ローン控除を受けるための「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 兼 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書」はそのうちの一つです。
住宅ローン控除を受けるためには、1年目に確定申告を行う必要があります。住宅ローン控除を受ける最初の年にあたる従業員であれば、の提出が必要です。
住宅ローンを借りた金融機関から11月ごろに送付される「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」も、あわせて提出します。複数の金融機関で住宅ローンを組んでいる場合は、すべての金融機関の年末残高等証明書が必要です。
ほかにも、対象者のみ提出が必要となる書類には、以下のようなものがあります。
- 生命保険料の控除証明書
- 地震保険料の控除証明書
- 国民年金の保険料や国民年金基金の掛金を支払ったことの証明書
- 配偶者特別控除を受けるために必要な源泉徴収票
年末調整の手順

この項では、年末調整の手順について説明します。年末調整は毎年10月ごろから始まり、翌年の1月10日が納付期限です。スケジュールが決まっているため、スムーズに事務処理を進めるための準備は欠かせません。
1.申告書類の配布と回収
人事・労務部門などから必要書類を従業員に配布し、記入を依頼することから年末調整は始まります。11月中には書類をそろえられるよう、10月ごろから配布を始めるのが一般的です。
配布と回収が必要な書類は、以下のとおりです。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得⾦額調整控除申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書
定額減税は2024年のみ実施されています。今後、経済対策の観点から実施論が浮上する可能性もあるため、注視が必要です。
提出書類を回収したら、抜けや漏れがないか入念にチェックしてください。申告書に不備があると、計算結果に誤りが生じ、再計算が必要になるなどの二度手間になりかねません。
なお、年の途中に他社から転職してきた従業員がいる場合には、前の勤務先で発行された源泉徴収票を提出してもらいます。
2.年調年税額の算出
提出書類がそろったら、必要な計算を行います。「年調年税額」とは、収入から各種税額控除を行った「1年間の本来の所得税額」のことです。
年調年税額の算出は、年末調整に関する事務におけるポイントの一つといえます。詳しい手順は以下のとおりです。
1.給与収入を計算する
第1段階として、その年の1月1日から12月31日までに支給した給与・賞与・各種手当の合計額を算出します。
2.給与収入から給与所得控除を差し引く
給与収入から「給与所得控除」の額を差し引き、「給与所得」を算出するのが、第2段階です。所得控除の額は、給与等の収入金額によって異なります。
3.給与所得から所得控除額を差し引く
従業員の提出した申告書に基づいて、所得控除の合計額を計算します。その分を差し引いて算出されるのが「課税給与所得金額」です。課税給与所得金額は、所得税を課す際のベースにあたります。
4.所得税額を確定する
課税給与所得金額を基に、「年調所得税額」を確定します。これは、年末調整により算出された、本来納めるべき所得税額のことです。
国税庁は「年末調整のための算出所得税額の速算表」を公表しています。システムを導入していない企業では、速算表を利用するのが一般的です。速算表は所得に対応した税率と控除額が一覧表になったものです。
税額を計算した後、2年目以降の住宅ローン控除を受ける従業員に対して控除を行います。住宅ローン控除は24年の税制改正で、省エネルギー基準を満たさない新築住宅は対象外になるなど、制度が変更されています。23年以前に購入した人に対する2年目以降の住宅ローン控除は、税制改正の影響を受けません。
2024年分では、年調所得税額から定額減税分を差し引く処理が必要でした。定額減税は2024年分のみの措置とされていますが、経済情勢や政治状況の変化によって再実施されることになった場合は、同じ処理を行うことになります。再び実施されるかどうかは、2025年3月時点では未定です。
定額減税が行われない場合、年調所得税額に復興特別所得税の2.1%を加えることで、最終的な「年調年税額」が算出されます。
なお、東日本大震災からの復興に必要な財源を確保するため、2013年から復興特別所得税の徴収が開始されました。所得税法の一部を改正する法律として施行されたものです。2037年までの間、各年分の所得税と復興特別所得税の年末調整をまとめて行います。
5.所得税の過不足を算出する
年調年税額と給与から差し引かれた源泉徴収税額を比較し、過不足を計算します。源泉徴収税額の方が多い場合は差額が還付され、少ない場合は追加で徴収されます。
通常であれば、12月分の源泉徴収で差額を精算し、最終的な源泉徴収税の納期限は翌年1月10日です。
年末調整の計算終了後、各従業員の源泉徴収票を作成します。同票には、以下のような内容が記載されています。同票は、12月の給与支払いと同時に交付するのが一般的です。
- 年間の支払合計金額
- 給与所得控除をした後の金額
- 所得控除額の合計
- 源泉徴収税額
- 社会保険料等の金額
- 控除対象配偶者の有無
3.申告書類の提出
計算が完了したら、税務署や、従業員の居住する市区町村に必要書類を提出します。いずれの書類も、翌年1月31日が納期限です。それぞれの提出書類については、以下の項で示します。
税務署に提出する書類
税務署に提出する書類は、以下のとおりです。
- 支払調書
- 法定調書合計表
- 源泉徴収票
支払調書には、企業が従業員に支払った給与や外部の取引先に支払った金額、天引きした源泉徴収額などを記載します。
また、法定調書合計表の正式名称は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」で、税務署に提出する各種の法定調書の内容をまとめた書類です。法定調書とは、法律により税務署への報告が定められている書類のことで、全部で60種類あります。
そのうちの6種類の法定調書は、年末調整時に取りまとめて法定調書合計表とともに提出することになっています。対象となる法定調書は、以下のとおりです。
- 給与所得の源泉徴収票
- 退職所得の源泉徴収票
- 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
- 不動産の使用料等の支払調書
- 不動産等の譲受けの対価の支払調書
- 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
法定調書合計表は、これら6種類の法定調書を取りまとめた冊子の表紙に相当します。
源泉徴収票は、従業員に交付する書類と同じものを税務署に提出します。
市区町村に提出する書類
市区町村に提出する書類は、「給与支払報告書」です。この報告書には「個人別明細書」と「総括表」の2種類があり、双方とも提出します。
個人別明細書は従業員ごとに給与の支払い状況をまとめたもので、総括表は事業所ごとに個人別明細書をまとめたものです。
関連記事:年末調整を効率化させる3つの方法!給与計算システムも紹介
年末調整をしないとどうなる?

年末調整は、源泉徴収を行っている企業や団体に対して課されており、所得税法190条にその旨が規定されています。
年末調整を行わない場合、所得税法違反で罰則を負う可能性があることに加え、以下のようなリスクも生じます。
- 従業員が所得税の還付を受けられない
- 従業員が所得控除を受けられない
- 従業員に確定申告の負担がかかる
以下の項で、年末調整を行わないデメリットやリスクについて解説します。
罰則のリスクがある
年末調整は、所得税法で義務付けられている手続きです。企業が年末調整にかかる源泉徴収義務を怠った場合、罰則として1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、年末調整を行ったにもかかわらず追加の徴収額を納付しない場合には、10年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその両方が科されます。これらの罰則は、所得税法240条、同242条の規定に基づくものです。
一方、従業員の申告書未提出や書類の紛失など、従業員の過失により年末調整を行えなかった場合には、罰則の対象にはなりません。従業員が後日、自分で確定申告を行うことになります。
従業員が所得税の還付を受けられない
年末調整を行わなければ、従業員が所得税を払いすぎていた場合でも還付は受けられません。年末調整では、実務上の還付が発生することが多く、追加徴収となるケースは希少です。
年末調整が行われなければ、税金の過払いにつながるのみでなく、過払い額がどの程度であるかがわかりません。
従業員が税金控除を受けられない
年末調整を行わなければ、従業員は所得控除を受けられません。前述のとおり、所得控除には16種類があり、そのうち12種類は年末調整で対応可能です。
所得控除を受けられなければ、所得税を課されるベースの金額が大きくなるため、税額も増えてしまいます。場合によっては、1段階上の税率がかかってしまうことも考えられます。
所得税率は所得金額によって7段階に分かれており、詳細は以下のとおりです。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円以上195万円未満 | 5% | 0円 |
| 195万円以上330万円未満 | 10% | 9万7,500円 |
| 330万円以上695万円未満 | 20% | 42万7,500円 |
| 695万円以上900万円未満 | 23% | 63万6,000円 |
| 900万円以上1800万円未満 | 33% | 153万6,000円 |
| 1800万円以上4000万円未満 | 40% | 279万6,000円 |
| 4000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
従業員に確定申告の負担がかかる
企業が年末調整をしなかった場合でも、従業員が自分で確定申告をすれば、払いすぎた税金の還付や所得控除の適用などを受けられます。
年末調整を行っていない企業は、源泉徴収票を交付していない可能性もあります。源泉徴収票がなければ確定申告は困難です。このような場合には、「源泉徴収票不交付の届出書」を税務署に提出することで、企業側に行政指導がなされます。
企業が年末調整を行わなければ、従業員の負荷が増すのみでなく、従業員の企業に対する信頼感が失われる可能性もあります。
年末調整業務を効率化する方法

年末調整業務では、書類の配布や回収などの手間が多く、限られた時間のなかで煩雑な事務処理をこなさなければなりません。この項では、年末調整業務を効率化する方法について解説していきます。
アウトソーシングサービスを利用する
年末調整業務を効率化する手段の一つに、アウトソーシングサービスの利用があります。事務処理のノウハウを持つ税理士や専門業者などに業務を任せることで、人事・労務部門の従業員を本来業務に集中させられる点がメリットです。
ただし、費用が発生するデメリットもあります。費用対効果を十分に検討したうえで、アウトソーシングサービスを利用するかどうかを決定してください。
関連記事:年末調整アウトソーシングとは?業務代行のメリットを解説
年末調整手続きを電子化する
紙ベースで行っていた事務手続きを電子化することも、効率化の一つの方法です。書類の配布や回収にかかる手間を削減できるほか、計算が自動化されることによりミスの減少に期待できます。また、従業員は書類作成の負荷が減ります。
給与システムと連携できるサービスを利用すれば、給与計算の自動化も可能です。年末調整手続きを電子化するためには、民間企業が扱うクラウドサービスなどを利用したり、国税庁が無償で提供している「年調ソフト」を利用したりする方法があります。
関連記事:年末調整の電子化で変わることとは?導入の流れも徹底解説!
給与計算・年末調整システムを導入する
年末調整の手続きのみを電子化するのではなく、給与計算から人事系の申請手続きなどを一括処理できるシステムの導入も一案です。年末調整のみでなく、毎月の給与計算や勤怠関連の事務処理もシステム化できます。
専用システムの導入は、帳簿の転記などにともなう人的なミスの防止に役立つ以外にも担当者の負担軽減にもつながり、より生産性の高い業務に人的リソースを配置できます。
関連記事:年末調整システムとは?メリットや比較ポイントについて解説
「ADPS(アドプス)」が年末調整のペーパーレス化を実現

カシオヒューマンシステムズ株式会社が提供する人事管理システム「ADPS(アドプス)」は、人事、給与、勤怠管理など、人事部門の事務処理をトータルでサポートします。年末調整のペーパーレス化にも対応しているため、書類の印刷や封入などの作業も不要です。
「ADPS」は累計5,000社以上に導入された実績を持つ、効率性と柔軟性に富んだシステムです。人事・労務部門の生産性を高めるために、ぜひ導入を検討してみてください。
まとめ

年末調整は、企業が従業員から天引きした所得税を年末に調整する手続きです。一方、確定申告は本人による手続きが必要です。
年末調整の手続きは、企業に義務として課されています。年末調整を行わなければ、従業員に税金の還付が行われなかったり、所得控除が受けられなかったりするなどのデメリットが生じます。
なお、年末調整では、書類の配布や回収、計算処理などの煩雑な作業が必要です。人的ミスや担当者の負荷を減らすための方法として、人事管理システムの導入が挙げられます。社内のリソースを最大限に生かし、効率的な事務運用をしたい場合には、導入を検討してはいかがでしょうか。
カシオヒューマンシステムズコラム編集チームです。
人事業務に関するソリューションを長年ご提供してきた知見を踏まえ、
定期的に「人事部の皆様に必ず今後の業務に役立つ情報」を紹介しています。