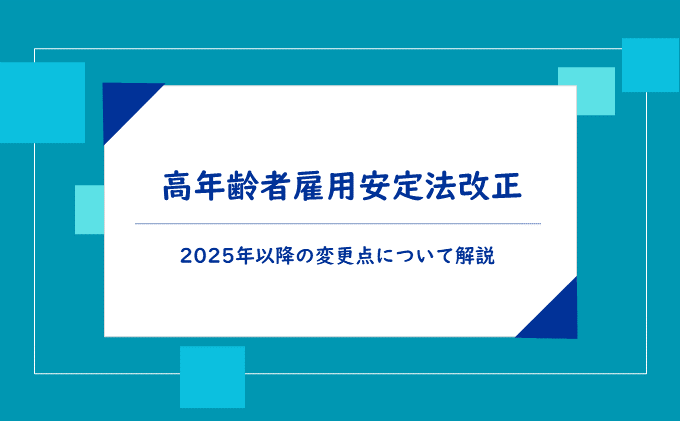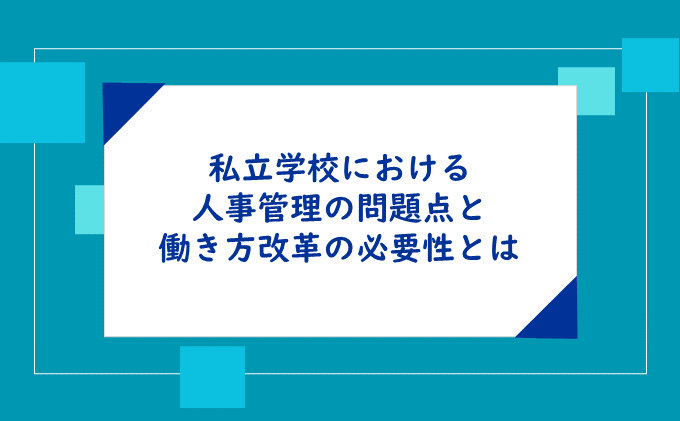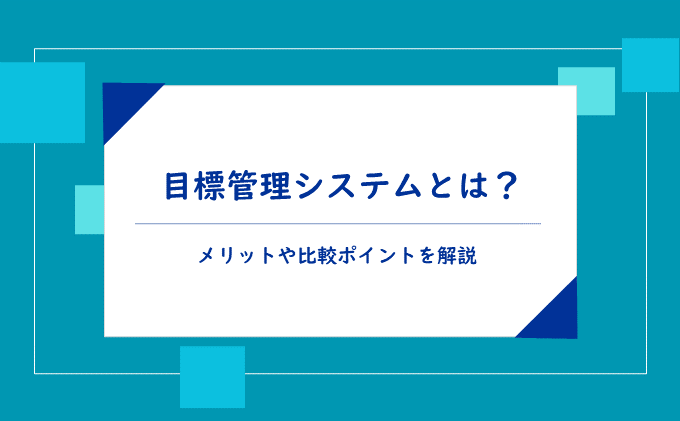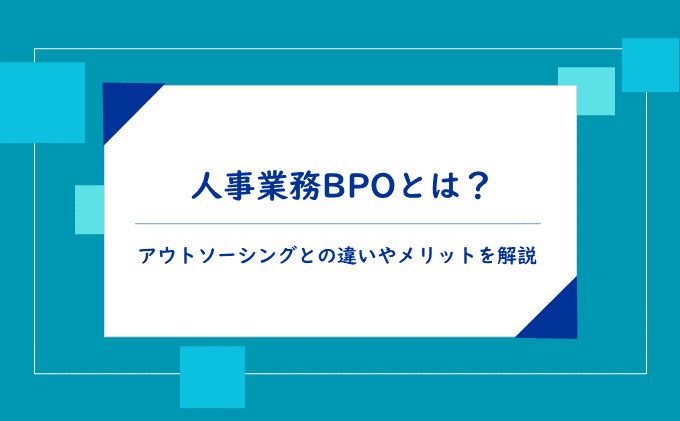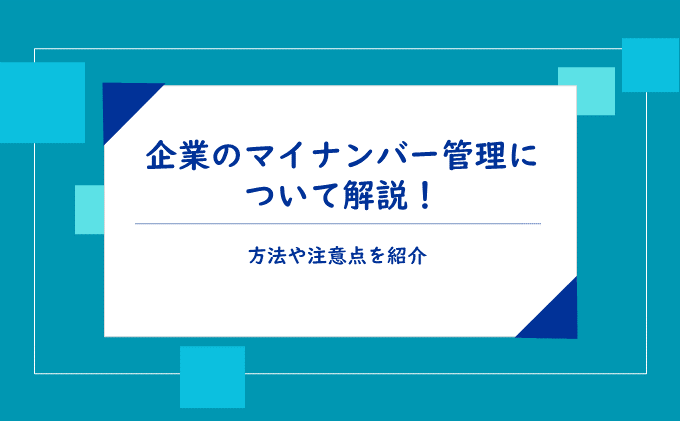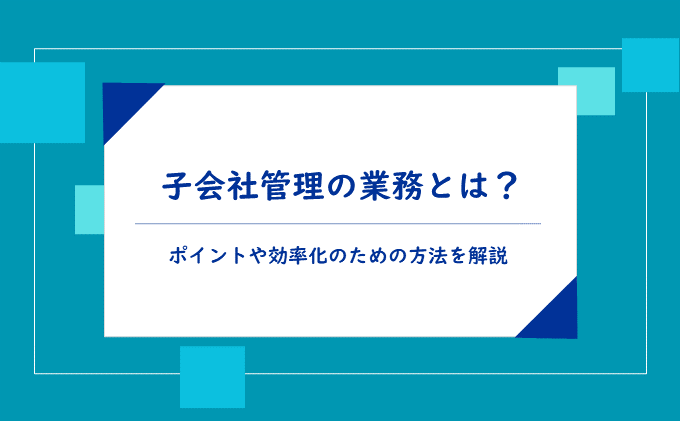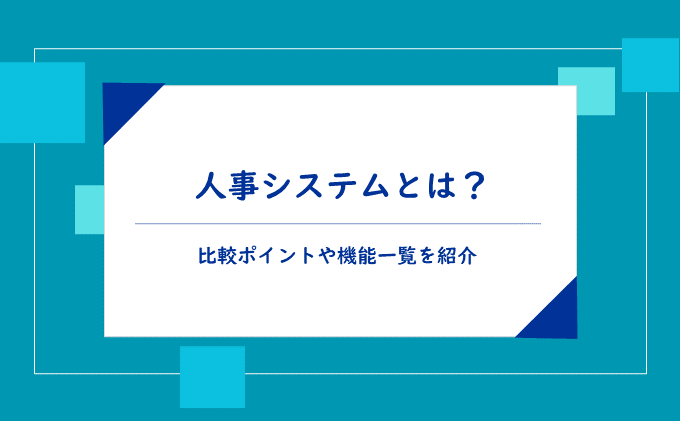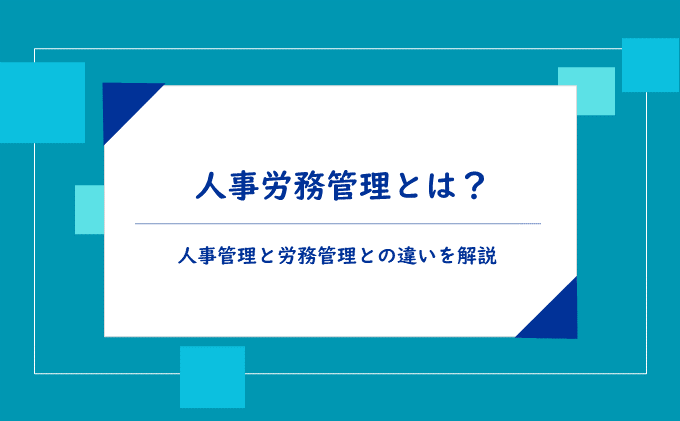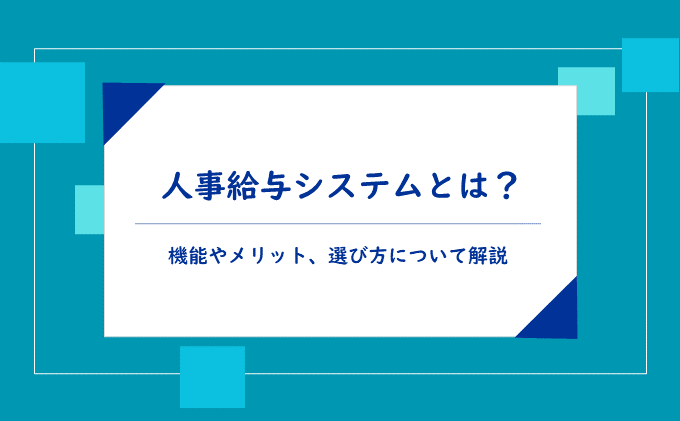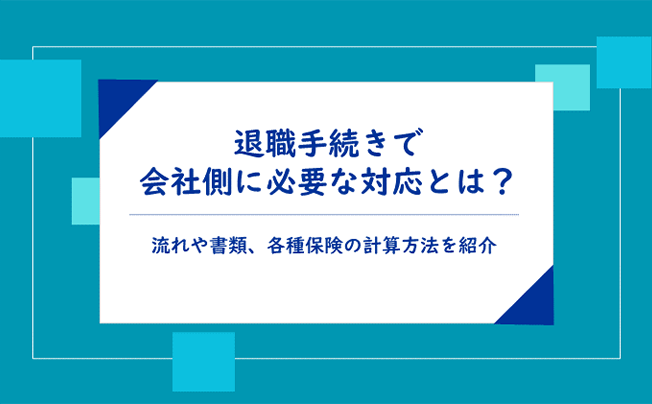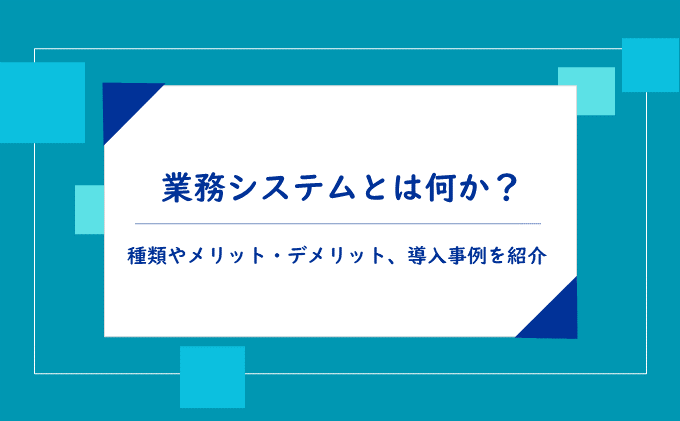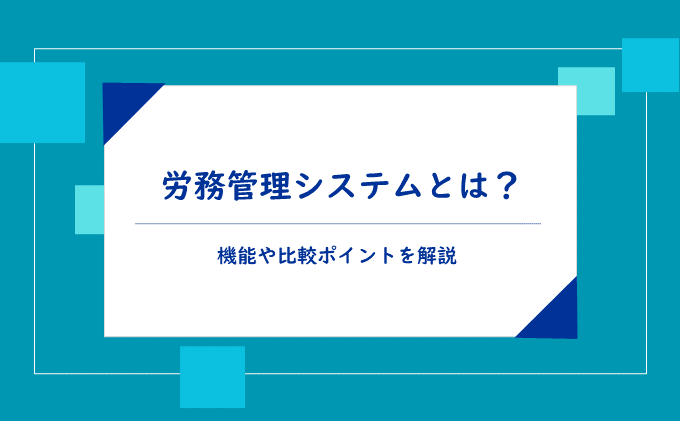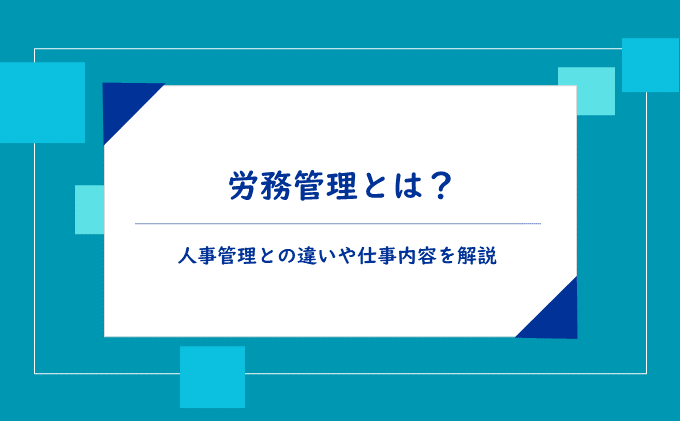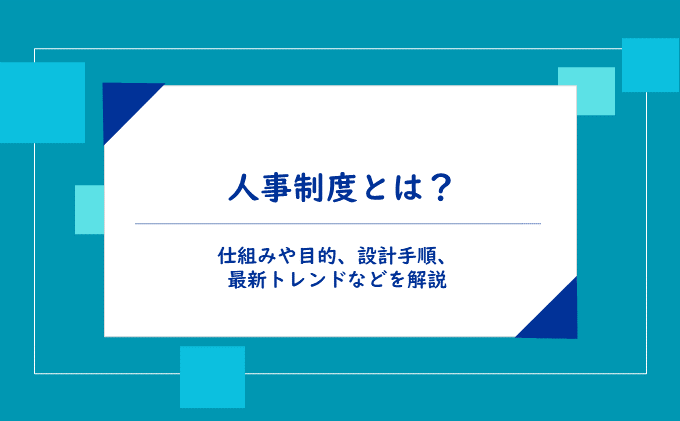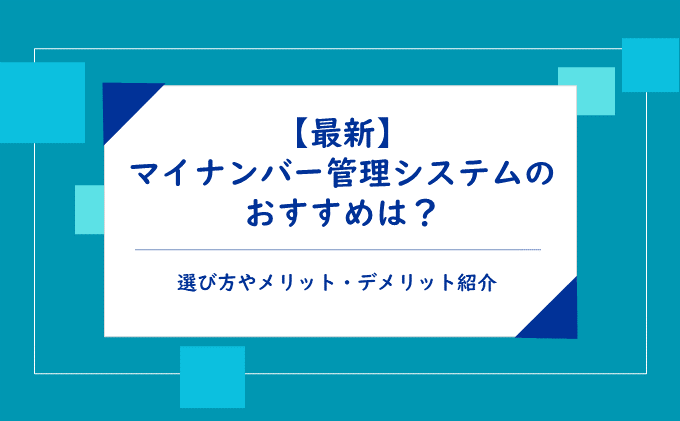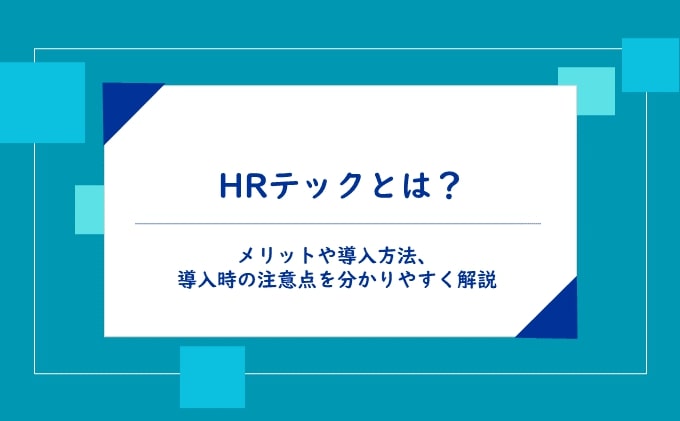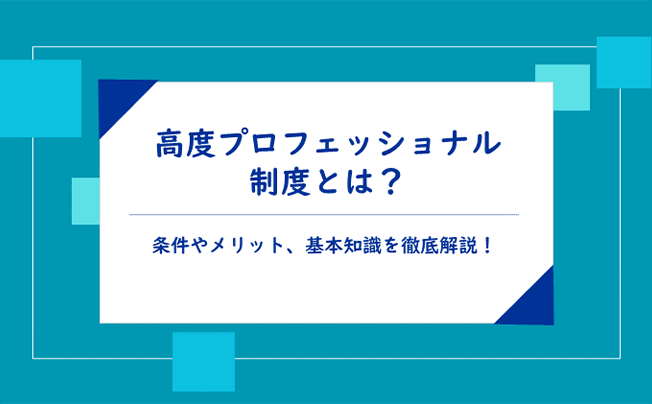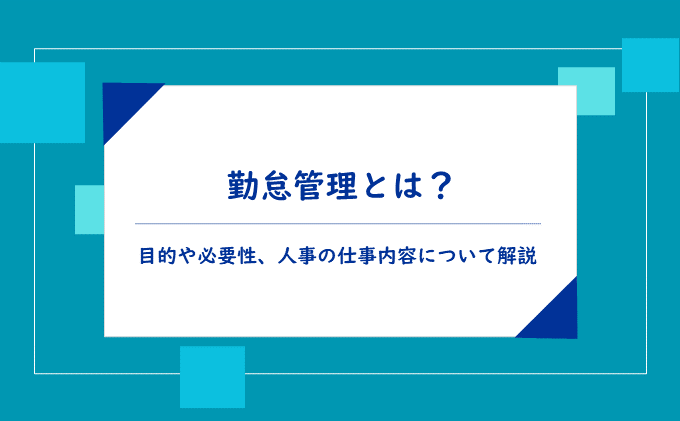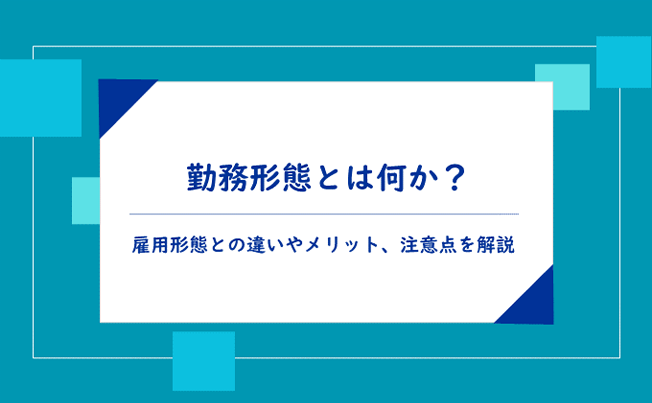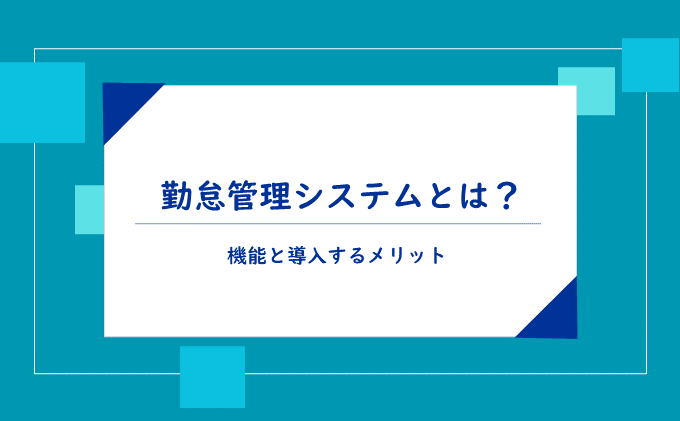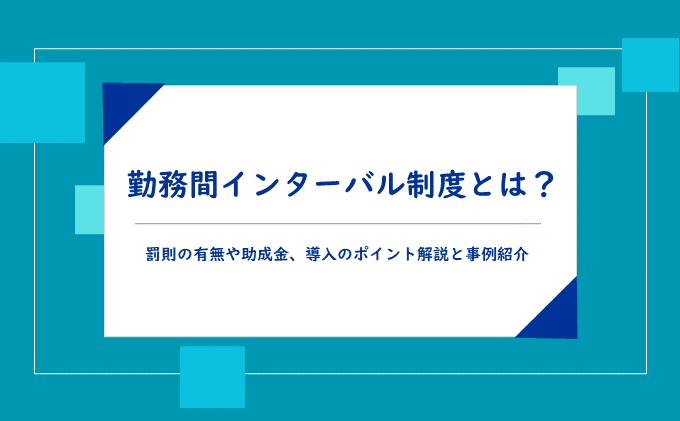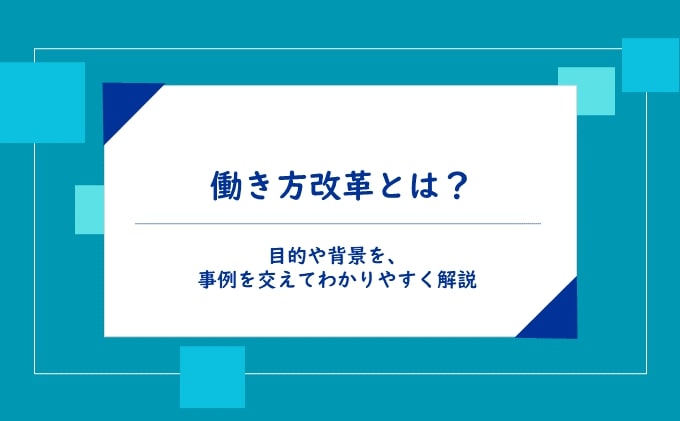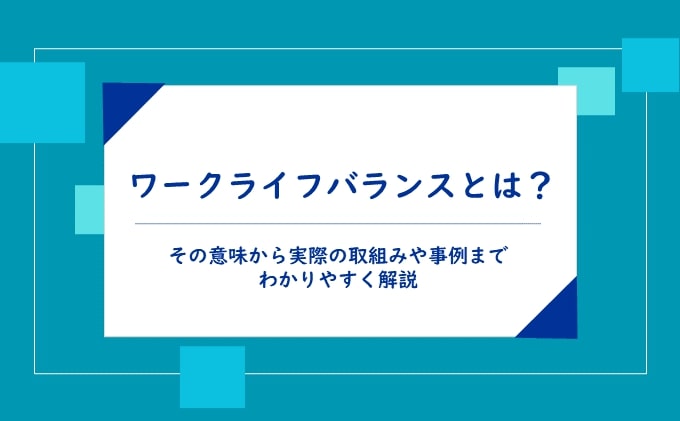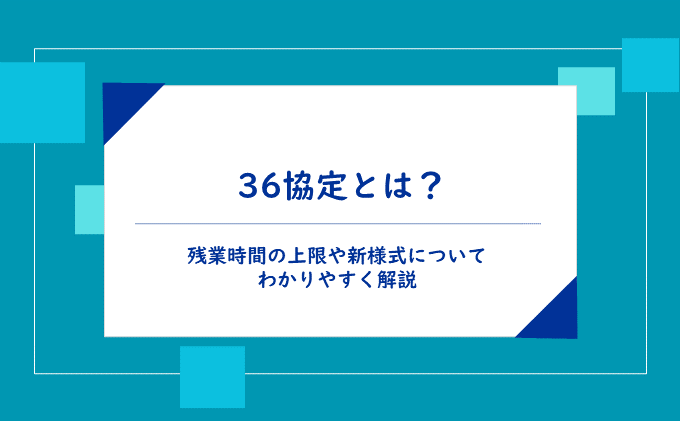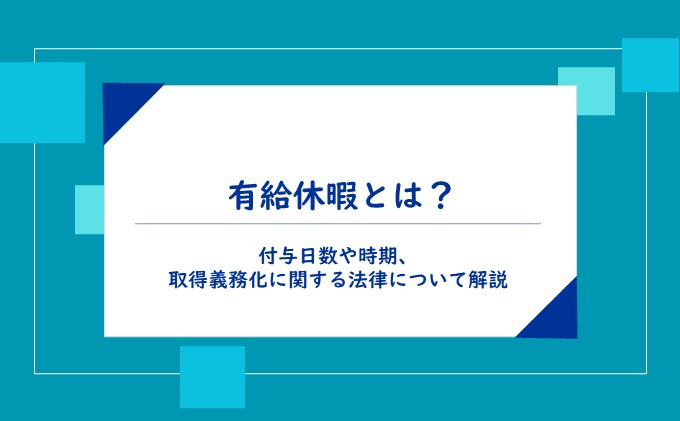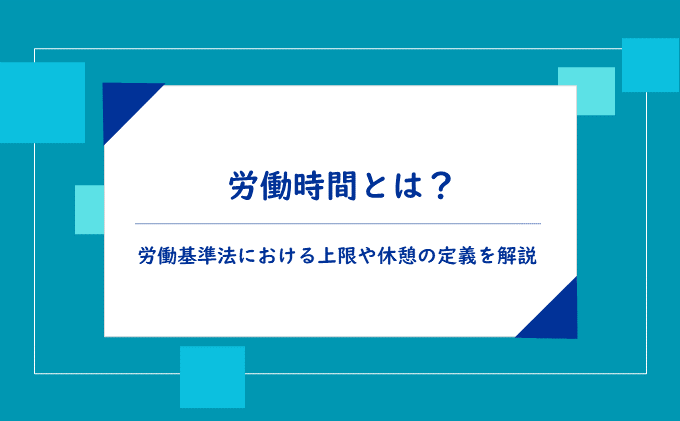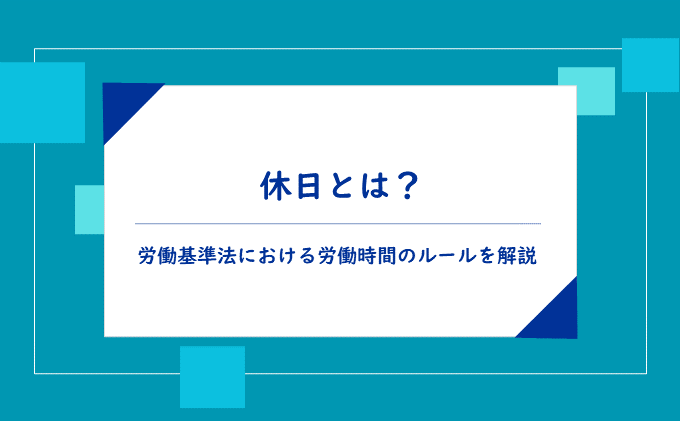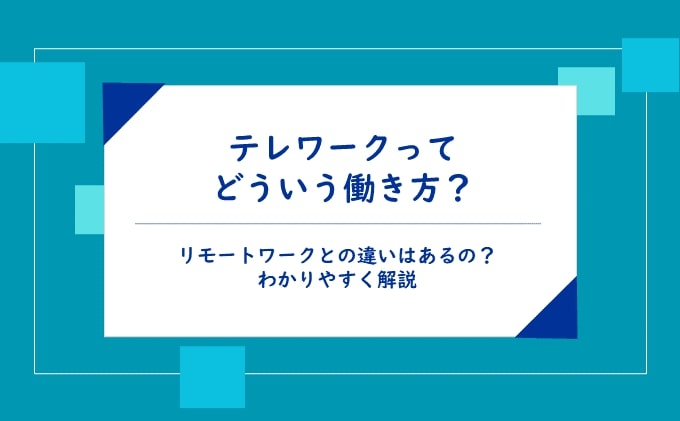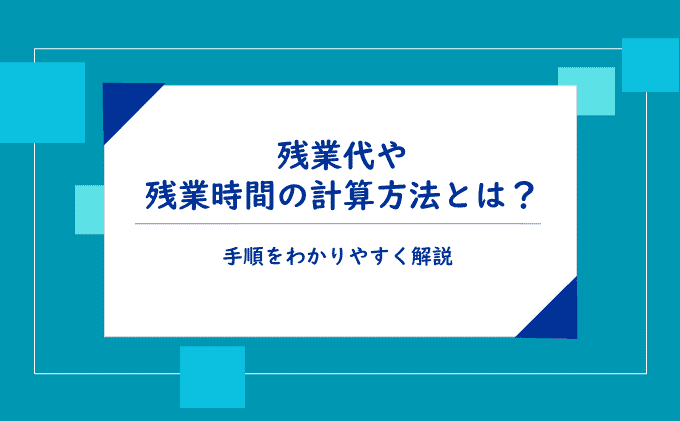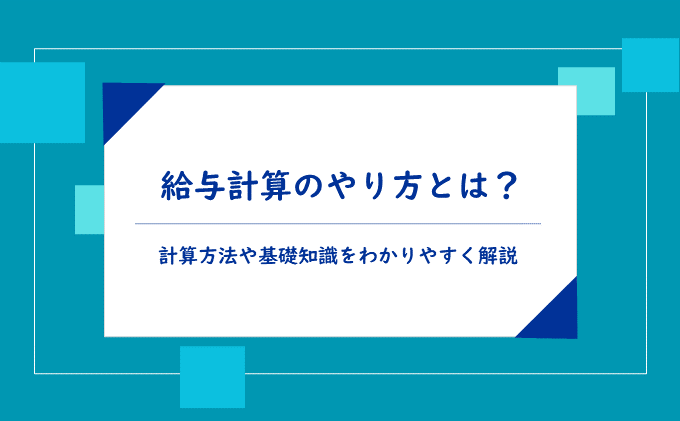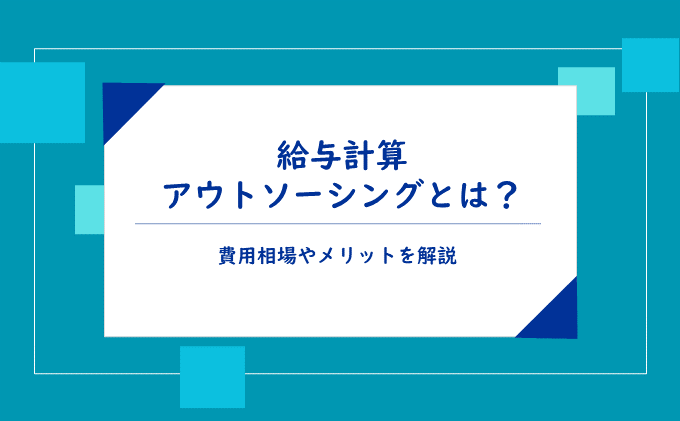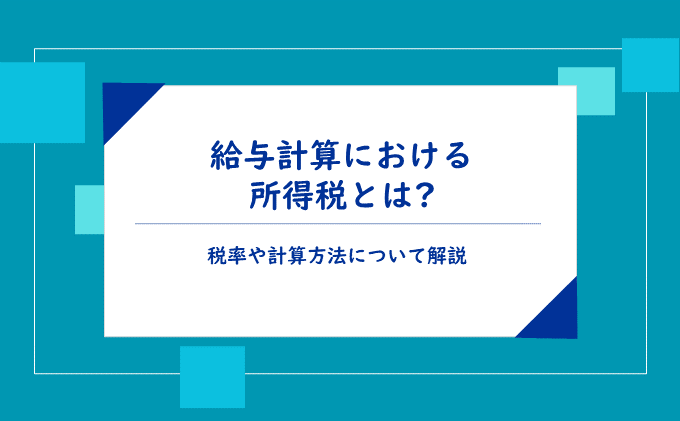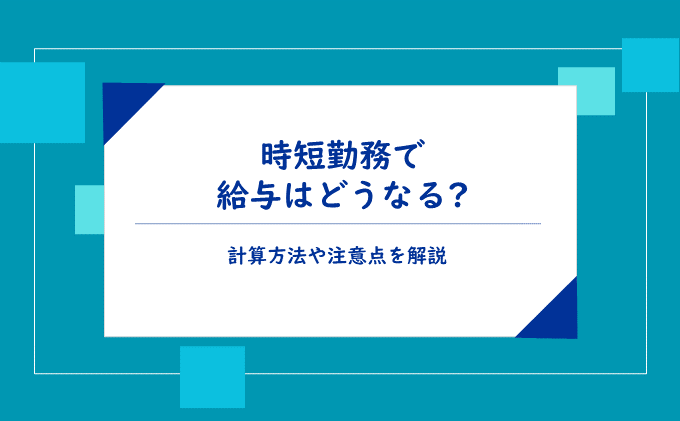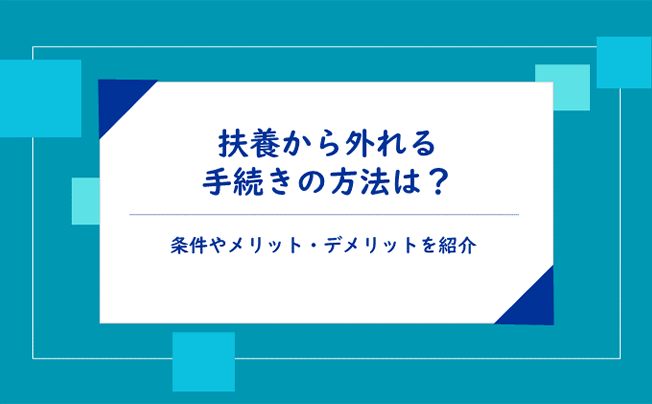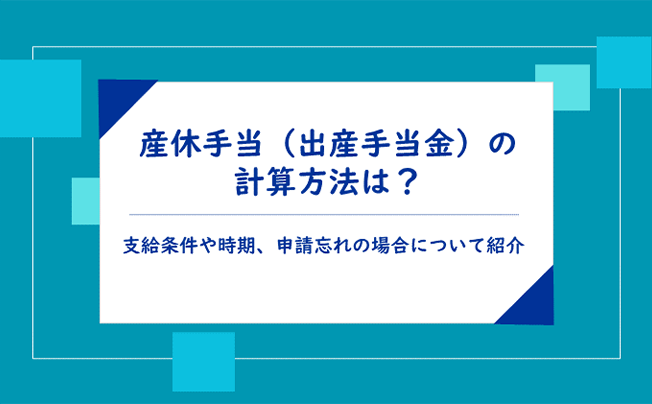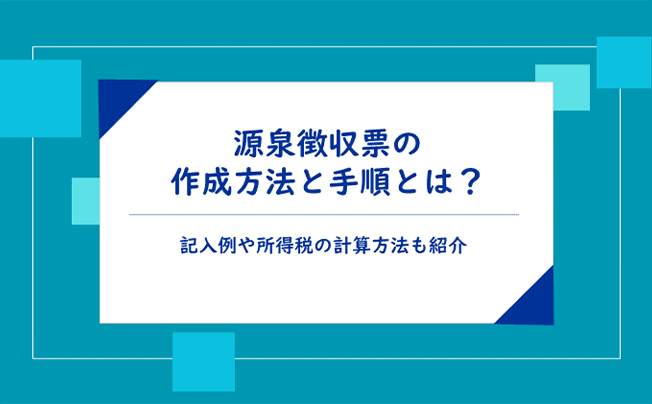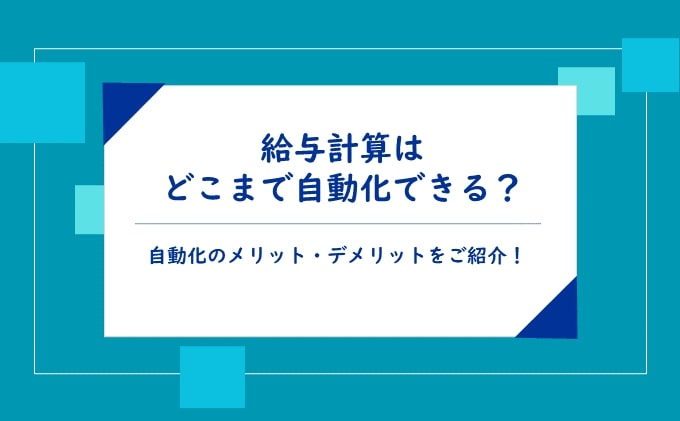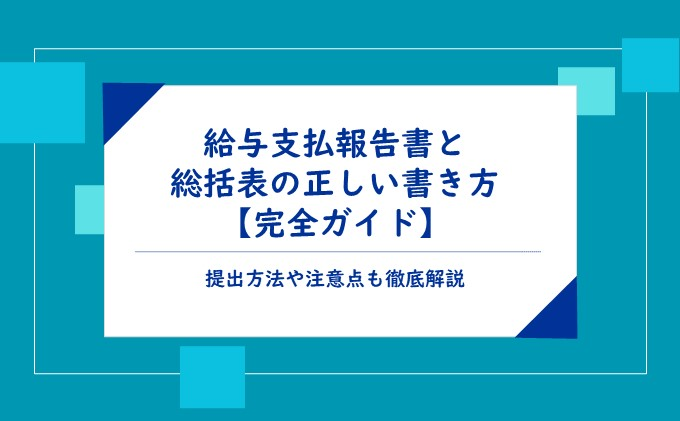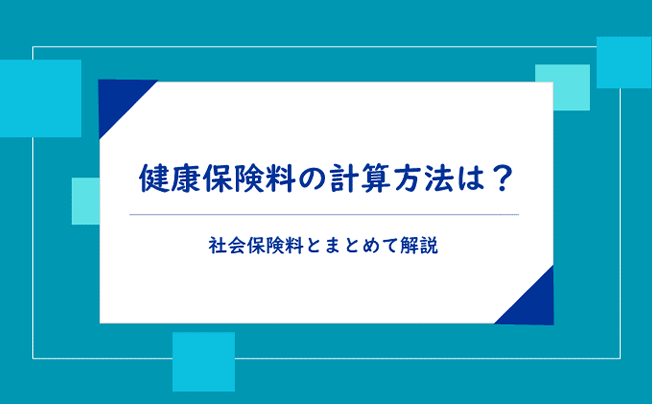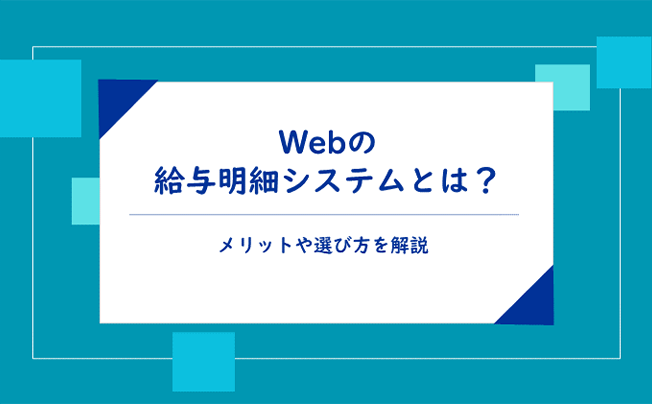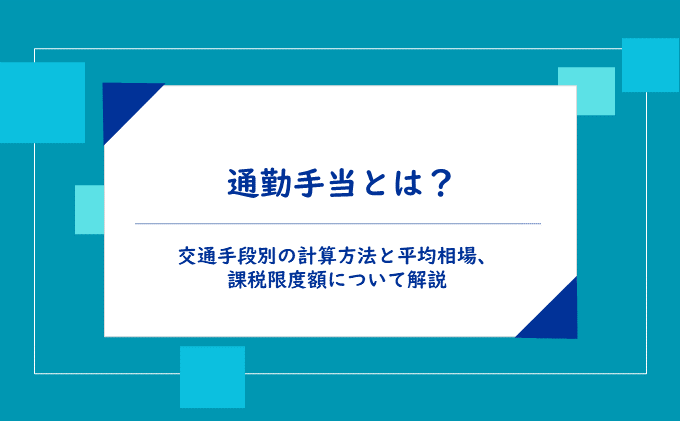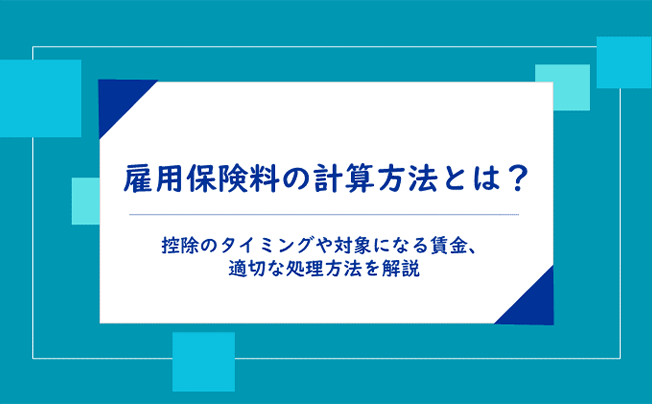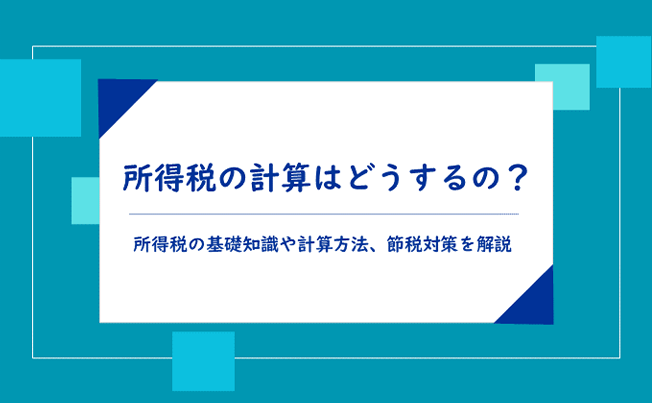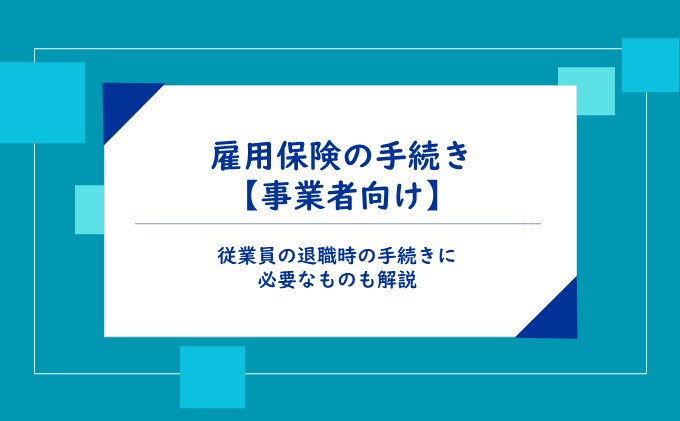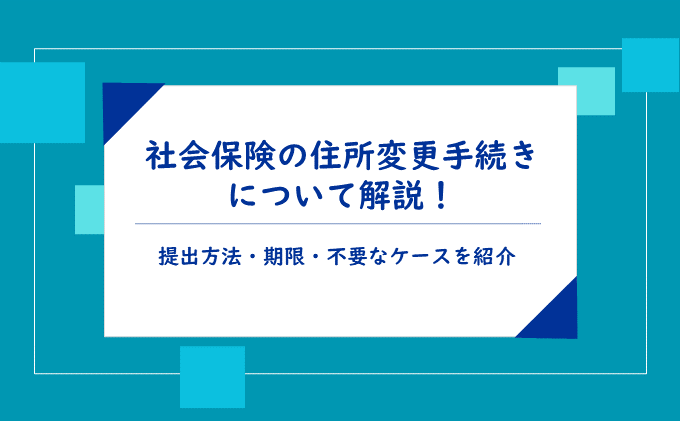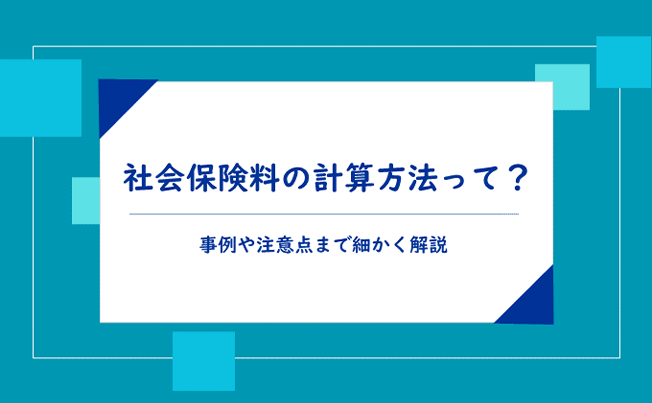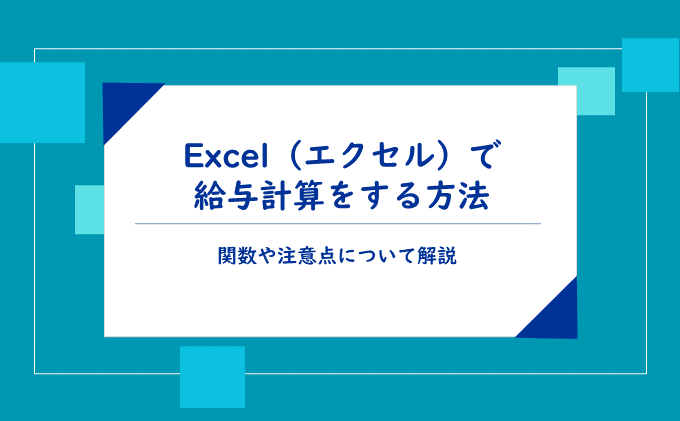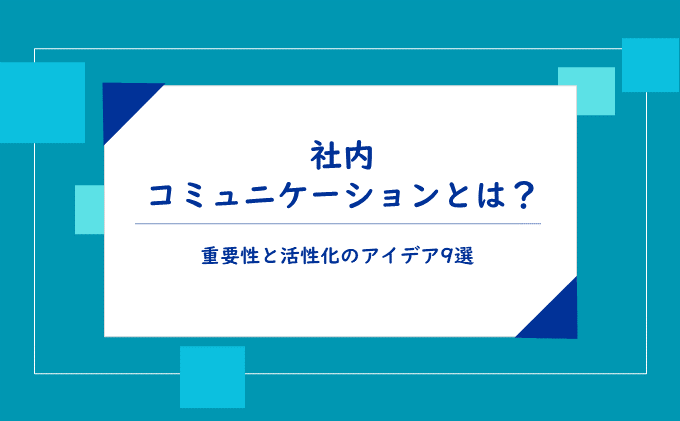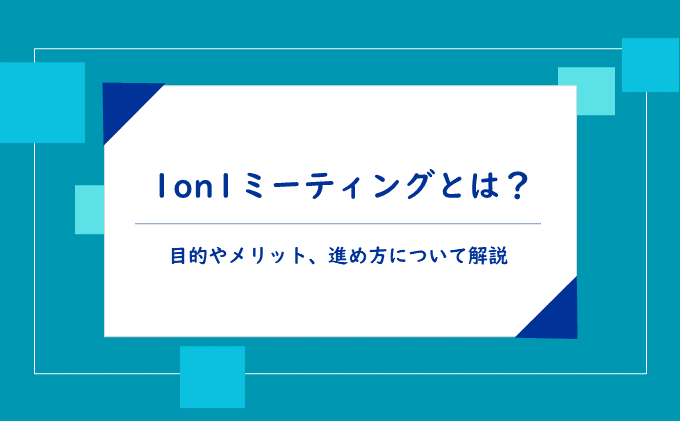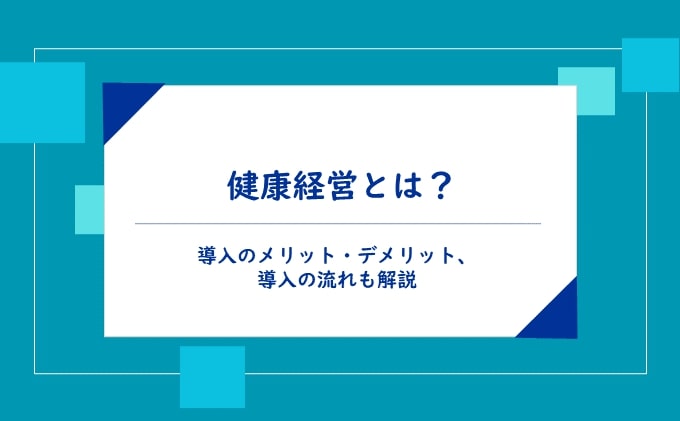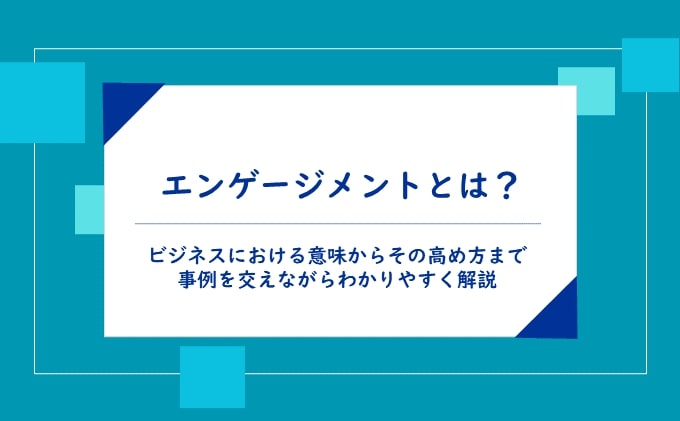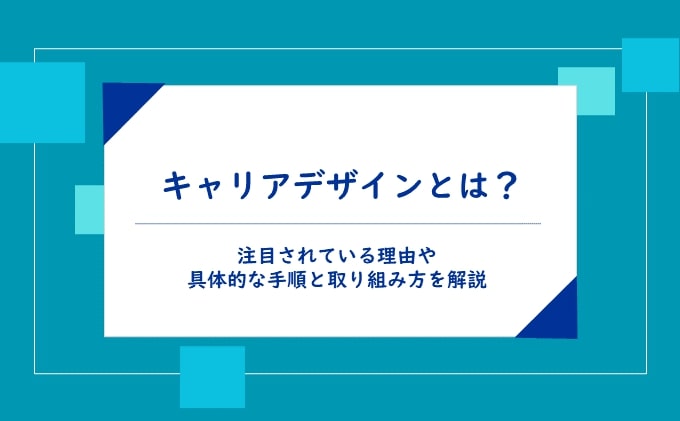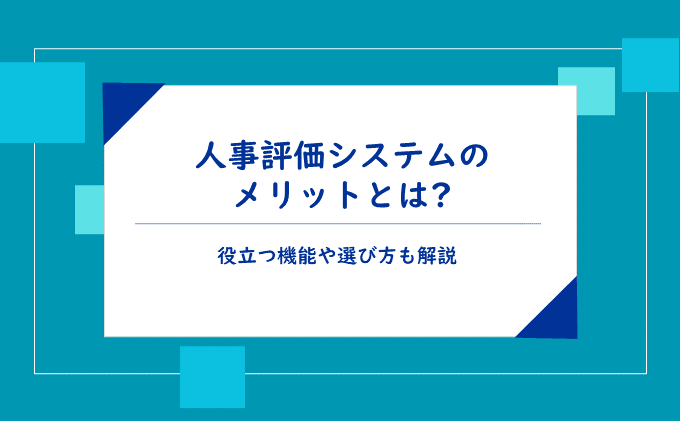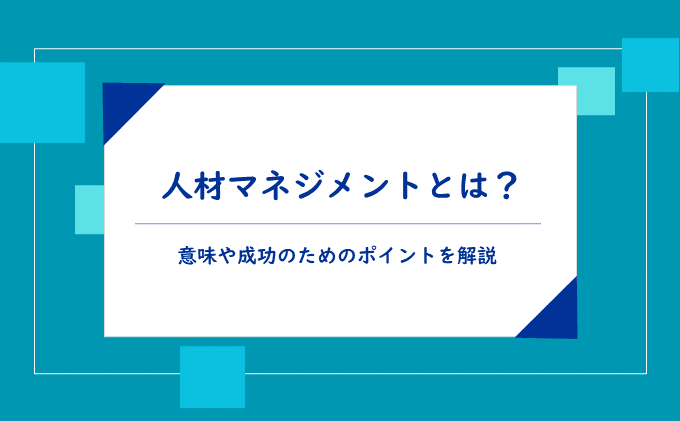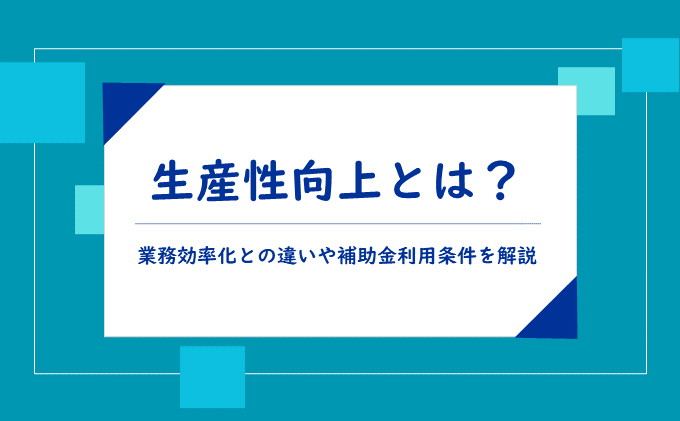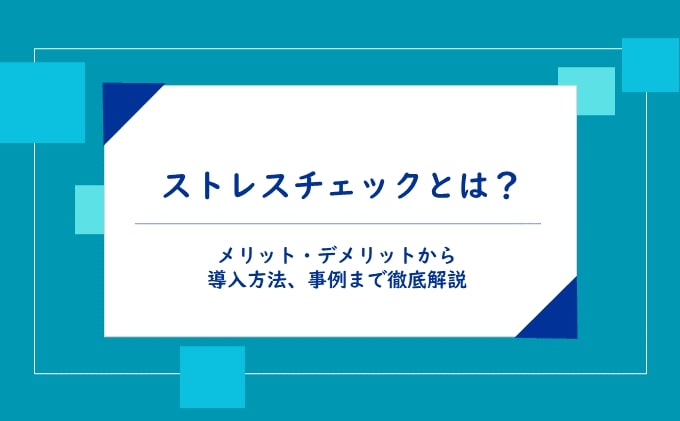賃金台帳とは?作成方法やポイント・給与明細との違いについて解説
2025.01.09
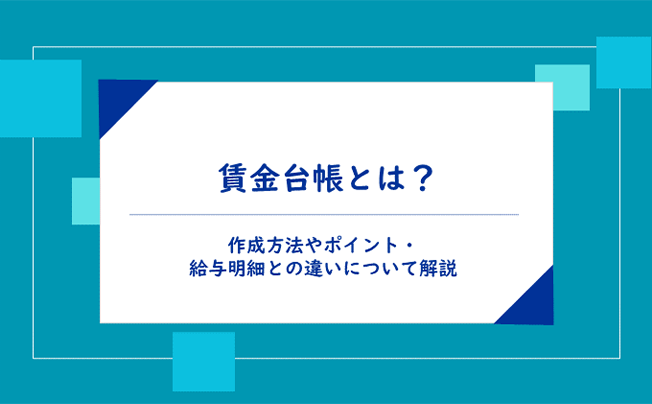
賃金台帳とは、従業員への給与の支払い状況について記載する帳簿のことで、法律で作成と保存が義務付けられています。正しい作成方法や記載項目を理解し、適切な管理を行いましょう。本記事では、賃金台帳の記入方法やポイント、給与明細との違いなどを解説します。
目次
製品の詳細を知りたい方はこちら
賃金台帳とは
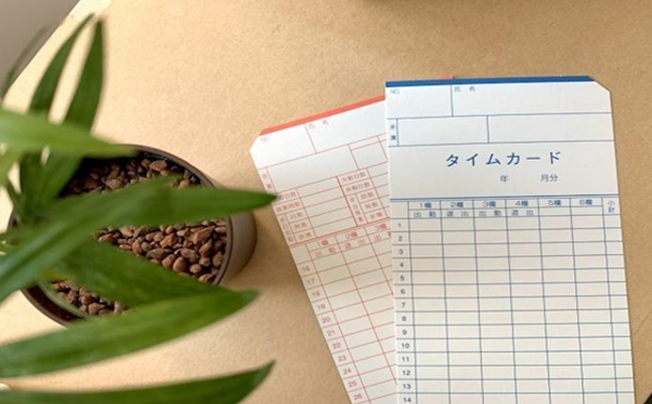
賃金台帳とは、従業員への給与の支払い状況に関する情報を記載する帳簿のことです。労働基準法の第108条で、従業員を雇用するすべての企業について、賃金台帳の作成と保存が義務づけられています。
従業員をひとりでも雇用している企業は、従業員の雇用形態にかかわらず、すべての従業員について賃金台帳を作成・保存しなければなりません。
参考:e-Gov法令検索「昭和二十二年法律第四十九号 労働基準法」
法定4帳簿とは
賃金台帳は、労働基準法で定められている「法定4帳簿」のひとつです。
法定4帳簿とは、以下の4つの帳簿のことを指します。
- 労働者名簿:従業員の氏名や生年月日、住所などの情報を記した名簿のこと。
- 賃金台帳:従業員の労働日数や労働時間、基本給や手当の種類・金額、控除項目・金額などを記した帳簿のこと。
- 出勤簿:従業員の出勤簿やタイムレコーダーの記録、残業命令書や労働時間報告書など、勤怠に関する情報を記した帳簿のこと。
- 年次有給休暇管理簿:従業員の年次有給休暇取得状況を把握するために作成・保管が必要な帳簿
賃金台帳と給与明細の違いは?
賃金台帳と混同しやすいのが給与明細です。
給与明細は、企業から従業員に対して交付するもので、所得税法第231条では支払明細書の交付が義務付けられています。賃金台帳は企業が作成して保存するものである一方、給与明細は従業員に交付するものである、というのが大きな違いです。
記載内容に大差はありませんが、賃金台帳では記載内容が定められている一方、給与明細については特別な定めがない点も異なります。
しかし、健康保険法や厚生年金保険法、労働保険料徴収法などで、控除した税額や保険料について記載した書類を交付することが義務付けられているため、給与明細にこれらの事項を記載するのが一般的です。
参考:e-Gov法令検索「昭和四十年法律第三十三号 所得税法」
関連記事:所得税の計算はどうするの?所得税の基礎知識や計算方法、節税対策を解説
賃金台帳の保存期間・保存方法
労働基準法第109条では、賃金台帳は5年間の保存が定められています。
これまで保存期間は3年間でしたが、2020年4月1日に施行された民法改正により、5年間に延長されました。ただし、経過措置として、「当分の間は3年間」と定められています。
起算日は、従業員の最後の賃金について記入した日です。しかし、最後に記入した日よりも賃金の支払期日のほうが遅い場合は、支払期日が起算日になる点に注意しましょう。
参考:e-Gov法令検索「昭和二十二年法律第四十九号 労働基準法」
参考:厚生労働省「未払賃金が請求できる期間などが延長されています」
保存方法は特に規定されておらず、紙媒体でも電子データでも問題ありません。労働基準監督署から提出を求められた際にすぐに見せられるようにしておきましょう。電子データの場合は、すぐに印刷できる形式で保存することが大切です。
関連記事:賃金台帳とは?保存期間と適切な保存方法について解説
賃金台帳の対象者

賃金台帳の対象となるのは、その企業で雇用されているすべての従業員です。役員、正社員、契約社員、アルバイト、短期就労者など、雇用形態は問いません。
ただし、派遣社員については対象外です。派遣社員についての賃金台帳は、派遣元の企業が作成します。
また、日雇労働者と労働基準法第41条に該当する管理監督者については、賃金台帳の作成は義務であるものの、一部記載が必要ない項目が存在します。
- 日雇労働者:継続勤務が1か月を超えない場合は、賃金計算期間の記載が不要。
- 管理監督者:労働時間・休憩・休日についての規定が適用されないため、労働時間や時間外労働、休日労働に関する時間数の記載が不要。(深夜手当に関する規定は対象であるため、深夜労働時間数の記載は必要。)
管理監督者については、賃金台帳について労働時間に関する記載をする必要はありませんが、企業が労働時間を把握することは必要です。2019年より、労働安全衛生法で使用者が労働時間の状況を把握することが義務付けられました。そのため、管理監督者についても、労働時間は必ず把握しなければなりません。タイムカードや勤怠管理システムなどの記録と併せて、賃金台帳に記載して把握するのもよいでしょう。
参考:e-Gov法令検索「昭和四十七年法律第五十七号 労働安全衛生法」
賃金台帳の作成方法

賃金台帳は、表計算ソフトやワードなどを使って、パソコンで作成・管理する方法が一般的です。しかし、賃金台帳の作成方法に決まりはありません。必須の記載事項を網羅していれば、どのような書式やフォーマットでも問題ないとされています。自社に適した方法で作成しましょう。
厚生労働省が様式をダウンロードできるページを公開しているため、必要に応じて利用してみてください。
参考:厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労働基準法等関係主要様式)」
関連記事:エクセルを使った給与計算方法を解説!役立つ関数も紹介
賃金台帳に記載する項目

従業員の氏名・性別
給与を支払った従業員の氏名と性別を記載しましょう。性別も記載することで従業員を特定しやすくなり、それぞれの賃金台帳がどの従業員のものであるかを明確にできます。
社員番号が存在する場合は、氏名と併せて記載しましょう。
賃金の計算期間
賃金の計算期間は、賃金を計算する対象期間のことです。賃金を計算する開始日から締め日を記載しましょう。
記載例は、以下のとおりです。
- 2023年6月分の賃金台帳で月末締めにしている場合:2023年6月1日〜6月30日
- 2023年4月分の賃金台帳で25日締めにしている場合:2023年3月26日〜4月25日
ただし、継続勤務が1か月を超えない日雇労働者については、前述のとおり賃金計算期間の記載は必要ありません。
労働日数と勤務時間数
賃金計算期間内に従業員が働いた日数と時間も記載しましょう。就業規則で定められた所定日数や勤務時間ではなく、実際に勤務した日数と時間を記載します。時間外労働分や、有給休暇を取得した分の日数や時間も含めた、すべての労働日数・勤務時間を記載する点に注意してください。
タイムカードや勤怠管理システムなどの客観的な記録を見ながら、正しい数値を記入しましょう。
関連記事:就業規則とは?記載内容や作成方法をわかりやすく解説
時間外勤務時間数
時間外勤務時間数についても記載が必要です。
時間外勤務時間とは、労働基準法で定められた法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた分のことを指します。時間外勤務時間数の記載は、会社が適切な労務管理を行っているかを判断するうえで非常に重要なポイントです。
時間外勤務の上限は、特別な事情がないかぎり月45時間・年360時間と定められています。月45時間を超えられるのは6か月までです。労働基準法に違反していないかをチェックする際は、企業が定めた所定労働時間ではなく、法定外労働時間の超過時間で判断されるため注意しましょう。
なお、労働時間の規定が適用されない管理監督者については、時間外勤務時間数の記載は不要です。
深夜・休日勤務時間数
深夜勤務時間数や休日勤務時間数についても記載しましょう。
深夜勤務に該当するのは、深夜手当が発生する夜22時から翌5時の時間帯での労働です。
また、休日勤務は、休日手当が発生する法定休日および法定外休日(雇用契約上の休日)での勤務を指します。
夜勤務時間数や休日勤務時間数も、正しく賃金が支払われているかをチェックするうえで重要な項目です。
なお、時間外勤務時間数と同様、管理監督者については休日勤務時間数を記載する必要がありません。深夜手当の支払いは必要であるため、深夜勤務時間数は忘れずに記載しましょう。
基本給や手当などの種類とその額
基本給のほか、各種手当の種類とその額についても記載しましょう。
基本給は、毎月一定額支払われる給与のことです。毎月支給される手当も含めて計算します。時給や日給で雇用している従業員については、時給(日給)×勤務時間数(労働日数)が基本給です。
そのほか、残業手当(所定時間外割増手当)や役職手当、通勤手当、扶養手当など、従業員に支払っている手当の種類とそれぞれの金額についても、正しく記載してください。
控除金
控除金は、毎月の給与から控除する分です。控除金には、以下のような項目が該当します。
- 所得税
- 住民税
- 健康保険料・介護保険料
- 雇用保険料
- 厚生年金保険料
- 減給処理時に控除した賃金
- 企業年金や社宅費のように、会社が独自に控除しているもの
賃金台帳に関する罰則

賃金台帳の作成・保存義務を果たさなかったり、必須項目を記載していなかったりする場合は、労働基準法違反に該当します。
違反すると、労働基準監督署による是正勧告のほか、30万円以下の罰金が科される可能性もあるため、注意してください。
賃金台帳のほか、法定4帳簿である労働者名簿や出勤簿についても、必ず作成・保存しましょう。
勤怠管理をするならカシオヒューマンシステムズがおすすめ

適切な勤怠管理を効率よく実現するためには、カシオヒューマンシステムズ株式会社が提供する人事統合システム「ADPS」の活用がおすすめです。
「ADPS」は、累計5,000社を超える導入実績を誇り、シンプルで使いやすいインターフェースが魅力のシステムです。給与計算や人事情報管理、採用管理など、煩雑な人事業務を流れに沿ってナビゲートします。業務負荷を軽減し、生産性向上を実現できます。
詳しくは、以下のページや導入事例をご覧ください。
人事統合システム ADPS
CASE STUDIES ADPS 導入事例
関連記事:給与計算はどこまで自動化できる?|自動化のメリット・デメリットをご紹介
まとめ

賃金台帳は、従業員を雇用する企業が必ず作成し、保存しなければならない重要な帳簿です。フォーマットは自由ですが、記載内容については定められています。賃金台帳を正しく作成・保存しなかった場合は、労働基準法違反に該当し、罰則を課せられる可能性もあるため、注意が必要です。見本も参考にしながら、正しい書き方や記載事項を理解して、賃金台帳を適切に作成しましょう。
勤怠管理の際は、煩雑な人事業務を効率化してくれるシステムの活用も検討してみましょう。
製品の詳細を知りたい方はこちら
カシオヒューマンシステムズコラム編集チームです。
人事業務に関するソリューションを長年ご提供してきた知見を踏まえ、
定期的に「人事部の皆様に必ず今後の業務に役立つ情報」を紹介しています。