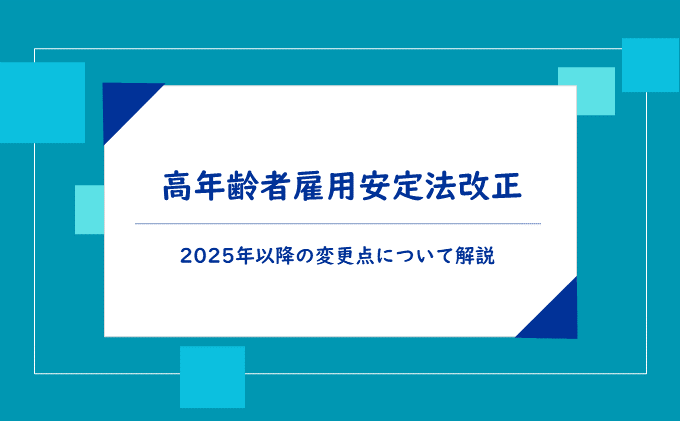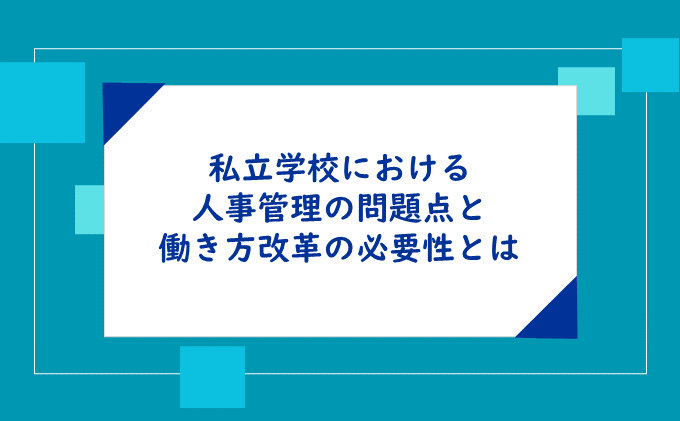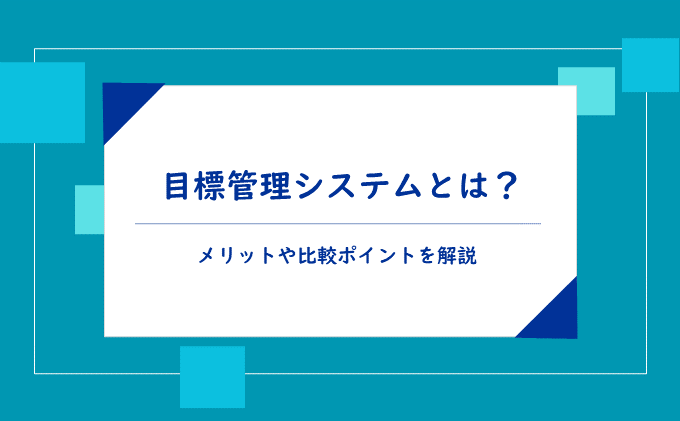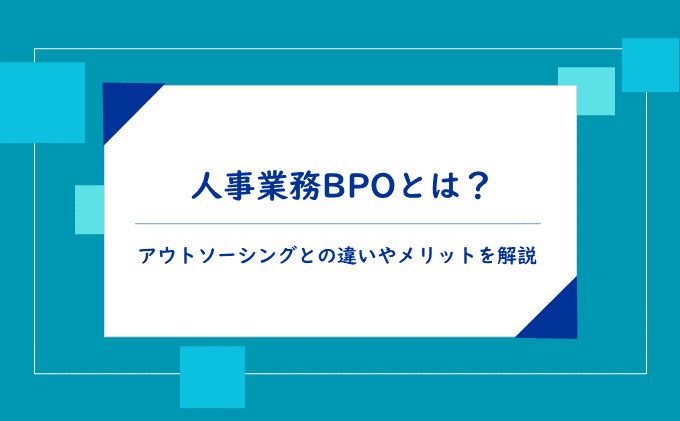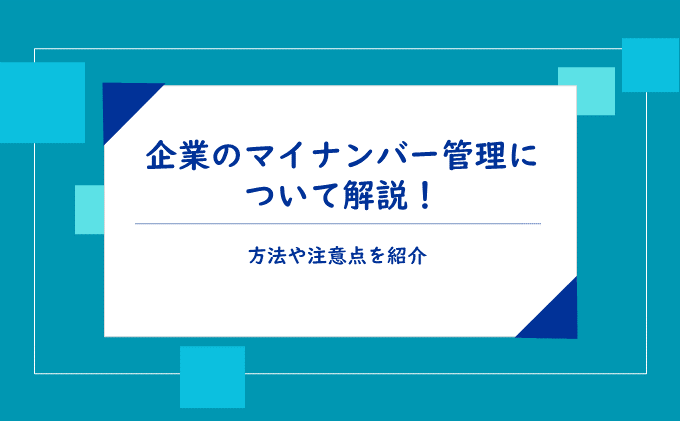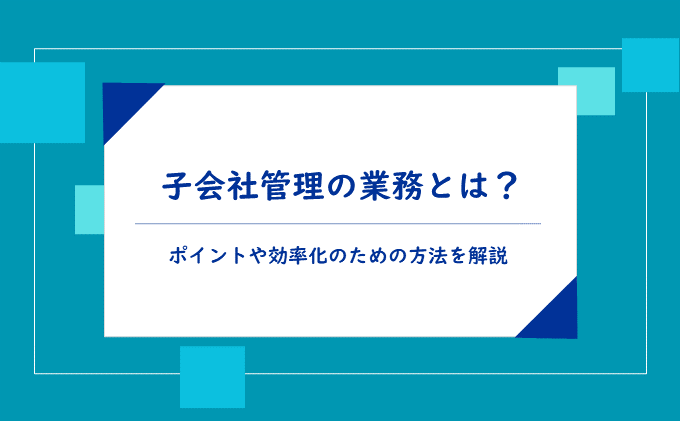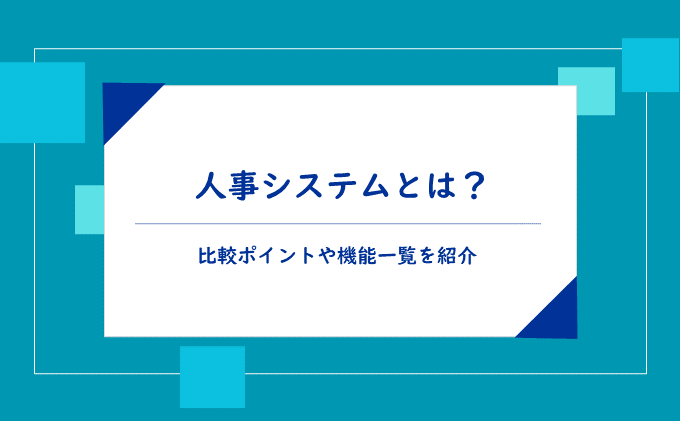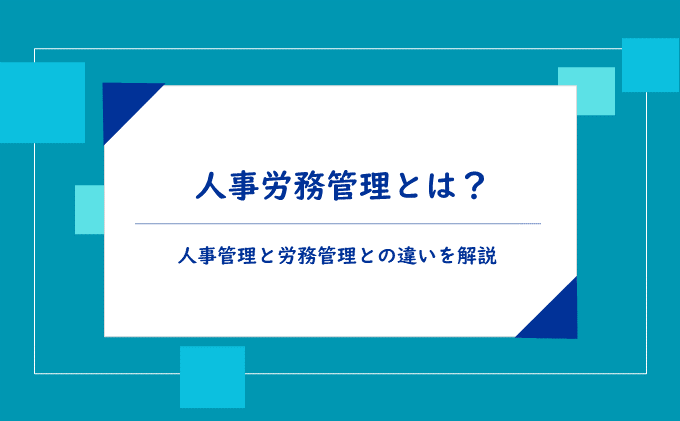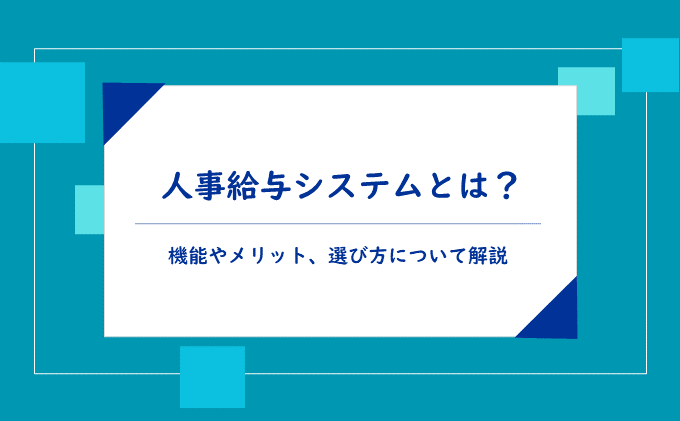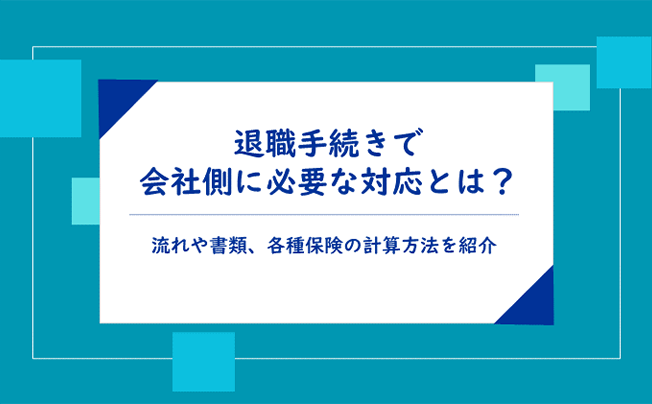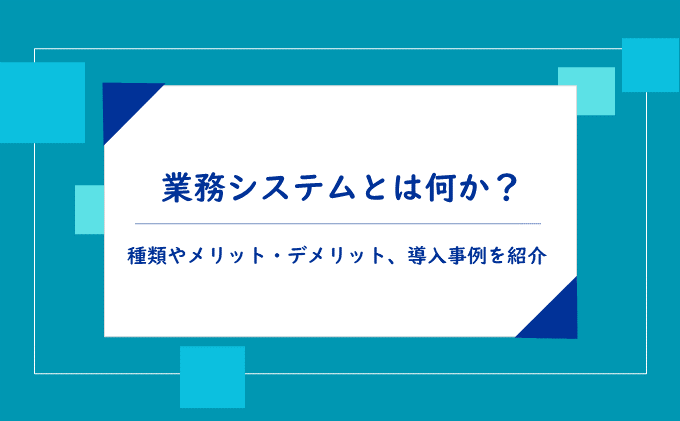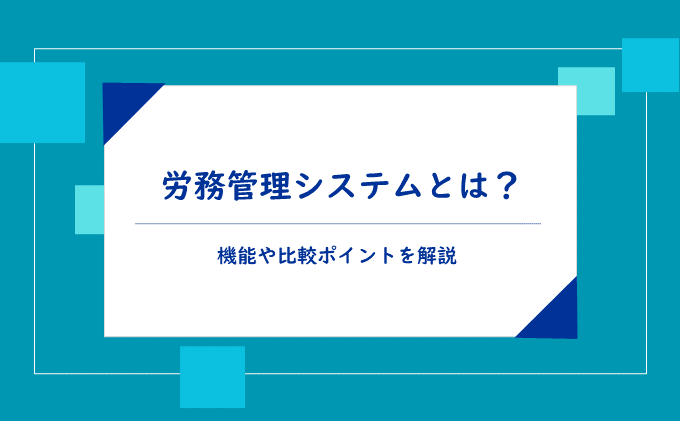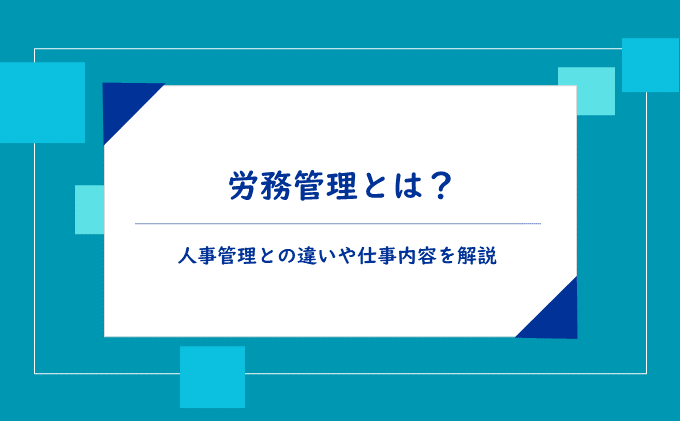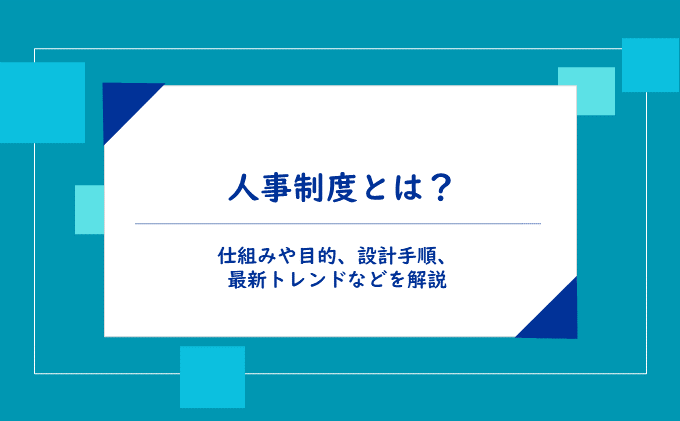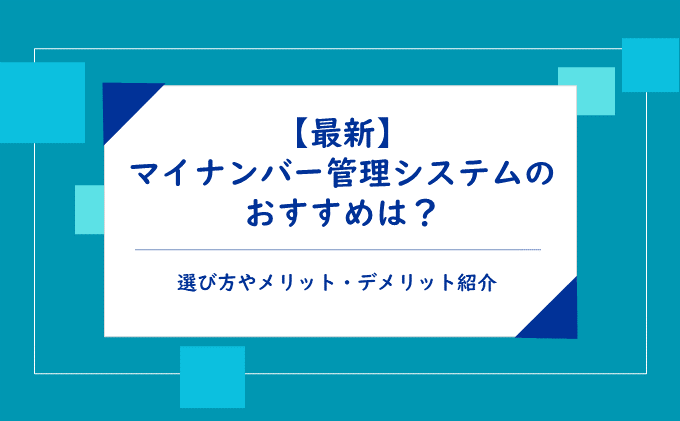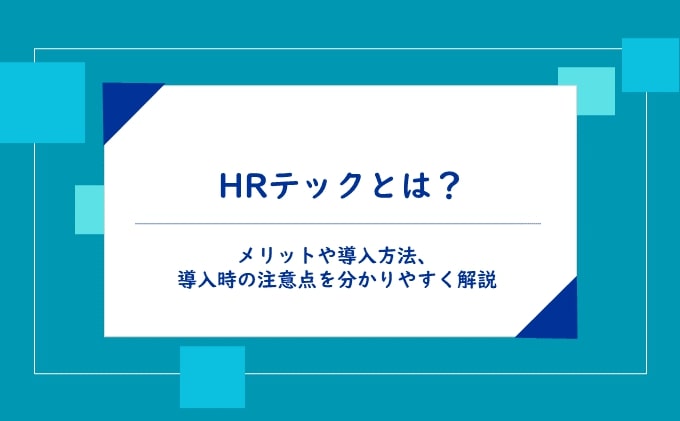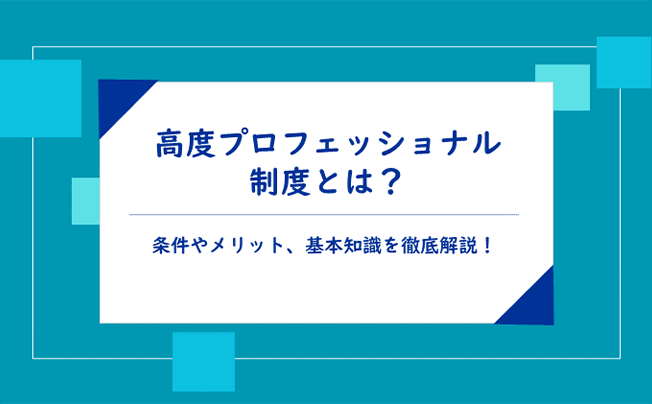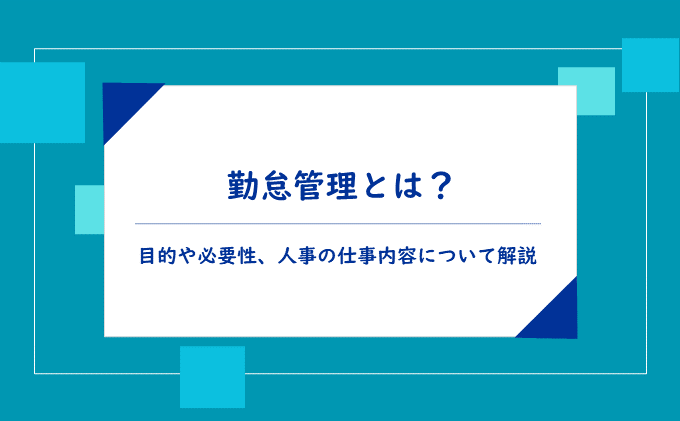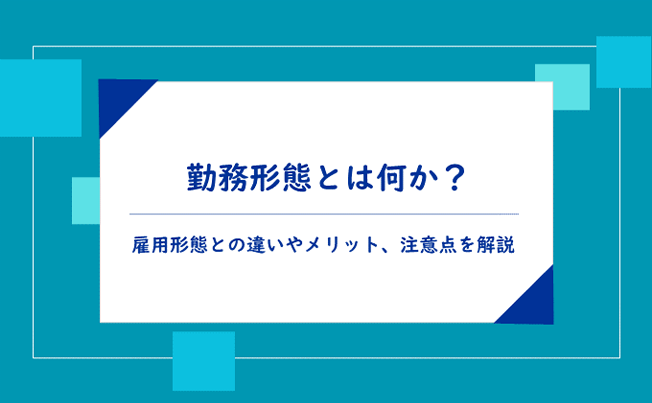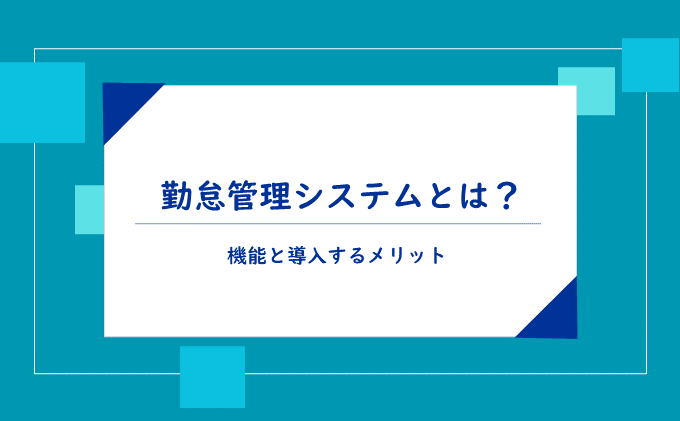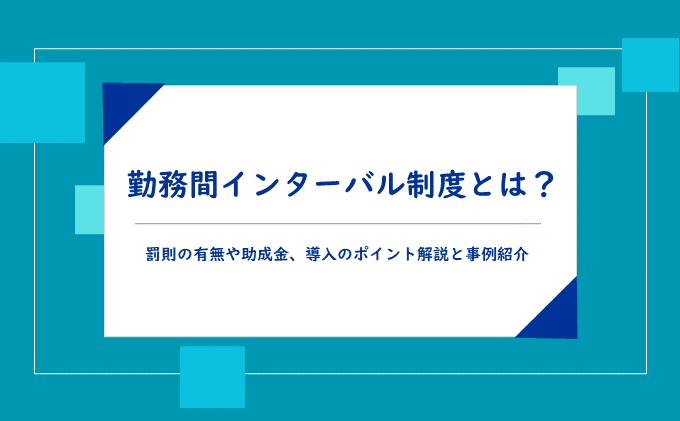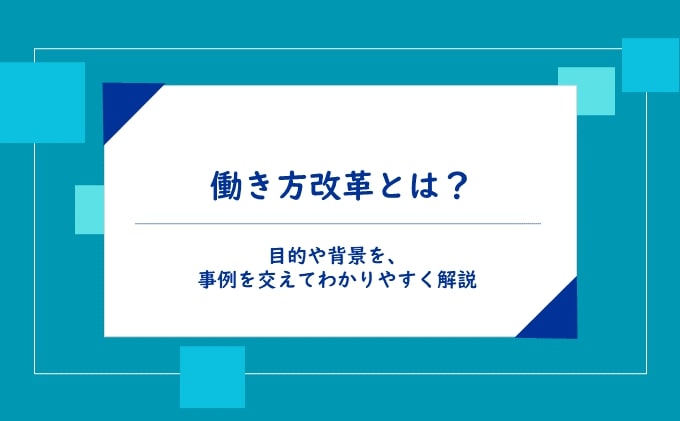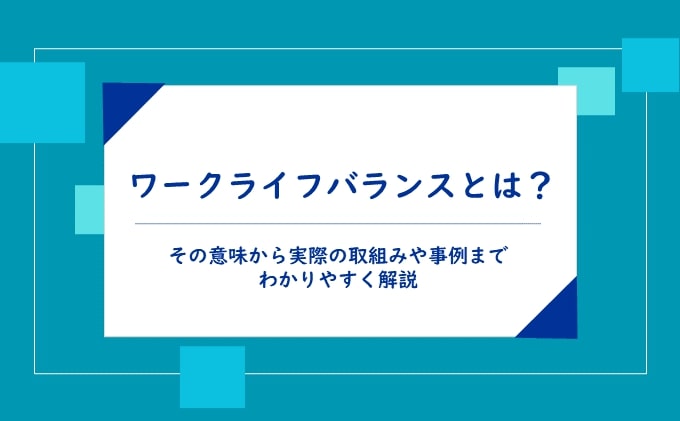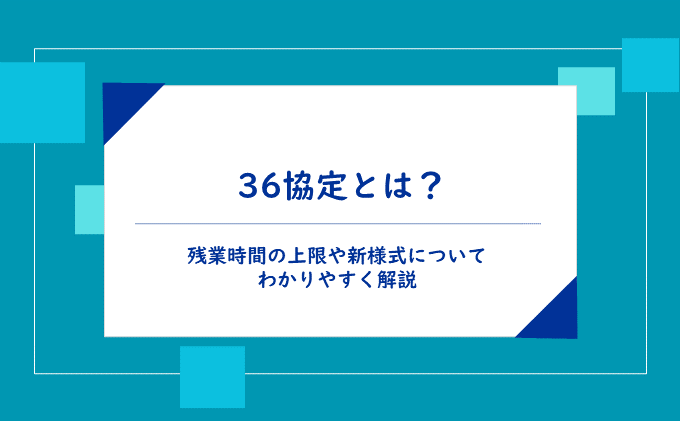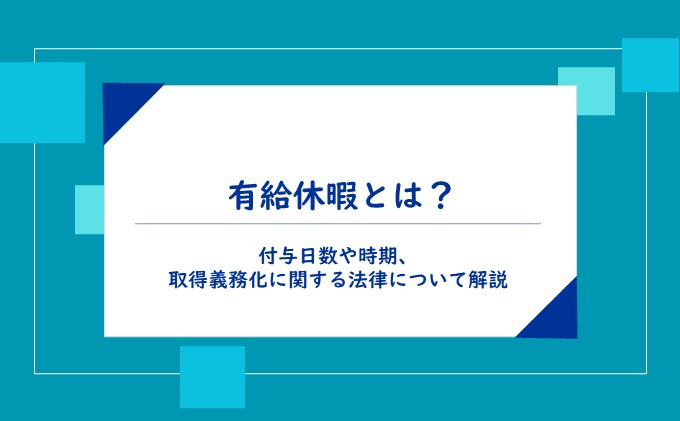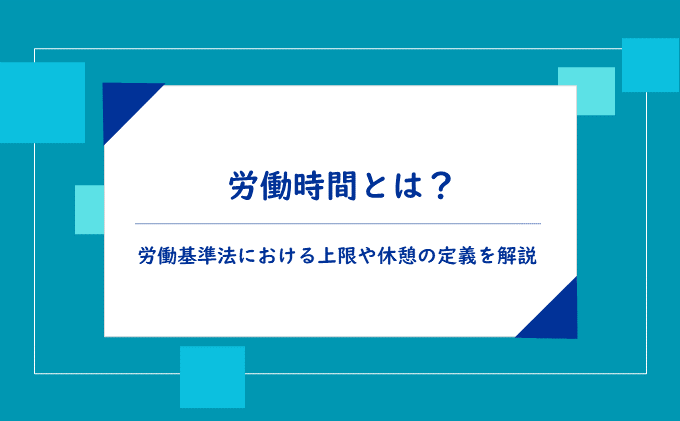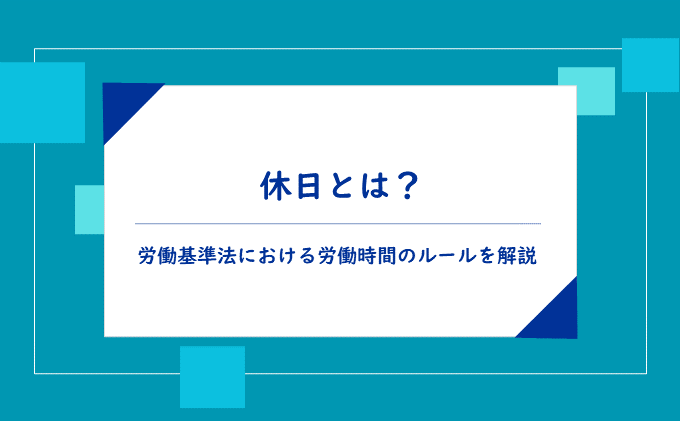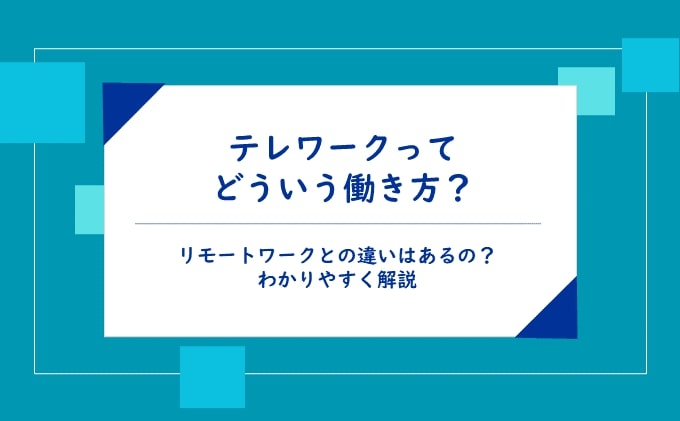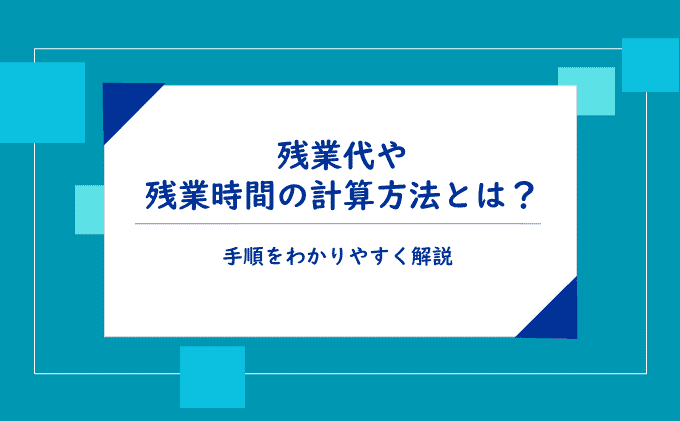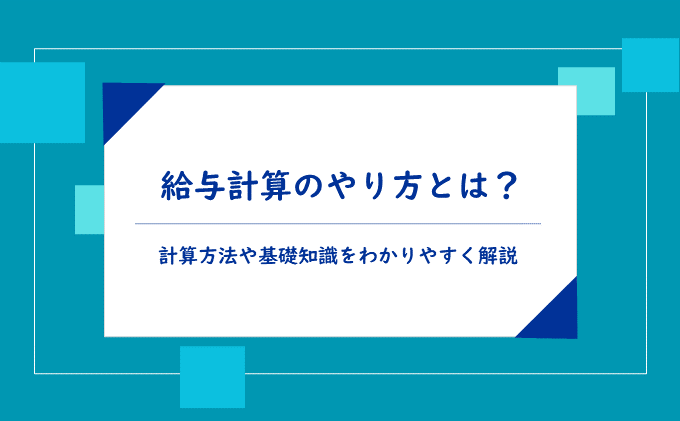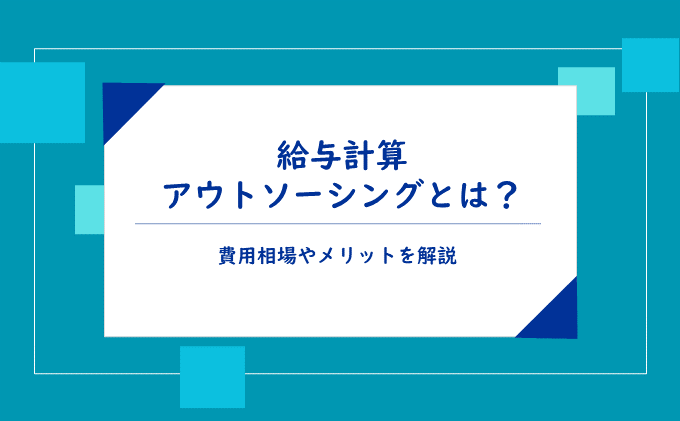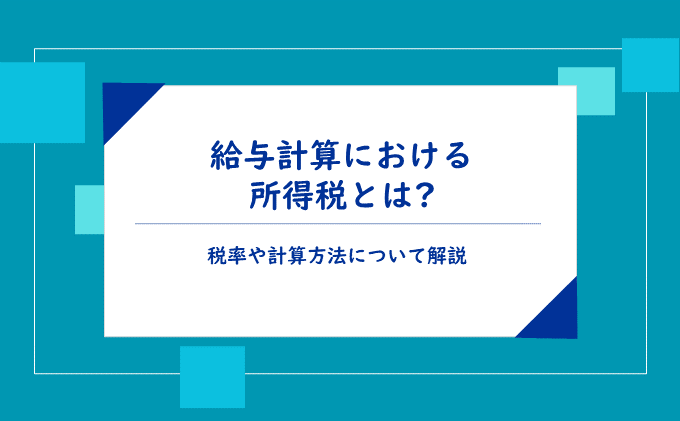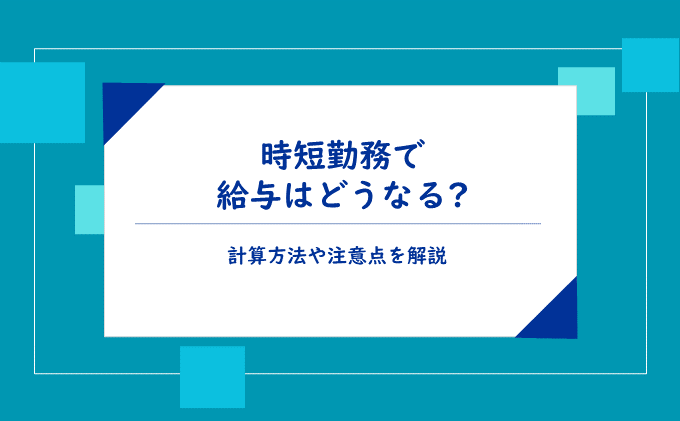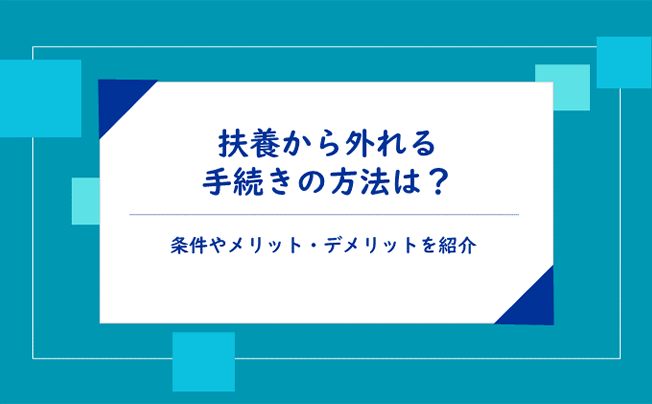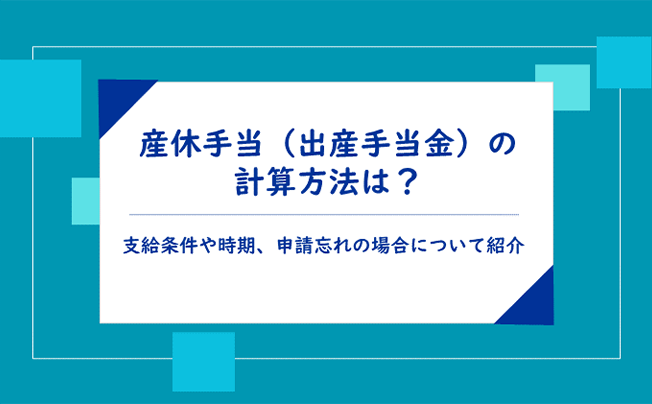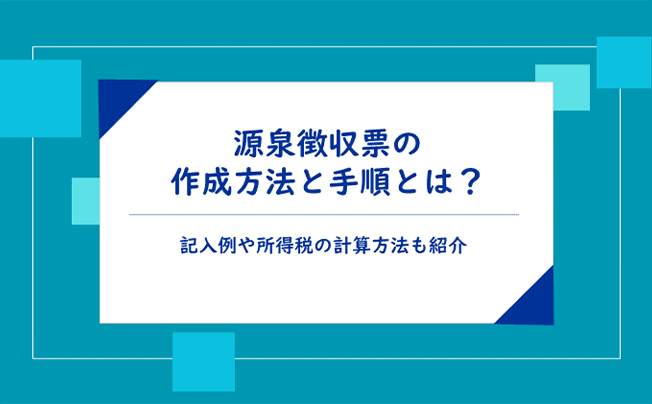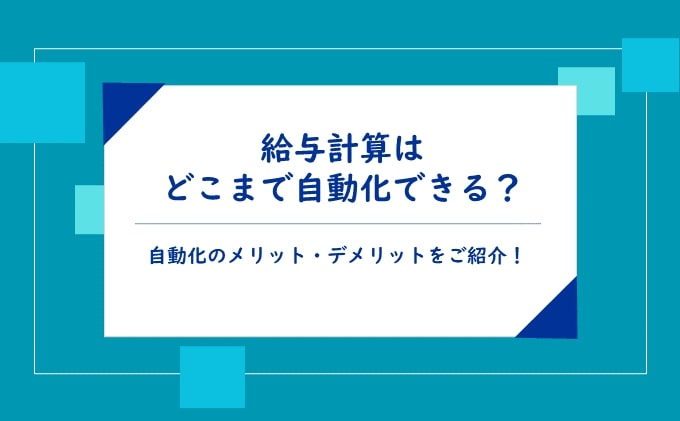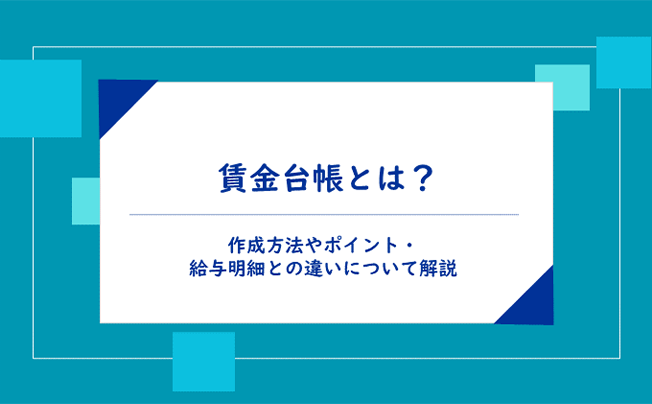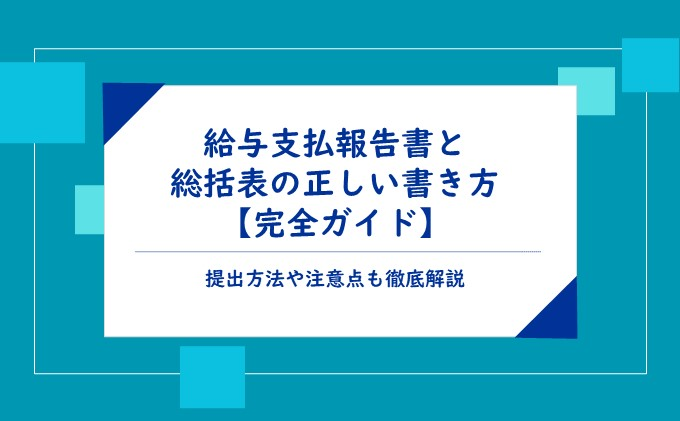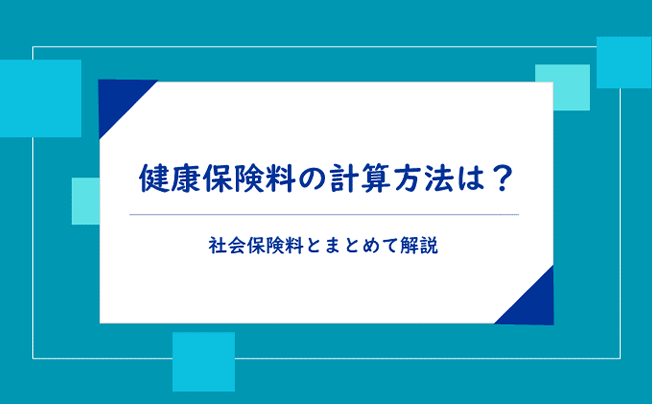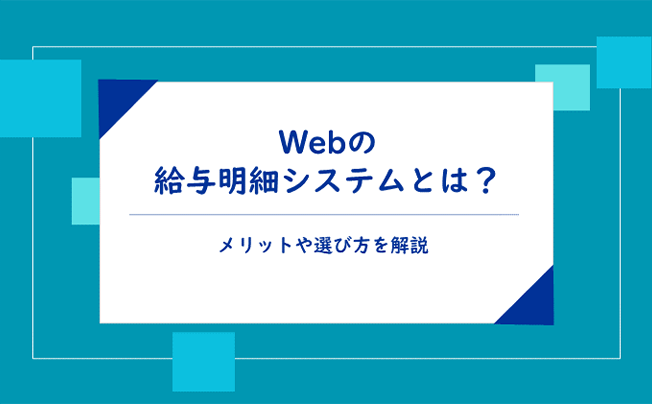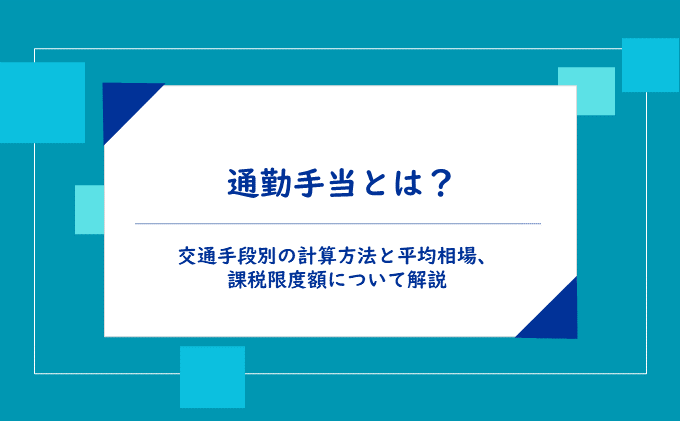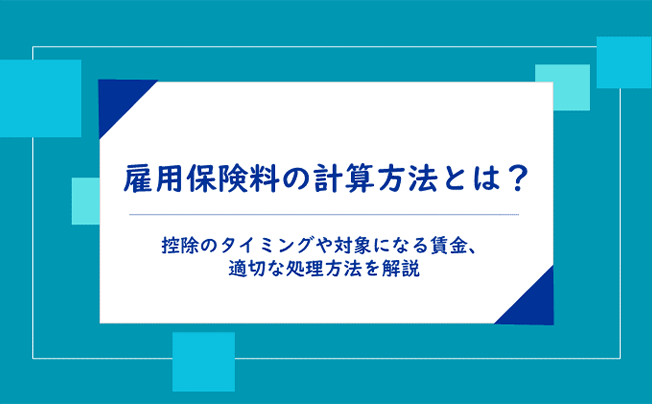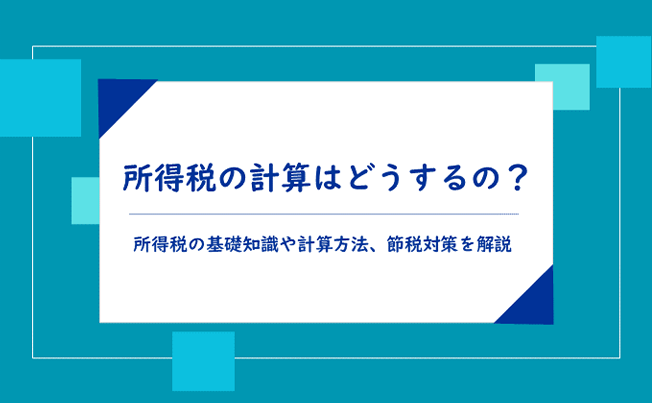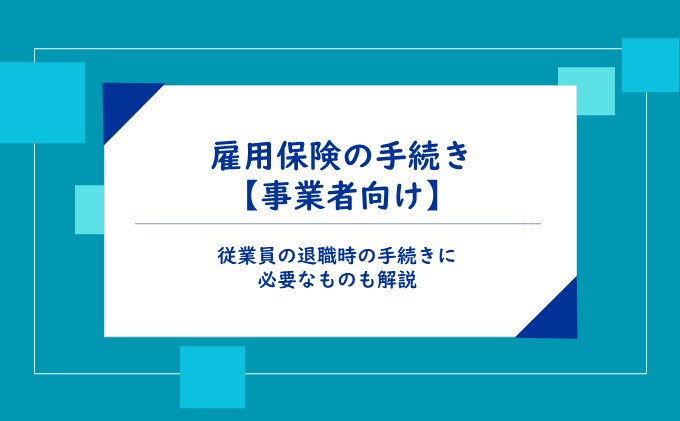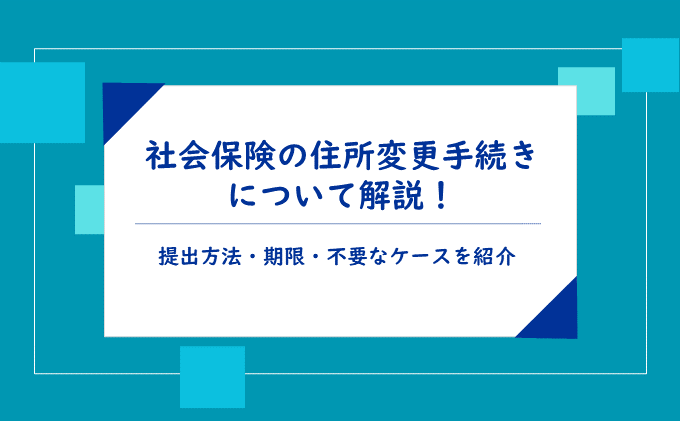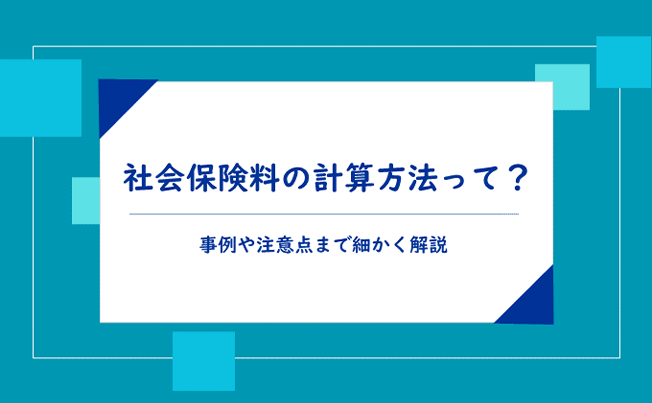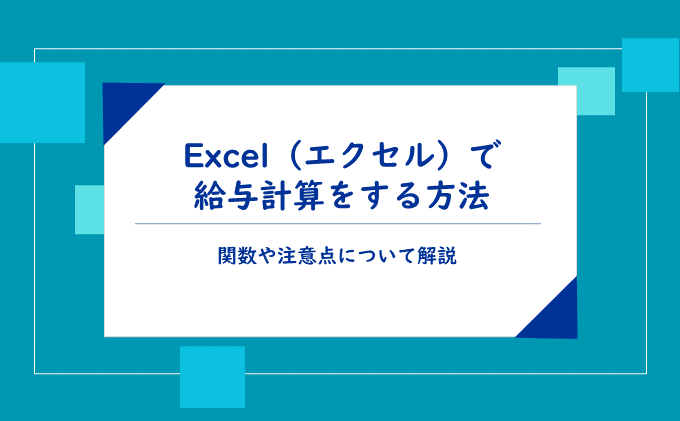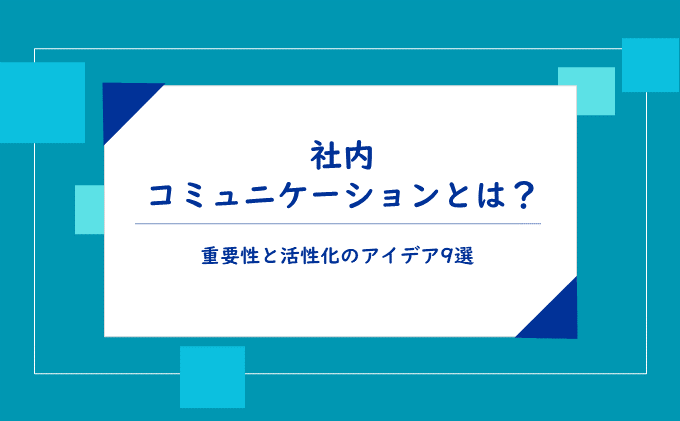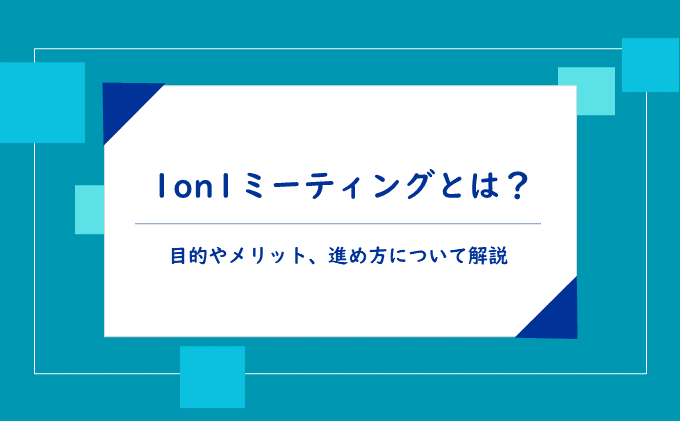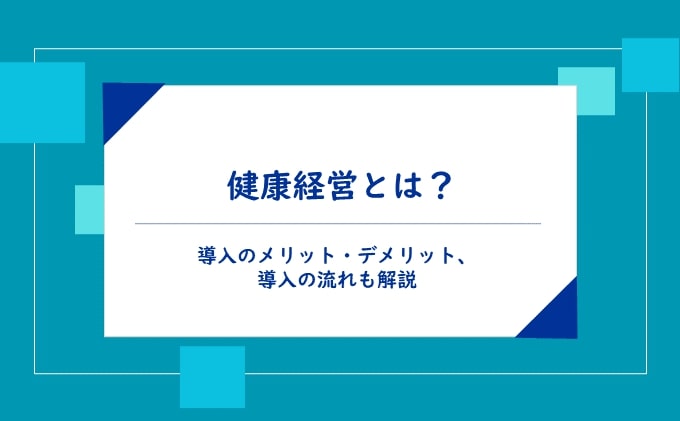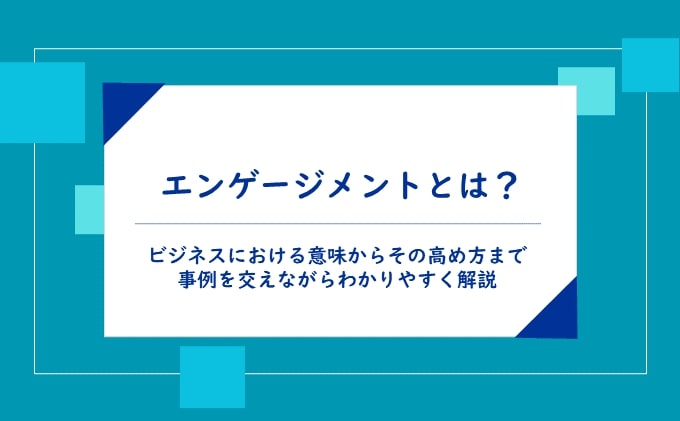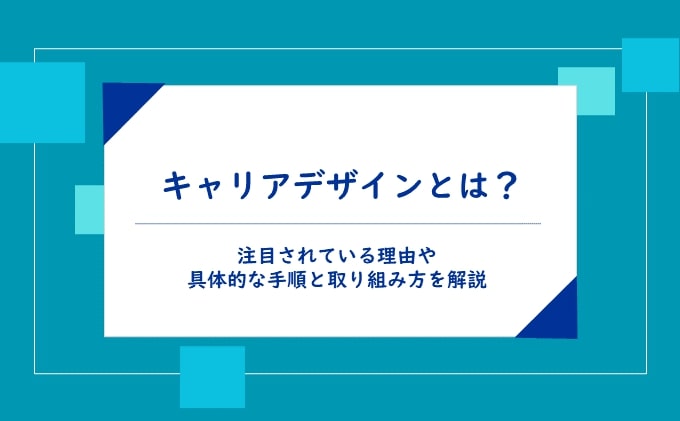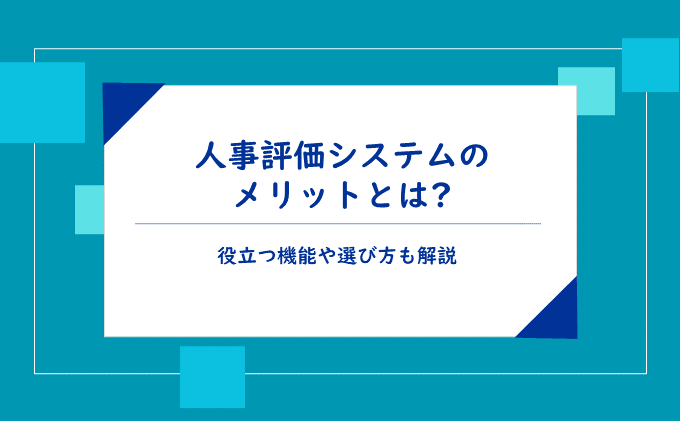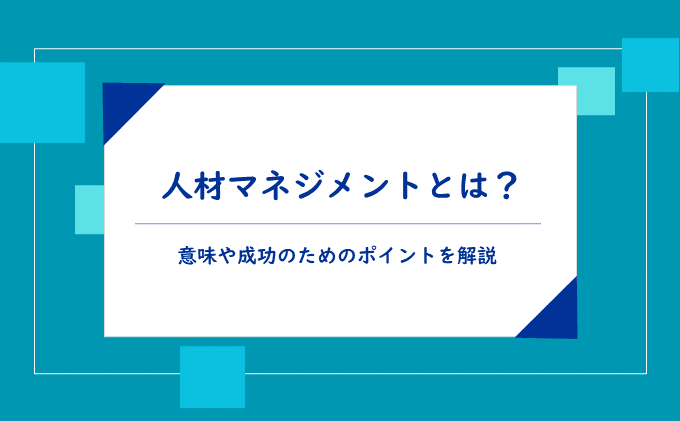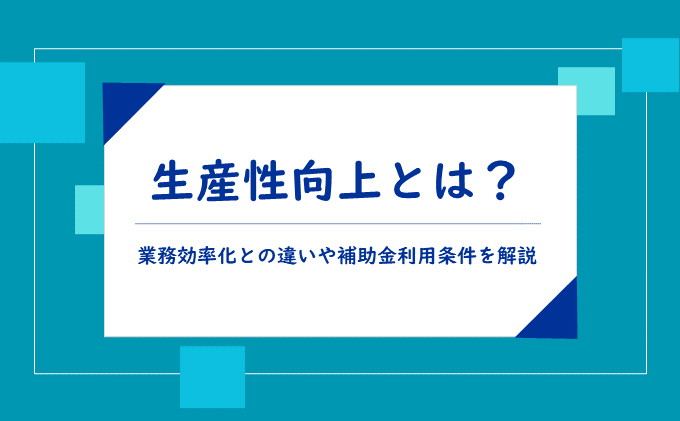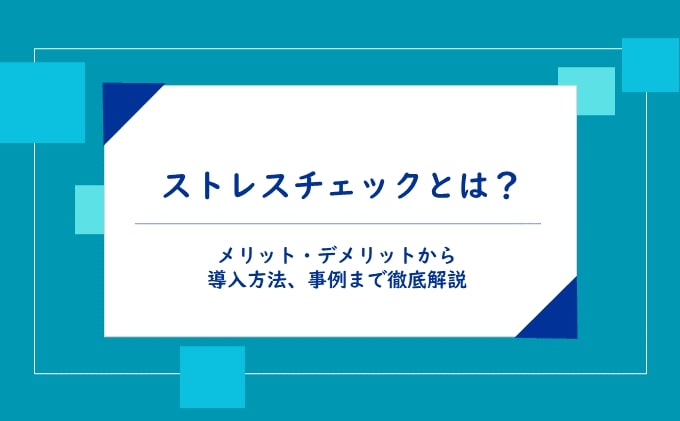年金制度の改正ポイントを徹底解説!
2024.01.12
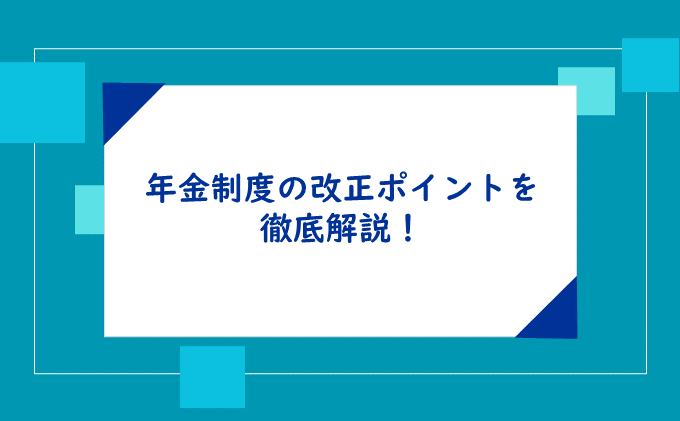
年金制度改正法とは、2020年に成立した「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」のことです。2022年4月1日より施行されています。
本記事では、年金制度改正法についてはもちろん、改正の目的や今回の改正ポイントを徹底解説します。
目次
製品の詳細を知りたい方はこちら
年金制度改正法とは

年金制度改正法とは、2020年に成立した「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」のことです。この法律は、2022年4月1日より施行されています(一部、同年10月1日、2024年10月1日に段階的に施行)。
そもそも年金とは、あらかじめ保険料を納めておくことで、必要なときに給付を受けられる社会保険の一つです。日本の公的年金制度は、老後や事故などにより自立した生活が困難になるリスクに備えて、社会全体で支えるという考えのもとで作られています。
そのような日本の年金制度は、以前から少しずつ改正が重ねられているのが特徴です。今回は、高齢化社会への対応を重視した改正になります。
年金制度改正法の目的
厚生労働省の「年金制度改正法の概要」によると、年金制度改正法の目的は「より多くの人がより長く多様な形で働く社会へと変わっていく中で、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るため」とあります。
現在、少子高齢化がますます進む中、労働人口の減少にも歯止めがかかっていません。改正に至った背景としては、以下のような点が挙げられます。
- 少子高齢化による現役世代の減少
- 高齢者や女性の就労割合の増加と、働き方の多様化
それぞれ詳しくみていきましょう。
まず、少子高齢化による現役世代の減少についてです。厚生労働省によると、2022年の合計特殊出生率は1.26であったことが発表されました。過去4番目に低い数値で、出生数も6年連続で低下しているのが現状です。出生率が増加していかないかぎり、将来の年金制度を支える現役世代の減少は避けられないと予測されています。
一方で、高齢者や女性の就労割合が増加することは、年金制度にとってはプラスです。高齢者の就業率については、総務省統計局「高齢就業者数の推移」によると、高齢就業者数は2010年の570万人から2022年の912万人へ増加しています。
また、女性の総就業者数も、内閣府男女共同参画局サイトの「就業者数及び就業率の推移」によると、2001年の2,629万人から2020年の2,968万人へと増加傾向にあるようです。
上記のように、高齢者と女性の就労割合が増加傾向にある一方で、課題もあります。それが従来の年金制度です。
従来の年金制度では、在職高齢者は年金の一部もしくはすべてを受給できない可能性がある、短時間だけ働く女性が厚生年金に加入できない、といった課題がありました。これらの課題を改善すべく、今回の年金制度改定では多様な働き方を認めて、社会保障費を現役世代だけでなく平等に負担してもらうのが狙いです。
今回の年金制度改正法の主な変更点は、以下の4つです。
- 被用者保険の適用拡大
- 在職中における年金受給の仕組みの見直し
- 受給開始時期における選択肢の拡大
- 確定拠出年金の加入可能要件の見直し
今回の年金制度改正法では、被用者保険の適用拡大により高齢者・既婚女性だけでなく、すべての年代の人の多様な働き方を支援・促進しています。
参考:厚生労働省「年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました」
参考:厚生労働省「令和4年(2022) 人口動態統計月報年計(概数)の概況」
年金制度の改正ポイント

続いて、今回の年金制度の改正ポイントについてもみていきましょう。主なポイントは、以下の5つです。
- 老齢年金の繰下げ年齢の上限引き上げ
- 繰上げ受給の減額率の変更
- 加給年金の支給停止の規定見直し
- 在職中の受給者の年金額改定
- 基礎年金番号通知書の発行
ひとつずつみていきましょう。
老齢年金の繰下げ年齢の上限引き上げ
今回の改正にともない、老齢年金の繰下げ受給の上限年齢が75歳に引き上げられています。従来の年金受給開始年齢は、60〜70歳の間で自由に選択可能でした。今回の年金制度改定では、受給開始年齢は同様ですが、受給開始時期の繰上げ上限が70歳から75歳まで引き上げられたため、選択肢が拡大しています。
対象者は、令和4年3月31日時点で以下の2つのいずれかに該当する方です。
- 70歳未満の人(昭和27年4月2日以降生まれ)
- 老齢年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過していない人(受給権発生日が平成29年4月1日以降)
※上記のいずれにも該当しない方は、令和4年3月まで同様、繰下げ上限年齢は70歳です
なお、受給開始時期を繰下げた場合の「繰下げ増額率」は、1月あたり0.7%です。仮に75歳まで繰下げた場合の繰下げ増額率は、最大184%になります。
繰上げ受給の減額率の変更
老齢年金の繰下げ年齢の上限引き上げと並んで、繰上げ受給の減額率も変更になっています。
繰上げ受給とは、受給開始年齢より早く年金を受け取ることです。老齢年金の支給開始年齢は原則65歳ですが、支給開始時期を60~64歳までの期間から月単位で選べます。
減額率とは1か月あたりの減額割合のことです。2022年3月までの減額率は「0.5%」でしたが、改正にともない0.4%に変更されています。ただし、新しい減額率が適用されるのは、2022年4月1日以降に60歳になる人(1962年4月2日以後生まれ)です。
老齢年金を繰上げ受給した場合、年金の支給額が減額されます。例として、65歳から5年(60か月)前倒しして支給開始年齢を60歳にした場合の減額値をみてみましょう。
2022年3月まで:30%(=0.5%×60か月)減る
改正後:24%(=0.4%×60か月)減る
加給年金の支給停止の規定見直し
制度改正にともない、加給年金の支給停止の規定が見直されています。規定の見直しにより、これまで加給年金の支給対象だった人が支給停止の対象になる場合もあるため、注意しましょう。
そもそも加給年金とは、厚生年金保険に20年以上加入している人が65歳になった時点で利用できる制度です。条件を満たす配偶者または子どもがいる場合にかぎり、老齢年金のうち老齢厚生年金の金額が一定期間にわたり加算され、支給されます。
改正前・改正後の変更点は以下のとおりです。
●改正前
配偶者の老齢(退職)年金が全額停止のとき→加給年金支給
配偶者の老齢(退職)年金が一部でも支給されているとき:加給年金支給停止
●改正後
配偶者の老齢(退職)年金の支給状態に関わらず→加給年金支給停止
ただし、以下の要件をすべて満たせば、加給年金が継続となる経過措置が設けられています。
- 2022年3月時点で、本人の老齢厚生年金、または障害厚生年金に加給年金が加算されている
- 2022年3月時点で、配偶者に厚生年金保険被保険者期間20年(240月以上)の老齢厚生年金受給権があり全額支給停止されている
在職中の受給者の年金額改定
今回の改正と合わせて、年金額の在職定時改定が新設されています。
これまで老齢厚生年金の額は、退職等により厚生年金被保険者の資格を喪失するまで改定されませんでした。しかし、在職定時改定により、老齢厚生年金額を年1回(毎年10月)改定するルールへと変更されます。
年金を受給しながら働く在職受給者の経済基盤の充実が狙いです。
基礎年金番号通知書の発行
改正以降、基礎年金番号を通知する書類として、年金手帳に代わり基礎年金番号通知書が発行されます。
発行される対象者は、以下のいずれかに該当する人です。
- 新たに年金制度に加入する人
- 年金手帳の紛失、またはき損にともない、基礎年金番号が確認できる書類の再発行を希望する人
年金手帳は、国民年金や厚生年金などの公的年金制度の加入者に発行される被保険者情報の載った手帳です。しかし、現在では被保険者の情報はシステムで管理されているほか、個人番号(マイナンバー)とも紐づけられているため、手帳の必要性が薄れ、廃止される形になりました。
年金の計算には給与計算の自動化がおすすめ

年金を算出するうえで、その基礎となる厚生年金保険料の計算及び徴収を給与業務において行いますが、控除額の計算など手間がかかります。そこで、給与計算の手間を省くためには、システムの導入がポイントです。
年金保険料の計算には給与計算を自動化できる、カシオヒューマンシステムズ株式会社が提供している人事統合システム「ADPS(アドプス)」の導入を検討してはいかがでしょうか。
「ADPS」は、人事情報管理・給与計算など各業務の流れに沿ってナビゲートするため、人事業務に初めて関わる人から、ベテランの人まで安心して活用できるシステムです。
また、企業の従業員規模や雇用形態の種類などに応じて、オンプレミス型/クラウド型/BPOの選択もできます。「ADPS」については、以下をご確認ください。
製品の詳細を知りたい方はこちら
関連記事:給与計算はどこまで自動化できる?|自動化のメリット・デメリットをご紹介!
まとめ

年金制度改正法について解説しました。年金制度改正法とは、2020年に成立した「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」のことです。2022年4月1日より施行されています。
改正法の主な変更点は、被用者保険の適用拡大、在職中における年金受給の仕組みの見直し、受給開始時期における選択肢の拡大などです。今回は、高齢化社会への対応を重視した改正になります。
年金制度は少しずつ改正が重ねられているため、年金の元となる給与計算においても注意が必要です。そこで、人事統合システムの導入を検討してみてはいかがでしょうか。人事統合システムを導入すれば、給与業務を含むさまざまな人事業務を効率化できる点がメリットです。
製品の詳細を知りたい方はこちら
カシオヒューマンシステムズコラム編集チームです。
人事業務に関するソリューションを長年ご提供してきた知見を踏まえ、
定期的に「人事部の皆様に必ず今後の業務に役立つ情報」を紹介しています。