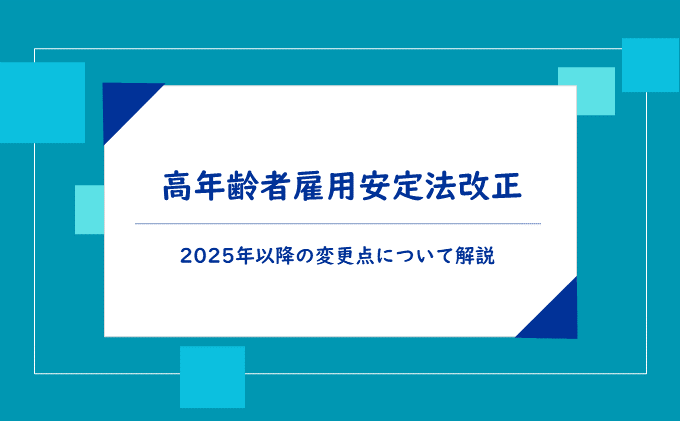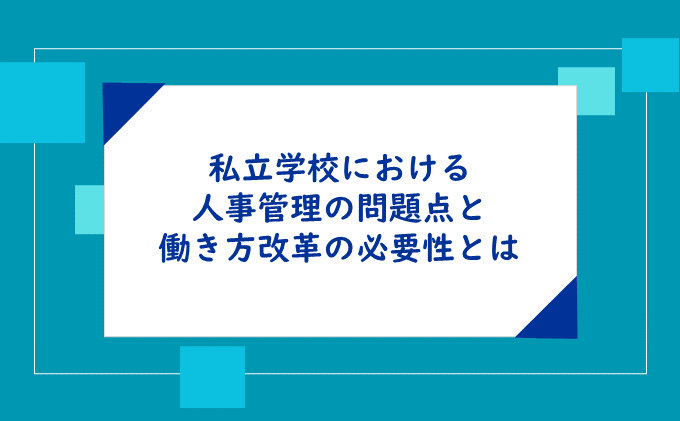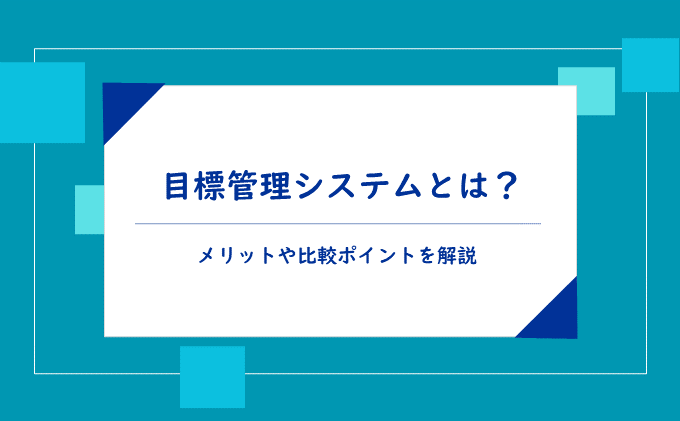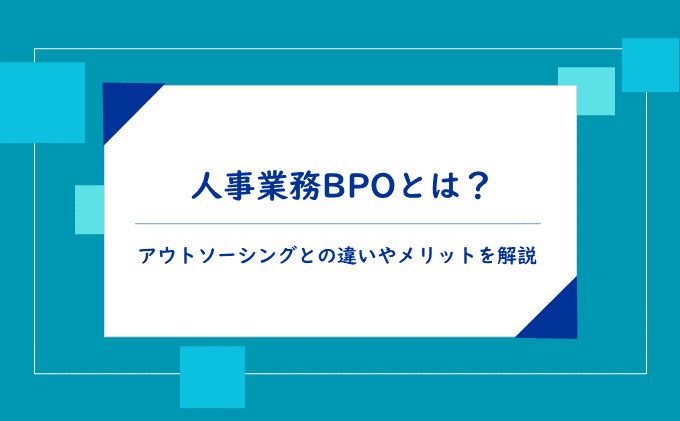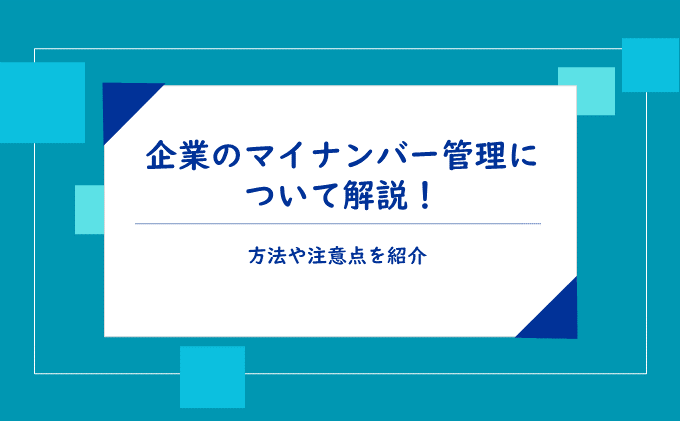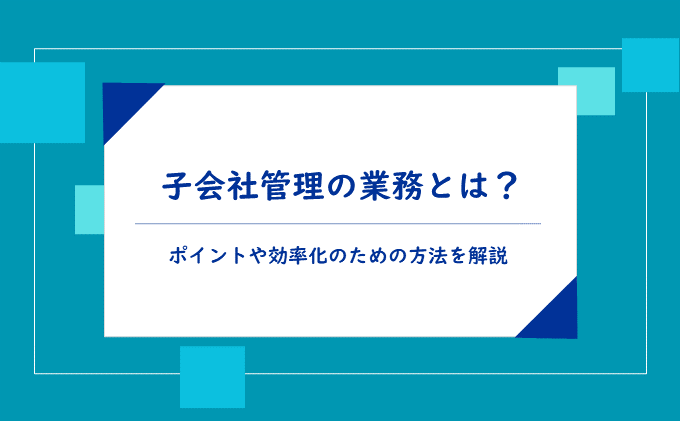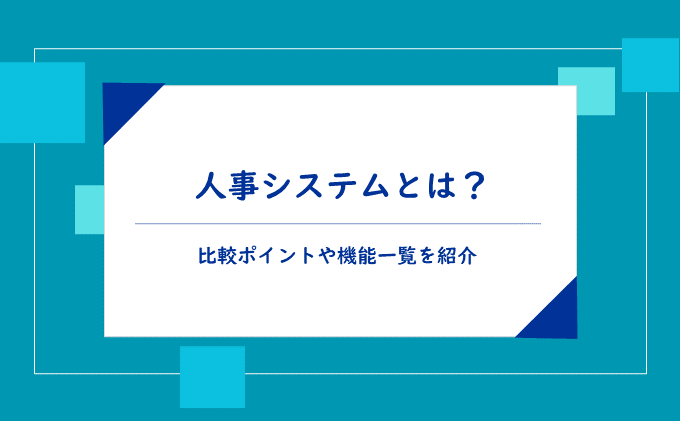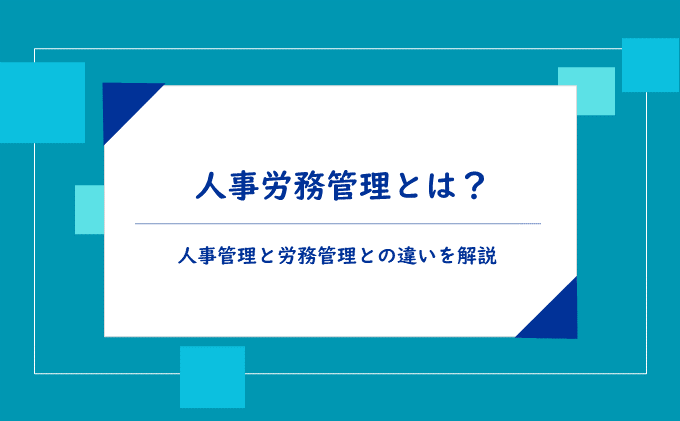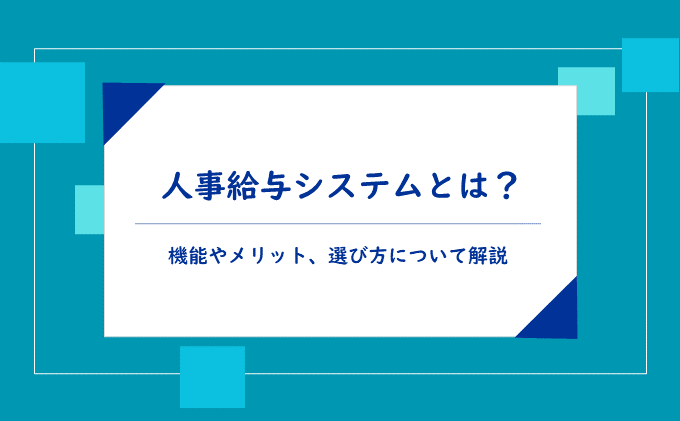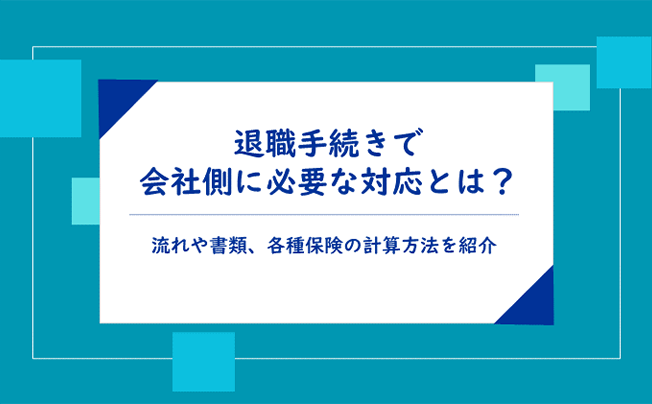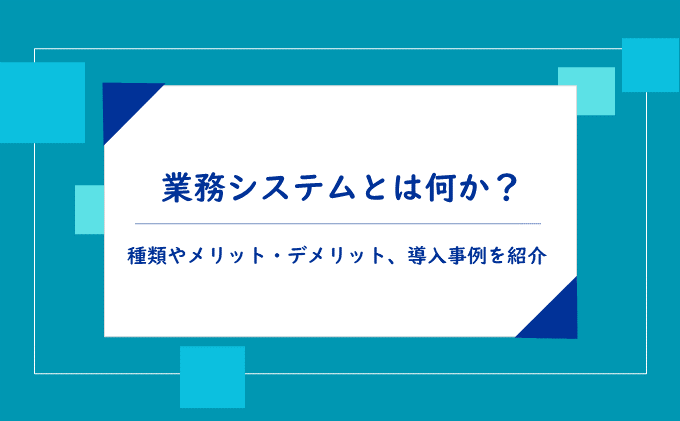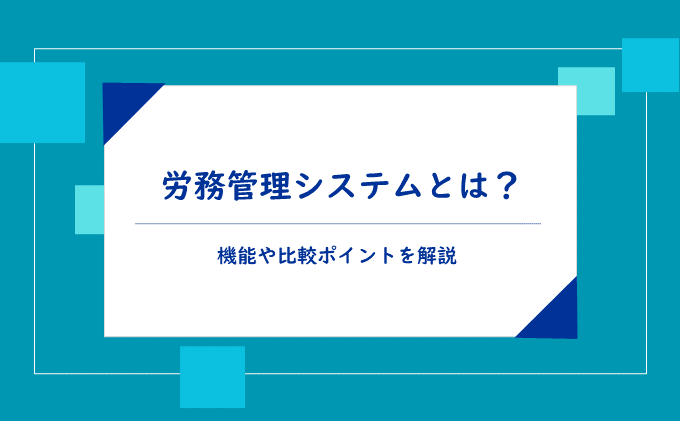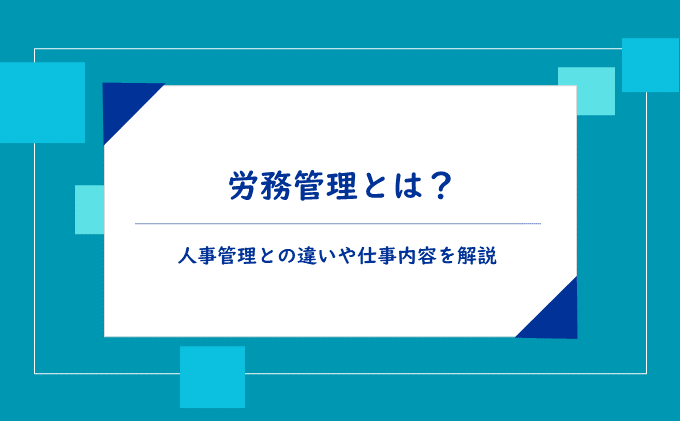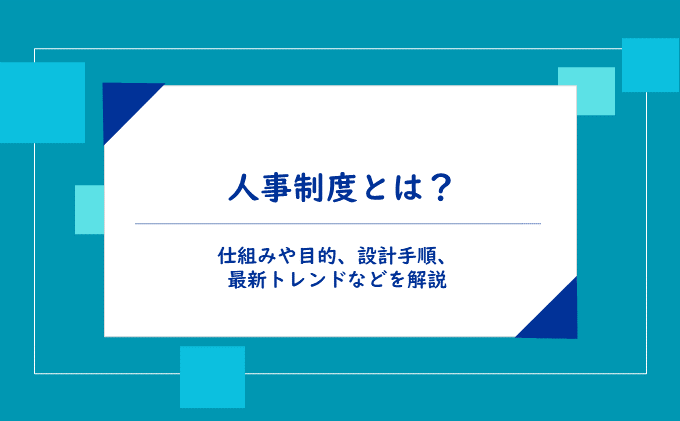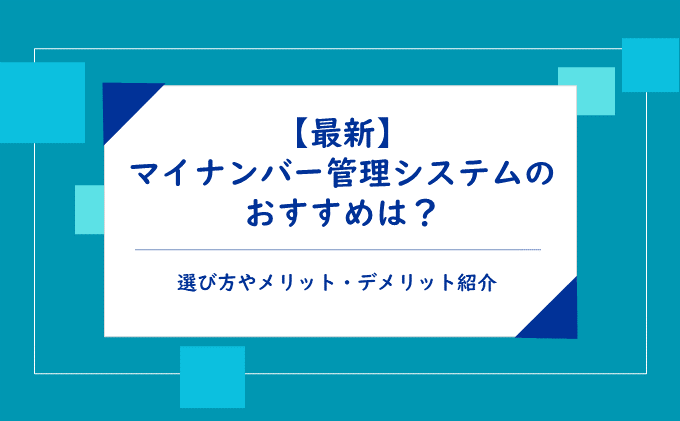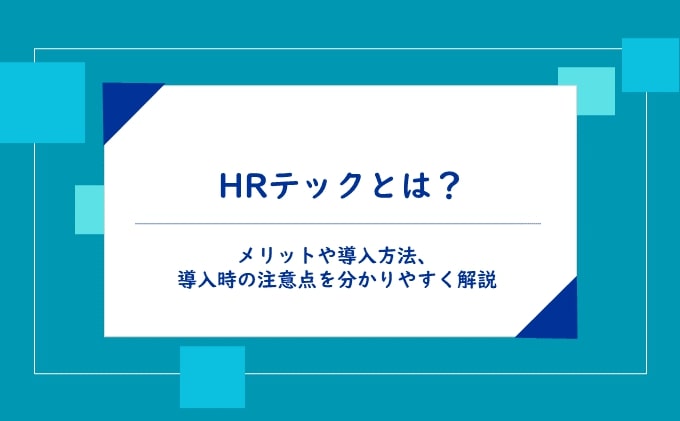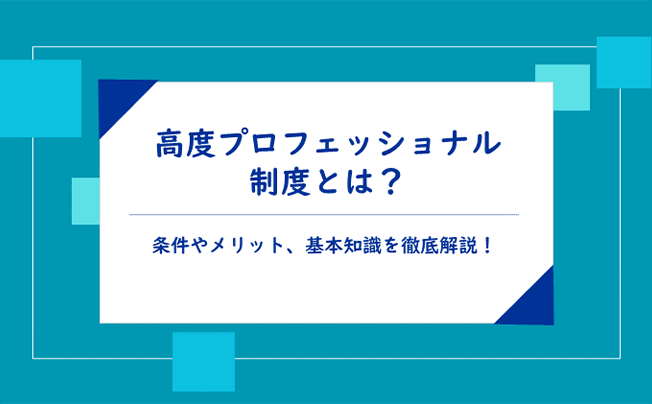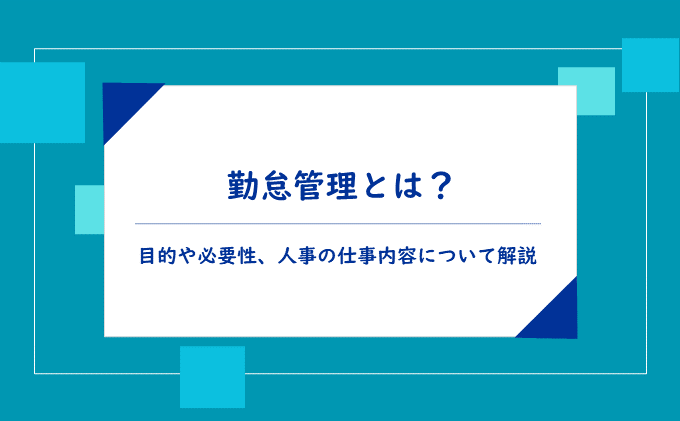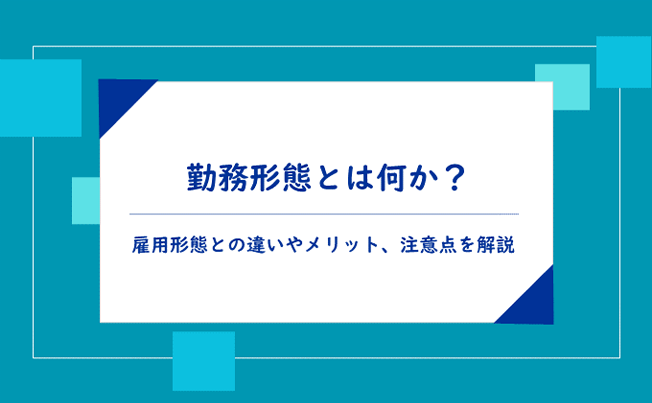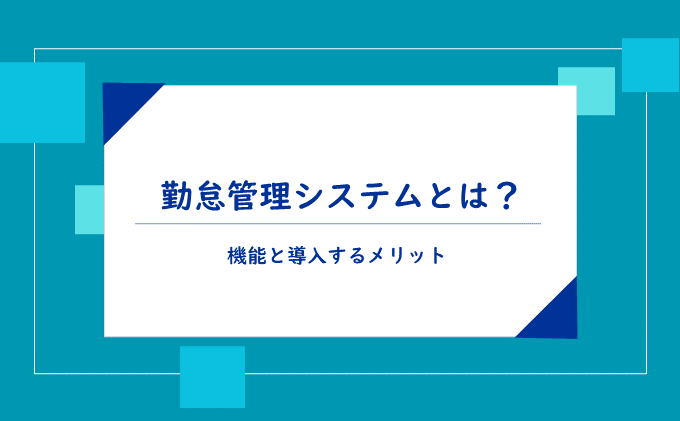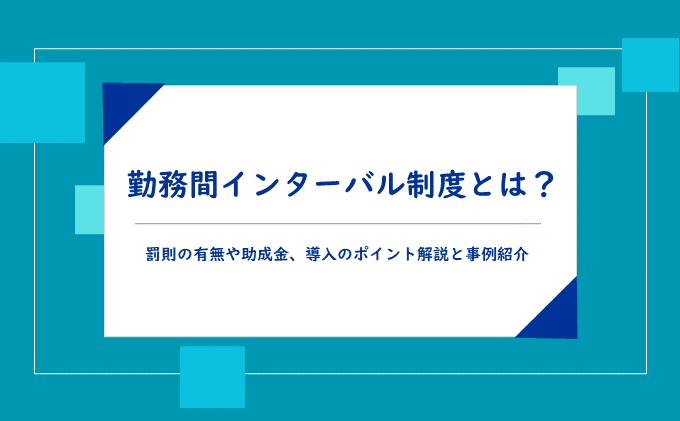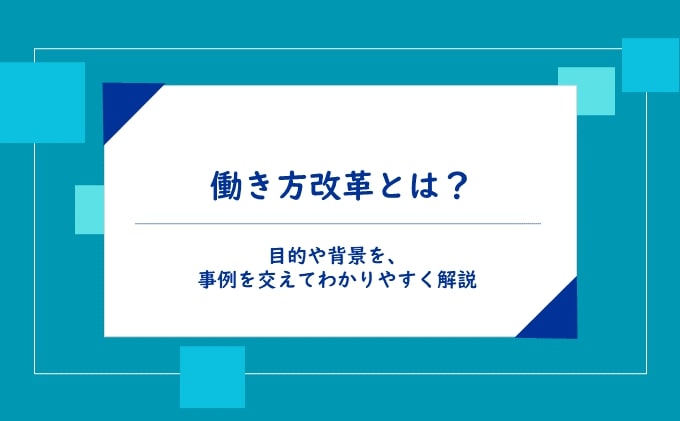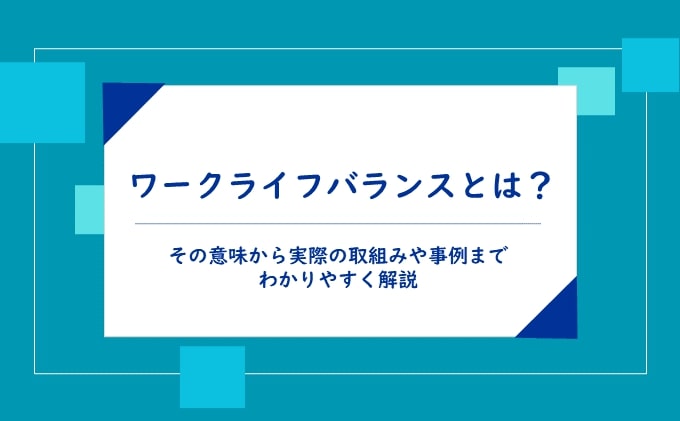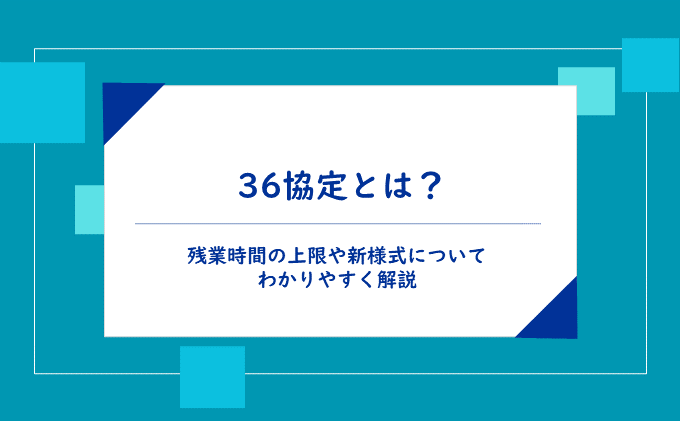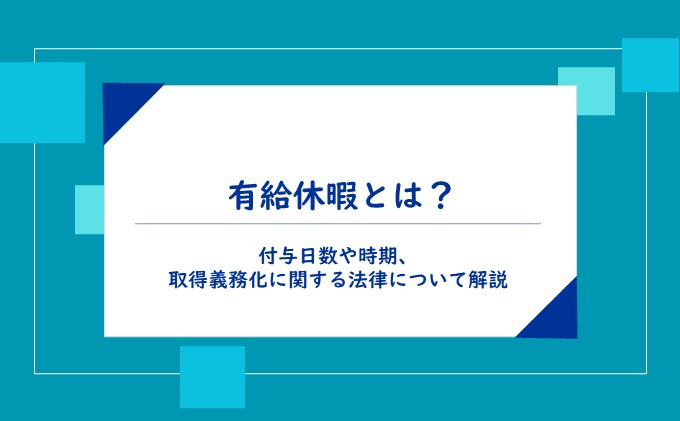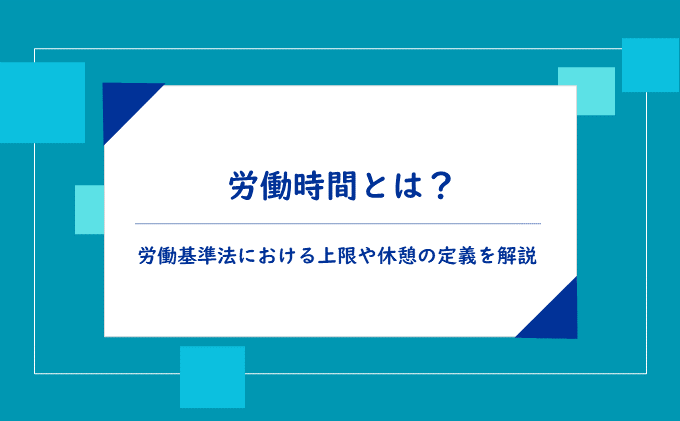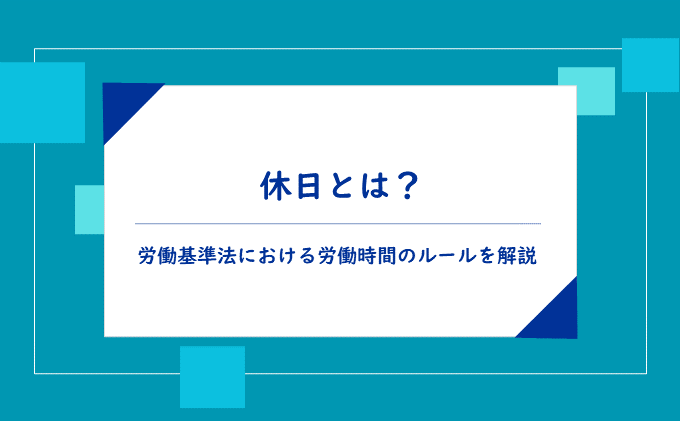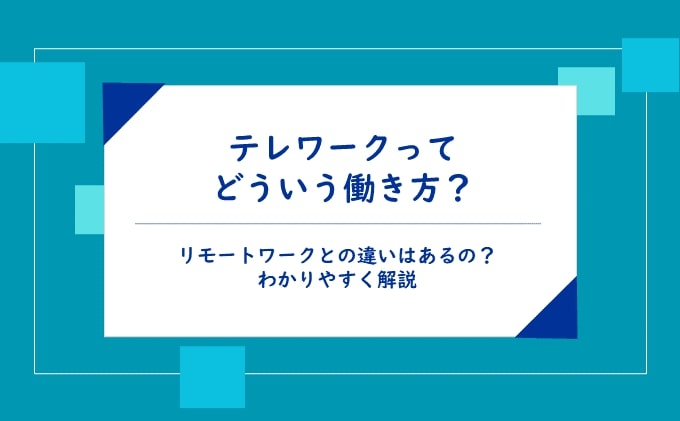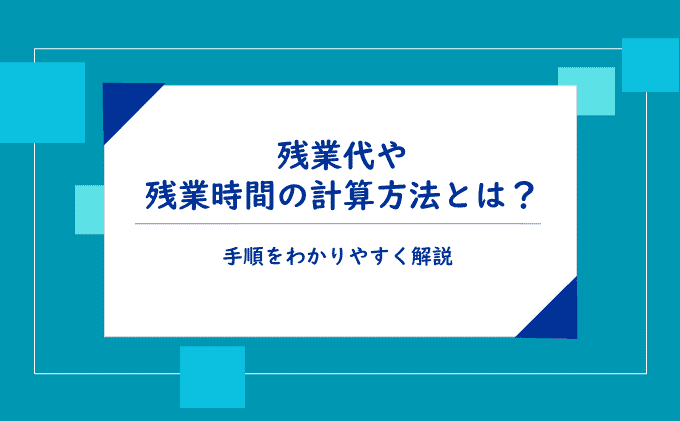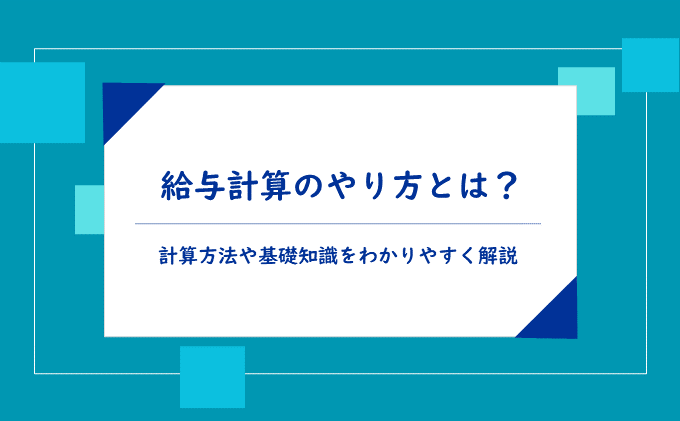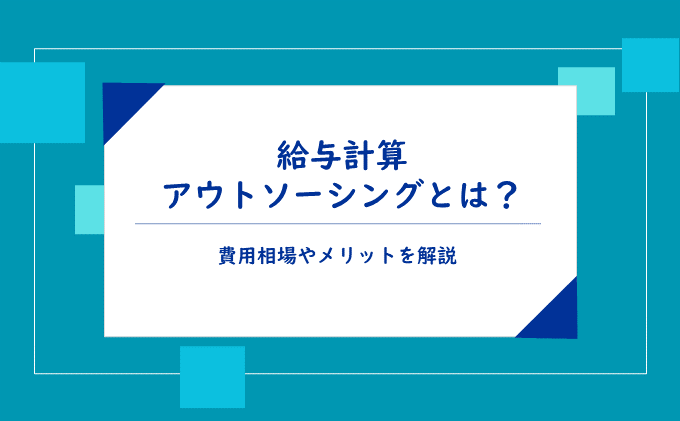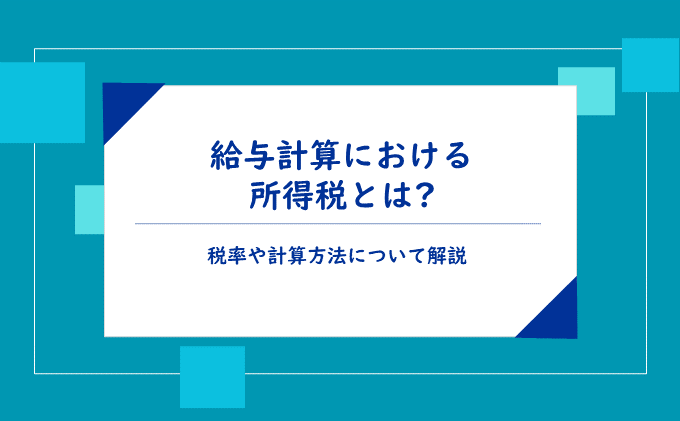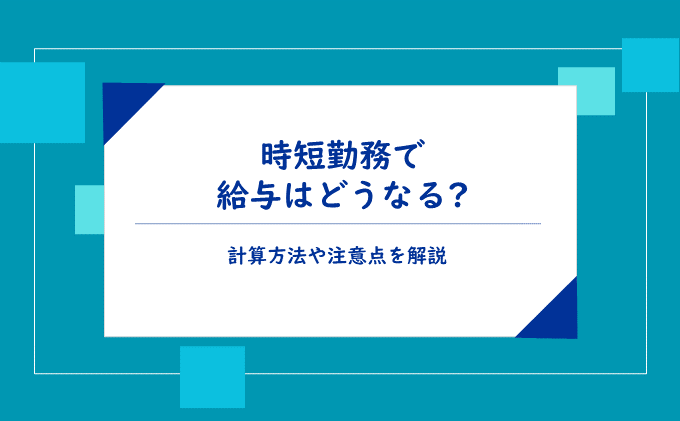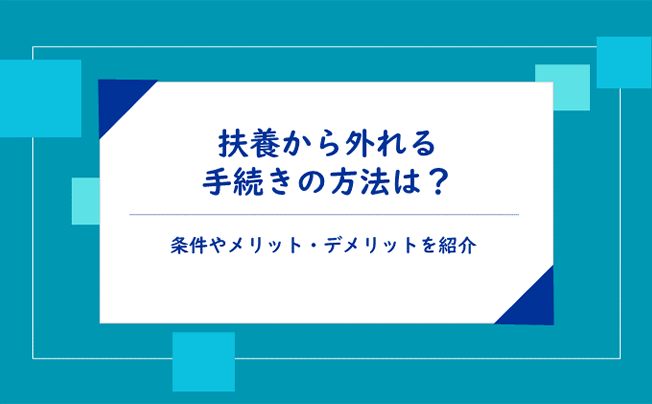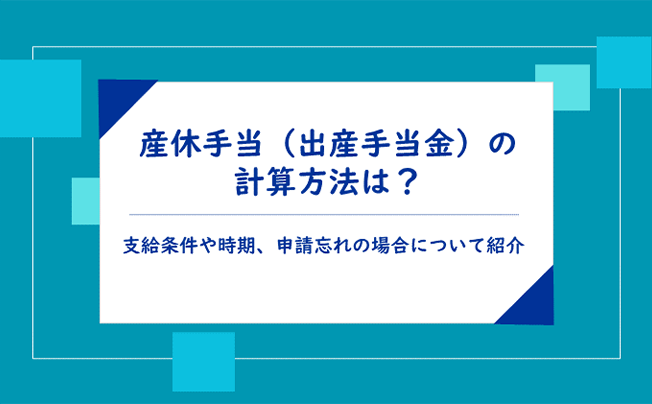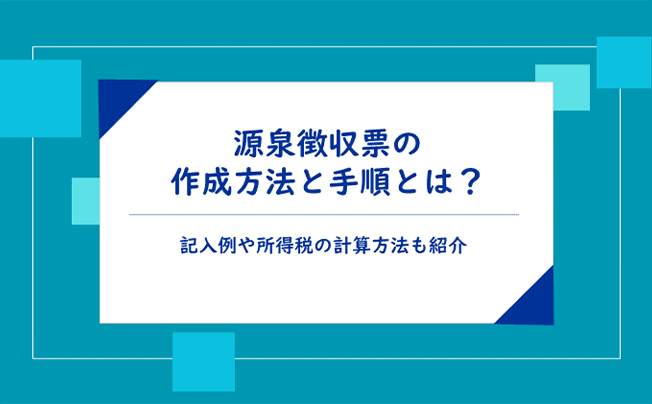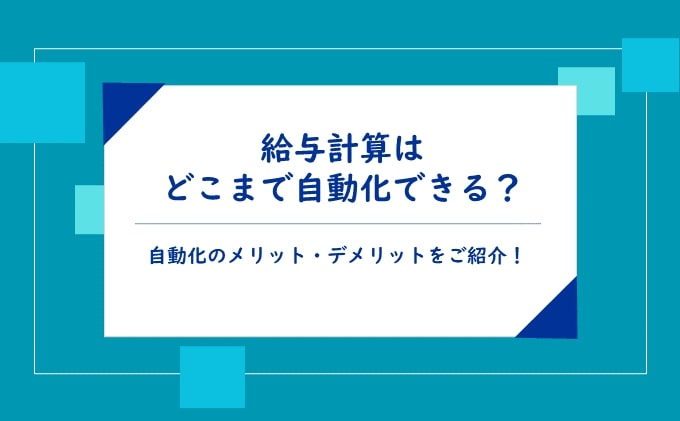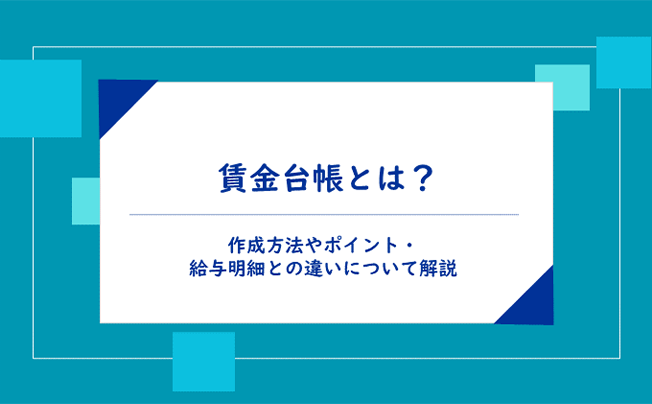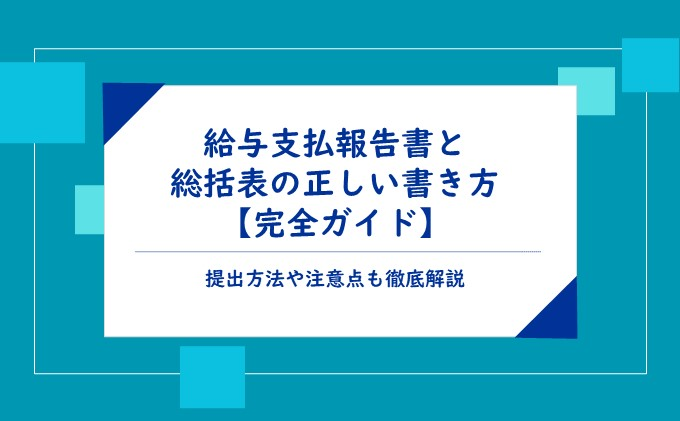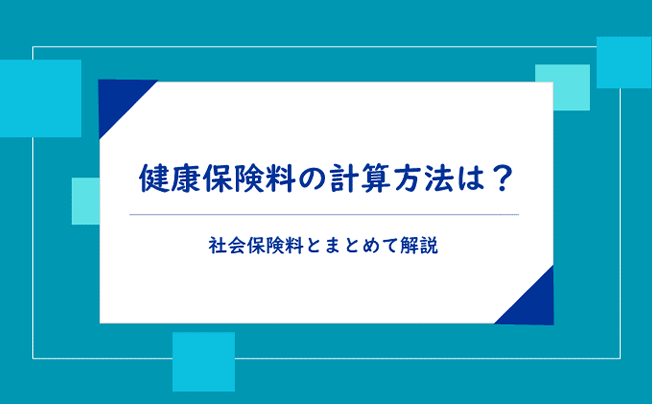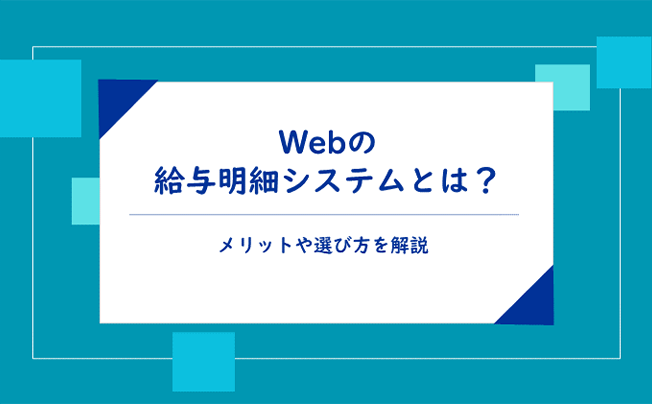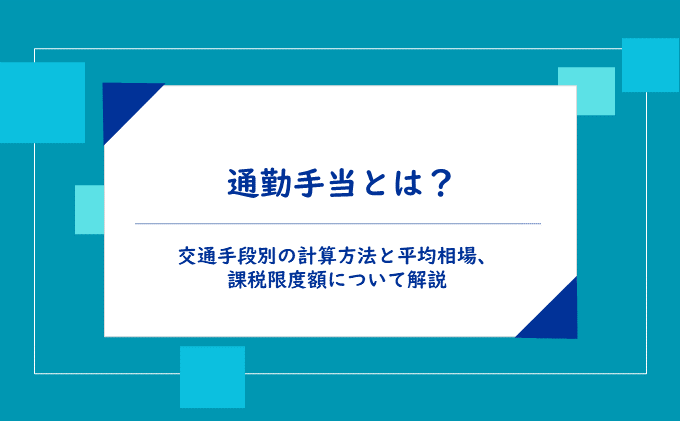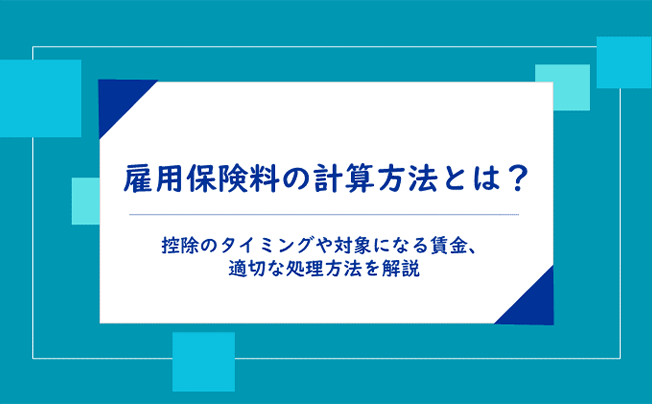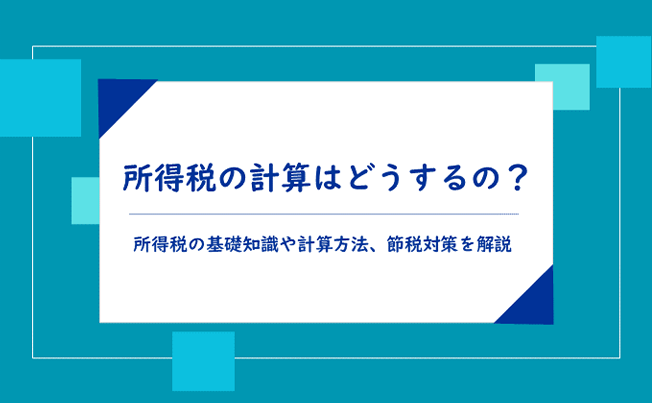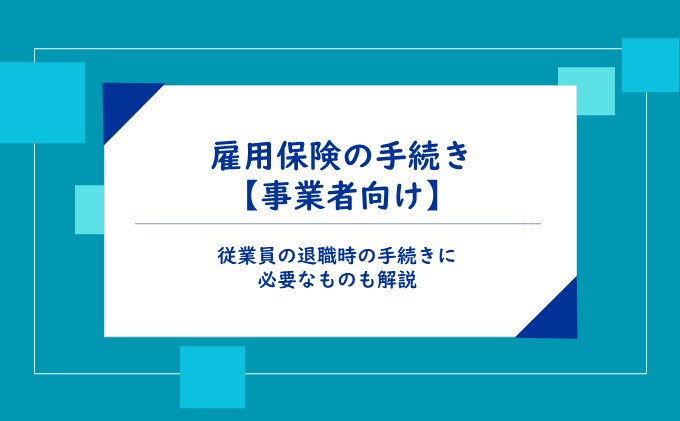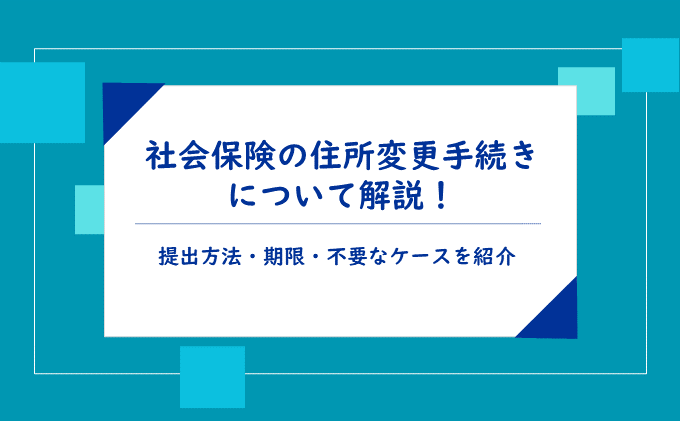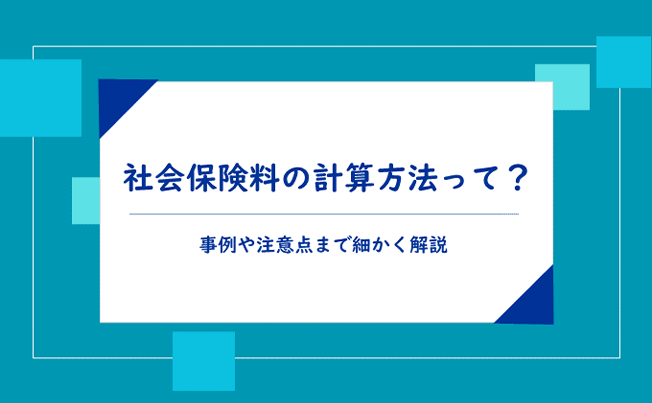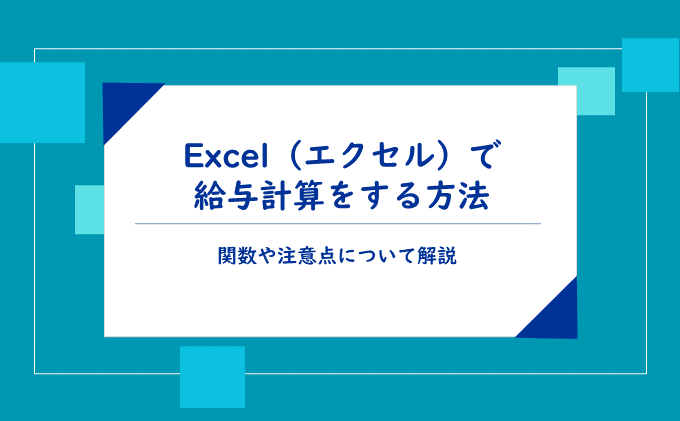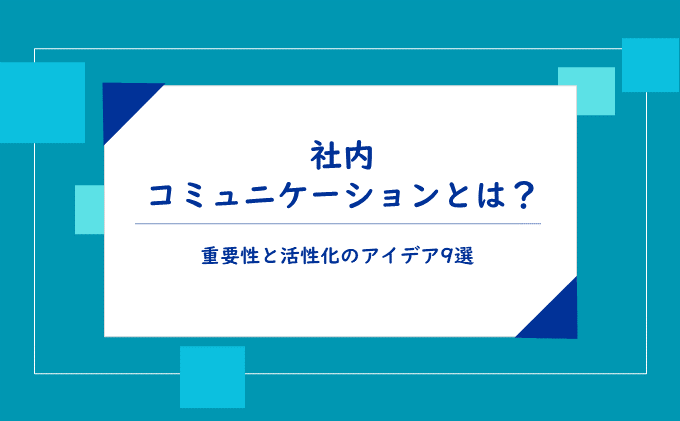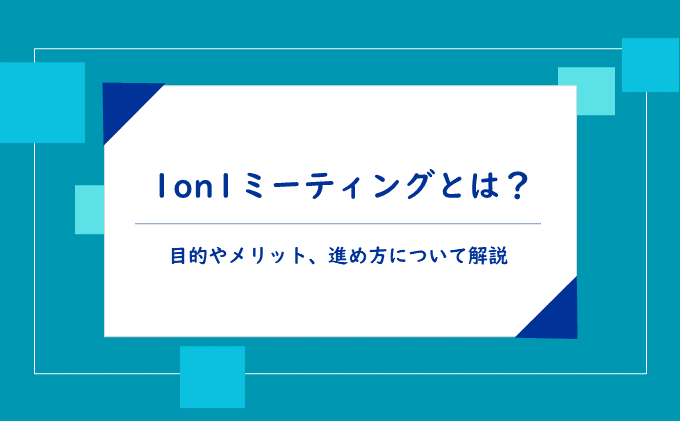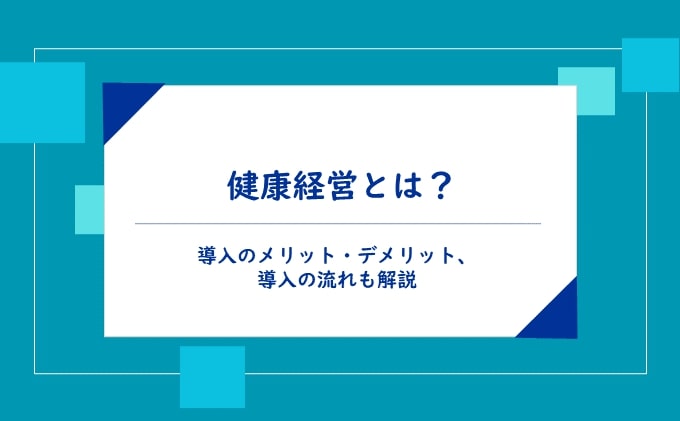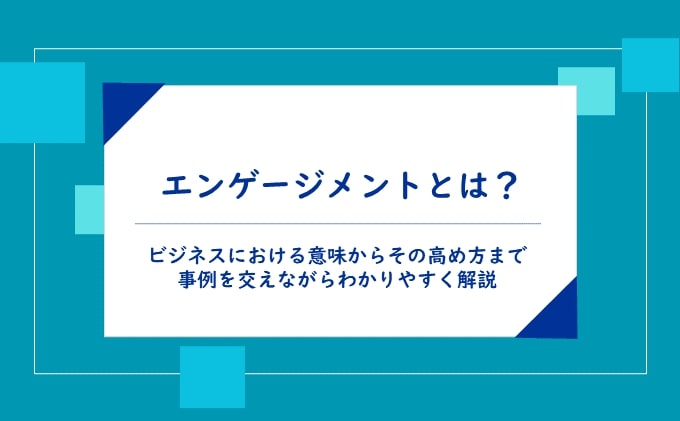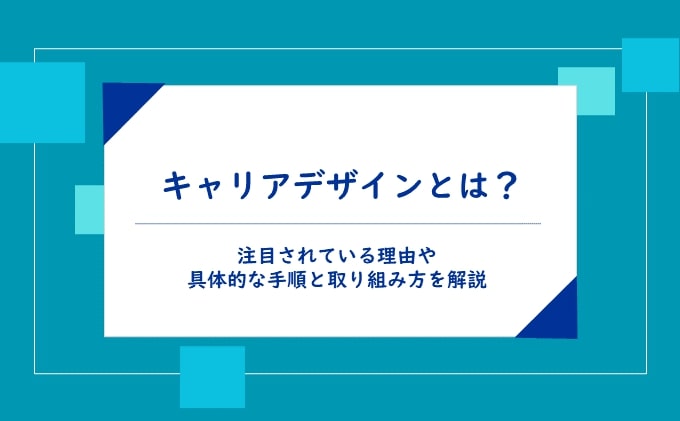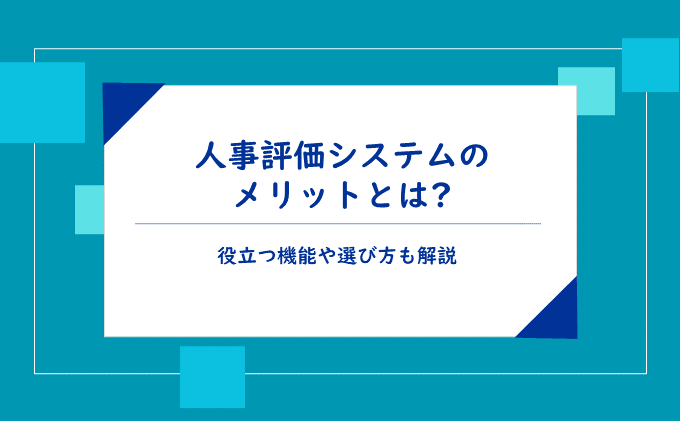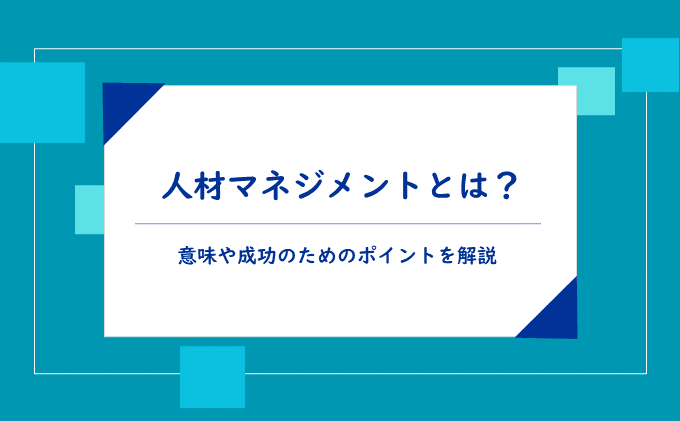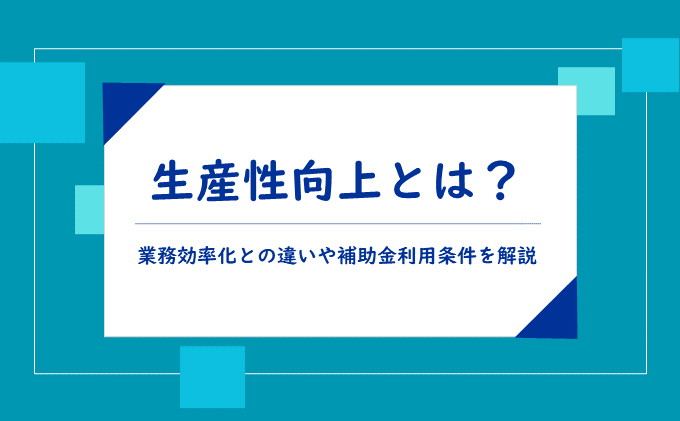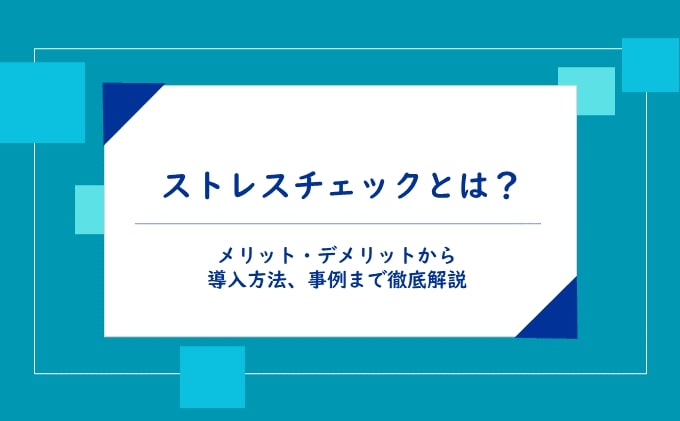サイロ化とは?意味や原因、解消方法をわかりやすく解説
2025.03.19
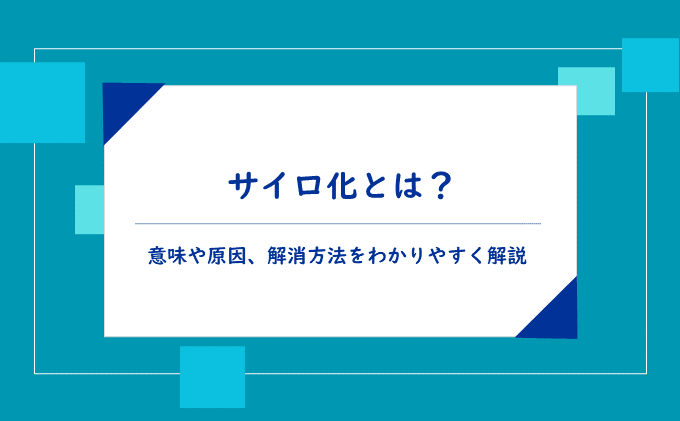
データや組織の連携ができていないため、情報共有や業務効率の面で問題が起こるのが「サイロ化」です。企業の競争力にも悪影響を与えるとして、近年、対策を講じる企業も増えています。本記事では、サイロ化の概要からその原因、解消するためのポイントなどについて幅広く解説します。
目次
製品の詳細を知りたい方はこちら
「サイロ化」の意味とは

「サイロ化」とは、農場などで見られる飼料などの貯蔵庫である「サイロ」になぞらえて作られた言葉です。本来のサイロは、牧草やトウモロコシなどの貯蔵物が混ざらないように、それぞれが独立しています。
これと同様に、組織や情報、システムが部署や拠点の中だけで使われ、他部署などとの連携や共有がなされない状態を表す用語がサイロ化です。英紙フィナンシャル・タイムズの東京支局長などを務めたジリアン・テット氏は、著作「サイロ・エフェクト 高度専門化社会の罠」で、名だたる大企業がサイロ化により凋落していった様子を描きました。
ここでは、サイロ化が問題となる3分野について説明していくほか、サイロ化が起こる原因に関しても解説していきます。
サイロ化の種類
サイロ化が問題となるのは、主に以下の3つの分野です。それぞれについて解説します。
- 組織
- システム
- データ
1.組織のサイロ化
企業内で、組織が縦割り化して拠点や部門の間で連携がうまく取れなくなっている状態が、組織のサイロ化です。こうした状態になると、連絡や確認が1回で済まなくなったり、人事異動がなく新陳代謝を促すことができません。
IT(情報技術)やAI(人工知能)など、技術の進化が速く広範になっているため、とりわけ先端的な分野では組織のサイロ化が起こりやすいといえます。組織の専門性が高まる点はメリットといえなくもありませんが、デメリットの方が大きいと考えるのが一般的です。
2.システムのサイロ化
組織の柔軟性が損なわれると、各部門がそれぞれに異なるシステムを導入してしまい、連携させての運用ができないなどの問題が生じることがあります。これがシステムのサイロ化です。
この状態になると、システムごとに扱うデータ形式がばらばらで統一性がないため、部門間で弊害が生じやすくなります。情報連携が複雑になったり、部門を越えた全社的なデータを揃えるのに時間がかかったりする点などがデメリットです。
これを放置すると、各部署がそれぞれのシステムを独自に発展させ、他部署との連携がますます困難になりかねません。
3.データのサイロ化
システムが部門ごとに異なれば、データ共有や連携が困難になるのは前述のとおりです。これに加え、紙に打ち出したり、数値を従業員が目視して記録したりするなど、アナログデータを使い続けている部署がある場合もあります。
こうしたデータのサイロ化が起こると、ノウハウの共有などがしにくいため、業務効率や生産性の向上を阻害する要因となります。生産や販売の数量など、同じようなデータを部署ごとに、異なる方法で抽出しているなど、業務にムダが生まれやすいのも難点です。
販売部門で集めたデータが開発部門に提供されていなければ、顧客のニーズにあった商品は作れません。データのサイロ化によって、こうした非効率が発生します。
サイロ化の主な原因
サイロ化の原因として考えられる要素は、以下のようなものです。
- 組織が縦割り構造となっている
- コミュニケーション不足
- 共通の目標がない
企業規模が大きくなるほど、組織は縦割りやタコつぼ的な構造となりがちです。部署が1つの会社のような構造となり、他部署とはライバルのような関係となり、情報共有が円滑に行われないなどの弊害が起こり得ます。
システムを部署ごとに、部分最適を優先して導入してしまうなどの事態も、縦割り構造から生まれやすい問題です。各部署が張り合うことは、営業成績の向上などには利点となる場合もありますが、部署間でのコミュニケーションは不足になりがちです。
自社内全体で有効に使えるデータを揃えるのであれば、各部署が十分にコミュニケーションを取る必要があります。全体の売上高を増加させるには、ある部署の営業データを別の部署でも使えると効率がよい、といったケースは少なくありません。売上高や利益の増加、生産性の向上など、全社的な共通の目標がないと、サイロ化に陥りやすくなります。
サイロ化により生じるデメリット

サイロ化は、企業内で部署ごとの縦割り構造が固定化し、組織、システム、データの連携が十全に機能しなくなるという問題です。この項では、サイロ化によって生じるデメリットについて、具体的に論じます。
生産性や業務効率の低下
社内の複数部署で同じ1つのデータを利用したい場合、どこかの部署で作成したものを共有するのが一般的です。サイロ化しているとこのようなことができず、各部署で同じデータをそれぞれに作るようなムダな動きが発生します。
システムでも同様です。同じような処理が必要であれば、システムを共用して効率的に使うのが一般的です。それぞれの部署で別システムを導入すると、データ形式や運用方法などが異なり、連携が困難になりかねません。
近年、クラウドやビッグデータ、AI(人工知能)などを活用した、新しいビジネスモデルへの転換を模索する企業が増えています。「DX(デジタルトランスフォーメーション)」と呼ばれるもので、企業内に蓄積されたデータの利用と連携が重要視されています。
経済産業省の「デジタルトランスフォーメーションに向けた研究会」が2018年にまとめた「DXレポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的展開~」では、クラウドやAIなど新たなデジタル技術を活用して「これまでにないビジネスモデルを展開する新規参入者が登場している」ことを指摘しました。そのうえで、「このような環境において、各企業は、競争力維持・強化のために、DXをスピーディーに進めていくことが死活問題となっている」と強調しています。
サイロ化されていると、どの部署にどのデータがあるのかが可視化されていないことが多く、DXの流れに乗り遅れる懸念も拭えません。まさに死活問題に直面しているといえます。
参考:経済産業省「DXレポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的展開~」
市場における競争力の低下
システムが部署の壁で分断されていると、例えば社内に散在するデータを集約して新規の企画などを立てようとする場合に、時間がかかってしまうことが考えられます。必要なデータが集まらなければ、企業としての意思決定もできません。
意思決定の遅れは、サービス品質の劣化に直結します。システム投資が重複した場合は、余計なコストがかかってしまう点も問題です。
素晴らしい商品を開発できたとしても、発売のタイミングを失しては、期待どおりの成果は望めません。意思決定が遅れることにより、ビジネスチャンスを逸するなど、市場における競争力の低下する恐れがあります。
サイロ化解消による3つのメリット

サイロ化のデメリットについて、前述してきました。サイロ化の解消で招来されるメリットには、以下のようなものがあります。
1.企業データの価値が向上する
サイロ化が解消されれば、企業内のさまざまなところにあったデータの集積が可能です。多彩で大容量のデータを解析することで、市場開拓や需要予測などにつなげられる可能性も高まります。
AIを活用したビッグデータの解析などにより、これまでは考えられなかったような新たなイノベーションを生み出す期待もあります。サイロ化の解消は、保有するデータの有効活用と企業価値の向上につながる点がメリットの1つです。
2.DX促進につながる
前述したDXの推進につながる点も、サイロ化解消のメリットです。部署ごとに異なるシステムを使うなど、データ連携が困難な仕組みとなっている場合には、全社で情報を統合してDXを進めようにも限界があります。
バラバラなシステムを全社で統一的なものに刷新することで、サイロ化を脱し、新たなデジタル技術の導入も容易になります。システムが統一されれば、運用するための教育・研修なども一本化が可能です。DX推進のみならず、業務効率の向上も期待できます。
DXに向けた取り組みは、1回やれば終了するものではありません。組織やシステム、データが再びサイロ化しないよう、市場環境やビジネスモデルの変化などにもあわせて、継続的な見直しが必要です。
3.顧客満足度が向上する
サイロ化の解消を通じて、購買関連のデータなど顧客に関する情報を一元的に扱えるようになれば、より顧客満足度の向上に資する施策の展開が可能です。顧客満足度が高まれば、取引の長期的な継続が期待でき、経営の安定につながります。
データやシステムの一元化により、作業の手間や従業員の負担を減らすことも可能です。それにより、顧客の要望への対応を迅速化できるメリットが生まれます。顧客満足度の高まりにより、自社の市場競争力の強化も図れます。
サイロ化を解消するためのポイント

サイロ化の解消が多くのメリットをもたらすことを、前項で論じてきました。では、解消はどのように行えばよいのでしょうか。ここからはそのポイントを解説していきます。
部門間の連携を図る
自社内の部署、部門が独立して施策を決め、情報を囲い込むところにサイロ化の問題点がありました。この問題を解消するためには、部門間の連携を図ることが重要です。
それぞれ独立して動いていた部署や部門を連携させるには、全社で共通の目標を設けることも一案です。共通の目標に向けて協力し合う雰囲気を作ることで、連携の進展が期待できます。各部門が全体最適を考えるようになれば、部分最適のサイロ化に陥る懸念は少なくなります。
全社的なプロジェクトを企画し、各部門から人を出してもらうなどのやり方も有効です。部署の枠を越えたジョブローテーション制度の導入、社内イベントの開催なども、よく使われる方法といえます。
統合型システムでデータを一元化する
ハード面からのアプローチでサイロ化を解消するには、統合型システムの導入が良策です。統合型システムを採用すると、勤怠管理や工数管理などが全社共通のシステムで対応できるようになり、データを一元化できます。
同じシステムを各部署で使え、他部署とのデータ連携も容易です。統合型システムの導入は、業務効率の改善や生産性向上にも役立ちます。
人事管理システム「ADPS」で人事業務を効率化

カシオヒューマンシステムズ株式会社が提供する人事管理システム「ADPS」は、1990年の誕生以来、累計5,000社を超える導入実績を重ねてきました。勤怠管理や給与計算はもとより、採用管理や各種申請など、幅広く人事業務をカバーできます。
単体からグループ連結までの多様化した運用形態にフレキシブルに対応できるため、多数のグループ会社がある場合に発生しがちなサイロ化の解消にも好適です。
ADPSは、各企業の業務プロセスにあわせたカスタマイズも可能です。システムの柔軟性が高いため、運用を大きく変えることなく導入できます。
複雑な業務手順をフロー化し、視覚的にわかりやすいオペレーションを採用している点も特徴です。担当の従業員にかかる運用負荷を軽減でき、業務の効率化が進められます。
製品の詳細を知りたい方はこちら
まとめ

サイロ化とは、社内の各部門でデータなどの連携が取れていない状態のことです。組織やシステム、データのサイロ化が起こると、業務効率の悪化や意思決定の遅れによる市場競争力の低下などのデメリットが生じます。
サイロ化を解消するためには、部門間の連携を図ったり、統合型システムを導入してデータを一元化したりする施策が有効です。統合型システムを導入すれば、従業員の運用負荷の軽減による生産性向上なども期待できます。サイロ化の防止や解消が課題になっているのなら、統合型システムの導入をご検討ください。
製品の詳細を知りたい方はこちら
カシオヒューマンシステムズコラム編集チームです。
人事業務に関するソリューションを長年ご提供してきた知見を踏まえ、
定期的に「人事部の皆様に必ず今後の業務に役立つ情報」を紹介しています。