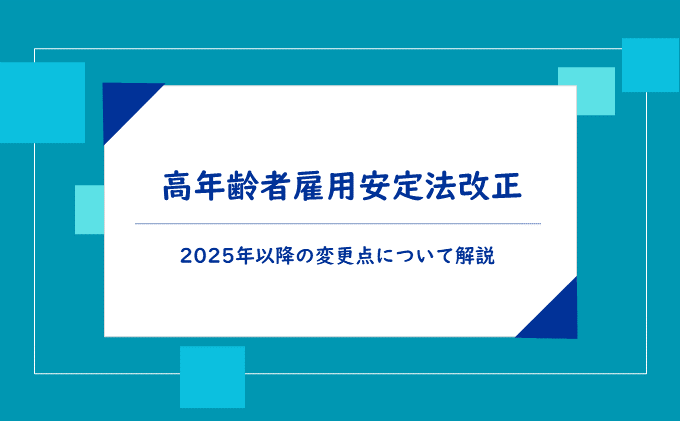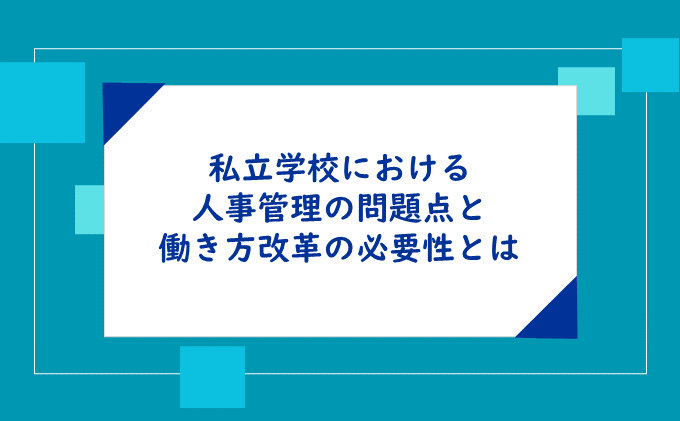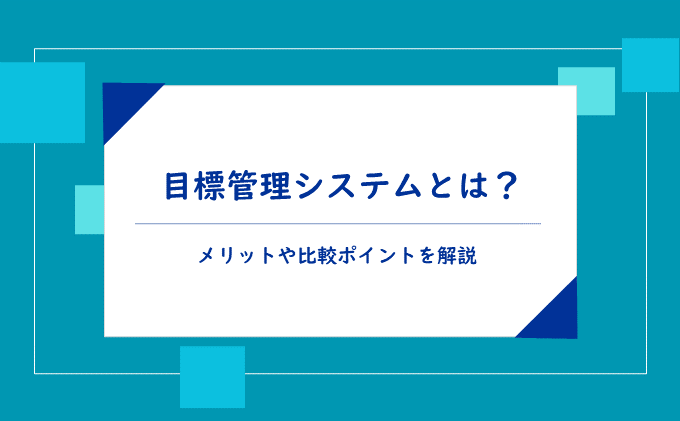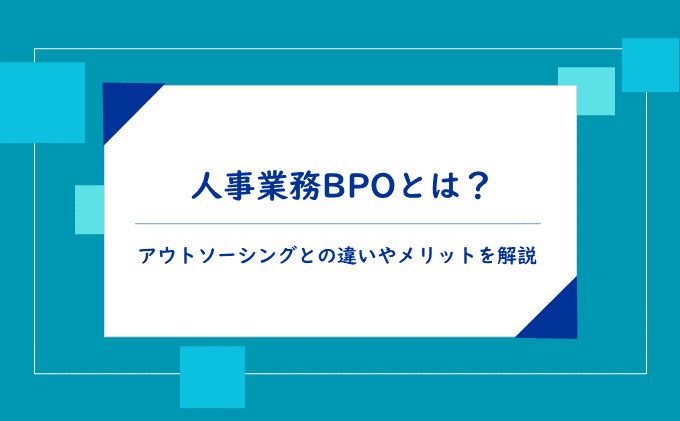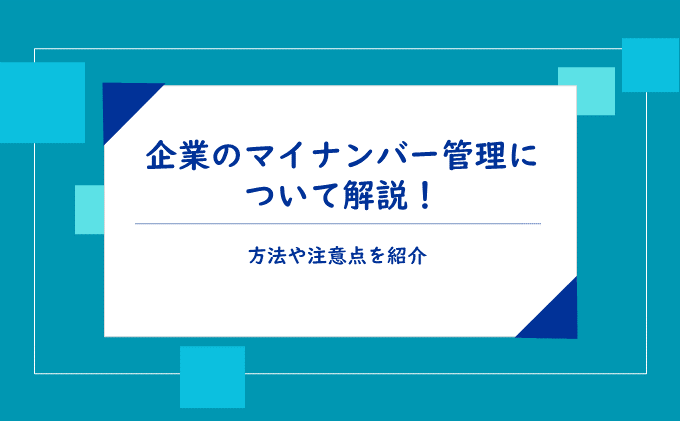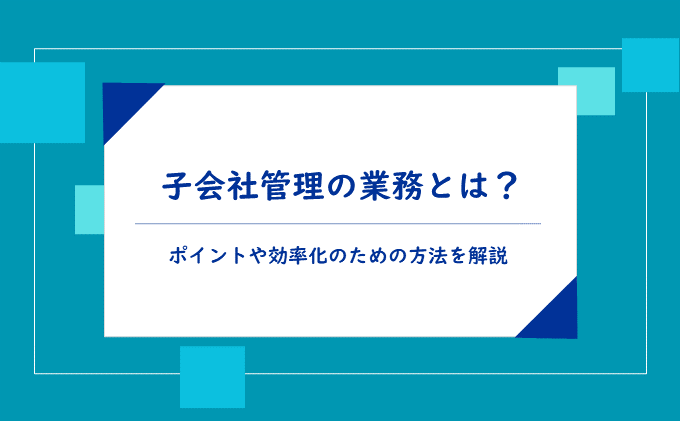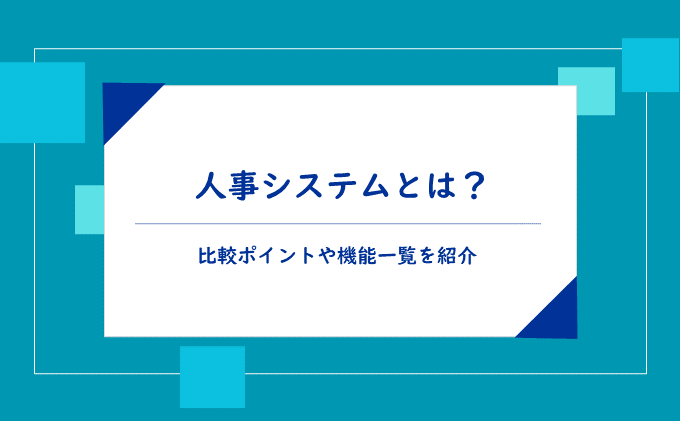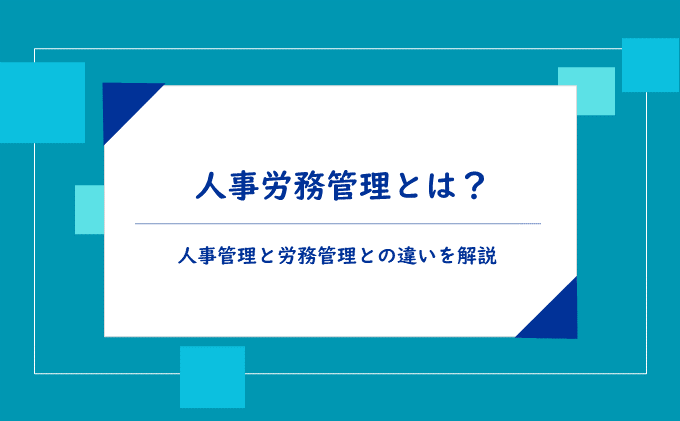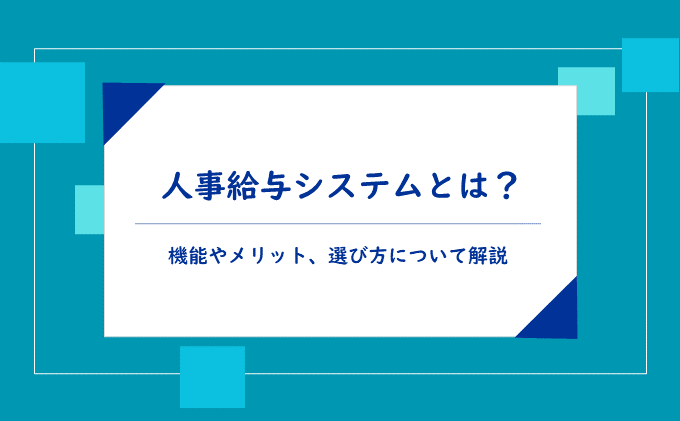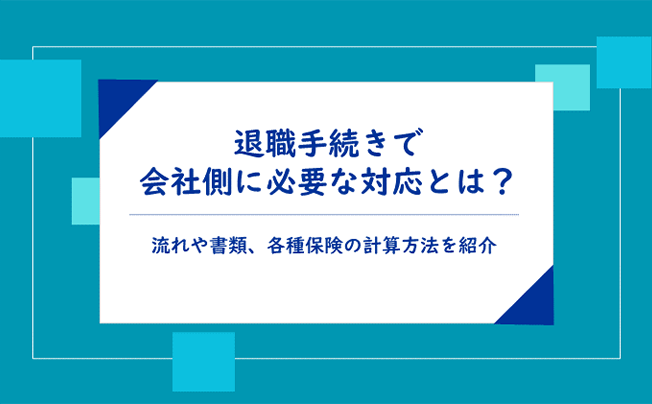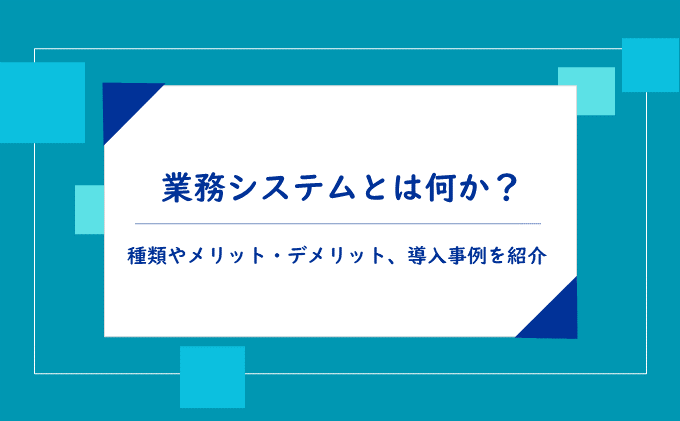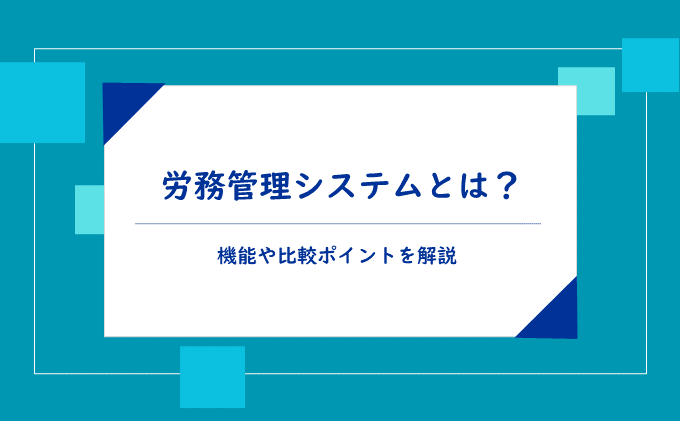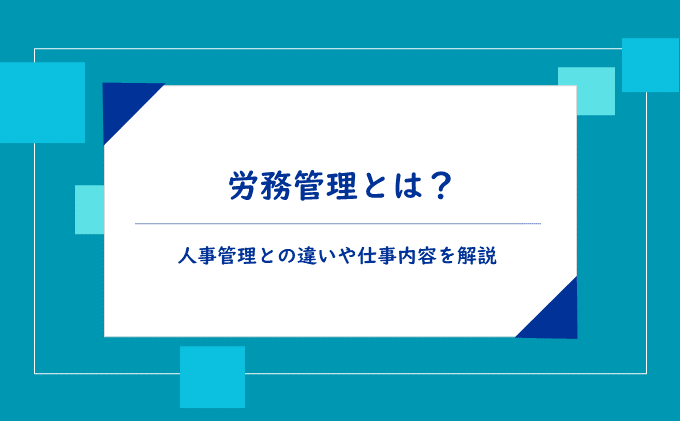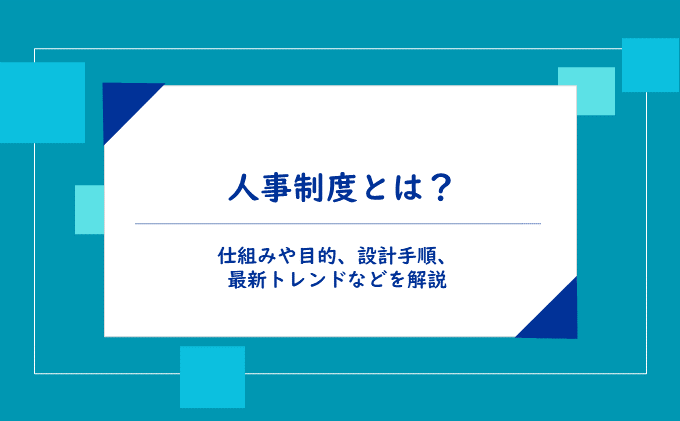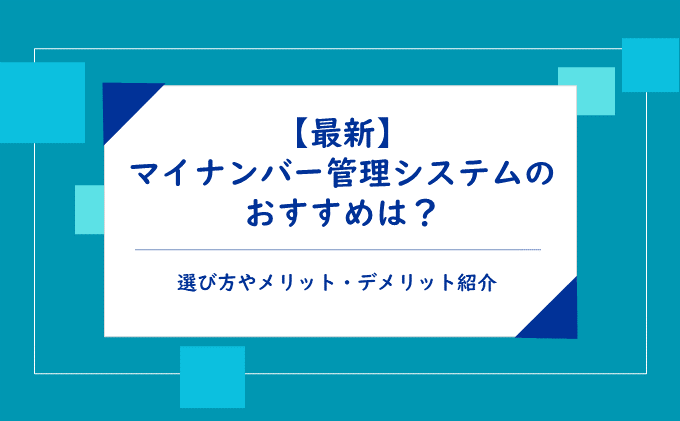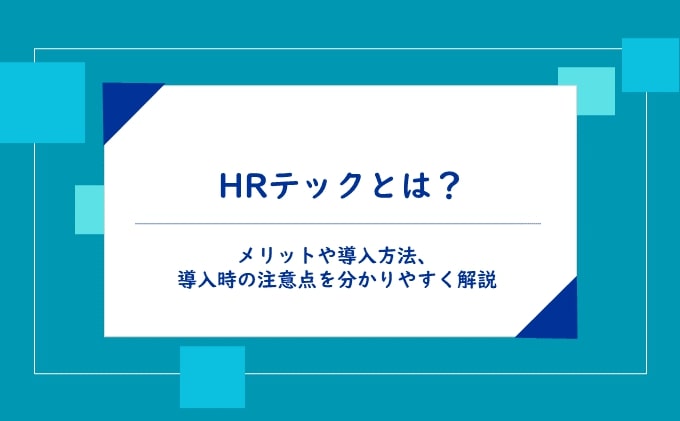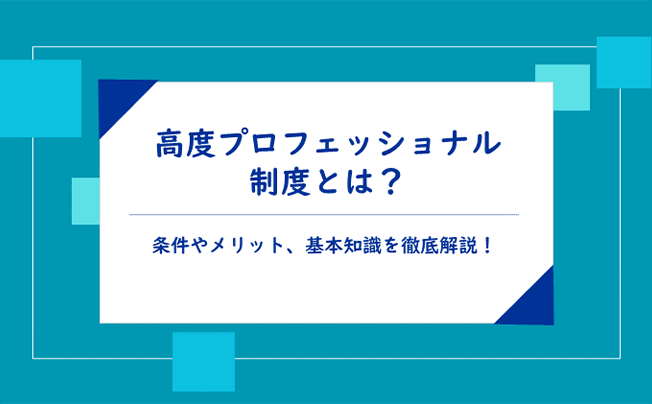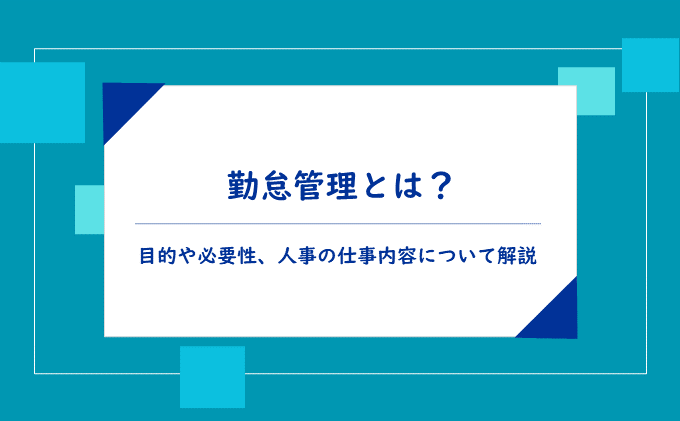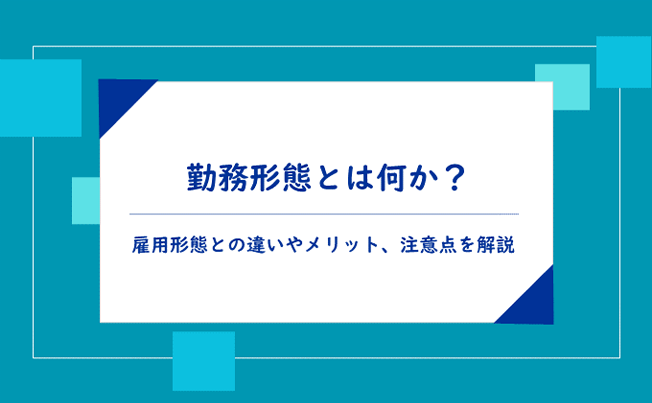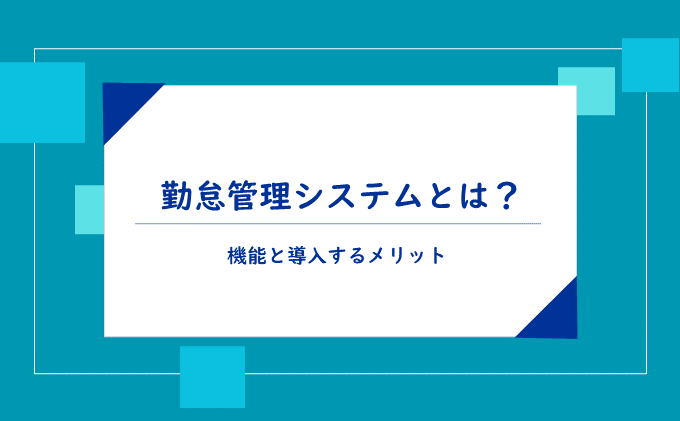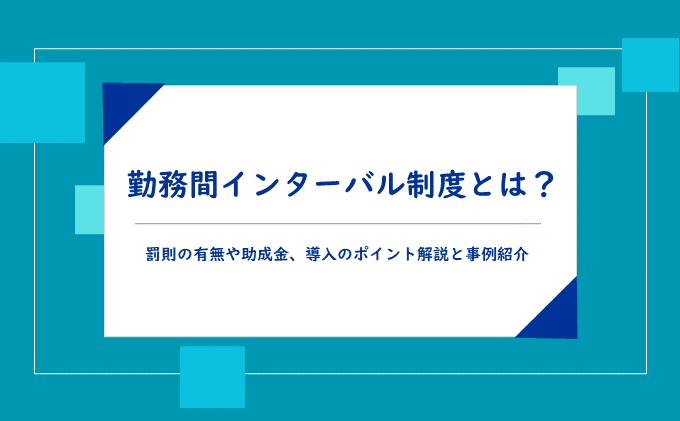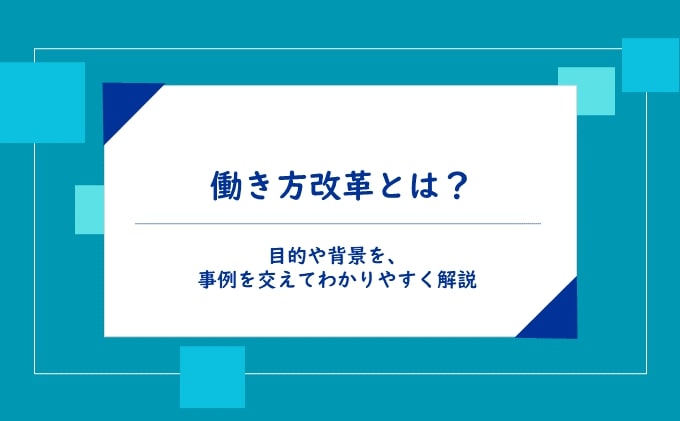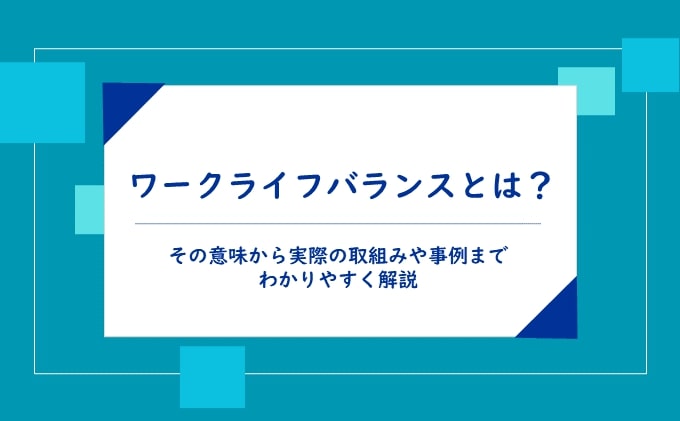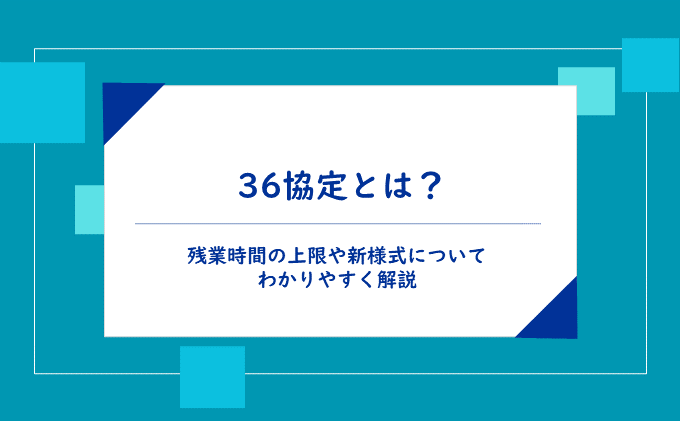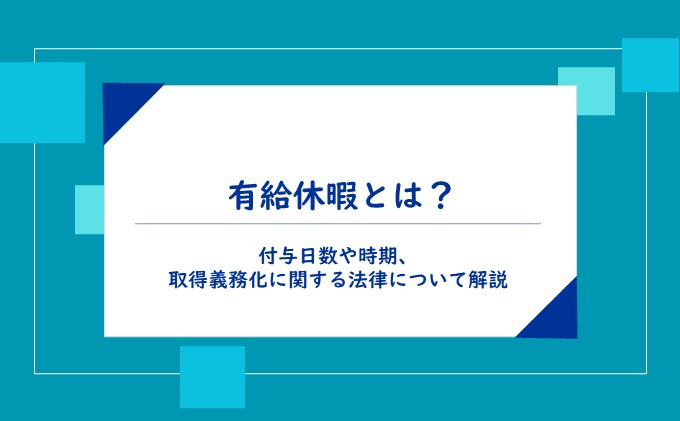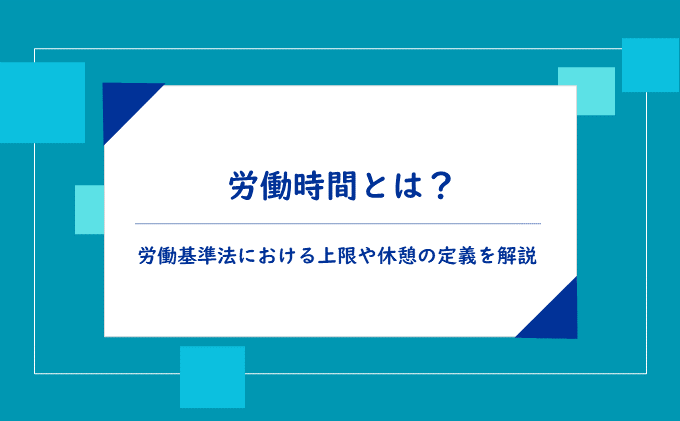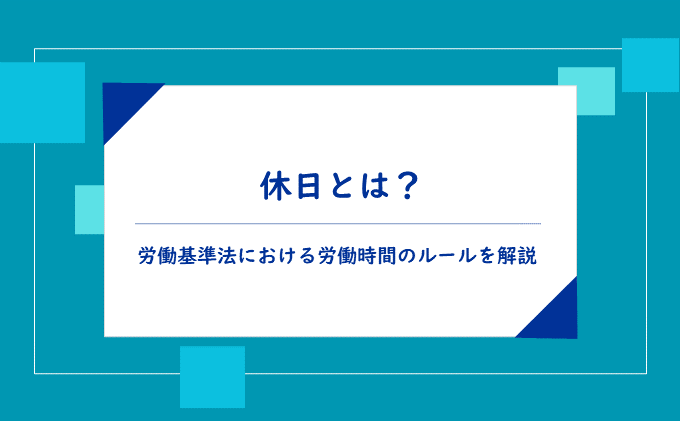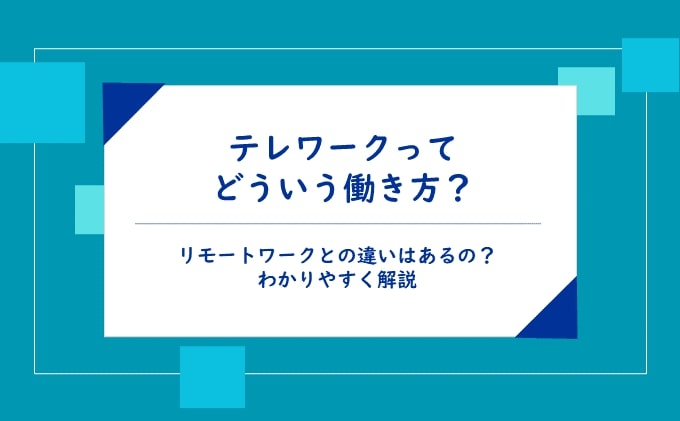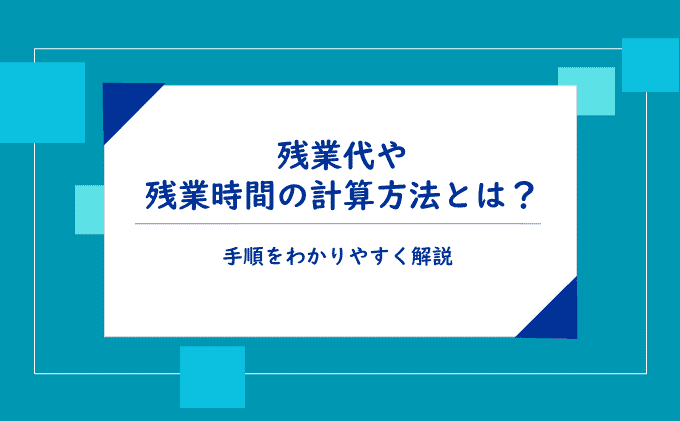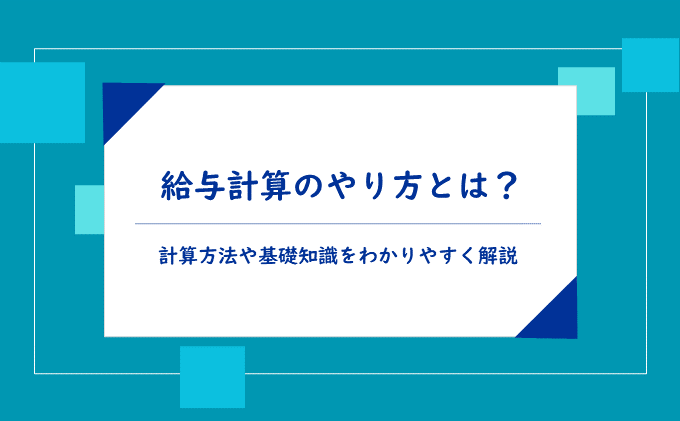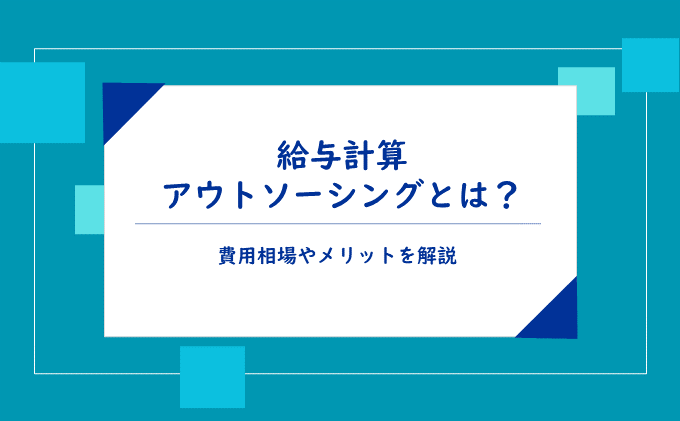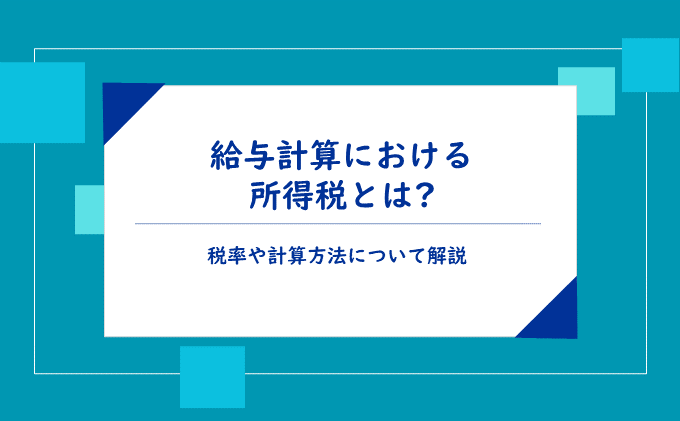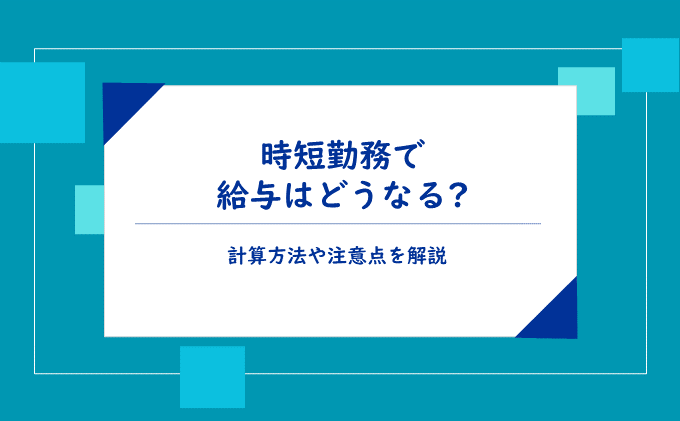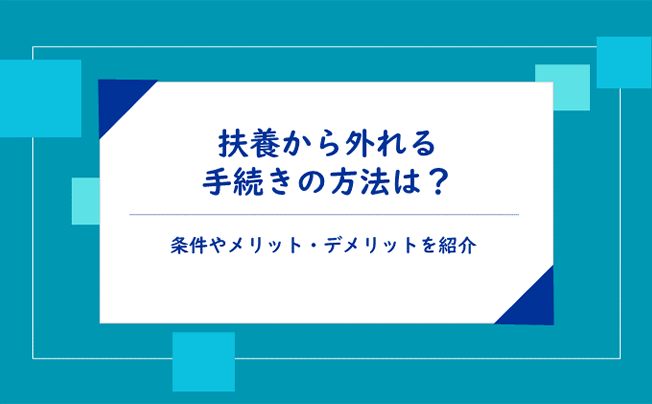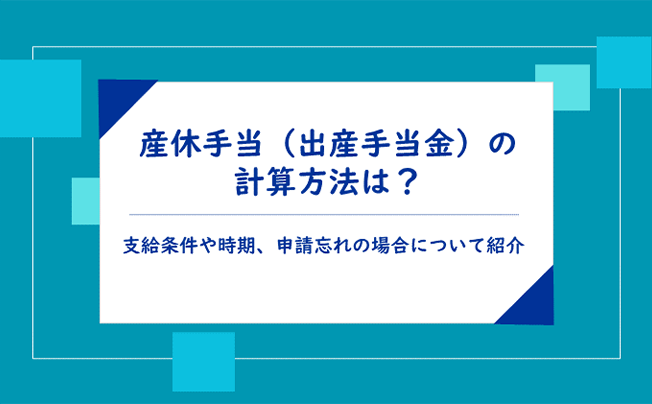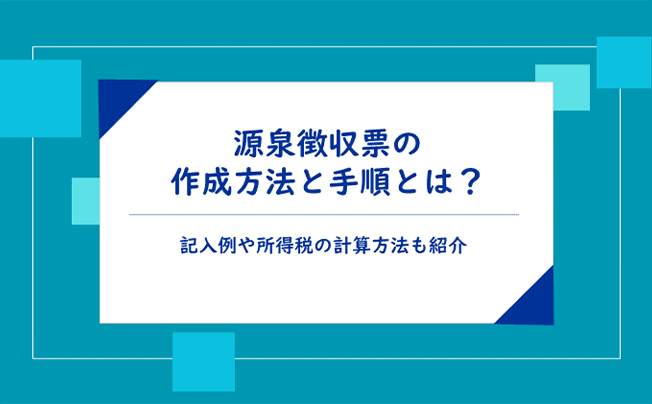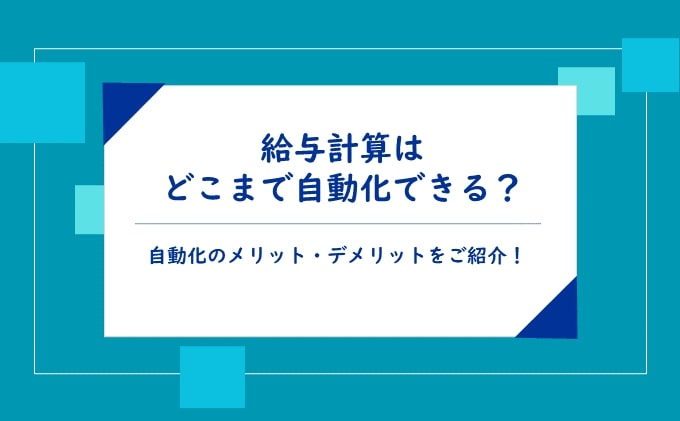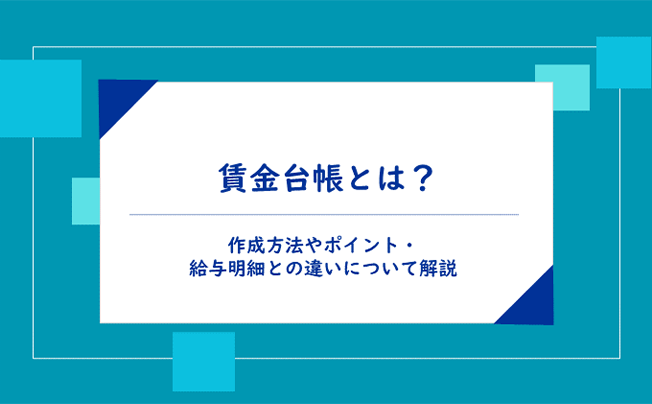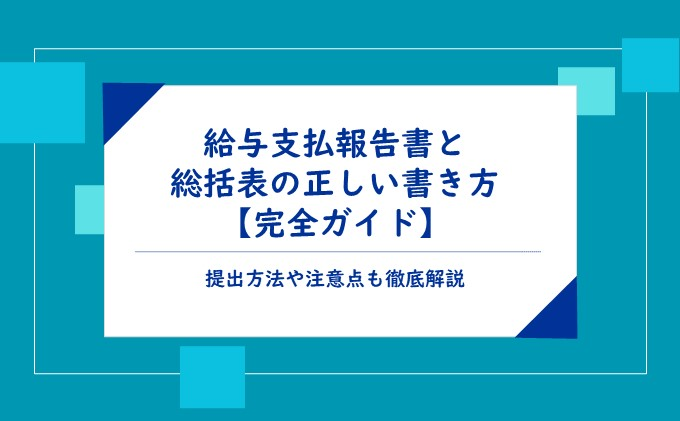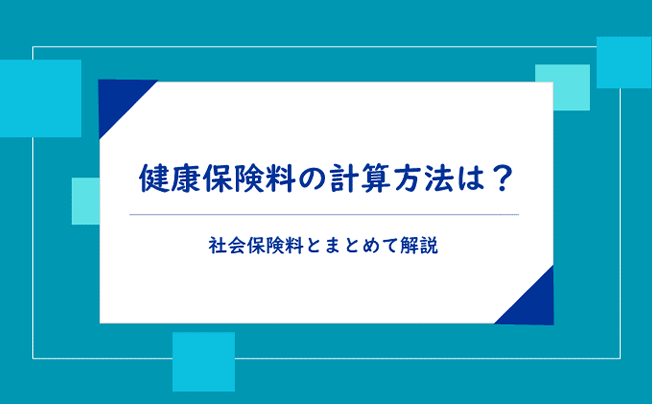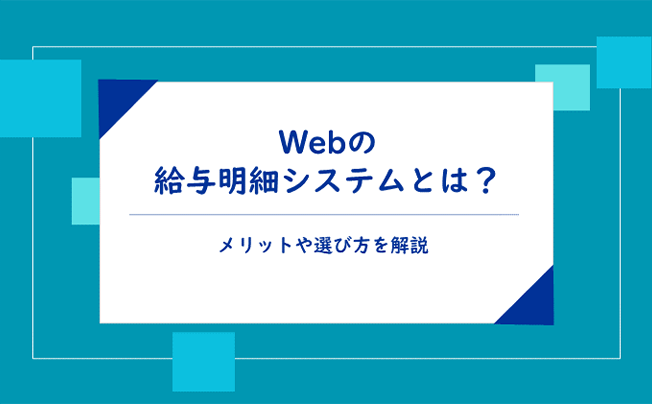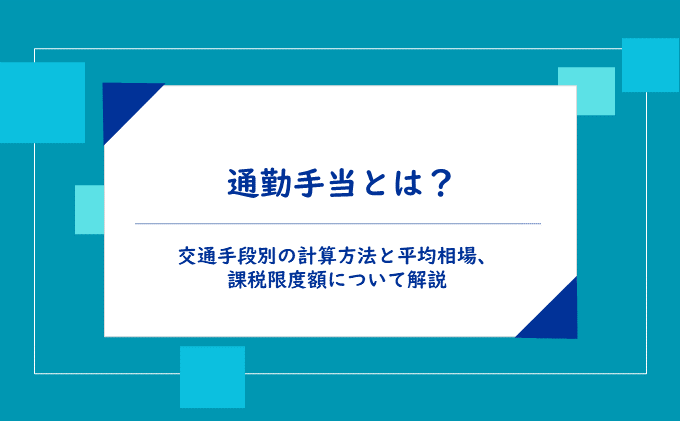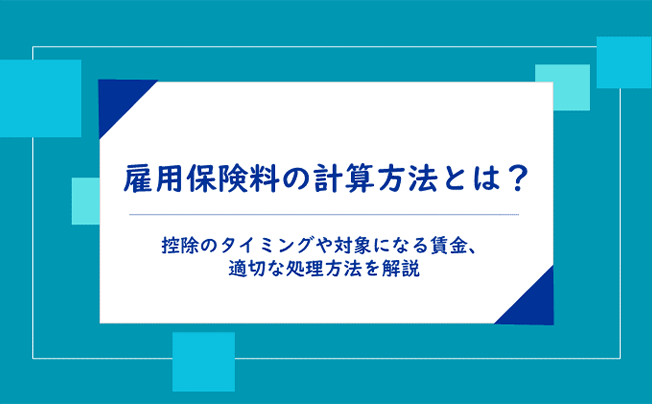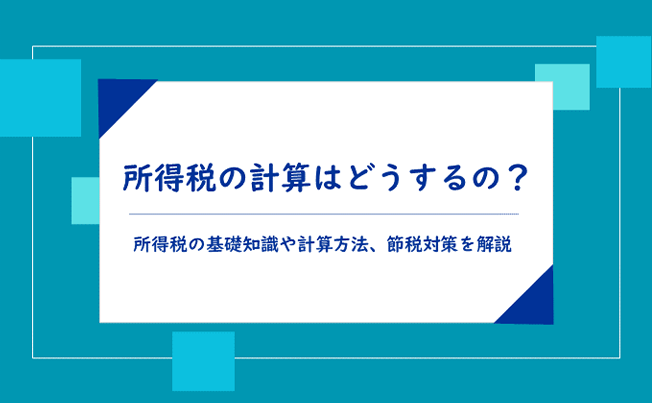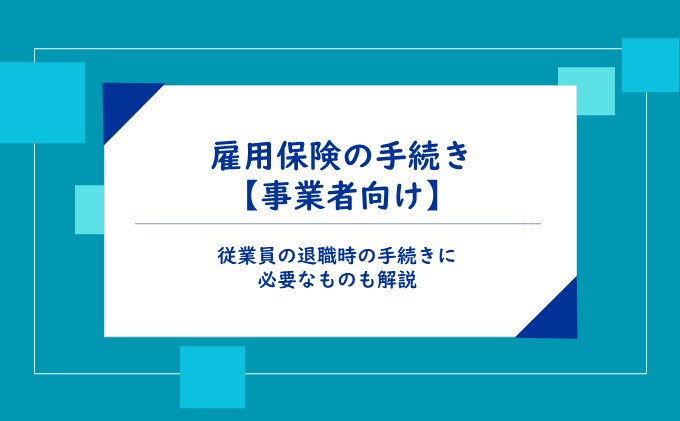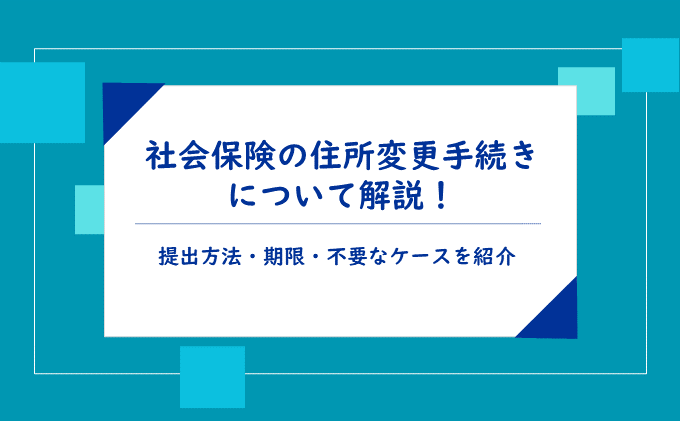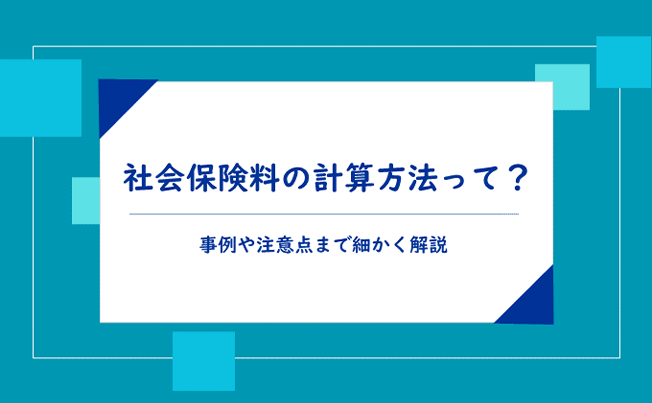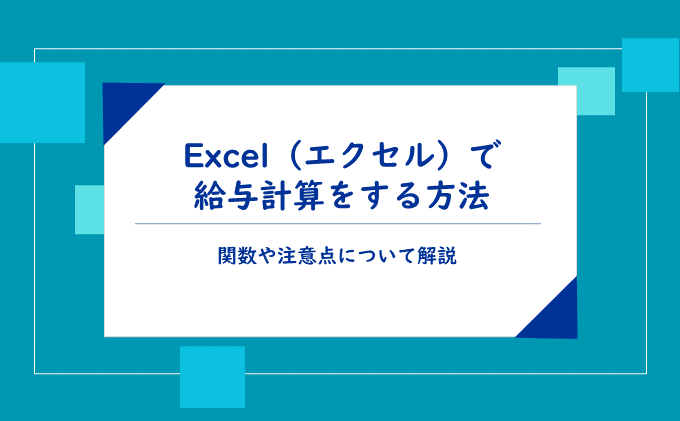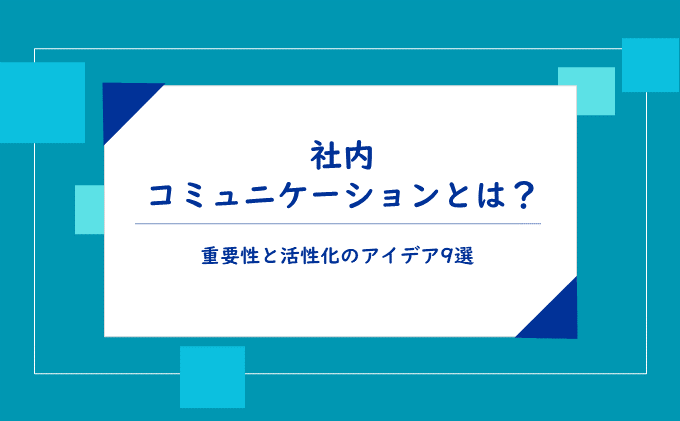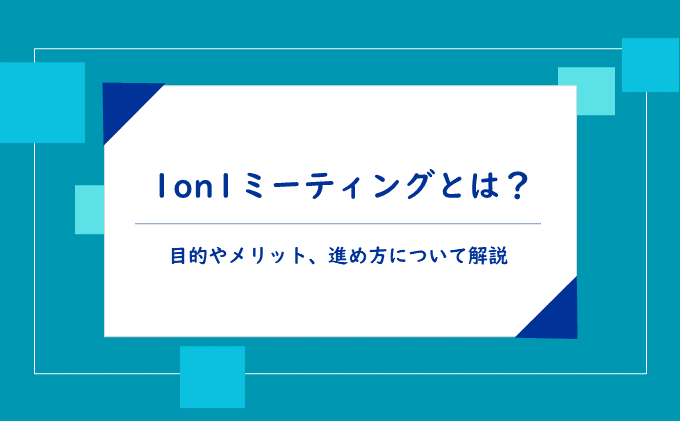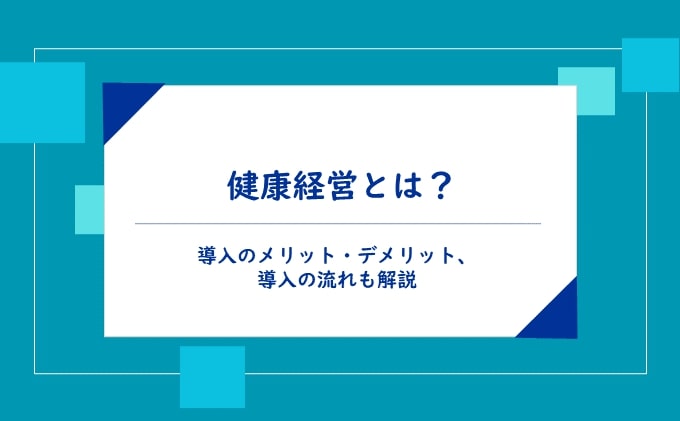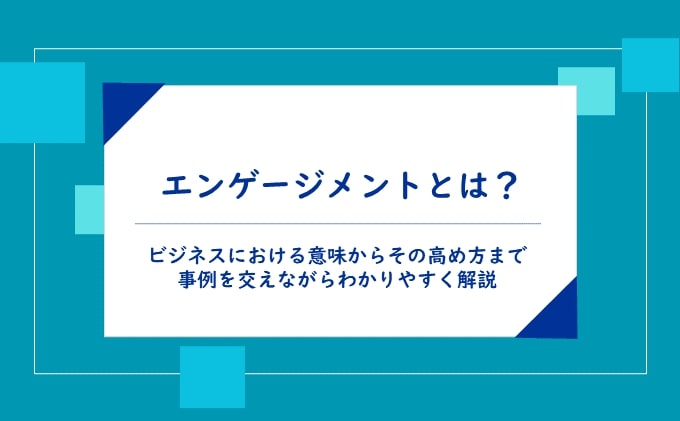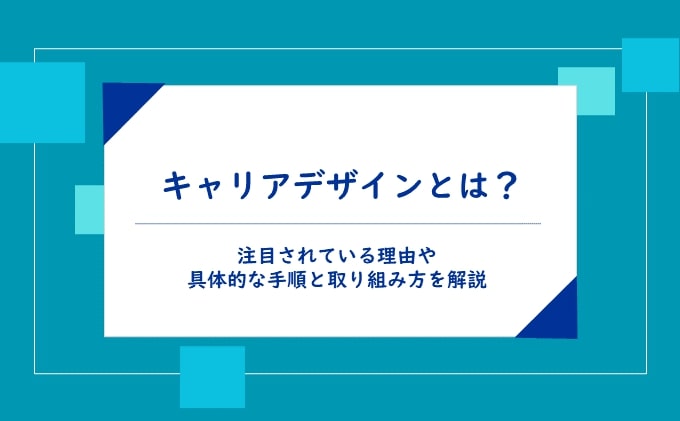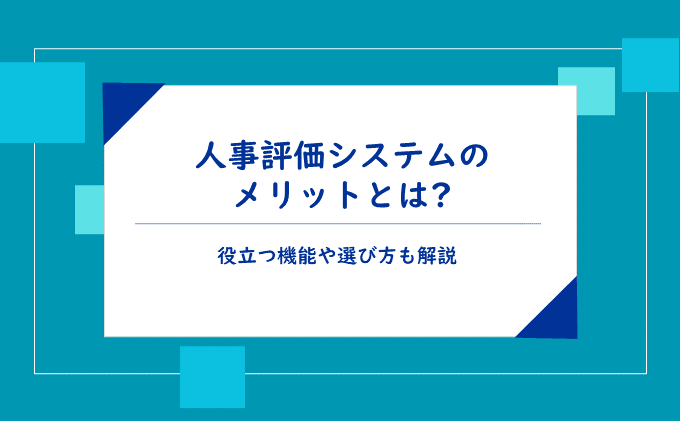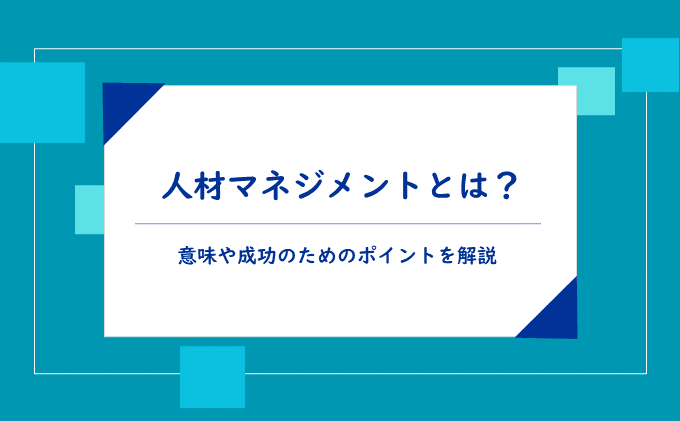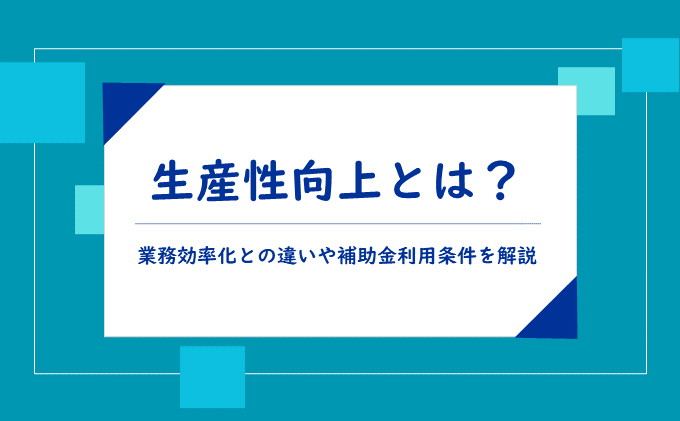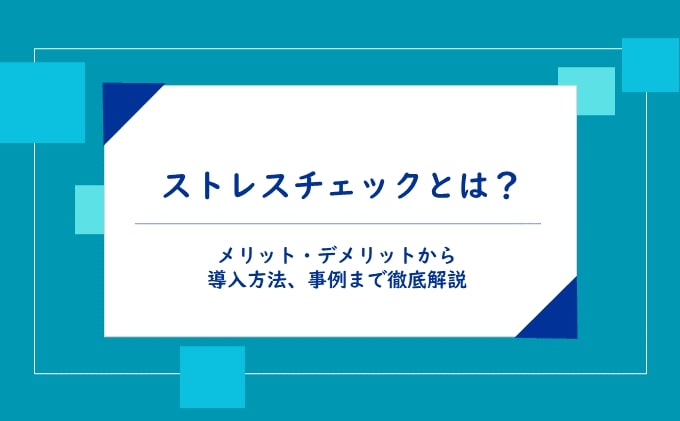労災保険料の計算方法│令和6年度(2024年度)の保険料率と注意点
2025.05.16
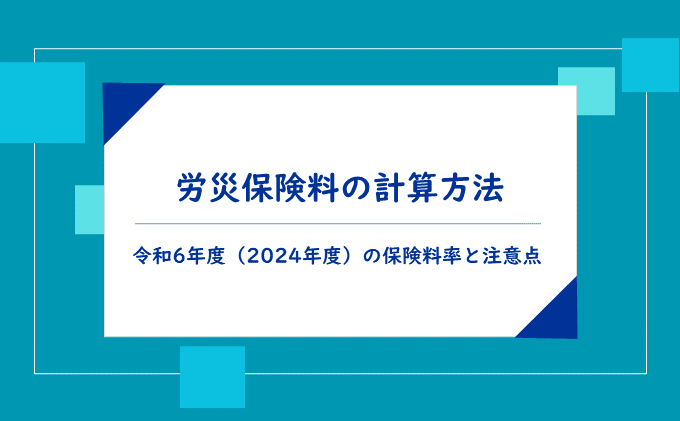
令和6年度(2024年度)に、労働者災害補償保険の料率が変更されました。料率の改定は原則として、3年ごとに行われます。本記事では労災保険制度の概要や賃金総額の算出方法に加え、正しく保険料を計算するための注意点などについて幅広く解説します。
目次
製品の詳細を知りたい方はこちら
「労災保険料」とは

業務中の事故や災害などでけがをして、働けなくなってしまった場合に補償してくれる制度が労災保険です。正式には「労働者災害補償保険」といい、労働者災害補償保険法で内容が規定されています。
業務に起因する事故などが原因で障害になったり、病気になったりした場合もこの保険で補償されます。仕事中だけでなく、仕事に向かう通勤途中の事故や災害などによるけがなども、補償の対象です。
労働者災害補償保険法の第1条には、法の目的として「疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等」も含まれると記されています。けがや病気で働けなくなった人への補償だけでなく、広範にわたる内容を持つ法律です。
労災保険による給付には、以下の7種類があります。
- 療養(補償)給付
- 休業(補償)給付
- 傷病(補償)年金
- 障害(補償)給付
- 遺族(補償)給付
- 葬祭料(葬祭給付)
- 介護(補償)給付
給付等の名称で、業務災害に対するものは「補償」が付き、通勤災害に関するものには付きません。
労災保険と雇用保険をあわせて、「労働保険」と呼ぶこともあります。雇用保険は、失業した人の生活の安定や、企業の雇用の安定を図るための給付を行うものです。
従業員が1人でもいれば、労災保険に加入する義務が生じます。パートやアルバイトなど雇用形態にかかわらず、従業員はすべて労災保険に加入させなければなりません。労災保険料は企業が全額を支払うもので、従業員の負担分はありません。
労災保険の保険料は、業種によって異なります。保険料の算出に使われるのが、業種ごとに定められる保険料率です。料率は、危険度の高い業種ほど高くなるよう設定されています。
料率は原則として3年ごとに見直されており、令和6年度(2024年度)が変更の年でした。料率の決め方は「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」で、労災保険の給付などに要する費用の予想額を勘案し、将来にわたって労災保険事業に関する財政を均衡させ得る水準とすることが求められています。
料率の決定に際して考慮される要素は、以下のようなものです。同法では、これらを考慮して「厚生労働大臣が定める」としています。
- 労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害
- 複数業務要因災害及び通勤災害にかかる災害率
- 二次健康診断等給付に要した費用の額
- 社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容
- その他の事情
参考:e-Gov 法令検索「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」
【令和6年度(2024年度)】労災保険率の変更点

労災保険の保険料率は、原則として3年ごとに改定されています。令和6年度(2024年度)の改定で、令和6年(2024年)4月以降の料率は以下の表の通りになりました。
危険度の高い業種ほど料率が高く設定されており、令和6年度(2024年度)の改定後、最も高いのは「金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く)又は石炭鉱業」の1000分の88、ついで高いのは「林業」の1000分の52でした。
「原油又は天然ガス鉱業」「通信業、放送業、新聞業又は出版業」「金融業、保険業又は不動産業」などは料率が低く、いずれも1000分の2.5となっています。
| 分類 | 事業の種類 | 労災保険率 | |
|---|---|---|---|
| 新 | 旧 | ||
| 林業 | 林業 | 52/1,000 | 60/1,000 |
| 漁業 | 海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く) | 18/1,000 | 18/1,000 |
| 定置網漁業又は海面魚類養殖業 | 37/1,000 | 38/1,000 | |
| 金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く)又は石炭鉱業 | 88/1,000 | 88/1,000 | |
| 石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 | 13/1,000 | 16/1,000 | |
| 原油又は天然ガス鉱業 | 2.5/1,000 | 2.5/1,000 | |
| 採石業 | 37/1,000 | 49/1,000 | |
| その他の鉱業 | 26/1,000 | 26/1,000 | |
| 建設事業 | 水力発電施設、ずい道等新設事業 | 34/1,000 | 62/1,000 |
| 道路新設事業 | 11/1,000 | 11/1,000 | |
| 舗装工事業 | 9/1,000 | 9/1,000 | |
| 鉄道又は軌道新設事業 | 9/1,000 | 9/1,000 | |
| 建築事業(既設建築物設備工事業を除く) | 9.5/1,000 | 9.5/1,000 | |
| 既設建築物設備工事業 | 12/1,000 | 12/1,000 | |
| 機械装置の組立て又は据付けの事業 | 6/1,000 | 6.5/1,000 | |
| その他の建設事業 | 15/1,000 | 15/1,000 | |
| 製造業 | 食料品製造業 | 5.5/1,000 | 6/1,000 |
| 繊維工業又は繊維製品製造業 | 4/1,000 | 4/1,000 | |
| 木材又は木製品製造業 | 13/1,000 | 14/1,000 | |
| パルプ又は紙製造業 | 7/1,000 | 6.5/1,000 | |
| 印刷又は製本業 | 3.5/1,000 | 3.5/1,000 | |
| 化学工業 | 4.5/1,000 | 4.5/1,000 | |
| ガラス又はセメント製造業 | 6/1,000 | 6/1,000 | |
| コンクリート製造業 | 13/1,000 | 13/1,000 | |
| 陶磁器製品製造業 | 17/1,000 | 18/1,000 | |
| その他の窯業又は土石製品製造業 | 23/1,000 | 26/1,000 | |
| 金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く) | 6.5/1,000 | 6.5/1,000 | |
| 非鉄金属精錬業 | 7/1,000 | 7/1,000 | |
| 金属材料品製造業(鋳物業を除く) | 5/1,000 | 5.5/1,000 | |
| 鋳物業 | 16/1,000 | 16/1,000 | |
| 金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめっき業を除く) | 9/1,000 | 10/1,000 | |
| 洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業(めっき業を除く) | 6.5/1,000 | 6.5/1,000 | |
| めっき業 | 6.5/1,000 | 7/1,000 | |
| 機械器具製造業(電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く) | 5/1,000 | 5/1,000 | |
| 輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く) | 4/1,000 | 4/1,000 | |
| 船舶製造又は修理業 | 23/1,000 | 23/1,000 | |
| 計量器、光学機械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く) | 2.5/1,000 | 2.5/1,000 | |
| その他の製造業 | 6/1,000 | 6.5/1,000 | |
| 運輸業 | 交通運輸事業 | 4/1,000 | 4/1,000 |
| 貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く) | 8.5/1,000 | 9/1,000 | |
| 港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く) | 9/1,000 | 9/1,000 | |
| 港湾荷役業 | 12/1,000 | 13/1,000 | |
| 電気、ガス、水道等 | 電気、ガス、水道又は熱供給の事業 | 3/1,000 | 3/1,000 |
| その他の事業 | 農業又は海面漁業以外の漁業 | 13/1,000 | 13/1,000 |
| 清掃、火葬又はと畜の事業 | 13/1,000 | 13/1,000 | |
| ビルメンテナンス業 | 6/1,000 | 5.5/1,000 | |
| 倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 | 6.5/1,000 | 6.5/1,000 | |
| 通信業、放送業、新聞業又は出版業 | 2.5/1,000 | 2.5/1,000 | |
| 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 | 3/1,000 | 3/1,000 | |
| 金融業、保険業又は不動産業 | 2.5/1,000 | 2.5/1,000 | |
| その他の各種事業 | 3/1,000 | 3/1,000 | |
| 船舶所有者の事業 | 42/1,000 | 47/1,000 | |
労災保険料の計算方法と計算例
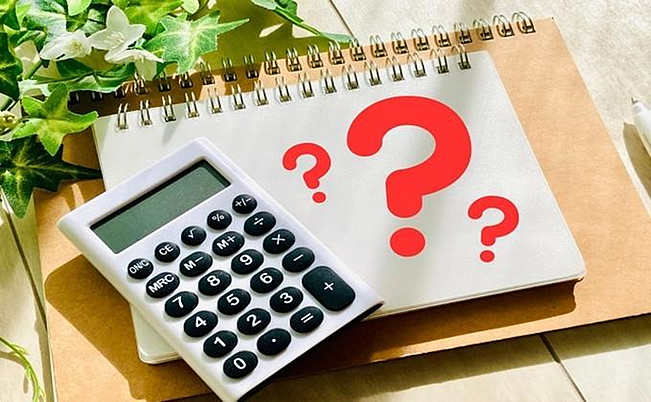
この項では、労災保険料の計算方法と計算例を示します。
労災保険料の計算方法
労災保険料は、「前年度1年間の全従業員の賃金総額 × 労災保険率」で計算されます。4月1日から3月31日までの1年間で、保険料を算出します。計算する際に注意が必要なのは、「賃金総額」に含まれるものと含まれないものがある点です。
賃金総額は、すべての従業員に支払った賃金の総額を指します。通勤手当や残業手当などの各種手当は含まれる一方、役員報酬などは含まれません。含まれるものとしては、以下のような項目があります。
- 基本給
- 賞与
- 通勤手当
- 残業手当
- 家族手当
- 住宅手当
- 扶養手当
- 単身赴任手当
含まれないものの代表的な例は、以下のとおりです。
- 役員報酬
- 退職金
- 出張旅費
- 結婚祝金
- 弔慰金
- 休業補償費
退職金は、退職時などに一時払いされる場合は賃金総額に含まれませんが、前払いで在職中の給与や賞与などに上乗せして支払われるものは含まれます。
労災保険料の計算例
日給制は、働いた日数に応じて給与が支払われる給与形態です。
ここでは具体的な数字を当てはめて、計算例を提示します。従業員が10人の小売業で、1人あたりの年間賃金見込額が360万円(毎月25万円、賞与が年間60万円)とした場合、企業が支払う労災保険料は以下のとおりです。
(10人 × 360万円) × 3/1000 = 10万8000円
前掲の表にあるように、小売業の労災保険率は1000分の3です。したがって、計算すると労災保険料は10万8000円となります。
労災保険料を計算する際の注意点

労災保険料の計算式そのものは単純ですが、計算する際には注意点もあります。主な注意点は、賃金総額を正しく見積もること、保険料は概算で納付するため前年度分の精算が必要となること、事業に適した保険率を使うことなどです。
以下で、各注意点について詳しく見ていきます。
賃金総額を正しく集計する
前述のとおり、賃金総額には含まれる項目と、そうでないものがあります。この仕分けを間違わないことが重要です。
賃金総額の計算対象となるのは、すべての従業員です。パートやアルバイト、契約社員、日雇い労働者といった雇用形態にかかわらず、計算に含める必要があります。
年度の途中で入社した従業員がいる場合も、同様に計算に含めます。総額を集計する前に、対象者の洗い出しをしっかりと行うことが大事です。
納付時は前年度との差額を精算する
保険料の納付は、前年度の確定保険料と、今年度の概算保険料をあわせて行います。「年度更新」方式と呼ばれるやり方です。
企業の多くは今年度分を確定できないため、年間賃金は見込額で計算します。そのため、前年度に概算で納付した保険料に対して、実際に納付すべき保険料との差額を精算しなくてはなりません。
納付が不足していた場合にはその分を加算し、超過だった場合には減算します。実務上は、保険料の納付は雇用保険料とあわせて行われることが多い点にも注意が必要です。
保険料は事業に適した保険率で算出する
前掲の表でもわかるように、労働保険率は業種によって大きく異なります。業種ごとに危険度に差があるためです。自社の事業に適した保険率で算出するよう注意してください。
自社で展開している事業が複数の業種にわたる場合は、事業ごとに保険料を算出します。1つの事業に対し、1つの料率が適用されるのが原則です。
労災保険法における業種の捉え方は、労働基準法や労働安全衛生法など他の労働関係法とは異なる部分があることも要注意です。
建設業では、工事や建築の現場と事務所で、それぞれ別個に保険料を算出します。現場と事務所とでは危険度が違うため、別々の事業として届け出るという特殊性があるためです。
派遣社員や出向社員の扱いに気を付ける
派遣社員の保険料は、原籍となる企業が支払うのが原則です。派遣社員の場合、他社から自社に派遣されているのであれば、他社が計算して納付します。
自社から他社に従業員を派遣している場合は、自社の計算に含めます。派遣していることは同じでも、業種が異なれば保険料率が違ってくることもあり得る点には注意が必要です。
出向社員の場合は、出向先が保険料を負担します。派遣社員とは扱いが異なるため、間違いがないよう気を付けてください。
労災保険料の申告・納付方法

ここでは労災保険料の申告と納付の方法について解説します。主なポイントは、以下の4項目です。
- 納付時期と期限
- 延納・分割が認められるケース
- 増加概算保険料が必要となる場合
- 具体的な納付方法
いずれも実務上重要なポイントです。
労災保険料の納付期限
労働保険料の納付時期は、原則として6月1日から7月10日までの間です。多くの企業では、この期間に労災保険料と雇用保険料をあわせて、「労働保険料」として支払います。
1年度分を概算で納付しておき、賃金総額の確定後に精算を行う年度更新方式です。年度更新では、今年度分の保険料の概算支払いと、前年度分の概算支払い分と確定分の差額の精算を行います。
6月1日や7月10日が土日に当たる場合などは、開始と終了の日が1~2日後ずれするため注意が必要です。納付は都道府県労働局か労働基準監督署、あるいは銀行などの金融機関で行います。
延納・分割方法
労働保険料は、以下の条件を満たす場合には延納・分割納付が認められています。
- 概算保険料が40万円以上(労働保険料のみの場合は20万円以上)
- 労働保険事務組合に労働保険事務を委託している
延納・分割できるタイミングは3期に分かれており、原則として第1期は7月10日まで、第2期は10月31日まで、第3期は翌年1月31日までです。労働保険事務組合に委託している場合は、第2期と第3期の納期限が2週間延長されます。
事業が10月1日以降に成立した場合は、延納・分割は認められません。労働保険事務組合とは、労働保険に関する事務処理を企業側に代わって行うことのできる、厚生労働大臣の認可を受けた団体です。
増加概算保険料の要件
業容の拡大などで従業員数が大幅に増え、年度中に賃金総額の見込みが当初概算の2倍以上になるなど、一定の要件にかかる場合は、増加概算保険料の支払いが必要になります。
増加概算保険料が必要となるのは、以下の2つをともに満たすケースです。
- 賃金総額の見込額が当初の申告より2倍以上となる
- 概算保険料として申告済みの額より13万円以上増加する
2つの要件に当てはまった場合は、増加した日から30日以内に増加概算保険料申告書の提出と、増加分の納付が必要です。
納付の流れ
保険料納付の流れは、以下の通りです。
- 前年度分の保険料を確定し、支払い済みの概算保険料との差額を計算
- 今年度分の労働保険料を概算
- 前年度分の差額と今年度分の概算額を合算して申告、納付
前年度分の保険料の確定は、3月31日までの賃金が対象です。「月末締め、翌月20日支払い」の締日を設定している企業であれば、4月20日に支払われる賃金までが計算範囲に含まれます。概算保険料との差額は、不足が出ていれば概算保険料にプラスして、支払い超過であったならその分をマイナスします。
今年度分の概算保険料は、前年度と大きな違いが出ないと見込まれる場合は、前年度の確定保険料と同額です。具体的には、前年度の2分の1から2倍の間に収まると見積もられる場合です。年度中に大きく増えるとわかった場合は、前述の増加概算保険料を申告、納付します。
労働保険料の申告は、「労働保険概算・確定保険料申告書」に記入して行います。申告書の提出は都道府県労働局や労働基準監督署、金融機関などを訪れるやり方のほか、e-Govによる電子申請も可能です。
e-Govから電子申請した場合は、保険料も電子納付が行えます。金融機関での申告は、納付する金額がない場合には受け付けられないため、注意が必要です。
申告、納付が期限内に行われなかった場合は、追徴金が課せられる可能性があります。申告、納付は期限内に、確実に行いましょう。
人事管理システム「ADPS」が人事業務の効率化を実現

複雑で間違いの許されない労働保険料の計算を効率的に進めるには、人事システムの導入がカギとなり得ます。カシオヒューマンシステムズ株式会社が提供する「ADPS(アドプス)」は、1990年の登場以来、累計5000社を超える導入実績を持つ人事管理システムです。
シンプルでわかりやすいインターフェースを備え、労働保険に初めて携わる担当者からベテラン従業員まで、安心して使える点が特徴です。労働保険に関連する事務だけでなく、人事、給与、就業管理などさまざまな業務をトータルでサポートします。
製品の詳細を知りたい方はこちら
まとめ

令和6年度(2024年度)に、労災保険料の料率が改定されました。企業は毎年、労災保険料を計算して申告、納付する必要があります。賃金総額の算出など手順は煩雑で、納期限も決まっていることから担当者には大きな負荷がかかりがちです。
労働保険関連に代表される、手間のかかる事務処理には人事システムの導入が適しています。業務効率を向上させ、担当者をより生産性の高い業務にあてられます。事務処理負担にお悩みなら、システム化によるバックオフィス部門の構造改革を検討してみてはいかがでしょうか。
製品の詳細を知りたい方はこちら
カシオヒューマンシステムズコラム編集チームです。
人事業務に関するソリューションを長年ご提供してきた知見を踏まえ、
定期的に「人事部の皆様に必ず今後の業務に役立つ情報」を紹介しています。