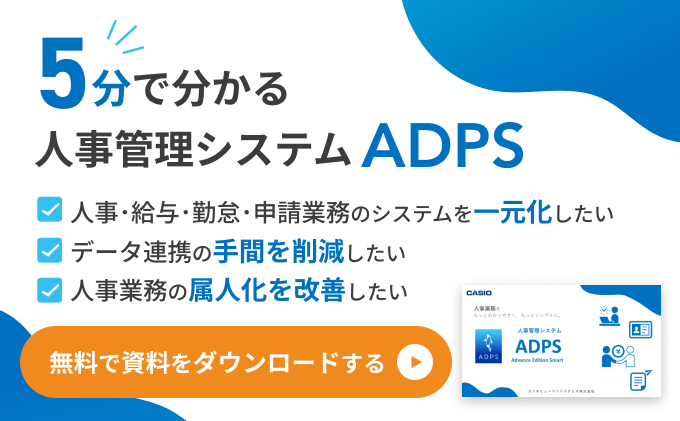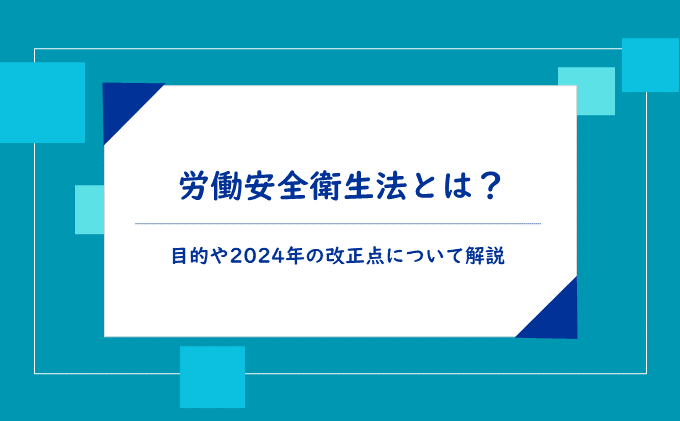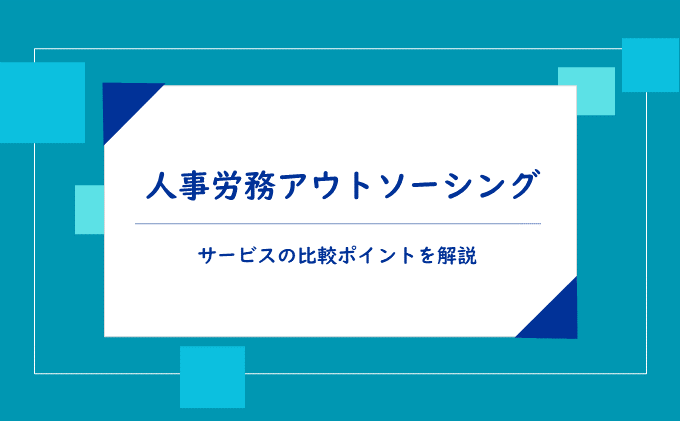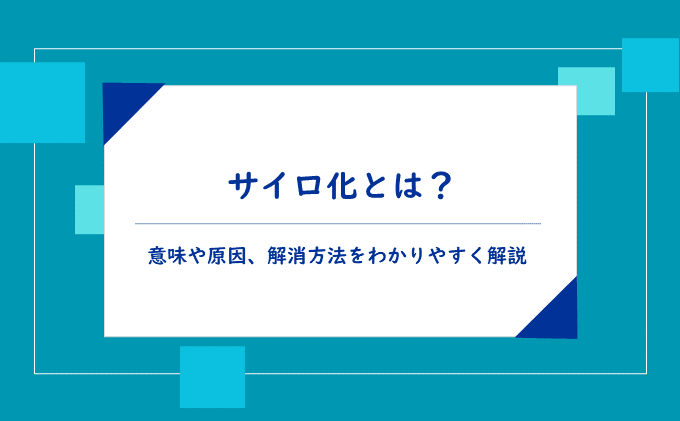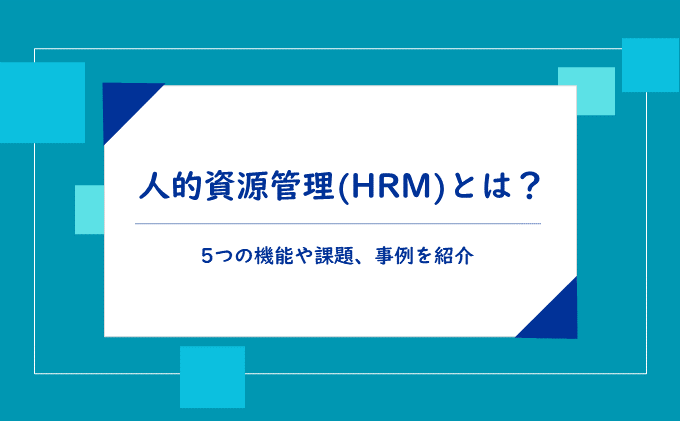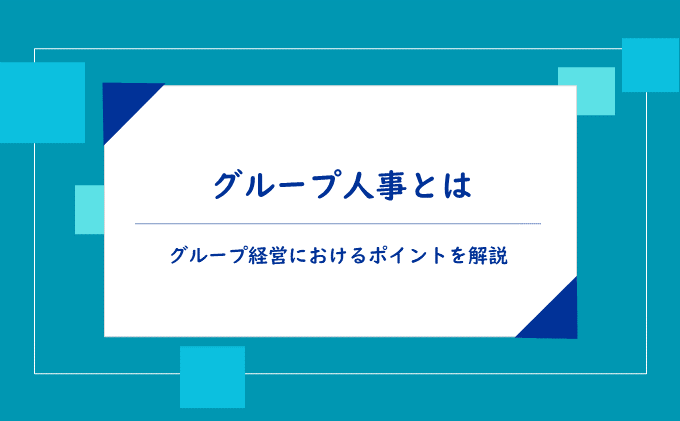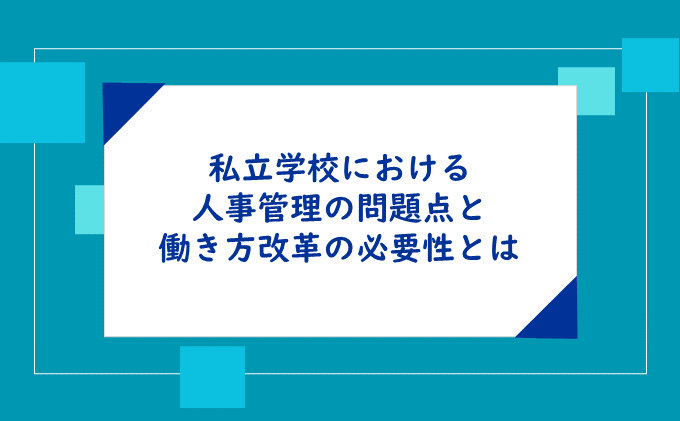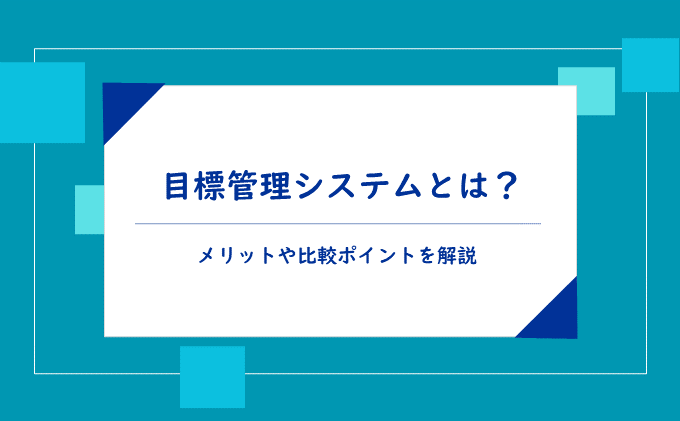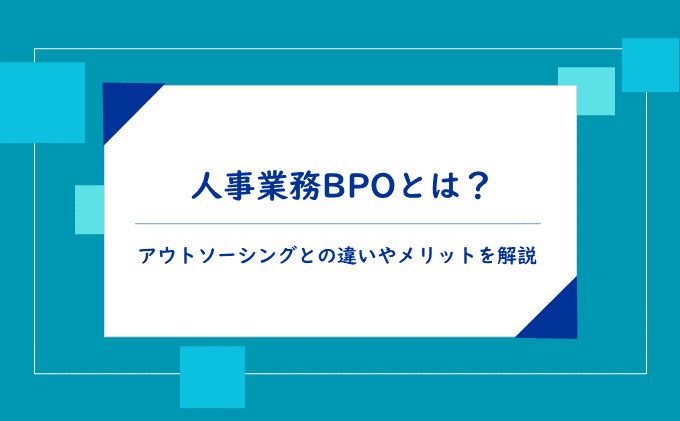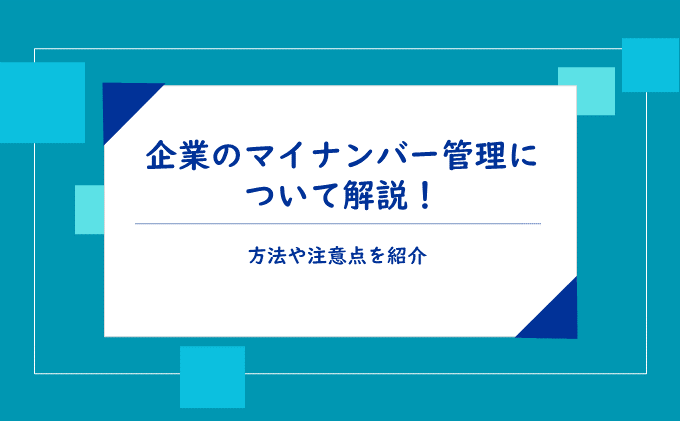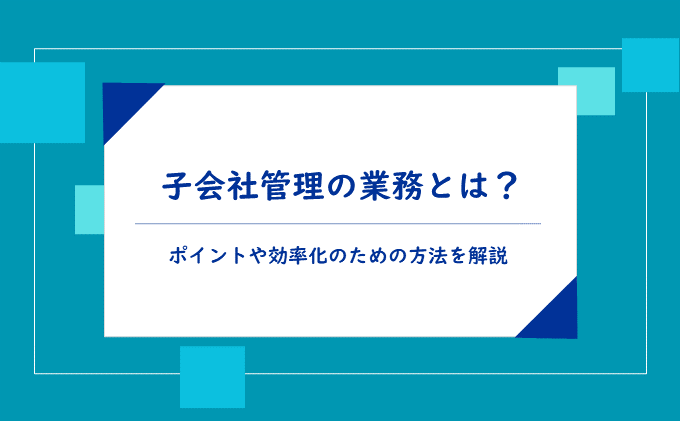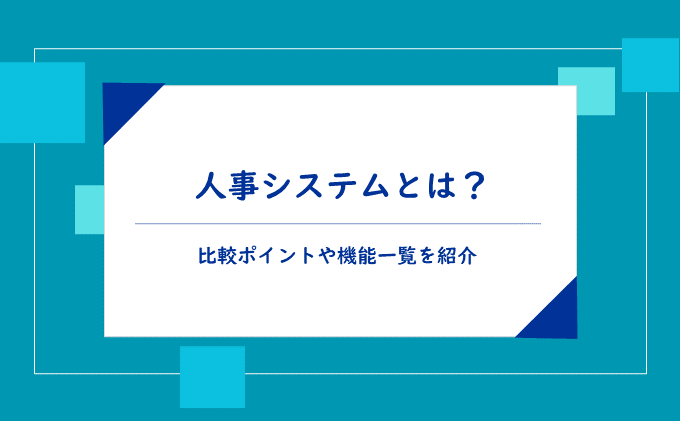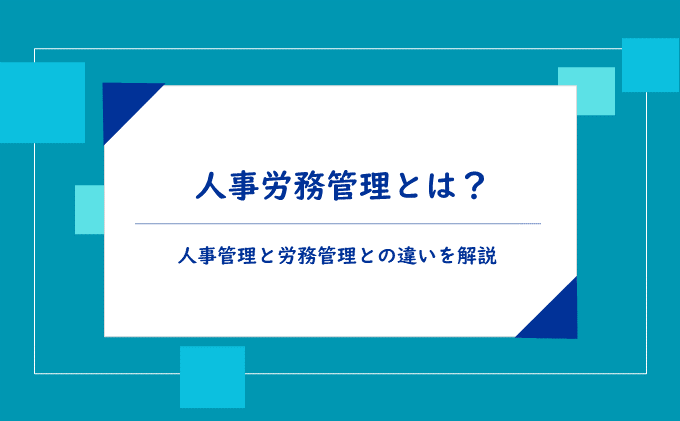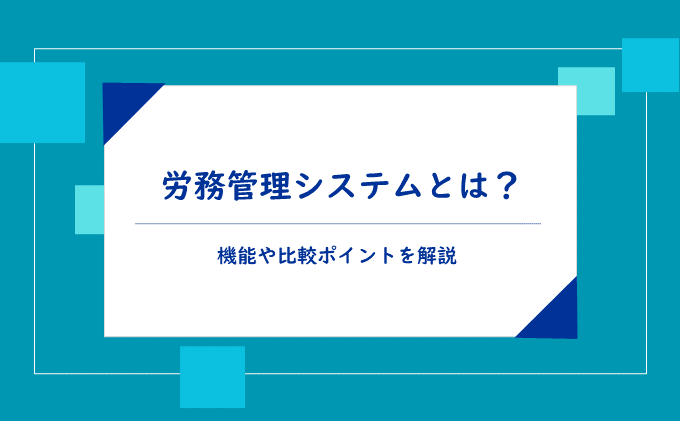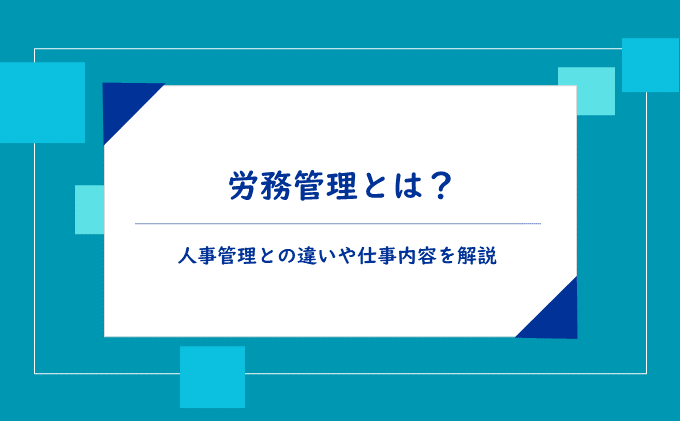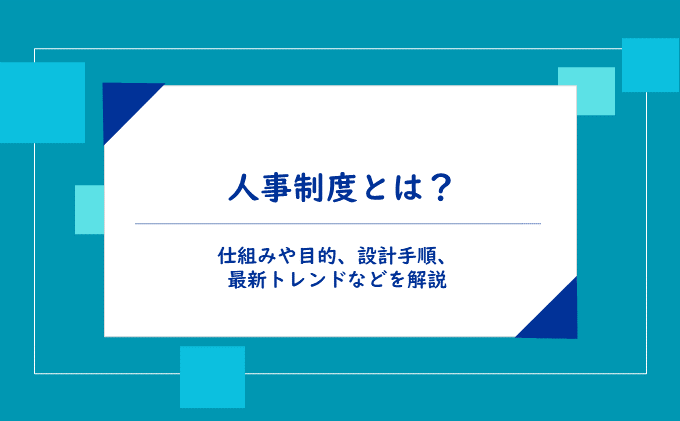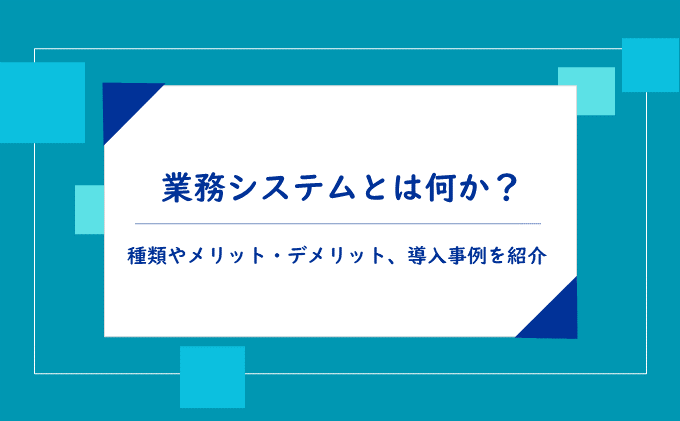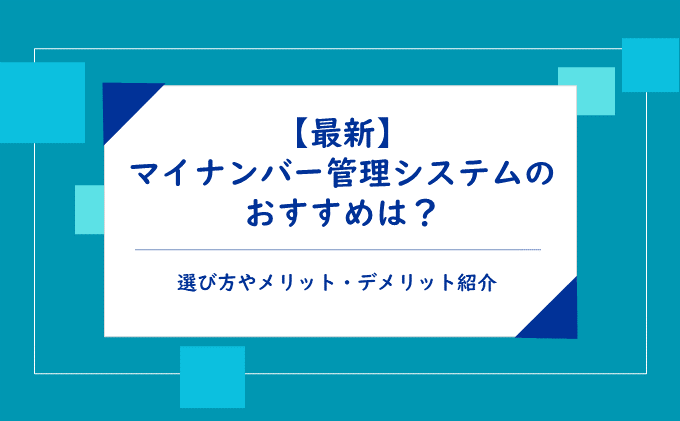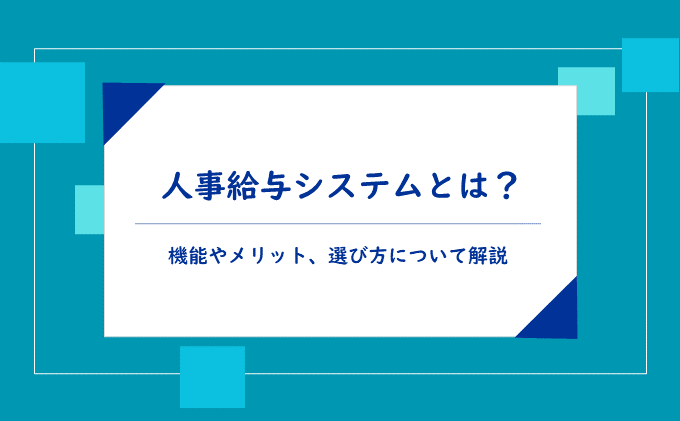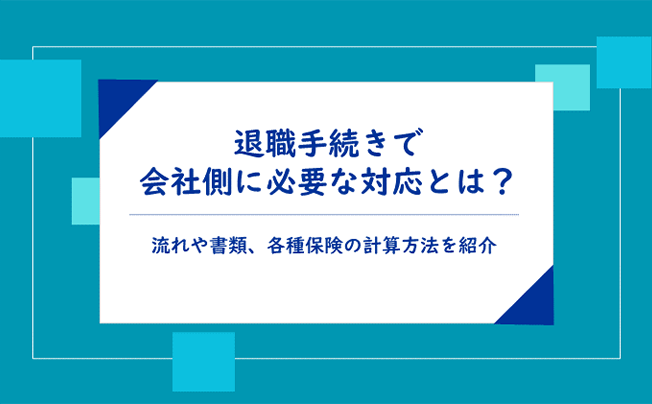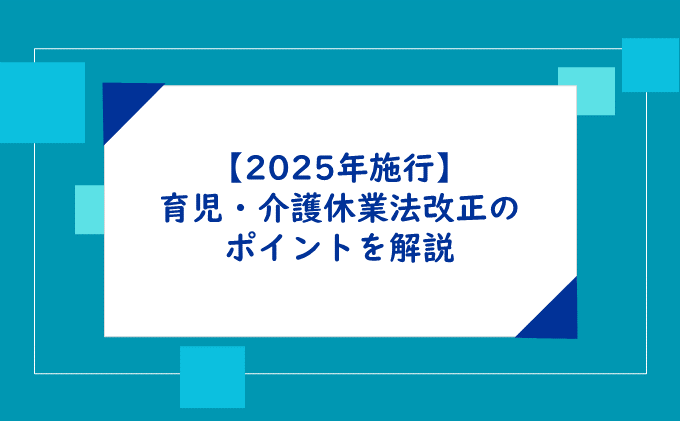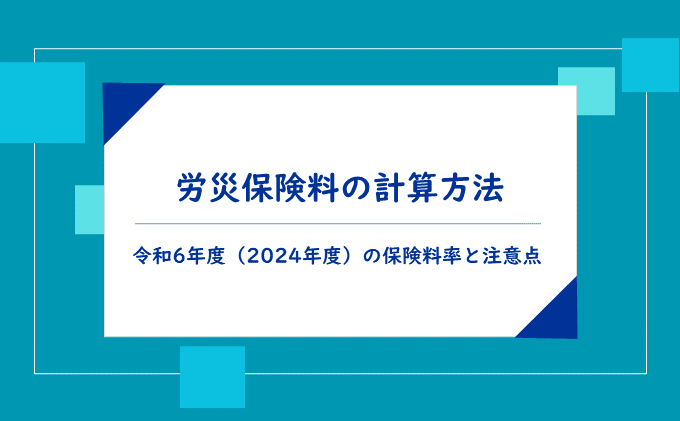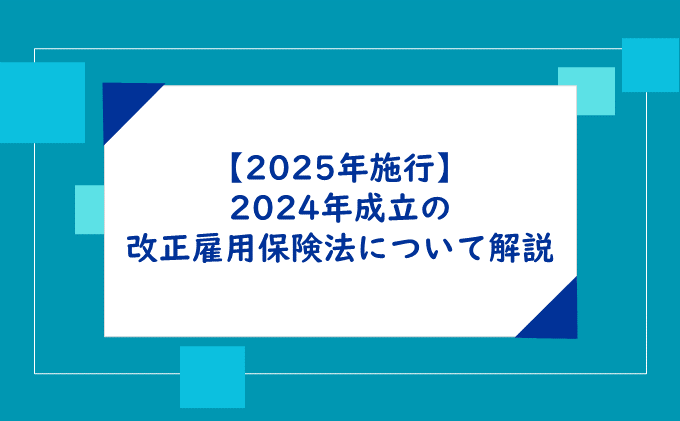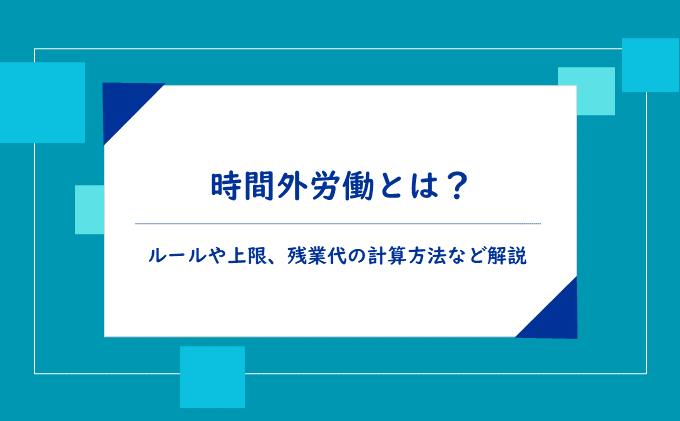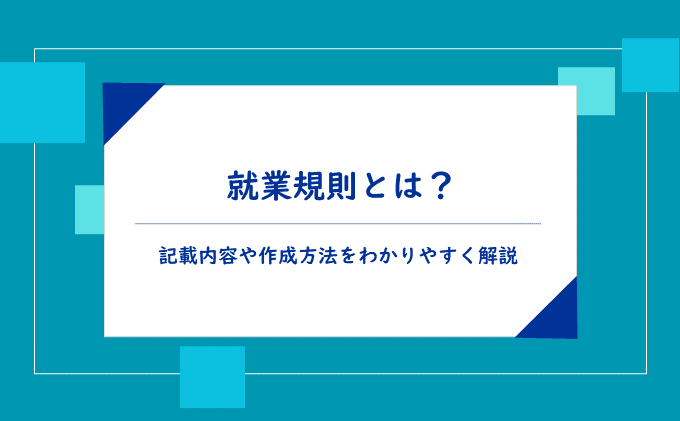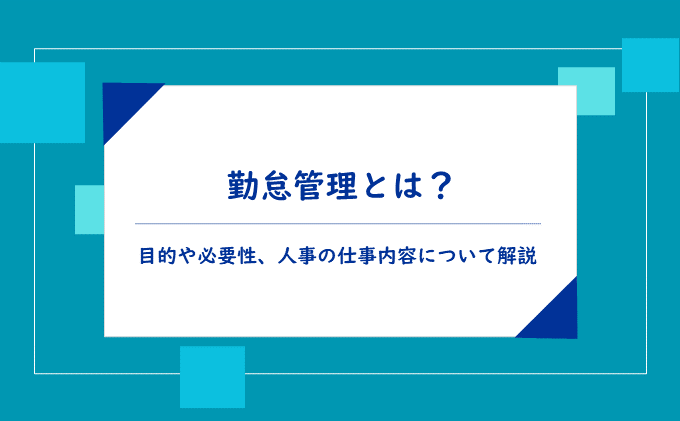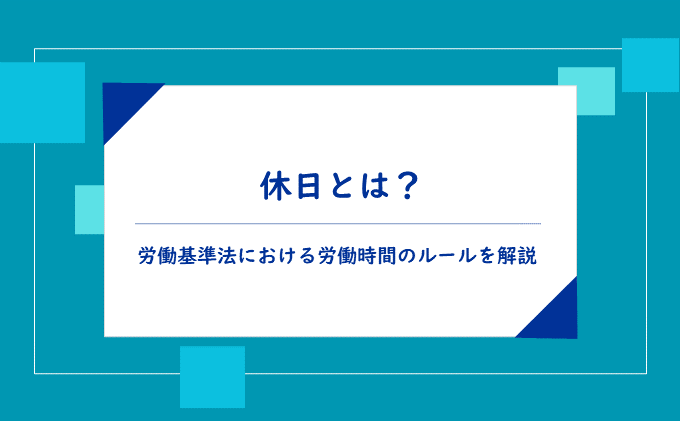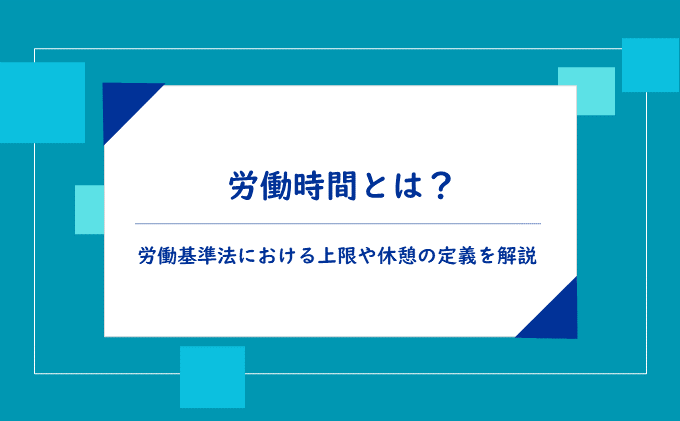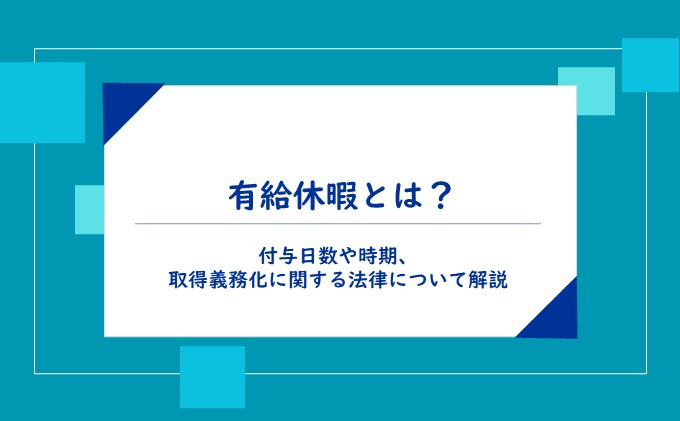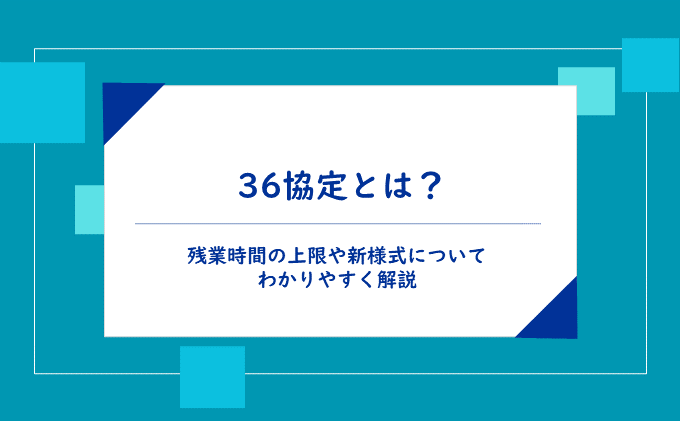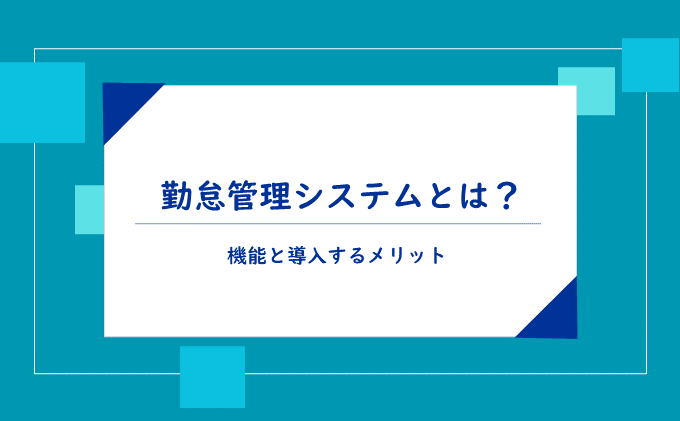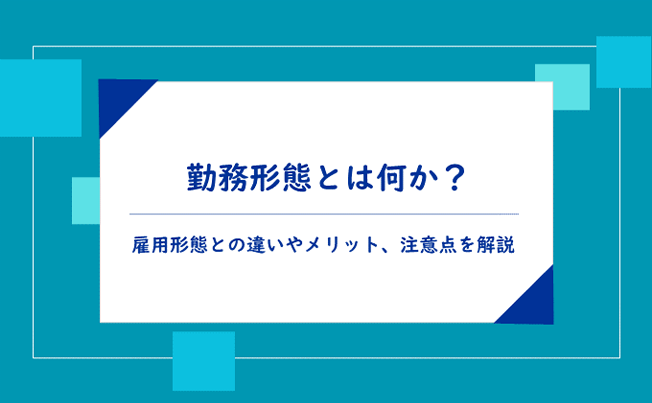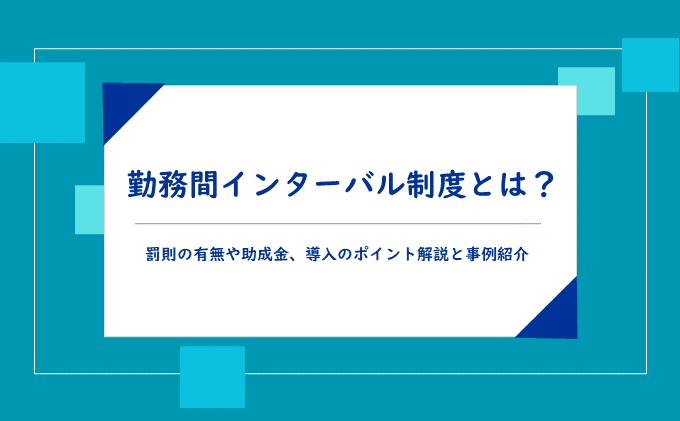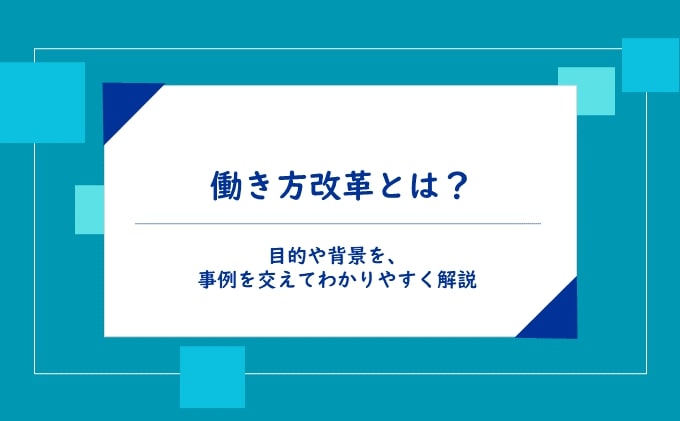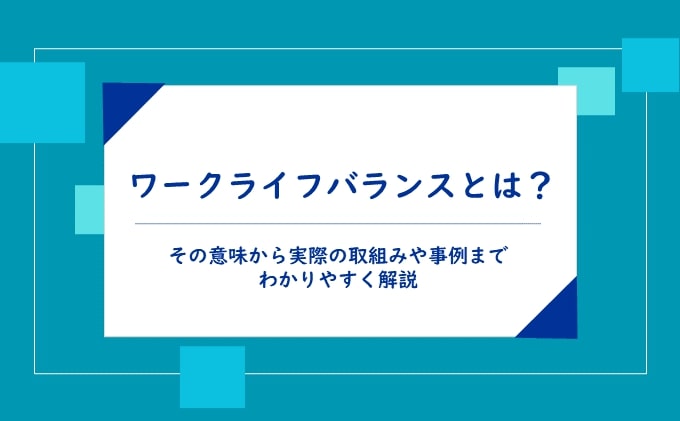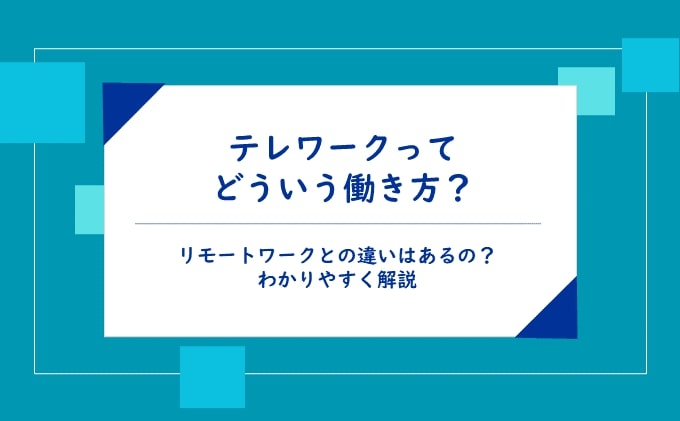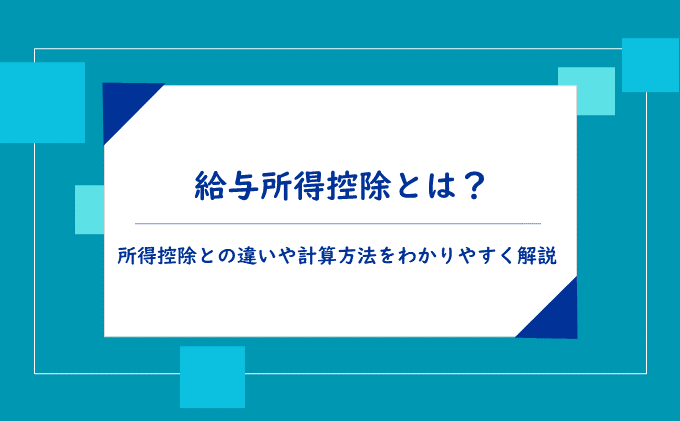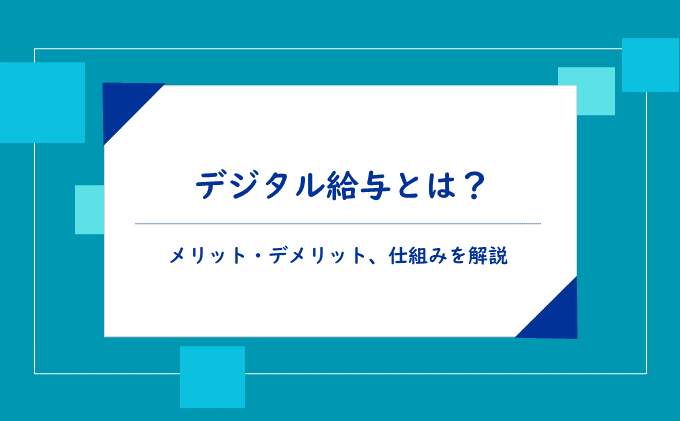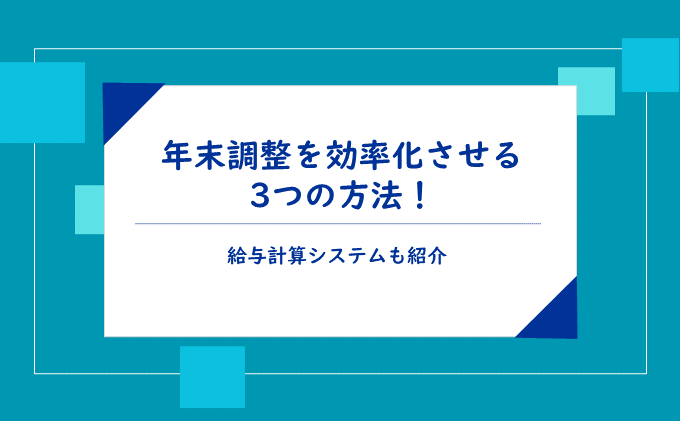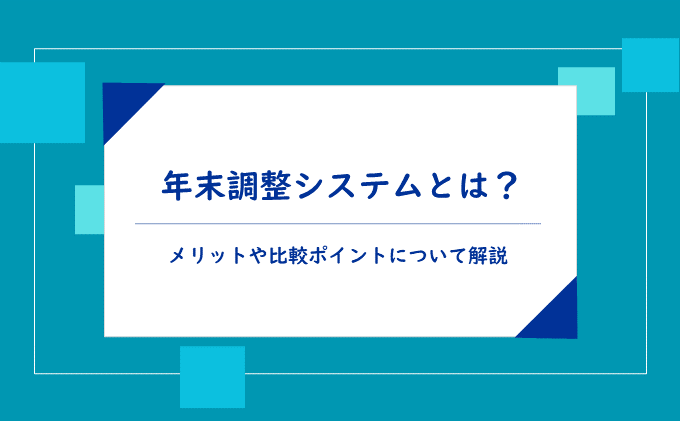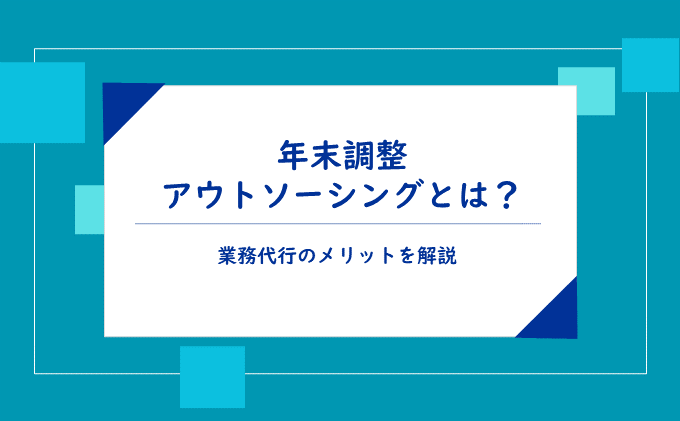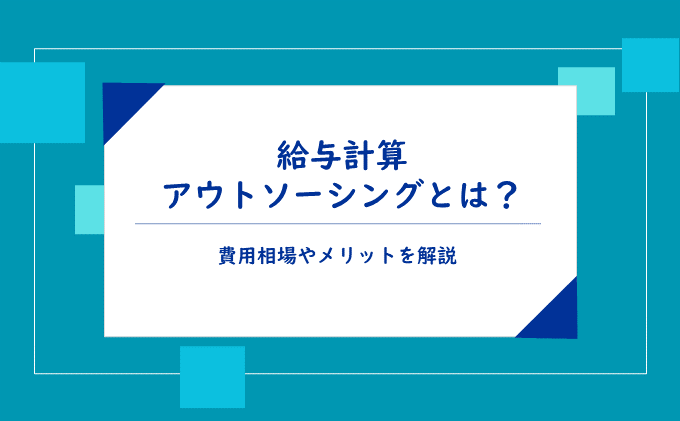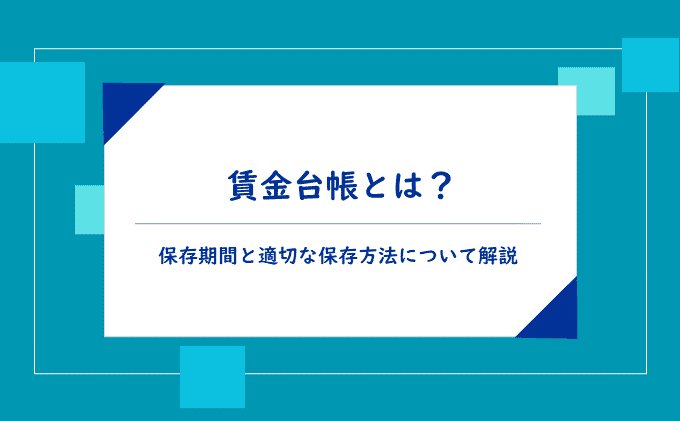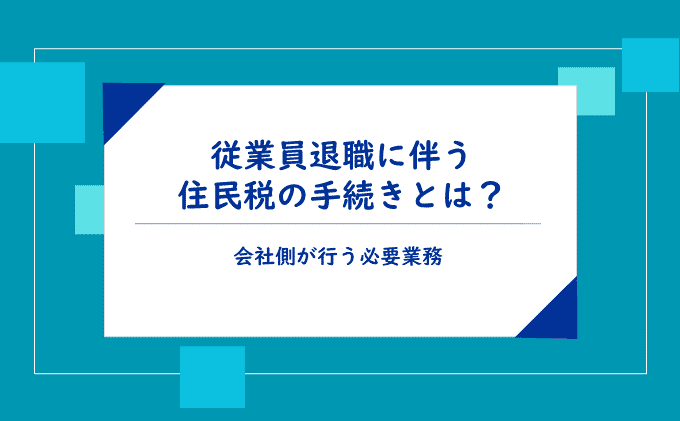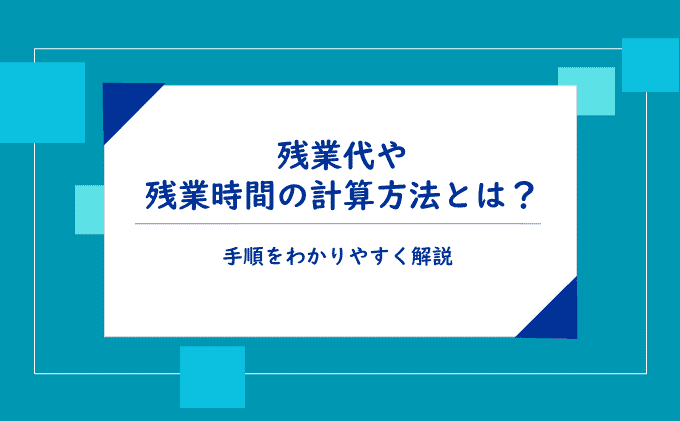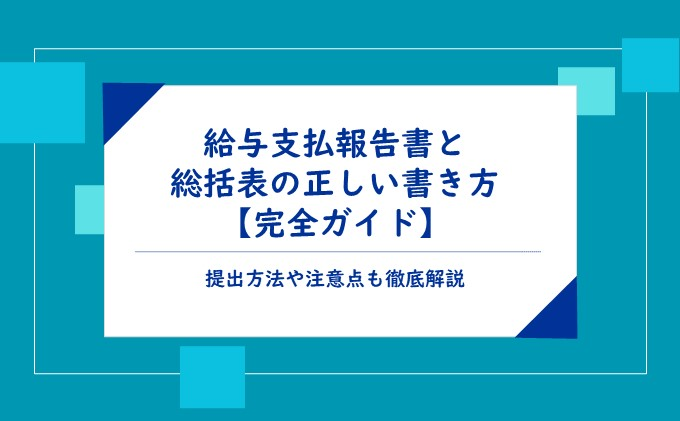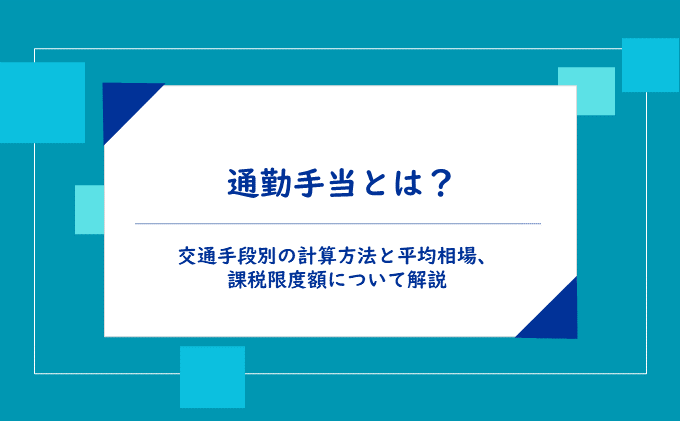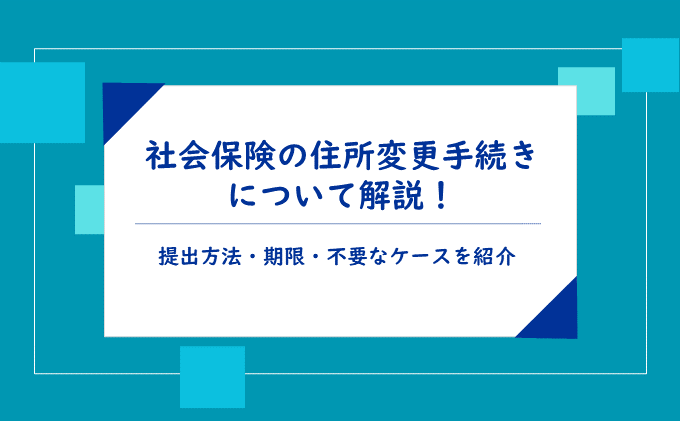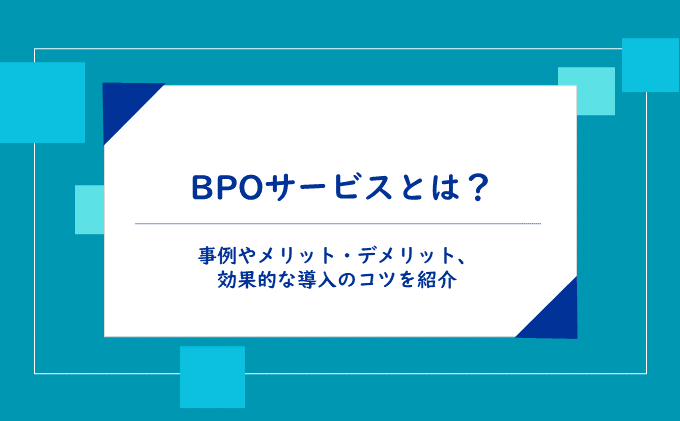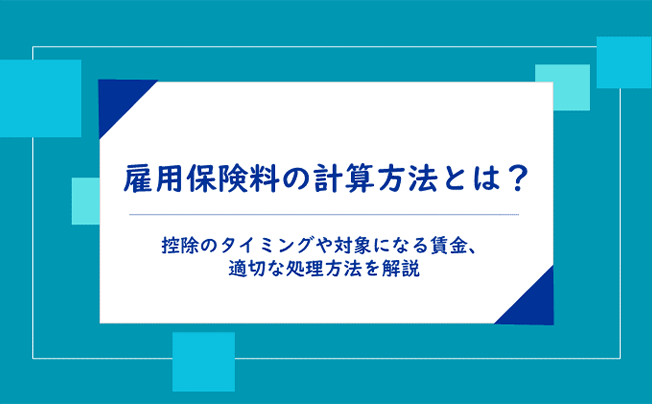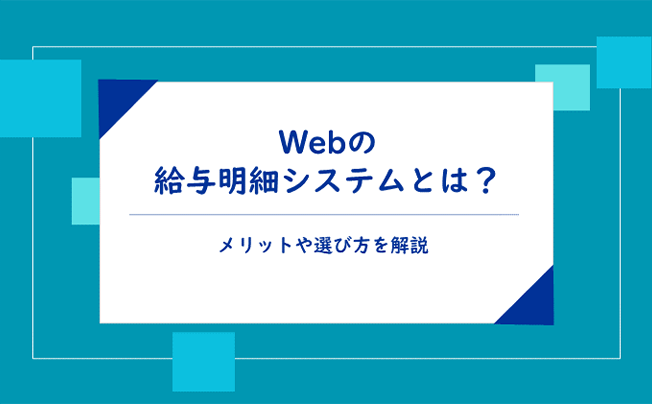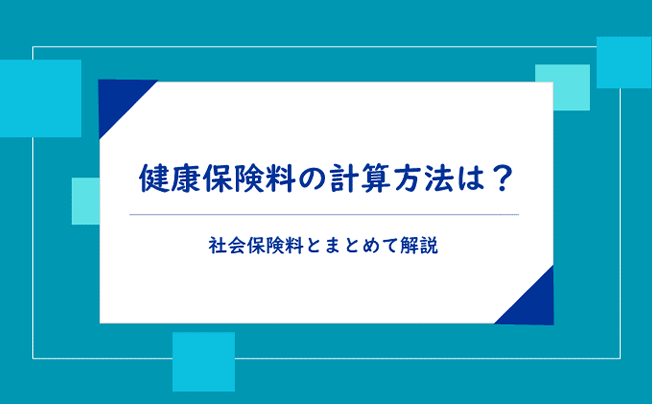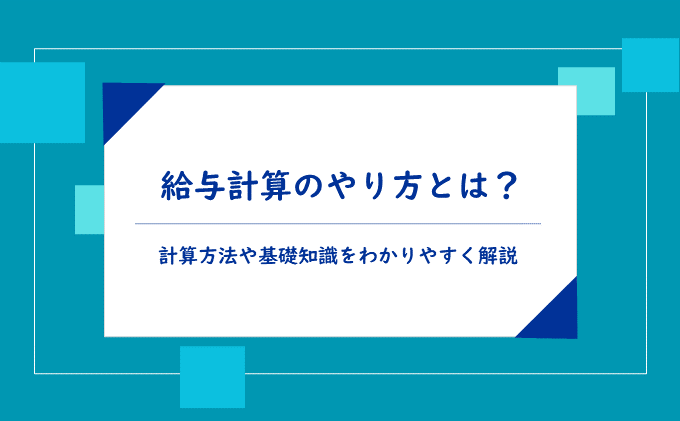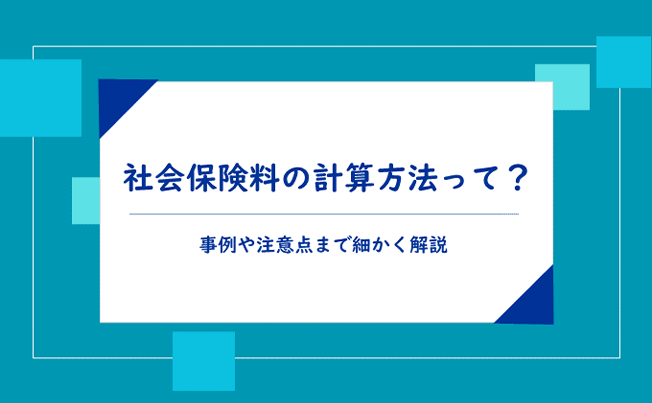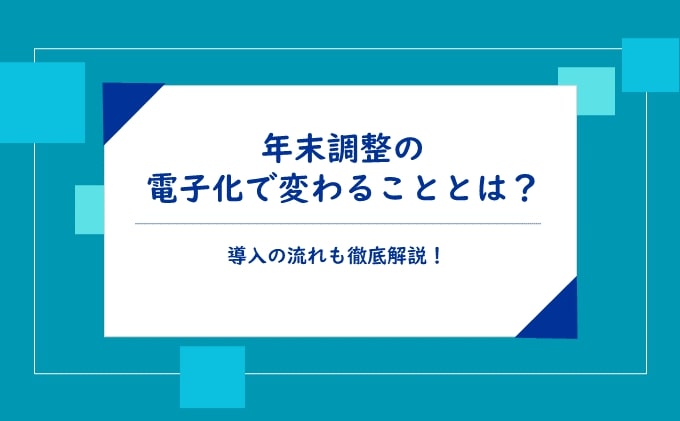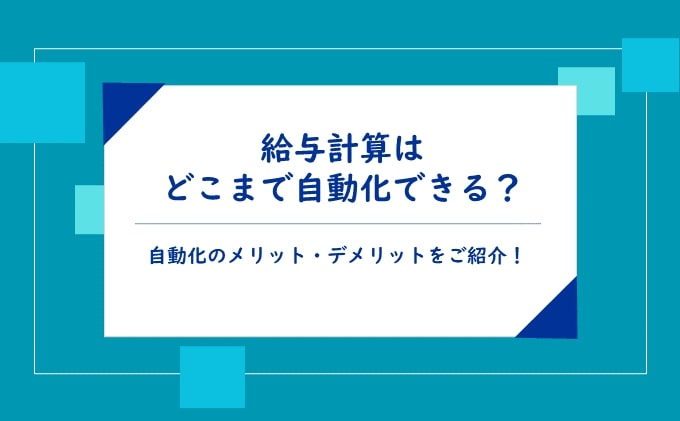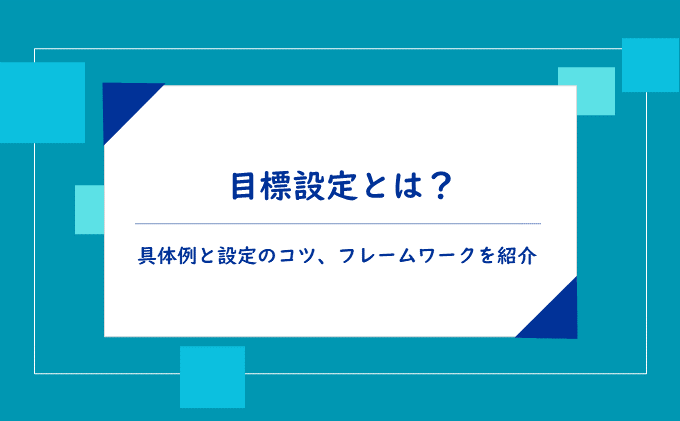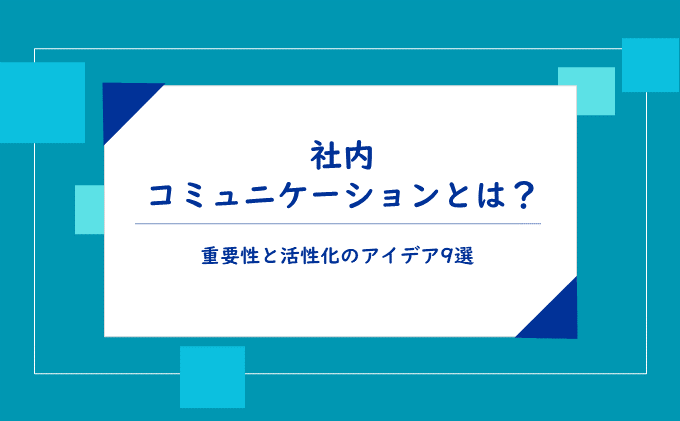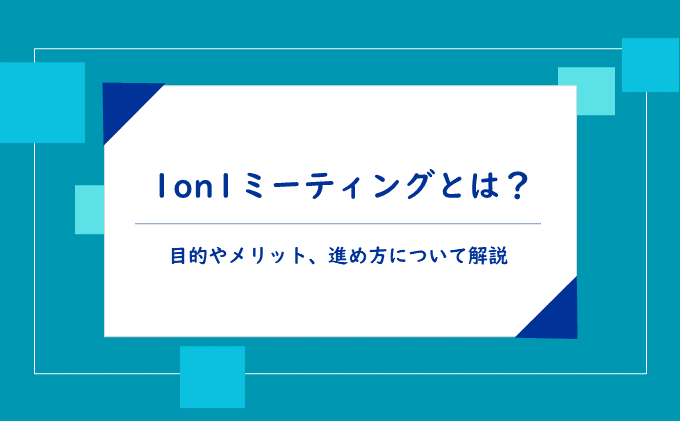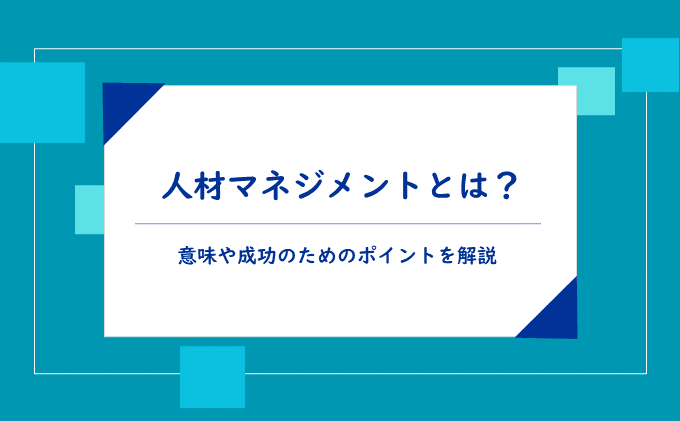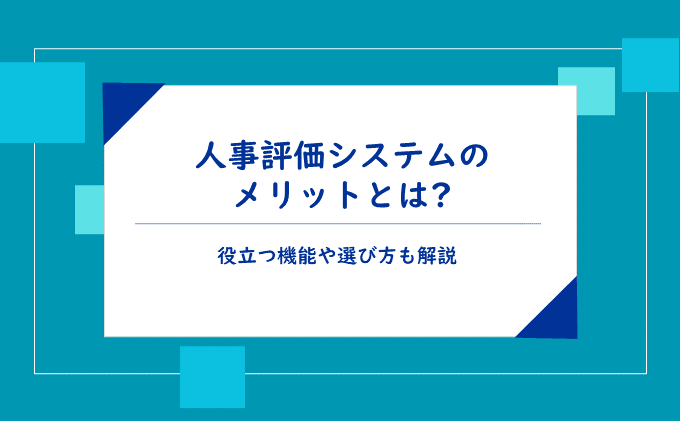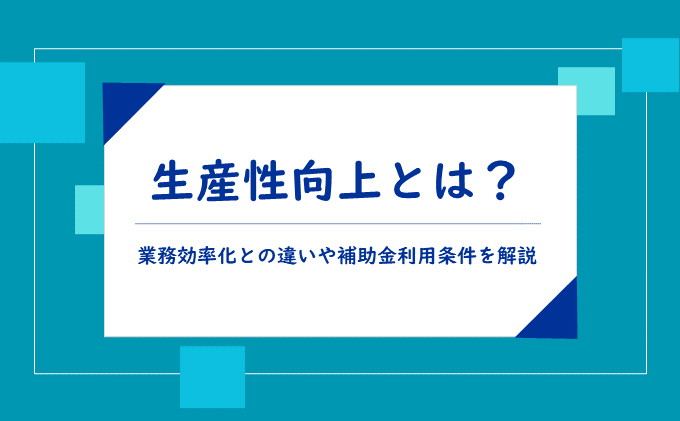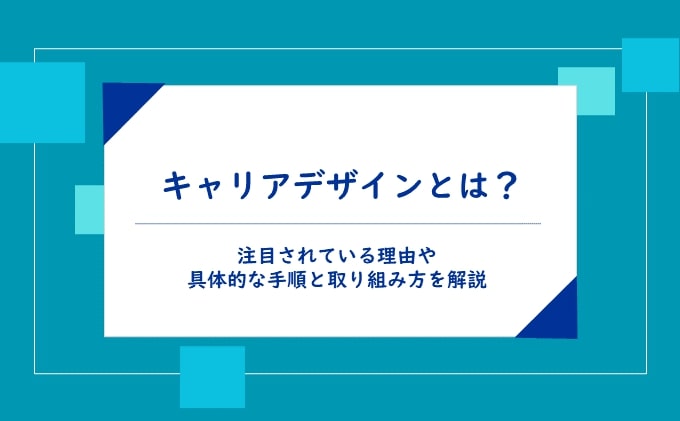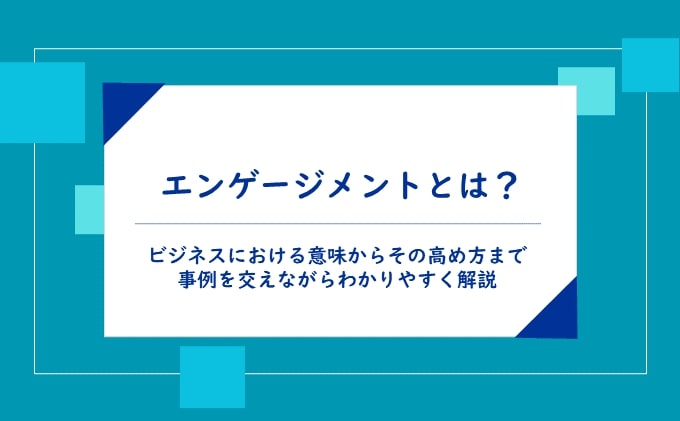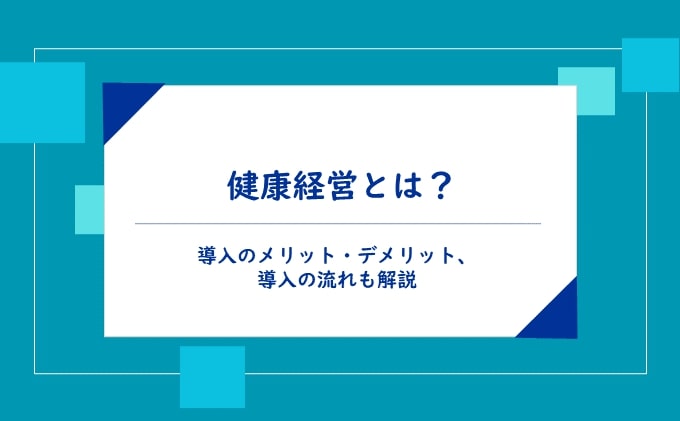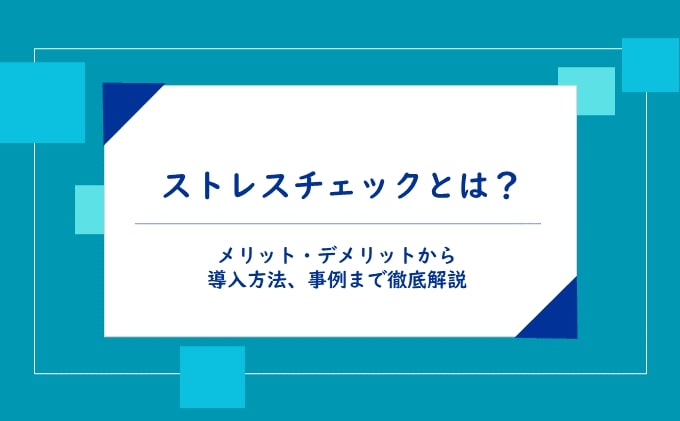所得税の計算方法│税率や控除についてわかりやすく解説
2025.08.28
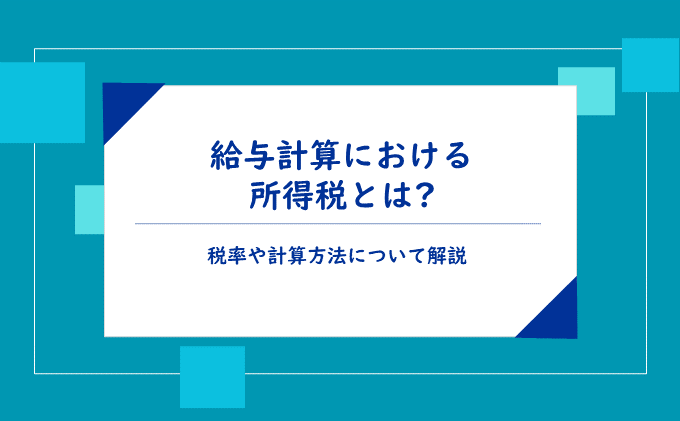
適切に給与計算をするためには、所得税の仕組みを正確に理解しておかなければなりません。基本的には、企業が従業員の所得税を源泉徴収して納付するため、経理担当者であれば所得税の計算方法に対する理解は重要なことです。
本記事では、所得税や復興特別所得税、源泉所得税の税率と計算方法をはじめ、源泉所得税の納付方法や、給与の所得税計算を効率化させる方法などについて解説します。
目次
ADPS導入事例:名港海運株式会社様のADPSの機能と手厚い保守体制により業務効率化が加速
所得税とは所得に課せられる税金のこと
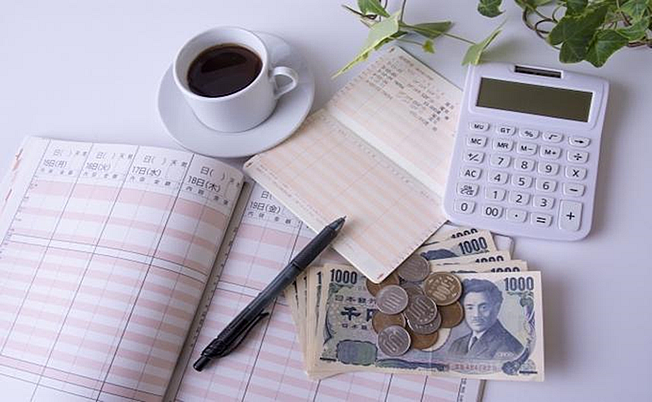
所得税とは、個人が1年間に得た所得(給与所得)に対してかかる税金のことです。所得税は1月1日から12月31日までの1年間の所得の合計から所得控除を差し引いた部分に対してかかります。
所得と似た言葉に給与がありますが、異なる意味の言葉であることをあらかじめ理解しておきましょう。所得とは、収入から必要経費を差し引いた残額のことです。一方の給与とは、会社が従業員に対して支払う基本給や賞与、各種手当などのことを指します。
所得に関する税金には、所得税と源泉所得税、住民税などがあります。ここでは、所得税と源泉所得税、住民税の違いについて見ていきましょう。
関連記事:令和7年度(2025年度)税制改正大綱についてわかりやすく解説
所得税と源泉所得税の違い
所得税と源泉所得税の違いは、税金の納め方です。所得税は個人の所得に対してかかる税金で、原則として納税者個人が申告して納税する「申告納税制度」を採用しています。一方、自営業や副業などのある個人が自ら納税する所得税は「申告所得税」と呼ばれています。
企業に勤める従業員の場合は、企業が給与から所得税をあらかじめ天引きして個人に代わって国に納付することが一般的です。企業が従業員から一定割合を徴収して国に納める税金を源泉所得税といいます。
源泉所得税は、給与や報酬を支払う側が、従業員に代わって納める所得税の一部です。ただし、源泉所得税はあくまでも概算金額であるため、年末調整では実際に納める所得税額を計算し、源泉徴収で支払った所得税との差額を清算する必要があります。
所得税と住民税の違い
個人の1年間の所得に対してかかる所得税と住民税の違いは、次の2点です。
- 税金の納付先
- 税金の対象年度
所得税は国へ納める国税であるのに対し、住民税は地方に納める地方税に該当します。納付先が異なるため、税額は別々に計算され、それぞれ別々に徴収されます。
また、所得税は1月から12月までの1年間の所得をもとに計算されますが、税額を決める所得額はその年が終わらないと確定できません。
年末調整や確定申告をした時点で確定し、会社員であれば会社が給与から天引きして納付しているため、12月の年末調整で差額を精算することが一般的な流れです。
一方の住民税は、前年の所得をもとに計算されます。前年の所得にもとづき、6月から翌年5月までの住民税が決定される流れです。決定した住民税は、毎年6月ごろに届く住民税決定通知書で確認できます。
なお、会社勤めであれば、住民税も会社が給与から天引きして納付します。
所得で異なる所得税率

所得税の税率は、課税所得金額に応じて7段階(5~45%まで)に区分されています。所得税には超過累進税率が採用されており、課税所得金額が一定以上になった場合にその超えた金額に対してのみ高い税率を当てはめるというものです。
所得税率は、次の表のとおりです。
| 課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
所得税は「課税所得金額 × 税率 - 控除額」で算出します。例えば、課税所得税額が400万円の場合は税率20%、控除額42万7,500円が適用されます。この条件で計算をすると所得税は「400万円 × 20% - 42万7,500円 = 372,500円」となります。
所得税はいくらから課税される?
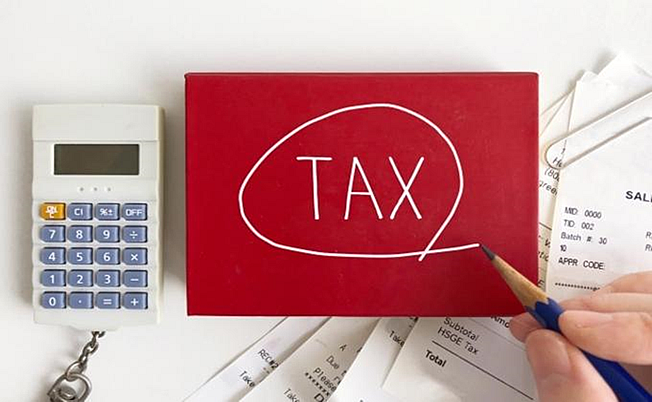
所得税は、課税所得の額に応じて課せられます。課税所得とは、1年間の所得から所得控除を差し引いた額のことです。所得控除が所得を上回る場合、課税所得は0円となります。この結果所得税は0円となり、徴収する必要はありません。
以下では、所得税が発生する年収のラインについて解説します。
給与所得者は年収103万円超
給与所得者の場合、基本的には年収が103万円を超えると所得税の納付が必要です。103万円を超えると、給与所得控除と基礎控除の合計額を上回り、課税所得がプラスになります。これがいわゆる「103万円の壁」と呼ばれるボーダーラインです。
ただし、適用される所得控除によっては、年収103万円を超えていても所得税がかからない場合があります。たとえば、扶養控除や配偶者控除の対象である場合は、年収103万円を超えていても課税所得0円となり、所得税の納付が必要ない可能性があります。
関連記事:令和7年度(2025年度)税制改正大綱についてわかりやすく解説
パートやアルバイトの場合は月収8万8,000円超
パートやアルバイトとして働いている場合、月収が8万8,000円を超えると所得税が源泉徴収されます。ただし、給与所得者と同様に年収が103万円以下の場合、所得税を徴収する必要はありません。
たとえば、8月の月収が10万円であったものの、ほかの月はすべて5万円であったとします。この場合、8月については8万8,000円を超えているため、源泉徴収の対象です。しかし、年間の所得税は65万円であり、103万円以下です。つまり、本来は所得税を徴収する必要はなかった人となります。
この場合、年末調整の際に源泉徴収によって納めすぎていた税金が還付されます。
個人事業主は年間所得48万円超
個人事業主の場合、年間の所得が48万円を超えた場合は所得税が課税されます。
個人事業主は給与所得を得るわけではないため、給与所得控除は適用されません。しかし、合計所得金額が2,400万円以下の場合は基礎控除48万円が適用されます。つまり、年間所得が48万円以下である場合は、課税所得が0円となるため所得税を徴収する必要はありません。
関連記事:令和7年度(2025年度)税制改正大綱についてわかりやすく解説
給与所得者の所得税の計算方法と具体例

給与所得者の所得税の計算方法と具体例について解説します。所得税額の計算は、年末調整において重要な意味合いを持つため、経理担当者としては計算方法を理解しておくことが大切です。
年末調整では、従業員それぞれの所得税額と毎月の源泉徴収税額との差分を計算し、差額を清算します。ただし、従業員ごとに給与額や控除は異なるため、計算方法を正しく理解しておかなければなりません。給与所得者の所得税の計算式は、次のとおりです。
所得税額 =(給与総収入 - 給与所得控除 - 所得控除)× 所得税率 - 税額控除
ここでは、給与所得者の所得税を計算する手順をそれぞれ見ていきましょう。
1.給与総収入を算出する
まずは、給与総収入を算出しましょう。給与総収入は、従業員が1年間で受け取る給与の総額です。基本給に加え、賞与や残業手当、職務手当なども含まれます。
ただし、非課税となる手当については、給与総収入には含まれません。非課税となる手当は様々にありますが、給与の実務上ではごく限られた項目です。ここでは以下3つを例とします。
| 非課税となる手当 | 条件 |
|---|---|
| 通勤手当 | 1か月の通勤手当が15万円以下の場合は非課税となる |
| 宿日直手当 | 1回の宿直・日直に対して支給される手当が4,000円以下の場合は非課税となる |
| 転勤・出張手当 | 転勤や出張のために通常必要と認められる範囲であれば非課税となる |
関連記事:2026年3月JR東日本が運賃改定┃通勤手当業務における注意点
2.給与所得控除額を算出する
次に、給与所得控除額を算出します。給与所得控除は、給与所得者が受けられる控除です。1年間の給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額)に応じて、給与総収入から一定額を控除できます。
令和2年分以降の給与所得控除額は以下のとおりです。【※1】
| 給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 |
|---|---|
| 1,625,000円まで | 550,000円 |
| 1,625,001円から1,800,000円まで | 収入金額 × 40% - 100,000円 |
| 1,800,001円から3,600,000円まで | 収入金額 × 30% + 80,000円 |
| 3,600,001円から6,600,000円まで | 収入金額 × 20% + 440,000円 |
| 6,600,001円から8,500,000円まで | 収入金額 × 10% + 1,100,000円 |
| 8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
たとえば、給与等の収入金額が700万円である場合、給与所得控除額は以下のように算出できます。
700万円 × 10% + 110万円 = 180万円
同1年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合は、2枚の支払金額の合計額をもとに、上記の表から給与所得控除額を求めましょう。
なお、給与等の収入金額が660万円以上の場合、給与所得計算には以下の速算表が用いられます。
| 給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 |
|---|---|
| 6,600,000円以上8,500,000円未満 | 収入金額 × 90% - 1,100,000円 |
| 8,500,000円以上 | 収入金額 - 1,950,000円 |
※1:2025年3月、税制改正案が国会で可決されました。2025(令和7)年分の年末調整より、所得要件が変更となります。
関連記事:給与所得控除とは?所得控除との違いや計算方法をわかりやすく解説
3.所得控除額を算出する
所得控除額の算出も必要です。所得控除には15の種類があり、年末調整で対応できるのは以下の12種類です。【※2】
| 所得控除 | 控除額 |
|---|---|
| 基礎控除 | 合計所得金額2,400万円以下:48万円 2,400万円超2,450万円以下:32万円 2,450万円超2,500万円以下:16万円 |
| 社会保険料控除 | 支払った社会保険料の合計額(上限なし) |
| 生命保険料控除 | 一定の方法で計算した金額 (最大12万円) |
| 地震保険料控除 | 一定の方法で計算した金額 (最大5万円) |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 支払った掛金の合計額 (上限なし) |
| 扶養控除 | 一般の控除対象扶養親族:38万円 特定扶養親族:63万円 老人扶養親族のうち同居老親等以外の者:48万円 老人扶養親族のうち同居老親等:58万円 |
| 配偶者控除 | 一般の控除対象配偶者:最大38万円 老人控除対象配偶者(控除対象配偶者のうち年齢が70歳以上):最大48万円 |
| 配偶者特別控除 | 従業員の合計所得金額および配偶者の合計所得金額に応じて異なる (最大38万円) |
| 寡婦控除 | 27万円 |
| ひとり親控除 | 35万円 |
| 勤労学生控除 | 27万円 |
| 障害者控除 | 障害者:27万円 特別障害者:40万円 同居特別障害者:75万円 |
※2:2025年3月、税制改正案が国会で可決されました。2025(令和7)年分の年末調整より、新たに「特定親族特別控除」が創設されます。
参考:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
一方、以下の3種類については年末調整では対応できません。従業員が確定申告する必要があります。
| 所得控除 | 控除額 |
|---|---|
| 医療費控除 | 一定の方法で計算した金額 (最大200万円) |
| 寄附金控除 | (寄附金支出合計額と所得 ×40%のうち、いずれか低い金額) - 2000円 |
| 雑損控除 | (1)(損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10% (2) (災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円 上記のいずれか |
所得控除を正確に適用できるよう、税制改正の有無や従業員の状況について正しく理解しておきましょう。
4.課税所得を算出し所得税率を掛ける
1の給与総収入から2の給与所得控除額と3の所得控除額を差し引き、課税所得を算出します。給与総収入が700万円、所得控除は基礎控除(48万円)と社会保険料控除(ここでは100万円とします)が適用される場合、課税所得は以下のように求められます。
700万円(給与総収入) - 180万円(給与所得控除額) - 48万円(基礎控除)- 100万円(社会保険料控除) = 372万円(課税所得)
この課税所得に所得税率を掛けましょう。税率が10%以上の場合は、掛けた後の額からさらに、料率に応じた控除額を差し引きます。所得税には超過累進税率が採用されており、所得が多いほど、所得税率も高くなる仕組みです。
所得税率は5%から45%までであり、課税所得に応じて以下の7つに区分されています。
| 課税所得(1,000円未満の端数金額を切り捨てた後の金額) | 所得税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
5.税額控除を差し引く
課税所得に所得税率を掛けた額から税額控除を差し引き、所得税額を求めましょう。
税額控除には以下のような種類があります。
- 配当控除
- 分配時調整外国税相当額控除
- 外国税額控除
- 政党等寄附金特別控除
- 認定NPO法人等寄附金特別控除
- 公益社団法人等寄附金特別控除
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除
- 住宅耐震改修特別控除
- 住宅特定改修特別税額控除
- 認定住宅等新築等特別税額控除
これらは、課税所得に所得税率を掛けた額から控除するものです。給与所得控除や所得控除のように、課税所得を計算する前に控除しないよう注意しましょう。
関連記事:所得税の計算はどうするの?所得税の基礎知識や計算方法、節税対策を解説
関連記事:給与所得控除とは?所得控除との違いや計算方法をわかりやすく解説
2037年まで徴収される「復興特別所得税」の計算方法

2037年12月31日まで、所得税を納める義務を負う個人については、所得税と併せて復興特別所得税が徴収されます。復興特別所得税は、東日本大震災の復興に向けて財源を確保するために導入された所得税です。2013年から課税が始まりました。
復興特別所得税の税額は、各年の基準所得税額の2.1%です。基準所得税額は、日本国籍がある方の場合、すべての所得に対する所得税額です。たとえば、その年の所得税が20万円だった場合、復興特別所得税は4,200円と算出されます。
源泉徴収の際は、所得税だけではなく復興特別所得税についても計算して徴収しましょう。
参考:国税庁「復興特別所得税の源泉徴収のあらまし(平成 25 年1月以降の源泉徴収) 」
所得から差し引かれる源泉徴収税の計算方法

源泉徴収税の計算方法について、次の4つのケースに分けて解説します。
- 給与に対する源泉徴収税
- 賞与に対する源泉徴収税
- 退職金に対する源泉徴収税
- 報酬・料金に対する源泉徴収税
給与に対する源泉徴収税の計算方法
給与から徴収する源泉徴収税は、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」を用いて計算します。
1. 課税支給額を確定し社会保険料を差し引く
まずは課税支給額を求めます。課税支給額は、基本給や残業手当、各種手当などの合計額から欠勤控除や遅刻早退控除などの金額を差し引いた金額です。なお、課税支給額には非課税の手当を含めないよう注意しましょう。
その後、課税支給額から健康保険料や厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料といった社会保険料を差し引きます。
関連記事:残業代や残業時間の計算方法とは?手順をわかりやすく解説
2. 源泉徴収税を算出する
国税庁が発表している「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」を用いて、源泉徴収税を確認しましょう。
源泉徴収税は、課税支給額から社会保険料を差し引いた金額と、扶養親族等の数によって細かく定められています。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している従業員の源泉徴収税については甲欄、提出していない従業員の源泉徴収税については乙欄を参照しましょう。
賞与に対する源泉徴収税の計算方法
賞与から徴収する源泉徴収税は、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を用いて計算します。
1.賞与支給額から社会保険料を差し引く
まずは、賞与額から社会保険料を差し引きましょう。
2.賞与の所得税率を求める
次に、賞与の所得税率を求めます。
賞与の税率は、賞与の支給月の「前月の月例給与」の実績(課税支給額、社会保険料)を使用します。前月の月例給与の金額から課税支給額(非課税の手当は除く)を求め、その月の社会保険料を差し引きましょう。
この金額と扶養親族等の数を用いて、国税庁が発表している「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を参照し、税率を求めてください。
参考:国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和 6 年分)」
3.税率をもとに源泉徴収税を算出する
前述の1.で求めた社会保険料差し引いた後の賞与の額に、前述2.で求めた賞与の税率をかけることで、賞与に対する源泉徴収税が求められます。
退職金に対する源泉徴収税の計算方法
役員や従業員に対して退職金を支払う場合も、所得税を源泉徴収して原則翌月の10日までに納めなければなりません。この退職金には、退職したことによって支払われるすべての給与が含まれます。そのため、退職手当のほかに功労金を支給した場合も、忘れずに退職金に含めましょう。
1. 退職所得金額を算出する
まずは、以下の計算式で課税される退職所得金額を算出しましょう。
課税退職所得金額 =(退職金額 - 退職所得控除額) ÷ 2
退職所得控除額は、勤続年数によって以下のように計算方法が変わります。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年超え | 800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年) |
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数(80万円に満たない場合には80万円) |
参考:国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」
なお、勤続年数は端数を切り上げる点に注意しましょう。たとえば、勤続年数が10年1か月の場合、1か月を1年に切り上げて11年として計算します。
2. 所得税額を算出する
課税退職所得金額がわかったら、以下の計算式で退職金にかかる所得税額を算出しましょう。
退職金にかかる所得税額 = 課税退職所得金額 × 所得税率 - 控除額
所得税率と控除額は、国税庁が発表している「退職所得の源泉徴収税額の速算表」をもとにしてください。
参考:国税庁「退職所得の源泉徴収税額の速算表(令和 5 年分)」
報酬・料金に対する源泉徴収税の計算方法
そのほか、外部の個人に支払う報酬や料金についても、源泉徴収の対象となる場合があります。具体的には、以下のような報酬や料金です。
- 原稿料や講演料
- 弁護士、公認会計士、司法書士などの有資格者に支払う報酬・料金
- 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
- プロスポーツ選手やモデル、外交員などに支払う報酬・料金
- 映画や演劇、テレビ出演に対する報酬・料金
- 芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
源泉徴収税は、以下のように求められます。
源泉徴収税 = 支払金額 × 10.21%
ただし、同じ個人に対する1回の支払額が100万円を超える場合、100万円を超えた部分については20.42%の税率が適用されます。
たとえば、1人に110万円を支払った場合、源泉徴収税は以下のとおりです。
(110万円 - 100万円)× 20.42% + 100万円 × 10.21% =122,520円
参考:国税庁「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」
関連記事:賞与にかかる所得税の計算方法を解説!計算時の注意点も紹介
【令和6年(2024年)分所得税】定額減税について

令和6年(2024年)度税制改正にともない、令和6年(2024年)分所得税に対して定額減税が実施されました。定額減税とは、令和6年(2024年)4月1日施行の「令和6年度税制改正法」に盛り込まれた制度です。
令和7(2025年)年3月現在、定額減税の対象は令和6年(2024年)度分のみとなっています。ここでは、定額減税の対象者と定額減税額について解説します。
定額減税の対象
対象となる人は、所得税と住民税で異なります。所得税の減税対象となる人は、次のとおりです。
- 日本国内に居住している
- 令和6年(2024年)分の所得税の納税者
- 令和6年(2024年)分の合計所得金額が1,805万円以下
※給与収入のみの場合は、2,000万円以下
※子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける場合は、給与収入が2,015万円以下
一方、住民税の減税対象となる人は、次のとおりです。
- 日本国内に居住している
- 令和6年(2024年)分の所得税の納税者
- 令和5年(2023年)分の合計所得金額が1,805万円以下
※給与収入のみの場合は、令和6年(2024年)分の給与収入が2,000万円以下
※子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける場合は、給与収入が2,015万円以下
定額減税額
定額減税額は、家族構成によって異なることに注意しましょう。所得税の減税額は、納税者本人は3万円、同一生計配偶者または扶養親族がいる場合では1人につき3万円です。
次の4人家族であれば、所得税から減税される額は120,000円です。
- 納税者本人
- 同一生計配偶者
- 子ども(扶養親族)2人
住民税の減税額は、納税者本人は1万円、同一生計配偶者または扶養親族がいる場合では1人につき1万円になります。
上記のような4人家族であれば、住民税から減税される額は40,000円です。
源泉所得税の納付方法と納付期限

源泉所得税は、納税者本人に代わって事業主が国に納付しなければなりません。納付には期限が定められているため、忘れずに納付しましょう。
以下では、源泉所得税の納付方法や納付期限について解説します。
源泉所得税の納付方法は4つ
源泉所得税の納付方法は、主に以下の4つです。
- 税務署や金融機関の窓口で、現金に納付書を添えて納付する
- 税務署が発行するバーコード付き納付書、あるいは国税庁のWebサイトから出力したQRコードを使い、コンビニエンスストアで納付する
- e-Taxを利用した口座引き落とし、あるいはインターネットバンキング口座から納付する(キャッシュレス納付)
- クレジットカードで納付する(キャッシュレス納付)
スマホアプリから納付するという方法もありますが、納付金額が30万円を超える場合は利用できないため注意しましょう。
なお、キャッシュレスで納付する場合は、事前にe-Taxで徴収高計算書データを作成・送信する必要があります。
納付期限は給与や報酬などを支払った月の翌月10日まで
源泉徴収した所得税や復興特別所得税の納付期限は、原則給与や報酬などを実際に支払った月の翌月10日までです。
ただし、給与の支給人員が常時10人未満である場合は、半年分をまとめて納付できるという特例があります。これを納期の特例といい、適用を受けるためには、事前に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する必要があります。
参考:国税庁「No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」
給与所得者による確定申告

給与取得者の多くは、基本的には確定申告は必要ありません。事業者が本人に代わって所得税を納めているためです。
しかし、中には確定申告が必要なケースもあります。また、確定申告を行うことで源泉徴収された所得税や復興特別所得税が還付される場合もあります。
それぞれのケースについて見ていきましょう。
確定申告が必要なケース
確定申告が必要なケースとしては、主に以下が挙げられます。
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合
- 1か所から給与の支払いを受けており、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える場合
- 2か所以上から給与の支払いを受けており、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える場合
特に注意が必要なのが、従業員が副業や株式売買をしている場合です。本業以外で20万円を超える所得を得ている場合は、確定申告をする必要があります。
確定申告により税金が還付されるケース
確定申告により税金が還付される主なケースは以下のとおりです。
- 災害や盗難、横領などの被害を受けて雑損控除を受ける場合
- 医療費控除を受ける場合
- ふるさと納税や寄附を行い、寄附金控除を受ける場合(ワンストップ特例を受ける場合を除く)
- 住宅ローンを組み、住宅借入金等特別控除を受ける場合
確定申告の義務がない場合でも、上記に当てはまる方は確定申告をすることで税金の還付を受けられます。
給与の所得税計算を効率化させる方法
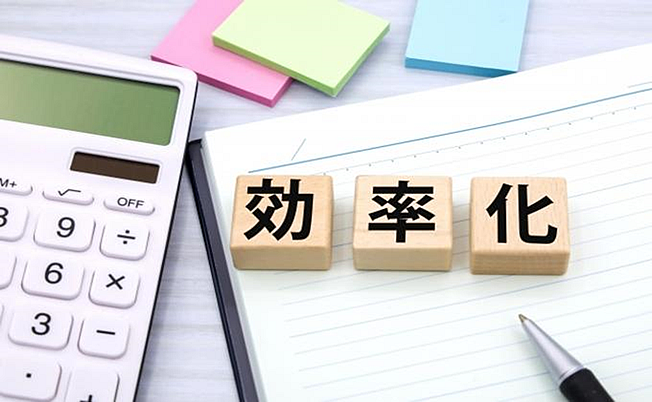
ここでは、所得税計算を効率化させるための方法を解説します。おすすめの方法は、次の2つです。
- 計算業務をアウトソーシングする
- 自動計算システムを導入する
それぞれの方法の特徴を解説します。
計算業務をアウトソーシングする
計算業務のアウトソーシングとは、税理士や社会保険労務士、アウトソーシング会などに給与計算業務代行を依頼することです。
アウトソーシングのメリット・デメリットは、次の通りです。
<メリット>
- 正確な給与計算ができる
- 社内リソースを他の業務に集中できる
- 法改正への対応がスムーズにできる
<デメリット>
- コストがかかる
- 社内にノウハウが蓄積されない
- 情報漏洩などセキュリティリスクがつきまとう
自動計算システムを導入する
自動計算システムとは、勤怠管理データや雇用情報などから、自動で給与計算できるシステムのことです。
給与計算機能や給与に関するデータ管理機能が備わっているシステムを活用すれば、計算業務の効率化につながります。
以下では、給与の所得税計算にシステムを活用するメリットについて詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。
給与の所得税計算にシステムを活用するメリット

給与の所得税計算にシステムを活用するメリットについて解説します。代表的なメリットは、次の3つです。
- 人的ミスを防げる
- 制度改正に対応できる
- 人件費削減につながる
システム導入によるメリットを把握して、自社にあったシステムを選びましょう。
人的ミスを防げる
給与の所得税計算にシステムを活用することで、人的ミスを防げます。給与計算では、従業員の労働状況に応じた細かな計算が必要です。
Excelなどで計算している企業であれば、入力ミスや計算ミスなどの人的ミスが発生するかもしれません。一方、給与計算ソフトを導入すれば、勤怠データから残業時間を自動取得して給与計算が可能です。従来の作業工数や計算間違いのリスクを減らせるため、業務効率化にもつながります。
また、給与計算ソフトを活用すれば、属人化の防止も可能です。Excelで作業する場合、作業者によって入力スキルに差があるため、作業に慣れたスタッフが退職すると業務の質が落ちるデメリットがあります。給与計算ソフトであれば、専門知識は不要です。必要な数値を入力するだけで給与計算を行えるため、誰でも簡単に経理業務を進められます。
制度改正に対応できる
多くの給与計算システムは自動アップデートされるため、制度改正に対応できます。
Excelで作業する場合には、制度改正の度に保険料率の変更などを手作業で行わなくてはなりません。手入力による変更には手間と時間がかかるだけでなく、入力ミスもつきまとうでしょう。
一方、給与計算ソフトを活用すれば自動的に制度改正に対応できるため、ミスなく正しい給与の計算が可能です。
人件費削減につながる
給与計算システムを導入すると、人件費削減につながります。Excelでの給与計算には作業時間がかかり、その分人件費も必要です。一方、給与計算システムを活用すれば、必要な数値を入力するだけで作業が完了します。給与計算時間を大幅に削減できるため、人件費の削減にも効果的です。
給与計算システムの選び方
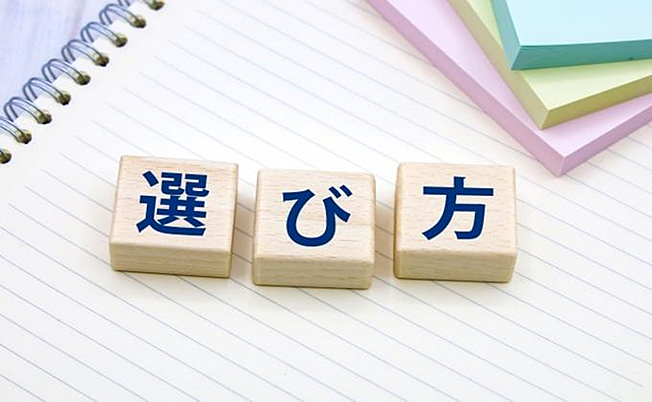
給与計算システムを選ぶ際には、以下3つのポイントを押さえたうえで、自社にあったシステムを選びましょう。
- 自社の課題を解決できるシステムを選ぶ
- 他システムと連携可能なシステムを選ぶ
- セキュリティが強固なシステムを選ぶ
自社の課題を解決できるシステムを選ぶ
自社で解決すべき課題を明確にして、自社のニーズを満たせる給与計算システムを選びましょう。契約社員や派遣社員、アルバイト・パートなど、複数の雇用形態で従業員を採用している企業であれば、各雇用形態に応じた計算ができるものを選ぶことも大切です。
システムに勤怠管理機能や年末調整などの機能が備わっていれば、所得税計算に役立ちます。
他システムと連携可能なシステムを選ぶ
導入済みの勤怠管理システムや会計ソフトなどのシステムに連携できれば、計算業務をより効率化できます。
既存のシステムに給与計算システムを連携できなければ、給与計算業務の効率化は進みません。他システムと連携できるかどうかをあらかじめ確認しておきましょう。
セキュリティが強固なシステムを選ぶ
給与計算システムは多くの個人情報を扱うため、セキュリティが強固なものを選ぶことが大切です。アクセス制限やログ解析などのセキュリティ対策についても、事前に確認しておきましょう。
なお、トラブルが生じた際のサポート体制が整ったシステムであれば、より安心して活用できます。
カシオヒューマンシステムズの「ADPS」で給与計算を自動化した事例
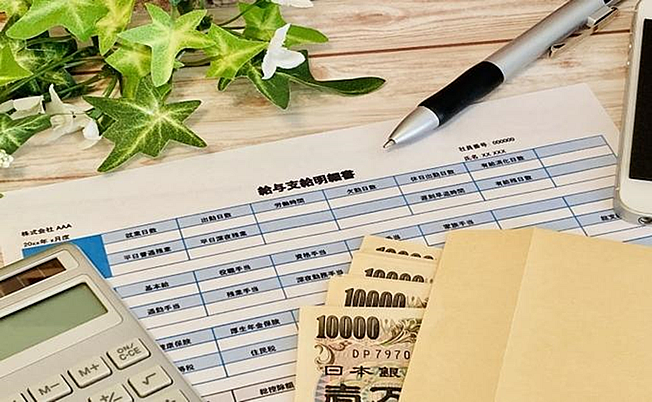
カシオヒューマンシステムズの「ADPS」で給与計算を自動化した事例を紹介します。「コーナンPRO」などのホームセンターを展開するコーナン商事株式会社は、「人事管理システム ADPS」を導入して業務時間の大幅な短縮を実現しています。
全国に300を越える店舗展開を行っている同社の時間給は12区分あり、従業員の働き方もさまざまです。また、給与区分が細分化されており、人事部にとっては業務負荷をいかに軽減するかが課題でした。
1999年からADPSを活用し煩雑な人事管理に対応していましたが、ADPSのバージョンアップを決定しました。他社と比較検討した結果、旧システムで追加した独自の機能やカスタマイズといった資産をそのまま活かせるほか、移行サポートの充実が決め手となりました。
システムのリニューアルにともない、給与情報の取り込みが1/4、計算は1/6になるなど、大幅な時間短縮に成功しています。
ほかにも、最低賃金額改定への対応や働き方改革にともなうさまざまな法改正に対しても、ADPSを活用できているそうです。
人事管理システム ADPS 導入事例:コーナン商事株式会社
給与の所得税計算を自動化するならカシオヒューマンシステムズ

複雑な所得税の計算をミスなく効率的にこなすためには、給与や所得税を自動で計算できるシステムを導入しましょう。
カシオヒューマンシステムズ株式会社が提供する人事管理システム「ADPS」は、給与計算や人事情報管理、採用管理などを効率化できます。累計5,000社を超える導入実績を誇る、信頼性の高いシステムです。
給与計算や人事情報管理、採用管理など、人事業務を 「イベント」というスタイルにまとめ、各業務の流れに沿ってナビゲートしてくれます。人事業務に初めて携わる方も、安心して業務を進められます。
所得税や給与の計算自動化はもちろん、人事業務をトータルでサポートしてくれるサービスを探している方におすすめです。
詳細は、以下をご覧ください。
ADPS導入事例:名港海運株式会社様のADPSの機能と手厚い保守体制により業務効率化が加速
まとめ
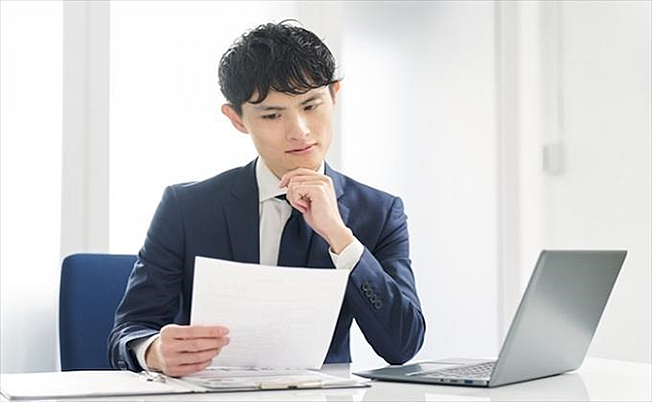
所得税は、個人が1年間に得た所得に対して課せられる税金のことです。本人が直接申告して納付するパターンと、企業が源泉徴収して代わりに納付するパターンがあります。後者の場合、企業が所得から源泉所得税を計算し、本人に代わって納付しなければなりません。源泉所得税の計算方法は、給与や賞与、退職金、報酬・料金でそれぞれ異なります。
所得税や源泉所得税の計算方法は複雑です。正しく計算するためには、システムを活用した計算の自動化を検討してはいかがでしょうか。
ADPS導入事例:名港海運株式会社様のADPSの機能と手厚い保守体制により業務効率化が加速
カシオヒューマンシステムズコラム編集チームです。
人事業務に関するソリューションを長年ご提供してきた知見を踏まえ、
定期的に「人事部の皆様に必ず今後の業務に役立つ情報」を紹介しています。